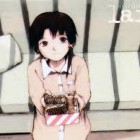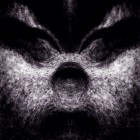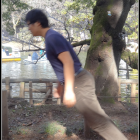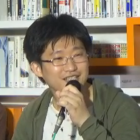「透明な〈私〉」の発見 ―ポストニューウェーブ短歌における〈私〉の位相
平成3年生まれの筆者は昭和を知らない。筆者と昭和との隔たりはせいぜい3年ほどだが、この隔たりは埋めることのできない隔たりである。だから筆者が昭和について書く場合、どうしても文献に頼らざるをえないことを先に示しておく。
さて、ではそんな筆者が感じた昭和とはどのようなものだろうか。それは昭和が「いま・ここ」の現実ではなく「物語」を必要とした時代だったのではないか、ということだ。まあ何のことはない、これは大澤真幸がすでに『不可能性の時代』において提示した問題である。大澤は、1945年から1970年までを「理想の時代」、1970年から1995年までを「虚構の時代」と呼び、この間の社会がそれぞれイデオロギーやブランド消費といった「反現実」を基盤に駆動してきたことを示している。しかし筆者はむしろこうした現象を昭和から平成に至る間の〈私〉像の変遷のうちに見出したいと考えている。
周知の通り近代以降、小説においては〈私〉という要素が極めて重要な役割を果たしてきた。たとえば私小説における〈私〉は世界を映し出す鏡であり、物語の起動装置としての役割を果たしていたといえるだろう。しかし、小説以上に〈私〉が決定的な役割を果たしてきた分野がある。短歌だ。
短歌における〈私性〉というのは、作品の背後に一人の人の――そう、ただ一人だけの人の顔が見えるということです。そしてそれに尽きます。そういう一人の人物(それが即作者である場合もそうでない場合もあ ることは、前に注記しましたが)を予想することなくしては、この定型短詩は、表現として自立できないのです。(岡井隆『現代短歌入門』)
岡井が述べるように短歌において〈私〉は歌全体の、はたまた歌人の作った歌全体の通奏低音をなしてきたといっても過言ではない。しかし、こうした短歌における〈私〉のあり方は90年代を境にはっきりとした形で変質している。今回はこの問題について短歌における昭和の〈私〉像と比較する形で考えていきたい。
短歌における〈私〉像
本題に入る前にまずは歌人の斉藤斎藤の議論を参考に、近代以降の短歌における〈私〉の流れをざっとおさらいしておこう。
まずは斎藤茂吉や土屋文明を擁するアララギ派に代表されるような「実在の〈私〉」。これは作中に登場する〈私〉と現実の〈私〉が完全に一致するような〈私〉であり、歌の内容がすべて作者の経験に基づかなければならないような、もっともオーソドックスな形式だ。
ひた走るわか道暗ししんしんと堪へかねたるわが道くらし 斎藤茂吉『赤光』
そして戦後、前衛短歌運動のもとで新たな〈私〉が提示されることになる。それが「虚構の〈私〉」だ。
革命歌作詞家に凭りかかられてすこしづつ液化するピアノ 塚本邦雄『水葬物語』
五月祭の汗の青年 病むわれは火のごとき孤獨もちてへだたる. 同『装飾楽句』
塚本邦雄は、この「虚構の〈私〉」を通して、現実にはありえないような風景や、事実とは異なる出来事を寓意として詠みこんだ。その背後には戦後の日本の現実に対する深い失望があったとされており、塚本自身「短歌考幻学」において述べているように単なる自然主義を超えた「眞のリアリズム」を目論んだものであった。こうした点で、むしろこの時代の「虚構の〈私〉」こそ、先に述べた大澤の「理想の時代」の〈私〉にあてはめることができるだろう。
さて1980年代になると、ニューウェーブと呼ばれる歌人が登場し始める。この運動に関しては歌人それぞれ作風も著しく異なっておりまだ議論の余地があるが、斉藤斎藤によればニューウェーブにおける〈私〉は「特別な〈私〉」だ。
「嫁さんになれよ」だなんてカンチューハイ二本で言ってしまっていいの 俵万智『サラダ記念日』
斉藤斎藤はニューウェーブの短歌が「わがまま」な短歌であると語っている。それはそれまで前衛短歌において歌われてきた「虚構の〈私〉」、つまり〈私〉だけが歌いうる虚構という「大きな物語」を無化し、歌人それぞれが自分の物語の主役として機能しているということを示している。こうした気軽さから1980年代以降短歌は一気に大衆化し、人口に膾炙するものとなったわけだ。
では、90年代に入ってからの〈私〉というのは、いったいどのような〈私〉なのだろうか。
「透明な〈私〉」の発見
彦坂美喜子は、「短歌に評論は必要か?」(『短歌ヴァ―サス』8号)において、90年代以降、歌の背後に作者像を結ばないような匿名性の高い短歌が増えてきたと論じている。一方斉藤は、「生きるは人生とは違う」(『短歌ヴァ―サス』11号所収)において、90年代以降の歌人を「ポストニューウェーブ」としたうえで、こうした短歌の匿名性が〈私〉の位相の変化に根ざすものだと喝破している。
斉藤は80年代以前の短歌が主観的な〈私〉と客観的な対象としての〈私〉が少なからず折り重なってできていたという点を指摘する。たとえば
飛ぶ雪の碓氷をすぎて昏みゆくいま紛れなき男のこころ 岡井隆『天河庭園集』
という歌。斉藤斎藤は、車窓を吹きすさぶ雪が飛んでいるようにみえ、一瞬暗くなったところに〈私〉の横顔が映るという解釈を採用しているが、どのような解釈であれここには二つの〈私〉が織り込まれていることがお分かりだろう。それは、「飛ぶ雪の碓氷をすぎて昏みゆく」という風景を対象化する〈私〉と、紛れなきこころでゆこうとする〈私〉を対象化する〈私〉だ。柄谷行人は『日本近代文学の起源』において文学における内面性や自我といった側面と写実は実際には軌を一にすると述べているが、短歌も例外ではない。作中の風景というのは、作中に描写された〈私〉を媒介にすることによってはじめて描写されるのである。
さて、ではポストニューウェーブにおける〈私〉についてはどうか。
本を持って帰って返しに行く道に植木や壊しかけのビルがある
カーテンの隙間に見える雨が降る夜の手すりが水に濡れてる
昼過ぎにシャンプーをする浴槽が白く光って歯磨き粉がある 中田有里「今日」
これらの歌には、先の岡井の歌に見られたように、〈私〉を対象化する視点がない。〈私〉が作中に対象化されることもないから、水も歯磨き粉も植木も壊しかけのビルも、それら以上でも未満でもない。見たまんまのまさに「水」であり「歯磨き粉」であり、「植木」であり「壊しかけのビル」なのだ。
先に述べたように、短歌において風景というのは対象化された半透明な〈私〉を媒介として描写されるものであり、あくまでこの〈私〉が見た情景であった。しかしポストニューウェーブにおいては、こうした情景を視る〈私〉を対象化するような視線はもはや存在しない。ただあるのは、まぎれもない「いま・ここ」を生きる、私以上でも私未満でもない無色透明な〈私〉のフレームしかないのだ。
ポストニューウェーブ世代において、「私」の特殊さは歌から排除され、あるいは「私」まるごと歌から排除され、そして〈私〉の生きるが残った。「生きるは人生とは違う」(『短歌ヴァ―サス』11号所収)
では、「透明な〈私〉」の「生きる」が発見されたことで、いったい何が変わったというのだろうか。それは「透明な〈私〉」とともに、その時々を生きる〈私〉の〈実感〉が発見されたということに他ならない。ではそもそも〈実感〉とは、いったい何なのだろうか。
「透明な〈私〉」と〈実感〉
精神科医の木村敏は、精神疾患をもとに、人間の心理的時間を分裂病的な「アンテ・フェストゥム(祭りの前)型」、鬱病的な「ポスト・フェストゥム(祭りの後)型」、癲癇的な「イントラ・フェストゥム(祭りの最中)型」の三つに分類している。詳細は省くが、木村によれば「アンテ・フェストゥム型」と「ポスト・フェストゥム型」の人間はそれぞれ未来と過去を志向し、またそれぞれこれまでの自己の否定とこれまでの自己の温存しようとする傾向にあるという。問題は「イントラ・フェストゥム型」である。木村によれば、それは合理性の解体であり、「永遠の現在」に対する意識でもあるという。そして「アンテ・フェストゥム型」と「ポスト・フェストゥム型」がともに「水平方向での日常の危機」であるのに対して、「イントラ・フェストゥム」は「垂直方向での日常の危機」である。
この第三の狂気(註:「イントラ・フェストゥム型」)は、人生の大半を理性的な日常性の中で過ごしているどんな健康人のもとにもときどき訪れる非理性の瞬間として、愛の恍惚、市との直面、自然との一体感、宗教や芸術の世界における超越性の体験、災害や旅における日常的な秩序からの離脱、呪術的な感応などの形で出現しうるものであるし、(…) 木村敏『時間と自己』
これまでの議論を踏まえれば、ポストニューウェーブの短歌における〈私〉が「イントラ・フェストゥム」的であるということがお分かりだろう。つまりポストニューウェーブの短歌における〈私〉の「生きる」はそのまま永遠の現在の肯定であり、その現在の垂直性において、世界に〈実感〉がもたらされるのである。〈実感〉が「透明な〈私〉」にどっとなだれ込んできていること。それを肯定するということが重要であると筆者は感じる。
文字数:3856