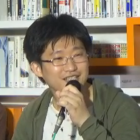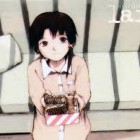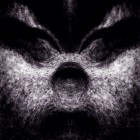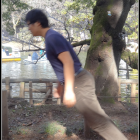未完でIFな物語
僕はゲンロンカフェの壇上に上がり、椅子に座った。そして会場を見渡す。そこには塾生たちが椅子に座って僕のことを見ている。何をしゃべるのかを期待して。僕は何故ここに座っているのだろう。そのことがとても不思議なのだ。普段この席に座れるのは佐々木敦塾長に選ばれた上位3名だけなのに。
このような事態となったのは、時を少し遡る。
年の瀬に行われたゲンロン総会。その中で新芸術学校と僕たち批評再生塾の麻雀対決が行われたのだ。その麻雀対決に勝利者に無料でゲンロンカフェでのイベント開催権を与えられるという。勝利を得ようと僕たちの中で事前に予選を行った。そして予選を勝ち上がった遠野よあけさんと批評再生塾で評価をほしいままにしている吉田雅史さんが代表として決まったのである。
だが、それは新芸術校も同じで精鋭を送り込んできたのだ。中野のネオン街にある五反田アトリエで芸術校と批評再生塾の意地と意地のぶつかり合い。勝負は一進一退を繰り広げる。3時間という熱戦。周囲で見守る人々もその熱戦に目を見張り、言葉が少なくなっていく。
「よし、勝った!」
遠野さんがそう静かに宣言する。その勝利がじわじわと応援していた塾生に広がっていく。
「やったぞ!」
そういう声も聞こえてきた。
ひとしきりの熱狂が過ぎ去ると、新たな問題が発生したことを僕たちは痛感させられた。
「何をしたらいいのだろう」
それが思いつかないのだ。僕たち塾生は言葉を紡ごうとしている。紡ぐことで森羅万象を言語化できると信じて。だが、僕たちの紡いだ言葉は2週間に一度、批評再生塾に掲載されている。別の場所で紡いだ言葉も文章や動画の形ですでにネット上で公開されている。改めて発表するものがないのである。
「車座になって、色々語ろうか」
「それ、わざわざ聞きに来てくれる人がいるか?」
「そうだよなぁ」
「佐々木敦さんに来てもらって、我々と座談会をしてもらおうか」
「それだと佐々木さんのイベントになってしまうよ」
「それはそれ、これはこれ。佐々木さんには客寄せパンダになってもらおう」
「批評家になろうと思ってきているのに、結局は佐々木さん頼みだなんて、なんか悲しくない?」
「いやいや、まずは顔を覚えてもらわないことにはそんなことも言ってられないでしょう」
ああでもない、こうでもないと批評を書くとき以上に頭を悩ませる塾生たち。卒業して独り立ちをした時、同じような悩みに直面する。プロとしてやっていきたいのなら、読者になり得る人々にプロとして認識させることをしなければならない。今回はとてもよい練習となるのだろう。悩むのもまた当然なのだ。
うんうんと頭を付き合わせて検討している中、僕はぽつりと呟く。
「ビブリオバトルなんてどうだろう」
「なんだ、それ?」
聞き慣れない言葉に別の塾生が質問する。その他の塾生も同様に僕に視線を向ける。
「紀伊國屋でやっているのを見たのだけど、一般の人が自分の本を紹介するというものだった」
急に注目されて驚いた僕は、自信なさげに答えるしかなかった。
「それ、面白いの?」
面白かったはずだった。僕は必死にルールを思い出す。
「たしか、複数人が登壇するんだったかな。そして1人の持ち時間は5分で会場との質疑応答が3分。それで紹介したい本の説明をする。最後に会場の投票で誰の紹介した本が一番読みたくなったのかを会場に集まった人の投票で決めるという感じだったと思う」
「うん、それで合っている」
スマホをポチポチやりながら、別の塾生が答えてくれた。
「紹介する本は自由に選んでいいんだね。でも、勝つためには観覧者の好みを考慮しなければならないようだ。その選択って批評的戦略といえるでしょう。それに選んだ本がどのように良いのかを説明するのって批評行為そのものでしょう」
「ビブリオバトルいいんじゃないの」
塾生がひとりひとり、ビブリオバトルに乗り気になってきた。
「自分たち主催のイベントとなるし、それぞれの塾生の個性も紹介することができる。それにさ、たとえ失敗したとしても、それはイベントに花を添えることにもなる」
やらない理由はないだろう。塾生たちの想いは一つとなった。そして他の塾生より上回るトークをしてやろうと心の奥で思いつつ、自分たち主催のイベントを行えることにとてもワクワクしているのだった。
さて、何の本を紹介しよう。僕は新宿のブックファーストに行った。批評再生塾の塾生がビブリオバトルをやるのだ。当然批評関連の本を用意するだろう。それに話題性のある本の方がさらにいい。
「うわ、すごいのができているぞ」
さやわか先生の『キャラの思考法』と並び、批評ふたたび!という書店員による批評関連の棚ができあがっていた。僕はその棚に平積みされた本を手に取った。
「そう、これこれ。これに決めた!」
批評再生塾、新芸術校の母体であるゲンロンが発売した雑誌『ゲンロン1』である。特に気になるのが特集の昭和批評の諸問題1975-1989である。批評とは何かを最初に東浩樹さんが語ったとき、自分は歴史の中でどこに立脚するのかが大切だと言っていた。その流れを知れるというのはとてもありがたい。どのような事が書かれているのかをとても楽しみにしつつ『ゲンロン1』をさやわかさんの本と共に購入したのだった。
読み始めると、滋養はあるのだけどちゃんと咀嚼をしないと飲み込めないなという濃厚な文章に、ちゃんと栄養として吸収できるのかなぁとおののいてしまう。なので、なかなか読み進められない。
「うーん、ちゃんと紹介できるのかなぁ」
僕は不安に思ってきた。でも、今さら本を変える余裕はないのだ。
「あれ、ここはわかるぞ!」
楽しみにしていた昭和批評の諸問題1975-1989を読み始めると、討論を元にしているためか、とても分かりやすい。
「わかる、わかるぞ!」
今まで批評の巨人として紹介されてきた柄谷行人、蓮實重彥といった人物が批評史の中でどのような役割を演じてきたのかが端的に紹介されている。そのことにより、彼らの言葉以上に何をしようとしてきたのかがよりはっきりと分かってくる。分かりやすくするために選択をして今までの歴史を切断してしまったこと、そのことにより批評というものが狭いものとなってしまったことが語られる。
「わかる、わかるぞ!」
その歴史の中で批評を読んで勝手に新たな流れが生まれる私生児の話が語られる。直系でなくても継続はされていくのだ。そのために、多様性が大切なのかもしれないなぁ。
「わかる、わかるぞ!」
でも、批評の歴史というけれど、劇評にかなりの功績を築いた扇田昭彦さんが出てこないんだなぁ。赤テント、黒テントなどの証人としての本とかかなり発行しているのに。でも、扇田さんがまだ生きていてそのことを聴いたら、
「ははっ、僕は批評家じゃありませんよ」
とニコニコしながら言ったんだろうなぁ。そして『海燕』とか出てくる。まさかこんな所に出てくるなんて。僕はもの書きを目指している。そのため、批評再生塾の他に小説教室にも通っている。その小説教室の先生の根本昌夫先生は海燕の編集長をしていた。あれ、意外に僕は批評の世界に親と言える人が多くいるみたい。
続く。
文字数:2908