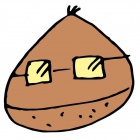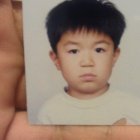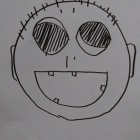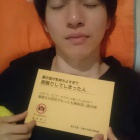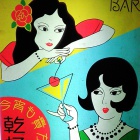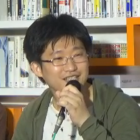六本木的な、あまりに六本木的な
~この文章はAからQまでの一定の流れを持った17つのブロックから成り立っているが、それぞれにおいて不自然に脈絡が無い部分がある。もしくは唐突に過去の話題について参照される場面がある。その場合には語の横にカッコで付けたブロックの番号にハイパーリンクを飛ばして読めば、全体の構造を把握することが出来る。もちろん、最初から最後までを流れに沿って読んでも理解することは可能である~
A
またべつの話から始めようと思う。
(『三月の5日間』の)「街区」について考えるなら、やはりここでもまた、なぜそれは渋谷だったか疑問が浮かぶ。六本木で出会った男女がセックスを目的にホテルを探すなら、そもそも六本木にもホテルはあったのではないかと奇妙に感じるし、少し歩けば、赤坂まで行っても円山町の距離とは大差がない。しかし、渋谷でなければならなかった。六本木という街区もまた、「東京の中のアメリカ」という文脈で語ることができ、やはりセクシーな街区、ストリートの魅力を備えているものの、それはまたべつの話になる。
(宮沢章夫「渋谷が語るもの」、『表象・メディア研究 第7号』所収)
B
『三月の5日間』は演劇団体チェルフィッチュの岡田利規が2004年に上演した演劇作品だ。
渋谷、円山町のラブホテルに閉じこもるミノベとユッキー(C)、ミノベの友達であるアズマと、アズマとたまたま映画館で知り合うことになるミッフィー(Q)、そしてイラク戦争反対のデモに参加するイシハラとヤスイが過ごすそれぞれの3月の5日間が描かれる。
そしてもう一人スズキ(N)という人間がこの戯曲には登場する。いや、登場という表現はどうだろうか。スズキは劇中で確かにしゃべっているのだが、最終的には話題の中心にならない、不思議な存在だ(N)(O)。
C
チェルフィッチュの演劇は「超口語」と呼ばれ、日常会話の中で実際に有り得る言い間違いや、脈絡のない話題などがそのまま台本になっている。例えば『三月の5日間』の冒頭。
男優1 それじゃ『三月の5日間』ってのをはじめようと思うんですけど、第1日目はまずこれは去年の三月の話っていう設定でこれからやっていこうと思ってるんですけど、朝起きたら、なんか、ミノベっていう男の話なんですけど、ホテルだったんですよ朝起きたら、なんでホテルにいるんだ俺とか思って、しかも隣にいる女誰だよこいつ知らねえっていうのがいて、なんか寝てるよとか思って、っていう、
岡田が言葉や身体に対して行うこうした操作は、日常生活の中で、確かにそこにあるが忘れ去られているものを拾い上げ、強調するという手法を取っている。
ミノベとユッキー(B)は、第1場で六本木のライブハウスにいる。偶然にもそのライブハウスで知り合うことになった二人はミノベの言葉で言う「即マン」をするために「タクって」六本木から渋谷へ向かう。「タクって」とは「タクシーを使って」という意味だが、この流れは不自然だ。六本木から渋谷までは2キロ以上ある。タクシーで向かったとしても5分ないしは10分はかかる距離だ。ミノベはライブ中にビールを2杯飲んでいることになっている。酔った勢いで「即マン」するとしてもこの移動距離はあまりにも長すぎはしないか。更に渋谷には既に戯曲の設定である2003年時点で渋谷O-westなどのライブハウスが立ち並んでいた。しかもこのO-westはミノベたちが宿泊していたラブホテルがあるとされる円山町の真ん中に位置している。
戯曲上の流れを自然にするならば全ての舞台設定を「渋谷」という独特の記号を背負った土地(J)にすることは出来なかったのか。ミノベとユッキーは渋谷にあるライブハウスで偶然知り合う。そしてその流れで近くにあったラブホテルに入る。これではだめなのか。しかし岡田は「六本木」について過度に執着する。なぜ第1場の最初で六本木の地理について詳細な説明がなされるのか。
えっと、六本木で、まだ六本木ヒルズとかって去年の三月ってまだできる前の、だからこれは話で、ってところから始めようと思ってるんですけど、すごい今って六本木の駅って地面に地下鉄から降りて上がって、それで上がったら麻布のほうに行こうとか思って坂下るほう行くじゃないですか、そしたらちょうどヒルズ出来たあたりの辺って今は歩道橋じゃないけどなんて言うかあれ、一回昇って降りてってしないと、その先、西麻布の交差点方面にもう行けないようになっちゃったけど今は、でもまだ普通に一年前とかはただ普通にすごい真っ直ぐストレートに歩いて行けたじゃないですか、
E
六本木という街は六本木ヒルズの登場によってどう変わったか。
六本木ヒルズのキャッチコピーは何であったか。それは「六本木人、生まれる」である。その運営母体である森ビルはその土地の場所の歴史に関係なく、ある建物を決められたコンセプトで建てていく。それは六本木でもいいし、虎ノ門でもいいし、上海でもいい。その土地の歴史(K)を塗り替えるように森ビルはその空間戦略を進める。そして「六本木人」という新しい人種を作るのだ。
F
「三月の5日間」において六本木という街は、異質な存在として映る。舞台の大半は渋谷であるにもかかわらず、六本木の街区の移り変わりについて、長々と語られる。六本木について語られる部分を詳しく見てみよう。
えっと、六本木で、まだ六本木ヒルズとかって去年の三月ってまだできる前の、だからこれは話で、ってところから始めようと思ってるんですけど、すごい今って六本木の駅って地面に地下鉄から降りて上がって、それで上がったら麻布のほうに行こうとか思って坂下るほう行くじゃないですか、そしたらちょうどヒルズ出来たあたりの辺って今は歩道橋じゃないけどなんて言うかあれ、一回昇って降りてってしないと、その先、西麻布の交差点方面にもう行けないようになっちゃったけど今は、でもまだ普通に一年前とかはただ普通にすごい真っ直ぐストレートに歩いて行けたじゃないですか、
G
六本木通り(F)が現在の形に整備されたのは、1964年の東京オリンピックを前にしてのことである。六本木通り(F)は渋谷と六本木を結ぶ道路である。ミノベとユッキー(B)(C)はこの六本木通りを「タクって」渋谷へと向かう。何気なく使われるこの道路は東京オリンピックや、六本木ヒルズ建設のたびに(F)更新されているのである。
H
2017年の12月、『三月の5日間』(B)は再演される。初演から既に13年。東京も変わったし、また変わるだろう。例えば次のように。
「Fashion press」2017年9月30日の記事「東京の再開発スポットまとめ――来たるオリンピックに向けて」の抜粋から。
◎渋谷駅の風景が圧巻の変化!未来の“SHIBUYA”に向けた再開発進む
【再開発概要】
・道玄坂一丁目駅前地区第一種市街地再開発事業
施行地区:東京都渋谷区道玄坂一丁目2番地・8番地
階数:地上18階、地下4階
高さ:約110m
用途:店舗、事務所、駐車場等
・渋谷駅桜丘口地区(桜丘町1地区)開発計画
所在:東京都渋谷区桜丘町1番地、2番地、3番地、及び4番地、8番地の各地内、他
用途:事務所、店舗、住宅、生活支援施設、起業支援施設、教会、駐車場等
開業予定:2020年
◎渋谷パルコが複合施設として生まれ変わる
◎渋谷・宇田川町に新たな商業施設オープン
開業:2016年秋頃 ※予定
住所:東京都渋谷区宇田川町83番4、5、6
構造・規模(予定):地下2 階/地上10階
◎宮下公園が東京オリンピックに向け、リニューアル、商業施設も
開業日:2019年8月
・新宮下公園(施設屋上部分)
・駐車場(現状の都市計画台数243台以上)
・民間施設(商業施設、宿泊施設)
I
かつて宮沢章夫は「渋谷が語るもの」というエッセイの中で次のように書いた。
岡田利規が(『三月の5日間』で)書こうとしたのは、「小さな死」の堆積である。
宵闇せまる円山町をそぞろ歩いていると、ああ、道の両脇に積み重ねられた小部屋の中で、今夜もたくさんの男女が、セックスという「小さな死」にむかって、性愛の儀式を繰り広げているのだなあ、という感慨に打たれる。セックスをして、オルガスムに達するたびに、男も女も、生きたからだのまま、少しだけ死のリアリティに触れるのである。
(中沢新一『アースダイバー』)
宮沢は「なぜ、『三月の5日間』は渋谷が舞台なのか」という問いを考え、ミノベとユッキーが古来から「小さな死」を堆積する場所であった渋谷という土地の「土地の記憶」に引き付けられているからなのだと指摘した。
そして今考えているのは、それとちょうど反対のこと、「なぜ六本木なのか」(A)ということだ。そして六本木もまた一つの「土地の記憶」(K)に引き付けられているのではないか。そしてそれが『三月の5日間』がなぜ六本木から始まるのかを指し示しているのかもしれない。
J
渋谷がパルコの空間戦略によってまるで外国であるかのような装飾が街全体をあげて施されたことは北田彰大の『広告都市東京 その誕生と死』で詳細に述べられるが、その異国を装った渋谷は90年代になって凋落する。渋谷を特別たらしめていたスペイン坂やオルガン坂と言った外国風の通り沿いに多くのチェーン店が立ち並び、郊外に見られる風景と変わらなくなってしまったからだ。
「広告都市」もしくは「特別性」という記号を背負った渋谷は死んでしまった。そういえばユッキーとミノベは劇中でこんなことを言う。
「なんか、すごい渋谷なのに、なんか、旅行に来たみたいですごい楽しいんだけど」って言って、ミノベくんは「あ、ほんと」って言って、「あ、でも俺もなんか分かる」って言って、そのときはもう二人ともホテルにいたんですけど
K
六本木の「シャンティ」は日本に出来た初めてのイタリアン・レストランである。「シャンティ」には1960年前後に多くの文化人、業界人が集い、当時としては珍しかった異国の文化の中心地として賑わっていた。当時日本人にとって最も身近な異国であったアメリカの文化は六本木を中心として発信されており、当時の日本人にとって六本木は「異国の文化の中心地」であり、そして同時に「特別な場所」でもあったのだ。
六本木が「東京の中のアメリカ」や「東京の中の異国」と呼ばれたのには、戦後まもなくGHQの軍人や官僚がそこに多く住んでいたという歴史があるからだ。そのためにアメリカンフードやその他多くの国々の料理を出すレストランが数多くオープンした。日本で初めて本格的なインドカレーを提供したレストラン「MOTI」もその一つだ。インドカレーと言えば、ミノベとユッキーもまた『三月の5日間』の途中でインドカレー屋に立ち寄るが、こうした本格的なインド料理屋の始まりは六本木にあったのだ。
このように六本木は多国籍な人種が集う街であった。渋谷においてパルコがまるでその街区を異国のように演出し始めた1970年代(J)の前、六本木は「東京の中のアメリカ」、「東京の中の異国」として存在していた。当時この街区に集った若者たちは「六本木族」と呼ばれ、そしてその50年後に森グループは「六本木人」を謳って六本木ヒルズを建てた(E)。
L
「シャンティ」という店名(K)は、当時もっとも高級とされていた赤ワインの名前にちなんでいるが、当時珍しかったこのワインも現在では全国に広く分布するファミリーレストラン「サイゼリヤ」にて税込み価格1080円でボトル一本を飲むことが出来る。六本木を特別たらしめていた異国の文化である「シャンティ」という固有名詞も既に全国にまんべんなく広がっている(P)。
M
2010年代、ハロウィンは一般化した。
それは渋谷のスクランブル交差点でのみ見られる特異な現象ではなく、他の都市、池袋、原宿、そして六本木でも既に一般的なものになったのである。既に現在、多くの街を「異国」の文化が歪曲した形で包み込んでいる。そしてそれが戦後最も早い形で日本にもたらされた六本木の特別性は失われている。もう、東京の都市をある特徴で峻別するということ自体が意味を成さないのかもしれない。「三月の5日間」を読み解きながらあえて固執した「六本木的なるもの」は2017年の現在、既にして壊れている。
ところで日本人とハロウィンが初めて出会った場所は、1983年に開園した東京ディズニーランドであった。ディズニーランドは1997年にハロウィンイベントを始めて開催している。1950~60年代において六本木が「東京の中の異国」の象徴であった(K)とするならば、その後に日本人に「異国」的なるものを提供したのは1970~80年代、パルコによって装飾された渋谷(J)と1983年に開園したディズニーランドだろう。
しかしそうした異国的なるものはハロウィンの例でも確認したように既に多くの街に遍在している。ハロウィンは渋谷の特権ではない。幽霊に変装する特別な儀式は日本においてどの街でも見られるものになったのだ。
N
スズキ(B)については以下のように語られる。
男優5 スズキっていうのはすごい体の柔らかい人なんですけど、でも体が柔らかいことはあんまりっていうか全然関係今からする話とは別にないんですけど、その前にここでちょっと十分ぐらい休憩にしようかなっていうのがあって、
男優5 さっきアズマがミノベとライブハウスで別れてから、その翌日にアズマと会ったっていう、アズマのかつてのバイト仲間だったっていう人がちょっと出てきたと思うんですけど、(いつのまにか)彼が一応、今話題のっていうか、これから話題にしようとしてるっていうか、話題って言ってもそんなたぶん盛り上がらないと思うんですけど、でもまあ今言ったその彼がスズキっていうことではあるんですけど、
まさにスズキは観客にそれと知らされないまま、幽霊のようにふっと姿を現し、そして消えていく(O)。
O
畢竟、スズキとは六本木のことなのではないか。
六本木は第1場のシーンにちらりと出てきて彼らはもうそこに戻ることはない。しかしその六本木はかつて「東京の中の異国」としてあり、六本木周辺の再開発により(E)(G)「既にない」世界である。その「東京の中の異国」は70~80年代に渋谷に移り、最終的に現在ではもう異国からもたらされたものが日常の一部と化し、そこにある「特別性」は見いだせなくなった(L)(M)(H)。
すでに「特別性」を帯びた街はないのだ。そして2020年の東京オリンピック(H)を前に再開発は更に進む。六本木は現在の六本木ヒルズを中心とする姿の前に、「東京の中の異国」としてあった(K)。
『三月の5日間』の中に出てくる多くの場所は、「すでにない」。それはかつての六本木(K)であり、劇中で言及される具体的な店の数々(アンミラ、ロッテリア……)であり、今は死んでしまった渋谷(J)である。しかしそれは完全に存在しなかったものでもない。なぜならばそれは幽霊だからである。
P
『三月の5日間』は、『わたしたちに許された特別な時間の終わり』というタイトルで小説になっている。このタイトルからも分かるように、『三月の5日間』で強調されるのは「特別な時間」だ。そして今僕たちが注目しているのはその「特別な時間」の舞台となる「場所」だ。
そしてその「場所」はミノベとユッキーが見た「外国のような渋谷」のように「特別な場所」である。それは移ろいやすくすぐに消えてしまう。
では六本木は?
時代によってその性格は異なれ、六本木は常に選民思想的な場所であった(K)。「特別な場所」を作ってしまう磁場が確かにそこにはある。しかしその特別性、つまり戦後において六本木が保持していた「東京の中のアメリカ」という「特別なもの」は現代において表面上、すでにどのような街にも拡散している(L)(M)。一方で六本木はそうした異国的なものが拡散した後にもその「選民思想性」が「六本木族」から「六本木人」に至るまで「幽霊」のように存在し続けているのだ(O)。「六本木人」という言い回しの中にそれは発見することが出来る。
そしてチェルフィッチュの演劇を貫く幽霊性(C)。岡田利規は忘れさられた身体や言語のノイズ(しかしそれは確かに存在している)をその演劇に導入すると共に、六本木に住み着く幽霊をも『三月の5日間』の中に取り入れる。その幽霊は「特別な場所」の幽霊である。だから『三月の5日間』には六本木と言う街が必要だったのだ。それは渋谷という異国を装った街(J)よりも前に異国性を、「特別な場所」というポジションを保持していた六本木の宿命だったと言える(G)(K)(O)。岡田利規もまた、六本木の「土地の記憶」に引き付けられたのである。
Q
もう一つ、渋谷でもなく、六本木でもない、また別の地名がある。
秋葉原だ。『三月の5日間』でもいくつかの箇所でそれについて言及が成される。秋葉原は2000年代から「オタク」の街として知られるようになった。『三月の5日間』で言えば、電子空間に閉じこもるミッフィーは典型的な「オタク」かもしれない。では、なぜそれは渋谷と六本木の間に挟まれて、『三月の5日間』に存在しているのか。ヒントはやはり「土地の記憶」としての「幽霊」にあるのではないか。電気街からオタクの街へ。この変化は『三月の5日間』においてどのような意義を担っているのか。しかしそれはまたべつの話だ。
文字数:9225