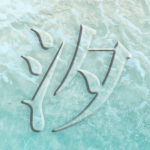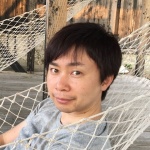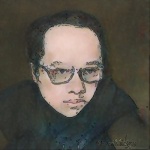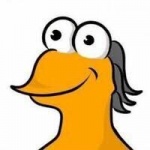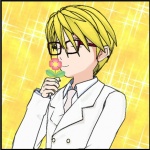梗 概
ロボ棄て山のおじいさん
・遠い未来の昔話。絶滅期のヒトに関する話の一編である。辺境に長い間一人で住んでいたおじいさんが、自分の作ったロボットと一緒に暮らし、なくなるまでの話だ。
・おじいさんは廃コンテナを住居にして、暮らしていた。この辺りは、かつて機械ロボットのリサイクル工場やスクラップ工場が数軒あったが、今は廃墟となり、不要なロボット全般を投棄するロボ棄て山になっていた。数十キロ先にヒトの過疎集落が一つあったが、ロボ棄て山の方まで立ち寄る住民は誰もいなかった。
・月に1回ほど、巨大なダンプカーがロボ棄て山にやってき、既に高価な部品の抜き取られた機械ロボットやヒト型ロボットが大量に廃棄される。がけ崩れのような、大きな音が夜更けに聞こえると、おじいさんは目を覚ます。朝になると、決まっておじいさんは、ロボ棄て山へ向かい、部品を選定して拾い集め、台車で家へと運んでいく。家に戻ると、コンテナの前でヒト型の小型ロボット(小人)が、主人を待つ犬のように待っている。
・絶滅期のヒトは全て、小人によって、居住地および住居の維持管理、ヒトの栄養、体調、情緒、記憶、生殖などを世話されていた。そのため、全てのヒトの居住地、種、属性は把握されているが、ロボ棄て山のおじいさんだけは違った。いわばホームレスだった。おじいさんの周りいる小人はどれもヒト型といえるものはなく、顔や体もバラバラで醜く、突然動きが止まったり、急に動き出したり、いずれも通信できないようなひどい代物ばかりであった。
・おじいさんは、小人たちによく話しかけた。おじいさんは小人のことを「子ども」と呼び、一人一人に名前を付けていた。おとり。ことり。そとり。ととり。のとり。ほとり。時々、「体を見せてごらん」と医者のように、小人の修理をしたり、作り直したりしたが、直ったためしは一度もなかった。
・おじいさんは毎朝小人たちと一緒に、ロボ棄て山の少し奥にある川べりまで散歩にいった。数十年以上誰も寄り付かない川は葦をはじめ雑草が生い茂り、川面は全く見えなかったが、川のそばまで来ると風が変わるのが感じられた。おじいさんはそこで散歩を終えると家へ引き返し、必ず午後から小人たちに“授業”をした。昔話を話すこともあったが、「愛すること」「助けること」「死ぬこと」「生きること」「友達」「恋人」などについて長話しをした。しかし、不良品ともいうべき小人たちに、ヒトの音声がちゃんと記録されているのか、そもそも音声自体が入力されているかどうかも曖昧だった。
・ある時、そとりとほとりが大喧嘩をして、ほとりを壊してしまうことがあった。おじいさんは、ほとりの一部を土に埋め、残った一部をそとりの体に付けることにした。おじいさんはぶつぶつ言いながらほとりを埋め、静かに泣いていた。小人たちはおじいさんをじっと見ていた。
・一年後、おじいさんはなくなる。通常のヒトの死では、ヒトのサンプルを取り終えると、死体はそのままに小人はすぐに別の居住地へ移るのだが、この小人たちはおじいさんを土に埋め、小人たちのエネルギーがなくなるまでそこにとどまっていたという。
文字数:1277