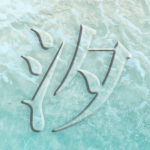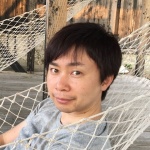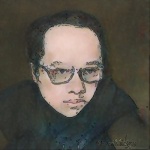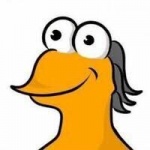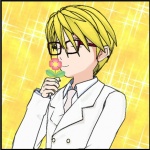梗 概
環世界より
+3℃の温暖化が進んだ未来。生物多様性は大きく損なわれ、地球の種の三割がすでに失われた。干ばつと砂漠化が進み、人類は都市に集約され、かろうじて文明を維持していた。基礎研究など「余白の営み」は切り捨てられ、生存優先の社会になっていた。
地球物理を専攻していた久遠は、博士課程を修了後、研究職のポストが得られず食料生産の企業に就職した。夢を手放し、日々の仕事に埋もれていた。
彼のもとに、ある日、訃報が届く。かつての親友であり、同じ研究室で未来を語り合った志摩が亡くなったという。
数日後、小さな包みが届く。中には鍵と座標のメモ、そして短い手紙が添えられていた。
久遠へ
地球は終わったように見える。でもそれは人間の目に映る世界だ。
僕はこの場所で、もうひとつの世界を見た。
――志摩
座標を衛星地図で調べると、山岳地帯の頂上にある旧式の天文台だった。志摩は研究資金も支援も絶えた中で、ひとり環境観測を続けていたのだ。
誰にも使われていないその施設へ、久遠は三ヶ月の休職をとって向かう決意をする。
天文台は、風と岩に囲まれた孤独な場所だった。水道はなく、通信も衛星電話のみ。霧からわずかに水を濾過する装置があるが、故障したら命はない。
呼吸や汗から水分を回収するスーツを着て、久遠は持参したレーションで生活を始める。
動物の気配はない。風が地表を這うだけの土漠だ。
天文台には志摩の観測ノートが残されていた。紐綴じのノートに鉛筆でびっしりと書かれた記録と考察。几帳面な筆跡は学生時代と変わらず、久遠は思わず笑みをこぼす。観測機器も自動で動き続け、温度、湿度、気圧、放射線、地磁気などのデータが今も蓄積されていた。
久遠は規則正しい生活を送る。毎朝ログを確認し、昼はノートを読み、夜には志摩が棚に遺していた安物のスコッチを少しだけ口に含む。志摩と対話するような時間だった。
ノートを読み進めていると、一週間分だけ記録が抜けている箇所があった。ちょうど五年前。
その後から、志摩の記述は微かに変化し、「人類の活動が弱まり、環境は回復の兆しを見せているのでは」と書かれていた。
ある朝、空に分厚い雲がかかり、風の匂いが変わった。観測ログには「五年ぶりの降雨」と記録された。雨は七日間続き、三日目の夜、蛙の鳴き声が響き始める。
久遠が外に出ると、硬く閉じていた土の割れ目から草が芽吹き、橙色の花が咲き乱れ、足の短い蛙たちが歩きまわっていた。
蛙たちは五年に一度、雨とともに時間が動き出す。
彼らにとって、この地は終わってなどいない。「環世界(Umwelt)」――それぞれの種が持つ独自の知覚と時間。その世界が、確かにここにあった。
久遠はスーツを脱ぎ、雨に濡れながら地面に膝をつく。地球は終わったように見える。でもそれは人間の目に映る世界にすぎない。
その夜、彼は蛙の声に包まれて眠る。夢の中で、百年後の地球にも、静かに雨が降り続けていた。
文字数:1192
内容に関するアピール
「辺境を描くSF」というお題に対し、地理的な“遠さ”ではなく、知覚と時間の“遠さ”にある辺境を描こうと思いました。
描きたかったのは、終末を迎えたと思い込んでいるのは、あくまで人間の時間と視点においてであって、他の生命にとってはまったく違うリズムと世界が流れているという事実です。
逆に、人間のとっての楽園が生物にとっては感覚汚染になっているという例もあるので、そのテーマでも書いてみたいと思いました。
文字数:199
環世界より
「本日の予想最高気温は35℃を超える見込みです。熱中症にご注意ください」
枕元のスピーカーが、いつもの声で繰り返す。都市部の温度は平気で40℃以上になるようになっていた。まぶたの裏に光が滲み、しばらくして僕は片目を開けた。暑い。まだ朝なのに、Tシャツは湿っていた。首元の不快感に耐えかねて、起き上がる。
「久遠、出勤の時間です」
AIアシスタントの声が続く。どこか抑揚が足りないその口調にも慣れてしまった。
「今日のニュースを教えて」
目を擦りながら呟くと、応答は淡々としていた。
「本日、15種の動植物が新たに絶滅登録されました。砂漠の面積は、先月比で0.1%増加。その他、大きなニュースはありません」
なにが“大きなニュース”ではないのか、最近ではもう判断もつかなくなってきた。
僕はいつも通り顔を洗い、食事の代わりに栄養ゼリーを一本飲み干すと、ラボへ向かった。
昨日の夜仕込んだ人工肉は培養液の中で、静かに大きくなっていた。ビッグテックの社長が鶏は飼料からタンパク質への変換効率が一番いいと力説していたが、それは昔の話だ。今では、虫の数も減り、多くの植物も枯れてしまった。こうなると、鶏も成長できない。職場では、合成肉の培養とタンパク質収量の確認作業が続く。鶏肉と同じ成分だ。清潔な白衣、無菌室、冷やされた空気。それらに包まれた空間では、世界の終わりなど存在しないように思える。
だが、それは錯覚だ。帰りの電車の車窓に映る街は、乾ききった地面と、空を遮るダストフィルターに覆われている。クーラーなしでは、生きられない環境に人間がしてしまった。
目に映るものすべてが、何かを失った後の世界に見えた。
*
ラボを出て、自宅に戻ったのは夜9時過ぎだった。一人暮らしの部屋には、机と本棚、ベッドしかない。 狭い1DKのマンションだ。しかし、クーラーさえよく効けば問題ない。
冷蔵庫から冷凍のスープパックを取り出し、電子レンジに入れる。その間に、携帯をネットワークに再接続する。通知が3件。スクロールすると、見覚えのある名前が目に留まった。
志摩。
その文字を見た瞬間、胸の奥が苦しくなった。
メッセージは、短かった。
――志摩 了、逝去のお知らせ。通夜および葬儀は近親者のみで執り行われました。
手からスマートフォンが滑り落ち、床に当たって鈍い音を立てた。
志摩とは、大学から大学院までを共に過ごした。同じ地球物理学専攻で、彼は気象と環境変動、僕は地殻変動と気温の相関を研究していた。興味の領域が近く、自然と行動も共にするようになった。僕が経済的理由で研究者の道を断念し、企業に就職したあとも、彼は博士課程に残った。国の政策の中で、ほとんどの基礎研究への費用は削減されてしまった。物理学など理学領域への投資は少なくポストドクターのポジションも限られている。志摩はそんな中、国際学会への論文投稿を続け、なんとか研究費を稼いでいた。
最後に会ったのは、大学院の送別会の夜だった。
「いつか、また一緒に研究しよう」
彼はそう言って笑った。その後、連絡は自然と少なくなっていった。僕は、彼の論文が載った学会誌を読むたびに、少しだけ胸が詰まる思いをしていた。どこかで、彼が失敗すればいいと思ったことさえ、あった気がする。あれから7年、会っていない。
そして、今日――もう二度と会えなくなってしまった。この世界から志摩が消えてしまったことに現実感がわかない。
スープが温まったと知らせる音がした。飲む気にはなれず、冷めるのを待たず冷蔵庫に戻した。
**
その数日後のことだった。
帰宅すると、アパートのポストに封筒が入っていた。差出人の記載はない。クリーム色のシンプルな封筒だ。中には、折りたたまれた便箋と、小さな金属の鍵が一つ。便箋を開くと、見覚えのある筆跡が目に入った。
久遠へ
地球は終わりつつあるように見える。
でも、それは人間の目に映る世界だ。
僕は、この場所で、もう一つの世界を見つけた。
――志摩
そして、鉛筆で書かれた数字の列。
緯度と経度と思われるそれは、衛星地図で調べると、ある山岳地帯の頂上を示していた。
地図には「旧・霞ヶ峰天文台」と記されている。検索をかけてみると、10年以上前にウェブ更新が停止しており、現在は廃止施設との情報だけが残っていた。どうやら、税制改革の一環で閉鎖されたままになっているらしい。
僕はディスプレイに映る灰色の衛星写真をじっと見つめた。その奥に、志摩が最後に見た世界があるのだろうか。
何かが、僕をそこへ向かわせようとしていた。
***
翌朝、地図を何度も確認したあと、天文台に最も近い集落の名前を頼りに、現地の管理人に連絡を取った。
電話口に出たのは、年配の男性のようだった。僕が「志摩了の友人です」と名乗ると、彼は一瞬の沈黙の後、静かな声で言った。
「そうか、来ないと思ったら。志摩は元気か?」
彼が亡くなったことを伝えると、しばらく沈黙があった。
「残念だ」
その声には、本当に友人を亡くした悲しみがあった。そして、彼は、少しずつ語り始めた。
志摩は、大学からの支援が途絶えたあとも、あの天文台に残り一人で観測を続けていたという。資金も人手もない中で、機材の修理や最低限の生活を自力でこなしていたらしい。
「月に一度、食料を届けていたんだよ。あの頑固者に頼まれてね」
老人は少し笑いながらそう言った。
「いつもビスケットにチーズ、果物を少し。志摩は何も言わないが、リンゴが好きだったんだ」
天文台に滞在したい旨を伝えると、彼はしばらく黙ったのち、静かに答えた。
「君が彼の友人なら、構わん。ただし、水は少ない。山岳保険に入ること。そして、砂漠用のスーツを必ず用意すること。それが条件だ」
僕は頷きながら、自分の銀行口座の残高を思い浮かべた。すぐに使える現金は120万円。決して十分とはいえないが、行ける。特に趣味もなく、何かあった時のために貯金しておいた。その時が来たのかと、思った。
その日の夕方、僕は職場に電話をかけた。
「両親の体調が思わしくなくて……三ヶ月、休職させてください」
上司も労務担当も露骨に嫌そうな声を出したが、最終的には了承してくれた。帰ってきたら、ポストがなくなっているかもしれないが、それはその時に考えようと思った。皺寄せが行きそうな同僚に、謝罪と引き継ぎ手順をメールで送信した。
切符を手配すると、心の奥に重く沈んでいた何かが少しだけ軽くなった気がした。
山岳装備をレンタルし、下着と最低限の生活用品をリュックに詰める。
そして、迷うことなく一冊の文庫本を押し込んだ。志摩が何度も語っていた、萩原朔太郎の『猫町』だった。異世界に旅に出るには、この本が似合うと思った。これから、誰もいない場所に行くと思うと活字が必要になる。本が良いのは、電源がいらないことだ。
****
待ち合わせの駅には、例の管理人が迎えに来てくれた。電話口の声でイメージしていたよりも年配だった。駅は、ただのコンクリートの台があるだけで、誰も利用している気配はなかった。この駅は、山の中腹に位置している。
山道を下りきった先に、小さな集落が見えた。
家々はまばらに点在しており、密集するというよりは、土地の凹凸に寄り添うように建っていた。灰色の屋根は風にきしみ、壁の塗料はところどころ剥がれていたが、それでも煙突からは細く煙が上がっていた。
遠くには、青みを帯びた山の尾根がいくつも連なっていた。雲の切れ間から差し込む陽に照らされて、稜線が静かに浮かび上がっている。麓には、かつての畑が広がっていた。土は乾いてひび割れ、その風景にはそぐわない半透明のドームが点在していた。かつて耕作地だった場所に、ドーム状の植物工場が建設されているのだった。
集落には人の気配はあったが、姿はあまり見えなかった。道端のベンチには、誰かが置いたままの麦わら帽子が裏返っていた。
挨拶もそこそこに、軽トラックに乗り込む。山道を進むにつれ、舗装は途切れ、土の地肌が剥き出しになっていく。ガタガタと車が揺れる。ガソリン車の特有の音に、本当に遠くに来たのだと実感させる。
空には、薄く乾いた雲。風は強く、遠くの雲が流れていくのが見えた。標高が上がるにつれ、気温は10度以下となりかなり冷え込む。
やがて車が停まり、彼は無言で後部を開けた。食料の箱を取り出すと、それを六脚バギーに積み替えて言った。一月分の食料だ。バギーは車輪タイプではなく、六足の足が生えている首のない犬を思わせるデザインだ。サイバネティクスにより、足場が悪い環境でも安定して資材を運ぶことができる。動力部分は、山岳用のため、ガソリンで動くエンジン式だ。電力タイプより、細かい制御はできないが馬力がある。
「ここから先はバギーで、歩いて1時間ほどだ。また一月後に来る」
その一言を残し、彼は車に乗り込むと、何事もなかったように来た道を下っていった。
突然、世界は静寂に包まれた。バギーがゆっくりと歩き出す。
まわりには、風に削られた岩と、乾いた土ばかりの風景が広がっていた。足元の土は白っぽく、踏むたびに細かな砂粒が舞い上がる。植生はほとんどなく、わずかに岩陰に苔のようなものが張りついているだけだ。
空は灰色で、雲が低い。風は絶え間なく吹きつけ、耳の奥まで乾いた音が入り込んでくる。遠くには、尾根を連ねる山々がかすんで見えた。この場所には、人の痕跡も、時間の流れすらも感じられなかった。色のない場所だ。
バギーの後ろを歩きながら、足元の土を踏みしめる。風が吹き、舞い上がる砂が頬をかすめた。砂漠のように見えるが、すべて乾燥した土だ。地学講義で、土漠と習ったなと思い出した。
どこまでも同じような岩と土の風景が続き、GPSがなければ確実に迷ってしまう。一面同じ風景だ。目隠しをしてぐるりと回ったら、方向感覚を失い、このまま迷って死ぬかもしれない――そんな悪い想像が頭をよぎる。
ようやく、天文台らしき建物が視界に入った。錆びたドームと、崩れかけた観測機器の影。ドアを探し、志摩から届いた鍵を差し込む。ギイ、と音を立てて扉が開いた。ドアの塗料は所々剥げているが、塗り直した後があった。
中は薄暗く、冷たい空気が流れ込んでくる。バギーを中に引き入れ、扉を閉めた。
奥の一室だけが、明らかに手入れされていた。壁紙はところどころ薄く剥がれかけていたが、陽に焼けてやわらかく色づき、清潔さが保たれていた。空間は狭く、6畳ほどだろうか。天井は低く、声を出せば反響しそうなほど静まり返っている。簡易ベッド、机、書棚、ストーブだけがある。そして、部屋の正面には大きな二重窓があった。机が窓の前に設置されており、ガラス越しに外の風景がはっきりと見えた。雲が流れていく空、岩肌と草が混じる尾根、遠くの稜線。陽は低く、斜めに差し込んで、床に長い影を描いていた。窓枠の隅には断熱用のゴムが張られており、そこだけわずかに黄ばんでいた。他の部屋が埃と寒気に満ちていたのに比べて、この部屋だけは、驚くほど整っていた。整えられたというより、そのまま時が止まっていたようだった。
ここは、志摩が暮らしていた場所――彼が、ただ一人で、観測と生を重ねていた空間だった。
ストーブに灯油を入れ、マッチを擦る。炎が揺れる。空気が少しだけ生き返った気がした。
まずは水の確認から始めた。空気中の水分を濾過する装置が備え付けられていた。電源を入れると、機械はかすかに音を立てて動き出した。12時間で500ml程度。とても贅沢には使えない。
持参した砂漠用のスーツに着替える。スーツは身体に密着し、ある程度の体温調整と身体から出る水分を集めてくれる。スーツ内部の除湿フィルターから得られる水分も加えれば、1日1.5リットルほどは確保できそうだった。決して余裕はないが、命を繋ぐには十分だ。
万が一に備え、SOS用の衛星発信機をチェックし、バギーの燃料も確認する。ベッド周り3メートル以内に生存に必要なものは揃え、暗闇の中でも物の場所が分かるように配置を確認する。目を閉じ、水の位置、衛星発信器、鍵、ランタンを手探りで探せるか試す。一通りチェックを終えて、少し安心感が出てきた。
そして最後に、志摩の書棚を静かに開いた。
中には、大学時代によく使っていた糸綴じのノートが何冊も並んでいた。おそらく150冊ほどにあるだろう。表紙には、年と月。鉛筆でびっしりと書き込まれたページを開くと、そこには観測記録と彼の魂が詰まっていた。
気温、放射線量、雲の輝度、風速。繰り返される日々の観測。数値の隙間に、彼のつぶやきのような心情が綴られている。一番古い日付のノートは棚の一番左端にあった。日付を見ると、6年前だ。僕が研究室を出てから、1年後にはここに来始めていたのだ。
この山の天文台を、彼が選んだ理由もそこに書かれていた。6年前の最初1ページ。
『都市や平野部では、すでに人間の活動が環境データに混入してしまう。だが、山岳地帯は、人の影響が少ない。だからこそ、温暖化による変化が最も早く、鋭く観測される“前線基地”になると考えた』
静かで、厳しい土地だからこそ、地球そのものの声が聞こえる――彼のそんな信念が文字の端々に滲んでいた。
「ほんとうに……学生の頃から変わらないな」
文字の筆圧、文体、観測項目、どれもあの頃のままだ。思わず、笑みがこぼれる。環境がどう変わろうと、彼は彼のままで観測を続けていた。たった一人で、ここで彼は人類の代表として地球と向き合っていたのだ。
そのことが、なぜか胸に迫って、しばらくノートの前から動けなかった。
年代が後ろに行くにつれ、ノートの冊数が増えて行っている。この場所で本格的に観測を始めたと推測される。志摩は確かに、ここで寝起きし生活をしていたのだ。
*****
翌朝から、僕は志摩のように日課を始めた。午前は観測。朝夕の気温差、風速、放射線量、空の明度、空気中の浮遊粒子。装置を扱う手つきは、大学時代の記憶が自然と身体を動かしていた。記録には忍耐が必要だが、データ量が溜まってくる頃に習慣化し、生活にリズムが出てくる。地球や宇宙を対象にした研究には、リズムを掴むことが重要だ。研究室時代のことを思い出しながら、記録を整理していった。
午後になると、記録ノートを一冊ずつ手に取り、志摩の観測と心情をなぞる時間にあてた。
食事は簡素だ。朝はパックの栄養スープ、昼は乾いたレーションと林檎をひとつ。夜は缶詰を温め、クラッカーと一緒に食べる。風の音だけがする、この場所では自分の咀嚼音が大きく聞こえた。不思議なことに、都心のマンションで食事していたときよりも食事を旨く感じた。時間の流れも遅く感じる。
夜が深くなると、書棚の奥にあったスコッチをほんの少し口に含んだ。赤いラベルの安いウィスキーだ。懐かしい味だった。志摩と研究室でこのウィスキーを飲みながら語り合った。酔いも醒めないまま帰ったあの時間が蘇る。いつも帰宅は遅く、二人で霞んだ月が浮かぶ夜空を眺めながら歩いた。
ふと、星が見たくなった。ここならよく見えるだろう。
星を見ようと外に出たが、土埃が舞い上がっておりぼんやりしか見えなかった。これでは、天文台としての機能が失われるはずだと思った。
眠る前に、彼が何度も読んでいた『猫町』を読み返しながら、眠気がくるのを待つ。時々、風が窓を鳴らしていたが、不思議と怖くはなかった。孤独はあったが、寂しさはなかった。
******
ここに来てから3週間がたった。記録を続け、ここの生活にリズムが出てきた。
毎日同じ物を食べ、記録をつけ、ノートを読む。そして、夜はウィスキーを少しだけ飲み文庫を読む。最初は残してきた仕事が気になったが、時間がたつにつれ思い出す時間が減っていった。目の前の観測対象に向き合う時間が何よりも大切だった。
まとまったデータが溜まってきたため分析をしようと思った。志摩のノートから、過去のデータも含め分析を始めた。
そんな中、志摩の記録ノートに、不自然な空白を見つけた。7日間。観測データも、日記の文字も抜けている。ちょうど3年前の今頃だ。
観測機器のログを確認すると、その期間だけ数値が異常に乱れていた。ノイズか、センサーの故障か。全てのパラメーターがいきなり狂う事があるだろうかと疑問が浮かんだ。しかし、奇妙なのはその後だった。志摩のノートの記述が、明らかに変わっていたのだ。
記録:10月14日
昼間気温:16.8℃ → 夜間気温:-3.2℃
日較差:20.0℃
この場所で、日較差が20℃を超えるのは6年ぶりだ。(前任者が残した記録templog_Slab_20511015.csvを参照)。過去5年間、夜の気温が下がりきらない傾向が続いていた。熱放射が回復始めている。
加えて、雷の発生回数が減っている。観測所の周囲半径50km圏内で、9月〜10月の雷はわずか3件。これは、記録上最も少ない。雷は、大気の不安定さの象徴だ。これは空が落ち着いてきているということだ。地球の環境は再生しつつあるのでは、という仮説を立てる。人類の人口も活動も、すでにピークアウトし、今、その余波がようやく静けさとして現れ始めたのかもしれない。
結論を出すにはデータが少ないので、観測を続けることにする。
以前の彼からは考えられないような、穏やかで前向きな言葉だった。科学者としての目は失われていないが、その語調には何か希望に似た光が差していた。
いつものように、観測を続けていると、窓の外が光った。僕は反射的に息を止め、カウントを始めた。
「……いち、に、さん、し、ご」
五秒後、低く重い音が空の奥から届いた。
「1秒=約340メートル」雷は1.7キロ先で落ちた。
思っていたより近い。けれど、雨の気配はどこにもない。
「雨のない雷……乾雷か」
きっと彼もこうして、観測を続けていたのだろう。ここに来て初めての雷だ。
雷の記録は、データには残らないため志摩のノートに雷の記載があるところを探していった。150冊のノートを調査するのは、手間だった。
雷の記録を調べていると、メモを見つけた。それはここ1年で書かれたものだった。
『最近、体調がよくないせいか悲観的になることが増えた。久遠ともう一度、話がしたい。思い出すのは研究室時代のことばかりだ。君なら、わかってくれると思う』
突然、僕の名前が記されていた。
胸の奥が締めつけられるような感覚。彼が、最期の時間に、僕のことを思い出していた。
なぜ、もっと早く連絡を取らなかったのか。なぜ、あの時、放ってしまったのか。後悔だけ、頭の中を目まぐるしくまわっている。僕は、残された記録を引き継ぎ、観測を続けた。記録を続けていれば、許される気がした。
志摩の仮説通り、この時期の雷は減少傾向だった。僕が来てからの3週間、1度だけなのでかなり少ない。以前は、3週間で3回が平均だったようだ。
*******
朝、目覚めた瞬間に違和感があった。世界が騒がしい。風の音が、いつもと違う。
外に出ると、視界が一気に白くなった。
雨――それも、信じられないほどの豪雨だった。土埃は、雨によって舞い上がり、灰色の霧のようになっている。久しぶりの雨の匂いに、むせそうになる。
空を見上げると、雲が厚く流れ、水が空から降り続いていた。ロガーには「降雨」とはっきり記録され、湿度も通常の3倍だった。
3年ぶりの雨だった。驚きと同時に、込み上げるものがあった。窓を開けて、雨音を聞く。少し肌寒かったが、気持ちよかった。ノートに記録を書こうと思ったが、外の光景があまりにも予想外で何を書こうか迷った。土埃は少しずつ落ち着き、空気が澄んでくるのを感じた。
記録することを諦め、ウィスキーをコップに少しだけ注いだ。それをゆっくりと口に含む。雨と麦の匂いが、鼻に広がる。
窓から、ただ雨が降り続くのを見ていた。地球が水底の沈んでいくようだと思った。
雨の音を聞いていると眠気がやってきた。
――志摩が現れた。
彼は学生時代と変わらず、白いシャツにデニムという格好だった。
言葉はなかった。ただ、僕の隣に座り、空を見ていた。
何か声をかけようと思ったが、言葉が見つからない。話したいことが、たくさんあった気がするのに。
志摩の真剣な横顔を見ていると、胸がいっぱいになった。
目が覚めたのは夕方だった。雨はまだ続いていた。夕日の色で、雲はうっすらと黄色味がかっていた。部屋の温度が、下がり始めていたためストーブに火を入れた。柔らかい光が、部屋をぼんやりと照らした。まだ夢の気配が残っていた。
それから3日間、雨は降り続けた。僕は、眠気に任せて眠り続けていた。眠りの間に食事をし、眠りの間に本を少しだけ読んだ。穴に引きこもる熊のように眠った。
こんなに眠ったのは久しぶりだった。
********
4日目、霧雨に変わった朝、遠くで「ゴロゴロ」という音が聞こえた。雷ではない。何かの鳴き声だ。その声が聞こえると、眠気は嘘のように治まった。
外に出ると、土の大地に草が生え始めていた。色のない場所に、急に緑が発生したので眩しい。芽吹きは一面に広がっていた。土の裂け目から、小さな若芽が次々に顔を出していく。たった一晩のうちに、岩肌の隙間やひび割れた地表が柔らかな緑に覆われていた。草が風に揺れて波打っている。風が吹くたびに、草の香りとともに、かすかな水気が運ばれてきた。
そして、その草の間を、黒い蛙たちが歩き回っていた。墨のような艶を持ち、丸くて短い体に短足が生えた、小さな生き物たち。光を吸い込むようなその黒さは、まるで長い眠りの中で煤けた石のようにも見えた。動くたびに、わずかに濡れた皮膚が鈍く光を反射する。
地面には無数の小さな穴が開いていて、その一つひとつから蛙たちが這い出してくる。どこを見ても、黒い影が地を這い、草の隙間をのそのそと進んでいる。まるで地面そのものが命を宿して動き出したかのようだった。
彼らは、よたよたと動きながら、低く、湿った声で鳴いていた。どこか楽しげを感じる。この沈黙の土地に、命の音があふれていた。
翌朝も蛙の鳴き声で目が覚めた。やけに部屋が明るい。窓を開けると、天気雨だった。空はまだ少し曇っていたが、雨粒はきらきらと輝いていた。久しぶりに、青い空を見た。
草地が広がり、橙色の小さな花が咲き乱れていた。思わず外に出た。 雨上がりの水たまりを覗き込むと、無数の命が蠢いていた。
土肌はなく揺れる花の合間に、水たまりができ、そこに足の生えたオタマジャクシが泳いでいた。あの蛙たちの子供だろう。この雨をきっかけに、繁殖を始めている。
透明な水の底を、小さなエビのような生き物が這っていた。体長はわずか数ミリ、半透明の殻の中で赤褐色の内臓が脈打っている。時折、細い脚をふわりと広げて泳ぎ、水の中をゆっくりと移動した。その甲殻類が、濁り始めた花の根元に群がり細い根をついばんでいる。その動きに反応するように、水中を泳ぎまわっていたオタマジャクシの一匹が、鋭く身体をひるがえした。
一閃。
まるで刈り取るように、エビをひとつ飲み込んだ。
いずれこのオタマジャクシも、あの地表を歩く丸い蛙へと育つだろう。そして、彼らが排泄する糞が、土に栄養を与え、周囲の草を育てる。
草は花をつけ、橙色の花弁が風に揺れる。やがて乾いた風が吹きはじめ、花からこぼれた種と、乾燥に耐えるエビの卵が混ざった土粒が、さらさらと運ばれていく。
次の雨まで、誰もが眠りにつくのだ。蛙たちも、卵も、種も、静かにひっそりと。
その完結性に、息をのんだ。こんなに精密で、整った世界があるのか――そう思った。
荒廃した世界にしか見えなかった。しかし、この場所が彼らには楽園だった。
志摩はこの世界を見つけ、僕に残そうとしたのだと、はっきりとわかった。この環世界から彼は手紙をくれたのだ。
僕は、スーツのジッパーを下ろした。何かに突き動かされるように、裸の肌で雨に触れた。乾いた肌に潤いが戻るのがわかる。冷たく、そして優しかった。
髪から滴をかき揚げ、空を見た。雲がゆっくりと動いていた。どれだけ眺めても、流れていく雲は綺麗で見飽きることはなかった。
*********
夜、夢を見た。
雨の降る、100年後の地球。
草は広がり、空は青く、子どもたちが泥の上を駆けている。そこには、かつての静かな天文台もあった。だが、それはもう観測所ではなかった。木々に囲まれ、風が鳴る音だけが残る、小さな祠のような場所だった。
夢の中で、誰かが言った。
「風が止んで、雨が降った。そして、すべてが息を吹き返した。……ただ、それだけのことだったんだよ」
志摩の声だった。
僕は、ゆっくりと目を開けた。
涙が目頭を伝っていった。志摩が、向こうに行ってしまったのを感じた。
雨が止んでいた。外に出ると、そこには一面の星空が広がっていた。空気は澄みきっていて、息を吸い込むと胸の奥がひりつくほど冷たい。頬に触れる風は鋭く、感覚がなくなっていく。指先もかじかみ、白い息が、空にゆっくりと立ち上っていった。
頭上には、信じられないほどの星があった。
そのあまりの多さに、しばらくはただ立ち尽くすしかなかった。
都市ではもう、こんな空は見られなかった。空はいつも鈍く濁り、ダストフィルターと光害で、夜空の向こうに何があるのか思い出すことすら難しくなっていた。けれど今、南の空には教科書でしか見たことのなかった「冬の大三角」が、たしかに浮かんでいた。三つの星は、まるで記憶から抜け出した図形のように、静かに空に浮かんでいる。
「これが、本物なのか……」
思わず、声が漏れた。
星は、ただそこにあるだけだった。なのに、涙が滲んできた。思い出せない誰かの言葉や、研究室の光景、志摩の声が、一瞬にして重なった。
かつて当たり前だったはずの空が、今ではほとんど奇跡のような存在になってしまったのだと、あらためて気づかされた。
夜空が、こんなにも明るいものだとは知らなかった。
次の雨までは、この景色が見られない。誰かに教えたくなるような夜だった。この光景が、もう一度誰かの目に届く未来を、少しだけ信じたくなった。
文字数:10728