梗 概
絶頂のキータ
惑星須彌(シュミ)は天然の曼荼羅を織りなすアーカーシャ銀河の真ん中の星で、標高十二億九六◌◌万メートルの直方体の山。アーヴィンとマロリーを乗せた偵察機は巨大な雹の衝突によりその山麓に墜落する。機は大破し司令部との交信も途絶。救難を要請するため、二人は通信可能高度を目指して雪山登攀を開始する。
しかし通信はいっこうに回復せず、やむなくビヴァーク(露営)を敢行する。どぎつい星空から、一つ、また一つと星が降ってくる。——否。星のように光り輝く、大きなくらげのような生物だった。それは宙を泳ぎ、氷壁に張りついた。ツェルト(簡易テント)越しに不気味なシルエットを見る。こいつらは、一体なんだ?
仮眠後にまた登る。通信が回復する。通信士は訓練生時代のアーヴィンたちの教官フルート・ボンゴ。「現段階で貴様らの座標を特定することは不可能だ」と彼は告げる。高度をさらに上げる必要があるのだ。「もう一つ悪い報せだ。黒雲が星を覆い始めた。じきに吹雪がくる」
登攀再開。直後、マロリーが吐血する。高度に順応できず、身体にガタがきている。アーヴィンは急峻なオーバーハングを持つ氷壁を、マロリーを背負って登る。
「もういい。俺を捨てろ」「馬鹿を言うな」「お前の足を引っ張りたくない」「できることがある。祈れ」
しかし氷壁の天辺は見えず、危険な岩壁途中でのビヴァークを余儀なくされる。マロリーのツェルトはもう捨てた。一つのツェルトに二人で入る。
吹雪になる。通信も途絶する。
四十八時間後に通信が蘇る。猛吹雪のため救助機の降下許可がおりないとフルートは告げる。
雹がツェルトに穴を空ける。アーヴィンは死を覚悟する。その時、視界の端に光を見た。近づいていくと、光がアーヴィンたちを飲み込む。
目が醒めると、頭上に天幕があった。くらげ生物の中にアーヴィンはいた。
隣で、マロリーは眠るように死んでいた。
吹雪はやんでいた。外に出ると新雪きらめく平地の先にもう一匹のくらげがいる。死んでおり、他者の手で加工が施されている。吊された獣のひづめが呼び鈴代わりに鳴る。
中に人がいる。それはヒトとパサン(ノヤギ)を混ぜたような姿をしている。
彼はこの星の探査中に消息を絶った先遣隊の隊長イシ・ブランケット。脳の退化が進行したイシはたどたどしく説明する。
この星のくらげに似た生物を、私は自分の部族の移動住居の名をとり〈ティピィ・ワカン(聖なる家)〉と呼んでいる。ティピィは我々を歓待している。ティピィは過酷な天候から我々の身を守るシェルターになってくれる。ティピィはストローに似た口で吸い上げた地中の〈露〉を我々に与える。その神秘の液体は我々の細胞をいつまでも若く保つ。
彼らは我々との共生を望んでいる。そして彼らと共生するということは、この星の環境に合わせて肉体が〈変異(メタモルフォシス)〉していくのを受け入れるということだ。私の肉体は獣に近づいている。自我が失われることに恐怖はない。感じるのは自由になる喜びだけだ。
一度だけティピィに入ったアーヴィンの身体にも既に変異は生じていた。腹に節が現れた。背中は丸まり、腕や足は退化を始めていた。眼は複眼に近づいていた。
フルートが伝える。「ようやく座標を捉えた。これより救難作業に入る」しかしすぐ声色が変わった。「すぐにそこを離れろ、雪崩がくる」
選択を迫られていた。アーヴィンは自身のうちに蘇った激しい情熱を自覚した。
「了解。悪いが救助は必要なくなった。俺は引き続き登攀を続ける」そしてマロリーの死を伝えた。
アンドリュー・アーヴィンとジョージ・マロリー。二十世紀、エヴェレスト初登頂に挑み、敗北した、伝説的な登山家たち。ヒマラヤの凍土から見つかった保存状態良好な彼らの屍体は、後に二体のクローンを生んだ。
アーヴィンのDNAには、彼らの〈オリジナル〉が味わった悔恨が、深く刻まれている。
氷壁を見あげた。敵はあの時以上に巨大だ。だが今度こそ登頂を果たしてみせる。
フルートが言った。「なんの意味がある? なぜ登る?」
アーヴィンは言った。「マロリーならこう答えるだろう。『そこにエヴェレストより高い山があるからだ』とな」
一万二千年後、地球とは異なる星系の知的生命体が惑星須彌に降り立つ。彼らは一匹のキータ(虫)を発見する。白く輝く山の頂に、毒虫の化石が落ちている。それは全身をしならせ、果敢にのたくった姿で、凍りついている。
文字数:1822
内容に関するアピール

ジョージ・マロリーとアンドリュー・アーヴィンは実在の登山家。1924年に世界初のエヴェレスト登頂に挑むも、山頂間近で消息を絶った。以降、彼らが登頂に成功したか否かは不明で、未だに論議を呼んでいる。
——この二人の登山家のクローンたちがオリジナル同様にバディを組み、仏教神話を下地にした宇宙最高峰の山に挑む物語です。標榜するのは、SF本格山岳小説です。
課題「おもてなし」への取り組み
■感情を揺さぶる
今回の梗概では、「山岳小説」というジャンル小説を選択しました。「おもてなし」という課題に応える上で、最も必要なものは「エモさ」だと思ったからです。極寒の山、生死のかかった登攀、救助は来ず、食料も残り僅か——山を舞台とした極限的な状況における人物の葛藤やドラマを描くことで、映画のように映像的な没入感を読者に与えることをねらいます。
■知的好奇心を満たす
ジャンル小説が持つ最も優れた長所の一つは、「読者の知的好奇心を満たす」ということです。今回は「山岳もの」なので、「山」、「登山」の知識を徹底的にインプットし、読者に提供するつもりで書きます。加えて、インド〜仏教神話の蘊蓄等も組み込んでいきたいと思います。
■色気
マロリーとアーヴィンは二人ともルックスがよく、正直に申し上げてカップリングとしてそそるものがあります。バディの友情を、いわゆる萌え要素を含み、また恋愛感情に結びつく類いの直接的なBLではなく、海外ドラマ的な、たとえば『SHERLOCK』におけるシャーロック・ホームズとジョン・ワトソンの関係性のような「ブロマンス」の色気を絡めて、描きたいと思います。ちなみにアーヴィンとマロリーはともに大英帝国出身で、コナン・ドイルおよびホームズ、ワトソンもイギリス人。スタイリッシュでウィットに富み、それでいて熱っぽい筆致を目指します。
資料
■アンドリュー・アーヴィン
 イギリスによる第3次エベレスト遠征隊(1924年)に参加した若き登山家。当時弱冠21歳の学生だった。
イギリスによる第3次エベレスト遠征隊(1924年)に参加した若き登山家。当時弱冠21歳の学生だった。
1999年にパートナーであるマロリーが発見された時、マロリーの遺体はロープによって腰部が損傷していたことから、二人はロープで結び合ったまま滑落したのではないかと推測された。しかし推測に反して、アーヴィンの遺体は現在に至るまで発見されていない。
■ジョージ・マロリー
 1920年代、イギリスが国威発揚をかけたエベレスト遠征隊に三度にわたり参加した伝説の登山家。失踪から75年後の1999年、捜索隊によって遺体が発見された。
1920年代、イギリスが国威発揚をかけたエベレスト遠征隊に三度にわたり参加した伝説の登山家。失踪から75年後の1999年、捜索隊によって遺体が発見された。
マロリーは1923年のニューヨーク・タイムズの記事において「なぜあなたはエベレストに登りたかったのですか?」との質問を受け、「そこにエベレストがあるから(Because it’s there. )」と答えている。これが日本ではしばしば「そこに山があるから」と誤訳されて流布している。
■ティピィ
[Tipi, Teepee]はインディアンが利用するテントに似た移動用住居。作中では、インディアン出身のイシ・ブランケットが、惑星須彌のクラゲに似た生物にこの名をつける。
■須弥山
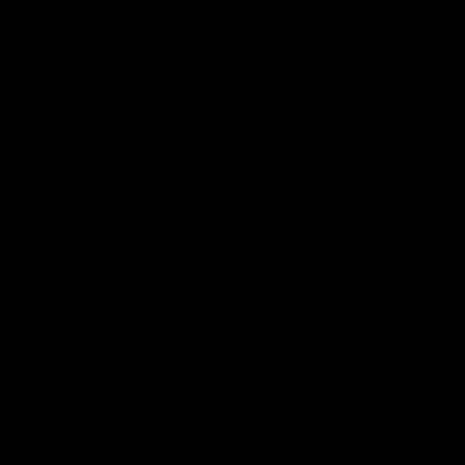
須弥山の概念図
「須弥山(しゅみせん、旧字体:須彌山)」は古代インドの世界観に端を発し、仏教世界にも伝播した聖山の名。作中ではアーカーシャ銀河の中央に位置する直方体の山「惑星須彌」として出る。なお、梗概で記した山の標高「12億9600万メートル」は、神話に忠実に基づく。須弥山の標高は8万由旬(ゆじゅん)とされている。「由旬」はインドの距離単位で、「帝王の軍勢が1日に行進する距離」とされ、中国の40里にあたるという。1里=約405メートルなので、1由旬=40里=1万6200メートルとなる。よって標高8万由旬=12億9600万メートルとなる。
※ちなみに、梗概では「這う虫(=キータ:サンスクリット語)」となり登頂を果たしたアーヴィンが発見されたのを1万2千年後としましたが、これは大雑把ですが計算に基づいてのことです。イモムシの時速は18~30メートルなので、間をとって時速24メートルとしました。須弥山の標高は12億9600万メートルに対し、時速24メートルで登った場合、かかる時間は5400万時間、年数換算で約6165年となります。途中、睡眠や休憩等も挟みつつの登攀となるだろうから、余裕をもって倍近く見積もり、1万2千年としました。
■甘露
仏教神話において、雨となり須弥山に降る霊液。空腹を満たし、かつ、飲んだものに不死を与えるという。
作中ではティピィが惑星須彌の地中から吸い上げる神秘の液体「露」として出す。細胞の老化を止める効力を持つ。この露の効力により、毒虫になったアーヴィンはその後8千年ものあいだ生き続け、登攀を続けた。
文字数:1938
宇宙姥捨山
1
一人はみんなのために。ワン・フォー・オール。
それは綺麗事などではなく勝利の為の必須条件なのだ。
森は白い。銀世界である。その一部だけが今、赤い。
雄鹿だ。矢の刺さった尻から流れ出した血が、周辺の雪を赤く染めているのだ。地面に倒れ伏して動けない。美しい角を持っている。美しく猛々しい。剥き出しの敵意の炎を宿して、誇り高い獣の瞳が、狩猟者たちを睨めつけていた。血走っている。近寄るなと、そう言っている。
「生きたいよな。わかるで。でもな、こっちも一緒じゃ。生きたい。生きねば。そのために、私らはあんたの命を奪う。ごめんやで。でも許してくれとは言わん。カルマを背負うでな。私らは今晩、あんたの身体全部まるごと、骨までしゃぶりつくすんや」
キヌは、傍から見れば小熊のようである。夏に獲った、熊の毛皮を着込んでいるのだ。
竹の幹の先端を斜めに切りとがらせてこさえた槍だ。それをキヌは握っている。この獲物は、巨体を持つ。ならば命を終わらせるため、余計に深く、肉を刺し貫かねばならぬ。
だから、ワン・フォー・オール。
キヌの後ろに五人の仲間が張りついている。そのうちの一人は腰が曲がっているから、背筋のまっすぐなキヌたちは、彼女に合わせて腰をかがめる。
「いくで!」キヌが怒号を上げた。
掛け声に合わせて雄鹿の下腹部に竹槍を突き刺した。キヌの背中を、三人組が力の限り後押しする。
腹を抉られた時、雄鹿の喉を通り抜けたのは、咆哮ではないのだ。
悲鳴だ。山に棲む獣の誇りが、挫かれたのだ。
竹槍の尾っぽから雄鹿の血が流れ出る。雪上の紅が、より広がっていく。雄鹿の瞳は次第に輝きを失って、いつしか虚ろにすり替わる。
仕留めた獲物はその場で解体する。解体した肉塊を、皆が分担して持ち帰るのだ。鉈を持った、解体班がいる。彼らが作業に取りかかる。
大仕事を終えた狩猟班は、解体班の仕事が終わるまで束の間休息をとる。
仲間たちが、自然とキヌを取り囲んだ。
狩猟班の面々——キヌがこころから信を置くかけがえのない仲間たちであった。気の良いキヌの同期威右衛門、妙ちくりんなしゃべり方の日系三世マリア・聖、身体は大きいが内気な老爺近藤シゲ造——。
キヌは仲間たちの顔を一通り見やった。
にまり、と笑った。
仲間も皆、満面の笑みを浮かべた。
「今晩は馳走じゃ!」キヌは言った。子どもみたいに顔をくしゃっと崩すと、顔全体をびっしりと覆い尽くした皺が、ぎゅっと締まって色濃くなる。
「バンザ〜イ! 死ヌマデハッピーヤデヨシナニ〜!」マリア・聖が言った。
「いよっ! おキヌちゃん、天晴れ、世界一〜!」威右衛門が言った。
「キヌさん、やっぱあんたがおれば百人力やな」シゲ造が言う。
「違うで」キヌは言った。「私の力やないわい。最後に勝つのは知恵と勇気じゃ。力がのうても、それさえあれば、凌いでいけるんや」
綺麗事ではない。勝利のため、この弱肉強食の世界で非力な人間が生き抜くための、それは必須条件なのだ。
キヌは今年、八十歳になる。村の中では、もうじき中堅といっていい年頃だ。
2
老人たちの朝は早い。いかなる季節であろうと、夜明けの手前、大体午前四時台には、「カファアオェーッ! グォエァーッ!」という音が聞こえてくる。喉で絡んだ痰を、吐き出そうと苦心する音である。それは別に、彼らの住処がコロニーであろうが信州の小村であろうが何ら変わらぬ。
午前中に作業をやるのは草刈り班である。装備は鍬と、各々が〈遺棄〉の手前に、船内で支給されたガスマスクである。一夜の間に新たに芽吹いた近辺のセイタカアワダチソウの赤子を、発芽の直後から刈り取ってしまうことが役割である。
村の敷地内に芽吹いたのを、まずやっつける。それから「楢山」に入る。無論、繁殖は村内よりも山に多い。それらを、手当たり次第根絶やしにする。
そうして午後にはキヌたちが入山する。狩猟をやるのだ。
楢山を、そのように名づけたのはマダム・アリであった。マダムは古い日本の映画から、元の名前などとうに忘れ去られた自分たちの狩猟場に名前をつけた。
楢山は母なる山、獣と緑を育む。守らねばならぬ。山を守り、山で育った植物を採り、山で育った獣を殺して、キヌたちは生きている。
今、村の中央広場に集っている。皆が集まり、火を取り囲んでいる。獣を焼く火だ。今日は立派な雄鹿がとれた。それを焼く火だ。
雄鹿が獲れたのは本当によかった。年に一度の祝宴なのだった。先日、一年ぶりにこの星に降り立った棄老船が、キヌたちの新たな家族を置いていった。その彼らを歓待する宴だった。
夕食は他にもある。鳥、獏、それに蛇。それらをむさぼる。食べなければ、活力が減じる。それでは明日の狩猟に響く。芽吹いたばかりの黄色の花を、うっかり見逃してしまうかもしれぬ。そうはいかぬのだ。しっかり喰らうこと、これが基本だ。
どよめきが起きた。
宴の広場に、マダム・アリが顔を出したのだ。それは久々のことであった。近頃は自分の邸宅に籠もりがちでなかなか外に出てこなかったから、皆彼女の体調を案じていた。
病に伏せてなお——否、よりいっそう。マダムは美しく、気品に満ちている。銀色の髪は広場の中心で燃える炎の色を映し、生き物のようにうねっている。きりっと端正な眉の下で、強い引力を持つ目が、碧い知性を輝かせている。すっと伸びた鼻、引き締まった口元は力強く整って、ギリシャ彫刻を彷彿とさせる。
無理をおしているのだろう、キヌはそう思った。責任感の強い人なのだ。新たな仲間の合流を祝う大事な日に、自分が出て行かぬわけにはいくまい——そのように考えているのだろう。
村の誰もが、羨望のまなざしを注ぐ人。
「お身体は大丈夫ですかね?」ハルが訊ねた。
「ええ、今日はね、いいの調子。お天気が良かったからかしら? 家の縁側にね、ええ。こしらえてもらって、そう寝床をね。それでひなたぼっこをしていたのよ。よかったのよきっと、それがね」
声も快活だった。幾分、普段より饒舌と感じた。喜ばしい。
「まあ、大きいわね、あら」マダム・アリは雄鹿に目を留めた。「これね、マチ? あなたが言っていたのは」
「左様でございます、マダム・アリ」
マダムの世話役、マチがふごふごと答えた。ほとんど直角といってよいくらいに腰の曲がった老婆だが、頭の回転が非常に速く、聡い女性であった。
「もしよろしければ、切り分けますかぇ?」
このところマダムはすっかり食が細くなっている。
「いいえ、いいのよ」今宵もそう答える。
マチは恭しく頭を下げて、下がる。
「狩猟班、本日はお手柄でしたね」マダムは言った。「キヌ、よくやってくれました」
「いや、私の力とちゃいます。みんなの力や」
「相変わらず。キヌは謙虚」くふ、と息を漏らしてマダムは微笑した。
マダムは村人全員の名前を覚えているといわれる。それは本当のことだとキヌは信じる。彼女は今日の雄鹿討伐に参加した者たちを、一人ずつねぎらい、感謝の言葉を贈る。感動のあまり思わず泣く者もいる。当たり前に皆、若い時分ほどに涙もろくはないのだが、それでもマダムの前ではなぜか、こころがうっかり童に立ち返ってしまう時があるのは、不思議なことだ。
戻ってきたハルは、大勢を引き連れている。
「今回、新たに降ろされよった者たちです」ハルが簡潔に言った。
マダムはまだ心持ち表情の硬い彼、彼女らに柔和な微笑を投げかけた。「初めまして。歓迎しますよ、私たち、あなた方をね。驚いたでしょ? ここに村があるなんてね」
彼女たちはマダムの言葉を受け、互いに顔を見合わせたあと、おそるおそるというように、各々うなずいてみせた。
人類が地球を見限って、もう久しい。
世界中を席巻する巨大なセイタカアワダチソウの増殖、その猛威のため、地球をあきらめた人類は、今は宇宙に点在する無数のコロニーに居を移している。未知の災害に追い立てられる形での避難であったため、移住の当初より、準備不足から来る問題が頻発していたが、コロニー相互間のインフラ整備は未だ難航しており、運営は一貫して各々の〈自治体〉に一任されてきた。そんな中、生活がようやっと安定期に入ったと言われる昨今になり、新たに生じ始めた問題がある。すなわち、小規模コロニーにおける人口増加、および密度過多問題である。
日系移民によって構成される末端の小型コロニー〈サンナナ〉が、かつて人類が見限った地球に再度注目したのは、そのような経緯による。
簡単な話だ。サンナナの自治体が問題解決のために始めたのは、「棄老」である。役立たずの高齢者——具体的に七十歳以上と決まっている——これを船に乗せる。地球へ連れてゆき、棄て、そして戻ってくるのである。
皮肉な話だ。老人たちの遺棄の先が、かつての母星というのは。
セイタカアワダチソウは、駆除せねばならぬ。さもなくば山が死ぬ。彼らは、黄色い死神である。生態系は易々と破壊される。突然変異のセイタカアワダチソウの茎は、放っておけばすぐに、樹齢ウン千年の大樹のごとく、太く、たくましく育つ。彼らは途方もなく食欲旺盛で、大地の養分を徹底的に搾取する。脅威的な繁殖力を持ち、滅茶苦茶に増える。あらゆる場所、あらゆる都市が、今や、樹海に飲まれて消えてしまった。セイタカアワダチソウの黄色の樹海の中では、動物も植物も生き長らえることはできない。
始まりは、ブラジルであったという。かの国より全方位へと拡散したセイタカソウ、その最後の侵攻先となったのが、丁度地球の裏側にあたる日本であった。
サンナナの棄老船〈孫〉が〈棄老地点(フォール・ポイント)〉として日本列島を設定したのは、そういう事情からなのだった。中部地方、信州。——そこは今や、いうなれば「世界の果て」であり、地球上で人類と動物たちとが辛うじて生きてゆける、最後のはらいそなのだった。
ならば、守ってゆかねばならぬ。生き延びるために。
「犬死の運命にあったのよ、私たちはね」マダムは新たな仲間たちに向け、話をする。この村の、歴史を伝える。「でもね、はねのけたの。だって厭じゃない、犬死は」
大丈夫だ、安心せよ。新人らの不安を取り除いていく。
ここには、生き延びるための系統がある。それは、この地区に遺棄された最初の老人たちが、ゼロから作り上げたのだ。キヌたちのこの集落が、セイタカソウはびこる外界から完全に独立した場所として存在し続けている要因として、彼ら先駆者たちの功績は非常に大きいのだった。彼らは老体に鞭打ち、黄色の死神を駆逐し焼き払ってきた。命を賭して戦いに明け暮れた、反逆の老兵たち——そんな始まりの世代を率いたのが、マダム・アリ。
百戦錬磨の女戦士(アマゾネス)。
伝説の英雄。
逸話も多い。たとえば、ある時マダムの元を訪れた者が、眠るマダムの身体が、仄かに光り輝いているのを見たという。生きながらにして、既に半ば神格化されているのだ。
マダムの激励を受けて、何の感銘も受けない者は少ない。その場合、大なり小なり、痴呆が始まっていることがほとんどである。病を患い、肉体は弱っても、なお迸るそのカリスマは衰えることを知らぬ。
新たにやってきた新人らに、今宵もまた、マダムのカリスマが刺さる。老後のセカンドライフを謳歌する勇ましい老戦士が、マダムの接触に呼応して産声をあげる。幾人も。
3
「キヌ? ねえ、キヌ? あなた、似てる気がしてるのよ、私に、どこかね」
「えー。どこがやな?」
「性格とか?」
「いやいや〜むしろ正反対やろ〜? うちはガサツやし、アリさんはマダムや」
わからん。
「ね、あなたね、これから、引っ張っていってね。どうか、他のお婆ちゃまたちのことをね」
「何言ってはるんですか。縁起でもないことを言うもんやないで。まだまだや」
「勿論そうよ。でもね」
「弱気にならんでください」
「なってないわよ。私、ほら、元気よ?」
「ああ〜っと、ちょちょ、もう〜。そんな勢いつけて急に立ち上がるからよろけてまうんですよ。気ぃつけてくださいって」
「うふ。ごめんね?」
「うちよか他におりますやろ」
「……?」
「ほれ、ハルがおるやろ? リーダーにうってつけなんは、ああいう人とちゃいますかね」
「うぅん、そうねえ……」マダムは言葉を濁した。ぴんと突き立てた人差し指を、唇の端にあてながら。
女らしい人、とキヌは思う。もっと若い頃に出会っていたら、憧れの気持ちが強くなるあまり、恋にすり替わっていたかもしれない。
今日はなんだか、元気なのよ。
マダム・アリがそう言ったので、キヌは彼女が起き出すのを手伝い、河原のほとりまで付き添ってやってきたのだ。村の中心を流れる川だ。キヌたちは流木の上に腰を下ろして暗い水面を眺めた。夏でもここは、夜には涼しい。
特別な夜だ。そう、キヌと感じた。
腹を割って、大事な話を、じっくり時間をかけて、したのではなかった。
むしろ、逆である。二人は、取るに足らない何気ない雑談を、ほどほどにして、そうしてそれぞれの住居に帰ったのだ。
そんな何気ない夜のことほど、長い間よく、覚えていたりするものだ。
今のことも、いつか懐かしく思い返したりするのだろうか。——年甲斐もなくそんなことを思った。けれども、思った傍から渇いた苦笑が滲む程度には、キヌは年を取っている。夜に物思いにふけることは、幾つになっても、感傷的になりすぎる。
ここまででいいわよ、とマダムは戸口の前で言ったので、キヌは外でマダムと別れた。月が雲隠れした夜だったので、闇に慣れた目でも、せいぜい彼女の顔の輪郭くらいしか読み取ることは出来なかった。
「おやすみ」マダム・アリが言った。
「おやすみ」キヌも言った。
マダムが死んだことは、マチが見つけた。朝、ベッドの上で冷たくなった彼女は、穏やかな顔だったという。
老人だけの村だ。死と別離は日常と隣り合わせのものとしてある。次々と死ぬ。
キヌたちは、獣を喰らって生きている。普段から一方的に、搾取を繰り返している。
だから時に、恩を返すこともする。獣に。山に。
死んだ者を、くれてやるのだ。山に差し出す。獣たちに肉を与える。
そういうことに決まっている。異論を唱える者はいない。ちゃんと、自然なことに思えるからだ。
例外は作らない。無論、そうだ。取り決めは、マダム・アリにもきちんと当てはめる。
キヌたちは屍体を荷車に乗せて、数人がかりで楢山に登る。見晴らしがよく、よく陽の当たる天然のテラスを、豊かな樹木の狭間をかいくぐった先に見つけて、屍体を降ろした。
キヌは、近くで石を三つ——大、中、小と拾い上げて、横たえた屍体のそばに積み石をした。
手を合わせる。
ゆっくり、休んでください。
村の没落はマダム・アリの臨終を経て、じきに始まる。
まずは分断がある。
「クーデターてあんた……」キヌが言った。「そない物騒なことやめとき!」
「そうは言ってもあたしらはジリ貧だ」ハルが答えた。「このままマダムの遺産を食いつぶしてくだけじゃね」
「このままみんなで頑張って、よりいっそうの豊かさを手に入れていったらええんとちがうんか」
「『よりいっそうの豊かさ』」ハルはその言葉を繰り返した。「そいつは難しいね。キヌちゃんだってわかってんだろう?
豊かになるってことは、生き長らえるもんも増えるってことだ。楢山は、小さな山さね。あたしたちの山に、これ以上あたしたちが増えたとき、それをまるごと養いつづける度量はないさ」
それに、とハルは言葉を継いだ。
「『頑張り』というがね、キヌちゃん。その頑張りを強いられてるこの現状を、そもそもあんたは仕方ないことだと、本当にそう思ってんのかい?」
「そうは言わんけどなー……」
「言えるわけないさね! 追放されたんだ、理不尽に。あたしらはそういう集まりだ。本来、そうなんだ」
しゃべりながら、ハルの頭にはますます血を上っていっているようだった。
「棄老だ。口減らしだ。宇宙時代の姥捨だ。黙ってる手があるか。抗わなきゃ!『あたしたちは、迫害を受けている!』声高に叫ぶんだそのことをさ! 目に物を見せてやるんだよ、目に物を!」
ハルは自ら、マダムなき後のこの村の、新たな指導者となることを決めたのだ。
ハルは自分たちを棄てたコロニーへの復讐計画をぶち上げた。
コロニー〈サンナナ〉——地球間を往復する『棄老船〈孫〉』が棄老地点に降り立つのは、一年に一度、地球時間で、正月の三日前のことである。村ではこの日を「歓待の日」と呼んでいる。今年は十一月末にはもう雪が降り始めた。間もなく到来する歓待の日も、雪景色の中で迎えることとなるだろう。
〈孫〉を、ハイジャックする。乗っ取り、船乗りを脅して、コロニーへ帰還する。そして権利を主張する。老人一同の、コロニー帰還を要求する。
多くの者が賛同し、計画に乗ると言った。その中には、長らく狩猟班メンバーとしてキヌとともに狩りを行ってきた、寡黙な老爺シゲ造もいた。
正直なところ、ハルたちの気持ちもキヌには痛いほどよくわかる。キヌ自身、胸中には間違いなく、彼らのそれと同じ類いの屈辱を秘めている。
人は誰しも年をとる。肉体は衰え、頭の回転は鈍くなる。それが理由で棄てられるならば、棄老こそがすべての人の末路ということになる。
馬鹿な。あまりに悲しい。キヌだってそう思う。
しかし、ハルの提唱する強行策に同調することの方がもっと難しいのだ。今さら、人間同士傷つけ合い、血を流し合う道をなぜ選ぶ? 虚しいことではないか。長く生きてきた。幾つかの戦火をくぐった。その中で身近な人間の死も経験した。夫を亡くしたのはもう二十年も前だ。
ハルも、同じだと言っていた。愛する男を戦争に奪っていったと。それがどうして、闘争の道を選ぶ?
恨みか。
復讐か。
同意できないと、キヌは伝えた。
加えて、無謀である、とも伝えた。安直にすぎる。必ず失敗するだろう。
キヌの側にも多くの賛同者がついた。
キヌには、政治はわからぬ。だが、村の花形である「狩猟班」に属し、中でもトップの腕前を持つエース中のエースなのである。村人たちの信頼は篤い。
勢力は完全に五分と五分と分かたれた。もっとも、どちらにもつかずの静観を決めた者が最も多くいた。割合としては、三対三対四。四が、中立の者たちである。
キヌとハルは、両派の代表として、歓待の日までに幾度か折衝を重ねたが、対立は深まるばかりだった。
「武力行為には、反対や」キヌは言った。
「反対ということは、わかったよ」ハルは言った。「で、どうするつもりだい?」
「反対するっちゅうことは、止めるってことや」
「ふぅん。けどさ、具体的にはどうやってさ? よもや、力尽くで、というんじゃないだろうね? そんなのは本末転倒だと、猿でもわかる論理さね」
「もしそうなった時には、うちらは船の側につくっちゅうことじゃ。暴力は振るわん。そんでも、何かしら武器は持つかもな。抑止力としてな」
「そうかい」不敵に笑った。「じゃあ歓待の日当日に、結託されて数で押し負けちまうようなことにならないようにするためにも、前日までにちょいと、掃除しておいた方がいいかもしれないねえ」
「なあ、ハルちゃん……。天国のマダムは、今みたいなこと、望んどられんかったと思うで……」
「マダムのことは尊敬してるさ。けどね——」
あたしはあたしだよ、とハルは言う。
そして緊張感が極限まで高まった歓待の日の前日深夜、轟音が響き、楢山に隕石が落ちる。家を出て山を見やると、山頂付近が明るい。
「火じゃ」「まずいのう」「延焼するじゃろうか」「山火事かえ?! まずいんでないか?」「山火事!」「山火事!」「火事じゃ、山火事じゃあ!」「えらいことじゃあ! 大変なことじゃあ!」
夜の山に入ることは無謀なことだ。さらに、この雪である。
しかし、非常事態なのだった。
キヌは楢山へ入る。幾度も協力して狩猟をやってきた狩猟班の仲間を伴ってだ。
すぐに火を焚き、松明をこさえ、各々がそれを手にする。火が拡大すれば必要はなくなるが、麓からの山道は、今も暗闇に沈んでいるのだ。
一刻を争う時だ。
さあ、出発だ。
毎日狩りのために山に入り鍛えているとはいえ、老いた身体だ、一たび木の根に足を取られてすっ転べば、重傷は免れぬ。足並みは慎重すぎて、困ることはない。ゆっくりと、ゆっくりとだ。
それで落下地点についた時には、明け方になっている。
その部分だけ、雪がすっかりはげ上がっている。
クレーターだ。直径七、八メートルの大きさを持っている。延焼被害はないようだ。幾つかの樹が折れ、あるいは焼けていたが、樹の密度の薄い場所であったことが幸いした。
「棄老船のお早いおつきかと思ったんだが」
キヌは振り返った。「ハルちゃん。あんたも来たんか」
先日狩猟班より離反したシゲ造を含む、ハル派の男衆が、祭りの神輿よろしく、木の柱を組み合わせたその上にハルを乗せて、ここまで運んできたらしかった。
クレーターの中心部に、えげつない物体が落ちている。
それは真っ黒な色をした二枚貝のように見える。それでいて貝よりか、ふっくらとした丸いフォルムと肉づきとを持っている。
えげつないのは、それがけったいな罠のように見える点である。それはさながら、獲物の足が乗ると跳ね上がり鋸歯状の歯で獲物を拘束するトラバサミである。あるいは、二枚の捕虫葉に剥き出しの牙をずらりと揃えた食虫植物、ハエジゴクのようである。大きい。長い方の身幅はざっと二メートル近くもある。
ハルは、杖を突き立てながらクレーターの斜面を降りる。巨大ハエジゴクに、躊躇なく近づいていく。「ハルちゃん」キヌは言う。「待ちいな! 危ないかもしれんで!」ハルは聞く耳を持たない。おそるおそる、キヌたちもハルの後に続いた。
その時、キヌは見た。
ヴヴ……。
ハエジゴクが、ひとりでに、僅かに震えた。
「ちょい待たいて!」キヌは声を荒げた。「ハルちゃん、そいつ今動いたで!」
ハルが返事を返すだけの猶予もなかった。
ヒュッ——。
何かが、ハエジゴクのすぐ上を、素早く横切ったように見えた。
「あん……?」キヌの隣で、威右衛門が呟いた。
気づけば、ハエジゴクと地面の間から、太く長いものが一本生えて、くねくねと蠢いていた。
「な、なんじゃあ……」威右衛門が言う。「尾っぽ……?」
キヌにも、尾のように見えた。その先端に、赤黒い色がこびりついている。液体が付着しているのだ。
それが、滴る。
としゃり、と音をたてて、血だらけの腕が一本、地面に落っこちた。
それより遅れて、思い出したように、いつの間にか綺麗な黒い切断面を晒しているハルの肩から、血がぶばっと溢れ出た。
認識が追いつかず、気づきの順番が変になっている。
ハルの、腕がない。
「あぁ〜?」とハルは言った。まだ、そのこころは忘我の域にあるのだ。驚きのあまり、まだ痛みを感じるに至らない。
皆、一様に似た顔をしている。口をあんぐりと開けて、惚けている。
二本の腕が、土の中から飛び出した。禍々しいかぎ爪を持った手のひらで地面をぐっと押し込んだ。勢いをつけて、今度は胴体全部が外に躍り出た。
猛禽のそれに似た、鋭い爪を持つ細い二本の足が大地を踏み、そうして、立った。
真っ黒い身体全体が、甲冑のように硬質な鱗状の皮膚で覆われている。
二枚の捕虫葉を彷彿とさせる口腔が、激しい痙攣を伴って、ばっくりと大きく天地に裂けた。口蓋の奥までびっしりと、禍々しい鋭利な牙が無数に生え揃っているのが覗いた。
怪物は、しばらく大口を開いたまま、身体を震わせ続けた。その姿は咆哮しているようにも見えたが、しかし声はないのだ。起床直後なのかしらん。もしかすると、あくびか。
それから怪物の首が、ぐりゅん、としなやかに、すごい速さで躍動した。それから、ガキンと歯が鳴った。
獲物に、喰らいついたのだ。
古くからハルに熱をあげてきた、熱烈な崇拝者サワディ・クラップが餌食となった。一瞬でその肉体のほとんどが消え、地面の上に残されたがに股の下半身が、即座に血の紅に染まった。
ハルはすぐ隣で行われた容易い殺戮を見る。それから血だらけの自分の肩に視線を移動させる。
ようやっと知覚する。
叫んだ。
「うわああああああああ!! あたしの、あたしの、あたしのあたしの腕がああああああ!!」
「うわあああああああ!!」ハルの恐慌を目の当たりにして、ようやくキヌも我を取り戻し、そういうわけだから無論叫んだのだ。「で、で、出たあああ! お、オオ、オ、オニじゃあ〜〜!!!」
キヌはそしてどういうわけかこの凶悪な殺戮者に向かって突っ込んでいった。
「な、何しとるんじゃ!?」
威右衛門が驚いて声を上げた。
キヌはしかし止まらず、殺戮者の傍らに辿り着くと、その場で凍りついているハルの、残っているもう一方の腕を掴んだ。「逃げるで!」
「あ、キヌちゃ——オオゥ!?」
ハルが転倒した。
「ああん、もうハルちゃんなんしてるんや!」
「急かされても! ちがうんだよ、腰、腰、腰がー!」
恐怖に腰が抜けたのか?とキヌは最初思うが、様子がおかしい。これは……。
腰をひしと押さえてうずくまっている。普段は人一倍気丈なハルが、涙さえ浮かべている。
キヌは察した。「あかん! この人、ぎっくり腰や!」
あまりのことに、ハルは白目を剥き、泡を吹いて気絶してしまう。
「そこの人ら、ハルちゃんの足持って! ほれ、何してるんや、シゲ造!」
シゲ造が今目を醒ましたというように「わ、わかった!」と言う。
「ほれ逃げるで! みんな逃げや! このままここおったら殺されてまう! はよう、はよう!」
キヌたちはクレーター斜面を必死でよじ登る。てっぺんまでなかなか行き着かない。登れば登るほど傾斜がきつくなる、老体には酷な試練だ。
振り返る。ハエジゴクは電池の切れた玩具のように、元いた場所に依然、突っ立っている。
何を考えとるんや……!?
ええい、ええ、今はそんなことは。
なんとか登り切った。さあ、下山だ。
最後にもう一度振り返る。まだ、同じ場所にいる。
「おお……やっぱ、オニや……!」
鬼。まさに鬼。鬼ごっこの鬼——皆が散開するのを待っている……。
逃げ回るのは高齢者で、鬼役はエイリアンかいな。老人の身体に鞭打つにも程がある、全然笑えん冗談や、まったくもって悪趣味や。仏様〜!
ハエジゴクの首がゆっくり、ぐりりと、こちらを向いた。
口を開いた。
今度は、あくびではない。
怪物の発した咆哮が、キヌたちの心の臓を雑巾みたいに絞り上げた。楢山に棲むあらゆる動物よりも獰猛な、殺意に溢れた咆哮だ。
ほれ、ほれ、捕まえに来よるぞ!
4
村に残った者たち——ハル派にもキヌ派にも与さない中立の爺婆たちは、狐に化かされているような気分を味わっていた。
「新規の『移民』が、今回はありませんのであしからず」
そう最初に断ったのはこれまで毎年やってきていたコロニー〈サンナナ〉の船乗り・渡承知之介ではないのだ。
「船長のジョン・アーモンドです」と彼は言った。
山高帽を被り立派な口ひげをたくわえたダンディな男の風貌に、姥たちは色めき立ち、翁たちはそのために必死の炎を燃やしてふごふごといまいち聞き取れぬ何事かを口走ったりした。ともあれヒゲのジョンの言葉の通り、新たに連行された老人はいないのだった。
代わりに、船を下りてくる者たちの集団があった。
「へえ。ここがそうなのですね」
「なるほど、緑に囲まれた美しいところだなあ」
「空気が綺麗な気がするわ。気のせい?」
「あ、見て!」
コサージュをあしらったキャペリンを目深に被った貴婦人が、老人たちを指さした。
「おお」
「この人たちが」
「いや、噂はかねがね聞いておりますぞ!」
好奇の視線が、無遠慮に老人たちを突き刺す。
「口減らしのため、すべてを喰らい尽くす巨大セイタカアワダチソウの群生地となりはてた地球……。この星に棄てられたるは、齢七十を超える老人たち!」大仰な口振りでしゃべる男の腕の中では、撮影用のカメラが老人たちの不安げな表情をじっと映している。「だが彼らは滅びてはいなかった! 力を合わせ、知恵をしぼり、神なき絶望の星に、一大帝国を築きあげた!」
貴婦人が感慨深げに言った。「人は、このような場所でもちゃんと生きてゆけるのね。頑張ってる人って、私、好きよ。お爺ちゃまお婆ちゃまが、年甲斐もなく、プライドもかなぐり捨てて死にものぐるいになっているなんてね」
ねえ、と貴婦人が老人の一人に声をかける。
「ここの生活は、楽しいですか?」
突然の訪問客。彼らは皆、小綺麗に着飾っている。
そのことが、老人たちにやりきれなさを与えていた。
彼らに比べ、私らはどうだ。
まるで、けだものである。
村の冬は、過酷である。高齢者の集まりだ。寒さが、すぐに死を連れてくる。そういう例を、たくさん見てきた。防寒を怠れば、そうなるのだ。
冬の間、皆、様々な動物の毛皮を着込むのだ。
そういうのは、慣れるものだ。
そこに、異邦の者たちがどかどかと上がりこみ、老人たちの、文明の記憶を呼び覚ました。彼ら老人とて、一度その文明の色を目の当たりにすれば、自己を見つめ直さぬわけにはいかぬ。
女たちは特にそうだった。好奇の目に晒されている——訪問者と自身との、身なりの差を知るにつけ、羞じらい、強烈な嫌悪を覚えた。
彼らは〈サンナナ〉周辺のコロニーの重鎮たちだ。噂を聞きつけた金持ちの好事家たちだ。大枚をはたいて、手前勝手な地球観光にやってきた。
「撮影は自由となっています。シェアもご自由に」ジョンが自分の客に、さながら自身がこの星の主であるかのように、言った。
「愚かな」キヌは呟いた。
木々の網の向こう、目と鼻の先に村を捉えていた。棄老船〈孫〉が降りている。それが〈孫〉だと、形でわかる。が、外面ががらりと一新されている。塗装はけばけばしく塗り替えられ、元の無骨な雰囲気が、今はもうない。公園の遊具のようだ、キヌはそう思った。
キヌは村へと小走りに走り続けながら声を張り上げた。「船! 船乗って来たもんらは、今すぐ発ちなさい!」
何人かの者が、キヌの方を向いた。
「おっと、これは! 狩りの帰りでしょうか!」若い男が、大型カメラをキヌに向けた。
「聞かいて! 危ないんや! このままやと——」
——その時、キヌは、自分の真上を大きな影が飛び越えていくのに気づいた。
ハエジゴク!
ハエジゴクは全身をバネのようにたゆませてしなやかに着地する。
三メートルを超える巨躯である。それが、今一度跳ねた。——今度は前方に向けて。
「殺されてまうで!」キヌは叫んだ。
外敵の存在しないコロニーだ。長年そんな揺り籠で危機管理能力を鈍磨させ続けてきた彼らであった。怪物の姿を目の当たりにして、件の貴婦人が開口一番に言ったのは、「ほら、あれ、撮ってくださる?」だった。
「オヤ!?」
そう言ったのは船長のジョン・アーモンドで、それがこの男の最期の言葉になった。ハエジゴクがすっと腕を振ると、口ひげの男の首は、黒ひげ危機一髪さながらにぽーんと飛んだ。
村人たちは既にその場を離れちりちりに退散を始めていた。宙を舞ったジョン・アーモンドの生首がぼとりと落ち、積もった雪の中に半分を埋まるのを目撃したそのあとで、ようやく観光客たちも狂乱を始めた。
もう遅いのだった。
「ちょっと待ってよ!」
狼狽のあまりそう漏らしたのは例の貴婦人で、彼女はハエジゴクの口が二枚貝のようにぱっくりと開くのを正面から目の当たりにする。直後、身体の半分を囓りとられて即死した。
惨劇が展開した。
あらゆる首が飛び、あらゆる胴体が裂かれ、細切れの骨と肉と血が雪の村を飾り立てる。
このままでは村は全滅だ。皆が皆キヌや狩猟班メンバーのように足腰が丈夫なわけではない。
守る。
「威右衛門」キヌは呼んだ。
「ここにおるで!」
すぐ傍らにいた。
「村の連中全員、〈孫〉に乗せるんや。ぎりぎりかもしれんが、なんとか乗れるはずや」
「なんやキヌちゃん、コロニーには戻らんのでは? 方針転換か!?」威右衛門が言った。
「そうやない! 和解や、復讐や、クーデターやなんや、そういうんはとりあえず二の次じゃ。ともかくこのまま鬼と一緒んとこ居続けるわけにはいかんやろ! お空の上が、一番安心じゃ!」
「よしきた、任せとき! 行くで、マリア!」
マリア・聖がガッツポーズをした。「イェー。ヨキニハカラエ! フォー!!」
キヌは阿吽の呼吸で意志が伝わる仲間の存在を、これまで以上にありがたく感じた。長年共に狩猟をやってきた同志である。意思疎通は迅速だ。言っても移動速度は当然年相応だが、行動開始後はもうキヌを振り返りもしない。この場を仕切る、キヌのことを信じているのだ。
さあて、どないしよか。
石でも投げてみるか!
キヌは石を拾い投げつけた。背中にそれは的中したが、ハエジゴクは蚊に刺された程度の反応すら見せない。
が、キヌの方を向く。
「そうや、来い、ハエジゴクのバケモンめが!」
「キヌちゃん!」
キヌに気づいた村人たちが口々に叫んだ。
「ここはうちに任せいい!」キヌは自信に満ちた笑みを浮かべて言った。少しでも安心感を与えてやるのだ。
ハエジゴクの一足跳びで、キヌと怪物の間合いは一気に半分まで詰まる。
圧が、物凄い。ひりひりする。
これまで幾つかの、それなりの苦難を乗り越えてきたつもりであったが——思い知った——今回は、度合いが違うのだ。
たちまち、足がすくんだ。動けない。
駄目だ。
——その時。
ウォン! ウォウウォウ! ウゥ〜! ウォン! ウォンフ! ウォォウォンフ!
「おおい! ハチ!」
ハチが、キヌの家を飛び出してきた。
ハチは白髪の狼。楢山で負傷してうずくまっていたのを、キヌが発見し、保護して怪我が治るまで世話してやった。自由に走り回れるようになり、自分の獲物を自分で狩ることができるまでに完全に回復したあとも、キヌと一緒に住んでいる。
そのハチが、ハエジゴクの殺意を自身に引きつけた。
「出てきたらアカン! 戻れハチ! はうす! はうす!」
キヌの言うことを聞かない。
しかしそれは当たり前かもしれぬ。キヌには、ハチに芸を仕込んだ記憶が特にないのである。
ハチは、エイリアンの前に躍り出た。
グーグルルルル……!
声を低くして威嚇している。
ハエジゴクはこれに応じるように、大口を開けて「ヴォイ!」と吠えた。
怪物の振り上げた腕がハチを襲う。ハチはこれをすんでのところでなんとか避ける。ハチの後方の樹が震え——ハエジゴクの爪が切り裂いたのだ——幹がミシミシと音を立て、倒れた。
ウォウウォウ! ウォンフ! ウゥ〜ウォンフ! ヴォルフ、ヴォルフ!!
ハチはけたたましく吠え続け、なんの前触れもなくいきなりダッシュ!
ハエジゴクがその身体を捕まえようと飛び出す。ハチはそこでフェイク! 左に一端身を振り、即座に右方に切り返してハエジゴクを軽やかにかわす。
そのままハエジゴクのすぐそばを駆け抜け——
「あああ〜待て、待て、そっちアカンて! ハチ! カム! カム!」
「カム」は「こっちに来い」という意味だと、そのように芸を仕込んだためしも別にない。よってハチは特に気を止めずまだまだダッシュ!
それでハチは棄老船〈孫〉に入っていってしまい、ハエジゴクもその後を追いかけて入っていってしまう。
直前の計画が、すでに台無しである。
「キヌちゃん、どうする!?」すぐに威右衛門が戻ってきてキヌに訊ねる。
「ハチを助ける」とキヌは言う。
「ヤメトキナハレ!」マリア・聖が言う。「ハチ、ゾンガイ、ケダカキオオカミ! ソンジョソコラデ、ツカマル、チャイマス!」
「いや。行かせてくれや」
折れる気は微塵もなかった。キヌとハチは深い愛情で互いを結び合っているのだ。
「それに、これはチャンスじゃ。中ぁ入ったら、ハエジゴクのやつも簡単に出ていかれんように、入り口はさっさと閉めてまうで。決着着けたるで!」
キヌの目が、強い意志を饒舌に語った。仲間たちはそれを、受け止めないわけにはいかなかった。
「ほならわかった。こうしよう!」
そう言って威右衛門はマリア・聖と顔を見合わせ、うなずきあった。
「ちょ、待ちいな、あんたらもしかして——」
「ソノ、マサカナンヤデ。協力スルニ、ヤブサカデアラヘン!」
「狩猟班のチームワーク、あのハエジゴクに見せたろかい!」
「あんたら……」
キヌは、協力の拒否をあきらめる。
「ほんま、お人好しやであんたら」
キヌは村一番の活力でタラップを駆け上った。
ご機嫌な男・伊右衛門、奇天烈弁士マリア・聖がその後に続いた。
キヌは船の開閉ボタンを押した。
「無事で帰ってきいや!」
「ハチによろしくな〜!」
村の仲間たちの声援を受け、キヌたちは船の奥へと進んだ。
ゆっくりとタラップが収納されていく。これが閉じきったら、中と外はシャットアウトされる。——その間際に、小走りでやってくる者がある。ぎりぎりのところで、タラップに飛び乗る。それはシゲ造で、背中にハルを抱えている。
5
棄老船〈孫〉には医療室があって、コロニーの最新医療設備を備えているのだ。
ハルはこれに目をつけた。ハエジゴクに切り落とされた片腕を修復するくらいのことは、わけがない。
死に体だった。泡を吹いて倒れ、シゲ造に担がれ運ばれている最中に一度目を醒まして、ギックリ腰の鬼畜的な痛みのあまり、また気絶した。次に目を醒ましたときには痛みの感覚は後退していた。感覚が、麻痺しているのだ。もうじき死ぬのだとわかった。血を流しすぎている。「ふねに」と言った。「ふねに。おいしゃ。きかい。なおす」
意識は、海だ。
それが現れ出るのは、ハルの浜辺に波となり寄せたときだ。
寄せては、返す。——すなわち、落ちる。
また寄せる——目を、醒ました。
ハルは自身の言葉が正しくシゲ造に届いていたのだと知る。
知らない天井。白い。懐かしい、文明の香り、機械の質感。よし、〈孫〉船内だ。
ハルの身体は横たえられている。医療カプセルの中だ。視線を伏せて身体を見た。ちぎれた左手が、今は元通りにあった。切断部を、カプセル天蓋より降りてきたマニピュレーターが、緻密な動きで縫合をしている最中だ。
「大丈夫か」
カプセル内にスピーカーを介したくぐもった声が響いた。
外に目を向けた。透明な強化ガラスの向こうに、シゲ造がいた。不安の面差しで、ハルを見ている。
「ここに入ってどれくらい経った」
「十分」
十分。あの致命傷が、ものの十分でここまで。
改めて、馬鹿らしくなる。野蛮な地球。戻りたい、不自由ないコロニーの暮らしの中へ。
シゲ造に訊ねた。ハルが一度気を失ってから、現在に至るまでの状況について。
ハルたちの他に、船にいるのは、キヌと狩猟班の仲間二人、キヌの忠狼ハチ、そしてハエジゴク。
「こいつが治ったら——」ハルは言う。「——ブリッジへ向かうよ」
「ブリッジで何を?」シゲ造が訊ねた。
「決まってるさ。この船を飛ばすんだ。なつかしいコロニー〈サンナナ〉へね」
最初からそういう計画だからね、とハルは言った。
「けどな、ハル」たしなめるようにシゲ造が言う。「ホンマにわかってんのか? この船には、キヌさん以外、他の村人らも乗っとらんねやで? 俺は……自分らだけ生き残ろう言うのは……仲間を放って行くんは……」
「必要なのは、清濁併せ持つことさ」ハルは言った。「なるほど、あのエイリアンが入り込んじまってるってのは、非常にいただけないがね。かといって今さら引き返すわけにもいくまい。村の連中を危険に晒す気かい?」
「それは……」
「そんな顔するんじゃないよ」ハルは正面を向いたままで言った。「頼りにしてるんだからさ」
「……」何も言わないが、シゲ造は歓喜に震えていた。
キヌ派を造反したシゲ造。大きな身体の寡黙な老爺。誘ったのはハルの方だった。動機は不純であった。有能な彼を自身の派閥へ引き込むため、ハルは色仕掛けをやった。うなじと太腿をちらと見せ、あとは少々のスキンシップ。それで言うことを聞かせるつもりだった。だがそうはならなかった。ハルは、自身の内の女の蘇りを感じた。その後は速かった。二人は坂道を転がるように同衾した。老練なシゲ造の手技は、ハルの身体をいかなる時も、熟した果実のごとく、くれない色に火照らせた。
「どんな時も最善の方策を。一人が、皆のために。いつだってそう考えてるさ。マダム・アリがかつてそうだったようにね。あたしは、あたしの行動に誰も文句を言わせやしないよ」
「ハルさん……」シゲ造は呟いた。「俺は、あんたについてくわ」
「コロニーに着いたらさ」ハルはついている左の手のひらを、強化ガラスの表面にそっと当てた。「一緒に……」
シゲ造は深くうなずいた。カプセル越しに、手のひらをハルの手と重ね合わせる。
直後、ハルのまなこが大きく見開かれる。
「どうし——」
——どうしたんや。
その短い言葉を、シゲ造は紡ぐことができない。
圧倒的な力の前で、人間の命はあまりにも脆弱だ。
*
何せ、高齢なのだ。いざブリッジにやってきたものの、威右衛門とマリア・聖には、キヌが一体何をしているのか、とりあえず全然わからなかった。
キヌはものすごい速さでタッチパネルを操作している。その操作に合わせてなのか、正面の大画面で複雑な文字列がぱっぱぱっぱと切り替わりまくっている。意味不明だ。
「これでよし!」キヌは言った。
船は浮上を始める。
「妖術じゃ」威右衛門は言った。
「あとは自動運行じゃ」
「勝手に、目的地まで飛んでいきよるっちゅうことか?」威右衛門が訊ねた。
「せや」
「〈サンナナ〉デスケ?」マリア・聖が聞いた。
キヌはかぶりを振った。
「ロクヨンや」と答えた。
「ロクヨンゆうたら……」
キヌたちの故郷、コロニー〈サンナナ〉にほど近い、無人のコロニー、それがロクヨンだった。
サンナナよりもさらに小さなコロニーで、かつては地方コロニーにしてはそれなりの活気を見せていた時分もあったが、小型隕石の衝突以降は「維持していくよりもいっそ捨て去り他に移住した方が安くつく」と判断され、捨て去られた。今では人の住めないゴーストタウンである。
「けったいなバケモン積んどるんや。人間のいる場所に、連れていくわけにはいかんやろ? ほいでその前に、もし無事に鬼退治に成功したら、そん時はUターンや」
そう言いながら、キヌはハチの背中を撫でている。
「なあ、ハチ? 傷つくもんは、少ない方がええ。そうやろ」
威右衛門とマリアは、やりきれない気持ちで目を伏せた。
ハチのその牙には、紫色の液体が付着している。それはあのハエジゴクの血に違いなかった。ハチは、命の最後の瞬間まで、勇敢に戦っただろう。
「よう頑張ったな」キヌは言った。「ゆっくり眠り。あの世で待っとってね。うちもじきに行くさかい」
警報が鳴った。
キヌは表情を強ばらせ、両耳に手を当て聞き耳をたてた。
すぐに大きな音がした。何かが壊れた。あまり遠くない。
そして、足音だ。
キヌは仲間たちの顔を見た。二人とも一様に、青ざめた顔をぶらさげ、凍りついたように立ち尽くしている。
ブリッジへ、近づいてくる。
足音。大きい。
キヌはゆっくりと、通路への扉へ歩み寄っていく。
「キヌ」マリア・聖が小声で言う。「ドコ、イクンヤデ、シカシ?」
自動扉が開く。キヌは通路へ出た。
一言きり、伝えた。「うちに任せとき!」
ここは、一人で。たぶん、二人がいれば、キヌの足手まといになる。なぜか強く、そう思った。
——力がみなぎっている。
扉が閉まる。
キヌは深く息を吸い込んだ。
ヴォウウォウ! ヴォウ! ヴォウォウオン! グルルルルルフ! グルルルルルフ!
大声で吠えた! そうしながら、船内通路を無我夢中で走りまくった。
——さあついてきな、おつむの弱い怪物くん。
うちの仲間を、あんたの好きにはさせへんからな!
走る。走る。不思議と力が溢れてくる! 呼吸は全然荒くならん。
走る!
破壊音。近い。砕かれたパイプからガスの漏れる音。危険レベルを上昇させさらに速く大きくこだまする警報の音。照明も切り替わる。通路という通路が、警報音とリズムが同期した赤い点滅で満たされる。
そして前方の十字路左手から、真っ黒の巨体が姿を現す。
そいつは、最初に会った時よりも成長しているように見える。今はざっと、四メートル半はある。天井に頭を擦っている。
一瞬、キヌは息をするのを忘れる。ハエジゴクの腕の先、禍々しい爪の先に、ぶら下がっているものがある。
ハルの屍体だった。
(ハチに続いて……)
絶望は、けれども、キヌのこころと身体をすぐに通り過ぎていく。
あとには、強い活力だけが残る。
生きねば。キヌはそう思う。
その頭部に、目とおぼしき器官は見当たらないのだ。しかし目の前の怪物は、どうやらキヌを捕捉したらしく、首をまっすぐこっちに向けた。
ハエジゴクは地面を思い切り蹴り、キヌとの間合いを一瞬で詰めた。
同時に腕を振り上げていた。人体を砕き粉みじんに化してしまう凶悪な一撃が、キヌ目がけて振り下ろされた。
バチン! 音がした。
それは、キヌの発達した前腕屈筋群が、ハエジゴクの一撃を受け止めた音だった。
「いい加減にしいや」キヌは呟いた。「うちはもう、あんたを許さへん」
キヌの全身が、金色の光を放っている。
6
実力は、五分と五分だった。
かつて長き時間をかけて培った格闘のスキルを駆使して、キヌはハエジゴクと渡り合っている。血の滲むような努力の末に極限まで高めたロシア軍隊格闘術「システマ」——その理論を頭がすっかり忘れても、どっこい身体は、不思議に覚えている。
〈おそロシアのキヌ〉——それが若い時分、キヌが戴いた異名だった。幾多の戦場に立ち、命を救い続けた。授与された勲章の数は知れぬ。元来、キヌは名声なんぞに興味がない。
少しでも気を抜けばやられる。キヌの命は、常に死線の上にある。
だがそれは相手とて同じことである。少しでも隙を見せれば、その首に腕を引っかけ、砕けて飛ぶまで絞めつけてくれるわ。
ハエジゴクが、捕虫葉の大口を開く。熱い唾液が飛び散る。口腔内を覆い尽くす、禍々しい牙が覗く。噛みつかれたら、鋼のごとき硬度を得たキヌの上腕二頭筋とて、容易く粉砕されてしまうだろう。
選べ、キヌよ。
懐に飛びこむか?
——否。
まず、退くか?
——応。
大きく身体を仰け反らせた。たった今までキヌの身体があったその空間上で、噛み合わされたハエジゴクの顎が金属のそれに酷似した硬い音を立てた。
キヌはそのまま、一歩、二歩と後退した。
キヌの軌跡を喰らうように、ガキン、ガキンと、ハエジゴクは前進しつつ何度も口を噛み合わせた。
「あかん……!」
いつの間にか壁際にまで追い詰められていたのである。
もう後方には退けぬ。
選べ。
横に跳ぶか?
どちらに。——右か。
右! と見せかけ、ハエジゴクの即座の反応を捉え左に跳んだ!
フェイク。
ハチにその技を伝授したのは、キヌだ。
——が。
「!!」
右の脇腹に衝撃。
どうなっている?——気づく。尻尾だ。尻尾が、やつの身振りとはまったく無関係のものとして、独立してキヌを狙っていた。
吹き飛び、後方の壁に叩きつけられる。
「……ッ!」
思わず意識が飛びそうになるのを、純粋な気合い一つで押しとどめた。覚束ない両足と両膝と腰と——それらは全部自分の支配下にあるものなのだと強く意識する。倒れぬ。歯を食いしばり立ち続ける。倒れたらそこで運命は決まる。
血痰を吐き捨てた。
「決めるのはうちや!」怒号で強気を引き戻す。
ハエジゴクの腕が飛んでくる。
かっと目を見開いた。
ヌボボッ!
まただ。
まだだ!
「オオオゥッ!」
筋肉が急成長してキヌの身体が強くなる。
いける。
「返り討ちじゃ!」
渾身のストレートを放った。
ハエジゴクがその図体の割に小振りな手を開き、キヌの拳を真っ向から受け止めた。
かまへん。——そのまま、拳固を振り抜く。
ハエジゴクの腕がひしゃげる。バケモンが吠えた。
「泣いても許したらへんぞ! もう一発じゃ!」
右ストレートでぶっ飛ばす!
ハエジゴクは反応できない。キヌの拳が、怪物の胸部をもろに捉えた。
インパクトの瞬間に腕全体をぐるりと回転させることで、より深く、拳固を怪物の体内にねじ込んだ。
「オラァァァッ!!!」
キヌは雄叫びをあげながら、でかい図体を地面にねじ伏せた。
ハエジゴクが川辺の鳥の啼き声に似たか細い叫びをあげ、紫色の体液を吐き出す。
「んなッ!?」
キヌは思わず、密着した怪物の懐から飛び退く。
やばい。
これは。
やられた。
よもや。
あかん。あかんで? あかんかも!?
死——。
キヌの中で久々に目を醒ました戦いの勘が、高らかに警鐘を鳴らしていた。
紫の体液の飛沫が、手前の船の床を一瞬で溶かしていくのが視界の隅っこに見えた。そして船の心配をしている余裕などキヌにはなかった。
身体が、半身が、熱い。
強力な酸性の体液を、浴びたのはキヌの右半身全部だ。
ハエジゴクに対する注視を解けば、同じ瞬間に死がやってくる。目を離すことはできない。だから、自身の身体がどうなっているか、目で捉えることは困難だ。が——
——右のこの手はもう使い物にならぬ。そのことはわかった。焼けただれているだろう。
こめかみに手を当てた。そこにはもう皮膚がなかった。強酸に溶かされてぐんにゃりと変形した骨が露出していた。
これは、死ぬな。さすがに。
そのことがわかった。
「すまんな、みんな」
キヌには、この死闘の始まりから、決めていたことがあった。
『おそロシアのキヌ』は、一つの時代にあってその名を馳せた、戦闘のスペシャリストである。何の計算もなくただ攻撃をかわすのに必死だったというだけの理由で、このように壁際まで追い詰められたわけではない。
今、目の前の壁には、一個のレバーがあった。真っ赤な色に白抜きの文字で “CAUTION” 。
いざとなれば、それを。あらかじめそう思っていた。
キヌは躊躇わず、レバーを引く——
——否。重くて、引くことが出来ない。
ハエジゴクが雄叫びをあげる。耳をつんざく。口をあんぐりと開ける。
やられる!
その時、レバーにかけた手の裏側で、親指が出っ張りに触れた。
安全装置だ。
押し込んだ。
解除。いける。
ワン・フォー・オール。一人はみんなのために。
貫くのだ。
マダム・アリ、見とってくれよ、これがうちの心意気や!
改めてレバーを引いた。
ガコン! バーン!
緊急ハッチが開く。
次の瞬間もう、キヌの身体は地面という寄る辺を喪失している——浮遊感。
二人の身体が、船から投げ出される!
即座に視界が開けた。
世界は、全身に銀の色をまとっていた。いつの間にか、雪が降り出していたのだ。
超高度の冷気が、千の針のように身体を刺した。
落ちてゆく。
船はたちまち、はるか上空の点となる。後続の雪の内側に、隠れて消える。
見ればわずか数メートル先で、ハエジゴクは泳ぐようにもがいて、体勢を直している。
まなこのないその顔を、キヌに向けた。
「闘争本能の塊かい!」
キヌはもはや恐怖を感じない。意識は、さすがに朦朧としてきている。加えて、あまりにも強烈な剥き出しの本能にあてられて、恐れを通り越して呆れを感じ始めてもいるのだった。思わず、口元を歪めた。
「ああ、ああ、ええ! かかってきいや!」半ばヤケクソである。「来い! 来いや! 最後まできっちり相手したる!」
ハエジゴクが大口を開けて迫り来る。
それを、かわす! かわす!
イメージの奔流。
「ああ?」
花開く。
内なる花。
「なんじゃあ!?」
とくん。
心臓が。
花。
——キヌ。ねえ、キヌ。あなたは似てる気がしてるのよ、私に、どこかね。
どうして今頃になって、マダム・アリの言葉を思い出すのだ。
ぎりぎりのところで身をかわし続けるキヌの動きに、苛立ちが沸点を超えたのか、またハエジゴクが咆哮した。
「じゃかぁしい! 黙っとれ!」
視界を極端に狭める吹雪のさなか、キヌの身体は、いつしか再び発光を始めていた。
ごく自然な所作で、ハエジゴクのことなどまるで無視して、キヌは地上を見下ろした。
地上のすべてが、輝きを放っていた。
地球が、光に充ち満ちていた。
成長している。
この星の頂点。地球を統べる、獰猛な繁殖力を持つ現世君主——群生する、セイタカアワダチソウ。
伸びてくる。力強く天へと。太くたくましい茎が、若く元気な男性器のように。
先端に、花。黄色い花。咲き誇る。
萌える。世界が萌える。黄色く萌える。
キヌは、ふと、気がついた。これらの花々と、今現在の自分とはきっと、力の源を同じくしているのだろう。
思考が連鎖する。
たちまちにわかる。すべてが。
自分は、選ばれたのだ。それをキヌは知った。本当はマダムの役割だった。だがマダムは道半ばで生涯を終えた。だから、キヌが代わりに選ばれたのだ。
ハエジゴクの残忍な爪の先端が、キヌの頬にかすかに触れた。ぴっと赤い血が飛ぶが、動じない。その爪先にキヌはそっと手を触れる。
軽々といなす。
ハエジゴクは、おはじきの玉のごとく、後方にはじけ飛んだ。
「なあ、あんた」こころが、ひどく穏やかだった。——キヌはハエジゴクに語りかけた。「あんた、どっから来たんや? それに、なんの用事や……」
無論、答えはない。
キヌが相手にしているこの化け物は、一貫して変わらない。ただただ、剥き出しの殺意だけがそこにあるのみだ。
「あんたのことは知らんし、ようわからんわ。でもな、こっちかて、むざむざ嬲り殺しにされるわけにはいかんのじゃ。生きたい。生きねば。皆でな。せやで——」
キヌは、静かに告げた。
「——うちは、あんたの命を奪おう」
カルマや。今日から、あんたも、うちの。
地球を覆い尽くすセイタカアワダチソウの茎たちのように、キヌの胴体はたちまちのうちに、太く、屈強に膨れあがった。
今、虚空に瞬く天体の内、萌える花の敷き詰められた丸い球体の上に、一体の光の巨人が降臨した。
はるか上空で、〈孫〉船内の二人がその様を、地上の様子をじっと見下ろしていた。
威右衛門が、独り言のように呟いた。「デイダラボウシや」
吹雪吹き荒れる中、突如として楢山の後方に現れた巨人の姿を、村に残った爺婆たちもまた、見ている。
ダイダラ様じゃ。
巨人様。
デイダラボッチ様じゃ。
ありがたや。ありがたや……。
「ちあうわ」
独り言のように、静かに否定したその小さな呟きは、しかし不思議と、その場にいる皆に伝わった。
呟きの主は、かつてマダム・アリの世話役としてその篤い信頼を受けていた老女マチである。
皆が注目する中、マチは静かに続けた。「ボウシはおのこじゃでな。ちあう。あそこにおるんは、おキヌさんやで、女じゃ。〈メ〉じゃ」
——メ。
——デイダラメ。
「デイダラメ、かの。言うなれば」
巨人のその片足が、大地の上に立つ。軽やかに、とん、と。
そして村人たちは見たのだ。
巨人は、そっと、両の手のひらを重ね合わせた。
その姿が、神々しい。後光さす、如来のごとし。
両の手のひらの内側で、殺意に溢れた一匹の生き物が、夏の蚊のように、ぷつりと潰れ、ささやかな命を終えた。
上空では、棄老船〈孫〉の伊右衛門とマリアが、どちらからともなく顔を見合わせた。
帰ろう。
帰ろう。
母なる星に——。
そういうことに決まった。
セイタカアワダチソウの咲き誇る黄色い花々が、光を強くして茎から離れ、蠕動する蟲のごとくうぞうぞと、巨人の元に集まっていく。無数の花弁の輝きが、巨人の足下に集結していった。
そうして、ふわ、と浮遊した。
花弁たちのよりあわせにより生まれたのは、金色の雲であった。
それが、浮いた。キヌは、さながら、紫雲に乗った如来であった。
物凄い速さで、天へと昇ってくる。やすやすと〈孫〉の高度を超えた。なおも、高く高く。
デイダラメはほうき星のごとく、長い尾を引き連れているのだ。それは、へその緒を彷彿とさせた。母なる星が、命の花の萌える内で孕んだ、神の人。
威右衛門は、いつしか自然と、巨女に向けて手を合わせていた。
「南無阿弥陀仏」
そう、唱えていた。
「ナマアミダブツ」
マリア・聖も唱えた。
光る御身が遠ざかってゆく。虚空に消えてゆく。
地上でその軌跡を見つめる村人たちもまた、申し合わせたわけでもないのに、誰からともなく唱え始める。
——南無阿弥陀仏。
——南無阿弥陀仏。
以来、ダイダラメが一度きり片足で踏んだその足跡の窪みには、大きな湖ができた。かつての母なる星がその母性を蘇らせた、最初の出来事であった。
あの日、産声をあげた湖、巨人の足跡(ジャイアント・ステップ)より天の虚空へと高く伸びた光の塔は、今も消えずにここにある。
老人たちは時々、それに手を合わせてみる。
南無阿弥陀仏。
南無阿弥陀仏。
南無阿弥陀仏。
文字数:23201






































