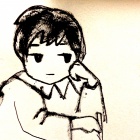作品プラン
《とある物語》ステートメント
新芸術校の前期を振り返って印象的だったのは,毎回異なる講師陣から投げかけられる様々な問いに対して生徒個々人が安易に答えを出そうとせず,それぞれの異なるバックボーンや問題意識に引き寄せた上で問いに答えようとしていたこと,言い換えれば,各個人がそれぞれ表現の核となるものを持っているということだった。
それに引き換え私自身は,自分の本当の問題意識を横に置いて,天皇や愛国者などのわかりやすく刺激的な表象を多用し,安易に極左主義者というポジションに落ち着いてしまった。確かに私はどちらかといえば左翼的な人間だが,本当の問題意識はそれよりもさらに「深い」ところにあり,今回の作品では前期のまとめというよりも,後期へ向けての再スタートとして,自分が本当に表現の核としたいものを見つめ直した。特に日本で美術をやる上で,作品が「自分語り」になることの危うさは承知しているつもりだが,強度のあるコンセプトは自分の実感に基づいたものでなければならない。よって今回は私の個人的な体験から作品を展開した。
私の父は私が3歳のときに自殺した。そのこと自体はまだ記憶のないときの出来事であったこと,その後の継父との関係が良好だったこともあり,さほど重要なことではなかった。ただ,自分の父親がどのような人間だったのかなんとなく興味はあったのだが,母はそのことについて一切喋らず,また自分から尋ねることもなかった。
しかし,小学校高学年のときに母が父について一つだけ教えてくれた。私の父は漁師だったということを。
それを聞いたとき,私は何故か無性に嬉しくなり,また,何かが腑に落ちたような気がした。継父はアウトドアが好きで,私をよく海水浴に連れて行った。私もまた海が好きで,海を見たときに感じる胸のざわつきは,自分の中に流れる「海の男の血」がそうさせていたのだと納得したのだ。
それ以来私にとって海は私と父が唯一繋がれるものとして一層特別なものになった。父の名前も知らず顔も見たことが無かったが,名も顔も知らなかったからこそ,一種の抽象性を保ったまま,全てを包み込む大海原のイメージと重なった。
やがて18歳になり,自分で物事を判断できる歳になったからと父の実家で祖父母に会うことになった。父が死んだため跡継ぎがいなくなった祖父母は私に会うことを長く待ち望んでいた。
父の実家へは母方の祖父母と3人で車で向かった。車内には重い空気が漂っておりほとんど口を利かなかったが,私はついに父の生まれ育った町,父の生まれ育った海を見ることができると内心浮かれていた。
しかし,運転する祖父が目的地は近いというにも関わらず,一向に海が見える気配がない。むしろ車は内陸へ進んでいるような気がする。徐々に不吉な予感が立ち込め,額には汗が噴き出してくる。そしてその予感は現実のものとなった。
「到着したよ」という一言を聞いた瞬間,頭の中が真っ白になった。そして,私の幻想は一挙にして打ち砕かれた。父の実家があったのは湖のほとりだったのだ。父は海の男ではなかった!
なんともいじらしくそこに佇む湖の姿は,私の期待からは程遠かった。荒波に立ち向かう海の男としての父も,私を包み込む大いなる父としての海も,全て私の幻想だった。父が漁師だったという唯一の情報から,海を見れば誰しもが少なからず感じる胸のざわめきを,「自分の中に流れる海の男の血が騒いでいる」と勝手に解釈し,思春期のナルシシズムも加わって,様々な物事を自分に都合の良いように解釈しながら虚構の物語を作り上げていたのだ。
しかしそれらは,たとえ虚構であったとしても確かな実感,リアリティが伴っていた。父の実家に行くまでは,海の男としての父も,大いなる父としての海も確かに存在したのだ。
そして,この体験は私にある考えを抱かせるようになった。私が父に関する虚構の物語を確かな実感を持ちながら生きていたように,この世のあらゆる物事には実体が無く,いくつかの約束のもとに,みんなが幻想を生きているのかもしれない。国家も性別も,家族も文化も,ありとあらゆることすべてが物語に過ぎず,何一つ実体として存在するものなどないのだと。私はこの後仏教に傾倒し,その確信を深めていく。
言語によって紡ぎだされる物語による,実体が存在するという錯覚から自由になること。仏教における「空」の実践こそが私が作品にすべきことである。
文字数:1792