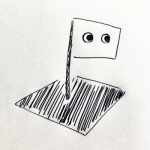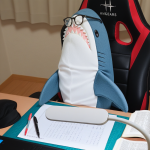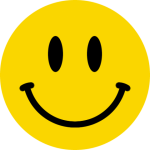そんなことはわかっている、と思われそうなテーマですが、この講座では繰り返し、梗概に頭をひねることになるわけです。
結局のところ梗概とはなんなのかというのは実は、小説とはなんなのか、というのと同じくらい不思議な問題であり、特に定見はないようです。
それでも、梗概と小説には大きく違うところがあって、梗概には「どんな大きさの話でもとりあえず入れることができ」ます。1200字の小説に大河ドラマを入れることはできませんが、梗概になら可能です。
一般的には、梗概には段取りが入っているはずです。登場人物の具体的な造形や、固有名詞は二次的なものです(そこから発想を広げるのは無論、大切なことです)。
何らかの段取りがあり、変換、変転があり、お話は終わる。その段階が書いてあるはずであり、特にこの頃のエンターテイメントにおいては、そうした作り込みが主流となりつつあります。
「どのようにして終わるのか」までを考えて効果的な配置を考えて下さい(続く、や、その謎とは……、にしない)。梗概の文章は小説の文章とは全く違ったものでありえます。
とはいえ、小説はそういうものではない、という意見もあるかと思います。自分もそう思います。実際に書いていく中でわかっていくことがあり、そのようにしか書けない、という人もいるかと思います。
しかし、(この講座において)実作の前にあるのが梗概の審査である以上、その場合でもなんらかの対策は必要でしょう。段取りを書けないのなら、段取りではないお話であることを提示する工夫をしてください。
実作と、梗概で予定されていた段取りの齟齬は問題としません(そこを判定するのは次回の講師の方々ですが……)。