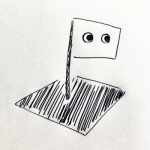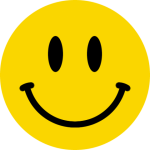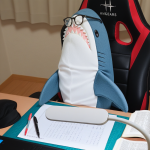梗 概
健康で文化的な最低限度の幸福または不幸
主人公は大学受験で全滅した。彼はその結果に絶望感を抱き、その感情が転機を迎えないという主観的事実が彼の究極的な不幸(BMIへの不応)を証明していた。だが彼はそれを隠している。珍しい不幸を背負った見世物としてJohn the Savageの如く扱われるのを怖れたのである(主人公は『すばらしい新世界』読了済)。
主人公はネット上であるVシンガーの曲に出会う。
「はぎ取らないで 仮面じゃないの
それは血が通う ほんとの皮膚なの
返品もできない たしかに不良品なの
それでも体温だけは 律儀に残るの」
不幸を排除しようとしない歌詞に主人公は惹かれていた。あるオンラインライブでファンの感想を募集するコーナーが設けられる。ライブ中に音声入力が解禁され入力された中からシンガーが気になる感想を読み上げるというのである。予想外のタイミングで音声入力が始まり主人公の口をついて出たのは
「不幸が表現されているのを聞いて幸福になってるって結局不幸を肯定するようで否定してる…」
主人公は自分のコメントを悔やむ。当然採用されず、だがライブ終了後に主人公のアカウント宛にメッセージが届いた。未発表の新曲を証明代わりに添付したメッセージには病院の地図が添えられていた。そこに向かった主人公は昏睡状態の少女に会う。主人公のアカウントに再びメッセージが送られ、その少女が昏睡に至った経緯が伝えられる。少女の父親は賭け事に興じ、DVの気があった。12歳になった少女に手を出そうとして拒絶され家を出ていったが、以降母親はアルコール依存となり酔う度に「あんたのせいで全部だめになった」と口にした。結局行政が入り母親は生活保護の一貫としてBMIを受け取って娘への憎悪を覗かせたまま幸福を得た。やがてBMIは少女にも支給され、少女は母親と同じくBMIで幸福を得てしまったことに絶望して飛び降りたのだった。
主人公のアカウントにメッセージを送っているのは昏睡状態の脳活動を維持する努力を続けているBMIが生み出した仮想の人格だった。その人格は主人公に相談を持ち掛ける。曰く、ネットの海の中でBMIの致命的な欠陥を突くウイルスの存在を感知したというのである。そのウイルスの存在を公表しBMI社会を守るべきか、それともなすがままに任せて崩壊を静観するべきか。決める権利がある者を探していたのだ。
「人間というのは想像力に欠けた生き物で、遠くの誰かの苦しみを勘定する振りをしていても、結局は自分の周りのごく小さな世界で胸のすく思いのする方の選択肢を採る。そういう自分の不幸の代償行為に自覚的にふるまうのが僕たちの美学なんじゃないか?」
主人公の提案でウイルスは公表され、BMIを標的にしたテロが社会リスクとして認知されるようになる。結果BMIフリーな人間を安全装置として残すことが提唱されるようになった。主人公は立候補しBMI社会の中で居場所を得ることになる。
文字数:1196
内容に関するアピール
西暦2075年。ブレインマシンインターフェイス(BMI)による脳機能への介入技術は円熟期を迎え、安全面・倫理面・コスト面いずれにおいても社会実装に堪える水準に到達していた。開発当初は手術による脳への直接的な埋め込みが必要だったが、今や頭に被るだけで磁気刺激を介して脳内神経ネットワークとの相互通信が可能になっていた。
BMIがもたらすのは「幸福」そのもの。安易に快楽中枢を刺激するのではなく、過剰な主観的「不幸」により一定期間以上の脳活動の低下が見られた際に、本来は大した効果をもたない小さな主観的「幸福」を増強し各脳部位の活動を促進することで、最低限度の「幸福」を担保するという仕組みだった。
確かにBMI装着者は幸福になった。だが、装着者にとって人生の不幸はBMIによってもたらされる幸福の前奏曲に堕していく。それは他人の痛みへの鈍感さをもたらし、世界はむしろ不安定化していた。
文字数:389
メメント・フェリキタス
私は親の顔を知らない。親がいたという記憶もない。
そのことが他の人と自分を分かつ看板になるということを経験的に学んだとき、私は何かを喪失したというより何かを付加されたと感じたものだ。元から存在しないものを失うことができないのは自明の理である。
だから私はルーツを求めるなどという動機で旅に踏み切った自分をどこかで自虐的に見ていた。こんな自分探しめいた旅の話など十代の話でも酒の席の勢いがないと話せない。二十代に突入している今の私ならなおさらである。
でも実際に旅には出ているわけで、意識的に自虐すること自体が気恥ずかしさを誤魔化すための方便であるという自虐もできる。
タラップを渡りきればもう目的の島国の土を踏むことになる。眼下に揺蕩う海面は頭上の晴天の輝きを乱反射させていた。快晴らしいその輝きは清々しいものだったが、見つめているとサングラスモード越しでも網膜が焼かれるのを感じる。私は目をつぶって太陽光の残像を振り払うと、一思いにタラップを渡り切った。
異国の土。
事前に確認していた予想最高気温は34℃。不快指数は絡みつくような湿気のせいで気温相応以上をたたき出す。私はいつもの習慣で、地図アプリを開いた。○○鮮魚店、◇◇釣り具店。次々と見慣れない文字が視界上に現れ、同時にレストランやらカフェやら駐車場やらが世界共通アイコンで表示された。だが、アイコンではレストランと表示されている目の前の建物は、明らかに無人で放置されて久しいいでたちである。その隣にあるはずのスーパーマーケットも同じ。平地があればそれで充分なはずの駐車場さえも雨風や雑草の侵食を前になすがままになっていた。
私の知る限りこのアプリの表示が間違っていたことは一度もない。そんな人生で一度あるかないかの偶然を立て続けに経験している原因は視界上に表示されている赤文字のテロップが明らかにしていた。
地図の最終更新から十年以上が経過しています。
開いた瞬間からその警告は表示されている。私は今自分のいる場所が別のルールの下に動いていることを思い出した。地図一枚でも正確であればあるほどそれは軍事情報に近似されるものなのだ。
私はそれで渡航前に予めインストールしていた地図アプリを開いた。ARで地図情報が表示されるタイプではなく、ゴーグルの視界の片隅にGPSでの位置情報と周辺地図が表示されるタイプのものである。目的地を入力すると進路が地図上に表示される。開く前から分かっていたことだが、性能はお世辞にも良いものとは言えなかった。GPSの位置情報は1ブロック程度は簡単にずれる程度のお粗末なものだし、建物の情報も曖昧なものが多い。
だが、政府指定のアプリはこれしかないのである。私はため息をついてキャリーケースを片手に示されたルートに従って歩き始めた。
それから歩くこと十分後。
「……っはぁ、はぁ……ったく。高低差情報も……無いなんてね」
登り始める前からその坂が私の持つキャリーケースとの相性が壊滅的に悪いことは分かっていた。舗装が十分でないアスファルトはあちこちが窪んでいて、かなりの頻度で車輪がひっかかることになるし、動摩擦係数のみに依存した仕事というキャリーケースのコンセプトを根本から踏みにじるのが坂道である。普段なら当然高低差も考慮して最適なパターンがいくつか表示されるのだ。脳内のストレス性電気活動量から推奨負荷が計算され、最適化された道が示される。ストレス値が高いなら負荷を下げるために、例えば雨ならば水たまりが出来やすい低地や未舗装の道を避けるし、このように荷物がある場合には海抜変化が少ない順路が選ばれることになる。
目的地は山の上ということでもないので、最終的な海抜変動は大きくない。こんな坂道避けてしかるべきなのだ。
そんなことを考えながら空を仰ぐと、いつの間にか頭上には雄大ながらろくでもない景色が広がっていた。
入道雲。
夏場の積乱雲のことをこの国ではそんな風に呼んだらしい。そんな知識が頭をよぎり、私はすぐに雨宿りの場所を探さねばならないことに気づいた。
だが周囲にまともな建物はなく、今すぐ登ってきた坂を下って先ほどの廃墟を借りるか、坂道を上った先に何かあることを期待するかしかない。
これまでの苦労を無に帰して確実な雨宿りをするか、それとも坂を登りきった先に懸けるか。一瞬の逡巡の後、私は後者を選択して、下腿に力を込めた。
直ぐにゴロゴロという音が聞こえ始めて私は足を早める。ただでさえ高めな湿度がさらに服の中で籠って、私は既に飽きるほど体験したはずの窪みでの車輪の跳ねにすら舌打ちしかねないほど、苛だつのを感じていた。
息も絶え絶えにたどり着いた坂の頂上。そこには今にも崩れ落ちそうな確か寺とかいう伝統的建造物があるだけで、坂を下った先にも何も良さそうな雨宿り先は見つからなかった。どうしようかと迷っているとポツリと鼻根に冷たい感触があり、その感覚はすぐに額、頬と増えていく。周囲のアスファルトにも次々と雨粒が衝突し、その身を砕きながら雨音を響かせんとする。
仕方なく私は目の前の一番目立つ建造物へと走っていった。屋根のない門をくぐるとそこからは石畳の道が伸びている。最後の全力疾走でもキャリーケースは石畳のくぼみに引っ掛かり何度もバウンドした。プラスチックと御影石が何度も衝突を繰り返した。
何となくアスファルトよりも音が滑らかだったな。
そんなどことなく間の抜けた感想を抱いたのはとりあえず雨をしのぐ場所を確保できたからだろうか。
私はすっかり周りの音を押し流し始めた雨音に目を細めながら周囲に目をやった。座る場所を探って自分が今階段の目の前に立っていることに気づく。中に入れるのだろうかとその先に目をやると進路を阻むように人一人は入りそうな木箱があった。
無理矢理箱を避ければ中まで入っていくことはできそうだったが何となく気が引けて、私は階段の埃を少し手で払うと、そこに腰を下ろした。
雨の勢いはますます強まり一フィート先も朧げになってきた。雨粒が屋根を叩く音は強まり、周囲の建物すら曖昧になる。普段と違ってゴーグル上に周囲のアイコンが示されるわけではない。隔絶された空間にたった一人。ひょっとしたら外はノアの箱舟の如き大洪水で私は生き残った最後の人類かもしれない。
異国の廃墟の中でそんな気分に浸って我ながらちょっとハイになっていたのかもしれない。私は百年以上前の映画のテーマ曲を口ずさんでいた。雨を前に歌うにはぴったりの曲である。走ってきたせいですっかり汗をかいてしまって気分爽快とはいかないが、この曲を主演俳優が歌う名シーンでも俳優は高熱を出していたらしい。コンディションが悪いからこそ分かるこの曲の力強さ。なるほど世界の半分を支配していた頃の我らが国を感じさせる名曲である。
そうして、どこを見るでもなく外を眺め続けること十分ほど。次第に雨脚は遠のいていき、溶けていた輪郭がその本来の形を思い出し始める。
その中だった。ふと視界の端に赤色の何かが現れる。間違いなく赤系統の色ではあるのだが、あまり見たことがない類の赤。それに緋色(スカーレット)という名が付いていることは後ほど知った。
その赤色の物体はゆっくりとこちらに近づいてきて、段々その赤色の下に人の輪郭があることが分かってきた。そしてさらに近づいてくるとその赤の中に竹だろうか。骨組みのようなものが見えて、それが傘であることが分かってくる。
「おや。珍しい鳴き声の猫かと思っていましたが」
そこには一人の初老の男が立っていた。
音声が翻訳され、ゴーグル下部の方に字幕の形で表示される。自動翻訳(日本語→英語)の表記を見て私は思わず立ち上がった。
思いもよらず出会った目的の民。
「あ…」
何と返すか迷っている私を見て、老人は少し不思議そうな顔をした。
「珍しい若い同胞かと思いましたが違いましたか。これは失礼。もうデフォルト翻訳では我々の言語の翻訳はされないですかな」
翻訳はされている。そのためにわざわざアップデートされていない少し旧型の機種を探したくらいなのだ。
「いえ、分かります。ただ、こんなに直ぐに会えるとは思っていなかったものですから」
私が英語で話すと男の耳にかかっている機械が微かに点滅するのが分かった。
「そうですか。わざわざ訪ねられたとは何かご事情がありそうですが……」
言うと男は少し口元を緩める。
警戒されているという感じはしない。
たった五十年前には一億を超す人口を抱えながら今や消滅を前にしていると言われる民族の生き残り。だが、彼の表情には憤怒も哀切もない。
私が男の雰囲気に戸惑っているとそのまま三秒ほど間が開く。その間が違和感を抱かせるものになり、ようやく私は相手がこちらの言葉を待っていることに気づいた。
「えっと……その……」
私がしどろもどろになっていると男は柔和な表情そのままに口を開く。
「そちらの方は後で伺いましょう。一度御着替えされた方が良い」
そう言われた瞬間だった。額に張り付く髪の毛や皮膚に張り付くシャツの感触が意識の遡上に上る。あの一瞬でも意外と身体を濡らしてしまったらしい。
本来は指摘されて気持ちの良い話でもない。だが、何故かそのやり取りだけで私はすっかり毒気を抜かれてしまった。何となく頭の中で復習していた防犯スプレーの位置なども思考から流れ落ちていく。
「降ってきて直ぐに駆け込んだと思ったのですが」
今の自分の感覚に意識が向けば言葉も混線を起こすことはない。
「それでも間に合わないのがこの季節の風土というものですよ」
言うと男は傘を畳んだ。動作はゆっくりとしていながらもそつがなく、修練ではなく習慣によって洗練されたものであることが分かる。
「どうやら我らが民に興味をお持ちのようだが、数を減らしてしまった我らより、この地の風土を体験してもらうのが正しい理解に近いかもしれないですからな。国破れて山河在りとはよく言ったものです」
それが『春望』という唐の詩人・杜甫の律詩の引用であることが、自動翻訳の注釈で示される。
唐! 私は表情に出さないように気を付けながらも自身の中の驚きを噛みしめずにはいられなかった。まさかそんなところから引用するとは。
「この通り朽ちかけたものではありますが、裏の方では細々とやっております。せっかくですから御着替えがてら我らの服を試してみるのも良い経験になるでしょう」
言うと男は再びこちらに視線を向けた。その目にはそれこそ今の雲模様から天気を伺うかの如く純粋な情報収集の意図しか伝わってこない。なんと言うか距離感が難しい相手である。
私がそれで黙っているとそのまままた三秒ほど間が開いた。
男は急かすこともなくじっと立っている。
それで私は一度息を吸うと口を開いた。
「ぜひお願いします」
案内された先は雨宿りした建物と同じく床や柱梁は木製、屋根は石でできている(あとで確認したら瓦という粘土製のものらしい)構造だった。
踏むたびにぎしぎしと軋みを上げるのは少し不安要素だったが、中から案内に出てきたのが自分より一回り年下の少女だったからか次第に緊張も和らいでいく。
「◇◇様からは巫女装束の体験をさせてやれとおっしゃっていましたので……」
言いながら彼女は何かを読み取ろうとするように私の顔を見つめた。だが、私は文化体験に来ただけの酔狂な女という以上の情報は返さずにおく。
「少々お待ちください」
そんな表情と表情のやり取りは一瞬のことで彼女は床に正座するとゆっくりと紙でできているらしい扉を開けた。空いた先には緑がかった細かい縞模様の床が広がっていた。扉はふすま、床は畳というのは予習で勉強した話だ。
女性は先に部屋に足を踏み入れるとそのまま奥の方へと入っていった。雑然と物が散らかった机の上を整理するとそれをゆっくりとずらしていく。机が押し出されていく先には同じく雑然と物が散らかっていて、客人のために机の位置を調整していると言う風には見えなかった。
机を動かすこと五、六フィートだろうか。彼女は机の位置を確認して満足したように頷くと立ち上がった。そして畳の端の方を手で探るようにする。ちょうど中点くらいの場所で彼女の手が止まり、一瞬彼女の手が畳に沈み込んだように見えた。そして彼女はそのまま立ち上がる。
するとまるでそれが当然と言わんばかりに滑らかに、畳が舞い上がる埃を身に纏わせながら持ち上がった。そしてその下の空間が明らかになる。ギィと錆びた金属が軋む音がして畳はそのまま固定されたままになる。彼女は平然と畳の下の空間に降りると、そこから身の丈ほどもある薄い木箱を持ち上げた。
「お待たせしました」
畳を下ろし、机を元の位置に戻して、さらに雑然とした雰囲気すら元に戻して、そうして彼女が木箱を片手に戻ってきたとき、私は何やらとんでもない秘密に触れてしまったのではないかという気分になる。
だが、彼女は別に直接口止めをするでもなく、ゆっくりとまたどこかに歩き始めた。私はやや遅れてそれについていく。キャスターで木の床を擦るような無遠慮をするつもりはなかったので、万が一にと詰めた様々なものを恨めしく思いながらヨタヨタと歩いていく。
「シャワーを浴びていかれますか? その間にお着替えの用意もさせて頂きます」
おそらく自分の部屋なのだろう場所に着くと彼女は再び口を開いた。
私は言われたままに頷くとキャリーケースを手に部屋の中へ足を踏み入れた。瞬間、部屋の外から吹き込んできた湿った風が畳の香りと結びつきながら通り過ぎていく。何とも言えない調和に私は先ほどの「国破れて……」のくだりを思い出した。
シャワーは案外普通で、どこにでもありそうなシャワーとバスである。出てくる水の勢いが緩やかで、流速も水温も安定しているのは慣れない感覚だった。
タオルを巻いて出てきた私がキャリーケースを運び込んだ部屋へと向かうと、そこは既にふすまが閉め切られていた。
そして木箱から取り出された白と緋色の服が広げられている。
「これは……?」
「今では貴重な巫女装束です」
若干不機嫌そうなのは気のせいだろうか? リアルタイムとはいえ、あくまで字幕を介してのコミュニケーションである。イントネーションの違いでそんな風に聞こえるだけかもしれない。
私は彼女と目を合わせようとする。だが、彼女は丁寧に巫女装束を広げていてその視線は自身の手先に向けられていた。
何となく彼女が自分に良い感情を抱いていないという認識は正しいかもしれない。少なくとも確実なのは、この服が特別なものであるということだ。であれば、なぜ今日出会ったばかりの私が着ることを許されたのだろうか。
「貴重な機会をいただきありがとう」
「着付けは分かりますか?」
「ごめんなさい」
「そうですか」
やはり彼女の言い方には若干のとげがある。それで私は何となくいたたまれなくなってこんなことを口走ってしまった。
「でも、向こうでは色々勉強してきたんです。この床は畳と言うのでしょう?」
すると彼女は少し馬鹿にしたように顔をしかめた。
「そんなもの常識です。これを着るなら例えばそう、この神社が祀っているのか男神なのか女神なのかそれくらいは知っていてもらわないと」
言いながら彼女は少しだけふすまを開けた。
私は自分の恰好を思い出してふすまから漏れる光を避けるように飛び退ったが、やがてその動作がヒントを与えようとしているものだと気づく。私はゆっくりとふすまの隙間に近づくとそこから外を覗いた。
この部屋はちょうどこの神社(shrineという字幕表記で私はこの国にtempleとshrineがあることを思い出した。彼女の眉間の皺が増えるだけであろうということは想像できたから口に出そうとは思わなかったが)の全体が見渡せる場所であるようだった。駆け込んだときにくぐった屋根のない門も雨宿りした建物もその奥に実は控えていたもう一回り大きい建物もよく見える。ここから見て始めて分かったが、雨宿りした建物もその奥も随分と痛んでいるようだった。特に奥の方など屋根に穴が開いてそのままになっている。藁のようなもので作られているらしいそれは今にも崩れ落ちそうに見えた。
だが、どこを見渡してもここが祀っているものを示すようなものは見当たらない。私はふすまから身を離すと頭を下げた。
「何も知らないでごめんなさい。袖を通させていただく前に色々教えてもらえませんか?」
すると彼女は少したじろぐように後ずさった。
私が顔を上げると、彼女の目線は何があるでもないふすまの方に向いている。
「分かってくれればいいんですよ。あの屋根を見てください。千木と言うんですけどね、あの空に向かって伸びている軸木があるでしょう? あれの先端の断面が垂直に切られていると男の神様、水平になっていると女の神様なんです」
「するとここは女の神様なんですね。どういう名前の神様なんですか?」
「あの千木と屋根の材質を見れば大体決まっています。天照大御神ですよ。天照大御神と言えば太陽の神様で天の岩戸という逸話があって……」
彼女の言葉に熱がこもったのが分かった。
ここから主人公は神社の本殿で男から歴史の話を聞くことになります。
(申し訳ありません。スケジュール管理が甘く全編を書ききることができませんでした。)
約二十五年前、日本は大陸の国家と矛を交えた。国力差は明らかだったが同盟国たる米国の支援もあり、しばらくは善戦していた。だが、長引く戦争はじりじりと国民の生活を締め上げていく。
国民国家同士の戦争というのは総力戦であり言い換えれば血の一滴一滴までも天秤に載せる我慢比べである。時間が経てば経つほど日本国内の状況はひっ迫していった。その時に米国は極秘裏に開発していた技術を日本に提供したのである。
脳内ネットワークを磁気刺激によって調整することで直接的に幸福な状態を再現する。物理的な支援の限界を見越して、その不足に対する不満を消去する術はまさしく総力戦を戦い抜くための究極的な解決策だった。
だが、期待とは裏腹にそのツールこそが日本という国を亡ぼすことになった。戦線は急速に崩壊し、普及開始から僅か一年足らずで日本全土は占領下におかれることになった。
日本人の平均寿命は急速に減退。かつて八十を超えていた平均寿命は四十を割り急速にその人口を減らすことになったのだ。米国は直ちにその技術を規制したが全ては手遅れだった。
一方で占領軍はその苛烈な占領政策の象徴としてそのツールのコピー品を量産。それを占領地で住民に強制し、今では日本人という民族は消滅の危機にさらされている。私はそのように聞いていた。
「今の私には分かります。あれは素晴らしい贈り物でした」
私は耳を疑った(正確には字幕表示を読み取る目を疑った)。
「素晴らしい? 副作用のせいで急速に人口減少が進んだと」
すると彼は首をかしげるようにする。
「副作用? そんなものはありませんでしたよ。あのツールはただ身に着けた人を幸福にしただけです」
言いながら彼は耳にかかったツールを指さす。
「これは大陸の模造品ですが、未だにこうやって身に着けております。私がどこかおかしいように見えますかな?」
「それならなぜ戦争に負けたのですか?」
すると彼は当然のように言った。
「今この瞬間、幸福なのにどうして戦争に勝つ必要がありましょう?」
「……」
私は絶句した。そして同時にこれが「副作用」の正体であることを悟る。
その私の表情を見て、少し面白そうに彼は笑った。
「少し意地悪でしたな。今のあなたの戸惑いは私にとっては理解できるものです。このツールの適合率には個人差がありましてな。周囲の人々が皆幸福になっていく中、私はいっこうに幸福のこの字も感じられずに過ごしておりました。だからと言いますか、あなたが今疑問に思っていることも分かるつもりです」
今では彼は
そして彼は少し隣に御神木の苗木へと目を向けた。
「そもそも幸福とは何でしょうか?」
私は視線を落とす。
頭に浮かんだのはマズローのピラミッドだった。
「生理的にも社会的にも満たされて、自己実現ができることでしょうか?」
すると彼は少し悪戯っぽく笑った。
「ここが神社だからと遠慮しなくても良いのですよ。天国に行けると確信することなどはいかがですか?」
確かに私を育ててくれた組織に教会からも支援があったという話は聞いている。だが、毎週教会に行くような模範的信徒という訳でもない。
何となく後ろめたいところを突かれた気がして私が迷っていると彼は口を開いた。
「失礼。いたずら心を抑えなくてはいけませんな。気を悪くなさらないでください。別にあなたの中の答えを茶化すつもりも否定するつもりもないのです」
「では幸福とは何だったのですか?」
すると彼は答える代わりにこんなことを口にした。
「あなたは映画をご覧になることはありますか?」
私は頷いた。
映画は昔から好きだった。
映画を観ているとき、私は誰かの物語の傍観者で居られる。自分はどういう人間でどうして欲しいのか。それをプレゼンし続けなければならない責務から解放されるのだ。そしていつも私を囲む誰かのようにプレゼンを受ける側に回ることができる。しかも、映画の中のキャラクターはプレゼンを観ている者の存在に決して気づくことはない。どんなに勝手な受け取り方をしようとそれが誰かを傷つけることはないのだ。
「であればそうですね……幸福とは映画のスクリーンになることである。そんな風に言えるのかもしれません」
私はこの前に行った映画館を思い出す。自分がぺちゃんこに潰されてのっぺりとそこに張り付いていくイメージが頭に浮かんだ。私は検討外れなイメージを振り払うように視線を男に戻した。
「スクリーンは瞬間瞬間を切り取ってただそのままに表示します。物語という解釈に入力を流し込むことなくただ入力されたままに表示する。そしてそれを直ぐに手放してまた新しい入力をそのままに表示する。そんな感じ方でしょうか」
「それに至るのが簡単ではないことは分かります。ただ、それが幸福とどのように関連するのでしょうか?」
すると彼はまた三秒ほど間を開けた。
「……そうですね。では先ほど挙げて下さった例で考えてみましょうか。生理的に満たされる。例えば空腹を考えてみましょう。空腹なときそれを満たすために人は行動します。そして満腹な状態になることを希求する。そしていざ満腹になればその欲求から解放されるわけです。この一連の過程をもって幸福に至る。そこまではよろしいでしょうか?」
「はい」
「この構造から分かるのは幸福とは欲求が満たされない状態からの解放であるということです」
「そうなります」
「では解放されたあなたの認識は目の前の景色をどのように捉えるでしょうか? 空腹な間は食べ物を得られるか否かという基準で引かれていた境界線が消失することになる。その分だけあなたの認識はスクリーンのそれに近づいたのではないでしょうか?」
「ではツールがその境界線の消失をもたらすということですか? ですが、食料が必要ないということにはならないでしょう?」
「その通りです。それで食料が無くても良いということにはなりません。食糧というのはある一定を下回れば認識だけの問題ではなくなります。生化学的な過程が阻害されるほどに栄養状態が悪化すれば、どうにもなりません。ですが、例えば問題になっている欲求が社会的欲求であればどうでしょうか?」
彼は一拍置くと続けた。
「家族・友人・コミュニティ・国家。それらは全て人間の頭の中に存在する概念です。それが不足するということを脳が感じなくなったとき、つまりそれに対する欲求を失ったとき、新たにそれらを獲得しなければ破綻する瞬間はあるでしょうか? これは強がりでもなんでもありません。人々はたった一人で幸福でいることが可能になったわけです」
私は想像した。
誰もが孤独なままに幸せになっている世界。それはどこか寒々しく感じてしまう。それを彼は察したのだろう。笑顔のまま彼は続けた。
「別に皆が互いを疎外し合う訳ではありませんよ。お互いに心地よい言葉を投げかけ合う喜びが消えたわけではありませんから。そうではなく、誰かから愛されなければ幸せになれないという前提が消えただけです。だから家族という形態も残りました。次第に繋がりは緩んでいきましたが」
「でも国家は維持できなかったと」
「ええ。平時ならともかく総力戦の最中で欲求を失った人々が国民国家を維持するのは不可能でした。次第に占領地を広げていく中で相手もこのツールの供給を維持するメリットに気づき、そうなってからは全土が占領されるのにそう長くかかりませんでした」
私は思わず反駁する。
「戦争に勝てない理由は分かりました。でもそれだけで平均寿命が半分になるでしょうか?」
すると彼は飄々と言った。
「国家だとかそういった集団をまとめるための幻想を何故人は信じるのか。答えは明白で、信じてしまう人々が作る集団がそうでない孤独な人々を淘汰していったからです。信じるのが人の本来の形というわけではなく信じる人が生き残るという単純な話なのでしょう」
彼は再び一呼吸置いた。
「今の幸福を実感することに集中している人は未来を見つめなくなりますから。極端な話、一秒後に死ぬと分かっていたとしても幸福であることは可能なのです。ゼノンの矢のように、瞬間瞬間を生きている人にとって一秒後も千年後も無限遠に等しいのですから」
そこまで語ると彼は視線を私に戻した。
「ただ、あなたのような当時の未成年はそうもいきませんでした。神経ネットワークに干渉するツールを発達段階の子供に使用するリスクは未知数でしたから。故に彼らがただ不幸として祖国を失っていく苦痛は未解決の問題として残った。幸福に滅びていく人々にとって最後の楔として残ったのがあなた方と言えたでしょう」
「そして、あの子もそうなんですね」
私がそう言うと彼は苦笑した。
「おっしゃる通りです。彼女を見ていると国民国家のようなものがかつてこの地に存在していたということを思い出します」
この後、主人公は目的地に到着しそこでツールを身に着け、その効果を実感することになります。主人公は米国に戻る理由を失い、代わりにパスポート諸々を神社の少女に預けてしまいます。
主人公は親を探してやってきていたのですが、男が主人公の父親だったのだと、神社の少女は気づきます。娘の寿命が縮まっても良いのかと少女は言いますが、主人公も男も耳を貸しません。真の幸福を知る二人にとってそんなことは問題ではなかったのです。
(ここを一人称視点で書きたかったのですが、スケジュール管理が甘く間に合いませんでした。重ね重ね申し訳ありません。)
文字数:10801