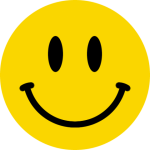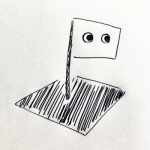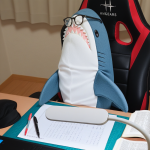梗 概
セーヴルの砂
陶芸家の真央は、学生時代にチベットの僧院で託された五色の砂を、白磁に小窓をはめた自作の砂時計に封じる。ろくろの前で彼女は「速い時」と「遅い時」の狭間に生まれる小さな“穴”を感じ取り土と会話する――それはチベットの「ルン(風・息・気)」に近い感覚だ。上野のギャラリーでその砂時計は、無口な来訪者・白石の目に留まる。彼は国際度量衡局(BIPM)の計測技術者。無言で計測し、その場で購入、後日波形データを携えて再訪する。注意が揺れやすく直感の鋭い真央(ADHD傾向)と、社交は不得手だが手順と精度に長ける白石(ASD)は、不器用に補い合うように惹かれていく。
二人はチベットへ。僧たちがチャクプル(金属製の漏斗)で砂曼荼羅を描く儀礼の最中、チャクプルの擦過音、真央の呼吸、白石の計測波形が一拍だけぴたりと重なる。同じ頃、世界各地のログに「時刻の微小な不整合」が報告されはじめる。白石はフランス・セーヴルのブルトゥイユ離宮(BIPM本部)へ真央を招き、局長は協定世界時(UTC)が原子時計と地球自転の“仲裁”で保たれてきたこと、しかし今は危うい揺らぎが出ていることを告げ、真央の“体感”が欠けている文脈を補うかもしれないと協力を求める。
実験室では、真央の呼吸と心拍、僧のリズムがある位相窓で一致し、外界では信号や決済に障害が走り世界のインフラが崩れ始めている。数値は明瞭に示す――「世界協定時は真央本来の時間に同期可能」。それは世界の時間を支える「守り人」の資質の証左だった。やがて二人は死期の迫る現役の守り人、イラン出身の細密画家アルマン・サーデギーの書斎に入る。机には二つの砂時計――古い陶器のラベルにはペルシャ語で〈نگهبان(守り人)〉、もう一つは真央の砂時計。僧のマントラと招かれたアボリジニ奏者のディジュリドゥが低く響く中、真央がアルマンの手を取り砂時計を反転させると、呼吸・鼓動・儀礼音が完全一致し、世界のログから赤い警告が引いていく。アルマンは拙い日本語で「アリガトウ」と告げ、静かに目を閉じる――火は移った。
世界は整い、通信も鉄道も平常に戻る。だが真央の内側では、長年ともにあった“穴=ルン”が閉じ、「土の声」が聴こえなくなる。日常は白石の不器用な愛情と優しさに支えられ続くが、白石の視線には“見張り人”としての役割も混じっている。真央は「ねえ、あなたがここにいるのはお仕事?」と問う。嘘をつくことの出来ない白石は「仕事です。でも、それだけじゃありません」と答える。
台所の水音の向こうで砂時計の粒が一つ、また一つ落ちる。世界は一つになった真央の時間と同期し整った。しかし、失ったルンの残像は真央の胸に居座る――いまはそれでよい、まだ「いまのところは」。ふと視界の端に、砂時計を壊す自分の姿がよぎる。守り人としての時間は動き出したが、その終わりの気配も、同じフレームに既に入り始めている。
文字数:1198
内容に関するアピール
共通の言葉や単位などを頼りに人間は暮らしていますが、時間も協定世界時が存在することで成り立っています。協定世界時は、原子時計と天文時計のズレを調整しながら運用されています。もし、その調整を特定個人の時間感覚が引き受けているとしたら?
この物語の主人公は、陶芸家の真央(ADHD)です。真央は二つの時間を生きていて、落ち着きがありません。でも、土をいじる時、時間の狭間の穴を通じて土と会話することができるのです。
その真央が、学生時代にチベットの僧院で授かった砂曼荼羅の砂を封じた砂時計を創ったところから物語は始まります。
協定世界時が揺らぎ始め、世界のシステムが崩れ落ちそうな中、白石(ASD)という計測者と不器用に惹かれ合っていき、最後に真央は創作の拠り所である「穴」と「世界」を天秤にかけられる選択を迫られます。
世界と齟齬を抱える陶芸家と計測者が、個の“ズレ”を武器に世界の綻びを繕うお話です。
文字数:396
セーヴルの砂
1
窯仕事を終えても手は止まらない。道具を拭くのをやめ、小さなガラス瓶の蓋を開けた。砂は息をひそめている。学生の頃、チベットの僧院の薄暗がりで受け取った色のついた砂。土と線香と凍った風の匂い。掌に落とすと細かく冷たい。
砂を白磁の器に詰める。胴には小さなガラス窓。じょうごを据え、ゆっくり注ぐ。粒は列を成して首を抜けるが、ときどきほどけ、色の点が奥で揺れた。私の砂時計だ。
あの夜の堂内がよみがえる。蝋燭の光が砂曼荼羅を撫で、マントラが時間を延ばしていた。年長の僧が金属の漏斗チャクプルの側面を金属の棒で擦る。きりきりという擦過音、細く落ちる色砂、立ち上がる文様。息を止めて見ていると、いつの間にか年老いた僧が私の前に立っていた。僧は小瓶を差し出し「ルン」と言った。五色の砂が入ったその瓶と、一語だけが胸に残った。
指先で土の流れを追いながら呼吸を整える。吸って二、止めて三、吐いて一――ろくろで覚えた呼吸。私の胸にはいつも二つの時がある。速い時が手を急がせ、遅い時が待ちをつくる。あいだに小さな「穴」が生まれ、そこへ指を入れて形を取り出す。「ルン」は風、息、気。私の「穴」はそれに近いのかもしれない。
色砂が混じりきらず揺れているのを見ると、私の「穴」が外へ移ったようで胸がざわつく。これが私の時間なら、可視化して誰かの手にも渡したい。古いストップウォッチを取り、砂時計を逆さにし、胴を軽く叩く。最初は3分ほどで止まり、砂を足す。次は5分。秒針と砂の音を心で重ね、詰まりを探って粒を抜き、また足した。
繰り返すうち、針と落下の間隔がぴたりと合う。最後の粒が落ちたとき、表示はちょうど10分。笑った。測ったのは機械だが、手の痕跡でもある。指の圧、砂についた皮脂、胴を抜けるリズム――それらが寄り合って、この10分になった。
棚に収める前に、砂の色をもう一度見る。青・黄・赤・白・黒が光を受けて層になる。あの曼荼羅が静かに眠っている。付箋に「チベット砂・10分」と日付を書き、底に貼った。
ろくろに戻る。土は黙っているが、触れれば応える。その日の手触りはその日だけ。棚の片隅で、白磁の砂時計は粒を落とし続けていた。
2
ギャラリーの白い光は工房より眩しい。曲線を平に見せ、影を細くする。棚のあいだで、チベットの砂を詰めた器だけが、自分の時を孕んでいるように見えた。
男が入ってきた。コートの襟を立て、革鞄を脇に。陳列の器を指で確かめ、間隔をそっと整える。そして砂時計を手に取った。私は黙って見ていた。ガラス窓の向こうの砂を、彼はじっと見つめている。表情は薄く、目だけが光っている。
小型のストップウォッチを出す。言葉はない。右手で砂時計を返し、左手でスタート。砂が首を抜ける音と、機械のカチリ。
粒は群れてはほどける。彼は砂だけを見ている。声をかけず、そばに立つ。私の方を見ることもしない。彼には「計る」だけが宿っていた。――この人。10分、このまま測るつもりだ。
砂が落ち切る。彼は息を吐き、ストップウォッチをしまってこちらを向いた。初めての声は穏やかだった。「これ、お幾らですか」
値を告げると、彼は札を揃え、硬貨を数え、「これでちょうどです」と言った。現実が戻る。包む前に、訊いた。
「それ、10分でしたか?」
彼は目を見ず、かすかに笑って頷く。「はい。あの砂なりの10分でした」
数値だけでなく、砂のありようを見ている人の答えだった。
包みながら、不思議な人だと思う。手渡すと、掌が触れて温度が行き交う。彼は砂時計を鞄にしまい、名刺を差し出した。日本語と英字が並ぶ。
「これを調べさせてください。必ず連絡します。領収書もお願いします」
ぎこちないが真摯だった。領収書の宛名に名刺どおり記す――「国際度量衡局」様。書くのに時間がかかった。
扉が閉まり、残ったのは静けさと、棚の空白だけ。手に包みの形がまだ残っている。付箋に記す――「砂時計。男性・測定後購入。連絡待ち」
夜、工房へ戻ると土の匂いが迎えてくれたが、胸の奥に小さな穴が一つ空いているのに気づいた。あの砂時計は、もうあの人のものだ。
3
自宅の工房の机に腰を下ろした。夜の釉薬の匂いがまだ指に残っている。電気窯の熱は遠のき、棚の一角だけが薄く光っている。あの砂時計はもうない。上野のギャラリーで、あの人に売った。残っているのは小さなガラス瓶の砂だけ。
スマートフォンがブルっと震えた。ギャラリー宛のメール通知。差出人は――<白石>
簡潔だった。測定結果の添付と、面会の願い。
<先日はありがとうございました。落下波形と時刻を添付します。詳細は直接お伝えします。ご都合をお知らせください>
添付を開く。緑の波線が小刻みに震え、ところどころ膨らみ、へこむ。隅には室温や湿度。私には、数字は模様だが、線の歪みは見て取れる。計測の静けさが画面越しに伝わり、胸が反応した。
チベットの黒陶器、展示室の冷たい光。切符代を貯めて触れた黒い器の驚き。寺院の暗がりのチャクプルのきしみ、緑・青・黄・赤・白の砂曼荼羅。年長の僧が差し出した小瓶は、その残り香だった。――あの砂を入れた器を計測する、あの人。
揺れる波形と、寺の蝋燭の橙が重なる。数値とあの夜が、どこかで触れ合っている気がした。
不安と期待が同時に広がる。会うのは怖い。けれど、どきどきする。客が来るだけだと自分に言い聞かせても、彼が何を伝えに来るのかが気になる。
文字を打った。丁寧に、でも構えすぎず。
<白石様
ご連絡ありがとうございます。添付、拝見しました。ご所見を直接伺えるのを楽しみにしております。金曜日でしたら午前十時から午後六時まで上野のギャラリーにおります。ご都合よろしければぜひお出でください。― 真央>
送信。胸に恐れと好奇が同時に立つ。返事までの時間が、針の音のように過ぎていく。
机の小瓶を取る。蓋を開けて指を差し込むと、砂が爪と指先の隙間に入り、冷たさが残る。もう砂時計のガラス窓越しにあの砂粒を見ることはできない。小瓶を掌で包み、窯の熱が消えるあいだ、金曜日の迎え方を想像した。よく知らない男との約束――不安はあるが、好奇心が勝っていた。
4
彼が来たとき、午後の光が傾いて器たちの輪郭が柔らく滲んだ。彼はコートの襟を直し、小さな紙包みを差し出す。「うさぎや」 どら焼きだ。思わず笑う。彼の所作は丁寧で、包みを渡す手はわずかに震えていた。
「お茶、いれましょう」 せかせかと動く。嬉しさに電気ケトルの蒸気を重ねる。急須の香りに、彼の顔がふっとほどけた。どら焼きを半分に切る。彼は一口で目を閉じた。目尻に満足の皺。餡はほのかな塩気、皮はしなやかだ。
最初は砂の話。彼は波形の特徴を示し、私は意味が分からないまま、画像の線に砂曼荼羅を見出す。言葉が足りないところは、湯気が覆ってくれた。
白石が顔を上げる。「よければ、少し飲みに。もう少し話を」 誘いは静かで強い。胸が一つ跳ねた。私はコートを羽織り、鍵を掴んだ。
湯島へ向かう道すがら、いつもの不注意を重ねる。角でつまずき、相手と同じ側に避けてぶつかり、ほどけた紐を踏みそうになる。白石はさっと支え、無言で肘を整える。その手つきが頼もしく、胸の奥があたたまる。
居酒屋。木と醤油の匂い。カウンターで彼がビールを頼み、小ぶりなグラスを受けとる。会話はまた砂。彼は測定の断片を細かく区切りながら説明し、私は箸置きをいじって落ち着かない指をなだめる。
箸置きが小皿に当たり、コップをはじき、ビールが小鉢に跳ねた。板前が笑って濡れ布巾を差し出す。慌てて拭き、謝る。白石は平然と袖を押さえ、「大丈夫ですか」とだけ。その声に、恥ずかしさが沈んだ。
酔いが回り、押し殺してきたことがこぼれた。
「よく落ち着きがないと言われます。注意が続かない、物をなくす、時間の感覚がずれる……子どもの頃から」 胸は妙に早鐘だった。白石は箸を止め、ただこちらを見る。それに救われ、続ける。
「ADHDかもしれません。でも診断に全部押し込まれたくなくて。仕事中だけ『時間の隙』が見つかる。土と話していると、まとまるんです」
白石は黙って頷き、それから正面を向く。
「私はASDです。社交は得意ではありません。言葉がずれることもあります。でも計測と手順には自信があります」
少し置いて付け加える。「ラベルは助けにも重荷にもなります。私は診断名を個性として扱っています。それはともかく『時間の隙』は興味深い。もっと真央さんのことを知りたいです」
私はその言葉に防御がほどけ、突飛な思いつきが口に出た。
「一緒にチベットへ行きませんか。もう一度、あの砂を見たい。チャクプルの音も、お坊さんの声も。私が感じたものを確かめたいんです」
白石は一拍置き、グラスを静かに置く。表情がいったん途切れ、すぐ戻る。
「チベットですか。面白い提案です。前向きに検討します」 事務的だが、真剣だった。
店を出る。夜風が頬を撫で、胸のざわつきは少し静まる。白石は次の連絡を示唆し、私は小瓶の砂を握るような気持ちで歩いた。距離は一気には詰まらない――けれど、歩幅は合い始めている。
5
ギャラリーの扉が押される音で手を止めた。午後の光が棚の縁を撫でるだけの空間に、白石が入ってくる。胸に小さな針が刺さる。長いコートをきちんと着て、片手に封筒。礼をして、口を開いた。
「真央さん、チベットに行きましょう」
飾りのない言葉がまっすぐ届く。息が詰まる。封筒には行程表と署名書類。声は淡々としているのに、端にいつもと違う緊張が乗っていた。
「局で正式に承認が出ました。費用は局負担。航空券、宿、現地調整は局名義で手配します。日程は真央さんに合わせます」
明確で事務的。封筒の『国際度量衡局』の文字を指でなぞると、胸のどこかにうら寂しさが落ちる。『手で触る旅』が『書類の旅』になっていく。
「つまり、仕事なんですね」
自分の声が少し硬い。公的になることを、どこかで期待していなかったのだ。
白石は封筒の端を整え、短く言った。
「仕事ですが、それだけではありません」
その一言で肩の力が抜ける。彼は候補日、滞在、受け入れ先の名を淡々と述べる。必要なことだけ話している。私がそこに『私的なもの』を混ぜているのも、多分、分かっていて、でも、触れてくれない。
外へ出ると、上野の夕暮れが湯島の輪郭を溶かしていた。白石は私の歩幅に合わせ、ぎりぎりの距離を保って歩く。私は看板やポスターに目を取られて何度かもつれ、そのたびに白石がさりげなく肘を取って整える。
居酒屋に着く頃には、安心と喪失が交互に来ていた。局が払うと言われると障壁は消えるのに、心は冷める。
カウンターで、白石は封筒からメモを出して見せた。過不足ない字で必要事項だけ。箸先で文字をなぞると、彼はいつもよりこちらを見ている。場を和らげようとした拙い冗談にも、笑う素振りをする。その笑みに「苦味」が混じっていた。
「子どもの頃から、非言語の合図や曖昧な指示を読むのが苦手でした。今は対処法はありますが、雑談や空気を読むのは得意ではありません。なので、伝えることは明確にします。無愛想に見えたら先に謝ります」
平坦で誠実な声。無駄のない動き、余計な言葉を足さない話し方、ぶつかりそうなときに距離を整える所作――全部がそこに繋がる。
私は小皿の縁をなぞり、言葉をこぼしていた。
「それでいいと思います。私は落ち着きがなくて、何を話しているか分からなくなったり、突然遠くへ行きたくなったり、周りの目が怖くなったりします。こちらこそごめんなさい」
白石は短く頷く。否定も肯定も足さない頷き。
店のテレビから時報。三つの短い音と一つの長い音。白石は腕時計で秒針を確かめる。その動きが彼の儀式に見えた。
「できるだけ早く出発したいです」 白石は封筒に手を置き、はっきり言う。「断片が積み重なる前に、現場で確認させてください」
言葉に焦りが混じっていた。
箸を置き、深く息を吸う。彼の明瞭さが真ん中を作る。さっきまで外へ飛んでいた注意が、今は一点に集まっていた。春先のチベットの輪郭が、そこでようやく形になった。
6
列車を降りた瞬間、東京の湿り気とは異なる大気が肌に触れた。薄く冷たい風、澄んだ空気が肺のすみまで入る。世界の輪郭が研がれていくようだった。白石は機材を無駄なく運び、私はポケットの小瓶を確かめた。
案内役の若いガイドが日本語で言う。「道が狭いので、歩きになります」 石畳が鳴り、軒先の線香が花の匂いを運ぶ。家並みが別世界の入口だった。
寺はすでに整っていた。砂曼荼羅の台に色砂の小皿が並び、チャクプルが出番を待つ。砂は宝石のように澄み、僧衣の衣擦れがさらさら響く。白石は計測器をセットし、いつものように「ため」のない動きで画面を立ち上げた。
ガイドが短く説明する。
「時輪は時間の輪。宇宙の巡りと人の内側が応じ合います。曼荼羅はその縮図。儀礼が終われば砂は壊されます。無常の真理です。それでも、外の時間とここで描かれる時間は、ときどき触れるのです」
僧がチャクプルに手を添え、胴を擦る。きりきりという金属音とともに、先端から砂が細い線を引く。色が幾重にも重なり、輪郭になる。膝の上で小瓶を転がすと、ガラスの冷たさと、目の前で流れる砂の温度差が掌に残った。
儀礼はゆっくり、確実に進む。擦過音に合わせ、白石の機器は微振動を拾う。最初はわずかにずれ、波形がふくらみ、へこむ。だが一瞬、音の伸びと画面の線がぴたりと重なった。
胸の奥で何かが「整列」した。チャクプルの音、機器のビープ音、僧のマントラが同じ拍を打つ。白石は画面に身を寄せ、数値を追った。音と数値と私の呼吸が、同じところに落ち始める。
年長の僧が来て、私の掌に触れた。鋭さが皺に染み、震えが走る。僧は掌を見つめ、低く一節。ガイドが訳す。
「掌は地図、砂は通路。時は輪だが縫い目がある。縫い目を触る者がいるなら、ただ見守る。時は、繕われることもある」
言葉は体内で往復し、意味の端が光る。白石が「位相が揃います」と言い、画面の二つの線が一つに重なった。
村人の小声が脇で交わる。外の音と、ここで起きた静かな一致が重なる。僧は砂曼荼羅を手で払い壊し「ルン」と言った。
言葉は、説明の余地を与えないまま胸に落ちた。白石の顔には計測者の厳しさが残り、かすかに柔らかさもにじんでいた。白石への淡い重さが、私の中で増していた。
帰り道、山の稜線が夕陽に縁取られて溶ける。ガイドは明日の集合を確かめ、白石は機材を点検。掌にはまだ僧の指の鋭さが残り、小瓶の砂はいつもより重い。あの一拍の共鳴が、内側に確かに宿っていた。
宿へ戻る道は、透明な夜気が肌を撫でた。屋根の端の灯りが道の奥行きを浅く切り取る。土間に低い卓、煤けた梁に鍋――その素朴さに体がほどける。一方で、私は小瓶を何度も確かめ、僧の手の鋭さの名残を探している。
宿の食堂の席に着く。湯気とスパイスが一気に立ちのぼる。白く濁ったポ・チャを含むと、塩と乳の丸みが喉を落ち、体が静まる。ティンモ、モモ、トゥクパ――どれも手に取りやすく、味がまっすぐだ。
トゥクパを取り分けたお椀を白石の前に置いた。白石はナプキンを正し、私を見た。
「真央さん、来てほしい。セーヴルに」
フランスの磁器の街、セーヴル。松濤美術館で見た薔薇色の記憶が一気に熱を帯びた。
「フランスの……セーヴルに?」
白石は頷く。
「セーヴルにあるブルトゥイユ離宮に本部があります。ここでの『位相の揺らぎ』と、セーヴルで管理する『協定世界時の揺らぎ』を突き合わせたい。真央さんの砂時計と、さきほどの儀礼の感覚を並べれば、定量データに意味が出るかもしれない。来てくれますか」
視線は不器用だが誠実。私の中で陶器の白がぎゅっと膨らむ。セーヴルはずっと触りたかった。
けれど、私にだって現実もある。展示会、窯出し。都合を考えているのに、白石がさらに言葉を重ねてくる。
「儀礼中の短い同調、真央さんの反応。それをセーヴルの基準と比較したい。費用は局で手配します」
事務的な言葉の向こうに切迫した顔が見える。私はモモでひと呼吸置き、正直に伝えた。
「行きたい気持ちが、どうしようもないんです。セーヴルの陶器に触りたいんです」
白石は一瞬だけ顔を緩め、すぐ真面目に戻した。
「真央さんの感覚が必要です。科学だけでは掬えないものを無意識に感知している。僧の儀礼と砂の振る舞いを繋げば、基準安定化の手がかりになります」
やりとりは不器用なまま。私は湯気に紛れて別の皿へ手を伸ばし、店先を走る子に気を取られ、足をバタつかせる。白石は全部を直そうとはせず、ときおり私を支える。配慮はぎこちないが確かだ。
彼は好みがはっきりしていて、モモには顔をしかめ、トゥクパをすすって「これは良い食べ物です」と評した。そして、すぐ段取りに戻る。白石はチケット、日取り、滞在を手短に述べ、私は窯とギャラリーの予定を勘定する。二週間か、一か月か――。
ふいに宿の電気が落ち、ろうそくが灯る。数十秒で明かりは戻り、誰もがひと息つく。白石が、私を見る。その張りつめ方は、怖いぐらいだった。
「断片が積み重なる前に、現場で確認させてください。なるべく早く」
「考えます。真剣に」
私が反射的に答えると、ようやく表情を和らげた。食事の終わり、私がティンモの端を割って差し出すと、白石は匂いを確かめてから口に入れ、「おいしい」と呟く。その奥に小さな喜びがのぞいた。湯気の中で、不器用な相互補完が静かに形になる。
外では山風が吹き、窓が小さく鳴った。小瓶を握ると、内側から何かが澄んでいく。セーヴルという名が、陶器の夢と計測の冷たさを同時に連れてくる。――あの僧の指先の気配が、もう私をそちらへ押していた。
7
展示室の光は、器の薄い殻を透かしていた。白い壁に沿って並ぶ皿や器は、どれも無言で自分の時間を抱えているように見える。釉薬の下にころんだ微かな気泡を見つけると、胸の内側にぽつんと共鳴が生まれた。セーヴルの国立陶磁器博物館。長い年月の燻しをまとった器たちの居場所。私は恍惚としていた。
白石は、流暢なフランス語で学芸員に礼を交わしながら私を案内してくれた。彼の言葉が、私が夢見てきた陶磁器の光景に現実の輪郭を与える。私は一つの浅鉢の前に立ち止まり、筆の運びの残した痕を目でなぞってみた。釉の薄さ、石粉のかすかな声のようなものが、チベットの砂と奇妙に繋がる感覚がした。展示室を出ると、庭の向こうに控えめに立つ仏塔――パゴダが見えた。
パゴダの扉を押すと、線香のやさしい匂いが立ち上がった。あのチベットの寺で嗅いだ匂いと地続きで、胸の奥がふるえた。中には僧が一人、佇んでいた。チベットで出会ったあの年長の僧だった。彼は私を見るとにっこりと笑い、手に抱えた粗い封筒を差し出した。封筒の端には、香の灰らしきものがうっすら付いていた。白石がその封を丁寧に破ると、中には便箋があり、チベット文字で書かれた言葉と赤い曼荼羅の捺印があった。
僧はそれを一瞥してから、ゆっくりと流暢なフランス語で語り始めた。驚いた。僧がそのままフランス語で、便箋の内容を要約して読み上げていったのだ。声は低く穏やかで、言葉は明瞭だった。白石はそれを聞き取り、すぐ日本語にしてくれる。
「僧院は、儀礼の最中に短い『同調』を観測しました。あなたの掌の印が示す可能性を、セーヴルで確認させていただきたい」
僧の表情には説明でも催促でもない、静かな確信があった。
石畳の向こうから規則的な足音が近づいてくる。白石は背筋を伸ばし、「局長です」と言った。堅い仕立てのコートに、計測を職務とする者の緻密さが滲む。彼は一礼してから、柔らかなフランス語で僧を労った。そして、私たちを隣のこぢんまりとした食堂へ案内した。木のテーブルにシンプルな皿が並んだ、落ち着いた空間だった。局長は席に着くと、私に微笑んだ。
食事が運ばれるまでの短いあいだ、自分の手が落ち着かないのを自覚する。パンの角を何度も指でつまみ、布ナプキンを引っ張り、視線が窓の外の木々へ飛ぶ。私の癖は、公的な場でもすぐ顔を出す。白石はそれを見逃さず、無言で私の肘にそっと手を添えた。
局長は私たちのやりとりを微笑んで見てから、食事を進めつつ要点を切り出した。声は白石と同じく事務的だが、奥に熱があった。白石が一語ずつ慎重に訳す。
「ここ数か月、我々は小さな時間の不整合の報告を受けています。各地のログで、時刻がわずかにずれる断片的な事象が観測されているのです。今は局所的ですが、条件が揃えば世界中のインフラの整合性に影響を及ぼす可能性があります」
局長の顔には冷静さがあるが、指先のわずかな動きが緊迫を隠しきれていない。
「僧院の手紙にある『同調』と、我々の観測は奇妙に重なっています。偶然とは言い切れない現象です。原因の特定が必要です」
局長はまっすぐ私を見る。研究者としての期待と、時間を預かる者としての切実さが混ざっていた。
「我々の計測と真央さんの体感を並べて観察することで、見落としている文脈を補えるかもしれません。ぜひ協力を」
私はナプキンをぎゅっと掴んでから白石を見た。白石は私の目を見返し、机の端で封筒を静かに握りしめていた。局長はしばらく私たちを慈しむように見守り、ふっと力を抜いた笑みを浮かべた。その視線は、ただの上司の観察を越え、私たち二人を愛おしそうに見ているようでもあった。だがその奥には、任務の硬さが潜んでいた。
パゴダを出るとき、僧が私の掌にそっと手をかざし、祝福とも確認ともつかない動きをした。「ルン」が皺の奥まで降りてきて、曼荼羅の砂が私の胸に落ちてくるような気がした。私はそのまま掌を胸の前で合わせ、見えない砂がこぼれないように受け止めた。
8
局長室は思ったより狭く、外の庭だけが光りとともにゆっくり動いていた。大きな机には計器が並び、壁には世界各地の時計がかかっていた。どの針も「正しくあれ」と言われているようだった。局長はその一つを指で押さえた。
「ここで扱っているのは協定世界時、UTCです。世界中の原子時計を集めた国際原子時、TAIを基に、地球の自転に合わせて閏秒を挿入します。天体と原子のあいだを、最後は人が縫い合わせています」
局長がグラフをめくると、細い山が続く線が現れた。「各地で観測された微細なずれです。今は点ですが、面になれば金融や通信が破綻します。やがて世界はほどけてしまいます」
窓際にいた僧が光の中で手を合わせ、低く言った。白石がすぐに訳す。
「時間は輪で、ときに裂けます。外からも内からも裂ける。わたしたちはその裂け目を繕ってきました」
白石が小さく息を吐く。「僧の言う『輪』は、宇宙の時間と人の時間が重なる、ごく狭い場所のことです。そこが裂けてしまわないよう、科学と神秘の両方で扱わないといけません」
私は掌を見た。チベットで触れられた線がまだ残っている気がする。白石は言う。
「真央さんは土をさわるとき『時間の隙』をつまむと言っていた。もしその感覚でこの揺らぎを一つの位相に留められるなら」
思わず出た。「どうして私なんですか」
「世界の時間を見張る『守り人』がいます。誰でもなれる役じゃない。私たちは候補を世界中から探していて、チベットであなたが『見つかった』。今の守り人の力が落ちていて、引き継ぎが必要なんです」
――私が、見つけられた?
「分かりやすく言えば、水晶時計の水晶です。微細な揺らぎを同じ振動に留める。真央さんはそれを身体でやる」
私はこらえきれずに言った。「時間って……そこまで守らなきゃいけないものなんですか」
僧が静かに頷く。「本当は、人はそれぞれの速さで生きていいのです。でも今の世界は、同じ時間の上でしか手を伸ばせなくなった」
局長が続ける。「時間だけじゃない。重さも長さも言語も、全部ばらばらなものを一本に束ねて、ようやく世界は回っています。あなたが感じた『隙』はその束のほころびです」
訳を終えた白石がぽつりと言った。「僕も、ときどき分からなくなります。でも、世界をばらばらにしたくはないんです、真央さん」
しばらく部屋はその余韻で静かになった。壁の時計は変わらず時を刻む。けれど正確さの裏で、何かがかすかに騒いでいるのが分かった。逃げたかった。けれど、必死な顔でこちらを見る白石からは、逃げられなかった。
9
実験室の空気は、局長室よりも冷たかった。白い机の上に並んだモニターの青白い光が、私の掌を別の肌合いに見せる。白石は機器の前で無駄なく手を動かし、僧は角ばった手を胸の前で組み直した。私は椅子に座り、目の前に置かれた耳栓と手袋のような装置を見つめた。これは「試験」なのだ。
「まず、顕微鏡写真を撮ります」
白石の声はいつもどおり淡々としていたが、ほんの少し硬かった。彼は小瓶からピンセットで砂粒を取り出し、スライドガラスに並べる。顕微鏡を覗くと、粒は肉眼で見るそれと違い、縁が鋭く、色の層が規則的な線を描いている。五色の砂の微粒子が、チャクプルの振動を覚えているかのように並んでいた。スクリーンに投影された一枚目の写真は、波状の微細構造を拡大して見せ、私の胸のざわつきと呼応する。
「単なる色の混合ではありません。微小な層と配向があります。あの儀礼の振る舞いが、粒子の並びに痕跡を残したと見られます」
僧は写真に近づき、目に見えない線を指でなぞるようにしてから、マントラを唱えた。冷気の中でその音が震え、スクリーンの画像さえ揺れたように見えた。
「真央さん、イヤホンを耳に。グローブもお願いします」
白石はモニターを切り替える。ノイズをかぶった線の中に、僧がチャクプルを擦ったときの「瞬間」が、薄い光の帯で刻まれている。
「フィルタリングして、位相抽出をかけます」
白石はその帯にカーソルを合わせ、私を見る。
「呼吸をこちらに合わせてください。吸って、止めて、吐く――を三回。僕の合図で。急がなくていいです」
クリック音が一定に鳴る。私は最初、息を合わせきれずに拍を飛び越えた。白石がそっと肩に手を置き、もう一度同じテンポを示す。僧も向かいで低く息を吐き、私の速い拍子を手前に引き戻す。機器は胸の膨らみを拾い、スクリーンに呼吸の曲線が描かれる。線はぐらつきながらも、白石が示す位相の窓にゆっくり寄っていった。
僧が私の掌を胸の上に当てる。白石が心拍センサーを取り付けると、スクリーン上で私の鼓動がグラフになる。最初はばらばらだった鼓動も、僧のマントラに寄せられて整ってくる。
「見てください」
白石がグラフを拡大する。呼吸波形、心拍のピーク、チャクプルの振動――三つの線が一瞬だけ、きれいに一つに重なった。スクリーン上で色づいた帯が点灯し、その間だけノイズが消え、一本の線だけが残る。僧は目を閉じて手を合わせ、白石は小声で数値を読み上げた。
そのとき、机の端で「コ、コ、コ」と一定の間隔で鳴る音が耳に入った。透明なアクリル枠に収められた小さな振り子時計の模型が置いてある。振り子が左右に振れるたび、二股のアンクルがギザギザの歯車を、止めては離し、止めては離している。流れ続ける力を、一拍ずつに切り分けているのが丸見えだった。私は思わず手を伸ばした。白石がすぐに言う。
「それがエスケープメント、脱進機です。時計が暴走しないように、エネルギーを『刻み』に変える部分。今、私たちがやっているのは、その世界版です」
振り子の揺れと、私の胸の波形の山が、同じリズムをまねし合っているように見えた。私のほうがあちらに寄っていっているのか、あちらが私を基準にしようとしているのか、分からない。
ちょうどそのとき、スクリーンの端で通知が点滅した。白石が画面を切り替える。テロップが流れる。
――国内主要都市で時刻不一致に伴う短時間の停電。負荷調整系に一瞬の記録齟齬。規模は限定的、原因調査中。
訳しながら白石の指が震えていた。
「……位相の裂けは、もう外に出ています」
部屋の空気が一段冷える。実験は止まらない。白石は記録を続け、僧は所作を繰り返す。チャクプルが再び擦られ、私はまた息を合わせる。白石は顔を伏せて数値を書きとめ、僧は時折、私の掌の線をなぞった。私の中の二つの時間が、この部屋で一つに重なっていく。
白石はカメラで私の胸元、掌の皺、そして顕微鏡像を同時に撮影した。違うスケールの時間が、同じフレームの中に積み重なる。そこへ局長が入り、画面を覗き込んでうなずいた。
「適合性は示されました。真央さんの本来の時間に、協定世界時が同期しています。数値がそう語っています」
試験は成功だったのだろう。けれど、その言い方が、胸の奥を冷やした。私は時計の中の一つの部品として合格したのだ。
エスケープメント――
そんなの、ぜんぜん嬉しくなかった。
10
離宮を出て、庭の端を回る細い道を抜けると、街の灯りがぽつりぽつりと見えて、パリの喧噪とは違う、地方の夜の匂いがした。白石が小さなワインバーを指さした。扉を押すと温かい空気が迎え、木のカウンターに腰を下ろすと、急に肩の力が抜けた。
カウンター越しに並ぶワインボトルの背が揺れ、グラスの縁が白く光る。注文したのは軽い食事と、温めた赤ワインだった。私たちは小皿をつまみながら、はじめは馬鹿話をした。白石は滞りなくフランス語でウエイターとやり取りし、私はその横顔を眺めながら、彼の無遠慮な物言いに笑いをこらえた。窯の火や砂の色の話を少し、展示のことを少し。彼はときどき私の手元の小瓶をちらりと見ては、ポケットのメモを軽くなぞる。いつものように仕事と感情が交差する瞬間だ。
しばらくして、カウンターの後ろのテーブルで小さな騒ぎが起きた。若いカップルの男が決済端末を何度も押している。表示がちらちらして、決済が通らないらしい。ウエイターは落ち着いて繰り返すが、端末の画面にエラー・メッセージが出ては消える。白石がふっと腕時計に視線を落とした。指先がわずかに震えた。
「時が裂けている……」
小声でそう言ってから、私にだけ聞こえるように続けた。
「端末のトランザクションタイムと、銀行サーバーの時刻がずれています」
苛立った男が声を上げると、白石は黙って財布から紙幣を出し、男に渡した。無駄のない行為だった。男は赤面してメルシーと繰り返す。
その直後、外で大きな音がしてガラスが震えた。通りに出ると、二台の車が交差点で折り重なるようにぶつかっていた。信号のライトが消えている。運転手同士が言い争い、通行人がスマートフォンを掲げる。遠くで救急車のサイレン。渋滞はすぐにふくらんだ。白石は道路の状態を冷静に見て、私の手を軽く引き寄せた。
「制御系が局所的に狂っているようです。信号のコントローラはUTCに同期したGPSで動かしているので、基準のずれが入ると受理できません」
説明は簡潔だった。私は胸が締め付けられるのを感じた。チャクプルのきりきりという音や、僧のマントラが、遠くの記憶として胸の奥で重なってくる。
店に戻ると、スタッフがテレビをつけた。テロップが流れる。
=都市部で時刻不一致に伴う通信ログの齟齬、銀行業務に遅延=
=鉄道の時刻表が一時的に停止、小規模な混乱=
白石が訳す。ワインの甘さが舌の上で苦くなった。客たちの顔も変わる。女性が電話で何かを告げ、誰かが「病院のモニターが狂っているらしい」と言っているらしい。フランス語の不安な響きだけが店の中に充満していき、私は理解できない言葉に溺れて大きな声を出していた。
白石がすぐに手を引き、抱きとめる。
「真央さん……大丈夫。大丈夫です」
震えていた。世界が怖かった。白石は抱きしめたまま、繰り返す。
「ぼくが一緒にいます。呼吸を戻してください。冷静に」
何度も頷いた。
外では救急車とパトカーがすれ違い、別の客が会計端末の前でパニックになっている。並んでいた人が押し合い、杖の老人が波に押されそうになる。小さな街角のバーの秩序が、薄い紙のようにたわんでいた。
白石が、私の手を強く握った。
「行こう」
それだけ言った。さっきまで「仕事だから私に近づいたの?」と訊くつもりでいた。けれど、サイレンが重なっているこの夜に、その問いは覆い隠された。実験室で『部品として合格した』と言われたときの冷たさはまだ残っているし、白石に惹かれていることも、もうごまかせない。世界をばらばらにしたくない気持ちもある。どれも捨てられないままだった。私は息を吸って、その全部をいったん夜の空気に吐き出すしかなかった。
11
書斎の戸を押すと、木と紙の匂いがふっと立ち上がった。机の上、棚の隙間、引き出しの縁――置かれているものすべてが時間を吸い込んで、埃の層になっていた。守り人アルマン・サーデギーは、その埃よりもさらに古い時間を身にまとってベッドに横たわっていた。やせた体に管が何本も差し込まれ、蝋燭の火は今にも消えそうに細い。
ベッド脇の小机には二つの砂時計が並んでいる。一つは色あせた陶の器に入った古いもの。ペルシア文字が書かれている。ペルシア語でنگهبان(ネガーバーン)。『守り人』という意味だという。もう一つは、私が作った砂時計。ガラス窓の奥で曼荼羅が見つめている。
部屋の端にはチベットの僧が座り、膝の上に鈍った金色のチャクプルを置いていた。もう一人、視線を引く大男がいた。白石に訊くと「アルマンさんと同調できる人です。オーストラリアから」と言う。アボリジニの演奏家だそうだ。長い木の管――ユーカリのディジュリドゥが机の端に横たわっている。長年、音で時間を測ってきた人の皺が、彼の顔に刻まれていた。
「マオ」
アルマンさんが、かすれた声で呼んだ。私はベッドに近づき、「真央です」と答える。大きくて筆だこのある掌が私の頬に触れ、「マオ」ともう一度言った。白石の説明では、彼は若い頃イランのイスファーファンで細密画を描いていたという。線をぶれさせないで時間を引き伸ばす、そういう手の人だ。
白石は手際よく機器を並べる。モニターには、アルマンさんと私の心拍と呼吸、ディジュリドゥの低周波、マントラの響き、それぞれの波形が同時に並んだ。僧がマントラを唱え、アボリジニの大男が息を送り続ける。書斎の空気が震えながら、二つの音の線が一つの太い帯になっていく。
アルマンさんが、私の掌を引き寄せた。彼の砂時計と、私の砂時計を、重ねた手のそばへ寄せていく。マントラとディジュリドゥが溶け合った音が、彼と私のあいだの境目をゆっくり薄くする。白石が見つめる画面の中央に、色のついた帯がぽっと浮いた。小さな位相の点が一つ、二つと灯る。
「呼吸を合わせて」
白石の声は、珍しく柔らかい。私は目を閉じて、アルマンさんの呼吸の深さに自分の呼吸を落としていく。ディジュリドゥの鳴りは地面の奥から来るように重く、マントラはそこへ呪文の糸を垂らす。掌の裏に、チベットの砂の冷たさがふっと戻る。あの寺で最初に瓶を渡された夜と、今ここの音が、きれいに折り畳まれたのがわかった。
私はアルマンさんの目を見た。逃げ道は、もうどこにも残っていなかった。私はアルマンさんに見つめられながら、砂時計を逆さにした。
最初の粒が落ちる。細いガラスの中をひと粒が通るだけなのに、胸の奥がきしむように締まる。体の細部が、世界の位相に呼応して動くのが分かる。マントラは振幅を増し、ディジュリドゥは羽根を広げ、アルマンさんの呼吸がさらに遅く、深くなり、白石の画面の線が一斉に太くなった。すべての波が一致した瞬間、部屋の張りつめたものが一拍だけゆるんだ。
「来ている」
白石が囁く。モニターの数値が一瞬で安定し、彼の端末で赤く点っていた表示が、次々と緑に変わっていくのが見えた。外で崩れかけていた秩序が、数字の上で戻り始めている。いま私の二つの時間は、一つの時間にきれいに揃っていた。アルマンさんの蝋燭の火が、私のほうへ移ってくるのが分かった。
アルマンさんの顔には、安堵と、喜びがあった。彼は拙い日本語で「アリガトウ」と言い、まぶたを閉じたまま動かなくなった。
アボリジニの大男はディジュリドゥを唇から離し、長く息を吐いてから、アルマンさんの頭をやさしく撫でた。私のほうを見たその目には、何十年も「合わせる」ためだけに仕事をしてきた人の疲れと、哀しみがあった。彼は私に深々と会釈し、そのままアルマンさんを抱きしめた。僧はベッドに向かい、アルマンさんにマントラを唱えた。
外の世界は息を整えた。通信は戻り、鉄道の時刻表は並び直し、金融の記録は再び列を成していく。白石の画面に積み上がっていた警告がゆっくり消えていく。白石が、そっと私の手に触れて言った。
「真央さん、完了です」
私は頷いた。けれど頷きながら、これが「引き継ぎ」という名の、終わりであり始まりなのだと、嫌というほど分かっていた。
12
朝の光は柔らかく、カーテンの隙間から差し込む白が部屋のものを淡く浮かび上がらせている。ニュースのヘッドラインは穏やかだ。駅の電光掲示は整然と列車の到着時刻を表示し、街の時計はいつものテンポを取り戻している。外の世界は整った。内側も、たしかに整った。ただ、土と話すためにあった小さな穴だけが、きれいに塞がれていた。
棚の中央にある砂時計を手に取る。ガラス窓に青・黄・赤・白・黒の五色が密やかに縞を作る。あのとき窯の火のそばで作ったものだ。上野のギャラリーに並べていたとき、白石がじっと見つめ、ストップウォッチで時間を測り、さらうように買っていった。そしてまたここにある。チベットの僧から分けてもらった砂が、いまはこの砂時計の中で世界の指標になっている。
あの夜、私はアルマンさんから「守り人」を引き継いだ。私の時間が一つになった瞬間、世界は救われた。けれど同時に、長いあいだ私のそばにいてくれた「ずれの居場所」――土と話すためのあの小さな穴――は閉じた。ろくろの前で手を動かせば、指先の感触はこれまでどおりなのに、土の声だけがしない。作品はできる。釉は光る。だが、そこにあった「ルン」はもうない。
日々は規則正しく回る。茶碗を洗い、釉薬を攪拌し、窯を覗く。白石は朝食を用意し、新聞をきちんと畳み、メールを一通ずつ片付ける。彼の動きは相変わらず正確だ。けれど、あの夜以降、私に向く視線の温度はほんの少しだけ上がった。不器用なやさしさは変わらない。笑いの間でふっと見せる、あのぎこちなさが私は好きだ。
夕暮れ、窓辺の椅子に座り、砂時計をそっと置く。耳を寄せると、粒の落ちる小さな音がする。粒は一つ、また一つ落ちる。そのテンポが外の街の時計とぴたりと合っているのを感じると、世界の針が整えられたことの重みが胸に満ちる。だが同時に、手の中に残った穴の痕跡がちくりと疼く。喪失は静かで、日常の隙間に住む。
ある晩、皿を洗いながら、どうしても確かめたくなった。問いというより、いまの暮らしの「時刻合わせ」だった。白石がカウンターでカップを拭き終え、私の方を向く。私は泡のついた手を止め、真っ直ぐに言う。
「ねえ、あなたがここにいるのは、お仕事?」
白石は一瞬だけ目を伏せ、ゆっくりと上げた。正直さと、ほんの少しの照れが混じった顔で言う。
「仕事です。でも、それだけじゃありません」
それだけだった。白石は私を見張りながら愛している。私は小さく笑う。私の『ルン』は消えてしまった。いまはそれでよい。
まだ、いまのところは。
(了)
文字数:15967