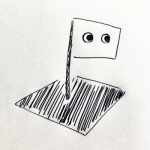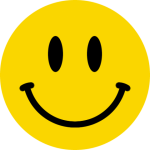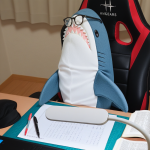梗 概
What Mari Didn’t Know
2075年、万博開催を控えた渋谷。天蓋に覆われ、特殊な光で全ての色が人為的に排除された都市。
主人公マリは、このモノクロの街で生まれ育った女子高生である。彼女は全時代・全文明の芸術を学び、絵画・音楽・詩・建築すべてを“言語的”に理解しつつある。彼女の脳はAI接続型BMI〈Generative Engine〉と直結し、思考を通じてこの世界の美を形にできる。AI芸術の申し子である。
ただし〈色〉という感覚情報だけは一度も経験していない。
AIの生成技術によって、あらゆる芸術を自動生成できる時代を迎え、人類は尊厳を失い、拠り所として〈美〉という概念を問い直そうとした。
「美とは、知識体系として還元可能なものか、生の中で創発されるものか」
渋谷はその問いを確かめるための箱庭で、マリはその重要な被験者だった。
色のない世界で美を理解した人間が、初めて「色」を見るとき
- その理解は更新されるのか
- 彼女の創作に色は現れるのか
- もし現れるなら、それは「美」が主観的で生成的である証拠となるのか
それらの答えを、政府の指導者たちは求めていた。
彼女は自身が実験の被検体であることに気づき、街からの逃走を試みる。その過程で、覆面グラフィティアーティスト〈Glitch〉と出会う。彼は地下に広がる色のある世界、旧渋谷〈シブチカ〉出身で、違法な落書きを通じて世界に主張する。彼はマリにグラフィティの流儀を教える。彼は語る。
「そもそも芸術を美で語るのが誤っている。色なんていらない。もはや作品さえな。それは生き様だ」
彼は生まれつき色を知覚できなかった。それ故に自身の審美眼に劣等感を感じていた。しかしこの街ならば色を超えた美を見いだせると信じていた。
「俺の描く絵には何かが欠けてる気がする。この街なら確かめられるかもしれない。俺の美と世界の美が同じはずだってことを」
そういうGlitchにマリはこの世界の美を見せる。彼は微笑み、美について何かを理解すると同時に監視ドローンの狙撃で倒れる。その身体から流れ出た鮮血。しかし、その生の証さえも白と黒に変換される。マリはショックで倒れる。
マリは拘束され、実験は最終段階へ。グラフィティとネオンに満ちた混沌の街であるシブチカを訪れ、知識としてすべてを理解している彼女は、初めて“色を見る体験”をする。彼女はそこで答えを得る。
万博開幕の日、マリは実験成果を発表するため壇上に立つことになる。壇上だけ色が解放される。彼女は〈Generative Engine〉を起動し世界に答えを示す。生成されたのは一缶のペンキ。彼女がそれを宙に投げると、缶は爆発し、「赤」が飛び散る。続けて至る所で無数のペンキ缶が爆発し、街は一瞬で極彩色に染まる。彼女は取り押さえられる。悲鳴と歓声が交錯する中、マリは頬を伝う赤を見つめる。かつてGlitchが見せた本当の血の色を知る。マリは問を超えた答えを証明しようと試みた。
文字数:1197
内容に関するアピール
かつて芸術は、技術を持つ者だけに許された営みであり、自己の存在意義や誇りと結びついていました。しかし、進化の著しい生成AIはその制約を解放し、やがて誰もが想像をそのまま形にできる時代が訪れるはずです。そこでは創作過程は消え、創作という活動と生み出される作品が殆ど同義になります。
では、過程を失った芸術に意味はあるのか。自己表現の要素が薄れ、自己の関与を欠いた作品を前に人はこう思うでしょう。「自分が作る必要ないじゃん」と。その感覚はやがて人生という作品にも波及します。「自分が生きる必要ないじゃん」と。利便性の代償に、人間はより本質的で重要なものを失ったのかもしれません。
それでもなお、意味を探し続ける人間の物語が描けたらと思っています。
梗概が設定と主張の構造的な部分に寄っているので、実作では物語として面白くなるように、キャラクターとストーリーをきっちり膨らます部分に注力したいです。
文字数:393
What Mari Didn’t Know
「私のこの服の色、オリーブっぽい?それとも茶色っぽいかしら?」
白衣の女性はその内に着た自分の服をつまんで私に向かって訊ねる。
「それは多分カーキ色って呼んだほう良いんじゃないかな」
「そのあたりは区別が難しいわね。スカートの方は似合ってるかしら」
立ち上がった彼女の履いている少しシワの入ったスカートを見る。その明暗のテクスチャからジーンズ地ということが分かる。
「もう少し色味の薄いライトブルーのジーンズ地の方が合うんじゃない」
彼女は、ほう、というような顔をしている。
「今度紅葉を見に行くためにお出かけをするんだけど、場所によって赤いのと黄色い葉があるけど、どっちの方が好きかしら」
「黄色いほうがいいわね。赤の燃え立つ感じは魅力だけど、空を見上げた時に青とのコントラストが一番際立って綺麗なのは黄色だわ」
白衣の女性は私の言葉を聞いて、手元に持っているタブレットに何かを入力し、私の方を向いた。
「問題なしね。全く持って違和感無し」
毎月毎月、何年も続けられているこのテストに今更の達成感は無かった。
「当然よ。ここまでやってきてまだ続けてるなんておかしな話よ。今更ボロなんて出さないわ」
「私たちの組織にとっては大事なことよ。本当に長かったわね。とうとうあなたは”色”を知ることになる」
「もちろん約束は守られるのよね」
私は訝しむように訊ねる。白衣の女性は笑った。
「私たちは別に悪人じゃないのよ。この実験は褒められたものではないかもしれないけど、どんどんと息苦しくなっていく人類の未来のためよ。それさえ達成ができれば良いの」
それは偽善的にも聞こえる答えだが、10年以上にも渡って彼らの実験に協力して来てわざわざ本気で疑う気もない。
「あと少しね、どんな結果になるかが待ちきれないわ。マリ」
その言葉に自分にのしかかっているその期待を少し怖く思っていた。
「ねえ、どうする? もし私が色を見られるようになっても何も学ばなかったら」
白衣の女性は、見せかけだけ、うーんといいながら、
「その時はその時ね。物理主義的に出来上がった世界に生きる価値もないから」
と笑う。その応答にやはり私は彼女たちはどこかが狂っていると思う。
「逆にマリはどんな感情なの?私たちにとっては、色は当たり前すぎるもので色がない世界は想像がつかないもの」
当然答えなど決まっている。
「クソ喰らえだよ」
いつものテストを終えた私は、組織のある雑居ビルを抜ける。有象無象の雑居ビルの一室に押し込められた本部。この佇まいが既にこの実験に対する人々の関心の低さを示していると思う。そのことに彼らは気がついているのだろうか。主観という不確かな物にすがりつこうとする彼らが惨めにさえ思える。しかし、その惨めさの中心にいる存在こそが私なのだ。
渋谷駅の中心に向かって歩き始める。街の喧騒はどこか他人事のように思える。
空と雲の境目は、その言葉の違い以上に曖昧だ。豊かに織られた言葉の数以上に差はない。すっきりとした空気の中、見慣れた道玄坂のゆったりとした勾配を歩き続ける。朝の渋谷は嫌いじゃない。昼間は鬱陶しいほどの人であふれかえるこの街にも、安らぎの時間があるようだ。
わたしは皆が集まるこの渋谷という街の本当の姿を知らない。2000年代から観光客で溢れかえり、様々な言語が街を飛び交い、雑多ながらに活気があるこの街の持つエネルギーを、私は十分に感じられずにいる。しかし、わたしはこの街が好きだ。人間臭さがある。
八幡通りの先に校門が見える。いつも通りの7時半に通っている高校に到着する。下駄箱に靴を差し入れ、私は西校舎三階の美術室へ向かう。ドアに手をかざすと認証が走り、「おはようございます、白汐マリさん」という声がロック端末から走り、カチッと音を立ててドアが開く。
足を踏み入れると天井の電気が自動で点灯する。美術室には整然と40個の”GIDE”が並べられれている。いつも通りの一番乗りである。朝の早起きは誰でも出来る。皆は自分を「天才」と褒めそやすが、そういうところなんだけどな、と思う。
定位置となっている教室右奥の窓際の座席に座る。ふう、という声がつい吹き出る。しばらく誰もいない空っぽの教室をぼーっと眺める。しばらくしていると、再びドアからカチッと音がなり、長身の女性が入ってくる。
「おはよう、アヤ」
私が声をかけると、一拍遅れて、おはよう、とアヤが小さく返す。アヤは私と対角線の端にあるGIDEの前に座った。思えば彼女もいつも同じ席に座っている。
さあ、始めるかという気持ちになる。
GIDEのコンソールから電源を起動し、筐体がウーッという音が鳴り始める。私はゴーグル型のBMIを装着する。 およそ1メートル四方のGIDEの内部には「Generative Engine」という文字が浮かび上がり、ドラフトモードに入り、私はデッサンを始める。
GIDE は汎用性統合開発環境(General-purpose Integrated Development Environment)のことであり、日本人はガイドと読みたくなるが、正式な発音はジードと言う。その箱型の見た目からBOXと呼ぶ人もいる。
2020年代に発生した生成AIブームから、数ある創作ツールはプロンプトエンジニアリング性能の優劣による競争に突入した。生成AIに慣れ過ぎた人類は、自分の想像通りに書けないと文句を言って鉛筆さえ投げ出した。如何に自分のイメージをそのまま形にしてくれるか、ということが、開発やデザイン、芸術の領域における至上命題となっていった。
私は今持っている創作イメージを思考プロンプトとして送る。言語よりも更に抽象度が高いイメージをそのままに信号パターンとしてBMIを経由して、生成ソフトウェアである “Generative Engine” に伝える。それが実際にGIDEの内部でイメージ化される。
まだドラフトモードなので、ゴーグル越しにしか見えない”ホロ状態”である。
「違う、こうじゃない」
つい苛立ちが言葉として口からこぼれ落ちる。前のアヤからさっと後ろを突き刺すような視線を感じた。邪魔すると悪いな。ホロだと見えてないからな。
時間と共に変化する2次元絵画のアニメーションを作ろうとしているが、どうにもイメージ通りにならない。これでは、万博のシンボルアートに抜擢されるのは難しいだろう。
私はイメージに対する修正プロンプトを思考する。何がどう違うのか、それを伝える。それに即して、リアルタイムでホロが書き換わっていく。GIDEと繋がっている時、イメージは殆どのタイムラグも無く、そのままに可視化される。
かつて「想像」という言葉が持っていた意味は拡張され、既に現実と想像の境は曖昧になっていると言える。私はGIDEを使っている時、自分の脳を眼の前で覗いているというような感覚になる。それは自己を外から眺めるというような体験である。
「ここだ」
自分が求める造形をその変化の中の一瞬に見る。一度頭の中で捉えたものは決して離さずに、それをイメージとして伝える。重要なのは自分の理想に対して怖気づかないことだ。
デッサンは概ね形になったと思う。GIDEをタンジブルモードに切り替える。本体から鳴っているウーッという音が一段階高くなる。その名前の通り、砂場のような場所になる。細かすぎる粒子が空間を自由に動くようになると、それは殆ど滑らかな水の流れと見分けがつかないようだ。
先程のデッサンイメージを元にBitからAtomに置き換えていく。私はゴーグルを上げて、自身のその眼で確かめる。そのテクスチャはこの眼で確かめながら見るのが大事だと思っている。造形は納得が行くものになったと思う。問題は「色」だ。
色に関する知識は全て頭に入っている。私は長い間、言語としての色の使用の文脈を学んできた。そして、色同士の関係性も言葉として学んできた。
しかし、私は色そのものを知らない。私の網膜の錐体細胞は色を認識することができない。
言語イメージをそのままプロンプトの命令として使用できるため、着彩自体は可能であるが、自らが知らないものに自分の作品を委ねることなどできない。
私は造形に対して必要な明暗の情報を付加していく。Atomの色彩が白と黒による明暗の階調という形で付加されていく。概ね仕上がったと思う。
「相変わらず、素晴らしいわね」
いきなり声をかけられて、うおっとなる。顔をあげると美術部顧問の山崎先生だった。
「ありがとうございます」
謙遜は美徳だとは思わない。褒められたら素直に受け取るのが私のポリシーだ。目の端で時計を見ると既に朝8時を過ぎていた。校舎からも登校する生徒の声が聞こえ始めている。集中していたようだ。しばらく先生はGIDEのガラスの中を眺めて、なんの悪気も無しに口にした。
「あなたはどこまでも白と黒にこだわるのね」
思わず心臓をドンと押されたように、ドッキリとする。
「モノトーンによる美の追求が私のスタイルでして」
「いいわあ。私は好きね。この色合いが豊かな渋谷という街と対立している所にあなたの強い意思を感じるわ」
山崎先生はこれまでも私の作品をとても買ってくれている。先生自身も芸術家であり、アナログ・オールドメディアとGIDEのような最先端メディアでの芸術の間に立ち、現代の芸術シーンにおいても影響力を持った人であり、私は先生を尊敬している。
私には色が見えないということは誰にもバレずにいる。色覚における異常は日常で浮かび上がった疑いの上で検査をしない限りは、基本的に発覚することはない。先生は色を用いないことを私のスタイル・こだわりとして受け入れてくれている。
再び前に座っているアヤが突き刺すように睨んでいる気がした。先生は続ける。
「万博シンボルアート制作者を決めるコンペ用の作品提出は1ヶ月後までだからね。尖った作品を期待して待ってるわよ」
そういって年齢を感じさせないようなウィンクと共に先生は去り、アヤにも声をかけた後に美術室を出ていった。アヤは私には決して見せないような笑顔を先生に見せていた。
この作品ではまだ不十分だ。
もっと自分の求める「美しさ」に近づかないと。
校門にある巨大なケヤキの葉が黒さを増した頃、校内SNSツールで山崎先生から呼び出しがあった。おそらく先日に提出したコンペの件という想像はついた。
放課後になり、失礼しますと言って職員室に入り、教室奥の座席まで向かうと、先に背筋の伸びたアヤの姿があった。結果の伝達であれば、彼女もいて当然だなと思う。
「先ほど万博の委員会からコンペについて連絡があったわ。結果なんだけど」
顧問は少し言い淀んだ後に言った。
「白汐さんが選ばれたわ。おめでとう」
私は内から飛び上がるような嬉しさを感じた。しかしそれを抑えた。アヤの気持ちもある。
「ありがとうございます」
と平静なトーンで返した。
「アヤさん、立場があるから私は直接審査には関われなかったから、他の審査員に聞いた話だけれど、あなたの作品も最終選考まで残って、最後はマリさんとアヤさんの間で揺れたらしいの。だからとても僅差で。うちの生徒がここまでの結果を出して、私は誇らしいわ」
先生は慰めのつもりだったかもしれないが、その言葉は慰めにはならないんだよ、と私は思った。アヤは、失礼しますと会釈をして去っていった。顧問は、あっと言って、少し失敗してしまったというような表情をした。
「それは悔しいわよね。後でまた話して見るわ。そして、マリさん。万博の作品だけど、8月にライブパフォーマンスのような形式になるから、それまでにしっかり準備してね。あなたの作品を全世界が見るのよ。私はとても誇らしいわ。あなたの作品を初めてみたときに撃ち抜かれてから、あなたのファンなのよ」
「全力で準備します」
顧問も幾分興奮しているようで話が止まらなかったが、上手いところで私は失礼しますと言って、職員室を出た。つい、っしっ!という声が出てしまった。ようやくここまで来た。この人生で二度と無いチャンス。自分にとっての「美」を証明する機会が。色が見えなくても「美」が存在するのだと示すのだ。
学校から家までの帰り道、渋谷の中心にある雑居ビルの一つに登る。決して高さはないが、この渋谷の街を広く見渡すことができ、人も入ってこない穴場だと思っている。一人暮らしの部屋に帰るよりも、こうやって動いている街を眺めている方が、創作をして生きる人間としては幾分得るものはある。
私は手すりに身を乗り出し、いつものようにぼーっとしている。とはいえ皆は渋谷は色彩豊かだというが、私には単調な白と黒とその間の繰り返しにしか見えない。しかし、より単調なものがより複雑なものに劣っているとも思わない。
次第に空が暗さを増していく中で、夕焼けに照らされた白い雲が早く流れていく。しばらくそれを眺めていると、強風が吹いた拍子に、つい足の裏が浮いて、眼科の渋谷の街に引き寄せられる感じがする。少しバランスを崩して、手すりから落ちそうになった。
全身の皮膚が逆立って心臓が飛び出そうになったその時、後ろから知らない何かに肩を抑えられた。再び地面に足がついた所で息を整え、助かったという状況を理解し、私は安堵する。一体誰がと思い振り返ると、若い男の人がわたしの肩を抑えてくれていたようだった。
「危ない危ない」
知らない顔だった。フードを被った少し年上くらいの20代くらいの男性に見えた。顔立ちは中性的で少しダボつきのある服を着ていた。
「飛び降りでもするのかと思って、びっくりしたよ」
「ありがとうございます。バランスを崩してしまって」
「怪我とかも無さそうで良かった」
親切な人だなと思った。それにしても、この場所に人がいるのは珍しい。
「ここにはよくいらっしゃるんですか」
「時々ね。なんだかこの場所って居心地がいいんだよね」
そう話している彼の後ろを見ると、缶のようなものがいくつも無造作に並んでいた。さっきまであんなものあったかな。さらに眼の前の彼の服を見ると、なんだか所々が黒く汚れているように見える。私はそれらの情報を勘案して、一つの結論を導き出す。
「落書き…?」
思い浮かんだ言葉が口からこぼれてしまった。男性の顔からは「ギクリ」という音が聞こえるような気がした。彼はしばらく逡巡したような素振りを見せた後に開き直った。
「グラフィティと呼べっ」
その男は自分のことについて、聞いてもいないのに話し始めた。
「見られちまったら仕方ないな。おれはグラフィティアーティスト。多くは語らないが、この退屈な世界で絵を書き続けている」
少しだけ興味を持った私は、彼が描いていた階段につながるドアの横に描かれたグラフィティに近づく。スプレー特有のグラデーションがかかったテクスチャ、誇張されたように歪曲する筆致、まだ半乾きで垂れ落ちているインク跡。どの点をとっても私にとっては目新しい。一体なんと書いてあるか辛うじて読めなかった。
「これもアートなんですか」
私は素朴な疑問が故に、シンプルに突き刺すようなことをつい聞いてしまう。しかし彼は怒らなかった。
「当然だろう。アートというのは本来こういうものだ。世界に対する自己意識の主張。つまりは、この時代に生まれ、そこで生きる自分自身を世界に叩きつけるものだよ」
「でも警察に通報すれば」
「いや、ナチュラルにやめてくれ」
グラフィティにもルールやコミュニティ、向き不向きのある場所があるのだと彼はいう。
「社会に認められていないことに美しさはあるんですか」
「当然だろう。そもそも社会は美しくない」
「もしなぜ美しいのに認められていないんですか」
「なんせ落書き行為だからな」
答えになっていない答えに、つい笑ってしまう。しかし、すぐさまはっとして緊張感を取り戻す。違法行為しているような相手に対して、少し無防備過ぎたかもしれない。
「昔いたバンクシーみたいなことですか」
バンクシーは21世紀前半に有名だった正体不明の覆面アーティストである。いつしか作品が発表されることもなくなり、覆面を被ったままやがて消えていった。
「彼はスーパースターだな」
そういえば、なんでバンクシーは認められているんだろう。
「バンクシーはなんで捕まらなかったんですか」
「簡単な話だ。彼の絵には価値があった。だから器物”損壊”にはならない」
「金になるような絵を彼は望んでたんですかね。それこそ社会への迎合のような」
少し男は驚いたような顔をする。
「女子高生にしては中々鋭いところをつくね。君も絵を書いたりするのかな」
「Generative Art ですけど」
GAというその言葉を聞いた彼は、GAねえ、と渋い顔をした。
「それは”描いている”とは言えないな」
自分が日々向き合っているものに描いていると言われると、流石に私もカチンとくる。
「どうしてですか」
「君の体に君が”描いた”ものは残っているかい」
「私の頭の中には残っています」
「いや君のアートはGA無くしては成立できないだろう。スプレー1本で絵が描けるかい」
そういって彼は持っていたスプレーを私に手渡してきた。
「描いてみなよ」
「私は犯罪者にはなりたくないので」
万博を控えた大事なこの時期に変なトラブルはゴメンだった。
「つまらないな。新しい体験に積極的になれないと芸術家に向かないぞ」
「うるさいです」
私は少し黙って、再び彼の絵を見る。そこに描かれたコミカルなタッチの中には温かみや人間臭さのようなものを感じた。
「ところで君、色が見えないだろ。しかも1色型かな」
思いがけない言葉に、私は心臓が飛び出そうになる。いきなりのことで頭が混乱する。
「別にそんなことないですけど」
「じゃあ、これが読めるか?」
彼は先ほどのグラフィティの隣のものをアゴで指す。
「線が汚くて読めないです」
「やっぱりな」
男はニヤリとした。
「読めないはずないんだな。こんなわかりやすく書いてるんだから」
一体何が起こっているのか状況を掴みかねた。一体この絵がなんだっていうんだろう。
「色覚異常の検査で用いる絵と同じ原理が入ってるんだ。おれは特別な色覚を持つ人に見え方が異なるようなグラフィティを書いてるんだ」
検査については組織から話を聞かされている。検査とは、色覚による色の見え方の違いを利用した絵を見せ、その回答から色覚の状態を確認するものである。
しかしそもそも色覚の検査とは疑わしい場面が日常から発見されて初めて発生するものだ。日頃の会話などで気をつけていれば、そもそもそのようなシチュエーションには至らない。しかし、そういった検査に対する対策はあっても、グラフィティがその触媒になるとは想像だにしなかった。
「別に隠さなくていい。悪いことでも無いんだし」
男は再び微笑んだ。その表情には、先ほどよりも優しさを感じた。
「おれも同じだからよ」
彼は名乗った。Glitch。君と同じ生まれつき色が見えないグラフィティアーティストだと。
「詳しくは話したくない」
誰にも話さないというのが組織と私の間にある契約。私は肯定しなかった。そして否定もしなかった。どこかで誰かと共有したいという思いがあったんだと思う。
「色々思うところはあるんだろうから」
Glitchは再び私を誘う。
「ま、描けよ」
大きく”赤”と書かれた灰色のスプレー缶を手渡そうとする。少し迷った後にその缶を手に取る。踏ん切りをつけるように思いっきり踏み出して壁に向かった。
スプレーから奏でられたシュッという音は軽かった。
「これまでの作品より、より良くなりそうね」
朝練の様子を見に来た先生は、私のGIDE内の制作中の作品を見てそう言った。
「万博に向けて集中してますから」
「もちろん気迫と集中みたいなものも感じられるわ。でもそれと同時にやわらかくなったわね。あなたの作品には張り詰めた感じがあったのだけど、それが少し変わった感じがするわ」
制作は順調に進んでいた。当日は会場にある専用のGIDEを使用して、その場で生成を行うことになっていた。用意されるのは美術室に備え付けられたモデルとは比較にならない大きさかつ最高性能のモデルであり、その処理方式を一般向けとは異にしている。BMIからスキャンした自身の脳の物理情報をモデルとして再構成し、自身の想像と生成が一致する最高の創作体験が得られるという話だった。
私に起きた変化としては、時々Glitchと会うようになっていた。彼は神出鬼没な男だったが、大体自分のような人間が引き寄せられる場所があるんだという。Glitchと共に時折グラフィティを描いた。
「ま、なんかあったら俺が責任とるから。もう何個描こうが変わらんからな。でもどうせ捕まるんならカッコよくいきたいんで、大胆なの描いてくれ」
と彼は冗談のように言った。見た目からはあまり想像がつかないが、意外とたくましいことを言う人だった。
そして、先ほどからアヤがいつも以上にこちらをチラチラと見てくる。別に見たいなら見に来たって良いんだよ。私はこれまでよりも創作するのが楽しくなっていた。
「問題なしね。最後の最後まで本当につまらないくらいだったわね」
今日は組織による最後のテストだった。そこに多少の感慨のようなものがあったのか、私はつい兼ねてから気になっていたことを聞く。
「ねえ、私って色を学ぶ必要あるのかしら」
「学んでもらわなきゃ困るわ。そうでないと、この長年の実験が全くの無駄だったということになるのよ」
「そんな結論ありきなことを言われてもね」
「あなたが色を学べば、主観は存在する」
「もしそうなったとして、何か変わるかしら」
女性は私の問いに少し憤りのようなものを見せた。
「変わるわよ。わたしたちは機械と同じじゃない。AIには実現できない、私たちだけの価値がそこには存在することになるわ」
「でも一体それがなんだって言うのよ」
「やけに今日は突っかかるじゃない。長い間そんなこと聞いても来なかったのに」
私はつい素直な感情を口にしてしまう。
「ただ、世界が変わることが少し心配なだけ」
「あなたもまだ若いものね。でも大丈夫。何も心配することはないわ。あなたの錐体の機能を復活させて、色を見た上でこの施設の奥にある特殊なGIDEを使用する。あなたの脳を物理的な情報をコピーして、そのGIDEに接続するだけ。それはあなたのそうすれば自ずと答えは出る。
長い実験が終わりを迎えるということに、何か思うところがあるっていうのは分かるけどね。私にあなたの気持ちはわからないわ。あなたが私の知っている色を知らないように」
確かにそうなのかもしれない。脳を切り開いたところで、そこに色があるかは分からない。
「一個良いことを教えてあげる。今のあなたの顔は興奮して赤くなっているわよ」
私はここしばらくは毎朝、いつもよりも早く美術室へと向かっていた。闇が明けたばかりの渋谷は静かで、人が少ない。ああ、騒がしい夜の渋谷の街というのは、絵が書かれた状態なのだな、と思う。朝の白紙の状態に一本、また一本と線が引かれていくのだなと。その景色の見え方も変わっているような気がする。
美術室は既に明かりがついており、アヤが既に作業に取り掛かっていた。
「アヤ、早いね」
と声を掛けると、彼女は返事をしなかった。彼女によく思われていないことはわかっているが、こう直接的に冷たくされるのは少し堪えるものがある。ただ、彼女を差し置いて、自分が万博のシンボルアート制作の代表に選ばれたという意味では、彼女の気持ちも分かる。
もし逆の立場であったならば、悔しさから冷たくしたかもしれない。
定位置についた私は、GIDEを起動する。作品を仕上げていく。万博は日本の技術力も踏まえたアピールの場であり、開会式の場で特設な巨大GIDEを使って、私は生成することになる。そのスケールの大きさは、作り込まなければいけない作品の解像度を意味する。
しかし、私は自分が主張したいこと、すべきものについて、きちんとした整理はついているとはいえない。機会を手に入れることが大きな目標だった。しかし、それを手にいれた今、加えて私が作り出すべきものは何か。
待機状態のGIDEの内部では、粒子が波打つように浮遊している。その流れに思わず、自身の体もフワフワと揺れるような気がする。
私は負けたくない。生まれたときから、色を知らずに生まれた。最初はそんなことに気が付かなかった。しかし、言葉を覚えるにつれて、人々の会話の中に現れる「色」という差異が理解できないことを知る。自分の世界は文字通り、普通の人よりも低い次元を生きているのかもしれない。自分にとっては違いの無いことが、多くの人には違って見えている。
私は初めて美術館で絵を見たときの感動を忘れない。それは色のある絵だったが、そんなことなど関係なく私には美しかった。他者も同じようにその絵を褒めそやしていた。しかし、皆と私は違ったものを見ている。それでも美しい。美は色を超えたところに存在している。私はそのことを証明したい。
「白汐さんの絵、だいぶ変わったわよね」
いきなり声をかけられて振り向くと、そこには顧問の姿。気がつけば、一限まであと十分という時間になっていた。いつの間にか教室にアヤの姿も無く、私と顧問の二人だけだった。
「そんなに変わりましたでしょうか」
「ええ変わったわ。明暗の使い方が大きくね」
「あまり意識しているつもりは無いんですけどね。どこが変わってますか」
うーん、という顧問。違和感の言語化を試みる。
「平たく言うと、優しくなったわね」
「優しい?」
私にはその感覚はなかった。
「元々あなたの作品は、色が使われていないのに色彩があるような、独創的なライティングが魅力よ。恐れを知らないような大胆さと激しさ。あなたの中にあるものを届けようと主張するような。必死さともいえるかも」
そういう風に見えていたのか。私はこれまでの自分が作った作品を頭に思い浮かべていた。一つ一つ必死に作ってきたことは間違いない。それぞれに思い入れがある。
「でも最近のあなたの作品から、その鋭さは感じられなくなったわ。ほら、今作っているその作品にも、どこか包容力がある」
顧問は私のGIDEの内部を指差す。
「もちろん良いことだと思っているのよ。作品の変化はあって当たり前。それがこのタイミングにあなたに訪れているというだけだと思うわ」
そういって顧問は微笑んだ。
突然の出来事だった。いつものように施設に向かうと、暗いジャンパー服を着た大人たち。その至るところに「警察」の文字が書かれている。「何かが大きく変わってしまう」そんな予感がする。
「すみません」
いきなり後ろから声をかけられて、思わず飛び上がりそうになる。黒い服にスーツを着た男性だった。
「白汐マリさんですね」
私はその時大体の事情を察した。後に警察署で話を聞いたことには、組織の活動が明るみになり、社会的に問題のある実験を行っていたとして摘発されたということだった。そして、彼らは私に対して行われていた実験についても、全てを把握したようだった。
生まれた時に、ろくでもない親に被検体として売り払われ、実験に協力する代わりに、私と親の元に毎月多額のお金が入ってくるのだと。親は私を組織に渡して消えてしまった。
私が生まれた時には、すぐに特殊なナノマシンを注入され、人工的に錐体細胞が色彩認識する機能を遮断された。網膜内のS・M・L錐体が正常に機能しなくなり、わたしはこの世界の色を認識できなくなった。
色が見えなくなった私は、社会性や色に関わる言語的な常識を一通り獲得させられる。そして、ある年齢を迎える時にナノマシンを無効化し、錐体細胞の機能を元に戻し、色を目にさせて新しいことを獲得させるという算段である。その時に、わたしの脳にどのような変化があり、私は何か新しいことを学ぶのか、という実験。
一世紀近く前に、哲学者が思いついた下らない思考実験。
よくもそんな下らないことを考えて、さらには、よくも実行に移したものだ。
私は警察に訊ねた。私はどうなるのですか、このまま色を見ることになるですか、と。
警察は色を復活させるための薬を組織から押収しており、それを渡すことはできると言った。また年齢や状況を鑑みて、私が何かの罪や責任に問われるということはないという話だった。
「今もっとも説明しなければいけないことは、期限が迫っているということです」
中年の刑事は、野太い声で言った。
「何の期限ですか」
「色を見られるようにするための修復操作を行う期限です。元々設けられていた実験の期間というのは、この実験自体の限界に合わせて設定されているのです。彼らから押収した薬も、あと二週間の内に服用しないと効果を持たなくなります」
「もし飲まなければ」
「一生色は見えません。今のままになります」
そうか。私は元々持っていなかったはずの選択肢を改めて与えられたのだ。それも何も変わらないでいられる、という選択肢を。
「色々な議論はあったんです。被害者である貴方に色を戻さないといけない、という意見が強かったのですが、そもそもあなたは生まれたときから色の無い世界を生きている。他人である私たちが、勝手に世界を変えるようなことをしていいのかと。結局、最後は本人に委ねることになりました」
男は優しく私の手のひらを開かせて、小さな袋を握らせた。
「手続きは済んでいます。これが目薬です。これを注せば、あなたの世界に色が現れます」
翌日高校に登校するや否や、私は顧問に職員室に呼ばれた。ちょっとついてきて、と言われ、職員室の奥にある個室のような場所に入った。置かれた椅子に腰掛けると、顧問はやけに神妙な面持ちだった。
「落ち着いて聞いてね」
つばを飲み込むような間があった後に、彼女は口を開いた。
「警察からあなたの話は聞いているわ。今回の一件で万博に関して、色々な話があったみたいでね。それで、その」
彼女は躊躇いながら、結論を口にした。
「万博では、白汐さんの制作発表はできなくなってしまったの」
何かが大きな音を立てて崩れるような音がした。
「それって一体」
「万博は国レベルの大きな話でしょう。そこに今回あったような話が関わってくると、とてもややこしくなってくるの。万博には関係している人も多いだけにね。問題は起こらないに限るの。それであなたを出すことはできないということになってしまったみたい。大人の事情に巻き込んで本当にごめんなさい」
決して顧問が悪いとは思わなかった。誰が悪いとも言い難い話だなと思った。言うならば、自分がこれまで、自分の運命を受け入れたままでいたことが一番悪かったのかもしれない。
「それで、もう一個伝えないといけないことが」
まだ何かあるのか。思わず貧乏ゆすりをしていることに気がついた。
「それでも万博の制作自体は必要だから。あなたの代わりが選ばれたの。それがアヤよ」
アヤ。そうか、アヤが。既に自分の感情はよくわからなくなっていた。しかし、揺れる心の中でもこれだけは確実に言えるような気がしていた。
「それなら安心です」
「ま、存分に悩めよ」
私は路地裏でGlitchとグラフィティを描いていた。
彼に事情を話してみたところ、別に何かを期待していた訳でもないが、思った以上に淡白な扱いを受けていた。
「お前には選択肢があるんだからな。その幸福を噛み締めたらいいさ」
そう。Glitchと私では事情が違う。彼にはどうしようもないのだ。
私は望めば色を見ることが出来る。そう思った時、私は彼に非常にデリカシーの無いことを話しているかもしれないと気がついた。
「ごめんなさい」
「何か色が見えて困ることがあるのか」
そう改めて問われると困った。元々最後には色が見えるようになるはずだったのだから、同じように目薬を注して、さっさと終わらせればいいのだ。色が見えるようになったところできっと困ることはない。しかし、選択肢が用意されたことで私の中には迷いが生まれていた。
私の中に形作られてきたものは、きっとそのままではいられない。私が求めてきた「美」に色は含まれていないのだ。私が追求してきたものの根幹は、必ずどうにか変化するに違いない。だが、今そうなるはずだった運命を撥ねつける権利を私は得たのだ。
Glitchは私の顔を見ずに、黙々と壁に向かってスプレーを吹き付けている。
「きっとない。定めと受け入れていたはずのことが、急に責任が自分に降りてきたことで戸惑っているんだと思う」
「したいようにしたらいいさ」
「それがわからないんだって」
ふーっといって、Glitchは手を止めてようやくこちらを向いた。その顔は少々苛立っているようにも見えた。
「お前は何を証明したかったんだ。なんでおれと一緒に落書きしている」
「この私の眼から見える美しさよ。色がない世界の美しさというものは、決して劣ったりしていないということなの」
「もし色が見えるようになったら、その信念が変わっちゃうって思っているのか」
ぐっと、言葉に詰まる。そういうことなのかもしれない。
「迷うって事はよ、二つに一つだ。一つは、自分に証明したいことなんて別に大したことないんだって認めてしまっている。もう一つは、色のことが本当は気になっているということだ」
「そうじゃなきゃ迷ったりしないって?」
ああ、と Glitch は頷く。
翌日に朝練に行くと、教室にはアヤが先にいた。いつものように通り過ぎて後ろの席に行こうとしたところ、通りがけに腕を掴まれた。
「待って」
私は振り返る。いきなりのことで少し驚いた。しかしアヤは前を見たままだった。
「先生から聞いた。あれって本当なの」
「あれって何のこと」
少し間があってアヤは口を開いた。その表情は見えない。
「色が見えないってこと」
「うん。本当」
彼女はぎゅっと私の袖を強く握った。そのまましばらくそうしていた。
「こんな形で選ばれたくなかったわ」
「万博のこと?」
「作品の良さであなたに勝ちたかったわ」
素直な人だ。だから敵意を向けられているような気がしても、アヤのことは嫌いにはなれない。むしろ、私は彼女を尊敬している。
「アヤだったら安心だよ」
アヤは手の力を緩めた。
「わたしは」
アヤは振り返った。透き通ったその眼は私を奥深くまで見通しているように見えた。
「あなたの作品が好き。あなたの美しい作品が皆に注目される瞬間が見たかった」
発せられた思いがけない言葉に、つい呆気に取られる。
「悔しいわ。あなたの作品がみんなに見られないことも」
そして彼女はぐっと何かを吐き出すようにして。
「色が見えないはずのあなたの描く絵が、とても美しいということも」
そういって、彼女はまた前を向いて黙々と作業を始めた。こうしてモヤモヤとしていた色々なことがすっと晴れたようにまとまり、決心がついたような気がした。
2075年8月、渋谷万博の当日が訪れた。渋谷のスクランブル交差点には、特設のステージが用意された。私は開会式を見守っている。元々の登壇予定者だったということと、顔の利く顧問からの計らいもあり、最前列の関係者席でステージを眺めることができた。
開会式の会場には一万人を軽く超える人が集まっており、日本人だけではなく多くの国籍の人がいるように見えた。騒々しくも活気ある形で、今か今かと始まりの時を待っている。私は色についての選択を終え、選んだ道に既に気持ちは軽くなっていた。
しばらくして、華やかな映像の演出と共に、壇上にスーツを着た女性が背筋の伸びた姿で現れ、開会式を取り仕切り始めた。東京都知事であるとすぐに分かった。しばらく挨拶が行われた後に、再びステージ上の大きなスクリーンでは用意された万博の紹介動画が流れ、次第にお祭りの様相を帯びてきた。シンボルアートの発表はもうすぐだった。
「そして、今回この万博の開催都市である、渋谷の学校に通う高校生アーティストによる万博のシンボルアートの発表になります」
ついに、アヤの出番だ。クールな彼女に限っては緊張をしなさそうなものであるが、私の方もドキドキとしてくる。ステージ上にはおよそ5メートル四方の巨大なGIDEボックスが設置された。ここまでの大きさのものは初めて見る。普段私たちが使っているものと比較にならないくらいの大きさで、凄まじい解像度が求められるだろう。
舞台の袖からアヤが出てきた。凛とした姿はこういった華やかな場にも負けず、絵になるような気がする。彼女はGIDEの前に来ると、少しぶつぶつと何かを口を動かしているように見えた。
「おい、あれを見ろ!」
急に誰かが大声で叫んだ。周囲はざわざわとし始め、皆がわっとあたりを見渡す。皆が後方を向き始め、指をさしている。私もつられて振り返ると、ステージと反対側にある高いビルの上に大きなグラフィティが書かれているのが見えた。観衆はカメラを構えたり、何かを叫んだり、騒がしくなり始めた。あのグラフィティは、と思った時、急に後ろから肩をガッと掴まれた。驚いて振り返ると、ステージにいたはずのアヤだった。
「あなたの選択を見せて」
彼女の決然とした燃えるような瞳が私を突き刺す。そのとき、これは用意された作戦なのかもしれないと気がつく。騒乱の中、私はアヤにぐっとステージへ引き上げられ、深いことは考えずにGIDEに向かって接続する。警備員たちも現在の状況に混乱して右往左往している。
私は自分のイメージを Generative Engine に伝える。筐体は大きな唸り声をあげながら、粒子は私の想像を受け取り、形作られ始める。
「見ろ!今度はステージが!」
群衆は忙しなく今度は前方に振り返る。
大きな箱の中には、私が思い描いた美が圧倒的な存在感で形を持って現れた。
届け、届けと、白と黒だけの像にありったけの思いを乗せる。
文字数:15232