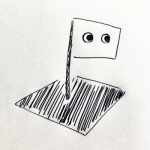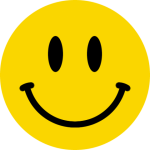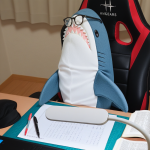梗 概
喉仏の歌
遺伝性の進行性神経疾患をもつケイと、その友人エルの話。3D映像プロジェクターを通し人々が空間移動することが日常となりつつある社会で、ふたりはリアルに顔を合わせて時間を過ごす貴重な友人だった。神経疾患の症状である筋力低下が進み外出が難しくなるなか、ケイが書いた絵がインターネット上で評判となる。3D映像として自分自身も巧みにプロモートしていくケイは、画家としてのみならず世界中の人の心をとらえ、一方エルとの関係は徐々に疎遠になっていった。ある日久しぶりにエルの部屋にきたケイが、喉仏の骨で作った笛を吹くことをエルに依頼して消える。気管切開し呼吸器を装着した車いすのケイを伴い、思い出の河辺でエルが笛を吹くとそれに呼応して鴬の声が響き渡った。
遺伝子治療を巡る倫理的問題について20世紀後半以降専門家が延々と議論している間に、テクノロジーは身体の持つ物理的制限を次々と超えていった。2075年現在、3D映像を投射するプロジェクター(通称:アラジン・スポット)は社会インフラとして定着し、人々は3D映像として物理空間を移動することを選んでいった。2040年までに極限まで進んだ高齢化と高い独居率が拍車をかけ、日本でもこのライフスタイルは着実に浸透していった。
ケイとエルは、インターネット上の愛鳥コミュニティを通じて知り合った。同い年で自宅も近かったことから、二人はアラジン・スポットを使うよりもリアルで会うことを楽しんだ。50年以上に渡る住民の熱心な環境保護活動の成果として、野川周辺にはアラジン・スポットはおろか街灯もほぼなく、一年を通じて様々な鳥が集まった。武蔵野にあるケアユニットにケイが入居した後も、野川沿いは二人のお気に入りの散歩エリアだった。主症状である筋力低下に伴いケイの歩行が徐々に難しくなると、ケイは絵を描きはじめた。インターネットに公開した作品は注目を集め、瞬く間に世界中から声がかかるようになった。ケイにとってアラジン・スポットを通じた交流こそ主要な日常になっていった。散歩の回数は減り、二人はすこしずつ疎遠になっていった。
2075年2月、バンコク市内にある美術館で行われた芸術祭授賞式会場にいるケイを、エルは自宅で見ていた。その日の夜、ケイが久しぶりにエルの部屋にやってきた。二人はかつて野川でみた鳥の話をした。ケイが帰った後、エルは夢のようなものをみた。ケイは自身の喉仏から小鳥を取り出すと、「喉仏の骨でつくった笛を吹いてほしい」と告げて消えた。翌日エルが武蔵野のケアユニットを訪れると、呼吸器を装着したケイのベッドサイドに鳥笛が置かれていた。呼吸筋が低下したケイは気管切開をしていた。電動車いすのケイを伴い野川沿いでエルが笛を吹くと、それに呼応して鴬の声が響き渡った。
文字数:1148
内容に関するアピール
50年前にあたる1975年に、身の回りにあったモノとなかったモノのことを考えていた。コンビニはないがスーパーと八百屋はあった。パソコンとスマホはなく、固定電話とテレビとラジカセはあった。メールはなく手紙とファックスはあった。インターネットとAIはなかった。電子マネーはなくずっと現金だけだった。いつのまにか浸透し振り返れば劇的な隔たりとして気づかれるこれらは、人間にとって実際どのような違いなのだろう。
50年後にあたる2075年は、VRゴーグルはすでに廃れてるかもしれない。ドローンと遠隔オペはずっと普及しているかもしれない。現金はもうないのだろう。そしてそこにあるのは、人間にとって実際どのような違いなのだろう。
そんなことを思いながら書いていました。
文字数:329