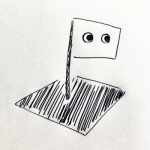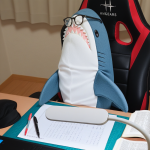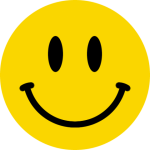梗 概
15億kmの孤独
人類が火星と金星に進出した未来のお話。
西暦2400年ごろ、火星と金星は地球からの独立を主張し、大規模な戦争が起こる。総力戦は凄惨を極め、宇宙船の残骸と乗組員の死体が各惑星間を大量に漂うようになる。人類の95%以上が死亡した後、地球が勝利するが、急激な人口減少と資源枯渇により人類滅亡の可能性が生じる。
およそ50年後、滅亡が現実味を帯びてきた時代。
科学者である主人公は、宇宙のはずれで奇妙な難破船を見つける。ほぼ無傷の状態で難破したように見えるが、内部の鉄製部品のみがボロボロになっている。また、乗組員の死骸の全身の骨がほぼ無くなっていた。不思議に思った主人公は、同行者の協力を受けながら、難破船に何が起こっているのかを調べる。
調査の結果、一連の現象は未知の微生物により引き起こされていたことが判明する。その生物は炭素ではなく珪素を基盤とした生命で、酸素をほとんど必要としない。主食は鉄で、代謝にリンを必要とする。どこからその生物がやってきたかは不明だが、その生物は宇宙船を構成していた鉄と、死体の骨に含まれていたリンを摂取しているらしい。リンは宇宙空間での存在量がとても少ない元素であり、人間の骨は珪素生物にとって「ごちそう」だったことだろう。主人公は政府に珪素生物の存在を報告。鉄と骨を食べるという性質は明らかに人類の脅威となるため、政府はパニック状態に。鉄を含む合金が露出しない仕様の宇宙船が急造され、主人公たちはさらなる調査に出る。
主人公たちは周辺の宙域の調査を進め、珪素生物が広範囲に広がっていることをつきとめる。さらに、珪素生物の観察を進め、珪素生物が胞子のようなものを宇宙空間に飛ばして繁殖していることも明らかになる。
胞子は宇宙空間を漂う間休眠状態にあり、真空状態やほぼ絶対零度の低温に耐えられるようになっている。鉄・リン・微量の酸素・適度な温度の4要素が揃った環境にたどり着いたタイミングで胞子は活性化し、成長し、胞子を飛ばす。珪素生物は長い時間をかけて、宇宙空間を渡ってきたのだ。
珪素生物の移動は遅いが、いずれ珪素生物は各惑星にたどり着き、人類は食い尽くされてしまう。絶望する同行者たち。一方、主人公はなぜか満足そうな表情をしている。
主人公は語る。
珪素生物にはどこかに故郷の星があるはずであり、そこから地球の近くまで移動するには少なくとも数万年はかかること。
それだけの時間があれば、故郷の星の珪素生物が、知性を持つ状態までに進化している可能性が十分にあること。
人類は宇宙でひとりぼっちではなかったと思える、それで十分じゃないか、と言い、主人公は珪素生物の作り出した結晶を愛おしそうに見つめる。
その数十年後、人類最後の一人が息絶えるその時。豊富な鉄と、極めて高濃度のリンを有する土星の衛星・エンケラドゥスでは、原始的な知性を持つ最初の生命が生まれていた。
文字数:1184
内容に関するアピール
「鯨骨生物群集」をご存知でしょうか。
深海に沈んだクジラの死骸に棲み着き、そこでひとつの生態系を構成する…という奇妙な生き物たちのことです。
いろいろ面白い要素を持っているのですが、中でも「飛び石仮説」が個人的には興味深く感じられます。
「飛び石仮説」とは、深海にある熱水噴出孔に棲む生物たちが、他の海域に広がるための足がかりとしてクジラの死体に棲んでいるのではないか、という仮説のこと。
今回の話は、クジラの死骸を人間の死体に置き換えて、そこに棲む生物が発見されたらどうなるだろう? という発想から作りました。
元々の構想では、絶滅に瀕した人類が珪素生物を使って生き延びる方法を見つける方向性にしたかったのですが、どうにもいい案が浮かばなかったので滅んでもらいました。
お話が思った方向性でオチてくれない場合、どうすればいいアイデアが浮かびやすいか、アドバイスいただけると嬉しいです。
文字数:387