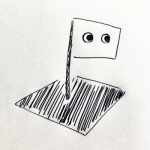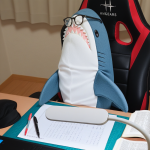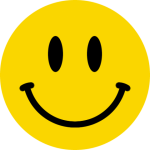梗 概
紙々の記憶
人口減少と資源枯渇により世界が衰退を辿って数十年。持続可能な世界の実現に向けていまだに技術研究と政策立案を続ける一握りの日本のエリートには様々な特権が与えられたが、AIインプラントによって桁外れの思考力と記憶力を獲得した都市の人々は、一般国民をルーラル民と呼ぶのに対してアーバン民という固有の民族の名で呼ばれるようになった。
アーバン民が提唱した地球回復施策の一つである紙木(しぎ)化プロジェクトは、分子生物学を活用した遺伝子交配によって精製紙を生きた植物へと巻き戻す技術である。焼け石に水でしかないことはアーバン民も承知していたが、彼らにとっては必要な役所仕事であり、正確な情報インフラと教育機会が失われて久しルーラル民に問題なく受け入れられていった。
九州最大の紙木林に勤めていたルーラル民のフナトは紙木林保護官として紙木の世話をしていたが、ある日彼女のもとに十年に一度あるかないかのアーバン民の来客があった。ヒノと名乗る女性が、自身が開発したという測定器をフナトに授けて言うには、紙木の表面をそれで測定することで、木になる前の紙の表面状態が浮かび上がる。つまりかつて紙だった樹木たちを「読める」という。
フナトが育てている木の多くは、その素材が図書、それも小説などの物語からできていた。ヒノは失われた物語を読みたくて、はるばる九州までやってきたのだった。ヒノの語るアーバン民の暮らしと、全く知らなかった物語という文化に魅了されたフナトは、測定結果を渡すために数年後にヒノと再会することを約束する。フナトはひたすら読林した。
時は経ち、ついにフナトのもとにアーバン民がやってくるが、それはヒノではなかった。ヒノの姪を名乗る後任者は、ヒノが死んだことを告げる。負担の大きい頭脳労働ばかりのアーバン民が短命であることをカナエは知らなかった。
失意の中でフナトは自分の仕事が無意味なものだったと語るが、姪はその仕事が、アーバン民が地球の寿命を延ばすことを責務としているのと同じで、無意味でも価値のある仕事だと説く。
フナトは彼女に、自分が精一杯覚えた物語を伝えられるだけ伝えようとした。だがアーバン民ほど賢くないフナトは、要領を得ない説明と不完全な情報伝達でアーバン民である姪の時間を奪ってしまうのを悔しく思う。
ヒノの姪が帰還してから、フナトは読林した紙木の上に更に文字を書き込むことを思いつく。展開やメッセージといった、物語の情報を圧縮してアーバン民や他のルーラル民に伝え、受け手に解凍してもらうことでその人だけの物語をたくさん楽しんでもらうことができる。効率化された文化の再創造によって、常にプレッシャーとストレスに苛まれていたアーバン民の寿命は平均で二年も伸びたという。フナトが生涯を捧げた仕事を、最後に訪れたアーバン民が称えた。いつも難しい顔をしたアーバン民が笑顔を浮かべるのをフナトは初めて見た。
文字数:1200
内容に関するアピール
「梗概を書こう」というテーマを受けて最初にしたことが、梗概と本文の違いはどこにあるのかを、書いている時の自分の様子から比較することでした。
自分が梗概を書く時には説明の取捨選択を重視する。一方で本文を書いているときは、プロットの整合性など以上に「描写の取捨選択」に悩まされる。ところが両者は完全に分けられるわけでもなく、情緒のある描写が単なる説明以上の情報を生み出してくれることもある……などと考えるうちに、梗概の要件というのは「とてつもなく賢い人が試行錯誤を繰り返せば、限りなく同じ本文を再生産できること」ではないかと思いつき、こんな物語を書いてみました。
記録しないとものを覚えられない我々のようなルーラル民と、賢くて記憶によってほとんどの情報伝達が可能なアーバン民の話は少し前に考えていたのですが、それを梗概というテーマ、及び「元は本だった樹木」という紙木の設定と組み合わせてみました。
文字数:395