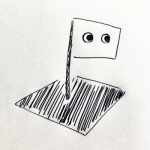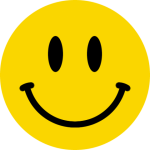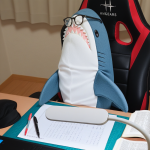梗 概
箱庭調査ONLINE
少子化と教員の人手不足により、日本は多くの教育や研修を人工知能によって実施するようになった。自分のやりたいことを学べる人間は一握りとなり、多くは人工知能による適性判断によって自分の進路を決められる社会となっていた。
子供達に適材適所の将来を用意するのに重要となったのが『箱庭調査』と呼ばれるシステムだった。それはゲーム中に出てくる様々な人と膨大な選択式の会話をし、最終的に特定の性格に分類するという、性格診断を延長したような他愛もない見た目をしたゲームだったが、実際にはその後の中等教育のカリキュラムと、将来進む業界までもほぼ決めるという受験以上にシビアなアンケートだった。箱庭調査はライフステージに応じて実施の通告が届き、特に10歳~12歳の子供が遊ぶことは半ば義務付けられている。プレイからクリアまでの数ヶ月間、両親は箱庭調査に関して子に入れ知恵をしてはならない。
主人公は箱庭調査の受験が義務化される前の最後の世代の生まれで、来年は自分の子供が受験することになっている。当然心穏やかではない。我が子は音楽が好きであったが歌は決して上手ではなく、逆に数学は好きではなくても好成績だった。
そんな折、彼はPTA経由で箱庭調査をハックしようとしている男の噂を聞く。彼とコンタクトを取りその腕前を信じた主人公は、転職を装って初めて箱庭調査をプレイし、必要なデータをかき集める仕事に出る。
ゲームの内容はテキストとデータが膨大なシミュレーションのようなもので、会う人間とひたすら選択式の会話をすることで自分のアバターを育てていくゲームだった。出会う人間は政治的によりどりみどりのスタンスを持っており、ある人間の味方をすれば別の人間のルートが途絶える。そうしてNPCたちと築いた絆が、そのまま自分の気質として評価されるらしい。
高度なシミュレーションで、気が滅入るほどのボリュームだったがこれで本当に人の本質が読み取れる訳が無い。そう考えていた矢先、プレイヤーの眼の前に「箱庭調査は悪だと思うか?」「データを流出させられる人間がいたら加担するか?」という趣旨の問いかけをするNPCが現れる。咄嗟に嘘をついて否定したが、怖くなって主人公はしばらく箱庭調査のプレイから離れた。
自分のプレイログが監視されているかもしれない恐怖に怯えながら、主人公はこのシステムで出てきたNPCたちが過去のプレイヤーのログによって作られた疑似的な現実であることに気づく。プレイ中に自分に寄ってくるNPCはあまりにも知り合いに酷似していた。
膨大なデータの中では自分の行動も予測され尽くしており、子供は自分の子供である限り調査で決められる運命を変えることはできない。主人公は嘆きながら、いもしないハッカーのために調査をプレイし続ける。
文字数:1151
内容に関するアピール
50年後の未来という点ではなくこの先50年の間にどんな事件がきっかけで世の中が変わるかという線として考えたときに、ナラティブの飽和による自己の感想・善悪判断の外部化というテーマに関心を持ちました。
昨今のSNSを追っていると、自分が何を許せないと感じるか、何を微笑ましいエピソードと感じるか(そのエピソードの裏で苦労した人から目を背けられるか)という自分自身のスタンスを受動的に決めさせられている気分になることが度々あります。
勿論それは私自身の主体性のなさ、社会参画意識の欠如にも大いに責任があるわけですが、不特定多数のネット上の人の言葉に耳を傾けていると『興味がなく、重要でもない議論に関して善悪の判断を迫られる』という作業の繰り返しによって自己がソナーのように形作られていくような体験をすることが時々あります。50年後は、誰もがそのようにして自己形成していく世界を想像しています。
文字数:393