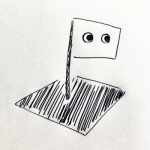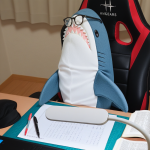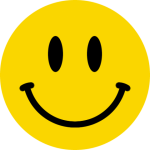梗 概
オートノモス・リハビリテーション
沿岸都市の再開発区で、無人の建設3Dプリンターが突如にして稼働を開始した。夜ごと低くうねるような振動音が響き、その翌朝には、見慣れぬ街並みが路地の奥に現れている。古い木造商店街のようなそれは、防災と環境保護の観点から木材の使用が全面禁止されて久しい時代には、本来あり得ない光景だった。行政は『自動補修プログラムの誤作動』と説明したが、都市工事に携わる者たちの間には、別の名が囁かれた。かつて中断された都市の自己修復計画AR計画(Autonomous Rehabilitation)の再起動である、と。
主人公の青年は、再開発区で働くゼネコン所長の父と二人暮らしだ。十数年前に亡くなった母は、AR計画の立ち上げに関わった大建築家だった。しかし、彼女の唱えた『自らの歴史を思い出す建築』という思想は、資源と効率を重視する国家方針と対立し、計画から外された。父はその理念を遠ざけ、以後、家で母の話題が語られることはなかった。
無人建築は、渦を巻くように拡大し始める。異なる時代の街区を継ぎ接ぎのように重ね合わせ、かつて存在したはずの街並みを再現する。だが、結果できた街はどの記録にも存在しない。かつての都市計画図、観光雑誌、SNSの写真など。プリンターが参照するのは実際の歴史ではなく、『もっとも頻繁に参照された過去』で、無人建築は統計的に復元しているにすぎなかった。既視感だけが不気味に渦巻く光景を人々は「懐かしい」と口にしながら受け入れていく。
父親から聞かされたAR計画の話をきっかけに、青年は母の残したノートを手にとり、成長し続ける街の中心へと向かう。内部は、時代の異なる建築様式が層状に堆積した迷路だった。中心部には母が最後に設計した〈図書館〉の図面をもとに構築された巨大なデータ群があり、壁面には都市の歴史記録が絶え間なく投影され、欠損部分を補うように更新を続けていた。
図書館の奥に小さな部屋があった。壁も床も完全な木材の風合いを持っている。青年は思わず足を止める。それは彼が幼い頃に母と過ごした、記憶の底に沈んでいた部屋の再現だった。木の香りを知らない世代であるはずの自分が、その空間に不思議な懐かしさを覚えた瞬間、青年は理解する。
AR計画とは、都市がかつて存在したかもしれない姿を、統計的な記憶の集積から無限に再構築する装置なのだ。
都市は人々の記録と欲望が生んだ類型的な過去を参照し続け、膨張するように増殖してきたのだ。そこには母の思想の残滓が、微かに息づいていた。
やがて無人建築の成長は止まり、街は深い静寂に包まれた。住民たちは安全のために街を離れ、父も避難していった。青年はしばらく廃墟となったこの街にとどまることにした。人工素材が再現した木の壁に手を触れながら彼は思う。
この街は誰の記憶にもない。だが、すべての時代の断片を宿す最も人間的な構造なのかもしれないと。
文字数:1200
内容に関するアピール
建設用3Dプリンター技術が進んだ未来を思い描きました。現在も社会実装される段階ではありますが、いまのところ階段やベンチなどの小さくて単純な構造を造るのに使われるのが一般的です。本作ではさらに大きな構造物の構築が可能となった世界を想定しており、土工・鉄筋、型枠の組立て・コンクリート打設・養生・仕上げの各工程をプリンターが役割分担するように建設します。リアリティは低いですが、うまくはったりができたらなと。
アイデアとしてはル・コルビュジエの「無限発展の美術館」から着想を得ています。彼の構想では渦巻き状に増築できる建物を思い描いており、実現例として国立西洋美術館が代表です。本作では建築や街が3次元方向にどんどん膨張するようなイメージです。
巨大建築が登場するSFといえば柞刈湯葉「横浜駅SF」やレナルズ「反転領域」等の先行作品も多いので改めて読みどう差別化できるかしっかり考えたいです。
文字数:395
オートノモス・リハビリテーション
1
僕が住む街に巨大な構造物が立ち上がってから、四ヶ月が過ぎていた。
再開発の工事現場で、それはいまも拡張を続けている。横方向にも、縦方向にも。まるで空間の余白を測るかのように、少しずつ形を変えながら。
その様子を路上に立ち止まって観察する人もいれば、視界に入ってもいっさい気にしない人もいた。最初の頃にあった騒ぎが薄れ、建物はいつのまにか、そこにあるものとして受け入れられつつあった。そしていつのまにか、数キロ平方メートルの広がりが生まれ、一番高いところは四〇メートルにもなった。
これが計画された形ではないことだけは、誰もが知っている。
工事のために設置されていた建設用三次元プリンターが、ある日を境に指示を受け付けなくなったらしい。『暴走』という言葉が使われることもあるが、実際に何が起きているのかを、はっきり言える人間はいない。すくなくとも、何らかの建物がだしぬけに、そしてめきめきとしたスピード感で造られているのは確かなことだった。建物というものは何らかの使い道があるのはさもありなん。でも、それが何のためのものなのかを、考える人はほとんどいなかった。
僕はある日、再開発区のほうへ足を向けることにした。研究室の課題で近くまできたから、そのついでに。特別な理由があったわけではない。ただしっかりと眺めたことがなかったから、きっと興味本位によって駆動されたものだと思う。
構造物は周辺に色濃い影をたたえていた。ばっさりと切り取られたように一足早い夜が訪れたようにも錯覚してしまう。現場周辺にはフェンスは張られていたけど、だからといって完全に閉じられているわけではなかった。仮設の通路が設けられ、作業員でなくても通れるようになっている。飛来物を防護する屋根が付いているから通りすがるぶんには構わない、ということなんだろう。注意書きの看板はあるものの、砂やモルタルがこびりついていてうまく読み取ることができなかった。空気には、樹脂と湿ったコンクリートが混じったような匂いがあった。耳をすますと、プリンターの働く様子が、ビープ音となって聞こえてくるけど、それがどこから鳴っているのかは判然としない。周囲では、街の表情がわずかに揺れて見えることがあった。舗装の色や、歩道に設置された案内板の書体、古い商店の看板の配色。どれもが統一されないまま並んでいるのに、不思議とちぐはぐには思えなかった。プリンターに記録されている設計データの影響だと言われれば、そうなのかもしれない。だが、工事が始まる以前からあったはずのものまでが、いつのまにか更新されているようにも見えた。街が、何かを思い出そうとしている。そんな考えも頭をよぎったのだが、根拠はなかった。
ここまで来ると全容は把握できない。壮大な塊は、遠景からは一棟の建物に見えるが、近くになってみると街のようにも思えた。壁らしき面が連続していると思えば、突然、玄関のような窪みが現れる。だが、その扉がどこへ続いているのかは、外から判断できない。視線を滑らせていると、景色ががらっと変わり、商店街のアーケードのような装飾がこらされた庇、レンガ風の舗装やガラスの嵌められていないショーウインドウがみえる。そのひとつ隣には昭和レトロらしい焦茶色の外観の建物があって、いかにもなフォントで『パティスリー』と書かれた看板が掲げられていた。少し離れた場所ではバス停小屋のようなものが鎮座していて、支柱には電気自動車用の充電口が取り付けられている。待合椅子の木製の──実際にはモルタルか鉄筋コンクリート製かもしれないが、座面からはケーブルが伸びていた。
どれも単体で見れば、どこかで見たことがある気がする。けれども、それらが同じ場所に並んでいる理由は、うまく説明できなかった。歩くたびに断片が少しずつ積み重なっていく感覚ばかりが僕を支配する。初めて来たはずの場所なのに。
外壁の一部には、案内板のようなものも取り付けられていた。矢印だけがいくつも並び、行き先の名称は書かれていない。塗り直された跡はあるが、文字が消されたのか、最初からなかったのかは答えのない予想にすぎない。いずれも正解かもしれないし、不正解かもしれない。
いずれにせよ、そこを起点に人が移動することが、最初から想定されているのは確かだった。だが、どこへ向かえばいいのかは示されていない。足を止めて眺めていると、自分がここに立っている理由まで、少し曖昧になってくる気がした。
家に帰ったのは、夜七時を少し回った頃だった。
玄関を開けると、台所のほうから油の弾く音がした。父さんがすでに帰宅していて、夕食の支度をしているらしい。
リビングのテレビはつけっぱなしになっていて、NHKのニュースが流れていた。ちょうど再開発区の話題が映り、画面の端に、日中見上げた巨大な構造物の俯瞰映像が広がる。キャスターはそれを、耳慣れない固有名で呼んでいたが、それは便宜的な呼び名だった。近況報告だけ伝えてそれ以上の説明に入ることはなく別の報道へ切り替わった。
おかえり、風呂沸いているから、とリビングに顔を出した僕に父さんが声をかけたのは、彼のマイルドな潔癖症が裏に潜んでいるからだ。あまり気にならなかったけど、家に入った途端に汗臭さを自覚した僕は、その言葉に甘えることにした。
風呂に入った後に食卓についた。夕飯はすでに支度しおえていて、父さんは対面する席に座しながらグラスビールに口をつけていた。配膳されたご飯と味噌汁は湯気がたっていて、中央にメンチカツとキャベツが盛られた皿がある。本社勤務になってからの父さんは少しずつ凝った料理を作るようになった。
タケル──食べ始めたから程なくして父さんは訊ねる。「今日はどうだった」
「そんな大したことはないよ。研究室の課題で、フィールドワークに出てた」
「そうか」
箸を動かしながら、僕はさっきテレビに映っていた映像のことを思い出した。
「そういえば、あそこ。父さんの現場だったよね」
父さんは一拍おいてから頷いた。
「まあな」
「実は近くまできたから寄ってみたけど、なんか変な建物だったよ」
僕が何気なく言うと、父さんは黙り込んだ。グラスにビールを注ぎ直し、それからテレビの音量を少し下げる。しばらくしてぽつりと言った。
「あまり近づきすぎるなよ。観光スポットじゃないんだ」
「──そうだね、いつ崩れるか分からないからね」
それ以上、この話題が続くこともなかった。言うべきものが見つからなかったから。
僕はそれ以降、あの構造物についてよく考えるようになった。いや考える、というより、思考の端に残り続けている、と言った方がより正しい。思い出そうとしなくても、何かの拍子になると勝手に浮かんでくる。卒論のテーマを決めようとする時期に差し掛かったいまではなんだか厄介な現象だ。
講義の空き時間になったから研究室へ顔を出すことにした。建築学科の研究棟の入ってすぐの共有スペースには、ちょうど卒業制作の準備をする設計分野の先輩たちが模型を取り囲みながら議論していた。その反対側は、研究資料や業界雑誌が無造作に収納された本棚が壁に埋め込まれている。一面が本に埋まっている見栄えの良さからなのか、学科の教授たちが映る宣材写真は決まってここを背景にしていた。
棚を何気なく眺めてみると、見覚えのある名前を見つけた。
母さんの名前だ。
それは都市修復計画に関する特集号で、十年以上前のものだった。母さんもこの記事に寄稿していた。ページめくると見慣れた筆致の文章が続いている。
『街は、人が暮らし続けるための器である。そして修復とは、単に過去を保存することではなく、そこに住む人々の感覚を回復させることに他ならない』
それは、どこかで何度も聞いた言葉だった。家で、食卓の向こう側から。あるいは資料を読みながら独り言のように呟いていた声として。その時は幼くて、ちんぷんかんぷんな呪文のように思えたけど、今は多少なりとも意味がわかるようになった。<オートノモス・リハビリテーション>。ざっとそういった用語で括られていた。母さんの文体は穏やかで、過剰な理想論には見えなかった。むしろ、中庸で、現実的ですらある。再開発によって失われるものを嘆くのではなく、どうすれば人が新しい街を受け入れ、いかにして街が人を受け止め続けられるかを、淡々と述べている。
奥付の発行日を見てると、僕は目を見開いた。その日は母さんの命日だった。癌によって痩せ細った身体から力を手放した日。つまり闘病中に書き上げた原稿に違いない。それもほとんど最後の方。それでもこの特集をまたとない機会だと捉えたに違いなかった。
僕はまた、あの構造物のことについて考えた。今度はもっと実態を伴ったものとして──つまり、母さんの言葉や記録と結びつく形で。
あれは、母さんが言っていた『回復』の形ではないか──そんな考えが、自然に浮かんできた。
父さんの書斎は、相変わらず物が多かった。壁際に立てかけられた図面の筒と、机の上に積まれた業界誌。画面を暗くしたままのモニタだけが、こちらを向いている。
「都市の保全技術の歴史的変遷についての研究、か」父さんは、書面を読み上げてからゆっくりと僕へ視線を移した。「いいじゃないか。今はすっかり保全の時代だ。お前たちの世代で評価しても早すぎることはない」
その言い方にどこか投げやりな印象を僕は抱いた。反対されているわけではない。そもそものこと、すでに教授に受理されている。このテーマで構わない、と。お伺いを立てようとしたわけではなく、単なる報告として話を切り出したのだ。だから父さんが今更なにを言ったってかわりやしないし、言ったところで学術的な責任を負う立場でもない。
「まあ、そんな感じの研究をしたいよ、ってこと。だから、もしかして母さんがやっていたことについても訊くことがあるかもしれないから、その時になった教えて欲しいんだけど」
「いや、語ることはない」
きっぱりと言われた。
「どうして? 知らないというのはないでしょう」
追求しようとしても父さんはがんとして譲らない。ゼネコンの所長までやっている人が、設計者である妻の取り組みに興味を持たないことはないだろう。もしかしてさっきから続いている違和感の正体がここにある気がした。
「資料で読み取れない情報もあるわけだよね。母さんが修復計画に関わっていたのはもうわかっているんだ。適当にソートをかけても簡単にひっかかる──それくらい有名な人なんだね」
「たしかに技術屋としては一流だ。だが、あいつには悪いが、結果を残したかどうかは言い難い」
机の上の示方書に、父さんの指先が触れた。
「オートノモス・リハビリテーションも?」
「昔の流行り言葉だ。思想として定着するまえに、条件が変わったんだ」
「条件が変わった?」
父さんは答えなかった。奇妙な沈黙だった。否定や保留でもなさそうな、根拠のない沈黙。
書斎から出た後も僕は父さんの言葉を頭の中で反芻した。
条件が変わった。それは、否定できない。技術というのは未知を手懐けることで、どこかで形を変える。実戦のたびに、思っていた輪郭から少しずつずれていく。その意味で思想は可塑的なものだ。
もし母さんの思想が完膚なきまで間違っていたのなら、父さんはもっとはっきりそう言ったはずだ。卓越した技術力を有していたことも、結果を残せなかったという評価も、どちらも否定しなかった。ただ、続かなかった理由を、時間の側に置いただけだった。
もし、あの頃には足りていなかった条件が、いま揃いつつあるのだとしたら。たとえば計測技術、都市データ、そして自律的に建築を更新し続ける仕組みとか。それこそ母さんの言っていた『回復』とどこか似ていた。でも似ているからこそ、まだ言い切れない。
そう考えてしまえば、あの構造物は、急に別のものに見えてきた。暴走した建設機械が偶然生み出した異物ではない。
遅れて立ち上がった、ひとつの試行のように。
2
「再開発区の構造物の件、か」
西浜教授はそう言いつつPCの画面から僕の方へ視線を移した。それから少し考え込むように椅子の背にもたれる。指摘はしないしすることはないけど、彼の領分は整っているとは言い難かった。デスクには書類や未開封の郵便物が並び、壁には地図がピンで留められている。どれも使われている最中のようで、放置されているわけではなさそうだ。
「藤岡、それはフィールドワークに向かいたい、ということでいいのか」
「行きたい──のはそうですが、行っておいた方がいいかどうか、です」
言いながら、自分でも曖昧な言い回しだと思った。卒論のテーマに絡むかどうかも、まだはっきりしていない。ただ、現場を一度も見ずにすませていいものなのか、それだけが引っかかっていた。
「念のため訊ねるが、藤岡は<第九更新区>のことを指しているんだな」
それは行政文書上の呼称だった。ニュースやネットでは、もう少し砕けた名前で呼ばれているのを見かけるが教授はそちらを使わなかった。
「知らないと思うが、実は調査団は結成されているんだ。官民学で連携して、安全確認と記録を残している」
思ったより話が進んでいるようだった。
「騒ぎになっている割には、現場は落ち着いているという報告がされているようだ。少なくとも、今のところは。だからこそ、余計に扱いが難しい」
教授はそう言って、机の上の書類をめくった。
「運が回ってきた。次の調査には、うちが同行させてもらうことになった。自分の他に、院生を数名。まあ希望をしてくれるなら学部生もできるだろう──しかし、藤岡はどうして更新区のことをリサーチしたいのか」
「母親が、もしかして関わっているかもしれないんです。三次元プリンターによるインフラの修復構想について──」
たどたどしくとも、僕は根拠を説明してみた。結局、父さんは口を閉ざしたままだった。自分なりに歴史を調べたなかで母さんの業績はどうも重要なところを占めたらしい。付け焼き刃の生半可な知識をもって教授に相対すること以上に肝が冷えることに違いない。
「あぁ、そうか。藤岡さん、なるほど──」教授はひと呼吸おいてから、「いいだろう。そこまで興味があって調べてこられたなら充分だ。調査に加わることを許可する。ただし、君のお母様が関わったことだからって、使命感は持たないこと。それは重荷になる。あまり言いふらさないこと。好奇心だけをもって望みなさい」
すこしだけ、気が楽になった。調査に参加する、ということより見せてもらう。そういう距離感の方が、今の自分にはあっている気がした。
お礼を伝えたことはそこそこに、教授は付け加えるように言った。
「構造物の中で何を感じても、すぐに答えを出そうとするな。問い続けるんだ。ああいう場所はこちらの理解の仕方を試してくる」
その言葉の意味を、僕はまだ十分に掴めていなかった。
調査は次の週末に決まった。教授からある程度の情報をもらったので、それを頭に叩き込んだ。調査当日は、研究棟の前に集合した。西浜教授と院生が数名、それから僕。学部から唯一の参加らしく余計にイレギュラーな存在に思えてしまう。簡単な確認を済ませて、大学の車に乗り込む。誰も特別な表情はしていなかった。遠足というほど浮ついてもいないし、緊張している様子もない。ただ、いつものフィールドワークより落ち着いていた。
車内では更新区に関する雑談めいた話が交わされた。最近は、世間でも呼称が固まってきているらしい。民俗学に素養のある先輩がインターネットや雑誌などメディアによっては呼び名が変わっていることに触れつつ、その多くが陰謀論めいた荒唐無稽なものに依拠しているのかもしれない、と独自の分析を繰り広げていた。そのことについて意見が割れたこと以外にはさしていざこざは起こらなかった。
現場が近づくにつれて、窓の外の風景が変わっていく。区画の輪郭が以前よりも曖昧になっている。設置されていた鋼製フェンスや防音壁がひしゃげていて、構造物に取り込まれていた。遠目に見ても、あきらかに大きくなっている。前回来たのはテーマを決める前で研究室に所属したばかりのころ。だから半年ぶりのことだった。ひとりでに肥大化する様は生物にも例えられるが、衰退を目の当たりにしていない以上はどの生物に適用できるのかはわからない。
河川敷に設けられた駐車場で降りることとなった。そこは騒然としているわけではない。規制線と警備員、それから少し離れて立つ人影。どれも想像としていたより整然としている。
かるくブリーフィングと注意事項を受けてから、現場に入る。すでに一〇〇メートルに達した構造物はもしかすると地盤沈下によって瓦解する恐れもあるらしい。細心の注意を。と釘をさされた。
規制線をくぐる直前、僕はなにか奇妙な香りを感じた。どう例えたらわからないけど、馴染みのあった香りだった。
幾何構造が鬱蒼としていると思うと、視界がひらけた。
最初に広がっていたのは、まるで駅前の広場のような空間だった。ロータリーがあって、その中央に噴水がある。人が集まることを前提にした空間の取り合いがあり、こじんまりとした落ち着きがあった。舗装は新しく、白線や案内表示らしきものもあるが、まっさらだったり見当違いのものが書いてある。少なくとも、迷宮の入口には見えなかった。
支柱や一部には、蛍光ピンクのリボンが結ばれている。調査団が進入経路を示すために設置したものだと説明を受けていた。視認性は高く、これを辿れば戻ることも難しくはない。そう思えた。
僕は西浜教授と院生たちの少し後ろを歩いていた。広場を抜け、通路のような場所に入る。形は定まらないが、動線としては素直だった。無茶な判断をした覚えはない。ただ、前に進んでいた。
気づいたときには、周囲に人の気配が消えていた。
声をかけたが、遠くの方に反響するだけで誰も反応することがなかった。無線に呼びかけると、ノイズの底から誰かの声が帰ってくるが、その声がいまいち識別できなかった。
蛍光ピンクのリボンを探すと、すぐに見つかった。来た道を戻ろうと、結び目を目印に歩いた。だが、しばらく歩いても誰にも出会わない。やがて最初の広場に戻ったけど、さっきの空間とは微妙に違って見えた。
逡巡した。進むか、待つか。ここで立ち止まっていても仕方がない。僕は諦めて、また歩くことにした。さっきよりも先に進む。
通路を抜けた先に、静かな部屋が見えた。
どうやらそこは図書館のようだった。壁一面に棚があり、机と椅子が規則正しく並んでいる。だが、本は置かれていない。代わりに、無垢の木材がふんだんに使われているのがわかった。節の残る板、加工しきれなかった角材。木材は、もう随分と前に使われなくなった建材だった。
空気がやわらかい。
鼻をくすぐる匂いがあった。新しい木の香りだった。規制線を越える直前に感じた香りは、これだったのだと、遅れて理解した。理由はわからないが、胸の奥が落ち着いた。僕はこの香りを初めてかいだはずなのに。いつのまにか涙が溢れ、止める術を失っていた。
ここで何かを見つけたわけではない。ただ、その場にいること自体が、ひとつの行為のように思えた。
しばらくして、無線からひとりの先輩の声が聞こえ、僕は合流する段取りをとった。あの広場でいいだろうと。
外に出てから、僕たちは互いの状況について報告をしあった。どうやら意図しない離散だったようで、みんな単独行動を強いられていた。その時の光景のことを、院生たちは口々に感想を述べ始めた。
小さい頃に通ってた公園に似てた。弟が生まれた病院のロビーを思い出した。合唱コンクールの市民会館みたいなところにいた。
僕たちはみんな一直線に進んでいたはずなのに。たどり着いたところはどれも一致していない。その事実をいまいち飲み込むことはできなかった。
西浜教授は、少し考えるように黙ってから言った。
「君らはその場所にいたときどう思った、どう感じた」
僕も含めて、順々に回答する。概して平静とした気分になったらしいと。教授はまた考え込んだ。
「君たちの──まあ僕もそうだが。情動の揺れの方向が一様になっているみたいだ」
そんな仮説を僕はそのまま受け取った。
調査からしばらくして再開発区の構造物について、一部が限定的に公開されることになった。
初期に形成された区画は、構造的にも法令上の基準を満たしていると判断されたらしい。安全確保のために動線を限定し、立ち入り可能な範囲を区切る。あくまで暫定的な措置だと、行政は繰り返し強調していた。
公開直前になって、メディア向けに編集された映像が配信された。
あのとき駅前の広場のような空間、使われなくなった素材を再現した内装、柔らかい光。どれも、危険性よりも技術の尊さや穏やかさな雰囲気を前面に押し出した構成だった。
その反応に対して、コメント欄の反応は意外と好意的だった。懐かしい、と。
具体的な記憶を挙げる人もいた。内容はまちまちだったけど否定的な反応は少ない。行政はその反応に、少なからず驚いているみたいだった。想定していたのは、異物に対する拒否や不安だったから。
西浜教授は、報告会のあとでぽつりと言った。僕を教授室に呼びつけた直後のことだった。
「人は、理由がなくても安心することがあるらしい」
その言葉が、妙に引っかかった。
「先生、たしかに構造自体は安全だと思います。でも安心と安全は違うものです。世間の反応はどうしてこのようなものになってしまったのでしょうか」
教授は一瞬だけ窓の外を見、それから僕に向き直した。
「それこそが<オートノモス・リハビリテーション計画>の肝要な部分だ」
「オートノモス──もしかして母親の……」
「正確には君のお母様が所属していた委員会が打ち立てた計画だ。回復の建築。つまり人々の記憶や生活史をもとに都市のありようを再構築する、というものだ。自律駆動という言葉にあるように、それはひとりでに考え、考えのとおりに変容するんだ」
「しかし、急に人が受け入れているのは疑問があります。最初の頃はむしろ畏怖というか、恐怖というか。そういったものが風潮としてあったじゃないですか」
そうだな、と教授は眼鏡を外しながら言った。
「キーワードは、懐かしい、だ。それも類型的郷愁とでもいって良いだろうが。しかしあれはでっち上げられた風景。統計によって、それらしい懐かしさに」
教授は淡々と言う。類型的郷愁。
「あの風景は本来ない景色だ。日本全国探してもあのロータリーはないだろう。たとえば、大学の景観データベースと照合しても〇・〇一から〇・一パーセント程度の適合率だ。つまり少しずつ似ている要素がロータリーにはある。藤岡が見たという図書館という施設もよく思い出してほしい」
地元はここで、幼少期をすごしたところは区画整理後の街並みだ。そのときにはすでに木材は使うことができなくて、見た目も手触りも香りも木材によせた精巧な代替素材によって内装はできていた。
「間違いなく、木の素材だと感じました。しかし実際には限りなくそっくりなもの、だと言うのですか」
教授は頷いた。
「そう言った方がいいだろう。認識によって記憶が補完されるんだ」
僕は、内部で感じた木の香りを思い出していた。
落ち着き。懐かしさ。だが、それは本当に「回復」だったのだろうか。
そのとき、父さんの言葉が頭をよぎった。観光スポットじゃない。
そして、母さんの論文。
やはり、そういうことなのだろう。
プリンターにインストールされていたのは、オートノモス・リハビリテーションという思想だった。あるいは母さんの願い。とにかくそういったものが意図せず――あるいは意図的に利用された。そう考えると、すべてが筋の通ったものに見えた。回復の建築とは、人の記憶に寄り添うための構造物——そう理解することもできた。
その理解によって誰かと争うことはなくなった。信じて疑わないことで、胸がすく思いがした。理由がある安心は、こんなに簡単に人をほどくのかと思った。
3
人々がなんとなしに構造物の存在を受け入れていく一方で、プリンターの建設機構は稼働を続けていた。
玄武岩繊維が敷設され、早強モルタルが積み重なり、有機化合物製造による意匠が形成されていく。それらの工程は、停止することなく繰り返されている。資材の枯渇による停止が対策の最後の砦だと報告会でも挙げられていたが、その見通しは甘かった。
構造物はとうとう工区を越えて広がることになった。ただし変化は、破壊という形では現れなかった。既存の建物が崩されることはなく、道路が寸断されることもない。ただ、街路の端や建物の隙間に、いつの間にか新しい構造が接続されていく。舗装の継ぎ目に沿って壁が伸び、使われていなかった裏道に、奥行きのある空間が差し込まれる。気づけば、そこは以前からそうだったかのように街の一部になっていた。
行政はこれを拡張期と呼んだ。成長フローに位置が置かれたイメージだった。
再開発区の境界線は引き直され、立ち入り規制の範囲も外側へ更新される。住人への避難は、当初は推奨という形で告知され、やがて勧告へと切り替えられた。用地買収も速やかに完了した。完全に地図上の色分けが変わるだけの、事務的な手続きだった。だが、画面に表示された俯瞰図を見ると、再開発区はもはや閉じた区画ではなく、周囲の市街地と連続している。更新は一区画に留まらず、隣接する街並みへと波及しているように見えた。
反応は一気に広がった。
限定公開のときには好意的だった論調も突如としてゆらいだ。構造物が街に触れた瞬間から、受け止め方が変わったのだ。愛称までつけられた構造物の呼び名は蔑称になり、コメンテーターの語調は不必要なほど荒く、それに倣うように世間の声も呼応する。
特にインターネットのコミュニティでは、いくつかの言葉が再び使われ始めていた。いずれも良い意味ではない。かつて棄却された自律的都市修繕計画の名称もそのひとつだった。公式には否定されたはずの構想が、あたかも裏で進行していたかのように語られる。それこそ荒唐無稽な情報だ。あるのは、過去の資料と、断片的な映像、それに憶測だけだった。
それでも、人々は納得しているように見えた。まるで院生の先輩が言っていたような陰謀論の火種が再燃していた。
理由が必要なのではなく、説明が欲しいだけなのだと、僕は思った。その輪郭の中に、『藤岡』という名前を見つけたとき、胸の奥がひやりとした。渦中の人物の関係者。母の思想。父の立場。そうした要素が、勝手に一本の線として汲み取られてしまうように。
だが、僕自身はいまひとつ混乱していなかった。
回復の建築という理解は、まだ崩れていなかったのだ。
気になっていたのは、ただひとつだけ。
なぜ、プリンターは止まらないのか。
自宅が避難勧告の対象地域に選ばれたのは、間もなくのこと。かなり早い段階だったと思う。あてがわれた高層マンションを新居にして引っ越すらしい。実質的な立ち退きだ。
避難勧告が出た日の夜、父さんが部屋に入ってきた。声は落ち着いていたが、要件は短かった。
「タケル、荷物をまとめろ。明日の朝に新居に向かう」
理由を尋ねる前に、次の言葉が続いた。
「街で行方がわからなくなっている人が出ているらしい。数は多くないが、増えている」
ニュースでは聞いていなかった話だった。
だが、噂なら耳にしていた。避難の途中で戻らなかった人がいる。構造物の中に住み始めているらしい、という話。冗談めかして語られていたが、完全な作り話とも言い切れなかった。
「警察沙汰になる前に動く。いいな」
父はそう言って、電話を切った。忠告というより、通達に近い調子だった。そのとき僕は、構造物が人を取り込んでいるという言い方を、まだ大げさだと思っていた。
まとめた荷物を玄関まで下ろして、リビングにいた父さんと向かい合った。夕食のはずだったが食パン二枚とスクランブルエッグだけのシンプルな構成だ。テレビは消されていて、部屋は妙に静かだった。昼間に流れていた速報の音が、嘘のように遠い。
「構造物に行くつもりだろ」
父は、確認するような口調ではなかった。
すでにわかっている、という言い方だった。
「一度、見ておきたいだけだよ」
自分でも、苦しい言い訳だと思った。だが父さんは、すぐには否定しなかった。ただ、やめておけ、という短い言葉を残した。
「理由は?」
問い返すと、しばらく黙った。考えているというより、どこまで話すべきかを選んでいる様子だった。
「あれは、人を使う」
それだけを言った。
「どういう意味?」
「測るためだ」
父さんは席を外すと、書斎にあったのだろう再開発区の全体図を机の上に広げた。図面を指で押さえながら、そこに線があるかのような仕草をした。
「元々は、都市開発の統計を取るための仕組みだった。人の流れ、滞留、視線、音、呼吸、触覚。そういうものを拾うための装置だ。基本設計の段階で建物に組み込むのは決定されていた」
「それが、どうして暴走を招いたの……」
「測定がうまくいったからだ」
父は、感情を込めずに言った。
「精度が出た。だから、もっと欲しがった──欲しがった、というより、最適化の先にそれしかないが残ったんだ。人がいると、狙った因果が導かれる。人がいなくなると、ばらつく。だったら留めてしまえばいい。目に見えない傷を癒すための幻想を、オートノモス・リハビリテーションは建築とインフラとその総体としての街に植え付けるのだ」
僕は、すぐに言葉を返せなかった。理屈としては、筋が通っているように聞こえたからだ。
「懐かしさも、そのため?」
父は頷かなかったが、否定もしなかった。
「居心地がよければ、人は動かない。閉じる理由がなくなる」
「でも、それは回復なんだろ。人にとって──」
言いかけて、止まった。父さんの視線が、こちらを正面から捉えたからだ。
「主体性を奪ってでもか?」
その言葉は、責める調子ではなかった。ただ、問いかけるように。諭すように。
「設計としては、そういう選択もあり得る。だが、技術は作るのではなく作らされるものにもなる。その自覚なしに出来上がったあれを、俺は建築だとは思っていない」
「じゃあ、何だと思ってるんだよ」
父さんは、少しだけ息を吐いた。
「なんでもないものだ。居場所を装った装置にすぎない。人が住むための場所ではないんだ」
その一語が、部屋に残った。
「だから近づくな。近づくならば、使われる前に離れろ」
父さんはそう言って立ち上がった。話は、それで終わりだった。僕は、納得していなかった。だが、その言い方。父さんが何かを恐れていることだけは、はっきりと伝わってきた。
結局、僕は構造物に向かうことに決めた。
闇に屹立する巨大な塊を、僕は目指した。住宅街のまばらな街灯のなかひたすら歩いた。
避難勧告が出てから数時間が経っていたが、街はまだ完全には空になっていなかった。引っ越しの途中のように明かりの点いた家もあれば、すでに鍵を閉め切ったままの家もある。人の気配は薄いが、生活の痕跡はそこかしこに残っていた。
構造物は、以前よりも街に近づいているように見えた。正確には、距離が縮んだのではなく、街の輪郭のほうが曖昧になっていたからだ。歩いているあいだ、構造物を直接見ることはほとんどなかった。建物の影が順々にある増えていく。そのどれが元からあったものなのか、途中から現れたものなのかは、すぐに区別がつかなくなっていた。
以前ははっきりしていたはずの再開発区との境目も、いまは見当たらない。フェンスや警告表示があった場所を通り過ぎた気がするが、確信はなかった。そして確かめるすべもない。街灯の配置や道路の幅は変わっていないのに、歩いている距離の感覚だけがずれていく。
気づいたときには、住宅街の景色は背後に遠ざかっていた。そして空気の密度が変わったのがはっきりとわかった。足音が、いつの間にか違う響きを帯びていた。舗装の感触は変わっていないはずなのに、音だけが少し奥へ沈む。自分がどこを歩いているのか、即座には判断できなくなった。もうすでに、ここは構造物の領域だったのだ。
さまざまな時代がコラージュされたような通路を抜け、僕はやがて街と地続きの広場に到達した。それはショッピングモールによくあるような広場で、商店街とはまた別の立体的に店舗が配された景観だった。てっきり前回入ったロータリーだと思っていたから予想と違うことに僕は驚いた。
さらに歩くと、前方に、吹き抜けめいた空間が現れた。駅前や公共施設の前庭を連想させる配置だが、案内板も出入口も見当たらない。人の流れだけが、設計として残されているように見えた。
広場の縁には、蛍光ピンクのリボンがところどころ結ばれていた。つまりいちど調査団が内部に立ち入ったということになる。薄暗い中でも視認性の高い色で、床や柱に無造作に括りつけられている。これを辿れば、外に戻ることも難しくはないはずだった。
僕は無意識のうちに、そのリボンを視界の端で追いながら歩いていた。進行方向に迷いはなく、むしろ整然とした導線が用意されているように感じられた。誰かと並んで歩いている感覚さえあったが、振り返っても人影は見えない。
しばらくして足を止め、来た道を確かめようとしたとき、リボンが見当たらないことに気づいた。結び目がほどけた様子もなく、取り外された形跡もない。ただ、最初からそこになかったかのように、視界から消えていた。
戻ろうと思えば戻れる。そう判断したはずなのに、僕はその場で引き返さなかった。
そのまま歩き続けていると、空気の質がまた少し変わった。湿り気を含んだ、どこか甘い匂いが混じる。しばらくして、それが木材の匂いだと気づいた。いや、思い出したと言った方が良い。記憶の中で、いつの間にか形を変えていた香りだ。それを自覚すればするほど、これが嘘だとは信じられなかった。
匂いは次第に空間そのものに溶け込んでいった。通路の壁や天井に、加工されていない木の面が増えていく。触れれば跡が残りそうな質感で、建材というより、置かれているという印象に近い。
気づくと、天井が高くなっていた。音は吸われ、足音だけが必要以上に残る。照明は均一だが、どこか落ち着かない。明るさが足りないわけではないのに、視線の置きどころが定まらなかった。
そこには、本棚が並んでいた。数は多くない。背表紙もまちまちで、体系だった配置には見えなかった。読むために集められたというより、集まってしまったものが置かれているようだった。僕はそこで、ここが図書館なのだと理解した。やっぱり読書をするための場所だとは、どうしても思えなかった。詳しく見ると棚に本はなく、そのかわり奥に文字が刻まれているばかりだったから。
本棚が作る通路を進んでいると、わずかな物音がした。
立ち止まって耳を澄ますと、一定の間隔で、小さな動きが続いているのがわかった。何かを並べ替えているようでもあり、整えているようでもある。作業音というには控えめで、気配だけが先に伝わってくる。
視線を向けると、本棚の向こうに、人影があった。
腰の高さほどの台に手を置き、背を丸めている。こちらに気づいた様子はない。声をかけるべきか迷っているうちに、その人は自分でこちらを振り向いた。
「探しものですか」
落ち着いた声だった。年齢ははっきりしない。作業着とも私服ともつかない格好で、名札のようなものはつけていない。
「いえ……」
そう答えてから、自分が何をしに来たのか、うまく言葉にできないことに気づいた。
「初めて来た人は、だいたいそう言います」
その人は軽く頷き、本棚に戻った。
「ここ、図書館なんですか。僕はそう思っているんですが」
問いかけると、その人は少し考える間を置いた。
「そう呼ばれることが多いですね。でも、本を読む人に来る人はあまりいません。なんせ本がないのですから」
「じゃあ……」
言葉を探していると、その人は先に続けた。
「座る人はいます。長くいる人も。帰る人もいます。きっとそれ自体がケアになるのでしょう」
それだけを言って、また作業に戻った。説明はなかったが、拒まれている感じもしなかった。
僕はその場に立ったまま、ここに人がいるという事実だけを、ゆっくりと受け取っていた。
その人が手を止めたのは、僕の背後で小さく何かが鳴ったからだった。金属ではない。木が触れ合う音だ。振り返ると、棚の陰からもう一人、姿を現した。僕より少し年上に見える。頬はやせているが、目は落ち着いていた。
「藤岡君、だよね」
名前を呼ばれて、息が詰まった。面識はなかったはずなのに、声の調子だけが妙に覚えがある。大学で一度、質問を投げた院生の声。掲示板で見かけた名。行方不明者の一覧に載っていた、どれか。僕の中で散らばっていた断片が、一つの人間に収束した。
「ここにいるんですか」
僕が言うと、彼は頷いた。
「いる、っていうか──戻らなかった。戻る理由が、途中で消えたんだと思う」
図書館の人が本棚の背を揃えながら、淡々と言った。
「ここは、回復の建築です。癒す、というより——閉じます。人が、閉じたがっているときに」
閉じる。父の言葉がよぎった。囲い。装置。だが目の前の二人は、囲われているようには見えない。逃げようと思えば逃げられる。その事実が、逆に僕を落ち着かせなかった。
「どうして、人が必要なんですか」
僕の問いに、彼は少し笑った。
「見極めるため、って言えばそれっぽい。でもたぶん、それは手段なんだ。ここは、人の戻り方を選別してる。帰れるように見せて、帰らない選択が自然になるように」
図書館の人は首をかしげた。
「帰ることだけが回復じゃないでしょう。痛みが消えると、動機も消えます。動く理由の方が、あとから作られるものです」
その言葉は正しかった。正しすぎた。だからこそ、怖かった。回復が、ケアが、誰の自由も奪わずに、人を静かに留めてしまう。
ポケットで端末が震えた。西浜教授からの短いメッセージだった。
『更新区にいるんだな。親父さんから連絡がきた。無事なら返信はいらない。そのまま行け。君には確かめる資格がある。答えを急ぐな』
僕は画面を閉じた。避難は可能だろう。出口は、来た道の先にあるはずだった。街にはまだ、灯りも、人の生活も残っている。父さんもいる。それでも僕は、図書館の机に手を置いた。
「行くんだ」
彼が言った。
「行きます」
僕は立ち上がり、本棚の隙間の空間に自然と足が向かった。ここは滞留の入口だ。
振り返ると、二人は止めなかった。ただ、そこにいるだけだった。僕は手を口にやる。長年の癖のように。掌にはもう、木の匂いが移っていた。嘘みたいに具体的で、息を吸うたびに喉の奥へ貼りつく。その匂いのせいで、外の空気の匂いを思い出せなくなった。
文字数:15883