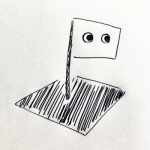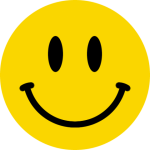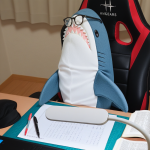ガラス張りの自動扉をくぐると、ロビーは無人だった。笹原遼は昨晩、どうしても終わらせなければならない作業に根をつめて取り組んでいており、そのせいで深夜まで職場に張り付いていた。出勤時間の調整し、今日はいつもよりも遅い時間に出社することにしていた。
社外の人物と打ち合わせをするために設置された椅子と机が数組のほかには何ひとつない空間に平坦で張りつめた静寂に包まれている。しかし、耳を澄ますと空気がわずかに震えていた。天井裏を走る冷却剤の循環音だ。彼はあたりを見渡しながら額からとめどなく流れる汗を拭った。
時計を確認し、ため息がもれた。ちょうど『起動前の祈祷』の時刻が迫っていた。
タイミングが悪すぎた。もう少し会社の周辺を歩いていればやりすごす手もあったが、今日は真夏のたけなわを思わせる陽気で、駅からそこそこの距離を歩いてきた身体には、もういちど外に出る気力など残っていなかった。
観念して顔をあげると、視線はちょうど壁面一体のモニターにぶつかった。会議室のホワイトボードをそのままもってきたような大きさのモニターは、ふだんはロゴ映像や自社技術を宣伝する映像が延々と流れされているが、この時間帯だけは社内向けのおしらせに切り替わっていた。
──おはようございます。演算開始まであと十五分です。定型的な文の単調なアニメーションが繰りかえされていた。
社屋の奥へ続く廊下、執務室に入る手前に量子コンピュータが収められている演算室がある。歩いていると、ちょうど上司や同僚たちが演算室に入っていく姿と鉢合わせした。
笹原は気づかれぬよう、その小さな人の波に加わった。廊下はじわじわと冷気を帯びはじめ、ガラス・パネルの向こうには、淡い光の脈動が見える。どこからか低いハム音が絶えず響き、鼻先をかすかなオゾン臭がかすめた。反響する足音が、硬い床にいくつも折りかさなっていく。笹原は流れに身をまかせるように、演算室の扉をくぐる。表情は熱心な社員を装いながらも、内心では倦怠的な感情が張りついている。
コンピュータの本体は一見すると巨大な長躯体の箱だ。筐体の表面は走る光の紋様は一定の間隔でゆらぎ、まるで呼吸をするように明滅を続けいている。上下から伸びる配管やらケーブルは根のように天井裏や床下へ潜り込んでいて、その内部には極低温の冷凍庫が何層にも量子ビットを抱えている。再現不能な問題が発生したとき、既存の計算領域では対処できない事象が発生したとき、はじめてこの装置の出番がやってくる。
二〇七五年。国家や自治体、大企業の多くが、意思決定の基盤を分散型自律組織へと移行していた。都市の予算配分もインフラ投資も、膨大な投票データとシミュレーションを量子演算にかけ、その結果がそのまま自動執行する仕組みが標準化している。もちろん、笹原たちが扱う量子コンピュータも、その膨大な意思決定の一部を担う端末にすぎないが、見る人によってはまるで神に向けるような眼差しをもつだろう。
だからこそ、量子コンピュータが起動される際には、必ず『祈祷の儀式』が執行される決まりとなっていた。
儀式は出社している全員の参加が義務づけられている。社員は機械から一定の間をとるように整列し、最前列には社長をはじめとする幹部人が並ぶ。広々とした演算室が狭くるしい。部屋の隅には白い祓棒を握った老年の祈祷師とその隣に笙の吹き手が待機している。普段は照明の落とされた室内は、いまは淡い金色の灯りに満たされている。いわゆる会社のしきたりらしい。
機械の前にはやたら重厚感のある茶褐色の机が置かれ、ミニチュアの社とサカキの葉をいけた白い花瓶がある両側にある。机上には他に飲み物やお菓子が盛られたお盆が並べられている。
秘書課の女性が遅れて入り、よろしくお願いします、と祈祷師に声をかけた。笙の音色が響き渡ると、祈祷師がゆっくりと立ち上がり、足裏で空気を撫でなでるような間合いで祭壇へと向かう。衣の擦れる音すら儀式を一部かのように錯覚するほどの仰々しい精緻さがある。祭壇の前に到達し、社を直視した祈祷師は祓棒を掲げ、ゆっくりとゆらす。古風な祝詞が静かに唱えられ、鈴や紙垂のかすかな揺れ音が静謐な空間に溶けこんだ。荘厳で抑制の効いたその儀式は、会社の日課ではなく、それとは超越した本物の祭礼のような厳かさを帯びていた。
社員たちは頭を垂れ、目を閉じている。けれども、笹原だけは、目を伏せるふりだけして祈祷師の動きをまじまじと観察していた。面妖な動きだな、と心の中でつぶやきながら。この大層な雰囲気がどこから湧いてくるのか。そのようなことについて考察するのがここでの退屈しのぎとなっている。
やがて祈祷師が黙礼し、儀式は閉じた。社長がお礼の言葉を伝えるのを合図に、社員は散っていく。笹原も人混みの後ろに紛れ、部屋を出た。祈りの残響だけが、まだ空気のどこかに沈んでいるようだった。
一日は祈りからはじまる──これは量子コンピュータ業界での古い常識だった。豪華な供物を並べ、祝詞を唱え、厳かな所作を捧げる。人々が泰然とした心持ちになる。それは複雑で不安定なものを扱うなかでの、プラシーボ的手順を象徴するような決まり文句だ。
そもそもこの奇妙な習慣は、半世紀ほど前に始まったという。
社会実装された当初のNISQという量子コンピュータはある特定の問題を高速に解くことができるこそあれ、それ以外の問題では計算速度も精度も不安定で、しましば誤った結果を吐き出した。研究者も技術者もその特性は理解していたが、歯止めのかからない人口減と生産性の低下に悩む企業は、たとえ非効率でも継続して稼働せざる得なかった。当たっては砕け、失敗したら改善し、また挑む。プラグマティックな運用で計算精度の確立を試みていた。
そこで現れた手法が『祈祷』だった。
もちろん、科学的な根拠はどこにもない。可能性がどうであれ要因や対処方はいくらでも議論の俎上にあげられる。それでも儀式として厳かにやっていればなんとかなる気がする。そんな横着の連続で祈りは文化となった。
現在の万能機は能力は飛躍的に向上している。計算エラーも劇的に減り、誤った結果が出たところで容易な作業で訂正できる。然りしこうして、効果の検証はされないままに文化は形骸となり、形骸のまま連綿と続いていた。
※
笹原の所属する会社は、計算作業の委託業務のほか、演算監査を専門とする中立機関としての側面もある。各社の量子コンピュータが投票データやシミュレーション結果を正しく処理しているかどうかを検証する役目を負っている。この一週間は大手ゼネコン会社の設備部門に派遣されることになっていた。短期間の監査業務で、朝行って夕方になればそのまま帰る直行直帰の仕事だ。ありがたいことに、ふだん通っている自社のビルよりも現場は近い。通勤だけを考えれば、いつもの一日より負担は軽くなる。
なにより、祈祷の風習がないことが気楽に感じられた。朝の祈祷告知もなければ、供物台が視界を塞ぐこともない。あらかじめスケジュールに落とし込まれた工程表があり、それにしたがい職員たちは入力と出力を繰り返す。余計な手続きがなく、流れは単純だった。工数が多いだけ忙しい職場ではあるが、できる限り合理化に努める姿勢は、業務に入って最初に受けた好印象の点だった。監査役として派遣されている以上、こうした働きやすさも評価項目の一つになる。
昼過ぎ、計算士のひとりが訝しげに眉をひそめ、再計測をかけた。演算結果に不具合があったらしい。正しさを保証する厳密な基準は曖昧だが、少なくとも既知の傾向とは異なっているらしい。
ベテラン職員の怒号が飛び交う。どうした、今日は忙しいというのに。
若手計算士の助け舟を求めるような視線に応え、笹原は肩越しからモニタを覗き込み、計算状況を目測で診る。不具合らしい不具合はない。それにもかかわらず、異常だと訴えているのだから余計に晦渋に思えた。
注意深く観察すると、一瞬だけ、モニタに映る波形の山が呼吸を乱した。目を凝らさなければ見逃してしまうほどの、かすかな乱れだった。
笹原はそのことを指摘し、計算結果から補正なりエラー訂正作業を施したらどうかとアドバイスを送った。
「ははあ、これがエラーですか……」とベテラン職員が難色を示す。
「もちろん可能性のひとつとしてのお話ですよ」と笹原。「つまり正の確率振幅の中に偽の確立振幅が微妙に干渉しているのではないか、ということです」
「おっしゃることは分かりますが、これが誤りなら、この程度、機械がなんとかしてくれているでしょう。問題ないのなら問題ないのです。たしかに昔はひとつひとつ照査するの業務の一部でしたが、あいにくそんな時間、我々にはありません」
その言い草にむかっとしたが、職員の反論にも一理あった。たしかにこの程度のエラーだ。見逃してもおかしくないほどに微細なもの。しかしその誤差が意思決定に無自覚な悪影響を与えてしまうことは、過去の事例でも挙げられているし経験則としても知っている。
「とにかく、この結果であげさせてもらいます。何度もトライしたことなので、同意でいいでしょ?」
しかし納得いかなかった。
「──では私からは、留保付きで良し、というコメントでよろしくお願いします」
「どうして? まあ、いいです……」
壮年の男は慇懃な態度を崩さないまま、不満の見え透いた嘆息をついた。
トラブルの対応で予定の時間が喫緊となってしまったため、それ以降は休憩もなしに計算を進め、ようやく全ての作業をやりきった頃には定時を大きく回っていた。
報告をしおえた頃には、とうにへとへとになっていた。帰宅する前に自販機から一本、ペットボトルのコーヒーを買って、観測室のそばにあるベンチで一息つくことにした。
ひとたび落ち着くと、昼間のやりとりがごちゃごちゃした思考の中から浮き彫りになってくる。あのおやじが現場を掌握しているのだろう。指摘は少なくとも間違ってはいない。現場によっては聞いてくれることもある。しかし、無茶な要求であることも承知している。このような板挟みはよくあることだ。だからといって慣れることはない。心を殺してうまくやるしかないのだ。この業務は頭脳に負担はかからないぶん、精神的に多大な労力がかかる。
考え事が深まったとき、廊下の向こうから誰かの影がこちらに向かってくるのに気がついた。ここは出入り口に向かう通路だから定時からしばらく経ったとしても特別不可解には思えない。
その影の主は女性のものだった。背が高く、華奢だ。
彼女は笹原の前までくると唐突に足を止めた。よくみると昼間、計算作業中にみかけた人物だったので、エンジニアのメンバーだということだけは分かった。
「お疲れ様です」
「昼間はとんだ災難でしたね」と笹原は会釈する。
「そうでしたね。喉もかわいていたみたいなので」
「──あぁ、まあ休憩もなしに働き詰めでしたからね。すみませんお気遣いいただいて」
笹原は立ち上がり、同じ状況を共有する女性にも何か飲み物を贈ろうとした。ただ、彼女はぎょっとした後、考えるようにして顎に手をやった。水滴のような静寂が落ちる。
「どうされました?」と会話の機を窺うように笹原が切り出す。
「す、すみません。さっきの言葉、あなたに対してではなかったです」
笹原は一瞬、唖然とした。さっきの沈黙は笹原の発言の真意を確かめていたようだが、そのほかに何かを量っていた気配もある。
「喉が渇いていたのは、コンピュータのほうです」
頭の整理がつかない。妙なことを口走ったなこの人はと受け流しかけたが、すぐに冗談を言っているわけではないと気づいた。彼女の表情はやたら確信めいた色が浮かんでいて、まるでこの問題に対する唯一の解を有しているような自信があった。
「どういうことですか?」
「ああやって、偽の確立振幅が干渉していたのは、コンピュータがそれを欲している状態なんです。お水でもなんでもいいですが、最も効果的なのは炭酸飲料です」
ますます分からなくなった。いっさい真面目な表情をしながら不思議な言葉を滔々とした口調で並べている、そのギャップにも驚いた。
「なにおっしゃっているのですか? つまりお供えでもすれば良いってことですか」
「そうです。供物です。あの程度なら供物をお捧げさえしたら大丈夫だと思いました」
まさか、うちの会社の社長のようなことを言い出すとは。いや、それよりも詳細で具体的に発言するあたり、社長よりもだんぜん信心深いと思える。見たところ自分よりも若く祈祷文化にどっぷりとつかった世代でもなかろうに。
「祈祷じたいは弊社でもやっていますよ。形式上ですが。けど、お言葉ですが──そういったたぐいのものは、あまり効果がないでしょう」
失礼します、と最後に付け足し、椅子から立ってその場から立ち去ろうとした。しかし女性は声をあげる。
「では、明日同じようなことが起きたらやってみましょう。補助的な処置として。もちろんこっそりと。放っておいたところで変わらないと思いますよ」
「それは、まあ──」
笹原はしぶしぶ了承した。気乗りはしない。ただそこまで食い下がってこられると、受け入れない限りは彼女の気がすまないだろう。笹原は自身のおしの弱さは自覚しているが、このしつこさはどれほど頑な性格の人だとしても通用しうるかもしれない。
別れ際に、首にかけた彼女の社員証が自販機の煌々とする光のなかに翻った。どうやら、彼女の名前はバトマエフ・アナスタシアというらしい。
翌日も症状は続いていた。同じ演算のフェーズで、波形の山が一瞬だけ呼吸を崩す。さりとて昨日の報告が誤差の範囲と処理された以上はなし崩し的に看過されている。最初に異常を突き止めた若手の職員も、すっかり萎縮して何も言う気ないらしく、モニタの前で、淡々と入力を繰り返す。その横顔には諦めとも習慣ともつかぬ無表情が張りついている。
そんな様子を眺めながら、笹原はあの会話を思い出していた。
喉が渇いていたのは、コンピュータのほうです。
冗談にしては妙に残っていた。疑問は尽きない。もし量子コンピュータに渇きという状態があるとしても、供物でどうにかなる道理がわからなかった。
その違和感に意識が集中した瞬間、横から小さな衝撃が走った。振り向くと、アナスタシアがじっとこちらを見ていた。この空間の中ではただひとり、敵意を有していない瞳で。
作戦開始です、といわんばかりの表情だった。右腕にはビニル袋を腕に通している。昨日の話が本当ならば、その中には飲み物が入っているのだろう。
午前中の計算作業が終了して、職員たちは昼食をとりにいく。室内が二人のほか誰もいなくなった時、アナスタシアが先陣を切った。二人はコンピュータがおさめられている小部屋に入り、筐体の背後の誰の目にもつかないようなところにまわりこむと、彼女はジャケットの内ポケットからサテン生地の布を敷き、それから袋から缶やペットボトルをとりだした。コーラ、サイダー、炭酸水──それらが光沢のある布地の上に整然と並べられる。手際が良い。こだわりも窺わせた。どこに置くか、どの順番か、それだけで結果が変わると言わんばかりの注意深さだった。
「さぁ祈りましょう」
「祈るっ?」
「声が大きいですよ。祈るんですよ。いつもやってることでしょう」
訳もわからず笹原は首をたれて目を瞑り祈るふりをする。瞼の裏の向こうでぶつぶつと唱える声が聞こえる。言語はわからない。だが、声調は一定ではなく、ラップのような韻を踏んでいた。どこかで途切れ、また別のリズムで立ち上がる。
「これでいいでしょう」とアナスタシアの平生とした声が響く。「もう終わりですよ。笹原さん、お昼ご飯、食べに行きましょう」
無人島に取り残された気分だった。あれは一体なんだったのか。やたらせわしない動作の連続で考える暇もなかったが、あまりにも不可思議なものだった。
「えっと、あれって……」
「祈祷です。今回は簡単にしちゃいましたが、格はいくらでもあげることができます。位相の像から渇水の形相を読み取りましたので──まあ、どうなるかは午後になってからですが」
笹原の質問に対して、アナスタシアはさも当たり前かのようにはきはきと答える。そして、そこには異様な説得力があった。
信憑が帯びたのは、それからすぐになってのことだった。午後の最初の計算で、波形のエラーが訂正されており、綺麗さっぱりと均等化されていたのだ。端正な、美しい輪郭。あれを『儀式の効果』以外に何が言えるのだろうか。業務を終えるまで、効果を示す確固たる証拠も、完膚無きまで否定できる根拠もなにも思いつかなった。
※
自社の職場のざわめきの中にいる笹原の胸中はいまだに疑問でいっぱいだった。
祈祷が終わってまもなく量子コンピュータを立ち上げ、そのほか朝の雑務がひととおり落ち着いたころ、計算室の前を通りがかった研究開発部の同僚が声をかけてきた。
「あれ、なんか久しぶりに顔を見た気がする」
「先週は別の企業さんに行ってたからね」
すると、どこの企業だと訊ねられたので笹原は社名を伝えた。
「へえ、あそこに行ってたんだ」と同僚が言った。「そこの量子コンピュータ、長く使っているからか、一癖あるマシンだって先輩が言っていたよ。水害対策とか都市計画とか、街の大きな決めごとの試算をいくつも通してきた古株だってさ」
その先輩はいったい誰のことを指しているのだろうか。ただ、それを追求したら話題が散るのでその感情は無視した。
「まあ、少しだけ……変な波形が発生していたな。原因もよくわからなかったけど」
笹原は曖昧に答えた。どこまで話すべきか、自分でも判断がつかない。
ほほぉ、と同僚は机の端に腰掛けつつ気軽な口調を崩さずに続けた。
「原因が、わからなかったんだ」
「そう。ずっと考えていたり仮説を立てたりしたけど、結局わからずじまい。とうぜん出先でそんなことは言えなかったわけだけど。主任のおじさんに『どんな手品を使ったんですか?』なんて、おべっか使われたよ」
そう述べたあとで笹原は、すまん、と謝った。愚痴をいってしまったことに対して、そんなつもりはなかった、と。
「まあ、なくもないだろうな。そういうとこ、昔は『シャーマン』を呼んでたらしいよ」
「シャーマン?」
「正式にはプロトコル・シャーマンって呼ばれてた人たちだ。非万能量子コンピュータの時代にさ、演算のデバックを取るために『儀礼』を行う専門家がいたらしいんだよ。自治体の予算配分とか、選挙の集計とか、そういうデリケートな計算の前にはよく呼ばれたみたいだ。けっこう影響をもっていたらしいよ」同僚は、すこし間をおいて付け足した。「俺の母校では細々とだったけど、研究もしていたらしい。民俗学とコンピュータ科学のあいだ、みたいな変な立ち位置で。まあ象牙の塔だよ」
笹原は思わず息を呑んだ。サテン布の光沢、整然と並んだ炭酸飲料、ぶつぶつとした唱え声──そのような光景が脳裡に蘇る。
「研究って、具体的には?」
質問に対し同僚は、この理解で良いかはわからないけど、という前置きをして続けた。
「いつも祈っているだろ? あんな仰々しい祭壇なんて用意して、神主さんまできてさ。あれがプロトコル・シャーマンから興っているんじゃないかって主張。モンゴルだったかロシアだったか、そこらへんの儀礼の形式が量子技術の補助に転用されて、そのあと文化として定着した──だなんて話だよ」
「本当に、そんなものがこの社会に存在していたのか? その、シャーマンって」
「さあな。技術史でもほとんど触れられていないし、もう都市伝説みたいな扱いなんだろ。でも効果があったって記録だけは妙に多い。まあ昔、講義で聞いた話で、これも話半分だと思うがな」
同僚は軽く笑った。
それから業務の合間や昼休みを使って、笹原は資料室に出入りするようになった。今ではかなり珍しい紙媒体で保管されているのは、会社のローカルな出来事に関わるものが主となるが、その最たるものが企業のCSR活動の一環として編纂された分厚い社史台帳だった。祈祷が『伝統』として語られるとすれば、このあたりに起源があるはずだと笹原は踏んでいた。
台帳の中はおしなべて知らない歴史が記されていた。創業当時のメンバーの写真や、地域行事への協賛報告、いまの社屋への移転の様子。
この企業はかねてから自治体の意思決定に関わる計算作業の委託をおこなっていた。すなわち、新興だった自治体DAOのインフラを支える立場にあり、量子演算の正確性は地域の意思決定の質に直結していた。だからこそ、儀礼の専門家が、演算の一部として招かれていたのだ。
ページを繰るうちに、古いコンピュータ室の写真が目に留まった。まだ床下配線もむき出しで、みるからに旧式の筐体がある。
「うわ……」
笹原が声を漏らしたのは、写真のほぼ中央にある筐体の前に横たわる動物の屍体だった。詳しく判別できないが形や大きさからヤギの子供にみえる。そして、その横でカラフルな衣装をまとった男が舞踏するように両手両足を投げ出している。その姿は、決して神道の神主ではない。
写真の下には、細い活字でキャプションが添えられていた。
『バトマエフ師による安定稼働祈祷のようす(創業三年目)』
笹原は思わず、指先で文字をなぞった。
バトマエフ師。
まさか。
※
待ち合わせの喫茶店は、自社ビルの斜向かいにあるチェーン店だった。サラリーマンや学生、習いごと帰りの親子とでほとんどの席が埋まっている。
アナスタシアは、すでに窓際の席に座っていた。一週間前と同じジャケット姿で、コップを両手で包み、外を行き交う車を淡々と眺めている。気づいた様子もなく、ただ待ちぼうけている人として群衆に紛れていた。
「お待たせしました。急にお誘いしてすみません」
笹原が声をかけると、彼女はようやくこちらを見て、わずかに微笑んだ。
「いえ、とんでもないです」
そう形式的な挨拶を交わす。
この場に来てもらうまでには、少し準備がいった。社史台帳でバトマエフ師という名前を見つけた夜、笹原はアナスタシアに接触を試みた。何度か文面を書き直し、ようやく送信ボタンを押した。先日の助力への礼に加え『もしご迷惑でなければ、あのときの補助的な処置について教えていただけませんか』と添えた。社史に残る祈祷の写真については書かないことにした。
すると戻ってきた返事は拍子抜けするほど事務的で、『帰り道に近くを通りますので、少しだけなら』とだけ書かれていた。調整の結果、翌日の夕方になった。
しばらく、どうでもいい仕事の話を続けたあとで、笹原は本題に踏み込んだ。
「で、先日の件ですが」
「はい」
「お祈り、とおっしゃっていた一連の行為について教えてください。なんでもいいです。たとえば、供物のこととか」
アナスタシアは一拍置いてから、穏やかな表情のまま首をかしげた。
「結果は良かったんですよね?」
「それは、まあ。おっしゃるとおりです」
「でしたら、それで充分ではありませんか」アナスタシアの口元が綻ぶ。
「しかし、あれはいったい何だったのか、という話は別です」笹原は続けた。「偶然で片づけるには、少し、出来すぎている。あなたは、あの儀式が効果を持つと確信しているように見えた」
アナスタシアは結露で濡れたコップを指先で回しながら、窓の外に視線を戻した。
「確信、というほど大げさなものではありませんよ。私はただ、装置の癖を見ているだけです。必要があったら、少しだけ整えてあげる必要があるときがある。だから補助的なんですよ」
「プロトコル・シャーマン、という言葉を聞きました。あなたは──」
そこで彼女は、ようやく笹原の目を見る。薄い虹彩が、店内の照明を鈍く弾いた。
「私が何者か、というのはそんなに大事でしょうか」
声色は柔らかいが、その言葉だけは不意に鋭さを帯びていた。
「装置が安定して、結果が出る。それ以上の説明を求めるのは、信仰とあまり変わらない気がします」
反論しかけて、笹原は口をつぐんだ。
信仰を疑うために、より強い説明を求めている──そう言われているような気がしたからだ。
「プロトコル・シャーマンのお話、面白いですよね。私も学生時代、少しだけ勉強しましたよ」アナスタシアは続けた。「でも、私はエンジニアです。できることは、仕様書と、波形と、人の顔を読むことだけですよ」
喫茶店を出るときのアナスタシアは、最後まで穏当な態度だった。そっと境界線だけ分たれている。そこには敵意も警戒心もなかったが、こちらの探ろうとした方向だけが、するりとすべて手のひらから落ちていくような感触が残った。
うまくいなされてしまった──それが笹原の落胆の正体だった。それ以上、彼女は具体的に語ろうとしなかった。質問を投げかけても話題は少しずつずらされていく。彼女の話術はまるで幽玄にゆらめく漁火を掴みにいくようだ。肯定も否定もされたわけでもなかったが、あの会話のなかで収穫できたものもいっさいない。言い逃れの連続というよりは、言葉の選択によって語られない部分を意図的に残すような問答のすえ時間はきてしまった。
笹原は会社に戻り、観測室にいる計算士たちに夕食から戻ってきたことを伝え、帰らせた。夜中におよぶ計算作業は管理員が引き受けることになっていた。今回は国家の膨大なデータを処理している。
「こんにちは」
どこかからしゃがれた声が笹原の耳を打つ。計算士が出払ったあとのことだった。
演算室は量子コンピュータが稼働中のときだけ、一般にも開放されている。この方針は先代社長から定められた制度だった。見学しにわざわざ来社する人は少ないものの、さりとて全く来ないわけでもなかった。
笹原も挨拶を返す。声のした方向へと観測用のラップトップ端末から視線をはずと、廊下に一人の老人が立っていたのがわかった。笹原は作業を横目にして、対応することにした。老人の腰は大きく湾曲していて、声を聞き取るには自身が屈む必要があった。
「拝ませてほしいのですが」と老人は言う。
「ええ、どうぞ、足元に注意してください」
笹原は演算室の照明をつけた。
「すみませんねぇ、いつもいつも急にお訪ねして」
そう言って老人は手を合わせあながら何度も点頭する。祈る対象は自分ではないのは確かだろうが、もしかして同一視されているのかもしれない。
「いえいえ、こちらこそありがとうございます」
笹原はそう返す。彼の気を悪くさせないための方便だった。案内してあげると、老人は演算室にコンピュータの前に立ち胸の前に手を合わせた。掌に射した青白い光が、コンピュータの筐体を走る照明の明滅と重なった。
敬虔な老人──それが笹原の抱いた印象だった。特別視するわけでもないし、軽侮するつもりもない。ただわざわざ足を運び、しわがれた両手を重ねる行為の真意が、笹原の理解に及ばなかった。
老人が手を合わせたまま動かなくなったとき、冷却装置の唸りが一瞬だけ変調した。床を伝ってくるリズムが、笹原の足裏から脛へ、脈打つように上ってくる。いつの間にか、自分の心拍と同じ間隔で機械が鳴っているように感じられた。
咄嗟になにかが聞こえた。
──あなたたちの呼びかけが必要です。
誰の声でもなかった。ファンとポンプが不協和音的にそう聞こえただけだ。笹原がそう解釈したのは言うに及ばず、しかし胸の奥のどこかが、その言葉をはっきりと切り出していた。
祈り終えた老人の姿が扉の向こうに消えるまで、その場を離れられずにいた。合理性があるとも思えない行動。だがこの装置が扱うのは国家規模の投票データや意思決定の重みだ。自分の思いがほんのわずかでも届きますように。そういった願いが、その姿勢に宿っているように思えた。
感謝とともに老人が去ると、演算室には再び機械の音だけが満ちた。だが、先ほどまでの一定のリズムは戻らない。機械が、まるで呼吸を忘れた肺のように、ときおり深い溜めをつくって駆動した。
異変を感じたのはそれから数時間たったころのこと。ふと一瞥した観測画面に表示されている波形には、見落とすには少しだけ大きすぎる鋸歯状の乱れが残っていた。解析ツールはいちおう許容誤差内と判定している。しかしそれはいまだけであくまで決められた範囲の内側だけを見ての話だ。評価軸の外で生じている異常は、正常値に押し込められ、記号として失われる。胸の奥に、ざらりとした違和感がこびりついて離れなかった。人間だけが微細な破綻を先に察するあの感覚にちかい。
その懸念は当たった。時計の針が午後十一時を指しかけたころ、波形が突然跳ね上がった。ログが追いつかないほどの急激な乱れ。冷却系統が同時刻に異常値を記録し、画面の半分が赤く塗りつぶされていく。
「これはまずいな」
思わず声が漏れた。訂正アルゴリズムを走らせ、逐次的に再計算をかける。だが、乱れは収まらない。想定の周期が合わない。むしろ周期そのものが変質し機械内部のどこかが、別の秩序で独自に動き始てさえ思えた。どれほど補正をかけても、軌道がもどることはなかった。
もうどうにもすることができなかった。観測室は常夜灯と筐体から発せられる光が床に青白い膜をつくっている。外の廊下からは一切の気配が消え、聞こえるのはファンの不協和音だけだ。
そのとき、笹原の脳裡によぎった。呼びかけ。いいや、それはありえない。ただの幻聴だと決めただろう。否定しきれない何かが体内のどこかに残っている。説明の範囲では辻褄が合わない。だが、説明がつく範囲の中だけでは、この乱れはどうにも理解できない。
アナスタシアの名前がよぎった。この事態を治められる人物は彼女しかいない。
夕方の喫茶店でのわずかな苛立ちと、それでも頼りたいという矛盾が胸の中で複雑に絡む。技師としてのプライドが邪魔をしようとしたが、目の前の波形がそれを許さなかった。
意を決して、連絡画面を開いた。
〇時四十五分を過ぎたころだった。
自動扉の開閉音が、演算室の奥まで届いた。
笹原が廊下に出ると、深夜の闇のなかに浮かび上がるような麗容が視界にとどまった。
アナスタシアだった。つま先から頭頂まで群青色の衣装をまとい、光沢のある糸が室内の光を鈍く弾いている。羽織っているものは刺繍のはいった布や革紐などが流れるようにたれている。昼間に見た筈の姿が、まるで別の輪郭をまとって立っていた。
笹原は目を見張った。その衣装は社史にあったものと酷似している。
その背後には、人物が三名、続いていた。大柄な男たち。いずれも同系統の衣装を身につけているが、外套だけは毛皮を模したもので、髭だらけの顔面を合わせると、全体としてけむくじゃらだ。各々は太鼓、鐘、鈴を携えており、いずれも使い込まれている。彼らは無言のまま演算室を見渡し、それぞれの位置を確認するように視線を交わす。図体に大きさに反して動作は驚くほど静謐だ。
「来ていただいて、すみません」
笹原が言うと、アナスタシアはかすかに首を横に振った。
「必要があったのでしょう」その声は驚くほど落ち着いていた。「一応、そちらの社長には連絡しました。私の名前と、必要なことを伝えたら、承認が下りました。少数で行う性質上、お立ち会いは笹原さんのみでかましません」
彼女は笹原の横を静かに通り過ぎ、演算室の前に立った。
扉のガラス越しに、乱れた波形の光が青白く揺れている。アナスタシアは数秒だけじっとそれを見つめ、呼吸をひとつ整えた。まるで水面の揺れを目で測るような、集中の手前の静けさだった。
「まず、場を作りましょう」
そう告げると、三人はすぐに動き出した。
ひとりは筐体近くの床を指先でなぞって位置を測ってから角取りし、ひとりは持参した絨毯を筐体の前に敷き、水瓶、食肉が盛られたトレー、紙で巻かれたなにかを載せた陶器のうつわを設る、もうひとりは空調の流れを確かめるように天井へ手を伸ばし、木製の工芸品を四方にとるように設置する。鮮やかな手捌き、度重なる訓練により身体に沁みついたような滑らかさを有していた。
そのあいだ、アナスタシアは閉じられた扉にそっと手を置いていた。冷たいガラス越しに伝わるなにかを、掌でたしかめるように。その表情は、技師のものではなく、しかし宗教者のものでもなかった。
どこか中間にある、曖昧でいて確固とした気配──笹原はそれをどう言語化していいのかわからなかった。
「大丈夫です」
アナスタシアはようやく振り返った。
薄い色の虹彩が、深夜の光を静かに返している。
「すこし時間をください。整えれば、きっと収まります」
そう言って、彼女は扉を押し開けた。照明が衣装の刺繍や襟に滲み、ひとつの影となって演算室へ吸い込まれていった。
補助者たちは黙したまま、それぞれの持ち場についている。アナスタシアは男たちの中心、筐体に相対するように立つ。衣装が沈んだ色彩の光をはらみ、瞬き続ける。
演算室の扉が閉まると一気に雰囲気が変わった。観測室から眺める笹原も空気の変わり方に驚嘆した。
──はじまる。声としては聞き取れなかったが笹原はそう感じ取った。本当に補助者たちに声をかけたかもしれないし目配せだけであったかもしれない。とにかく、佇立していた補助者たちはそれぞれの持ち場から、アナスタシアの動きに合わせてゆっくりと動作を始めた。いつのまにかお香に火がつけられたらしく、肩越しに糸のような煙がたちあがり、薬草が焼けたような独特な香りが観測室に漂ってくる。
一瞬、沈黙が深まると、その中心に吸い込まれるように、太鼓の低音が鳴り始めた。鈴と鐘の音が混ざり、補助者たちの質実で迫力のある声がどよむ。韻律が強調された発声だった。アナスタシアがそのリズムにあわせて身をひらく。踊りとも所作とも言い切れない動きが、波形の乱れに寄せていくようだった。音の層は厚みを増し、演算室のガラスを細かく震わせた。
その瞬間だった。
ある時を境に、冷却装置の唸りが、すっと引いた。
代わりにもっと低い、地鳴りのような振動が床下から響いた。演算室で繰り広げられる動作だけではとても出せないような音。装置の中でなにかが共振しているのだ。笹原は反射的に波形モニタを確認した。乱れが変調していた。周期がずれ、そのずれが統一性を帯び始める。新しいリズムに組み変わろうとするように。アナスタシアの歩み、補助者たちの呼気、冷却装置の駆動音。その三つが、ひとつの拍動に収束していく。
観測室の暗がりで、笹原は波形に見入っていた。攪乱が少しずつ一定の律動を取り戻そうとしている。機械が、もがいているのかもしれない。このふるまいは、恒常性に向かう過程のように笹原は直感した。
笹原は胸の前で両手を組み、自然と頭が垂れた。逆らえなかった。自分が何をしているのかは理解している。羞恥も否定もそこにはない。ただ、波形に寄り添いたいという、ごく素朴な衝動だけが残る。
自然と目を瞑り集中した。空気の振動と自分の呼吸が一致していることに、奇妙な安堵があった。
ふたたび目をあけたとき、エラーを示す赤色は失くなっていた。波形の、鋸歯状の乱れが、誰かが指で形をなぞったかのように滑らかな正弦へと化している。
笹原の足は、床に貼り付いたように動かなかった。常識がどこかでひっくり返った気分だ。
アナスタシアが笹原のもとにきた。息は絶え絶えで、明確な疲労感を窺わせた。
「ありがとうございます。解消、しました」
礼を言った後、笹原は黙り込んだ。なにをどう付け足すか見当がつかなかった。
アナスタシアは頷きながら、
「よかったです。笹原さん、すこしお話できますか?」
深夜のロビーは、いつもより広く感じられた。照明は半分だけが落とされている、ぼんやりとした空気がそこにある。二人の他に誰もいない空間には、まだどこか儀式の残響が残っている気がした。
アナスタシアは、ソファにそっと腰を下ろしていた。儀式を終えたばかりの疲労が、肩のあたりに静かに溜まっている。
「昼間は、すみませんでした」
最初に口を開いたのは、彼女だった。笹原は返す言葉を探すのに少しだけ逡巡した。
「僕の方も踏み込みすぎたのかもしれません」
「違うんです。話したくなかったわけではないんです。ただ──言葉を選びすぎて、結局なにも伝えられなくなってしまった、だけです」
天井の希薄な灯りが、彼女の横顔を柔らかく照らしていた。帽子だけはすでに外していたが、瞳孔にはさっきまでの緊張がまだ影を落としている。
「笹原さん。私は、プロトコル・シャーマンです」
その言葉を聞いても笹原は動じず、次の言葉を待った。
「でも、私はシャーマンという肩書を自分から名乗りたくありませんでした。技師として働くなら、その名前はできるなら置いていきたかったので」
「お気持ちはわかります。このご時世ですからね」
アナスタシアは両手を膝の上で組み、少し息を整えてから続けた。
「ここ──あなたの会社はかつて祖父が祈祷していた場所でした。創業期の量子コンピュータを安定させるために、彼は何度もこの演算室で儀式を行ったんです。その会社から監査員が派遣されると知ったとき動揺したんです。自分も同じ名で呼ばれることが怖かった。祖父は、あの時代特有の混乱のなかで大きな影響力を持ちました。それは、今にして思えば、あまりにも大きすぎた特権だったのかもしれません」
それは儀礼を看板にした特権だろう。
「あのとき、どうして僕に祈祷を提案したんですか?」
「軽率な動機ですよ。あそこよりは祈祷文化の素地があるだろうって」
完璧な洞察だ。褒めたい気持ちもあったが言外しないことにした。
「でも今日のあなたを見て、ようやく少しだけ、自分を受け入れる気がしました」
「受け入れる、ですか」
「祈りは古い儀式の模倣ではありません。技術がどれだけ進んでも、人が向き合わざるを得ないゆらぎのようなものです。装置が扱うゆらぎ、人が抱えるゆらぎは、きっとどこかで混ざり合うと、これは祖父でもありますし、今の私の実感でもあります」
笹原は自然と手を組んでしまったあの瞬間を思い返しながら言葉をふりしぼる。
「僕は複雑な事象ですら解決できると自負していました。でも認識が甘かった。 祈りと計算の境界なんて、本当は最初からなかったかもしれません。それに気づかせたのは間違いなくあなたのおかげです」
ここまで言い切れることに驚いた。かつての自分ならこうした言葉は口にすることすら嫌悪していただろう。
補助者の一人が撤収作業にひと段落がついたこと告げると、ここでアナスタシアは立ち上がった。
「アナスタシアさん、最後に」笹原は呼び止めた。「私は演算室に出入りしたときある音を聞きました。あれは、量子コンピュータの声でしょうか」
彼女は微笑んだ。
「声、と言われたらそうでしょう。でも具体的にいえば──えぇ、もう答えは出ていますね。私たちが機械を必要とするように、機械も私たちを必要としているので」
それは透徹とした実体のないものを認めるような響きだった。