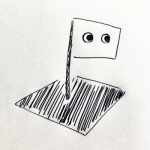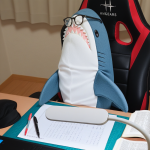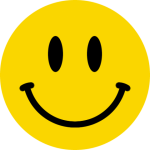梗 概
バス停の回収人
16歳のハヤテは3つ上の幼馴染・凪とトラックに乗り、廃村の古びたバス停を回収していく。
かつて限界集落の交通を支えた自動運転バスは、過疎化に抗えず廃線。カメラを搭載し地域の見守り役も担ったAIバス停は放置されたが、その脆弱性に目をつけた攻撃者のハッキングの経由地として近年悪用され、直接の初期化・回収が急務だった。監視AIに秒単位で命令される過酷な肉体労働だが、サイバー戦争による不況下、孤児の二人は仕事を選べなかった。
ある日二人は、故郷の村へ10年ぶりに足を踏み入れる。村はかつて祭りの日、過負荷処理でハードウェアを焼き切り、生体デバイスを介し人の感覚も奪うマルウェア「フラッシュ」で汚染。除染法も不明で、感染リスクから村人は全員避難、立ち入り禁止となっていた。まだ幼かった上、避難生活で精一杯だった彼らには村の記憶はほぼ残っていない。
バス停は自家発電で稼働を続け、無差別通信で襲いかかる感染躯体もあった。一刻を争う危険な作業環境だが、凪は村の記憶を丁寧に弔っていく。ハヤテはそれに苛立つも、逆にバス停が網膜デバイスに投影してきた偽の故郷の幻影に目を奪われ、その隙に感染しかける。監視AIはハヤテを見捨てろと命令するが、凪は無視してハヤテを助けトラックに乗せる。
最後のバス停には、浴衣姿の少女が座っていた。罠の映像と踏んだハヤテはバス停に初期化用端末を接続するが、凪が止める。凪の網膜にはラムネを差し出す老人が見えており、それは昔バス停でよくお菓子をくれた人だというのだ。3つ上の凪には僅かに村の記憶が残っていた。
ハヤテもまた浴衣少女が、バスが来ず不安な時間に遊んでくれた近所のお姉ちゃんだと思い出す。忘れていた取るに足らない記憶に胸を打たれる二人。さらに思い出すべく、監視AIの警告を無視し、各々の見える村人と共に、来るはずのないバスを待つ。急かされ続ける日々で久しぶりの待ち時間だった。
突如、除染不可能だったはずのフラッシュが除染される。接続を検知し攻撃準備に入ったフラッシュには、一定時間経つと、解析されるのを避けるため自己消去する仕様があったのだ。待つことが除染方法だった。
二人はバス停に、徘徊者を検知すると親しい人を投影し、その場に留まらせる認知症者向け機能があったと思い出す。バス停は二人を覚えていて、安全になるまで待たせたのだ。
やがて一台のバスが到着するが、これもバス停の映す幻影だ。バスには村の人々が乗っており、幻影は走馬灯のように移り変わりながら、どこかへ走り去って行く。
帰還後、二人は除染方法を見つけたにも拘らず、命令違反と遅延の罪で拘置所へ入れられる。監視者は二人の報告を元に、待ち時間を活用した新たな効率的巡回ルートの整備を告げる。
世界は結局、待つことを許さない。だが拘置所にいる間は村の記憶を弔う時間がたっぷりあった。二人は村の思い出を一つ一つ、確かめ合うように語り続ける。
文字数:1200
内容に関するアピール
僕の地元は限界集落で、バス無しに村の生活は成り立たない。そんな村がいつかは滅び、バス停だけが残る風景を想像した。
バス停は独特の空間だ。特に田舎のバスは電車より時間に曖昧で、いつ来るのかわからない。本当に来るのかすら不安になる。だから待つ時間が似合う。待つ人同士が出会い、話す交流の場でもある。
本作ではそんなバス停の魅力と、未来の超効率至上社会を組み合わせた。後者は最近個人的に「AIで仕事が急激に効率化したが、空いた時間に別の仕事を入れられ、労働の密度が上がっているだけ」という体験をしており、それを踏まえた。
ただし両者の対比を描く際は、監視AIにより治安が維持される場面を入れるなど、安直な効率化批判にはならないようにしたい。
なお「認知症者の徘徊を防止する『偽バス停』(バスが来ないため留まり続ける)」や「バス停の見守り機能(乗降車ログで安否確認できる)」は実在しており、着想を得た。
文字数:393
バス停の回収人
トラックが揺れ、尻が少し浮いた。脱輪しそうな感覚を覚え、思わずブレーキを踏む。恐る恐る窓から見下すと、道が一部滑落しているようだ。引き返すべきか。しかし時間のロスになる。
助手席の仁は、腹を出していびきをかいていた。朝方まで作業していたとはいえ、この悪路でよく眠れるものだ。車を後退させようとしたところで、脳内に女性の声が響いた。
【5秒遅延です】
ガイドの合成音声だ。僕は慌ててアクセルを踏み、細い山道を前進する。なんとか渡り切った先に、バス停があった。
丸い標識が立っているだけの、小さなバス停だ。標識はほとんど禿げてしまっているが、「病院前」という文字だけが読み取れる。
「さむっ」
目覚めた仁が、防寒着を羽織りながら降りてきた。
「人が住んでたなんて、思えねえな」
仁はそう言って目をこすった。辺りには朽ちた家屋がいくつか見えるものの、ほとんど草木に覆われている。
【10秒遅延です】
またガイドの声がした。
「急ぎましょう」
そう言って僕は、バックパックから旧式のタブレット端末を取り出した。バス停の裏側に接続口を見つけ、コネクタを差し込む。ビビ、と電子音が鳴り、丸い標識がぼんやり橙色に灯った。ここからはスピード勝負。端末を操作し、初期化の手順を実行していく。かじかんだ指が、なかなか思うように回らない。
「大丈夫かあ?」
「仁は黙っててください」
ほどなくして、「データ消去完了」の文字が端末に表示された。ほっと一息をつく。振り向くと仁が、欠伸をしながら突っ立っていた。
「道具は?」
僕が言うと、仁はやべっ、と小走りでトラックに駆け寄り、荷台から解体道具を持ってきた。受け取ったハンマーを振りかぶり、丸い標識に振り下ろす。グワン、と鉄の震える音がして、バス停の背骨がわずかに曲がった。素手に強い反動が返ってくる。
並行して仁がバールを土台の下に差し込み、てこの原理で持ち上げる。内部にハードディスクを搭載したバス停は、仁の馬鹿力を持ってしてもひと苦労だ。顔を真っ赤にさせた仁が唸ると、ようやく持ち上がった。
【40秒遅延です】
僕がハンマーを振り下ろし、仁が掘り起こす。白い息を吐きながら作業を続けるうちに、ようやくバス停が地面に倒れた。標識のライトが点滅しながら消えていく。パーツごとに分解したあと、重さに身体をふらつかせながら、荷台へと放り投げた。息を切らして車内に戻った瞬間、声が聞こえた。
【1分遅延。スコア減点です】
「あー!またかよ!」
仁が天を仰いだ。
「仁が馬鹿みたいに突っ立ってなければ、間に合ってました」
一方が初期化中に、もう一方が道具を揃える。そんなことはバディとしての、基本中の基本だ。
「お前さあ」
仁がトラックを発進させながら言う。次は仁が運転し、僕が眠る番だった。
「俺、もう来月でハタチよ。敬えよ」
「別にいくつになったって、年の差は変わらな……」
【違反講習チャプター1。バス停について】
僕の声を遮って、脳内でガイドが割り込んだ。今度は不自然に明るい、男性の声に変わっていた。
【かつて山村を支えたバス網は廃線になり……】
「うわ、始まったよ」
仁がうんざりした声をあげた。同じ音声が聞こえているのだろう。
【……それに伴い旧式スマートバス停も、廃棄コストの問題から放置され……】
声が続く。
スケジュールに1分以上遅れると、報酬を減らされる上、この違反講習が流れてくる。インプラント —— 僕らの頭蓋内に埋め込まれた生体デバイス —— が受信する音声を、止める権限はない。
【……攻撃者はハッキングの経由地として、古いバス停を悪用し……】
気を逸らすため、窓の外に目をやると、雪が降り始めていた。
「おいおい、勘弁してくれ」
仁が悪態をついた。廃道に積もると厄介だ。作業の危険性は増すし、何より遅延に直結する。
【チャプター2。回収人について】
軽やかな効果音が鳴って、講習が次のセクションへ移った。
「はあ、さっさとこんな仕事やめてえよ」
脳に講習を垂れ流されながら、平気で独り言を続けられる仁は、案外器用なのだろうか。
【……回収人は、社会的に極めて重要な任務を……】
「だったら手袋くらい支給しろっての」
仁が口を尖らせる。いや、ただ図太いだけだな、と僕は思い直した。
「バス停って冷てえんだよな。んで硬えし」
その台詞に、僕は自然と自分の手を揉んだ。何度も血豆が割れた掌には、硬い層が形成されている。その手でポケットをまさぐり、支給された睡眠薬を取り出した。
【……回収が必要なバス停は、全国で10万基にのぼり……】
薬を唾で飲み込んで、無理やり目を閉じる。眠らなければ。次のバス停に着いたら、また作業が始まる。短時間で体力を回復させることも、回収人の務めだった。
【……私たちは最新のアルゴリズムを用い、最も効率的な巡回ルートを導き出しました……】
トラックに揺られながら、ようやく意識が遠のいていく。
【……事態は一刻を争います。決して遅延は許されません……】
◇
翌日、仁の様子がおかしかった。
早朝に新たなエリアへ入った僕らは、雪道に苦戦しながらも、バス停の回収を進めていた。荒れ果ててはいるものの、これまでの派遣先に比べれば、人里としての原型を保っている。そんな廃村で、仁はまだ新しい家屋を見つけては土足で踏み入り、嬉しそうにモノを漁った。かと思えば拾い上げた茶碗を、どこか物憂げに見つめるのだった。
そして昼過ぎ、今日3つ目のバス停の回収に着手した時だった。仁が僕の腕を掴んだ。
「痛っ!」
僕は思わずうめいた。仁の腕は、僕より一回りも太い。
「見てみ」
仁が顎をしゃくった先には、まだ電光掲示板が動いていた。自家発電のバス停なら、別に不思議なことではない。
「離してください」
「気づかねえのか?」
仁が不機嫌そうに言うと、掲示板に文字が流れ始めた。
※本日は留山村祭り。17時より役場前の広場にて、盆踊り開始※
その瞬間、身体に衝撃が走った。
「このバス停に流れた、最後のニュースってわけだ」
仁が標識の雪を拭いながら言った。現れたのは「留山村 駐在所前」という表記だった。
唖然とした。僕はこの場所を知っている。
留山村は、僕と仁の故郷なのだ。
言葉の出ない僕に、仁は得意げに続けた。
「俺は昨日から気づいてたよ。なんなら前から予想してた」
身体がカッとなった。懐かしいのではない。恥ずかしかった。自分の故郷に気づけなかったことが、ひどく惨めに思えた。
「派遣先には、出身地も考慮されるからな。土地に明るい方が作業が進む」
僕らがこの村を出たのは、もう10年前のことだ。そう、ちょうどさっきバス停に表示された、村祭りの日。あの日、僕も仁も —— そして村人の誰もが、一斉に留山村から姿を消した。
「このバス停も俺らみたいに、あの日のまま止まってんだな」
仁が感慨深そうに言った。なにかを言い返そうとしたが、うまく表現できない。
「いいから腕を離してください」
そう呟くのが精一杯だった。仁が不満を垂れながら道具を取りに行っている間に、僕は初期化プログラムを実行する。10年前の村祭りのお知らせが、ゆっくりとフェードアウトしていった。
その後も僕らはバス停のデータを消去し、解体しては、荷台に積んでいった。中には映像が保管された筐体もあった。かつて山村の見守り役を担ったバス停は、カメラで村人ひとりひとりの顔を認識し、記録していたのだ。
僕は端末を操作し、それらのデータを跡形もなく抹消していく。プライバシーに甘かった昔とは違って、こういった個人記録は攻撃者に悪用されかねない。一切の隙も残さず、データを完全に破壊することが回収人の任務だった。
映像を保管するだけではなく、映し出すバス停もあった。屋根のついた大きめのバス停に到着した際、夏の田園風景が映し出されたのだ。バス停が僕らのインプラントに、ホログラムを直接投影していた。バス停の公衆通信には、こうした強い権限がある。それが攻撃者がバス停を狙う理由でもあった。
【警告。ウイルス感染の可能性あり】
威厳ある声が脳内に響いて、身体に緊張が走った。落ち着け。こういう時の対処方法を思い出せ。そう自分に言い聞かせる。
「急ぎましょう。もしバス停が感染してたら、無差別通信をしかけてくるかも……」
「お前、真面目すぎ!」
仁は手を叩いて笑った。
「『可能性あり』程度に反応してたらキリねえから」
「でも、このホログラムは……」
「バス停には元から映写機能があっただろ。あー、お前は覚えてねえかもだけど。バス待ってる間って、暇だからな。いい感じの景色みて時間潰すんだよ」
「じゃあなんでいま発動したんですか?」
食い下がる僕を、仁は手を振ってあしらった。
「ただの誤作動だろ。それにしても懐かしいな、この田んぼ。夏の村って、こんなんだったよな。冬は辛いけど、夏はいいんだよなあ」
目を細める仁を無視して、僕は端末に集中する。頭の中では、まだ警告音が聞こえていた。たとえ可能性が低くても、作業を遅らせる理由にはならない。
「早く道具を持ってきてください」
「おい、待て。手えくらい合わせようや」
そう言って仁はうやうやしく手を合わせ、目を瞑った。
「村に残った、貴重な記録だ。それを消すんだから、せめて弔おうぜ」
データを消して回る自分を、責められているような気がした。
「それにしても、お前もなんか一つくらい、思い出せないもんかよ」
仁が呆れたように言った。同時に脳内でガイドの警告音が鳴る。
うるさい。
僕は思わずバス停のコネクタに指を突っ込み、素手でこじ開けた。バキバキ、という音を立てて、基盤が露わになる。
「おい!何してんだ!」
【警告。ウイルス感染の危険性あり】
僕はただ回収に没頭したかった。仁が道具を持ってこないなら、自分で壊すのみだ。
乾燥した指先が裂け、血が滲んだ。構わず基盤から生えたケーブルをつかみ、根こそぎ引っ張った。ミチミチ、と音を立てて断線していく。力任せにケーブルを引き抜くと、田園風景はふっとたち消えた。
夜のトラックは冷える。燃料節約のため、暖房は許可されていない。車中泊はすっかり板についたが、寒さにだけは慣れることはなかった。
「な、俺が正しかったろ」
仁が僕の頭を強めに小突く。
ガイドの分析によると、結局あのバス停は感染していなかった。かつて「フラッシュ」と呼ばれるウイルスが侵入を試みた形跡はあったものの、バス停が見せた映像自体は、仁の言った通り、ただの誤作動だったようだ。
「それで、村祭りの日のことだけどさ」
仁が語り始めて、僕は毛布を顎まで引き上げた。休憩はきっかり3時間。夜が明ける前に、また次のバス停へ向かわなければいけない。
「あの日、留山村はフラッシュの標的になった」
—— フラッシュ。標的の処理を最大速度まで引き上げ、焼き切ってしまうウイルス。まだ有効な除染方法は見つかっていない。
「フラッシュは感染るからさ。それでみんな、必死に逃げたんだよな」
フラッシュの恐ろしさは、インプラントの通信を介し、人から人へと感染することにあった。感染ると神経伝達が過剰に加速し、最悪の場合死に至る。そのため中央システムを汚染された留山村は、立ち入り禁止地区となったのだ。
「でも、施設育ちの俺らが、おんなじ避難先だったのはラッキーだったよな。他の村人は、もうどこにいるかもわかんねえ」
僕は仁の話を聞き流しながら、毛布の下でケーブルを弄んでいた。さっきバス停から引きちぎったものだ。
「それで、えっと、あの日のこと。お前は覚えてないみたいだから教えてやろうと思って。あのとき一緒に逃げた俺らは……」
「その話、必要ですか?」
ケーブルを左右の指に巻きつけながら僕は言った。
「仁は年上だから、僕より覚えてるのは当然です。でもそれが任務の役に立ってますか?逆でしょ。いちいち作業が止まって、遅延につながってる」
ケーブルを力いっぱい引っ張る。裂けた指が痛んだ。
「フラッシュからは、1秒でも早く離れるのが合理的です。長居すれば、それだけ感染リスクが高まるから」
ガイドが僕らを急かすのもまた、その意味で合理的だと言えた。サイバー戦争下では、立ち止まること自体が危険なのだ。
「『合理的です』ってガイドかよ」
しかし仁は鼻で笑った。毛布の下で、引っ張ったケーブルが千切れる感覚があった。
「過去がある人は、いいですよね」
僕は言った。人は普通、過去の経験に基づいて行動する。仁にも、仁を支える故郷の記憶がある。それがない僕には、理屈だけが頼りだった。
「僕は今で、精一杯です」
そう言って睡眠薬を口に含み、毛布を頭まで被った。千切れて剥き出しになった導線が、指の腹にちくりと刺さった。
◇
翌朝、トラックを降りると、雪が膝まで降り積もっていた。冷気が足元から這い上がってくる。結局、昨晩はほとんど眠れなかった。
村のバス停はあと2つ。珍しく余裕があると思っていたが、目の前のバス停を見てうんざりした。待合小屋が併設されていたのだ。小屋ごと解体する必要があるとしたら、大仕事になる。
「ちゃっちゃと終わらせますかあ!」
仁が叫んだが、その声は反響することなく、ぶあつい雪に吸い込まれていった。
「と、その前にこれこれ」
懐から何やら取り出したと思ったら、古い煙草だった。いまや都市部でも見かけない代物だ。
「昨日、廃屋で見つけてさ。しけってなきゃいいけど」
「そんな時間ないですよ」
僕は呆れて言った。
「まあまあ、今日は楽勝だからいいじゃん」
煙草を奪い取ろうとしたが、昨晩のことを思い出し、手を引っ込めた。これ以上険悪になれば、作業効率に関わる。
「山火事になったら惨事です。小屋から離れて吸ってください」
はいはい、と言って仁はトラックの向こう側に消えていった。僕はため息をつき、準備を進める。すると隣接する待合小屋から、わずかに灯が漏れていることに気づいた。
もしかして。雪を踏みしめて扉まで移動し、ドアノブを回すと、低い音を立てて開いた。明かりのついた空間では、静かなピアノのBGMが流れている。そしてほのかに暖かい。思った通りだ。この小屋はバス停と一体となって、自家発電で稼働している。電気も空調も音響も、10年前の姿をそのまま残していた。
小屋の壁には時刻表やポスター、小さな黒板が架かっている。しかし僕の目を引いたのは、隅で音をたてる立方体の箱だった。鼓動が早まる。自販機だ。「あったか〜い」と表示された赤色のランプを、食い入るように見つめた。
生唾を飲み込んだ。思わずボタンを押したが、出てこない。型が古く、生体認証では買えないようだ。這いつくばって自販機の下を探したが、硬貨は落ちていない。懐をまさぐってみたところ、尖った感覚にあたった。これだ。
断線したケーブルの導線を鉤爪状に曲げて、硬貨の投入口に差し込んだ。出し入れを繰り返すと、何かがはまる感覚と同時に、ガコン、と鈍い音がした。当たりだ。受取口には、缶のミルクティーが落ちていた。しかもまだ暖かい。
ベンチに座って、恐る恐る口をつける。甘い香りが途端に広がり、くたびれた全身に行き渡った。冷えきった手が、じんわりと温まる。掌に刻まれた無数の傷が、ミルクティーの甘みで癒えていくようだった。
作業を始めなければ、とも思ったが、まだ警告音は流れてこない。仁だって煙草を吸ってるんだから、すこしくらい休んでもいいだろう。僕は茶葉の香りを楽しみながら、壁に架かった黒板を眺めた。
「今日も寒いですね!雪には気をつけて」
「バスさん、いつもありがとう」
「おまつり、たのしみだね」
たくさんの言葉が、寄せ書きのようにチョークで記されていた。バス停とは、村人の交流の場でもあったのだと僕は思った。だとしたら自分も、昔ここで暖かい飲み物を手に、誰かと笑い合うような、そんな時間を過ごしたのかもしれない。いや、きっと過ごしたはずだ。
かつてここに、自分の居場所があったと考えるだけで、急に胸がいっぱいになった。涙が溢れてきた。全身が火照って、鼓動の早打つ音が聞こえた。
「なにやってんだ?」
振り向くと、バールを手にした仁がいた。
「煙草はもういいんですか?」
僕は尋ねた。いまなら仁と、対等に話せる気がする。
「お前の言葉が気になってな。『小屋から離れて吸え』って言ったろ?」
ぶっきらぼうに言う。そんなことが気に障ったのだろうか。まったく昔から短気な奴だ。
「すいませんでしたね」
僕はなだめるように言って、ベージュ色の缶を見せた。
「でも、お詫びにミルクティーがあります」
「ないんだよ」
なぜかその表情は強張っている。
「いや、だから仁のぶんもあるって……」
「小屋なんて、ないんだよ」
なんだか悲しそうな目だな、と思った時、ふと黒板の寄せ書きに違和感を覚えた。よく見ると全ての文字が、同じ筆跡で書かれている。ポスターにも、自販機の「あったか〜い」の字さえにも、見知った手書きの癖がある。
これは、僕の書いた文字だ。
そう気づいた瞬間、BGMの曲調が狂い、鍵盤を出鱈目に叩き始めた。寄せ書きの文字が明滅しながら浮き上がり、音楽に合わせて旋回する。全身が燃えるように熱い。僕は上着を脱ぎ捨て、その場で嘔吐した。仁が叫ぶ声、それから何かを叩き壊す音が聞こえた。そのまま意識を失った。
【チャプター4……フラッシュについて……】
目を覚ますと、トラックの助手席に寝転がっていた。ひどい頭痛がする。
【フラッシュは、攻撃者最大の武器であり……】
頭の中では例の講習が流れていた。また遅延したようだ。重たい身体を無理やり起こそうとしたところ、仁が窓ガラスを叩いた。腕には鉄の塊を抱えている。
「お前、フラッシュにやられたんだよ。もうすぐ終わるから、しばらく寝てろ」
そう言ってバス停の残骸を、重そうに荷台へ運んでいった。
助手席に身を預ける。全身が気怠い。たしか待合小屋でミルクティーを飲んで、そしたら仁が戻ってきて、それで……それで仁は、小屋なんてない、と言った。
【フラッシュに感染すると、初期症状として極度の神経過敏に……】
ああ、そうか。僕はようやく気づいた。全部嘘だったのだ。小屋も自販機も、黒板も。甘さも温かさも。僕が思い出したと思った居場所は、すべてがウイルスの罠だった。
【フラッシュは私たちの声すら遮断し……】
「行くかあ!」
トラックに乗り込んできた仁が、講習をかき消すほどの大声で叫んだ。
「びっくりしたよ!お前、雪の中で座り込んでたんだぜ!口開けたままでさ!」
そう言って力強くアクセルを踏む。だがタイヤは雪で空転し、なかなか進まない。
「あ!これお前が握り締めてたやつ!なんか大事なもんか!?」
仁は前を向いたまま、千切れたケーブルを渡してきた。その手は真っ黒に煤けている。
【フラッシュの感染が広がると、全体の回収が遅れるリスクが生じ……】
「危ねっ!」
タイヤがスリップし、仁はハンドルを取られそうになる。
「すみません」
ケーブルを受け取って僕は言った。
「すみません。僕が油断したから……」
「なに!?聞こえねえ!」
仁が怒鳴った。
「ごめん!」
僕は叫び返した。仁はああ、といった感じで片手を振る。その目には苦悶の色が浮かんでいた。おかしい。不審に思った僕は、「なにが聞こえてる?」と端末に打ち込み、仁に見せた。それを横目で見た仁は、苦笑いした。
「ガイドが、金切り声で叫んでんだよ!」
やはりそうだ。僕に流れている講習は、仁には聞こえていない。ガイドは仁だけに、別の指令を伝えているのだ。
僕が「なんと言ってる?」と端末に書くと、仁はこめかみを押さえながら怒鳴った。
「お前を置いてけ、ってさ!」
なるほど、と僕は冷静に納得した。仁が止めてくれたとは言え、僕はすでに感染した可能性がある。ここで排除したほうが、合理的だと判断したのだろう。
「平気だ、じきに止むだろ!」
車体が左右に大きく揺れた。インプラントに響く大音量は、三半規管にも影響を与えるはずだ。僕は自分を鼓舞して半身を起こし、右手をハンドルに添えた。二人の運転するトラックがふらふら曲がりながら、雪道を徐行していった。
◇
最後のバス停に到着した頃には、日が暮れようとしていた。
警告音がようやく止んで、我慢勝ちだ、と仁は勝ち誇るように言ったが、かなりの疲労が溜まっているようだった。運転席に寝かせ、僕だけで回収作業を始める。
「さて、どうするかな」
バス停を眺めて、しかし僕はつぶやいた。「留山小学校前」という丸い標識に、ベンチが備え付けられただけの、いたって簡素な筐体だ。だが問題があった。少女が座っているのだ。
10歳くらいだろうか。薄紅色の浴衣を着て、後ろに結んだ豊かな黒髪に、銀色のかんざしを挿している。少女は木製のベンチに腰掛け、背筋をぴんと伸ばして正面を見据えていた。
留山村が立ち入り禁止になってから、もう10年が経つ。少女がバス停によるホログラムであることは明らかだ。「感染の可能性あり」の警告音も聞こえてくる。
僕は少女の前を通り過ぎ、回収の準備を進める。幻影の待合小屋に比べれば、粗雑な罠に見える。だが油断はできない。なにせ僕は、この少女をどこかで見たことがある、と感じてしまっているのだ。既にフラッシュの影響下にあるかもしれない。急ぐ必要があった。
「バス、なかなか来ないね」
突然、少女が前を向いたまま言った。
「一緒に、座って待つ?」
ゾクリとした。小屋で見た、寄せ書きが踊り出す景色が蘇った。あの失敗を、繰り返すわけにはいかない。無言で初期化プログラムを起動し、実行しようとした時だった。肩を叩かれ、飛び上がりそうになって顔を上げると、仁が立っていた。
「何が見えてる?」
仁が尋ねた。
「少女です。浴衣姿の」
「そうか。俺には白髪の爺さんが見える。ラムネをこっちに差し出してるよ」
「爺さん?」
「俺、この人知ってる。近所に住んでた爺さんだ」
そうして仁は懐かしそうに目を細めた。また昔話が始まるのか、とうんざりしながらも、僕はこの目が妬ましいと思った。
「罠か?」
しかし予想に反し、仁は眉をひそめて言った。
「なぜそう思うんです?」
「都合が良すぎる」
仁はささやいた。
「帰りのバスって、よく遅れたんだよ。で、一人で待ってるとき、この爺さんがよく一緒になってさ。こんなふうに菓子をくれたんだ」
珍しく戸惑っているようだ。
「ただの誤作動で、こんな都合のいい映像が出てくるか?それとも —— 」
よく見ると仁の目には、僕と同じ色も滲んでいた。恐怖の色だ。
「それともこの記憶自体が、フラッシュに創られたものなのか?」
【警告。作業を急ぎなさい】
僕は自分を落ち着かせる。大丈夫。少なくともまだ、ガイドの声が届く範囲にいる。
「いずれにせよ、やるべきことは変わりません。僕らは回収するだけです」
懐に入れたケーブルを握りしめる。尖った導線の感覚だけが、いまはリアルだった。
急いで端末をバス停に接続したところで、初めて浴衣姿の少女が動いた。地面からなにかを拾い上げ、僕のほうを向く。
「お相撲、しようよ」
少女は言った。頭の奥のほうがむず痒い。僕はこの子を知っている —— そう告げる本能と、罠である、という理性がせめぎ合う。
「私は、こっち側ね」
少女の手には、二股に別れたVの字の葉があった。松葉だ。
それを見た瞬間、しおりを挟んだ本を開くように、とある日の記憶が立ち上がった。
足元に溶け残った雪があるから、春だろうか。小学校から施設への帰り道、僕はバスを待っていた。仁は補習があるとかで、今日はひとりで帰らなきゃいけない。放課後にも勉強だなんて、4年生は大変だな。
冷たいベンチに座り、足をぶらぶら揺らす。遠くのスピーカーから童謡が流れてきた。下校を促す夕方の村内放送は、ふるさと、って曲名だったろうか。帰らなきゃ。でもバスの位置を示す電光掲示板は、いつまでも表示が変わらない。
もしかしてこのまま、バスは来ないんじゃないか。もう帰れないんじゃないか。次第にそんな不安が膨らんできて、目が潤んでくる。
「また遅れてるんだ」
不意に声がしてびっくりした。隣に知らないお姉ちゃんが座っている。
「何年生?」
お姉ちゃんは尋ねる。
「いち」
僕は答えた。
「私、6年生。◼️◼️地区に住んでるんだ」
場所の名前はよく知らなかったが、仁よりも年上だ。僕はすこし安心した。
「おうち、どこ? そう、あそこの園の子なんだ。だったら私と同じバスで行けるね。◼️番のバスと◼️番のバスは、途中まで行き先が同じなんだよ」
さすが6年生。なんでも知っている。僕が感心すると、お姉ちゃんは嬉しそうにいろんなことを教えてくれた。怖い先生のこと。光るバス停のこと。夏にあるお祭りのこと。僕はお姉ちゃんの話に夢中になった。
「そうだ、これ知ってる?」
そう言ってお姉ちゃんは足元の雪を蹴散らし、尖った葉を拾い上げた。
「松の葉だよ。一年中落ちてるから、いつでも遊べるんだ。クラスの◼️◼️ちゃんは、これで指輪を作るんだよ。私も練習中」
そう言って松葉をくるくる回す。
「でも君はまだ一年生だもんね……そうだ、松葉相撲にしよう。もう一本必要だから、一緒に探そ」
言われるがまま、僕はお姉ちゃんと雪をかきわけ、松葉を探す。ベンチの下に一本を見つけた。
「で、こうやって重ねるんだ」
2本のVの字を交差させ、互いの指で端を掴む。
「引っ張り合って、千切れたほうが負け」
よーいどん!とお姉ちゃんが言って、僕らは松葉を引き合った。松の葉は意外に硬く、なかなか千切れない。二人できゃっきゃと笑い合いながら、身体を前後に揺らした。バスが来ないことなんて、もうすっかり忘れていた。尖った感触がくすぐったくて、なんだか嬉しい。
「あ!」
ブチ、という音を立てて、どちらかの葉が千切れた。
【警告。接近を禁じる】
我に返ると、まだホログラムの少女が松葉を差し出していた。僕はふらふらとその隣へ座り込む。
「おい!」
仁が僕の腕を掴んだが、その力はいつもより弱かった。僕はそっと振り解く。
「座りましょう」
僕は言った。
「罠、じゃないのか?」
仁が怪訝そうに尋ねる。
「確証はありません。ただ……」
【警告。離れろ。離れろ】
ガイドの声が、次第に高音になっていた。
「小屋で襲われたときとは違う。あのときは懐かしくて涙が出ました。嬉しくて全身が熱くなった。でもいまはそんなふうには感じません」
そう言って仁の首筋に掌を押し当てた。冷たっ!と仁が縮こまる。冷え切って感覚を失いそうなこの手が、僕の正常を示していた。
「今はもっと落ち着いてます。うまく言えないんですが」
論理が紡げなくてもどかしい。それでも仁は、黙って聞いてくれていた。
「全然劇的じゃない、些細でどうでもいいような時間が、でもたしかに自分と繋がってる。そんな感じがするんです。想像なんですが、故郷って、そういう場所だったりするんですか」
「ああ、そうだな」
仁は短く頷き、ホログラムを挟んで反対側に座った。
【やめろ!!!】
甲高い声が頭に響いた。仁は構わず続ける。
「だったらやっぱり、手えくらい合わせようや」
そう言って仁は、ホログラムの少女 —— 仁にとってはホログラムの老人へと手を伸ばした。その仕草は、まるでラムネを受け取る子どものようだ。
【警告!警告!ケィコク!】
僕も少女に向き直り、同じように手を差し伸べる。
【ククグ……グァァァァァァァァァン】
壊れたような叫びが脳内で反響し、平衡感覚が揺らいだ。全身に痛みが走る。揺れる視界の中で、僕は少女に手を重ね、松葉を受け取った。刹那、ガイドの声がかき消え、静寂が訪れた。
物音ひとつしないバス停で、ホログラムの少女が、ただこちらを見つめていた。その向こう側では、仁が嬉しそうにモグモグと口を動かしている。
「今日の学校はどうだった?」
少女が僕に尋ねた。その声をたしかに知っていた。僕は覚えてる限りを話すことにした。村を出て、その日暮らしを続けたこと。回収人になったこと。バス停のデータを —— 村の記憶を消して回ったこと。少女は、お姉ちゃんは、うんうん、と頷きながら僕の話を聞いてくれた。
そのうち話も尽きてしまって、僕らは黙ってバスを待った。雪がしんしんと降り積もって、僕らの来た足跡を埋めていった。僕も仁も、何もせず、何も言わず、ホログラムを挟んで3人、ただ白く染まりゆく世界を眺めた。こんなふうに過ごすのは、ここ10年で初めてのことだった。
どれくらい経っただろう。ふと耳慣れない電子音が、遠くから聞こえてきた。インプラントではない。僕はバス停に接続したまま、放置していた端末のことを思い出した。慌てて画面を確認すると、「除染完了」と表示されている。
直後にガガ、とノイズがして、ガイドとの通信が再開した。
【お見事です】
妙な猫撫で声で、ガイドは告げた。
【あなた方は、フラッシュの除染に成功しました】
僕は仁と顔を見合わせた。除染だって?というかこのバス停は、やはりフラッシュに感染していたのか。
【バス停が外部デバイスに接続されたことで、フラッシュは攻撃準備体制に入りました。しかしあなた方は初期化プログラムを作動しなかった。それでフラッシュは、待機体制のまま動けなかったのです】
お陰で僕らは、フラッシュに感染しなかったらしい。だとしたら、かなり危険な綱渡りをしていたことになる。今更になって、背筋が凍るような思いがした。
【そしてフラッシュには、タイムアウトによる自己消去機能が実装されていました。検知・解析を避けるための仕様と考えられます】
仁が眉を上げた。ようやく話が見えてきた。つまり、僕らが何もせず、ぼうっとバス停で待っていたことで、フラッシュは自己消去を実行したらしい。とにかく迅速に対応することが常識だったから、こんなに単純な方法を、これまで誰も試してこなかったのだ。
【この除染記録は、直ちに全エリアへ共有されます】
そう言い残し、ガイドの声はプツンと途切れた。バス停にまた静けさが戻ってくる。
「なんか、とりあえず助かったみたいだな」
仁が大きく息を吐いた。
「でもフラッシュに感染してないなら —— こいつは結局なんなんだ?」
そう言ってホログラムに視線をやる。ホログラムは相変わらず、僕らに挟まれてバスを待っていた。
「いくつか思い出したんですが」
僕は口を開いた。松葉の記憶に触れて以来、別の小さな記憶が引き出されていく感覚があった。
「もしかして、高齢者向けの見守り機能じゃないですか?ほら、近所のお婆さんがよく引っかかってた」
僕が言うと、仁はあっと声を上げた。
留山村には、認知症の高齢者がそれなりにいた。そこで徘徊する老人を見つけると、行方不明にならないよう、その場に留まらせる機能がバス停にはあったのだ。
「あの婆さんが、バス停で映像を眺めてたあれか!」
バス停に留まらせることは、昔からある徘徊者の保護手段だ。さらに映写機能を備えたバス停は、その人にとって親しい景色を映し出すことで、より強い引き留め効果を発揮していた。
「でも、なんでそれが俺たちに?」
それについても、既に仮説があった。
「バス停が、僕らのことを覚えてたとしたら、どうでしょう」
見守り機能は、何も高齢者のためだけではない。カメラを通じて村人の顔を認識し、危険な行動に助け舟を出す。
「ガイドに言われるがまま、『効率的』なルートを回る僕らの姿は、バス停たちの目には、道に迷った徘徊者のように見えたんじゃないでしょうか」
それで僕らの記録を参照して、かつてバス停を一緒に待った人々を映し出したのではないか。バス停は、そうやって僕らをこの場に留めたのではないか。警告音がシャットダウンされたのも、僕らを引き留めようとしてのことかもしれない。
「じゃあ、昨日見えた田んぼの風景も —— 」
仁が言いかけたところで、低いエンジン音が聞こえた。振り向くと、一台のバスがこちらに走ってくる。バスは次第に減速し、バス停の前で停車した。扉が開いて、ホログラムの少女がすっと立ち上がった。
このバスもまた、ホログラムだ。そうはわかっていても、僕らの目は釘付けとなった。
「じゃあ、また明日」
少女はそう言って僕の手を取り、人差し指に何かをはめた。松葉の指輪だった。少女は微笑み、バスへと乗り込んでいく。仁もその背中を見つめていた。
扉が閉まり、再びエンジンがかかった。窓越しに乗客の姿が見えた。下校する小学生の姿をしていた乗客たちは、続いて新聞を読む大人たちに変化し、それから杖を持った老人たちになった。走馬灯みたいに移り変わるバスがゆっくりと発車し始めたとき、馴染みのある姿が一瞬見えた。帽子を被って笑い合っていたのは、幼い頃の、僕と仁だった。
バスはそのまま、どこかへ走り去っていく。万華鏡のように煌めく後ろ姿に、僕らは手を振り続けた。
「俺ら、フラッシュを除染したんだよな」
バスが見えなくなってから、仁がぽつりと言った。
「ガイドはそう言ってましたね」
すると仁は、僕の背中をばしんと叩いた。
「スコア、上がるんじゃね!」
そう言って小躍りする。
「いまスコアの話しないでくださいよ」
感傷的な空気を壊されたようで、文句を言ってみたものの、内心では同じようなことを考えていた。回収人を辞めて、都市部へ移り住み、新たな人生をスタートさせる —— いつかそんな日が来るのではないか。
◇
「よく徘徊してたあの近所の婆さん、たしか犬も飼ってたよな」
「あ、そうでしたっけ」
「前通るたんびに吠えられてたよ」
笑い声が閉じた空間に反響する。鉄格子の向こうに、細い月が浮かんでいた。
ベースに帰還した僕らは、拘置所にいた。度重なる遅延は、フラッシュ除染の功績を、帳消しにするほどだったらしい。
【フラッシュが除染できれば、回収人の損失率が下がります。リソースが限られている中で、重要な打ち手です】
帰還した僕らに、ガイドはそう言った。
【しかし問題がある。待つことを前提とした除染は、時間がかかりすぎます。巡回演算の一次結果では、待機時間による遅延は、回収人の損失率を補うほどではない】
「それは本当に、合理的なんですか?」
僕は思わず言い返した。
「回収作業は、治安のためなんですよね。だったら回収人に危険が及ぶのは、本末転倒じゃないですか?」
意味がないことはわかっている。ガイドがこちらの声に反応したことなど、これまで一度もなかった。
「一体、なんのための合理性なんですか」
それでも、言わずにはいられなかった。自分に芽生えた初めての疑問を、潰したくはなかったから。
【そこで私たちは、待機時間を前提とした、新たな巡回ルートを構築中です】
案の定、ガイドは僕の言葉など無視して続けた。
【バス停Aを除染している間に、バス停Bの回収へと向かう。そうすれば回収人の損失リスクを減らしながら、待機時間も最小にできます】
機械的な音声だ。作業を終えた僕らには、声色をカスタマイズする必要もないのだろう。
【新ルートの演算は、非常に複雑なものになります。結果が出るまで、こちらでお過ごしください】
そう言って僕らは、拘置所に放り込まれたのだった。
「なあ。村祭りの日のこと、どれくらい覚えてる?」
鉄格子の外を見ながら仁が尋ねた。その声色には、微かな逡巡が含まれていた。
「あんまり。仁に手を引かれて、がむしゃらに逃げたとか、それくらいです」
あの日のことだけは、いまだにほとんど思い出せない。
「音はどうだ?何か聞こえてなかったか」
探るように尋ねてくる。
「うーん。あ、でも」
鼓膜の奥がざわざわと疼く。
「なんか、うるさかったかもしれません」
「それだよ」
仁は言った。
「フラッシュは、村の防災無線を乗っ取ったらしい」
あとで調べてわかったことなんだけどさ、と仁は続けた。
「お前と逃げてたとき、つんざくような音が聞こえたんだよ。今思うと、あれがフラッシュだったんだ」
防災無線。いつも夕方の音楽が流れていたあのスピーカーに、特殊な周波数でも乗せたのだろうか。
「でも、僕らは無事でした」
僕が言うと、仁はこちらに向き直って居住まいを正した。
「……お前が、俺の耳を塞いでくれたんだ」
絞り出すように言う。
「俺は走るのに夢中で、気が回らなかった。俺は助けられたんだよ」
「知りませんでした」
事実だった。記憶には、僕の手を引く仁の背中しか残っていない。
「でも、代わりにお前は……」
仁は言い淀んだ。僕は無言で続きを促す。
「お前の記憶がぼやけてるのは、歳のせいだけじゃない。あの時、フラッシュを浴びた影響があるのかもしれない。それがずっと気がかりだった」
ごつごつした大きな手が、小刻みに震えている。
「それで村に行ったら思い出せるんじゃないかって。留山村への派遣を、俺が志願したんだ。黙ってて悪かった」
そうだったのか、と僕は納得した。村に着いてからの仁の言動が、つながった気がする。
「でも結局、こんな場所に入れられちまってさ」
無機質な空間を見渡し、仁は自嘲気味に笑った。
「新しい巡回ルート、とかガイドは言ってたよな。それってつまり、やることが増えて、もっと急かされるんじゃないのか。結局、自分で自分の首を締めただけだ」
仁が項垂れたので、僕はその背中を思い切り叩いた。痛え、と仁がうめく。
「おかげで、時間ができました」
月明かりに指をかざす。導線で作った指輪が、黄金に光った。
世界は結局、待たせてはくれない。だが少なくとも、拘置所にいる間だけは、こうしてゆっくり話ができる。この時間を手に入れられただけで、いまは満足だった。
「だからさっきの続きを聞かせてください。近所のお婆さんの、犬がなんでしたっけ?」
仁が顔を上げた。目の下には深い隈が刻まれている。それでもニヤリと、悪ガキのような顔をして言う。
「……知ってるか?婆さんが犬の散歩に行ったら、犬だけ先に帰ってきたって話」
「なんですか、それ」
取るに足らない村の記憶。僕らはそれをひとつひとつ、確かめ合うように語り始める。
文字数:15334