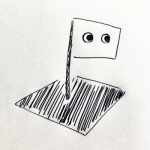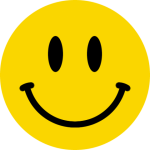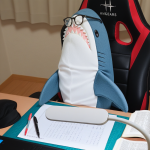梗 概
東京遷宮
ある日、東京が大移動を始めた —
2075年、急激な気候変動とインフラの老朽化により、あらゆる建築物にバイオナノマシン「常世」が埋め込まれる。生きた家が人々を守り、生活を記憶する社会基盤となった。各地域の建物同士は、菌糸ネットワークを模した地中ネットで密に接続され、いくつもの相互監視的なムラ社会が誕生。それらを管理局が統制することで、東京は成り立っていた。
代々続く宮大工の家に生まれた宮代聖一は、伝統的な技術を活かせないまま、ナノ建築の保守作業で生計を立てている。「常世」を拒否した父親のせいで村八分にされ、家庭崩壊した過去を持つ聖一。変わりたいと願うが、家には亡くなった母親の暗い記憶が宿っており、聖一を精神的・物理的に呪縛していた。
突如、東京に異変が起こる。生きた家たちが、時速1kmで一斉に西進を始めたのだ。管理局はこれを、定住を拒否する遊牧民族「天女」のサイバー攻撃だと断定。「常世」の強制停止を試みるも逆効果で、建築物たちは散り散りの方角へ進み始め、東京が切り裂かれていく。そして聖一の家だけが、動きを止めた。母の記憶に縛られた家は変化を拒み、取り残されたのだった。
混乱の中で聖一は、街が自らの意思で移動していることに気づく。「常世」のない家で育ち、宮大工の技能を継いだ聖一には、まるで建物の声が聴こえるような、常人離れした感覚が備わっていた。
都市はどこかへ向かおうとしている。だが管理局に妨害され、引き裂かれている。街の悲鳴に聖一は激しい頭痛を覚え、その痛みを取り残された自分と母にも重ねる。聖一は都市と自らを解放すべく、街の中心部へと向かう。
そこで聖一は「天女」のリーダーを名乗る謎の少女に出会う。自由奔放な態度に翻弄されつつも、彼女の導きによって聖一は「常世」の中枢へ入り込む。そして都市という巨大な家の構造を読み、材木の重心を探るように、「常世」の調律を行なう。
調律の過程で、この大移動が暴走ではないことを聖一は悟る。これは蓄積された膨大な記憶によって深い傷を抱えた都市が、記憶という穢れを洗い流し、生まれ変わるための「式年遷宮」の儀式だった。行進を止めるのではなく、先導することを聖一は選ぶ。
衝突寸前だった建築物たちは、まるで一つの群れのように調和を取り戻し、聖一の家も再起動する。地平線を滑るように巡礼する街を眺めながら、少女は満足げに仲間の元へ去って行った。「天女」にとっては、移動そのものが祝福だったのだ。
5日間かけて富士北麓に辿り着いた家たちは、樹海に広がる地中の菌糸ネットワークと接続し、記憶の穢れを落としていく。この遷宮によって聖一は母の呪縛から解放され、また母自身の魂も救われたように感じる。そして新しい土地に根を張る家で、引き続き暮らすことを決意する。それは放浪を続ける天女とはまた異なる、「変化によって不変を保つ」という宮大工流の解放の形だった。
文字数:1197
内容に関するアピール
ヌーの大移動は、百万頭を超える群れが、数百kmを移動する現象だ。ヌーが旅を続けることで草原の生態系は守られ、踏み締められた土壌は豊かになる。川渡りでは数十万頭が溺死するが、その死骸さえも川の貴重な栄養分になるという。
翻って人類も、その歴史の99%においては移動を続けてきた。ほんの1万年前に始まった定住は人類を急激に繁栄させたが、一方で環境破壊や格差を生み出し、生物としての遊動性を喪失させた。
そこで50年後の未来では、再び「移動」への揺り戻しが起き、定住と移動のあいだくらいの生活へと(半強制的に)シフトするのではないか。全く新しい住まいの形が現れるのではないか。そんな想像から、どこか日本的・神話的な姿を帯びながら、移動する都市の群れを書きたいと思いました。
なお作中の「天女」は実在するボーダレスな民族・ロマをイメージしており、実作化の際は既成概念の外側にある象徴として描く予定です。
文字数:394
帰巣する寺
金剛寺不動堂が移動している、という報せを受け、現場に到着したのは早朝のことだった。
「高幡不動尊」の通称で知られる金剛寺は、東京都日野市にある真言宗の寺院だ。境内の入り口すぐ、不動明王を安置する不動堂には安っぽい蛍光色のテープが巻かれ、立ち入り禁止となっていた。
第一発見者の僧侶によれば、夜中に見回りをしていたところ、異音が聞こえた。不思議に思って近寄ってみると、正面を見据えていたはずの不動明王が斜めを向いており、慌てて通報したのだという。
「お不動はんが動くとは、こりゃ見事」
巨漢の男が膝をつき、太い指で土をなぞっている。地面には建物ごと引きずったような跡があった。
「感心してる場合じゃないですよ、勝俣さん。なにかあったら誰が責任を……」
役所の職員が男に言う。僕はそれを横目に、指矩を不動堂の土台に当てた。L字型の定規は、幅10メートル、高さ12メートルを誇るこの建物が、きっかり30度向きを変えたことを示している。
「宮代さん、問題ないでしょうか」
職員が尋ねてきて、僕は不動堂を見上げる。焦茶色の伽藍は室町らしい、質実剛健な佇まいだ。
「はい、今のところは問題ないかと」
「でも700年前の建物ですよ。損傷がないはずが……」
「700年前だからですよ。いまのビルなんかと違って、古い木造の寺はよくしなる。地中にも固定されてない。だから衝撃ごと逃がすんです。地震で寺が数センチ移動した、なんて例もあるくらいで」
まあその地震が起きてないんですが、と言いかけて口を閉じた。宮大工としての僕の役割は、あくまで建物の安全性を確認することだ。
「ナノマシンの調子はどや?」
土を触っていた巨漢が、立ち上がって言った。ピチピチのシャツに膨らんだジーンズ。元トップ研究者とは思えない風貌をしたこの男は、名を勝俣修という。
「問題ないようですけど」
僕はノミを傾けて柱に当て、すこし力を入れた。僅かに表皮が削れる。
「というか建築用のナノマシンは、勝俣さんの専門でしょう」
柱の表皮を撫でると、傷はすっかり消えていた。
建築用のナノマシン —— 正式名称を自律型構造修復材という —— は、2040年代に開発された自己修復型システムのことだ。植物性由来のバイオナノマシンを注入すると、建物の傷や歪みを検知し、自動で修復する。老朽化するインフラの救世主と目されたものの、莫大な製造コストから普及が進まなかった。そこで代わりに注目されたのが、国の重要文化財だ。中でも金剛寺は都内最古の文化財として、最初にナノマシンの「接種」を受けていた。
「これはワシのやない。ワシが最後までみとったら、こんな実装にはせん」
勝俣がメガネを触りながら言った。小さすぎるフレームが顔に食い込むこの男こそ、ナノマシンの生みの親の一人であった。
「困ったときだけ泣きつきよって、と言いたいところやが、正直めっちゃ興味深い。ナノマシンの誤作動か?いや……」
ナノマシンの完成間際、勝俣は素行の悪さが問題となり、独立研究法人の技研から追放されたらしい。研究資金を私的に流用した、なんてきな臭い噂も耳にした。
「終わりましたよ。現状は問題ありません」
僕は大工道具を仕舞いながら言う。
「この先どうするかは、お偉いさんたちに任せます」
「投げやりやな。まだ若いいうても、日本最後の宮大工やろ」
勝俣が二重顎で僕を指した。
「あ、さてはお前、ナノマシンに問題が起こって内心喜んどるんか?」
そう言って大きな口を歪ませる。
「宮代聖一、やったな。親父によう似とる」
父親の話を持ち出されて、僕の身体は思わず硬直した。
「お前の親父も、ナノマシンには猛反対しとったで。そんな得体の知れんもん入れたら木が泣く、とか言うてな。木が泣くかい」
勝俣は饒舌に続ける。
「それで干されたんには同情するけど、ナノマシンに当たるのは筋違いや」
「僕は別に」
「時代に取り残された仕事がなくなるのは、当然や。そうやって新陳代謝が起こる。お前もさっさと見切りつけて……」
「原因がわからないからって、僕に当たるのは筋違いですよ」
手に持ったノミを道具袋にしまう。気付かぬうちによほど強く握り締めていたようで、手がじんじんと痺れた。
「またなにかあったら来ますから」
そう言い残して入り口に向かうと、香炉から線香の煙がふっと巻きついてきた。
「またなにか」のタイミングは、しかし思ったよりすぐに訪れた。三日後に再び金剛寺を訪れた僕は、横向きになった土方歳三像がトラックに乗せられ、撤去されゆくのを眺めていた。ここを寺が通る可能性があるためだ。
金剛寺不動堂はあれからも動き続けていた。一日数センチではあったが徐々に角度を変え、いまでは境内入り口、仁王門を向いている。外へ出ようとしているみたいだと、僕は思った。
「寺の礎石から僅かな揺れが観測された。人間では感知できんレベルや」
1時間ほど前。境内奥の客殿に設置されたモニター越しに、勝俣はそう説明した。
「で、やっぱりナノマシンが揺れの犯人やった」
勝俣の背景はゴミ屋敷のように散乱している。技研を退職後、独立したと聞いていたが、自宅だろうか。
「知っての通り、ナノマシンの素材は、導電性セルロースナノファイバー……要は木から作った人工筋肉みたいなもんやけど、こいつが寺に微弱な電流を流しとる。それで建材内のセルロースの結晶構造が変化して、振動が起きる。圧電効果やな」
僕はかつて、大地震で移動したという寺のことを思い出す。
「秒あたり数万回の非対称振動を起こし、摩擦係数を極限まで減らして、一方向へ推進力を生み出すことで……」
そう言って勝俣は、手元にあったマグカップを横に滑らせた。
「滑るように移動するわけや」
「なぜナノマシンは、寺を動かすんでしょうか」
「知らんがな」
菓子パンの袋を乱暴に開けながら勝俣が言う。
「重要なのは、動いとるいうことや。振動頻度も上がっとる。このままやと、2週間後には日に100メートル動くで」
「100メートルって……寺の周りは住宅街ですよ」
「それで技研の奴らは、寺の完全解体を国に進言したらしい」
「完全解体だって?」
思わず大声が出た。
「騒ぎになる前に、ナノマシンの誤作動を揉み消したいんやろな」
僕は頭を抱えた。そんなくだらない理由で、700年の文化財を壊されてはたまらない。
「江戸のならともかく、中世の寺院は現代でも再現できないような、精巧な技術が使われてるんです。全部バラしたら、二度と戻せませんよ」
「心配すんな。どうせ奴らにそんな権限あらへん。そもそも一度接種を受けた建物には、何兆個ものナノマシンが行き渡っとる。バラバラにしたところで、各部品が移動を続けるだけや」
そう言って勝俣は菓子パンを口にねじ込む。クチャクチャと咀嚼音が鳴った。
「クレーンで寺ごと持ち上げる、なんて案も出とるがまあ無理やろ。数百トンはあるし、第一、ナノマシンを制御できない状況で無理やり引き剥がしたら……」
刹那、入り口の方角から地響きのような音がした。通話を保留にし、慌てて駆け寄ると、作業員たちが尻餅をついている。寺が、側溝を乗り越えたのだという。
まるで寺が身震いしたようだった、と作業員の一人は語った。金剛寺はブルブル震えた後、音を立てながら一気に段差を乗り越えたらしい。建物からは、まだ小さく軋む音が響いていた。
そんなわけで急遽、こうして進路にある障害物を、すべて撤去することになったのだ。幸い「接種済み」なのは不動堂だけなので、ほかの建物はまだ取り扱いやすい。
「ええか、完全解体なんてワシは許さへん」
あらかたの作業を終えて、通話に戻ると勝俣はそう言った。現場の報告を受けて、さっきよりも興奮しているようだ。
「段差を秒で越えるなんて、予想以上や。このバケモンは、いけるところまで移動させる」
「僕も賛成です。こんな貴重な文化財は……」
「それはどうでもええ」
勝俣が顔の前で手を振った。
「ワシが寺を動かしたいのは、貴重なサンプルやからや。建物が自分で動くなんて、聞いたことあらへん。障害物全部壊してでも、時間を稼ぐ価値がある」
口元に泡をつくりながらまくし立てる。
「解体なんて、やろう思えばいつでもできる。最悪、重機で破壊すりゃええやろ」
言い返したいことは山ほどあるが、少なくとも寺はまだ解体されない。利害が一致している以上、この男の神経を逆撫ですべきではない、と僕は自分を落ち着けた。
「ただ時間を稼ぐって言ったって、限度がありますよ。寺が外に出ようとしてるのなら、仁王門の横幅が足りないですし」
「お前、ほんまに大工か?」
勝俣は鼻を鳴らして言った。
「門を通る必要あらへん。その横に石垣あるやろ。あれぶっ壊せ。手前の土産物屋も解体してまえ」
後方から地響きがした。また寺が移動したのだろうか。
果たしてあの寺が、僕らの意図通りに進むのか。道路に出たとして、そのあとはどうするのか? そんな疑問をぶつける猶予はなかった。僕は金剛寺の設計図を床に広げた。寺は胴体である母屋と、それよりはるかに大きな大屋根で構成されている。屋根は入母屋造と呼ばれる末広がりの形をしており、軒先が天に向かって緩やかに反り返っていた。道具袋から墨差しを取り出し、寺の重心を見極めるための基準線を引いていく。
金剛寺は、親父が最後に携わった仕事場だ。その寺がいま、自らの殻を破って動き出そうとしている。寺の行き先を、僕が見届けなければならない気がした。
◇
ズズ、と音がして僕は顔を上げた。寺がまた少し移動している。その速度は、もはや肉眼で確認できるほどまでに上がっていた。
「帰巣本能、やて」
ニュース映像を見ながら、勝俣が鼻で笑った。画面の中では、技研の局長が記者会見を行っている。
『え〜、木の細胞や年輪には、育った森の環境が刻まれています。ナノマシンはその記憶を読んで、ヒノキの産地……奥多摩地方に帰ろうとしているのではないかと』
技研の職員の説明に、取材陣がざわついた。
『開発段階で分からなかったのか!』
『他の寺は大丈夫なんですか!?』
次々と野次が飛ぶ。
『木材の古さが、この現象を指数関数的に引き上げてしまい….他の寺にはいまのところ異常は見られず……』
しどろもどろな姿を見て、ざまあみろ、と勝俣は愉快そうだ。
「要は実装ミスやろ。ナノマシンの自己修復機能が、過剰反応しとるんや」
勝俣曰く、ナノマシンは都会の大気と土壌を、寺院にとって有害な環境 —— さらに言えば「損傷」そのものだと判断した。それで豊かな自然に囲まれたヒノキの産地へと、寺院を移動させようとしているらしい。荒唐無稽な話に思えるが、木材の寿命は環境に左右される。一流の宮大工は、木を見ればすぐにその産地を当てられるほどだ。育った山が一番だ、という点だけ見れば、宮大工としても同意だった。もちろん、寺が自分でそこへ帰るなんて信じられないが。
「ナノマシンは、どうやって産地の方角まで把握してるんでしょう?」
僕が尋ねると、勝俣はぬぅと唸った。
「そこが正直まだ謎やねんけどな。ただ磁気生物学では、渡り鳥やイルカが、どうやって目的地を正確に把握できるんか、っちゅうのが研究されとる。その中で、植物も磁場の記憶 —— つまり座標データを持っとる、なんて説もあるんや」
「木に磁気が?」
「正確には、木が土壌から取り込んだ磁気や。木が育つ過程で、吸収した鉄鉱物からバイオマグネタイトいう磁石が合成されて、それが木に残留すんねん。普通は微々たる量しかないんやけど、樹齢千年を超えるヒノキなら、話が変わってくるんかもな」
木は土に育てられる。土に磁気があるなら、木にあってもおかしくはない。僕はヒノキの切り株に、小さなコンパスが埋め込まれている姿を想像する。
「ま、そんなちっぽけな手がかりで方角を特定する、ナノマシンの能力が予想以上やったってことやな。さすがワシの考えた技術」
「あれはワシのやない、って言ってたじゃないですか」
「だからそれは実装の話や……お、なんか盛り上がっとるで」
そう言って勝俣は記者会見の音量を上げた。
『ナノマシンを止めるようなワクチンをつくれないんですか!?』
記者の質問に、できるかい!と勝俣が先に答える。ナノマシンの研究スパンが十年単位であることくらい、僕でも知っていた。
『住民に被害が出る前に、寺を取り壊すべきという声もありますが!?』
『文化財ですし……えー、取り壊す判断はまだ待ちたいと』
ダウトや、と勝俣が呟いた。
「ほんまはさっさと壊したいんやろ。でも国が許可を出さへん」
技研と国は、どうやら一枚岩ではないらしい。
『待ちたいって、いつまで!?』
『あー……寺は境内から出るのを望んでいるのではないか、と思います。なんと言いますか、結界、つまり人間の定めた神域から、脱することが目的ではないかと。だとすれば、道路に出た時点で、動きは止まるはずでして….』
ふざけるな、とまた野次が飛ぶ。
『そんなの、ただの憶測じゃないか!』
せやせや、と勝俣が笑う。
「その憶測が外れたらどうするんですか?」
僕が尋ねると、勝俣は当然のように
「解体するしかないやろ」
と言い、モニターの電源を落とした。
「そろそろ出よる。見に行こや」
境内入り口では、仁王門以外の石垣がすべて取り壊され、寺が通れるよう解放されていた。ナノマシンには自己防衛のため、障害物を避ける習性があるらしい。迷路に入れられた蟻のように、自分で出口を見つけられるのだという。ならばその習性を利用して、安全に外へ出そうという試みだった。
僕たちが入り口に着いた頃には、まさにその思惑通り、金剛寺が道路へ出ようとするところだった。道路では車両の侵入が禁止され、代わりに報道陣がひしめき合っている。なめくじのような速度で仁王門を迂回していく金剛寺に、野次馬から拍手が起こった。
「なんや、えらい嬉しそうやん」
勝俣に言われて初めて、僕は自分が興奮していたことに気づいた。
「こんだけナノマシンがめちゃくちゃやれば、そら溜飲も下がるよな」
「違いますよ」
僕は否定する。実のところ、僕はナノマシンに、恨みなど抱いていなかった。むしろこれまで、助けられてきたとすら思っている。ナノマシンは当初、奈良や京都の寺に導入される予定だったが、保守的な関西仏教会がそれを許さず、代わりに東京に白羽の矢が立った。それで木材建築の専門家として、僕に声がかかったのだ。プロジェクトは10年に及び、仕事には困らなかった。農業高校を出て以来、宮大工の修行しかしてこなかった僕が、この時代に食い繋いで来れたのは、皮肉にもナノマシンのお陰だった。
「まもなく道路に出ます!」
レポーターが叫ぶと、金剛寺がひときわ大きな音を立てた。
そもそも、ひとつの寺の大規模修繕は、200年に一度で足りる。それだけ昔の寺は、しなやかで強い。人間の寿命よりはるかに長い時間を、職人の技術継承だけで維持するのが無理筋なのだ。ナノマシンという、人手に頼らない技術にそれを託すのは、自然な成り行きだと考えていた。
「金剛寺、脱出!」
ズシン、と鈍い音がして、ついに巨大な木造寺院が道路へと出た。700年過ごした神域を、自ら脱出したのだ。
僕は思わず歓声を上げる。僕が興奮していたのは、境内を出ようとする寺に、親父の姿を重ねたからだ。
親父の思い出は少ない。ぼんやり覚えているのは、僕の10歳の誕生日のこと。珍しく親父が家に帰ってきたと思ったら、そのまま仕事場へ連れて行かれた。「槌は腕力で打つんじゃない。ヘソで打つんだ」と言ったきり、そのまま作業に没頭して、話してくれなくなった。仕事場で過ごす時間だけが、僕と親父の唯一の接点だった。親父の人生は、代々続く宮大工の血に縛られていたのだと思う。金剛寺が外を飛び出したのをみて、親父がそんな呪縛から、ようやく解放されたような気がしたのだ。
寺が道路に出てしばらく、誰もが固唾を飲んで、移動が終わったかどうかを見守っていた。1分が経ち、職員の一人が「やったぞ!」と叫んで駆け寄った瞬間、ズドン、と爆発するような音がした。職員は尻餅をつき、畏敬の表情で寺を見上げた。
「こりゃすごい」
勝俣の両眼がぎょろりと輝いた。金剛寺は器用に右折し、川崎街道を進み始めていた。
◇
大屋根から見下ろす眺めは壮観だった。道路には交通規制が敷かれ、信号や標識が一時的に撤去されている。街頭には観衆たちが詰めかけ、正月の箱根駅伝みたいだと僕は思った。観衆に見守られながら、ランナーたる金剛寺不動堂がずるずる前進していく。隊列を組んだ警官たちが防護盾を手に、寺の進路を誘導していた。
道路に出ても、破壊はしない。ただし部分的な解体なら許容する —— それが国の判断だった。道幅は金剛寺よりも広いものの、しばらく行くと多摩モノレールの高架が待ち構えている。高架下の全高は金剛寺よりも低い。そこで寺を部分的に解体し、高架を通れるサイズまで縮小させるプランが採用された。
僕は滑り落ちないよう、銅瓦を伝って慎重に大屋根から降りていく。屋根は垂木と呼ばれる木材によって美しく反り返っており、この反りに職人の美学が現れると親父は語っていた。反りが小さすぎては見栄えが悪いし、大きすぎても粋ではない。宮大工たちは垂木に向き合いながら、理想の美を追求し続けた。
梁の上にのぼり、ヒノキの柱に触れる。「木と話せ」が現場での親父の口癖でもあった。木は強度にも曲がり方にもそれぞれ癖がある。だから昔の木造建築では、材木の寸法すら規格化されていない。鋸で均一に切るのではなく、木と話しながら、木目に合わせて割っていくのだと親父は言った。木に逆らわず、活かすことが、寺に永い命を与えるのだと。
金剛寺の円柱にも、それぞれまったく異なった木目が見て取れた。それぞれの柱は、出三斗組式で梁と接続されている。僕はノミを挿し、その木組みを緩めていく。
当初国から依頼された計画は、大屋根と母屋を切り離す —— つまり頭部と胴体を真っ二つに切断するというものだった。現代の家屋ならそれで済むかも知れない。しかし材木の調和によって成り立つ金剛寺を安易に切断すると、バランスが崩れ、伽藍ごと崩壊してしまう恐れがあった。そこで僕は代替案を提示した。
「高架下まで、あと4時間や。大丈夫なんか」
デバイスから勝俣の声がする。さすがに緊張しているのか、強張った声色に僕はちょっと可笑しくなる。
「やれることはやりましたよ」
寺の木組みの内部では、凹凸に加工された木材が、釘を使うことなく結びついている。それをロックする栓と貫は、すでにほとんど除去してあった。僕は道具袋から、掛矢と呼ばれる大型の槌を取り出す。医者が患者を触診するみたいに、木組みを叩いては反応を確かめ、寺の重心を最終確認した。
「あと2時間」
勝俣の声は既に遠くなっていた。全神経が木に注がれていた。木目、反り、強度。木と話せば話すほど、周りの景色が消えていき、ヒノキと僕だけが残る。
木材としてのヒノキの寿命は、千年を越える。切り出されてもなお、木は生き続けているのだ。だからヒノキが生まれ故郷に帰れることを、実は歓迎すべきではないか。それをサポートすることが、最後の宮大工としての、自分の役割ではないかと、そう思い始めていた。
息を吐き、意識を研ぎ澄ます。ヒノキと僕だけの世界に、中世の宮大工たちが立ち現れる。なぜこの木を選び、なぜこの箇所に組んだのか。込められた意図を読み、槌を打ち、反応を見る。700年を跨いだ会話が、右手の骨に響いてくる。
親父もまた、この時間の重みと戦っていたのだろう。巨木に触れるだけで、その重積に押しつぶされそうになる。だが宮代家の職人たちは、代々それを乗り越えてきた。今度はそのバトンを、ナノマシンに託すときだ。目には見えない小さな職人たちが、きっと金剛寺に永い命を与えてくれる。僕や勝俣や、この同時代に生きる誰よりも、永い命を。
「がんばれ!」
子どもの声がして我に返った。高架下が目と鼻の先に迫っていた。街頭の観衆が、手を振って寺院を応援しているのが見えた。まるで優勝パレードみたいな大騒ぎだ。国が寺の延命を決めたのも、この大衆心理に配慮したものだと言われている。
僕は深呼吸をし、掛矢を振りかぶる。そしてヘソに力をこめて、円柱の頭貫を固定する楔を、思いきり叩き飛ばした。そのまま飛び降りて道路へ出る。駆け寄ってきた勝俣が何かを言いかけた瞬間、金剛寺からバコン、と大きな破裂音がした。
まず母屋の円柱が、ゆっくり斜めに倒れていく。次に大屋根の垂木が天に反ったまま沈んでいった。メリメリと低音を響かせながら、上から押しつぶされるように、寺がハの字に広がっていく。木屑が舞い、古い木材の香りが漂う。大丈夫だと、僕は自分に言い聞かせる。
バキバキバキ、と金剛寺が呻いた。いまにも崩壊しそうな姿に、観衆から悲鳴があがる。しかしそこでぴたりと変形が止んだ。そして限界まで低くなった金剛寺は、そのまま高架下を通過していく。まるで自ら身を屈めて、高架をくぐり抜けていくようだった。
僕は思わずへたり込んだ。ナノマシンの自己修復機能と、寺の重みが釣り合うところまで重心を下げる —— そんな提案をした時は、ここまでうまくいくとは思っていなかった。
「ええ顔やん」
勝俣が肩を叩いてきた。路上で喝采が沸いた。ハの字に歪んだ金剛寺を、僕は恍惚と見上げた。これまで見た中で、もっとも美しい姿だと思った。
◇
川崎街道を10日かけて進んだ金剛寺不動堂は、境内から3km離れた野猿街道へと合流。そして出発から22日目、河川敷から多摩川へと入っていった。
お偉いさんたちが議論した結果、水深の浅い多摩川が、道路に比べると障壁の少ないルートだと結論づけられたらしい。水流によって勢いはやや衰えたものの、たしかに寺は力強く川を遡上している。
河川敷には、連日多くの人々が詰めかけていた。金剛寺が高架下を通過する映像が、世界中で大反響を呼んだのがきっかけだった。「日本の誇る匠の技術」なんて見出しの報道が、毎日のように飛び交った。そして2週間後、新たに判明した事実が、この熱狂をさらに加速させる。寺が通り過ぎた道路では、コンクリートのひび割れが綺麗に修復されていることがわかったのだ。勝俣はナノマシンの波及効果だろうと推測していたが、これが「聖進」だと話題になり、ご利益に預かろうと人が殺到した。
僕はこの熱狂を、日に日に冷めた目で眺めるようになっていた。世間というのは、ここまで態度を変えるものなのか。時代遅れだと後ろ指を刺されながら、必死に受け継いできた宮大工の技能を、まるで食い物にされているように思えた —— のは、おそらく僕が自分自身に対して、同じことを感じているからだろう。
寺が揺れたので、外陣の板敷に腰を下ろした。本来は礼拝用の荘厳な空間だが、寺が身を屈めた影響で、どの円柱も奇妙に傾いている。川に架かる橋をくぐるためには、この姿勢をまだ保つ必要があった。
雷の音が聞こえる。今日は天候が荒れていた。南で発生した台風の影響だというが、にもかかわらず桟唐戸の隙間から黒山の人だかりが見えた。それが僕の気持ちを一層と冷えさせる。
ふと思う。自分はただ、楽になりたかっただけではないか。ナノマシンで食い繋いできたことや、宮大工の技術を途絶えさせてしまうこと。そんな後ろめたさに耐えきれなくて、寺の移動を助けることが自分の使命であると、思い込みたかっただけではないか。寺を利用しているという意味では、河川敷でカメラを掲げている連中と、そう変わらないのかもしれない。
「お不動はんが無事で何よりや。窮屈そうやけど」
勝俣がのそりと奥から出てきた。不動明王の安置された、内陣で寝ていたという。
「そういやお不動はんって、大日如来が人間を叱るために変身した姿らしいな。それであんな怖い顔しとるんか」
口をもしゃもしゃ動かしながら言う。寝起きにもかからず、ドーナツを頬張っていた。
「この嵐も、寺を動かすなんて悪行に対する、ワシらへの神罰なんかもな。あ、神やなくて仏か」
「飲食禁止ですよ」
「なんや、欲しいんかい」
勝俣がドーナツを半分に折ると、破片がポロポロと板敷に落ちた。こぼさないで下さい、と言いながらも、僕は受け取ってそれを頬張る。甘ったるい味が口の中に広がった。
「国が、金剛寺の取り壊しを命じよった」
不意に勝俣が言って、僕は思わず咳き込んだ。こぼさないで下さい、と勝俣が軽口を返す。
「どういうことですか!?」
「台風の進路が変わったんや。3日後に上陸する。激流を寺は渡りきれへん、との判断や」
「そんなの、やってみないと分からないでしょう!」
「もし寺が流されたら、流木で二次災害が起きかねん。近隣住民の安全を第一に……ってのは表向きの理由や。実際は洪水で無惨に流されるより、自ら解体してもうた方が面子が保たれるんやろ」
「いまさら面子って」
「政治なんてそんなもんや。この騒ぎには、世界中が注目しとる。ここまで寺を連れてきて、自然の脅威の前に勇退すれば、いっぱしの物語になるやろ」
僕は力が抜けて座り込む。だとしたらこんな場所にまで寺は、僕は、一体なんのためにやってきたのか。
「技研は?」
「技研も賛同しとる。実証データも集まったし、他の寺のこともあるし、ちょうどいい引き際やろ」
「じゃあ……勝俣さんは?」
僕は目の前の太った男をじっと見つめた。
「勝俣さんは、どうしたいんです?」
「ワシか?」
勝俣はにやりと口角を上げる。
「もちろん、糞食らえや」
口の間から、茶色く変色したすきっ歯がのぞいた。
「そもそも激流を渡れへんのは、ナノマシンの実装が甘いからや。自然の脅威?神罰? アホ言え。ナノマシンは、そんなもんに負けん。ワシが証明したる」
「証明するって、どうやって?」
「寺にナノマシンを追加接種する。ただし技研の製品やなく、ワシが最後まで実装した、本来のナノマシンをな」
僕は呆気にとられた。この災厄を引き起こしたナノマシンを、追加接種するだって?それこそ仏に背くような悪行ではないのか。
「ナノマシンの追加で振動回数を増やし、推進力を上げる。ワシが作った製品なら問題は起きへん。研究資金ちょろまかしてまで、手ぇかけて育てた子らや」
愛おしそうに言うと勝俣は立ち上がり、模造紙を板敷に広げた。金剛寺が描かれた古い設計図だった。勝俣は寺の土台部分に、鉛筆で線を引いていく。
「で、最小量で最大の効果が出るポイントに打ちたいんやけど。どの柱脚がいいと思う?技術者としての意見を……」
「うるさい」
僕が言うと、勝俣が驚いたように顔を上げた。
「何が技術者としての意見だ。その技術を途絶えさせたのはあんたらだろ」
言葉が溢れてくる。
「あんたらはいつもそうだ。取り残された側のことなんて興味はない。面子がどうとか、誰の成果だとか、そんな話ばかり」
すらすらと罵り文句が出てくるのは、本心ではないからだ。本心であったなら、どれだけ良かったか。僕はため息をついて続ける。
「…..とか言える職人に、なりたかったよ。実際のところ、僕はあんたみたいに変革する側にも、親父みたいに取り残される側にも、なる勇気はなかった。今回の件を隠れ蓑にして、その場を凌いでるだけ。そんな自分が許せないんですよ」
なんて情けないんだろうと思う。でも日本の匠だなんて持て囃されるよりは、よっぽど自分のことを的確に表現している気がした。
「ダウトや」
黙ったまま聞いていた勝俣が、口を開いた。
「それもまた、本心の隠れ蓑やろ」
一瞬、何を言われたのか分からなかった。
「何枚重ねの蓑やねん。暑いやろ」
冗談めいた口調とは裏腹に、サイズの合っていないメガネの奥から、鋭い両眼が射抜いてくる。
「高架下をくぐった時を思い出せ。伝統がどうとか変革がどうとか、そんな小難しいこと考えとったか?」
勝俣の視線が苦しい。しかしなぜか目を離すことができなかった。僕は金剛寺の屋根裏で、楔を叩き飛ばした瞬間を思い出す。世界が僕と木だけになった瞬間。700年を跨いだ瞬間。
「ワシにはわかる。お前の本心はもっとシンプルや。当てたろか」
そして寺が身を屈めたときに覚えた、身体中を駆けずり回るような快感。
「お前は、自分の技術に酔うとる」
寺の外で稲光が走った。同時に、僕の身体も雷に打たれたようだった。ああ、そうだ。そうだったのだ。
「自分の技術を発揮できるんが嬉しい。自分の力で、寺を操れるんが気持ちがいい。お前を動かしとるんは、そんなエゴイズムや。お前は、自分の技術でこの寺がどこまで行けるのか、見届けたくてたまらんねや」
そう言うと勝俣は設計図に向き直り、柱脚にまた線を引き始めた。
「ワシもそうや。自分の作ったものの、行く末を見たい。ワシとお前は、根っこでは同じや」
寺が大きく揺れ、思わず足元がふらついた。水量が増しているのだろうか。揺れで勝俣の線も歪んだ。外から悲鳴とも歓声ともつかぬ声が聞こえてくる。
「……河川敷の連中と同じってことですよね」
僕はようやく悟っていた。観衆を見て白けたのは、寺の移動に興奮する、自分自身がそこに写っていたからだ。
「何言うとんねん。全然違うやろ」
しかし勝俣はあっさりと否定する。
「あいつらは傍観しとるだけや」
歪んだ線を消し、もう丁寧に一度引き直す。
「ワシがお前を技術者言うたんは、エゴが突き抜けとるからや。こんな状況、普通の人間やったらとっくに逃げ出しとる。でも高架下でのお前は、うっとりした目をしとった。まるで絶世の美女を眺めるみたいにな。はっきり言って異常や。でも技術者は異常やないとあかん」
また寺が揺れ、今度は設計図がずれる。勝俣は悪態をつきながら、古紙を広げ直す。
「…..大問題になりますよ」
「知らんがな」
勝俣はまた線を引く。四つん這いの体勢がきついのか、息が上がっていた。
「世間がどうとか社会責任がどうとか、気にする技術者は二流や。んな不味いもん、ぜんぶ政治家に食わせたれ」
また線が歪む。引く。歪む。引く。何度も、何度も、何度も。
僕は10歳の誕生日に見た、親父の仕事姿を思い出していた。親父の人生を突き動かしたのは、本当に宮大工としての責任感だったのか。そうではない。あのときの親父の目は、まるで木に取り憑かれたように、妖しく光っていた。
「小屋組はどうでしょう」
気づけば僕は、そう提案していた。
「たしかに寺を支えているのは柱脚です。でも金剛寺の重心は、母屋ではなく、もっと高いところ —— 大屋根の内部の小屋組にある。で、このしなやかな寺は、ちょっとくらいの振動はいなしてしまう。どうせ揺らすなら、寺の『ヘソ』をピンポイントで突いた方が、効率的に速度を上げられると思います」
確証があったわけではない。だがこれまで木と話してきた膨大な時間が、僕にそう告げていた。勝俣は少し考えたあと、
「接種作業もできるか?」
と言った。僕は頷き、ナノマシンを受け取って、梯子で小屋組へと登る。最大の効果を発揮する箇所を、ピンポイントに見極める必要があった。木組みをひとつひとつ、玄翁と呼ばれる小ぶりの槌で叩きながら、返ってきた音に耳を澄ます。
迷いに迷った末、ここだと決めた箇所にノミを差し込み、接続点である「仕口」を覗いたときだった。柱と梁の間に、斜めに組まれた木片を見つけた。この三角形は、トラス構造と呼ばれる技法だ。
木片は他の建材より随分と新しい。数十年くらい前のものだろうか。時期的に、親父が組んだと考えて間違いないだろう。しかし建物をがっちりと固めてしまうトラス構造は、西洋建築の技法であり、あえて遊びをつくる和建築とは真逆の思想を持つ。中世の寺院に適用した例なんて、聞いたことがない。
訝しんだ僕は、斜めに入った木片を軽く叩いた。すると木片がくるりと回った。木片は固定されず、ただ隙間に挟まっているだけだった。その瞬間、自分の中に親父の意図が流れ込んでくるような感覚を覚えた。
この木片は、トラス構造ではない。これは柱以外にも、通り道をつくるためのバイパス手術だ。なんのための通り道か? 一つしかない。ナノマシンだ。この構造は、ナノマシンが効率よく拡散するための血管として機能する。
驚きのあまり、危うく小屋組から転げ落ちるところだった。僕は直感した。親父は、将来的なナノマシンの接種を想定していたのだ。ナノマシンの接種を拒みながらも、いざ打ち込まれたとき、効果が最大化するような仕掛けを残していた。
おそらくトラス構造が埋め込まれているのは、この箇所だけではないだろう。別の種類の仕掛けもあるかもしれない。もしかすると都内の文化財の中で、金剛寺だけが最初に動き出した理由は、「最初にナノマシンを接種されたから」だけではないのではないか —— 。
木片の周りには墨付けで引かれた、何本もの下書きが残っていた。僕は思う。親父はきっと、ナノマシンを恐れたのではない。ナノマシンという禁忌に魅了される、自分自身を恐れたのだ。だが結局、その衝動を抑えることができなかった。
「ノウマク サンマンダーバーザラダン……」
河川敷の歓声に紛れ、遠くから誰かの念仏が聞こえた。それは祈りの歌のようであり、嘆きの声のようでもあった。僕は注射針を挿しこみ、親指に力を込めて、ナノマシンを寺へと送りこんだ。
◇
勝俣のナノマシンを追加接種された金剛寺は、じきに強い推進力を得た。ときに流れに負け、ときに濁流に飲まれそうになりながらも、川をじりじりと昇って行く。嵐のなか、巨大な寺が揺れながら多摩川を遡上していく光景は、この世のものではないように思えた。
そしてJR奥多摩駅の近く、多摩川と日原川の合流地点の平地まで辿り着いた寺は、そこで方向転換。臨時建設されたスロープに誘導されるように、陸へと戻っていった。そして3週間かけて日原街道を這うように北上したのち、ついにその動きを止める。出発から、ちょうど100日が経った朝のことだった。
金剛寺が新たな住処として選んだのは、ヒノキの原生林が残る日原森林だった。「東京最後の聖域」と呼ばれるこの広大な森林地帯こそが、旅の終着点であり、寺の故郷でもあった。金剛寺は樹齢千年を越えるであろう巨樹の傍らで、軋み音をあげながら、腰を下ろすように停止した。寺の柱脚がじわりじわりと、黒い腐葉土に埋まっていく。
「根を張っとる」
静かに見守っていた勝俣が、口を開いた。
「根?」
「ミネラルに炭素、ケイ素。修復に必要な栄養分を吸収できるよう、ナノマシンが土壌と……それから土壌にいる菌と連携しとるんや」
「菌根菌ですね」
菌根菌とは、樹木と共生する菌だ。菌は木の根っこに住まわせてもらう代わりに、地中に伸ばした菌糸によって栄養分を広く吸収し、木に分け与える。
「なんや、詳しいな」
「高校、農業系なんです」
木と菌は、土地の環境に合わせて、何万年もかけて共進化してきた。その森の、その土にしかいない菌根菌は、そこで育った木にとって、遺伝子レベルで適合した相棒だと言える。ひょっとして金剛寺は、日原の土地以上に、馴染んだ菌のもとへ帰りたかったのではないか —— 。
「なんでやねん、大工なら工業高校やろ」
勝俣に突っ込まれ、膨らんだ想像が弾ける。
「あ、いや、親父に行かされて」
「やっぱお前の親父も変わっとるのお」
勝俣が笑って、僕は思い出す。「宮大工は木と話せ」と仕事場で言った後、親父はたしかこうも続けた。木を知るにはまず土を知れ。だからお前は、まず土のことを学べる学校へ行け、と。
木と土。木と寺。そして木と親父。僕の頭の中で、一本の巨樹を中心とした曼荼羅が広がり、ぐるぐると回り始める。
「なんだか寺が、木に戻っていくみたいですね」
「ナノマシンあってこそや」
勝俣は誇らしげに言った。
「ワシの思い描いた、自己修復モデルの完成系とも言える」
「でもこれ、直せるんですか」
僕の問いかけに、勝俣は肩をすくめる。
「知らんがな。ワシの仕事ちゃうわ」
長い旅を経て、金剛寺は変わり果てた姿となっていた。濁流に洗われた壁面には無数の傷跡が残り、泥と苔がへばりついている。突き出した向拝はあらぬ方向へ屈折し、河原に落ちていた青いビニールシートが巻きついている。何より、寺を支える大屋根と円柱はハの字に歪んだまま、奇妙な角度を保っていた。ナノマシンだけで修復できるとは、到底思えない。
「人の手を入れるとして、どれくらいかかるんや?」
ヒノキの柱を撫でる。美しい焦茶を描いていた木目は削り取られ、琥珀色の生木が顔を出していた。
「なんせ背骨が歪んでます。損傷のひどい部分は、一度解体する必要がありそうだ。ざっと10年ってとこですかね。壊すのは簡単でも、戻すのは大変なんですよ」
「じゃあ良かったやん。また当面は食いっぱぐれへん」
悪びれもせずに言う。たぶん本心からそう思っているのだろう。
「どや。後悔しとるか?」
勝俣が試すような目を向けてきた。
「分かりません」
僕は異形の寺を見上げた。おかしな方向に歪んだ柱たちは、しかし別の観点から見れば、いまだ絶妙な均衡を保っているとも言える。
「でも、美しいと思います」
勝俣が腹を抱えて笑い、僕の背中を叩いた。思わずふらついて隣の巨樹に寄りかかると、手に痛みを覚えた。樹皮に刺さった指先から、血が流れていた。その瞬間、なにかとてつもなく大きなものが、上からのしかかってくるように思えた。僕は重みを振り払うため、自分に言い聞かせるように言う。
「もう始まってしまったから。やり続けるしかないんです、きっと」
700年前、この森でヒノキを切り出した時から、それは始まっていた。寺院を建立し、数百年ごとに修復を繰り返す。一度始めてしまったら、もう止めることはできない。僕はその壮大な不可逆性に、気が遠くなるような畏怖を抱いていた。と同時に、この寺に手を入れてきた人々に対して、ある種の連帯を感じてもいた。僕も勝俣も、そして親父も、きっとみんなが共犯者なのだ。
「行くわ。他の寺が気になるもんでな」
勝俣はそう言うと、玩具に興味を失った子供のように、金剛寺に一瞥もくれず歩き出した。
「あとは好きに直せや」
背を向けたまま手を振って、森の奥へと消えていく。
静寂が戻った。金剛寺が鳴くように軋む音だけが聞こえた。僕は傾いた円柱を玄翁で叩く。カン、とヒノキが乾いた音を返し、薄暗い森にこだました。
文字数:15522