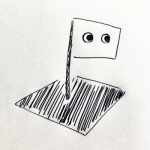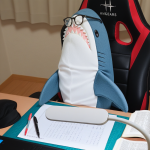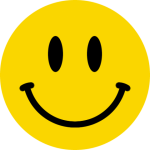梗 概
仮面の下の貴女に捧ぐ
1950年代、豪雪の降る土地の小屋で女性が目を覚ます。以前の記憶がなく、鏡を見ると醜い肉腫が顔の半分を覆っていることに気付く。
小屋の住人・前川が現れ、彼女に経緯を話す。前川は寄生虫研究者であり、地域で確認される条虫(サナダムシ)とその寄生虫症について研究しているという。
突然変異で生まれたと思わしきこの条虫は、宿主の頭部を膨張させる性質があった。到達した頭部で自らが核となって新しい脳を構築し、肥大化。頭部の形状を変え、最終的に顔の半分を覆う肉腫を発生させる。肉体の制御権を奪い、元々の脳と神経を連結させて宿主が生存できるよう動く。
「仮面頭症」と名付けたこの病に、共同研究者の女性・辻田ミツが冒された。元々の顔の眼球が動いておらず、現在身体を動かしているのは増えた脳による人格だと前川は推測。
状況を認識し、彼女は自身を新しい辻田ミツとして受け入れる。人間への寄生例、そして意思疎通できる寄生者として、ミツは前川との生活を送る。前川は優しくミツを扱い、人として惹かれるところがあった。部屋で日誌も見つかり、以前のミツの愉快な一面も知っていく。暮らしを楽しく思う一方、制御できない強烈な憎悪を、前川やこの環境に感じているのをミツは自覚する。
憎悪は日に日に強まっていく。これは寄生者としての感情なのだろうか。前川に吐露しようか迷い、彼が日中過ごしている研究室へ。普段は入るなと言われているそこで目にしたノートには肉腫のないミツの写真があり、意図的にミツを条虫に寄生させた主旨の文章が続く。
前川はミツを欲したが拒絶され、思いを拗らせ実験体として常時観察できる状態に置くという選択を取った。肥大化した脳が新しい人格を持つことは予想外で、これ幸いと利用したらしい。今まで感じていた憎悪は、宿主のミツが抱いていたものと知る。
真実を知ったミツの背後に前川が立つ。前川は素直に自分の行為を認めるが、何か状況を変えられるのか?と問う。外は豪雪で、集落に辿り着けても肉腫の顔では受け入れられるはずがない。前川の指摘通り、飼われるしかないとミツは悟る。
しかし、納得できない。研究室の工具を握ってミツは前川に殴りかかり、隙を突いて小屋を脱出。雪中を走りながら、自分がなぜ不可解な行動を取っているか考える。
寄生虫は宿主なしでは生きられない。自分の元になった条虫もそうだ。脳を連結させ、宿主が生存できるよう動く。寄生者である自分は繋がれた脳を通じて感じ取った宿主に、本来の姿を取り戻してほしいのだろう。飼われず生きられる、以前の姿に。
結論を下したミツは洞穴に入ると、顔の肉腫に工具を突き立てる。脱出はした、あとは自分が消えればいい。肉腫が抉られるごとに、寄生者の意識は薄れていく。
集落の村人に介抱され、顔を取り戻した辻田ミツが目を覚ます。起き抜けに、他に人はいないかと彼女は尋ねる。
誰かがいた気がする。私を守ってくれた誰かが、と。
文字数:1200
内容に関するアピール
転換点を意識して、最終的に設定を回収できるような構成を目指しました。
閉鎖空間にいる人物が豹変する、という状況が好きなので、雪山モノと掛け合わせる形で寄生虫の要素を入れています。
寄生虫を題材にした物語は既にかなりありますが、寄生者の視点で書かれたものは少ないはずです。そのため「脳を発生させる」という設定から自我を持つ寄生者を作り、そこから寄生者と宿主の関係性を描こうと思います。
脳が繋がっているのに剥いで大丈夫か、という疑問があるかと思いますが、実作では「仮面頭症」についての記述を増やし、描写を盛り込むことでこの疑問は回避したいです。具体的には、「主要な脳の発生部分が顔の皮膚なので、顔を剥がすだけなら宿主の命に関係ない」など。この辺りの設定も上手く使って、前川への不信感を強めていくのも手だと考えています。
文字数:355
仮面の下の貴女に捧ぐ
頬が痺れていた。
ぼんやりと、板で覆われた天井を捉える。薄闇が塗られたような暗い景色を眺めているうちに視界は何度も明滅して、自分が瞬きしているのを知る。朦朧としたまま身体を起こした。二枚重ねの布団に下半身を埋めたまま、辺りを見渡す。
木の床と漆喰の壁、閉ざされた引き戸。箪笥や書き物机が隅に置かれたこの部屋は、やたらと狭く感じられた。格子窓の外は灰色が埋め尽くし、粒のような雪が舞う。肌に寒気を感じながらも布団から這い出て、時間をかけて立ち上がる。ベッドから降りて、身体に纏った着物の裾が足元で揺れていた。
一歩踏み出そうとして、身体は前へ崩れていた。どんっと鳴った音を聞いて、そこで倒れたと悟る。腕で身体を支えてもう一度立とうとしたが、力は入れど上手く起き上がれない。発信した信号が途中で遮断されているような、奇妙な感覚に全身が包まれる。この瞬間に通電したような痺れが腕で生じて、何度も床に這いつくばった。
もがいているうちに、傍らに置かれた姿見に顔が映った。
若い女の顔が、鏡面には映っていた。長い髪を後ろで束ねた、知らない顔だった。それに驚きはない。おそらく自分の顔だろうから。
呆気に取られたのは、顔が二重になっていたからだ。
鏡で見て左半分——自分の顔の右半分が少し盛り上がっていて、そこにもう半分とは異なる顔が生まれていた。土台になっているらしい顔はほんのり茶色く、盛り上がりのある部分はやや青白い。まじまじと自分の顔を見つめるが、呼吸と連動して動くのは片側、白い方の鼻孔や唇だけだ。もう片方は、死んだように動かない。
見開かれた目が一つ、眠ったままの目が一つ。どれだけ顔に力を入れても、その瞼が開く気配はない。黒い瞳が一つだけ必死にあちこち泳ぎ回って、片側の口許から苦笑が零れ出た。
おそるおそる、顔に触れる。顔の境目に指を添え、なぞるように下へ。境目には段差とも呼べるような、爪全体の長さと同じくらいの厚みがあり、片側の顔と綺麗に繋がっていた。少しばかり波打った線が、額の真ん中から顎の真ん中へと通り抜け、首元でその厚みは消えていく。
なんなのだろう、これは。細くなる目も歪む唇も、どちらも白い顔の上にしかない。どう見たって浮き出ているのは白い顔なのに。
まるでこの顔を支配して、身体を代わりに動かしているような——。
募る不安が頭の隅まで、冷えた空気とともに浸透する。目覚めたばかりで見過ごしていた疑問が大挙して押し寄せ、余裕が踏み潰される。ここはどこかを自分は知らないし、何故眠っていたのかも、自分が何者なのかすらもわからない。
顔を動かそうと泳いでいた黒い瞳は、今では鏡の中で震え上がっていた。
立ち上がる。閉じた引き戸へ、まだ言うことを聞かない身体で歩く。自分でも不自然だとわかる格好で、それでもこの部屋立ち去りたくて。痺れを引き摺ったまま引き戸に手をかけようとして、戸は自ずと開く。
開いた戸の先には、これまた若い男がいた。歳は自分と同程度、背は高く、体格に合った厚い着物と羽織を着ていた。頬がこけた陰鬱な顔にある細い目で全身を凝視しては、口だけを微かに動かす。心底驚いているようで、言葉どころか声すらも出せないようだった。
何も発せないのがしばらく続いた後で、男はこちらの目をじっくりと見つめた。
「辻田先生、目覚めたんですか」
聞き入れてから、首を傾げた。かけられた言葉が名前であること、その名前はおそらく自分の名前であること。理解はできているが聞き馴染みがないのもまた事実で、立て続けに顔を横に振った。
男は訝しげに眉を寄せたが、何度か深く頷いてみせ、最後に指で顎を撫でた。
「辻田先生ではない、と……そうですか。そういうことが、起きましたか」
何かに合点がいったという様子で、男は歩き出す。部屋から後ろ姿を覗いていると、「ついてきてください」と呼びかけられた。拭えない不安を抱えたまま、男に続くように自分も廊下へと出た。
前川登志郎、と男は名乗った。「前川と呼んでください」とだけ言って自分を広い部屋に通すと、またどこかへと行ってしまった。
仕方ないので部屋にある椅子に腰かけた。意匠の彫られた横長の机に手を載せて、前川を待つ。身体を動かす度に流れていた痺れは随分と鎮まって、手にはただただ部屋の暖気が伝わってくる。ここは天井も高いのに先の部屋よりも暖かい。ストーブで燃える薪の熱がそうさせているらしい。相変わらず格子窓は雪景色を映していたが、その冷気を全く感じさせなかった。
それほど間を空けずに、前川は戻ってきた。片腕に書類の束を抱え、もう一方で小さな金属の籠を持つ。書類を机に置いて対面に座った前川は、「ああ」とか「ええ」とか言って切り出し方を迷っていた。机の下から、籠にいるらしい生物の声が聞こえる。
「改めて、僕は前川といいます。獣医学が専門の、いわゆる学者です。貴女も僕と同じで学者だったんですよ、辻田先生」
要領を得ない告白に、またしても首を傾げた。突然告げられてもこちらには実感がない。
声を出そうとして咳が出た。えづくように咳をしてしまったせいで前川が身を乗り出したが、片手でそれを制する。息を整えて口を開くと動かない片側の唇もその動作に引っ張られ、思った通りに声は出た。
「何も、わからない」
「そうだと思います。記憶障害に近い状態に陥っている理由を、これから説明しますね」
呆然とするしかないこちらを置き去りにするように、前川は書類を取った。紐で括られた紙束を捲りながら、淡々と話し続ける。
「僕と辻田先生が国の感染症研究所から北陸のこの地方に派遣されたのは一九六五年、つまり昨年のことでした。診療所で複数の症例が確認されたので調査命令が下りまして。本来なら辻田先生だけの仕事でしたが、人獣を跨るように感染する病だったので僕も担当する運びになりました」
おぼろげだった意識がようやく冴えて、矢のように前川へと向かった。前川は探り当てた頁をこちらに突き出している。一匹の長細い虫の写真が、古紙に刷られていた。
症例は三件。罹患者は高齢男性、中年女性、男子児童とばらけているものの、発症した症状に共通性が見られた。頭部の大部分に皮膚疾患が発生し、それに伴う精神の変調を確認。同時期には捕獲された野生動物に類似した症状が観察され、人獣共通感染症と推測された。
解剖の結果、野生動物からは線虫——サナダムシが回収されたという。
「線虫による皮膚疾患の発生は過去の症例にも記録が存在します。人間の方から虫は回収されていませんが、同一の寄生虫症と判断していいだろうとうちの組織も考えたらしい。ただ、この病にはきな臭いところが多くてですね」
前川が頁を捲って、補足事項という文字の上に指を置いた。
本症例は総じて患者自身の逃亡により、詳細な診断が完了していない——逃亡、という語句に思わず息を吞んだ。
「三人の患者が皆、消えているんですよ。自ら診療所を抜けて行方知れずになっています。男子児童は当時で十歳程度にもかかわらず。患者について聴取した際、患者の親族は迷信じみたことを口々に言っていました」
自分で発しておきながら、前川の声には笑いが漏れていた。
「人が代わったようだった、新しい顔が人間を乗っ取って動かしているに違いない……それが精神変調という報告の実態です。いや、寄生虫症の罹患者で行動が変容するというのは起こる話なんですよ。でも、人格が代わるほど大袈裟な変化ではない。新しい顔と言ったって結局は皮膚の病で、そこに魂が宿るわけではない……そう、僕も思っていたんですが」
籠を、前川は卓上に掲げて置いた。獣が鳴き、かしゃんかしゃんと音が立つ。
一匹のイタチが、籠の中で身を竦めていた。身体を丸め、尾で胴を包む。頭はまっすぐこちらへ向けられ、正面からイタチの顔を捉える羽目になった。
顔が二重になっていた。被り物をしているかのように、顔が不自然に頭を覆う。新しい顔は右耳から鼻先へと広がり、左耳と左目の周辺を境に段差ができていた。右耳が音を拾おうと小刻みに動く一方、左耳は飾りのように動かない。
手は勝手に籠へと伸びていた。目を近づけても、イタチの頭が作り物のようには見えない。震える指が自分の顔の境目をなぞって、顔に引かれる線がまた自分へと染み込んでいく。
「これ、同じじゃないですか」
「ええ。器官を含めて顔面が再現されています。この地域の線虫に寄生された動物は、決まってこの症状が出る。皮膚疾患どころの問題ではない。それでも性格が代わる変化の理由にはなりえないわけですが、僕と辻田先生で調査を続けたら、それもあながち嘘ではないとわかってきました」
書類の中から一冊のノートを抜き取って、前川は開く。鉛筆で記された文章や図と一緒に、頁には写真が貼られている。顔が二重になった小動物が切り裂かれ、肉の中心で先ほど見た線虫が渦を描く。肉の布団に包まれた虫は、いくらか気持ちよさそうでもあった。
「卵の状態で動物に潜り込んだ虫は、孵化とともに頭部皮膚へ移動。そこでこれまで見られた線虫のように宿主の身体を弄るわけですが、この虫の異常なところはここにあります。動物の顔を複製する際に、神経細胞に似た組織を発生させます」
「つまり、何が」
「虫自身が独自の脳となって、宿主の身体を奪うんです。宿主は休眠状態に陥り、操られる。自覚なく行動に影響を与えるなんてものではなく、思考すらできなくなると辻田先生は考察していました。実際、採取できた卵を使った実験で、気性の荒い個体が明確に大人しくなった例を確認しています。このイタチのように」
おそらく神経を宿主の脳と連結させ、命令を経由させるのだろうと前川は細々した仕組みの話を続けていたが、こちらの耳には届かなかった。右頬をつねる。線虫によって複製されたという皮膚は、やはり剥がせそうにない。
白い顔に虫が埋まっていて、その虫が今は新しい脳。虫が宿主の思考すら奪うというなら、今こうして考えている自分は——俯いているうちに、「辻田先生」と呼びかけられた。
「この寄生虫症を、僕と辻田先生は仮面頭症と呼んでいました。この虫がどれほどの影響を動物に及ぼすか、研究しなくてはならないこともまだ多い。その矢先でした。辻田先生が意識を失い、新たな顔が形成されたのは。何かに付着した卵を誤って飲み込んだのでしょう」
頭をよぎった直感が、確信に変わっていく。気を逸らそうとしても、対面に座る前川は容赦なく自分の正体へと迫ってくる。
「辻田先生、貴女に起きている記憶障害について考えられることは二つ。一つは、昏睡から覚めたばかりの一時的なもの。もう一つは——」
「こうして話している私自身が、辻田先生に寄生した虫そのもの、ということですか」
遮り、内側に溜め込んでいた思考を吐き出す。半分閉じた口を無理やり動かせば、すらすら声は紡がれた。こちらの出した言葉に、前川はただ頷いた。
「馬鹿げた話ですが、後者の可能性が高いと僕は考えています。貴女の顔の左側は、これまで観察された動物と同様に動いていないようだ。仮面頭症が人間に起きて、脳の思考機能を奪って会話している。過去症例の聴取内容とも辻褄が合う」
「だとして、私はどうすればいいんですか」
聞き返していた。整理できない頭を冷やそうとして、顔の片側だけが歪むのを感じる。
自分は虫だ、人間ではなく。この女に潜り込むまで自我すら持てなかった自分が、こうしてあれこれ考えている。それがまず受け入れ難いが、腑に落ちてしまう自分もいる。覚えていることは何もなく、ついさっき生まれたかのように記憶は空洞。しかし難解な用語は理解可能で、聞く度に新鮮さと懐かしさが混在して生じていた。
自分が虫だとして、その自分は病の原因でもあり、一人の女の意識を奪っている。ましてやそれが同僚であるなら、目の前の男はすぐに自分を女から除去して治療を試みるだろう。取り除かれた自分がどうなるのかは、想像もできない。
椅子から腰を上げ、扉の方へ身体を傾けていた。そうして動いた瞬間に、「待ってください」といまだに平静を保っている前川が発した。
「仮面頭症の治療方法は判明していません。研究中の症例ですから」
「顔に虫が埋まっているというなら、刃物でも入れたら私を簡単に剥がせるでしょう」
「宿主の脳と顔にある脳は接続しているんですよ。そんな強引な手段は取れない」
息を吐いて立ち上がると前川は机を回り込み、宥めるようにこちらの肩に手を置いた。緩やかな力で椅子に座らせて、自分は腰をかがめて目線を合わせる。唯一開いた目に、前川が真正面から映り込む。
「人間を相手にした症例観察は、僕たちではできていないんです。仮面頭症について、生きた症例がいるのは好都合です。研究対象とする代わりに、僕は虫である貴女を生かす。それが辻田先生を生かすことにも繋がります」
「いいんですか、本当にそれで」
「そうするしかありませんから」
素っ気なく前川は言って、右手を差し出した。その手が意味するところを察しながらも、少し躊躇が挟まる。辻田とやらに断りなくこの契約を結ぶのは、若干の後ろめたさを覚えないでもない。
それでも、と前川の手を握る。前川も手を握り返し、虫と研究者の協定関係がここに結ばれた。
*
研究といっても、こちらが騒ぐほど特殊な何かを施されることはなかった。変異が生じた頭部の触診、体調に関する問診、それから虫である自分が辻田の知識をどれだけ保有しているのか、問答形式での検査を度々受けた。何気なく答えていたが、どうやら自分は辻田が持つ知識や情報を引き出して使えるらしい。ただの虫でしかないのに人間の生活様式に対応できるのは、この能力に依るところが大きいようだ。
一日の検査が終わると昼食となり、前川と二人揃って食事を摂る。場所は大抵、ストーブの置かれたあの広い部屋だ。旧日本軍訓練所の診療施設を再利用したというこの研究小屋には、暮らしに必要な設備が揃っていた。調理場の隣には備蓄庫があり、冬を凌ぐ二人分の食料が確保されている。野生動物の観察のため山中に拠点を構えることになったが、冬は雪のため集落へ下りることが困難だと予想できたので、事前に食料を集めたらしい。
調理は当然、前川の担当だ。今日もまた、野菜と肉の入ったスープと缶詰が卓上に並ぶ。
この食事の場は、前川と何かを話す場でもあった。協定関係の結託から二週間ほどが経った今、スプーンを動かす手を止めて前川に尋ねる。
「私になる前の辻田先生って、どんな人間だったんですか」
前川は、自分から辻田の話をあまりしなかった。敢えて伏せていたのだろうが、こちらも関心を抑えられなかった。不意に身体を奪ってしまった人間が、これまでどうやって生きてきたのか。目覚めてから時間が経ち、一時的な記憶の混濁という線も消えかけている現状、尋ねずにはいられなかった。
視線を逸らし、前川は額を指で押さえた。それから観念したように瞬きをして、呟く。
「変な人間でしたよ。顕微鏡でただ虫を眺めている、変な人間です」
小さく笑いを挟んで「研究者なんて皆そうですけど」と足し、前川は彼女について語る。
本名を辻田ミツ。女性で研究者というのがまず珍しいが、根っからの寄生虫学者となればなお珍しい。寄生虫研究は病を根絶したいという熱意から取り組む人間も多いが、単純に虫を知って愛でたいがために研究を重ねる稀有な人間もいる。辻田もその一人だった。
「仮面頭症についても、その脅威を理解しながらも半ば喜んでいるようでした。こんなことをしでかす虫がいるのかって。生物の顔を生み出して自我を奪う大胆な虫なんて、なかなか居ませんから。研究者としては、これほど嬉しい研究対象もいないでしょう」
「そりゃあ、顔をこんな風にする虫は早々居ないですって」
「辻田先生が面白がっていたのは、顔に関する部分だけではないですよ」
前川曰く、仮面頭症に罹った獣は一様に落ち着いた振る舞いをするようになるらしい。最低限の動作だけで活動して体力に余裕を残し、以前より生存に適した行動を優先する。寄生虫によっては宿主に自死を促す事例もあり、それらと比べると仮面頭症を起こす線虫は宿主を保護する傾向にあるという。
寄生者が宿主に自死を促すのは、寄生者自身の世代交代を行うためだと前川は言った。宿主の体内で産んだ卵や幼虫を外界に解き放つために、宿主の殺害を試みる。
「自死を誘導する虫に対して、仮面頭症の虫は宿主の力を引き出して、生存に役立てようとする。僕が知識に関する問答をしていたのもこの能力を測るためです。その方が、この虫にとっては利益があるんでしょう。寒い気候で恒温動物に長期間密着するためと、辻田先生は専門家らしい分析もしていましたが……あの人らしいことも言っていましたね」
「何と言っていたんですか」
「人間と一緒に生きようとする虫が現れた、って。実際は、ただの操り人形なのに」
はっきりと辻田を貶すように言って、前川は乱雑にスプーンを皿に突っ込んだ。悪戯にスープを掻き混ぜる仕草にやり場のない怒りのようなものを感じ取って、申しわけのなさを覚える。自分が辻田の身体から出ていかなければ、辻田が意識を取り戻すことはないのだから。
「あの、本当に治療方法に糸口はないんですか?」
「ありません。まだ研究も早期段階でしたから」
「じゃあ、辻田先生はいつ私から解放されるんです?」
「わかりません。虫が死ねば自然と、という可能性もありますが、この虫は長命なようで。調査時に訪ねた集落に見世物小屋があったんですが、そこに仮面頭症の獣がいて、小屋の主は五年生きていると言っていました。信憑性に欠けますが、宿主の寿命の分だけ虫が生きる、という可能性も考えられます。いろいろと、貴女は規格外の虫ですからね。生き延びることに特化しているのかもしれない」
「そうですか」
相槌として発した声がいやに暗かった。その声の重さに自分でも戸惑っていると、前川が問いを投げかけた。
「残念そうですね。貴女からすれば都合のいい状況のはずですが」
「さあ、どうしてでしょうね」
咀嚼できない感情を零すことはできず、前川からの問いを受け流して食事は終わった。
辻田ミツに関する会話を前川と交わしてから、鏡を見るのが習慣になっていった。目覚めた部屋が自室となり、夕食から就寝までは自由に過ごしていいと前川からは言われている。夜に沈んだ部屋で、ランプの蝋燭に灯した火が赤く燃えていた。
姿見の前に立つ。足袋に白の着物を着た身体の上に、顔の折り重なった頭が変わらず乗っている。日中は洋装をしている前川から洋服を着るように薦められたが、こちらの方がしっくりと来ていた。最初に見た白装束の辻田ミツこそ、自分が認識する辻田ミツの姿だ。
鏡を見ながら顔に触れる。顔を見るようになった当初は一瞥する程度だったが、一週間ほどが経てば触れずにはいられなくなっていた。顔の半分を覆う白い皮膚の、厚みと弾力。この肉の裏側に、虫である自分が眠っている。
その隣で目を閉じて眠っているのが、本当の辻田ミツの顔。茶色く人間らしい肌をいくら触ったところで、目覚める素振りは見せない。
毎日、この顔を眺めている。声も聴いている。何を知っているかも、思考の奥を手繰れば自ずとわかる。だが、会ったことはない。言葉を交わし、彼女が笑う姿を見たこともない。
一度でいいから会ってみたかった。人語を解する寄生虫を、彼女はどう捉えただろうか。
左の頬に親指を、左の瞼に人差し指を置く。指同士の距離を離すにつれ、目が開いていく。既に開いている右目とこじ開けられた左目が、初めて鏡の中で並んでいた。
「見えていますか」
ひっそりと、己を嘲る。見えているはずがないのだから。
独り遊びに満足して指を離すと、左目は閉じてしまった。これが身勝手な真似なのは理解しているつもりだ。自分の思考の自由は彼女の犠牲の上に成り立っている。それでも、この身体の持ち主がどんな人間かは理解したい。折角、この身体で目覚めたのだ。
鏡を見つめていると、自然と右目の瞼も閉じかかった。眠気に従ってベッドに潜り、蝋燭の火を消す。格子窓の外に視線を送った。夜の風景の中でも大粒の雪が降り続いているのが見て取れる。この寒々しい景色に放り出されたくはないと思いつつ、ずっと目を離せなかった。
腕が、独りでに持ち上がる。緩やかに拳を握って、手は窓を殴りつけていた。
痛みで意識が覚醒する。歯を食いしばって、窓を殴った手をもう一方の手で包む。荒れる息を抑えるように目を瞑る。
このところ、こうだ。自分の内側に突然抑えられない衝動が湧き上がって、暴力的な行動を取ってしまう。仮面頭症に罹った動物は落ち着いた振る舞いをするのではなかったか。要因を考えながら一つ思い至ったのは、この病の過去症例についてだった。
人間の罹患者は全員が診療所から消えている。それを促すような力が、今の自分にも働いているのではないか。それを裏付けるように、突発的な衝動はいつも外へと向いている。こんな雪山に飛び出したら、間違いなく凍え死ぬのに。
そうなれば、辻井ミツを巻き込んでしまう。それだけは避けなくては。自分と彼女を切り離す方法を探している自分に気付いて、片方の口の端から笑いが零れ出た。
なぜ自分は寄生虫なのに、こんなにも宿主を守ろうとするのだろう。
*
数週間が経っても、前川の研究に進展はなかった。元よりこの研究は長期間を想定していて、一年は通して様子を見たいと彼は話す。だが悠長な予定には、もうこちらが付き合えそうになかった。
外への衝動は日に日に強さを増していった。逃げ出したいと感じる瞬間が増え、何度も壁を殴る日もあった。何が衝動の原因になっているのかは、やはり掴めそうにない。
最初の衝動が微弱で、そこから徐々に強まっていったせいで自分の感覚が麻痺していたらしい。身体が勝手に動いた時点で、前川に助けを求めるべきだった。
考えを纏め、自室のベッドから起き上がる。さっき昼食を摂ったばかりだと思っていたが、外は日が陰って暗くなりつつある。舞い落ちる雪も空の色を映し、黒い塊となって地面に積もっていく。
前川を探し、建物の中を歩き回る。ストーブのある部屋、調理場、彼の私室と探してみるが、一向に見つからない。この研究小屋はさして部屋の数は多くない。普段なら自室に引き返しているところだったが、やむを得ないと感じ、ある部屋を目指して歩き出す。
研究室、と前川は呼んでいた。引き戸を開き、照明を点ける。連なった蛍光灯が点灯し、木造の実験台がいくつも並ぶ。壁際にはシンクが並び、置かれた棚にはガラス製の実験器具の数々が見えた。研究用に捕獲された動物が並ぶ台もあり、小さな音が鳴っては消える。
前川との取り決めで、寄生虫研究を行っている研究室には立ち入りが禁止されていた。理由を深く聞くことはなかった。前川自身が研究を妨害されるのを嫌ったのだと、その辺りを想像して納得していた。
しかし、今はそうした事情に構っていられない。それに目的があるのは研究室ではなく前川だ。大した違反にはならないだろう、とこの部屋に立ち寄った。
部屋を見渡してみるが、前川本人はいない。長く息を吐き、踵を返そうとしたところで、実験台にある一冊のノートが目に入った。見覚えのある表紙だ。たしか、目覚めた最初の日に前川が手にしていた。
生じた迷いを振り切るように、研究室へ足を踏み入れた。動物に実験でもしたのだろうか、同じ実験台にはピンセットや小型のメスが、乾いた布の上で干されていた。
ノートを取って開く。前川を信頼していないわけではない。ただ、自分と辻田ミツを切り離す方法を、外への衝動の原因を探りたい。前川が見落としている記録も残っているかもしれない。ぱらぱらと紙を捲って、ある頁に引っかかりを覚える。
頁には、キツネらしき獣の頭部の図が描かれていた。仮面頭症に侵された頭の断面図で、本来のキツネの頭に被さるように線が引かれている。膨らんだ新しい顔が頭部を覆う様子を層として描写していたが、図の付近に記された走り書きに、思わず声が漏れた。
仮面頭症で発生する顔は一つの膜となっており、慎重に切断することを心がければ罹患者の顔を傷つけない形での分離が可能だと考えられる。寄生者である線虫が連結させた神経は細く、分離の際に影響を及ぼさない。
この膜の内部には線虫の他、孵化前の卵が発見された。卵は皮膚組織の密閉状態が解除された際に孵化が確認されたため、線虫は宿主を可能な限り生存させ、死亡してから卵を放つことで、通常の線虫より長期間での種の保存を試みている。
しばらく、その文章に釘付けになっていた。この記述が誤りではないなら、前川の発言は嘘になる。切除は強引な手段でもなんでもなく、仮面頭症における正当な対処方法だというのに。
なら、どうして。
「何をしているんですか」
張りのある、それでいて冷え切った声が飛んできた。
振り向く。研究室の入口に、前川が立っていた。細い目で射殺すように、ただただこちらを見つめている。
「研究室への立ち入りは禁止という約束だったはずです。何をしているんですか」
怒号、というほどの声ではなかった。淡々と責め立てる、圧し潰すような怒気が言葉の端々に籠められていた。手は震えていたが、その手を握り締め、前川へと向き直る。
「貴方を探して研究室に来ました。貴方こそ、何をしていたんですか」
「薪を切らしていたので暗くなる前に集めていたんです。というか、埒が明かないので聞いてしまいますね。そのノート、見ましたよね。どこまで読みました?」
気力のない普段の様子が嘘だったかのように、前川は問い詰め続ける。ここで及び腰になってはいけないような気がした。視線を外さず、口を開く。
「仮面頭症の切除は、注意を払えば安全に実施できること。私と辻田ミツはいつでも切り離せたのに、貴方はそれを隠していたんですね」
問い返すと、前川が小さく頷く。目的が読めず、苛立ちを奥歯で噛み殺した。
「なんでそんな、無意味なことを」
「その方が、好都合だったからですよ。そうに決まっているでしょう?」
平然と答えた前川に、こちらは黙っているしかなかった。何が好都合なのか、理屈が全く見つからない。沈黙したまま考えていると、前川は何度か首を横に振った。
「虫に人間のことはわからなくて当然ですよ。拒絶されてなお相手を求めたら、方法なんて選んでいられない。そこに人間を昏倒させる卵があったら、飲み込ませるだけです」
話す内容の大半は理解ができなかったが、最後に語られたことには唯一意識が向いた。
「卵を飲ませたのも貴方だったんですか」
「彼女がこちらを振り向かないのが、嫌で嫌で。せめて研究の期間中は、僕がいなければ暮らせないようにしたかった。でも、幸運でした。あの迷信じみた症状が本当に起こるなんて。おかげで、意識のある彼女と暮らすことまでできている」
前川が歩き出し、近づいてくる。警戒して構えるこちらに対して、前川は右手を差し出した。以前交わした、協定関係の握手を思わせる手だった。
「この通り、僕は辻田先生から貴女を切除するつもりはありません。引き続き、貴女にとって悪い話ではないはずです。上手く理由をつければ、研究が終わった後ですら貴女は生きられるかもしれない」
嘘が破られた後だというのに、前川の表情には余裕があった。たしかに、話には筋が通っている。寄生虫である自分の人格を守るなら、前川の態度は有難く感じるだろう。
だが、もはや信用はできなかった。
「もう、その話には乗れませんよ」
「それなら、貴女はこれからどうするんですか?」
前川に問われ、目を見開いた。
この暮らしを拒否して、研究小屋を出たとする。雪の降りしきるこの土地にいきなり放り出されたら、どうにもできず死んでしまう。雪を駆け抜けて人里に降りられたとしても、自分の頭には顔が被さっている。一目で奇病に侵されているとわかる自分を人々が受け入れてくれると、本当に断言できるだろうか。
選択する権利はない。ここにいた方が安全だ。状況を変えることなど、自分にはできない。
こちらが悟ったのを汲んだのか、前川は微笑を浮かべた。
「貴女が賢い人でよかった。これからも、ともに暮らしましょう」
差し出された前川の右手を凝視し、そこに自身の右手を合わせようとする。不服ではある。半ば脅迫のようなものだ。それでも、従うしかない。身体を借りている辻田ミツを守るなら、これが真っ当な選択であるはずだ。
理屈を付けて自分に何度も言い聞かせても、腕の動きは鈍かった。まるで自分の理性に身体が反抗するように、腕は掲げられたまま動こうとしない。そうして動かせば動かそうとするほど、内側から圧迫される。募り募って、やがて力は解き放たれる。
溜め込んでいた衝動が、突然身体を突き動かす。
実験台のメスを右手が素早く掠めていた。前へ飛び出し、横に振られたメスが前川の右手を切り裂く。血の飛沫を浴び、上がる悲鳴を後ろに聞いて、自分自身は目もくれず走り出す。
玄関戸を開け、雪の野外へ飛び込んだ。吹きつける大粒の雪と冷気を突っ切って、一面に広がる白い景色を足袋と羽織のない着物で駆け抜ける。待て、行かないでくれと呼び止める声が遠くから響く。雪を踏み締めて走るにつれ、やがて声は聞こえなくなった。
日が落ち切った暗闇で頭が冴えていく。息が切れて、ゆっくりと雪中を歩く。何をやっているんだ、自分は。初めて浴びる雪の冷たさを実感して、馬鹿な自分をりつけてやりたくなる。後ろを振り返ったが、研究小屋の外観は黒に潰されてとうに見えない。窓の明かりがわずかに灯っているだけだ。もう引き返せる距離でもない。
しかしどうやら、悪いことばかりでもないらしい。
どうやっても拭えなかった外への衝動が、すっかり抜けて空になっている。今までで一番清々しい気分だ。
なぜだろうと考えて、答えはすぐに導き出せた。
自分は虫だ。寄生虫だ。それも宿主を殺す寄生虫ではなく、宿主を守る寄生虫。
今まで抱えていた外への衝動とは、あの研究小屋から抜け出したいという辻田ミツの不快感だったのだろう。脳と連結した神経が汲み取り、常に自分へと伝えていた。
過去症例の罹患者に寄生していた虫も、似たものを感じ取って動いたに違いない。奇病に侵された人間を見る好奇の目から逃れるため、虫たちは宿主の身体を動かして外に出た。もっとも、そうした目で見られた原因は虫自身にあるのだが。
どうあろうと、自分たちは一度寄生した宿主を守るように動く。行動が不可解であっても逆らえない。そこには卵を宿主に長期間保持させるという、生物として合理的な理由もあるのだろう。だが、それ以上のものを感じている自分もいる。
身体を借りたこの宿主に、生き長らえてほしいと願っている。本人が最も健やかに過ごせる、誰の支配も受けない姿で。
どのみち、このままでは共倒れだ。できるだけ、彼女が生きられる可能性の高い選択を取ろう。前を向く。闇の中で、ぽつぽつと明かりが浮かび上がっている。山を下れば集落は近いと踏んで、再び走り出した。
身体を擦りながら走るうちに、集落の明かりはかなり近づいてきた。光に照らされ、家屋の陰が見える。山道から集落の光景を望んで、片側の顔が綻んでいく。
もう少し、と踏み出そうとして、身体は前へ崩れていた。全身を痺れが駆け抜け、肉体が限界に達しているのを知る。しかし、このまま朽ち果てるわけにはいかない。
腕を立て、這って進んでいく。集落に辿り着けなくてもいい。せめて人に見られる場所で倒れれば、誰かは彼女を助けてくれるはずだ。そのために一歩でも前に往かなければ。
進むうちに、地蔵の並ぶ場所へ出た。崖に彫られた空間に、数体の地蔵が横並びになっている。ここだ、とその脇へと潜り込んだ。人が座れる程度の広さが地蔵の横にはあり、雪も横風も入ってはこなかった。
安堵する自分の右頬を叩く。自分にはまだ仕事が残っている。
身体を、辻田ミツに返さなくてはならない。
メスを取り出した。着物の帯に挟んでいたが、落としていなくてよかった。前川を切った際の血は凍って、指でなぞれば簡単に崩れた。
集落からのおぼろな光に照らされ、メスが輝く。鋭い刃先に身体が震え、メスが揺れる。深呼吸をして心を落ち着かせ、その揺れを抑えていく。震えなくなった手を掲げ、顔に置いた。
この顔には境目がある。爪全体の長さと同じくらいの厚みを感じ取って、低い方にメスを添わせる。厚く膨らんだ側へ刃を当てると、ほんの微かな痛みが生じた。
きっと白いその皮膚へ、メスの刃を突き立てた。
今度は痛みがなかった。ぷつんぷつんと何かが断絶されていく感覚が頭を通っていった。少しずつ自分が千切れて、小さくなっていくような。
恐怖を振り払うために、顔を押さえた。自分の白い顔ではなく、宿主が持っていたあの茶色い顔。そこを掴んで、膨らみに押し当てたメスを下ろす。切られる感じが途絶えないように何度も繰り返して、意識はどんどん消えかけていく。
切除される。切り離される。離れ離れになる。それでいい。元より自分に思考なんてない。ここで消えてなくなるのが、宿主への恩を返すただ一つの方法だ。
開いた片目の裏をメスが走るとそれきり何も見えなくなって、勢いのままメスを振り上げるとずるっと皮膚の滑る音がした。軽くなった身体で、些細な電気信号が起きる。
頬が痺れていた。
*
何度も瞬きをしていた。ぼやけていた景色が一つに集約されて、格子状の板で覆われた天井が視界に映し出される。目が覚めたという認識が、古い畳の匂いと一緒に身体に入り込む。
ゴホッゴホッと酷い咳をして、感覚が鮮明になっていく。
少しだけ、身を起こした。襖と障子に囲まれた部屋の様子から、ここが仮設研究所ではないと把握する。あの建物にこんな部屋はなかった。とにかくどこだろうと顔を傾けると、にこやかな表情をしたお婆さんが布団の傍に座っていた。
「目が覚めたかい。よかったわぁ。あんた、お地蔵さんの隣で倒れてたんよ」
話を聞いても、何のことかまるで思い出せない。何気なく身体を擦ってみると、布団に潜っているのに身体はやたらと冷たかった。
「あんた、名前は思い出せるかい?」
「えっと……辻田、です。辻田ミツ、です」
自分の名前を応えられて安堵していると、由来のわからない不安が胸の根底から湧き上がってきた。
何か、何かを忘れている気がする。大切な何か。辺りを見渡して、不意に掲げていた手が顔の右側に触れる。
そうだ、人だ。人がいたはずだ。
「あの、他に人はいませんでしたか」
「あそこにはあんた以外おらなんだが」
「そんなことは、ないはずです」
自分でもわからないほど、強く否定していた。
「誰かがいたんです。私を守ってくれた誰かが。白い顔を、していました」
文字数:14121