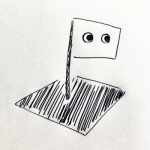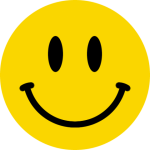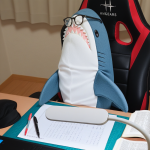梗 概
死を畏れる
超富裕層だけが老いを克服した世界。彼らは自らの代替臓器をips細胞で作り、血肉を少しずつ取り換えることで、寿命を引き伸ばすことに成功する。この”超長寿人間”たちは、自らの正体を隠しひっそりと生きていた。
一方で多くの市民は老化を防げない。圧倒的な寿命格差は不平不満を呼び、”超長寿人間”は市民から恨まれる。
そのような状況下で、“曝リスト”(曝露とテロリストの造語)が現れた。
彼らは、”超長寿人間”の個人情報を暴き、乱立したSNSに情報を投稿することで、注目を集めた。情報をバラされた”超長寿人間”は度々殺害されたのである。
超富裕層向けの雑誌「ディケ」の記者、田中は、”曝リスト”の実態を取材している。超富裕層は、自分の命をおびやかす”曝リスト”が何を考え、どのように生きているかを知りたがり、この雑誌の運営に出資をしているのである。
田中は個人情報保護法違反で逮捕された”曝リスト”鈴木の来し方を取材していた。鈴木の関係者に取材を重ねていく中で、ある老人の存在が浮かび上がってくる。大正元年生まれ、163歳の男性。医療革命が起きたのは30年前で、老人はその時点で133歳。あり得なかった。
与太話だと思った田中だが、取材データを上げても記事に反映させない編集デスクに対し、不審を感じる。
編集部は情報を秘匿しようとしているのではないか?
田中は独自に取材を進め、老人は福井県おおい町に住んでいるということが判明する。この町は40年前に原発事故が起きて以来、人は住んでいないはずだった。ところが、田中が訪れると、そこには、インターネットを全く使わない人々が住んでいた。彼らは医療を知らず、生まれ変わりを信じていた。死ぬことを厭わず、むしろ良いことだとさえ言う。
その集落で老人は神の如く君臨していた。
老人に聞いてみた。
本当に不死なのか?
「わしは確かに大正元年に生まれて死ぬことができていない。でも、それは決して良いことだとは思わない。生まれ変わることができないのだから」
実際に彼が163歳だと証明出来る者はいなかった。宗教じみていて胡散臭いと思った田中は老人の名前だけ控え、東京に帰ってしまう。
後日、新聞記事のデータベースにアクセスし、彼の名前を検索すると、50年前の記事が見つかった。113歳という高齢にも関わらず、おおい町の床屋で働いているという内容だった。
話は本当だったのか。
慌てておおい町に向かうと、もぬけの殻で勾留されているはずの鈴木がいた。
「彼は死ねない人を救おうとしているんだよ。彼は生まれ変われない苦しみを良く知っているから」
鈴木は老人の意思を受けて、”超長寿人間”の個人情報をばら撒いていたのだった。
すると田中は突然、意識を失う。目を覚ますと、鈴木の姿は消えていた。
鈴木がいた留置所に行くと、鈴木は自殺したという。
田中は老人の手がかりを探そうとする。しかし、いくら探しても見つからないのであった。
文字数:1200
内容に関するアピール
50年後、再生医療の発展による”超長寿革命”が起きる可能性はあると思います。それは単なる医療進化ではなく、人生の前提を覆す出来事になるはずです。
寿命格差が生じるのは必至で、それは現在の経済格差などとは比べ物にならないほどの深い溝になるでしょう。
今の医学では、どんなに長生きしてもせいぜい100年。だからこそ、我々は”どうせ死ぬのであれば限りある人生をより良く生きるべき”と考えてきました。しかし、寿命を乗り越えられるのであれば、まず第一に生存を考えるはず。
ダグラス•ラシュコフが「デジタル生存競争」で明らかにしたように、既に富豪たちは砂漠にシェルター施設を作り、自分たちだけが生き残ろうとしています。”超長寿革命”が起きた世界では、多くの富豪たちが長生きすることそのものを優先して生きるでしょう。”どう生きるか”という問いはなくなるかもしれません。この人生観の転倒を軸に作品を書きたいです。
文字数:395