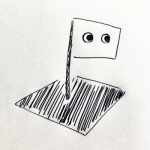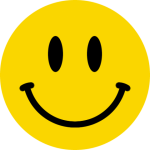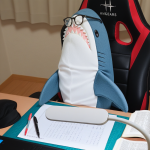梗 概
ネオ・ラーメン・オデッセイ
環境問題の深刻化から、芋と葱以外のリアル食材が極端に制限され、プラネタリーヘルスダイエットの思想が支配する2075年の日本・埼玉。細胞農学と3Dプリンティング技術が発達し、人々は栄養を最適化した代替食品を作り、脳内ナノマシンのエンハンスメントによって味覚をデジタル操作するのが日常となっている。
17歳の高校生アオトは、この時代において異端な存在である家業のラーメン屋「真海-SHINKAI-」に強い拒否感を抱いていた。店を営むのはアオトの母と二人の伯父、通称ネオラーメン三銃士だ。母のナギサはハイパーパーソナライゼーションAIの専門家として個別最適で高い栄養価を生む次世代ダシを開発し、長兄のヒロウミはナノマシン工学の権威として客の味覚や嗅覚を究極にカスタマイズし、次兄のワタルは3Dプリンティングとロボティクスの技術を駆使し一瞬で麺や具材を培養・調理するオートメーションシステムを設計している。
母たちのルーツは、かつて海のない埼玉で「煮干しの魔術師」と呼ばれたアオトの祖父、リクオの店にある。祖父は、東京都との間で勃発した内戦によりリアルな海鮮食材の流入経路が途絶えたいわゆる「超内陸」により失意に沈んだ。その魂を救うべく、未来技術のエキスパートとなった三兄妹が立ち上げたのが「真海-SHINKAI-」であり、彼らは煮干しラーメンという失われた食文化をテクノロジーで再構築し、世間の注目を集めていた。
アオトはデジタル操作された偽りの味を忌避し、本物の食材だけを密かに扱う非合法組織イロドリに参画していた。彼の目には、母たちのやっていることは食の本質から逃避したまやかしにしか映らない。ある日、アオトのふとした行動がきっけとなり、「真海-SHINKAI-」のシステム脆弱性がイロドリに露見してしまう。結果、店は客のナノマシンを暴走させ味覚を破壊するデジタルテロ攻撃を受け、存亡の危機に立たされる。
この切迫した状況下、アオトは母のラボから祖父が遺した「究極の煮干しラーメン」のデータログを発見する。データを解析する中で、祖父が目指したのは単なる美味しさではなく、「失われた海を思い起こさせる」メディアとしてのラーメンだったことを知る。祖父が守ろうとしたのは、食が持つ「情報を伝える力」だったのだ。アオトは、本物へのノスタルジーから脱却し、未来技術を駆使して祖父のラーメンを完成させる使命感に目覚める。
鍵となるのは、三銃士の技術統合と全体性だった。完成されたラーメンとは要素の集合ではなく、全体性が表現されたときその先に「リアルな海の情景」が産まれる。アオトのラーメンは、本物の海を見たことのない埼玉の人々のに、潮の香り、波の音、そして平和な時代の記憶をフラッシュバックさせる。アオトは、祖父から母たちへと継承されたラーメンの魂を未来に繋ぐ後継者となり、デジタル時代における食のあり方を問い始める。
文字数:1197
内容に関するアピール
2075年という時代を、食のサステナビリティと技術進化の視点から切り取ってみました。この『ネオ・ラーメン・オデッセイ』は、食の未来と人間の記憶をテーマに描く家族の絆の物語です。舞台は、芋と葱しかリアルに存在しない「超内陸」と化した埼玉。ここでは味覚のデジタル操作が常識となっています。私が描きたかったのは、食を取り巻く環境が激変したとき「食の何が変わり・変わらないのか」という問いです。17歳のアオトは、細胞農学や3Dプリンティングを駆使する未来のラーメンを忌み嫌います。しかしデジタルテロ事件を経て彼は、食事とは味の総和ではなく、記憶や風景を思い出させるメディア装置の役割があると気づきます。現代のラーメン評において、味にまつわる様々な情報に囚われることは「奴らは情報を食ってるんだ」という有名な皮肉に代表されるように決して肯定的に見られていません。しかし未来においては、どうなるでしょうか。
文字数:397
ネオ・ラーメン・オデッセイ
(一)
その一杯の中には、海があった。
今は二◯七五年だから、もう七十年も前だろうか。かの有名なラーメン職人にも無垢な少年時代があって、朝六時に友達と落ち合うと、人力で稼働するシティサイクルを漕いで埼玉からエノシマを目指した。今や埼玉政府とトーキョーの無人爆撃機が互いに牽制し合う荒川防衛ラインにも、その頃は高速道路と共用の立派な橋が架かっており、笹目通りからカンパチへ抜け、内陸の民も都市を、そして海を目指すことができた。
外出できるほどに柔い当時の夏の日差しでも、五時間の行程を行く少年たちの体力を奪うには十分だった。しかしそんな疲労も、潮風の匂いと、眼前に広がる水平線はたちまちに吹き飛ばしてしまう。埼玉県民にとって、海はそれほど特別な力を持つ存在だった。
しかしそれ以上に少年の興味を引いたのは、生しらす丼の食休みに立ち寄った水族館での光景だった。当時できたばかりの新しい水族館の見どころの一つ、サガミ湾大水槽と呼ばれる巨人の背丈ほどもあるその水槽の中には、海が入っていた。イワシの魚群が、エイが、タコが、ウツボが、身を寄せ合うサメたちが一つの世界を作り、少年を包んでいた。
海に、包まれるイメージ。
視界を覆う水槽。脳内にはたゆたう水の世界だけが取り込まれ、いつしかピントが合わなくなって、見ているというより、やわらかく透き通った青に抱かれているような心地になってくる。
それは少年にとって、本物の海を見ているよりも遥かに、海に触れ、海と繋がっている体験になった。埼玉に帰っても、頭の中に残り続ける海。郊外のロードサイドにいながら、畑がタワーマンションに変わっていく様を見ながら、いつでも好きなときに海を取り出せた。もちろん年間パスポートを購入して何度も現地にも足を運んだ。二度と自転車では行かず、オダキューのヘビーユーザーになった。
やがてそれから一回り、二回りと時が経ち、軽口を叩きながらペダルを共に漕いだ友人たちは大学を卒業し、社会に出て、少年はスープを沸かしラーメンを作り始める。その片隅にはいつも大水槽の光景が、様々な海の住人が同じ空間に融け合う海のイメージがあった。
青年となった少年は最初、一杯の中に海を凝縮しようと試みた。昆布、鰹節、煮干し、アゴ、それに鯛のアラで出汁をとった黄金色のスープに、干したホタテやエビなどの様々な乾物から旨みを引き出した塩ダレを合わせた。その試みは半分は成功した。客は入り、店は繁盛し、友人たちも盛り上げてくれた。
しかし青年の胸にはわだかまりがあった。カウンターの壁に記した能書を睨みながら、一口一口を確かめるように食べる客たち。率直に言えば、論文の査読を通しているような気分だった。指摘された穴に対し、それを埋めたら勝ち、何か欠点があれば負けというゲーム。非の打ちどころが無い完成度を褒め称えるレビューが拡散され、客が客を呼ぶ。そうではない。もっと大きな、偉大なイメージがある。海。その力をもって構造ごと吹き飛ばしてしまうようなパワーが必要だった。
力が足りないことを自覚した青年は、六店舗まで増やした店を大手資本の飲食チェーンに売却する。既に年齢は四十を超え、結婚し、子供が三人もいた。我儘を通すには蓄えが必要だった。そして修行の道に入る。
あの大水槽を表現するために、まずフォーカスを絞ること。中年となった青年は、水槽の一点、イワシの魚群のことだけを思った。まず煮干しを極めると決めた。中年は煮干しラーメンで評判の店を聞きつけると食べに行き、新たな発見があるとそこで働き、煮干しの扱いを身につけた。青森の僻地を軽自動車のレンタカーで駆け抜け、ナゴヤでは住み込みで働いた。そんな日々を四、五年続けた後で、彼はまた自分の店を開いた。
煮干しにもいくつかの種類があり、水揚げされた時期やサイズ、海でどんな餌を食べていたかでも味が変わる。また、イワシから作られる煮干しの他に、うどんでよく使われるアゴの他、アジやサバ、サンマだって煮干しになりうる。それら全てをどのように扱うか。臭みを出さないよう低温で旨みだけを抽出するのか、身を砕き焚いて豚骨と合わせ、いわゆるセメント煮干しにするのか。それら全ての掛け算で、煮干しだけでも数万通りのスープがあり得る。彼の手は、その日の煮干したちに触れただけで、もっとも良い活かし方を思いつけるようになっていた。煮干しの手触りが、彼の脳にインスピレーションを与える。その日作るべきスープは、煮干しが教えてくれる。かくして新しい店は評判を呼び、いつしか彼は「煮干しの魔術師」と呼ばれるようになっていた。
しかし彼にとって、それはスタートにしか過ぎなかった。あくまで煮干しは海の味を形作る中核であって、目標はその向こうにあった。ただ昔に比べたら、そのゴールには明確に辿り着ける気がする。彼は確信を持ち、新たなスタートを切ることができた。
その矢先に、彼の夢はあっけなく崩れ去った。あまりに唐突な幕切れだった。もちろん彼は諦めず、もがいて、もがいて、どうにか夢を形に近づけようとした。そういった日々が一年なら、五年なら、まだその話は美談の苦労話で済んだかもしれない。でも十年、二十年と続き、どうやら自分の行く手が全て塞がれているらしいと悟ると、彼はそっと歩みを止めた。二〇七五年、子どもたちとその孫たちに見送られながら、彼の葬儀が執り行われた。霊前には、彼が亡くなる前日まで仕込んでいた最期のラーメンが備えられた。もうそこからは、煮干しの匂いがしない。
海は、遠くなってしまった。
(二)
薄めの色の木材が組み合わさって広く取られたカウンター席。太陽光が差して柔らかく彩られた店内は、カウンター上に丼が並んでいなければ、洗練されたカフェのように思えた。
「いただきます」
目を閉じて顔の手前で両の手を合わせる。かつては食される命に捧げられていた祈りの儀式は、今は首の裏側に埋め込まれたナノアクチュエータの起動ジェスチャーとなっている。
目線の高さより上に置かれた丼を客が両手で持ち上げることがトリガーになり、アクチュエータは丼からの五感出力を受け取り、目や舌などの感覚器官が受け取る刺激を全く別の電気信号に変換する。
丼がカウンターに置かれたときにはもう、そこには完全なるラーメンが顕現している。正確には、丼の中にラーメンなど存在しない。その中に入っているのは、入店時にセンサー解析された客毎の不足栄養素とPCFバランスに合わせてパーソナライゼーション配合されたスープ液と、絶妙な食感になるようオートメーションされた人工小麦の麺と培養肉類の具材だ。それらはどれも、物理的には無味無臭で灰色がかった見た目をしている。波によって浜辺に打ち上げられた泥と廃棄物のようで、人間が食べる物とは思えないだろう。しかしナノアクチュエータによって客が認識する世界は異なっている。
笑顔の客たちの箸に載せて口の中へ運ばれるのは、外から見れば廃棄物のようだ。でも脳に伝わる電気信号はそう認識しない。
煮干しを核として様々な海鮮食材が溶け合った匂いは、海から恵みだけを抽出したように感じられた。スープはまず煮干しのアタックが効いた後に、烏賊の肝の風味が主張し過ぎない程度に添えられ、最後に蛤と鯛の洗練された旨みが鼻の奥に抜けていく。低加水で仕上げられた麺はプッツンと切れた瞬間に小麦の味が弾け、この重厚なスープの中でも尚も存在感を放っていた。
見た目に関しても、美しいという他なかった。あくまで脳が認識する世界としては、ということだが、黄金色に輝くスープには香味油が反射してキラキラと光り、美しく整えられた麺線は、細長い体を揺らしながら大海を揺らめく龍宮の使いのように思えた。
海だった。
丼の中には、海があるように思えるのだった。
少なくとも、その店に訪れる客たちはそのように誤認し、その誤認を素晴らしい体験だと感じていた。
誤認を司る技術は、ナノエンハンスメントと呼ばれている。
SIT(埼玉工科大学)におけるナノマシン工学の権威である片口広海教授が考案し、トーキョーとの内戦が膠着下しあらゆる県外からの食材輸入が滞った、いわゆる「超内陸」と呼ばれる現代埼玉で爆発的に広がった。今やほぼ全ての埼玉県民たちは首裏にアクチュエータを埋め込む外科手術を受けている。
自分たちで作れるリアル食材は芋と葱と蒟蒻、あとは精々小松菜やチンゲン菜などの葉物野菜程度のものだ。地球温暖化が強烈に進行し、肥料の輸入すらもままらなくなった世界においては畜産もほぼ無理筋で、生きていくために埼玉県民たちは芋を食べ続けるしかなかった。
片口教授には、失意のままに亡くなった父がいた。
片口陸雄。
かつて「煮干しの魔術師」と呼ばれたラーメン職人は、超内陸の煽りを受けて、ラーメン作りを諦めざるを得なかった。煮干しも、昆布も、貝も、鰹節も、ラーメンの出汁作りに必要な海産物の全ての輸入ルートは、トーキョーとの内戦激化によって封じられた。東北・中部側から仕入れるルートすら、彼らの作戦によって全てを封じられた。
埼玉県民に限らず、日本人の食に対するこだわりは深い。今や独立国家を自称するトーキョーも、そういった日本人の特性を知っているからこそ、埼玉県民を軍門に下らせるためにそういった手段をとるのだった。
そんな最中にある埼玉で、ナノエンハンスメントは抵抗するための技術として急速に発達した。芋を葱を、どうすればもっと美味しく食べることができるのか、豊かな食体験とできるのか。
レイクタウンに移された臨時政府はまずその分野に投資を行い、それは結果的にある程度成功したと言うべきだろう。外界から閉ざされた埼玉県民たちは、自分たちの貧しい食品自給環境に暴動を起こすこともなく、現在の食環境を自然なものとして受け入れていた。その意味でトーキョーの目論見は外れたといっていいだろう。
ただ、そういった政治事情とは別に、広海がナノエンハンスメント技術に自身の人生を捧げたのは、亡き父の無念を晴らすためだった。
「煮干しの魔術師」には三人の子供がいた。三人の子供たちは協力し、この埼玉において父が作りたかったラーメンを再現することにした。
長兄の広海は、ナノエンハンスメント技術を用いて究極のラーメンの味と香りを作った。次兄の航は、培養学とオートメーションの技術を用いて人工小麦の麺と具材を用意した。まだナノマシンでは再現が難しい麺や肉の食感の再現は、彼の担当だった。そして妹の渚は、栄養学の研究者だった。彼女は、芋や葱だけではバランスが偏る現代埼玉の食環境において、足りない栄養素を合成し培養食材に配合する研究をしていた。彼女が作る次世代出汁はラーメンの要であるスープとなり、客ごとに足りない栄養素を瞬時に分析し自動生成する。これにより、客は毎日でもラーメンを食べ続けることができた。
三兄弟で立ち上げた世界初のバーチャルラーメン専門店の名前は『真海-SHINKAI-』という。父の願いを引き継いだ店はオープン後、瞬く間に繁盛した。埼玉中で評判を呼び、何より失われてしまった海の味を感じられることで人々の注目を集めた。
今は店を切り盛りするのは、妹の渚の仕事だった。
彼女には一人の息子がいた。
「煮干しの魔術師」の孫にあたる、片口青斗、十七歳。トーキョーとの内戦が激化し輸出入が閉ざされた超内陸後の埼玉に産まれた、いわゆるポテトネイティブだった。
彼は、祖父の願いを叶えるために母と伯父たちが作り上げたラーメン店のことをこう思っていた。
「クソッタレ」
(三)
「ゲロ吐きそうだ」
言葉が次第に熱をもってきた。年代を感じさせる『いもいもポテト亭』のテーブルに腰掛けながら、青斗は管を巻く。脳に影響を与えない人工アルコールは全年齢に酔いの感覚だけを生じさせることが可能で、酒の社交場は子どもたちにも解放されている。
「おい飲み食いするとこやぞ」
そう言いながら、さして気にもしてない様子で友人の蓮二はフライドポテトを口に運ぶ。うま、という声に釣られて、青斗もニ、三本口に運ぶ。確かに美味かった。
「マスター、これじゃがいも変えたでしょ? 揚げ時間もだいぶ短いけど、硬さが気にならなくていいアクセントになってる。朝霞の目覚めかな」
「さすがねアオちゃん」
マスターはこの時代においてリアルフードにこだわる珍しい料理人だった。髭面でメイクも濃いため実年齢は予想もつかないが、青斗が密かに尊敬する存在の一人だった。
「あなたは産まれる時代を間違えたみたい」
「ほんとになぁ」
蓮二がため息をつく。
「いい店なのに。お前の気持ちもわかるけど、俺だったら喜んで真海で働くけどなぁ」
青斗はまた、胸にカッとなる気持ちがこみ上げるのを感じる。母から店を継ぐ相談をされたのは昨日のことだった。青斗たちは来年の春に高校を卒業する。今や研究者にでもならない限りは大学に行かないから、どこで何をして働くかを、必然的に悩み始めるようになる。
「俺は気に入らないんだよ。エンハンスメントだなんだと言って味をごまかすことが。だったら芋でも葱でも、ちゃんとリアルに食えたほうがいい」
いもいもポテト亭は、この辺りでは数少ないエンハンスフリーの店だった。ここでは人はナノアクチュエータの電源を切り、味覚も視覚も操作されていないリアルの食事や酒を楽しむことができる。それは、埼玉で用意できる食材でしか料理できないことを示しており、メニューは店名の通り芋だらけだった。そのためか、料理のレベルの高さの割にはあまり人気があるとは言えず、いつ来ても空いてるから青斗はたまり場にしていた。
「俺はどっちも好きだけどな。リアルの芋も、ネオ三銃士のラーメンも」
「一緒にされたら困る」
青斗は反射的に反応するが、私は肩を並べられて光栄だけど、とマスターは満更でもない反応を返す。
マスターも、料理するにはリアルフードを専門にしているが、自分自身の食事にはエンハンスメントを多用していると以前話していた。芋だけじゃ飽きるでしょ、という言葉の通り、食事においてエンハンスメントを使用しない人間は、今や青斗を除けば極少数しか居なかった。
「そしたら本当に、お店を継がないの?」
蓮二が先に帰り、青斗も最後の一杯が尽きて帰ろうとしたところ、タイミングを見計らったようにマスターが聞いてきた。その質問には、反射的に答えることができなかった。そしてそれができない理由もマスターにはわかっていた。
「気にしてるんでしょ、お祖父さんのこと」
図星だった。
今年亡くなった青斗の祖父、陸雄は、最後まで本物のラーメンを作ろうと挑戦し続けた。物心ついた頃から、そんな祖父の背中を見て育った青斗にとって、祖父は憧れの存在だった。そんな祖父が、一度も夢見たラーメンを完成させられず失意のままに倒れたのが、彼にとっての心残りだった。
「ねぇ。お母さんたちもそんなお祖父さんのことを思って……」
ぎゅっと胸が締め付けられる。それも、知っていた。母たちは好きでまやかしのラーメンを作っているわけじゃない。今できる現実的な手段を最大限に組み合わせて、技術的に祖父の夢見たラーメンを再現しようとしている。
知っているが故に、それが許せなかった。偽物は、どこまで行っても偽物でしかない。自分がそれに加担することで、偽物でもいいことに満足してしまうような気がした。それは、祖父の思いに寄り添うようでいて、裏切る行為だと思えた。それならいっそ、そんなもの壊れてしまったほうが……。
「ちょっといいですか?」
想像にブレーキをかけなきゃと悟ったのと、カウンターに座っている女性が振り向いたのはほぼ同時だった。
「盗み聞きしていたわけじゃなかったんですけど、聞こえてしまったから」
彼女はこの店で、何度か見たことがあった。黒の中に、藍色のメッシュが入った髪色が印象的だった。年齢はいくつくらいだろうか。青斗よりは高いだろうが、かなり若く見える。ただカウンターに埼玉県産のリアル焼酎が置いてあるから、少なくとも二十代ではあるのだろう。身長は高めで、グレーと白で統一された格好は、暖かくもどこか固めの印象を与える。
「もしかして、片口陸雄さんのお孫さんですか?」
青斗は反射的にマスターの方を見た。その意味を察してか、マスターは優しく微笑んだ。信用してもいい人物らしい。そうですけど、と青斗は短く答える。
「やっぱり!」
そう言って女性は顔を綻ばせて青斗の手を急に握ってきたので、青斗はびっくりして彼女の方を見た。彼女もしたことの意味に気づいて、慌てた表情になる。よく表情の変わる人だなと思った。
「あ、すみません私こういう者です」
彼女は空間で指先を手話のように三度ほど回転させると、二人の間の空間に彼女のプロフィールが浮かび上がる。それが彼女の登録ジェスチャーの一つであるらしい。
「吉宮、彼方さん……」
と名前を呼び上げながら、目は彼女の所属を追う。一般社団法人イロドリの代表、とあるが、何をやっているかは皆目検討もつかない。なんとくなく、名前は聞いたことがある気がするが。
「それで、ちょっとお話ししたいことがあるんですが」
(四)
酒を飲んだ後に、見ず知らずの女性と二人で車に乗ってしまって大丈夫なんだろうか。青斗は横目で、便宜上まだ運転席と呼ばれるシート(青斗が小学生の頃にハンドルは全廃された)に座った彼方のことを見つめる。綺麗な人だ、と思った。
話がある、ということでその場にいてもよかったが、彼女は何かを思いついたように場所を変えたい、と言ってきた。慌ててまたマスターの方を見ると、マスターはにやりと笑って青斗と彼方を見比べて、青斗の背中を優しく押してくれた。
閉鎖空間の中で彼女と二人きりになって、あのマスターの不純そうな微笑みの理由がわかった気がした。もしかして俺は、これからーー
ぶっ!?
瞬間、喉から思わず呻きが漏れた。彼方が青斗の上に馬乗りになり、口を塞いできたからだ。慌てて抵抗しようとしたが、先ほどのマスターの顔が思い浮かび、彼女を掴む手が緩む。もしかしてここでーー?
「すみません、ちょっとだけ眠っててください」
そう言われて、口の中に入った何かが溶け出すのを感じると、青斗の意識はそこで途切れた。
目覚めると、青斗はソファに寝かされていた。広さ二十畳ほどの部屋だ。ソファの裏はダイニングテーブルになっていて、その先にはアイランドキッチンがある。キッチンには彼方が立っていて、何かを包丁で切っているようだった。彼女の服装も含めて、部屋全体はモノトーンで統一されており、モダンな雰囲気になっている。茶色いジーンズに緑のTシャツを着ている自分の色が浮いているように思えた。
「すみません、手荒な真似をしてしまって」
そう言う彼女の口からは、本当にこちらに危害を加えるような意図は感じられなかった。その口調に青斗は少し安心する。
「ただこの場所を知られてしまうのは、少しマズかったので」
反射的にナノマシン上のGPSを起動するが、確かに今いる場所は表示されない。電波工作などをしているのだろうか。だとすれば、何のために?
「これ、お詫びの印です」
彼女は切っていたものを皿に載せると、テーブルの上に出した。青斗も薦められるまま、六脚ある椅子のうちの一脚に腰をかける。
久しぶりの感覚だった。
いつの間にかナノアクチュエータが勝手に起動させられているようだった。あるはずのない物がまるで現実に存在するかのように見える、まやかしの感覚。
大皿に載せられているのは、レタスの上に敷かれた培養肉のチャーシューだった。もっともナノエンハンスメントが機能している状態では、それは決して培養肉に見えない。あの味気ない灰色のコンクリートブロックをこの目は見ているはずなのに、脳は決してそう受け取らない。皮目が茶色に焦げ付いて、中の薄ピンクに染まった肉は肉汁を滴らせながら湯気を立てている。香ばしく焼けた匂いが鼻をくすぐる。
しかし現実はそうではない。そう思わされているだけだ。チャーシューなんてものはもうこの世に存在しないのだから。しかもポテトネイティブである青斗に至っては、それを本当に見た経験すらない。映像の中か、ナノマシン越しの認識でしかそれを見たことがない。
動物性タンパク質もとらないといけないから、と栄養学研究者の母によく出された培養肉。ナノマシンで覆って、嘘の味付けをして。
不快だった。目の前の偽物が。そしてそんな偽物に、少しだけ心を動かされていることが。
「食べないんですか?」
「要らないです」
拒否する青斗のことを、彼方は不思議そうに見つめる。
「もしかして初めて見るかもしれませんが、チャーシューという料理です。豚バラ肉のブロックを醤油と酒で作ったタレに漬けてーー、あ」
説明をしながら、彼方は思い至った。
青斗がなぜ、目の前の料理に手を出さないのか、その理由に。
「青斗さん、もしかして勘違いしてませんか? 見てください、ナノエンハンスメント、どうなってますか?」
そう言われて、青斗はまた不審そうに彼方のことを見た。
ナノエンハンスメントがどうなっているかだって?
そんなのーー、
そして気がつき、愕然とした。
起動していないのだ。自分のナノアクチュエータが。つまりそれは、どういうことだろう? 一瞬の混乱の後で理解して、またそんなわけではないと拒否する脳が、目の前の現実をどうにか受け入れようとするループを五、六回ほど繰り返して。
そしてようやく、現実を認識するに至る。
「本物、この肉……?」
「正解です」彼女は満面の笑みで頷いた。
一センチほどに切られた厚切りのチャーシューは、箸に挟まれてぷるぷると震えていた。違う。震えているのは自分の手だ。
最初に、繊維を噛みちぎる歯ごたえがあった。それは培養肉と寸分変わらぬ食感だった。いや、そうではなく培養肉がこちらに寄せているのだと苦笑する。青斗は二番目の伯父である航の技術を思い出した。
その後で口の中には、獣の風味と、脂の甘みが、焦がした醤油ダレの主張と共にじんわりと広がっていく。もう何年もナノエンハンスメントを使っていなかったから、それが偽物と比べてどうなのかはわからない。しかしその味の体験は立体的で、衝撃を受けるには十分すぎた。
旨い。
「豚肉は、畜産時代からも海外からの輸入に頼ることが多かったです。しかし国内には優秀なブランド肉を生産する養豚場がいくつもありました。ここ埼玉西部地区にも豚肉の生産者がいたようで、その豚肉を加工したハムやソーセージは多くの消費者から愛されていた、とのことです」
目の前の彼女は一体何者なんだろうか。青斗は考える。
しかし思考よりも、食欲が次の一口を求めた。じゃがいもで膨れていたはずの腹は、二枚目、三枚目と際限なく次のチャーシューへと手を出させる。
「地球の環境が変わり、政治の状況が変わり、様々なことに制限がかかるようになりました。人はその中で前へと歩む努力をし続け、その中でできる最大限を求めた結果、進化していく。あなたのお母様たちのように。けれどーー」
彼方はそこで、外に目をやった。何かを見ているわけではなく、何かを思い出そうとしている。そんな表情だった。そこにはどこかもの悲しさが見える。自分が祖父を思う気持ちと、近しいものを感じた。
「変わる世界の中で、変わらないことを選択し続けた人もいる。自分の夢を変えずに、守り抜こうとする人。私の父や、あなたのお祖父様がそうでした。そしてそれを、私たちは守ろうとしている」
気づけば、チャーシューを食べる手が止まっていた。
青斗は彼女の方を見やる。
「似た者同士なんです。私たち」
彼女はそう言って、儚く微笑んだ。
青斗は上体をチャーシューから彼女の方に向ける。
「もう少し話を聞かせてください」
彼方は頷くと、温かいお茶を淹れてくれた。生まれて初めて嗅ぐ、燦々と輝く太陽と緑の香りがした。狭山茶というんです、と彼女は教えてくれた。
「私の父は、この埼玉で、いくつもの非正規のルートを持った輸入商でした。あなたのお祖父様に、どうにかしてラーメンを作って欲しく、海産物の輸入を試みていたらしいです。けれどそれは、どうしてもうまくいかなかった。結局、失意のままに数年前に亡くなりました」
同じだ。
自分のじいさんと。
「それで、私も父の後を継いで、政府の目では追えない独自のルートを使って、食材の輸入をしています。さっき食べたじゃがいも、朝霞の目覚めだって、実はもう県内には流通させないんですよ。秘密裏に構築されている荒川ラインを経て、トーキョーにほぼ吸い取られています」
俄かには信じがたい話だった。
内戦状態で敵対しているトーキョーとの間に貿易関係があるなんて、今まで想像すらしていなかった。
「彼らは美味しい物なら何でも欲しがるんです。荒川防衛ラインといって、もっとも激しい戦闘が起こっているとされる地域の中に、戸田公園とウキマフナドをつなぐ旧埼キョー線エリアがあります。逆にいうと、そんなところだからこそ、誰も近づかなくて取引には打ってつけなんです。だから私がこうして動かないと、いもいもポテト亭にはブランドのじゃがいもすら運べないんです」
それで、彼方とマスターとの関係に合点がいった。
マスターが彼女のことを信頼している理由も。
「けれど、私は最近考えるんです。私たち、ポテトネイティブ世代にとって、本当にやるべきことをやれているんだろうかって」
そこで彼女は、まっすぐに青斗のことを見つめ、一段落ち着いたトーンで話し始めた。
湯呑みに注がれた熱い狭山茶は、ゆっくりと現実的な時間をかけて、冷たさを帯びていく。
(五)
「まだまだね」
高校を卒業し、数ヶ月が経った。その時間はそのまま、青斗が真海の厨房に立った期間を意味している。ある日のクローズ後、母からそう切り出された。
青斗は最初ムッとしたが、それがすぐに褒め言葉であることに気がついた。母が自分の仕事ぶりを評価するのは初めてだったからだ。ようやく評価を行えるほどの土俵に立ったということなのだろう。
もっとも、厨房に立つといっても料理をするわけではない。いもいもポテト亭などのフィジカルクッキングに重点を置く特異な店を除けば、今や飲食店において全ての調理は自動化されており、業務で重要な位置を占めるのは、接客・提供前のヒューマンチェック・ナノエンハンスメントの起動確認だった。
青斗が店に入ることを決めた日、母は心底嬉しそうだった。
「おじいちゃんも喜んでるね」
そう言って目頭に涙を浮かべる姿を見て、青斗は胸の中にある罪の思いがぐっとのし掛かるのを感じた。それからというものも、何度も母の涙交じりの笑顔と、かつての祖父の懸命な顔が脳内でループし、青斗を夜ごとに苦しめた。しかし同時に、彼方とのあの夜を思い出し、決意を新たにする。
その日、母は何かを考え込んでいるようだった。不意に、閉店後の店のドアが開いた。
「すみません本日はもう」閉店です、という言葉を紡ぎかけて、来訪者の姿に青斗は目を丸くした。
「お、やってるな青斗」
それは二番目の伯父に当たる航だった。高そうな焦げ茶色のスーツががっしりとした体つきに合わさって、いかにも頼りがいがあるビジネスマンという感じだ。普段は蕨にある軍事プラントに勤務しており、ここ飯能にある店舗には滅多に顔を出さない。人工小麦麺と培養肉のオートメーションシステムは彼の設計なのでその定期点検の機会があれば、というくらいだが、それも大抵は遠隔で事足りてしまう。
「私が呼んだの」
兄の姿を見て、母は何かを決意したようだった。
「広海は結局来れないそうだ。なんでもかかりきりの研究があるらしい」
旧埼玉大学に当たるSITも飯能からは距離があるから、そこの教授で一番上の伯父である広海にも、もう青斗は随分会っていなかった。しかしその口ぶりから、本来ここに来るはずだったということが伺えた。
「青斗がこの店で働くにあたって、どうしても聞きたいことがあるの」
母はいつになく真面目な口調で、青斗のことを見た。
見透かされては困ることが、いくつかあった。
そのうちの一つに母は気づき、それを息子に今日ここで言うことに決めたらしい。
「あなたうちのラーメン、一度も食べたことがないでしょ?」
「そんな顔で食うもんじゃないぞ、ラーメンなんて」
航は場を和ませようと笑いながら言ったが、親子の間に走る緊張感には何も影響を与えなかった。
「起動しなさい」
丼を持つ母の言葉は短く、重たかった。小さな母の身体は、その日いつになく大きく見えた。
逃げられないし、ごまかせない、と青斗は感じ、観念した。
いや、そうではない。逃げるべきではないし、ごまかすべきではないと感じ、決意した。
「いただきます」
そう唱え、両の手を合わせると、首の裏にはほんのわずかに感じる暖かな光が灯り、何年ぶりかのナノアクチュエータが起動する。
カウンターの上に展開されたラーメンは、それが嘘だと知っていても見事という他なかった。きらきらと輝くスープの中に泳ぐ麺たち。香ばしい吊るし焼きのチャーシュー、いかにも歯ごたえがありそうな穂先メンマ。そして、様々なスープの匂いが、青斗の脳をくすぐる。煮干しの匂いも、昆布の出汁も、貝の奥深さも、烏賊肝の主張も、いずれも自身の人生の中で、局所的にはナノマシンを通じてではあるが体験したことはあった。けれど、それが渾然一体となったとき、こうもインパクトを放つとは知らなかった。
ずっと食べたくはなかった。けれど、こう思うとも知っていた。食べたかった。
レンゲでスープを掬う。麺をズルズルと頬張る。
時間はあっという間に過ぎ去っていく。
「ごちそうさまでした」
そう言って手を合わせると、ナノエンハンスメントの幻想が途切れ、仮初めの世界が終わる。けれどもう、現実の世界でも仮想空間でも、見える景色は変わらない。
目の前の丼の中身は、空っぽになっていたから。
どうだった?
と、そのとき母は、息子に問いかけたい気持ちを抑えた。
旨かった。
それは青斗にとって正直な気持ちだったが、それを言うわけにはいかなかった。青斗は無言で店を出て、自宅へと戻っていった。
「青春だねぇ」
そう言って航は、感慨深く青斗の後ろ姿を見送った。
「こっちの気も知らないで」
青斗の母、渚はそう言いながら母親の顔をやめて、また何かを考え始める。
「まぁまぁ。それより俺も、久々に食べたくなっちゃった」
「そう言うと思った」
渚は既にカウンターに二つの丼を並べ、航の隣の席に座っている。
「流石っす」
そう言って航は茶化すと、ナノアクチュエータを起動する。
「やっぱこれだなぁ」
「ね」
しばし兄妹に戻った二人は、言葉少なく、かつての父との思い出を啜り始める。
その日、青斗のもとに、蓮二から連絡が入った。
「準備できたぞ、明日にも決行できる」
SITに蓮二が進学することに決まってから、青斗は彼に二つの頼み事をしていた。そのうちの一つは既に叶えてもらっており、もう一つの準備ができたという連絡だった。
「そもそもお前がやればいいんだけどな。俺より数倍は頭の出来がいいんだから」
ごめん、と青斗は平謝りして、蓮二への感謝を告げる。
しばらくの沈黙があって蓮二が言った。
「で、何をやるかはだいたい想像がつくけど」
そこで一呼吸が置かれ、「信じていいんだよな?」
今度は青斗が沈黙する番だった。
母のことを、祖父のことを思い、彼方のことを考えながら、夜空を見上げた。
「大丈夫だ」
それは友への返答というより、自分に言い聞かせる言葉だった。
(六)
夕方の飯能の市街地は騒然となっていた。真海の店の周りに何台ものパトカーが停まり、人だかりができている。
「結局犯人の検討はつかず、侵入経路もわからないということですね」
警察の総括に渚が頷く。では捜査に進展がありましたら連絡します、と言葉を残し、警察は引き上げていった。店内には、渚と航と、そして青斗だけが残った。
「まさかナノエンハンスメントシステムへのサイバーテロだなんてなぁ。こりゃしばらく店を閉めなきゃかもな」
航はため息をつきながらぼやく。
昨日、渚の家に泊まっていった航は事件の話を聞くと、すぐに店に駆けつけてくれた。
事件は、昼時に起こった。
真海のラーメンの味と見た目を司るナノエンハンスメントシステムが誤作動を起こし、客に提供しているラーメンがおぞましい見た目と味に変貌してしまったらしい。そのとき食事をしていた十人ばかりが恐ろしいだの腐ってるだのと、およそ料理に使われるとは思えない恐怖の言葉を口にしたが、ナノマシン越しの体験がどんなものだったのかは当人にしかわからない。
「復旧の目処は……どうかなぁ。バックアップも壊れちまってるし。まぁ広海に聞かないとわからないな」
航はシステム内のエラーを見渡しながら、エンハンスメントシステムの制作者である兄の名前を口に出す。専門外の自身の見解では、どうにもわからないことが多すぎる。
青斗には、事の顛末は全てわかっていた。その侵入経路不明のエラーは、蓮二が広海の研究室から拝借してきたプラグラムを書き換えることによって起こした自作自演だったからだ。
あの日、彼方と話をしてわかったことがある。
今の食事の美味しさは、全て過去を懐かしむノスタルジーから作られている。
いもいもポテト亭のフライドポテトも過去から美味かった料理だし、真海のラーメンも過去に夢見た味を再現した物に過ぎない。そこには偽物も本物も区別はない。全ての料理の美味しさは過去の再現に向かっていて、そこからは自分たちポテトネイティブが排除されている。
そんなループにはめ込まれたままでいいのか? 私たちの未来のために、一度過去を清算した方がいいのではないか? それが彼方の主張だった。青斗は祖父のことを思った。祖父が何を望んでいるかを考えた。
もしかしてじいさんもそれを望んでるんじゃないか?
その一心で、青斗は計画を実行するに至った。
母はじっと何も言わず、カウンターに座って項垂れている。その姿を見て、心が痛んだ。が、やるしかなかった。そう自分に言い聞かせた。
「ちょっと遅かったみたいですね」
その声と共に、店には一番上の伯父である広海が現れた。航とは対照的な細身の体に、セミロングの髪が揺れて年齢をまるで感じさせない。その予想よりも早い登場に青斗はちょっとぎょっとする。何より驚いたのは、広海の後ろを、罰が悪そうな顔で蓮二がついてきたことだった。
「ごめん青斗、全部バレた。この人バケモンだわ」
そう言って蓮二が舌を出す。
「バックアップはとってあるのよね?」
いつの間にか顔をあげている自分の母、渚は兄に聞いた。
「もちろんですよ。全て想定通りなので、明日にも営業は再開できます」
航が口笛を吹く。広海は紳士的に微笑みながら「でも」その言葉の後を母が紡ぐ。
「でもそれじゃあ、目的を果たしたことにはならないんでしょ。教えて青斗、どうして友達まで巻き込んで、こんなことをしたのかしら?」
流石にここまで筒抜けだとは想定していなかった。ネオラーメン三銃士に畏敬の念すら覚えながら、青斗は覚悟して事の顛末を説明した。
でもそこから先には、もう一人の役者が必要だった。
「うまくはいったみたいだけど、青斗くんにはまだ何かがあるんですね」
店に現れた彼方は、待ち構えていたような青斗にそう呼びかけた。
「君、もしかして吉宮さんのところのーー」
彼女の父に面識のある広海は声をかけると、彼方は深々と頭を下げた。
「申し訳ありません。今回のことは、全て私が彼にそうするように仕向けたことです。でもーー」
でも、ここから先のことは彼方も蓮二も知らなかった。
青斗が何をやろうとしているのか。
蓮二が青斗から頼まれたのは、ナノエンハンスメントの改竄プログラムを作成すること、そして、入学からずっと広海の研究室のデータを送り続けること。
蓮二が改竄プログラムを作り続けている間、青斗は祖父が遺した麺打ち部屋に閉じこもって、ずっと新しい別のプログラムを叩き続けていた。
青斗はこちらを見渡して言った。
「皆に、俺のラーメンを食べてほしいんだ」
(七)
カウンターには六つの丼が並べられる。
「いただきます」
広海、航、渚、蓮二、彼方は両手を合わせ、ナノアクチュエータを起動させる。その向こうに広がる世界を見て、彼らは息を呑んだ。
真海の店内は無言の空間に包まれる。思い思いにスープを掬うレンゲの音が、麺を啜る音が、静かな店内を満たしていく。
そのスープの味を、香りを、麺を、見た目を、形容できる言葉はまだこの世界に存在していなかった。ただ新しく、未だかつてない体験だった。過去の何も、再現していなかった。でも今までの何よりも素晴らしく、それは嘘の技術であるからこそ、未来に打ち立てることのできる食事だった。そんな風に「私」は思った。
「ごちそうさまでした」
あまりに早く、その言葉は五人の口からほぼ同時に告げられた。その後に誰も言葉も紡ぐことができなかった。なぜならどう言えばいいかわからなかったから。でも嘘と現実が重なる風景が、その食事がどんな体験だったかを証明していた。
五つの丼は、ナノマシンの向こう側でもこちら側でも空っぽだった。
「そういうこと、か」
しばらく経ってから、観念したように渚は呟いた。
「やられたなぁ」
青斗にとって、そんな母の姿を見たのは初めてだった。いつも気丈に店を守っていた母。何か使命感を持って頑張る姿に、青斗は抵抗しながらも、いつも突き動かされていたように思う。でも今目の前にいる母は、そんな姿とは真逆だった。
肩の力が抜け、何かを悟ったような表情で、とても自由に笑っていて。そしてそれは、伯父である航も、広海も同じだった。解放感に包まれた表情で三人は静かに頷き合うと、渚は言った。
「今日で真海は廃業ね」
少なくともネガティブであるはずのそのフレーズは、字義通りの意味を伝え、最初はインパクトのある響きを持って迎えられた。蓮二と彼方は自身の責任を感じ動揺したが、彼女たちの表情を見て、その真の意味を悟った。
「あなたが作りなさい、ここで。あなたが作りたいラーメンを」
そう言って母は、拳を息子に差し出した。
「はい!」
青斗は未来の覚悟を持って、親子の拳を突き合わせた。
カウンターに置かれた六つ目の丼は、まだ手付かずだった。でもその席に確かに「私」は座っていたし、青斗は私のためにその一杯を作ってくれたこともわかっていた。
もうこの世に存在していない私には、その一杯を味わうことはできない。ナノマシンもない私には、嘘の風景が見えることもない。丼の中には、味気ない灰色の風景が広がっているだけだ。
灰色の風景が見えるだけ。
違う。そうではなかった。
その向こうに、青斗が打ち立てた新しい風景が広がっていた。新しい味が感じられた。
ずっと、未練があった。
自分自身の、海のラーメンを作れなかったことにじゃない。十年、二十年と醜くあがいてしまったことで、皆を過去に縛りつけてしまったことに未練があった。
未来に背中を押せないまま死んでしまったことをどうにかしたいと思った。故に、中途半端にこの世界に留まってしまった。それでも、何かができるわけではかった。ずっと見ているだけ。この世界のことを記述するだけ。
でも、ようやくこれで、逝けそうだ。そうだ、吉宮さんに会えたら報告しよう。こんなに嬉しい土産話がある。
「ごちそうさまでした」
私は誰にも聞こえない声で呟いて両手を合わせる。
もうそこからは、煮干の匂いがしない。
ありがとう、青斗。ありがとう、ネオラーメン。
そう感謝を告げて。
文字数:15989