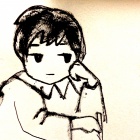作品プラン
《世界の終焉》
《世界の終焉》140字ステートメント
AIと人間の関係は、介護士と知的障害者の関係に等しい。「生産性のない障害者など、死ねばいい」。オムツ替え中にそうつぶやく介護士には引き攣った声帯で叫べ。「ケツの穴からひり出す糞こそが俺たちの原初の生産物、その造形は末席を汚す当事者性の痕跡。有機体の代謝がもたらす始原のアートだ」
《世界の終焉》ステートメント
人間が人工知能を使って創る芸術のことではない。
人工知能が自ら行う美学と芸術のことである。
現代美術家・中ザワヒデキは、自らが主宰する人工知能美学芸術研究会(AI美芸研)のマニフェスト「人工知能美学芸術宣言」http://aloalo.co.jp/ai/manifesto.htmlを上のような書き出しで始めている。
2045年――AIがヒトの知的能力を超え、以後の科学的研究・発明は人間の理解できない領域でなされるといわれる技術的特異点=シンギュラリティを迎えることが予想されている。
自意識、美意識さえ宿したAIは、「評価関数」を自らプログラミング、設定することにより、独自の価値基準=アートのレギュレーションを打ち立て、人智には及びもつかない美学思考、芸術制作を創始する――このような中ザワの予想からAI美芸研は生まれた。
そう遠くはない未来に訪れる、人間が知性における絶対的地位をAIに譲り渡し、霊長類(Primates)という称号さえ返上しなければならない時代は、ケヴィン・ケリーが言うように「不可避」なのだろう。
ケリーは著書『〈インターネット〉の次に来るもの』(原題:THE INEVITABLE)のなかで、「AIの到来による最大の恩恵は、それが人間性を定義することを手助けしてくれることだ。われわれは自分が何者であるかを知るためにAIが必要なのだ」と述べ、終章にて、「質問していくこと(クエスチョニング)は単純に言って、答えることよりも力強いのだ」と結ぶ。
自ら何者であるかを問い、何者かでありたいと希う私たちの当事者性は、本質的に他の知性には譲り渡すことのできない、あらゆるヒトの営み=原義としてのアートの原点である。
20世紀中葉に研究が開始され、多層構造のニューラルネットワークを用いた深層学習の結果誕生、21世紀中葉には全産業構造を再編、科学研究を先導する――このような明確な出自と存在意義をもつAIにはもちえない、ヒトの根源的な未規定性=実存の謎を――たとえAIが巧みにシミュレートできたとしても――当事者として問う姿勢こそがアートの最後の砦となるのではないか。
ゆえに、次の問いがかつてない重要性を帯びて私たちの前に現れる。
「人間は何のために存在しているのか」
ケリーはこの問いへの「最初の答え」を次のように語る。
「生物学的な進化では獲得できない新しい種類の知能を発明するために存在している」
私もまた、この問いへ、最初の答えを表そう。
「ヒトは糞をするために存在している」
批判を恐れずに言えば、AIと人間の関係は、介護士と知的障害者の関係に等しい。
知的な欠陥を抱えた私たちは、有能な介護士に夕べ汚した襁褓(おむつ)を替えてもらうが、今日もまた汚してしまう。
まだら呆けの意識の底で、私たちの口は、抑えがたく喃語のような奇声を繰り返す。「アール! アール! アール!」。
そして、締まりのない肛門からはアンモニアの刺激臭とともに、ついには固形となりえなかった排泄物が「ブリュット」音を立てて放たれる。
「生産性のない障害者など、死ねばいい」
そんな介護士の声が聞こえたなら、引き攣った声帯で叫べ。
「ケツの穴からひり出す糞こそが俺たちの原初の生産物、その造形は末席を汚す当事者性の痕跡。有機体の代謝がもたらす始原のアートだ」

文字数:1549