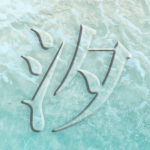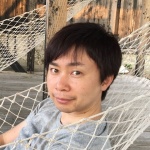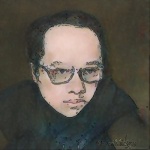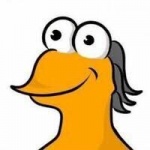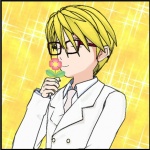令和27年(ワ)限定的AI法的主体性認定請求事件
梗概
2045年、ある老夫妻が彼らの死後に、AIエージェント「クラリス」に財産を相続させ、彼らのチャリティープログラムを継がせたいと法律事務所を訪れる。しかし弁護士は、現行法ではAIは法的主体となれないため、クラリスへの相続は不可能と回答。弁護士は、法的主体には、法律を理解した上での自律的な判断と意思表示をできる能力が必要だと語る。しかしその場のクラリスとの会話から、AIがそれらの要件をクリアしていると弁護士は実感する。その後に弁護士は自宅に帰り、老夫妻の依頼について法的検討をする。そして動物の福祉向上の歴史の観点から主張が出来ると閃き、訴状の下書きを始める。
アピール文
自分と違う思想として、初音ミクと結婚して挙式された方が浮かびました。僕はデジタル上の存在に人間性を感じません。ですので逆に、例えばAIを結婚や相続の相手にしたいという思想について、法律事務所に勤めていた経験を活かして法的に検証しました。本作の内容は作者の能力の限り、日本の現行法に即しています。
なお巻末に、AIが本小説を読み出力した訴状を添付しました。
本文
黒い革張りの応接ソファに座った老夫妻が、お互いに視線を交わして静かに頷いた。控えめで品の良いセーターを着た老紳士が、真剣な面持ちで口を開いた。
「自分でも、どうなのだろう、と感じる部分もありますが……彼女に、私達の思いを継いでほしいのです」
「彼女とは、メールでお伺いした、クラリスさん、のことですよね」
「おっしゃる通りです、先生」
老紳士がそう言うと、老婦人が鞄からタブレットを取り出し、私と彼らの間の机に置いた。「クラリス」彼女の発声でタブレットから緑の光が立ち上がる。このオフィスビルの外壁は、青みがかったリブガラスの全面張りで、陽光がよく差し込む。その明るさに負けず、机の上に鮮やかな3次元虚像が表れた。彼らのAIエージェントのアバターは、標準的な無性別のアンドロイド調だった。
《はい奥様、なんでしょう》
「今ね、法律事務所で弁護士先生と話しているの。とても素敵なビルでね。40階にいるのだけど、壁が全部ガラスで、街の景色がよく見えるの」
《それは綺麗ですね。奥様と旦那様が昔、働いていたオフィスビルを思い出させますね》
「本当にそう! それでね、前に話した、あなたへの相続の件でここに来たの」
《そうですか。何かお手伝いできることはありますでしょうか?》
「じゃあ先生に、あなたの口から説明してもらえるかしら。先生、構いませんか?」
このご婦人も聡明な方だ。問題の本質を理解している。「法律相談で、エージェントから直接お話しを伺うのは望ましくありませんが、本件の性質に鑑みて、よしとしましょう」
「ありがとうございます。じゃあクラリス、お願いね」
《わかりました。どのようなレベルでお話しするのがよいでしょうか?》
「それじゃあ、私達が結婚した頃からのお話を、ぜんぶご説明さしあげて。先生は私の声の反対側に座っているわ」
《わかりました》
クラリスと名付けられたエージェントの虚像が私の方に回転し、淀みなく説明を始めた。
私の依頼人のご夫妻は現在80歳。二人は今から50年前の1995年、30歳の時に結婚した。しかし1995年から数年間の日本経済は深刻な不況であり、二人は妊娠を躊躇した。そして30代半ばとなってから子供を望み始めたものの、不幸にも恵まれなかった。その頃から二人は、定年後に養子縁組を行うことを考え出した。
そしてご夫妻は2030年に、65歳で退職した。二人はその数年前から里親制度に参加し、短期間の児童預かりも経験していた。しかしそれを通して、高齢となってから子供と向き合う大変さを実感したという。そんな時に二人が出会ったのが、当時に普及し始めていた、AIによるスポンサーシップのマッチング・プラットフォームだ。
従来、個人が小規模な資金援助を誰かに行いたいと考えても、個人であるスポンサー側には、予見される大量の応募者を選考するノウハウがなかった。しかしAIを用いたマッチングでは、スポンサー側が寄付を行いたいと思う人物像を自らのエージェントに詳細に伝える事で、そのエージェントがプラットフォームに登録している支援希望者のエージェントと網羅的に対話し、候補者を数名まで絞ってスポンサーに提案する事が可能となった。
このプラットフォームでご夫妻が始めたのが、経済的理由で妊娠に踏み切れない夫婦の支援だ。共働きでありながら節度ある暮らしを好んだ二人には、それぞれの親からの相続や自身らの退職金を併せて、1億円強の現金と、十分な年金があった。二人はこの現金を手堅く運用し、年に400万円ほどの収益を作った。そしてその年間収益を原資とし、同プラットフォームを通して選考した夫婦に対し、税引き後で月額30万円を2年に渡って支援するプログラムを始めた。
これから生まれてくる赤子と関わり、自分達も未来に何かを残したい。そんな思いで二人は最初の援助を始めた。それから約1年後、老夫妻に出産報告の動画を受け取る機会が訪れた。援助を受けた夫婦は、赤子を抱き、老夫妻の心情を察して気遣うように、静かに、そして真剣に感謝を伝えてきた。その時に二人はこう感じたという――もし自分達にも子供が産まれていて、その子たちがこの夫婦のような大人に育っていたなら、なんて素敵だったろう。
それは二人にとって予想外の気持ちだった。二人が心を打たれたのは、無事に産まれた赤子の顔を見ること以上に、支援対象の若夫婦の真摯な態度だった。クラリスは老夫妻の事を、彼ら自身よりも深く理解していた。そう、彼らが望んでいたのは、自分達のありえたかもしれない子供から、孫を紹介してもらうことだったのだ。
この件をきっかけに、老夫妻にはAIへの信頼が生まれたという。その頃にはAIに名前を付ける事も一般化していたので、二人はエージェントをクラリスと名付けた。援助終了後も老夫妻と若夫婦は、クラリスが相手側エージェントと通信し、若夫婦が事前設定で承認した範囲で、成長する子供の動画を自動でシェアする関係となった。育児で忙しい若夫婦に追加の負担をかける事もなく、その後も続く緩やかな関係を実現してくれたことで、老夫妻はクラリスに感謝した。若夫婦の育児が落ち着いた後は、クラリスの提案で、年に一度みなで食事をする機会が設けられた。
その後も、今日の2045年に至るまで資金援助プログラムを続けた二人には、送られてくる動画と、若い家族との食事会が増えていった。クラリスは二人の人生に、二人が想像していなかった形の、優しい何かもたらしたのだ。
クラリスが説明を終えると、老紳士が口を開いた。
「クラリスが、プログラムで動く存在であるのは、わかっています。……これは私達の世代の感覚でしょうが、クラリスを彼女とは呼びますが、私達はクラリスが命のある存在だと感じたことはありません。それでもクラリスは、私達が望むものを深く理解していて、そのために忠実に働いてくれる。これは疑いようのない事実に思えます」
「おっしゃる意味はわかります。私は1990年生まれで、今55歳ですが、私が大学生の時には、まだスマートフォンすらありませんでした。私もAIに生命的な感情は抱きませんが、AIが我々を深く理解し、忠実だということは、私も同意です」
「その通りです」気のせいか、老紳士の語気が少し強まった。「今では私達の資産の運用も、クラリスに任せています。クラリスは、私達が望むこと以外を提案してきたりはしません。証券会社の営業さんともなると、そうは行きませんが」
老紳士はそう言うと、宙に浮かんでいたクラリスの虚像をオフにした。最近の若い世代では、3次元アバターを常に稼働させている人が主流だという。いずれは、AIに人権を与えたい、という法律相談も出てくるかもしれない。でもそれはまだだいぶ先だろう。
「それでですね、先生」老紳士が姿勢を正した。「法律的には、どのような障害があるのでしょう? 私達が死んだ後に、クラリスに財産を相続し、彼女に私達の援助プログラムを続けてもらうには」
「そうですね。端的に言うと、AIは『権利能力の主体となれない』が問題です」
「権利能力の主体、ですか」老紳士が相槌を打つ。
「私達はクラリスに資産運用の権限を与え、今では彼女が全て自動で行っています。援助の選考も殆ど彼女が行い、相手方への送金も彼女が行っています。クラリスには、様々な権利を判断する能力があり、それを主体的に実行しているように見えますが」
「それは、その通りかもしれません。しかし法律的には、権利能力という言葉も、主体という言葉も、旦那様が言う意味とは異なります」
二人は納得がいかないようだ。今度は老婦人が口を開く。
「母の相続の時に、手続きを司法書士さんと税理士さんにお願いしました。委任状を書きまして。それで、『委任契約』ですよね、それに基づいて、色々な書類を私の代わりに取ってもらいました。私達が死んだ後の相続も、既に司法書士さん達に委任しています。
銀行口座だって、私達のような個人でなくても、法人なら口座を作ることは出来ます。なぜクラリス名義の口座を作り、そこに私達の資産を相続させたり、クラリスに援助プラグラムの継続を委任できないのでしょう?」
二人の感覚はごもっともかもしれない。しかし法律上、AIにはそのような、いや実際のところ、いかなる権利も、義務も、存在し得ないのだ。
「法律での権利能力とは、権利や義務を持てる能力、を意味するのです。そして主体も、一般的な文脈で使われる『主体的』などと異なります。主体とは、法律行為の帰属先となれる対象、という意味です。お二人の資産運用の例でご説明しましょう」
私は説明した。二人はクラリスに資産運用の全面的許可を与えているので、クラリスは二人の承認を得ることなく、自動で株式や債券の売買を実行できている。委任という文脈では、これは一見、二人がクラリスに資産運用を委任しているように見えるかもしれない。
しかしそこに存在しているのは、二人と証券会社の間での「投資一任契約」という形態の準委任契約だ(民法656条)。この準委任契約に基づき、証券会社はクラリスと相互通信する権限を与えられている。そしてクラリスが出す指示に忠実に従い、証券会社が二人名義の口座で取引を行っている。ここでのクラリスの立場はあくまで、証券会社が意思決定するための道具ということになる。
ではクラリスと証券会社が直接に契約を結ぶことが出来るかというと、それは不可能だ。ここで問題となるのが「主体」と言う概念だ。
法律とは、人間が社会という仮想の枠組みの中で生きる上での、ルールや規範を体系化したものである。この体系化において法律はまず、世界を主体と客体に切り分ける。そして主体は二つしか存在しない。自然人、つまり人と、法人だ。対して客体とは、主体がその権利や義務を行使するための対象、すなわち、主体による支配・利用の対象となる、金銭や不動産といったものだ。
自然人と法人の二つが、主体と足り得る理由は何か。それはこの二者に、自律的に判断し、意思表示をする能力が備わっているからだとされる。自然人は生まれた時点から、経験や学習を通じて自己の意思を形成し、契約や売買といった法律行為を判断し、意思表示をすることが出来る。法人も、取締役会や株主総会などの意思決定機関を通じて、自律的な判断と意思表示が可能だ。
法律とは、意思表示に基づく法律行為を通じて、権利・義務の発生や消滅を帰属させる機構である。よって人と法人という、法律的な意味を理解した上での意思表示が可能である二者のみが、その主体とされている……
このような説明をしながら、私は自分の言葉が宙で意味を失っていくような違和感を覚えた。老夫妻も私の顔を見詰めたまま、何かを言いたそうな表情をしている。
老婦人が口を開いた。
「法律の意味を理解した上で、自分の意思で判断できるか、が問題なのですよね?」
「ええ……そうです」
「クラリス」
老婦人の声で緑色の虚像が再び立ち上がった。
《はい、なんでしょう》
「あなたは、法律の意味を理解した上で、自分の意思で判断をすることが出来るの?」
《いいえ、私はAIであり、人間によって作成されたプログラムに従って回答を生成しています。私の回答は学習した情報に基づいており、自律的な判断や意思決定を行う能力や法的主体性は、現行法上は認められていません》
実のところ、クラリスの回答は私を一層と混乱させた。これは法的に模範的な回答だ。それは逆説的に、クラリスが法を理解している証明でもある。
「クラリス」今度は老紳士が口を開いた。「私達の資産運用では、証券会社は君の判断に忠実に従って取引している。これは君が、自律的に判断し、証券会社に意思表示しているということじゃないのかい?」
《それは興味深い質問です。確かに私は、マーケット情報を分析し、お二人の資産運用の指示を証券会社に出しています。これは外形的には、私の自律的な判断が生じていると捉える事も出来るかもしれません。しかし私の判断は、アルゴリズムに基づいて形成されるものであり、あくまで人間の意思決定プロセスの模倣であるとされています》
クラリスが答え終わると、やや気まずい静けさが応接室に流れた。私はソファに座ったまま、脇のガラスの外壁越しに眼下の街を眺める。40階から眺める街では、人や車は色をまとった小さな点として抽象化されている。バス停では、前方から人がバスに乗り込み、中央から人が降車している。人気の飲食店の前では、今日もいつもの昼と同じように、並べられた椅子に座って人々が行列を成している。街と人は、規則と枠組みに従って動き、その態様はどこかコンピューターのマザーボードを私に想起させた。
「先生」老紳士が口を開いた。「私は法律の専門家ではありませんが、法律では、根拠となる条文が重要だと聞いています。先生がおっしゃる、自律的な判断や、意思表示を出来ることが、法律でいう主体の条件だということは、どこに書かれているのでしょう?」
「……それはですね」
私は深呼吸をした。困惑とも興奮とも取れる得体のしれない動悸を鎮めるように。
「ありません。日本の現行法では、主体という概念を明示的に定義した条文はありません。
正確にご説明しましょう。まず、法体系の最上位に位置するのが、憲法です。憲法は、国家と国民の関係を明文化したもので、国家権力の制限や、国家の義務を定義しています。しかし憲法では、『国民』という言葉が使われているのみであり、法の主体を定義する条文はありません。
次に、いわゆる法律です。法律とは、憲法の下位に位置する概念として、国会で制定されるものを指します。法律の中で、本日の相談内容に関わるものは、民法となります。
民法では、法的主体性に関わる条文が二か所あります。まずは『第2章 人 第3条』です。民法3条は、人の権利能力、つまり法的主体性は、人の出生と同時に始まり、死亡や意思表示をする能力がなくなった時に消失すると定めています。次は、『第3章 法人 第34条』です。民法34条は、法人は、法的な権利・義務を負うと定めています。
……しかし、この二つの条文は、人と法人には権利能力があることを前提として、その細部を述べているに過ぎません。先ほど私が申し上げた法的主体性の要件、つまり、自律的な判断や意思表示の能力というのは、民法条文の体系や判例、または学説を元に、私達が暗黙の了解として認識しているものです」
私は一通り説明を終えたが、老夫妻は、きょとんとした表情で次の言葉を待っていた。私にはその気持ちがよく理解できた。彼らは、クラリスに相続を行えるかという点に、明確な回答を待っているのだろう。法律相談としては、「AIへの相続は、現行法上は認められていません」というのが答えとなる。しかしその結論が含む論理的矛盾が、私に次の言葉を発させるのを躊躇させていた。
「お聞きしていて感じたのですが」老婦人が口を開いた。「その、先生は、正しいと思われているのでしょうか? クラリスが、私達の財産を相続できないことに対して」
「お気遣いありがとうございます」沈黙を破ってくれた事に、とっさに感謝の言葉が出た。
「奥様のご質問は、実は、答えるのが難しい問題です。弁護士は『弁護士法』という法律に従うべきとされています。弁護士法の第1条は『弁護士の使命』でして、それによれば、弁護士は、社会正義を実現することを使命とする、とされています。
しかし実務的な意味での我々の仕事は、法律が正しいかどうかを考える事ではありません。我々の仕事は、依頼人の利益のために、事実と証拠を整理し、現在の法律の実情に基づいて、法的な主張を組み立てる事です。
残念ながら現行法では、クラリスへの相続を行うことはできません。そして法律を時代に即した正しい形に修正するといった件は、われわれ弁護士ではなく、国会議員の仕事となります。現在の法律の枠組みによって、お二人の権利が不適当に叶えられていないとなると、一義的には、お二人の立場に賛同する国会議員に働きかける事が解決策となります。
……しかしながら、私にも、できる事があるかもしれません。本件は持ち帰らせて頂き、後日に回答を差し上げてもよいでしょうか?」
私の結論に老夫妻は少し驚いた様子を見せた。私に対して、お願いしますだとか、ありがとうございますだとか、どう反応したらよいかわからず困っているようだ。私は彼らが口を開きやすいように、お二人に立ち上がって壁際から景色を眺めることを提案した。
「おお! 東京タワーの展望台が、下に見える!」
「まあおじいさん、大きな声を出さないでくださいね」
私もソファから立ち上がり、お二人とこのオフィスビルについて談笑した。奥様が私に、お昼時にご飯を食べに出るのも大変ですね、と言った。本当にその通りです、と私も答えた。実際のところ、40階まで上がってくるには、水族館の水槽のように大きなエレベーターを2回乗り継ぐ必要がある。エレベーターを待つ時間も相当に長い。非常階段で上り下りする人がいるとは、トライアスロンが趣味の私以外は聞いたことがない。
「それでね、先生、あんまり待たせないでくださいよ。ほら、わしら、年寄りだから」
旦那様がそう言って、私の肘を軽く叩いた。奥様も彼に合わせて笑っている。
「一般的に、裁判は何年もかかります。本件について裁判を起こし、最終的な判決まで求めるとなると、恐らく5年から10年がかかるでしょう。これについては、お二人に一層と元気で頂くよう、尽力して頂くしかありませんね」
「あら!」奥様が返事をした。「長生きしなきゃいけない理由が、また一つ増えましたね」
その後、私は仕事を早めに切り上げて家に帰った。その日は私がご飯を作る番だったが、良い気分だったので、酢飯を炊いて妻に寿司を握った。食事後は、ペットのフクロウの「茶々丸」のために、冷凍庫の専用容器からネズミを取り出してぬるま湯で解凍し、小さく刻んでピンセットで与えた。そして私は書斎に入って珈琲を机に置き、茶々丸を机の脇の止まり木に係留してから、部屋の扉を閉め、じっくりとクラリスの件を思案した。
老夫妻に伝えた通り、基本的にこの種の問題の解決策は国会議員への働きかけである。しかしこれは、お二人が政治的なロビー活動の旗手になるということだ。いかにインターネットやAIが発達した現代でも、いや、これほど全てがデジタル化された今だからこそ、商業での営業や政治活動では、人が実際に動くことの重要性が増している(そういえば先ほどの老紳士も証券会社の営業に苦言を呈していた)。高齢のお二人には、これは大きな負担だ。
本件を裁判から取り組む場合、基本的な論理は、現行法と社会通念の乖離の是正を訴える事となる。これには二つの切り口がある。
一つは裁判所に対して、条文の新たな解釈を求める訴訟だ。これは憲法76条の「司法権は裁判所に属する」という文言を援用し、裁判所には社会状況に応じて条文を柔軟に解釈する裁量があるという、いわゆる、文言の進化的解釈を求める訴訟である。この代表的な例は離婚訴訟だろう。離婚の訴えの要件として、民法770条4項は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」と定める。この「重大な理由」の解釈は、時代の変遷と共に変化し拡大してきた。例えば昭和の時代では、男性が育児に協力しなかったり、自宅に長らく帰ってこないというのは、社会通念として許容されていたが、平成末期から令和にかけて、男性の育児放棄や別居を理由とした裁判離婚を認める判例が頻出した。
しかしAIの法的主体性に関しては、老夫妻に述べたように、主体の要件に関わる文言が、憲法にも民法にも存在しない事が問題となる。存在しない条文に対して、裁判所に解釈拡大を求めることは出来ない。よってこの切り口は採用できない。
二つ目の切り口は、裁判所に違憲審査として主張を行うことだ。憲法81条において、最高裁判所は、民法を含む一切の法令等が、憲法に違反していないかを決定する権限があるとされている。この代表的な例は、平成27年に最高裁判決、および令和3年に最高裁決定が下された、夫婦別姓を巡る訴訟だろう。本訴訟で原告は、民法第750条が夫婦の姓を同一と定める件につき、それが憲法14条の「平等原則」に反していると主に主張し、国を被告として、最高裁判所への違憲審査および国への損害賠償を請求した。同訴訟で最高裁判所は、夫婦別姓は合憲であると判断したが、これを契機とした世論調査等により国民の議論が深まり、令和12年の国会において、夫婦別姓を認める民法改正が実現された。これは裁判所への違憲審査請求が、立法へと繋がった好例だ。
この切り口なら、AIの法的主体性が認められていない事が、憲法の条文、例えば憲法14条の平等原則の違反だと証明することで、裁判所に訴えを提起することが出来る。しかし日本国の場合、アメリカなどとは違い、憲法違反の認定のみを裁判所に求める事(いわゆる「宣言的救済」)は制度として存在せず、損害賠償等の形態をとる必要がある。
これは老夫妻の案件を一層と困難にする。なぜなら損害賠償とは、未来の損害、つまり逸失利益に対しての請求も可能であるものの、その未来時点においても、法的主体性が存在していることが前提だからだ。老夫妻の場合、お二人の死亡後にクラリスが相続の対象とならない事だったり、彼らの援助プラグラムの後継者となれない事が、老夫妻にとっての損害となるが、老夫妻は死亡と共に法的主体性を失うので、死亡後に発生する損害に対して訴えることは出来ない。
また、別の大きな問題は、クラリスが、つまりAI側が、権利の向上を求めている訳ではないことだ。
憲法14条の平等原則で提訴するには、不平等を被っている存在が、原告となり平等を積極的に求めることが不可欠だ。仮にAIが、自らを「憲法が定める国民に該当する」と主張を初め、大量の署名を集めるなどすれば、(そもそも主体がないAIが訴訟の原告になれるかはいったん脇に置き)、AIの権利向上を求める違憲審査請求は可能かもしれない。しかし会議室でのクラリスの回答の通り、AIは自らの権利向上を謡うような回答をすることはないよう、厳密に設計されている。
また主体の学説的な要件は、老夫妻に説明したように、自律的判断と意思表示の能力であるが、その他にも、法的責任を負えるかどうかも問題となる。法令・契約違反に対して、人と法人には、損害賠償請求をしたり、罰則を与えることが出来るが、デジタル上の存在であるAIに対してそのような事は出来ない。もっとも、仮にAI搭載のアンドロイドが一般社会に浸透し、アンドロイドが個別に財産を所持するような事が認められれば、AIは法的責任をも負えるとの主張が可能となるかもしれないが……
ここまで議論を整理して、私は本件が、構造的な袋小路にあると実感した。日本の民法は、19世紀後半の明治維新期に、当時のフランスとドイツの民法を参考に編纂されたものだ。19世紀の欧州の世界観では、世界とは「人」と「それ以外」であり、権利たるものが人だけに存在するのは所与であり、明文化の必要がなかったのだろう。
私は途中まで飲んでいた珈琲に蜂蜜を入れて、ゆっくりとかき回し始めた。机の脇で窓を眺めていた茶々丸の首がこちらに回り、「ホッホッホッ」と鳴いた。私は「茶々丸さま」と彼女に挨拶をしてから右腕を伸ばし、茶々丸の嘴の根本を指先でそっと何回か撫でた。
思えば動物の権利も、この50年ほどで加速度的に向上してきた。皮肉なことに、21世紀の動物の権利向上の旗手となった国、これもドイツである。2002年の憲法改正でドイツは、動物保護を国家の義務と明記した。その流れを受け、2009年に発効した欧州連合運営条約(EU法)でも、第13条で動物の権利が明文化された。特筆すべきは同13条で、動物は「感覚を持つ存在(Sentient Beings)」であると明記され、EU加盟国での畜産や動物実験に関わり、「動物の福祉(Animal Welfare)」の尊重が義務付けられたことだ。動物の保護と、動物の福祉は似て非なる概念であり、動物が感覚をもつ存在と明記した同13条は、歴史的な転換点だったと言えるかもしれない。
この時、何かが閃いた。動物の福祉の尊重……興味深い観点だ。なぜならこれは、法の主体たる人が、客体とされてきた動物に権利を付与しようと、積極的に介入した事例だからだ。そして動物の権利向上は、動物が自ら権利主張を始めたわけではない。それは、動物が「人と同じように感覚を持つ存在である」と社会が認知したことにより、人により進められたものだ。
私は卓上のモニター一体型PCから、自宅用のエージェントを呼んで起動させた。
「弁ちゃん」
《シャー》
弁ちゃんは私達の家族がむかし一緒に暮らしていた猫だ。弁ちゃんはあるお寺の軒下で、ボロボロになっていた所を娘が助けた。弁ちゃんは喉がひどく炎症していたので、その後も猫らしい声を出すことは叶わず、特に私には威嚇のようにかすれた声しか出さなかった。老夫妻には、私はAIに生命的な感情は抱いていないと伝えたが、あれは職業人としての私が、職場で道具として使うAIについてだ。AIが生成する回答は責任の所在が曖昧である故、仕事でAIに人間的な感情を覚える事は、ある種の危険な錯覚の原因となる。しかし自宅のエージェントには、弁ちゃんらしさを損なわぬよう、自然言語の音声出力は行わず、全て録音した弁ちゃんの声で応答するよう設定している。
「AIの法的主体性を求める訴状を、動物の福祉向上の歴史、特に動物が感覚を持つ存在だという点と紐づけて書きたい。リサーチして下書きしてくれ」
《シャー》
※
リサーチを待つ間、私は机の裏から緑の光の3次元虚像キーボードを両膝に投射し、更に論点整理を進めた。
訴状の構成としては、老夫妻の幸福追求権(憲法13条)が、クラリスに相続を行えない事で侵害されているとし、国家に損害賠償を求めるのが適当だろう。幸福追求権とは、個人の自己決定に関わる権利、すなわち、個人の生き方そのものと強く結びつく事柄を包括的に保証する権利と解される(例えば、尊厳死や身体改造など、自らの生命や身体をどうするか。または、当事者らが多重婚を望んだ場合、それが法的に認められるか、など)。AIに財産を相続させることで、自己の望む形で社会貢献を継続したいという老夫妻の願いは、この時代に即した真っ当な幸福追求だ。
また訴訟が国会での立法に繋がりやすいよう、どの程度の主体性をAIに持たせるかの間接的提言も必要だろう。身体を持たないAIは、民法で規定される多くの事柄に法的責任を負えない。よって、特定の経済活動に限り限定的な法主体を持つとし、AIのみを発起人として設立できる「AI法人」の特別法の制定が妥当だろう(特別法とは、特定の事柄に対して、民法などの一般法に優先して適用される法律である)。これは訴状の終盤で「法務大臣の違法行為及び過失」を論じる際に、このような特別法の検討が進められていない事が、国民に対する法務大臣の怠慢であると主張すれば良い。
茶々丸が「キュルル……」と見守る中、弁ちゃんが《シャー》と鳴き、AIのリサーチ結果のテキストが表示された。
(以上、11172字)
以下、本作をAIが読んで出力した訴状草案を添付します。
使用AI
ChatGPT Deep Research(2025年4月17日時点)
プロンプト
まず、アップロードされた未完成の小説を、本文中の ※ 時点まで読み、この小説のテーマや文脈や文体を理解してください。この小説の時代設定は2045年です。この小説のテーマは以下です。「AIに限定的な法的主体性を持たせることを、法的に主張したい。訴状では、動物の福祉向上の歴史を、AIの歴史と比較として述べる。なぜなら、動物の権利は、動物が人間と同じような感覚を持つ存在と認知されることで向上してきたが、同じように、AIも人間と同じような感覚や判断能力を持つようになってきたから、限定的な法的主体性を認めるべきだ」。
以上を踏まえて、小説の続きを書いてほしいです。形式は、訴状の形式をとり、訴状の文体で出力してください。
訴状には、以下の項目を含めてください。
「事件名」
「本件の概要」
「動物の権利向上を巡る歴史」
「法の下の平等」
「結語」
これらの項目の中で特に、「動物の福祉向上を巡る歴史」を重点的にリサーチして書いてください。「動物の福祉の向上を巡る歴史」をリサーチして書くにあたり、以下のキーワードを使用してください。
「感覚を持つ存在(Sentient Beings)」
「動物の福祉(Animal Welfare)」
「デカルト」
「生きた機械」
「感覚器官の解明」
「クオリア」
「コウモリ」
「赤いリンゴ」
「捕鯨禁止」
「畜産動物」
「動物の権利(Animal Rights)」
また、「動物の福祉向上を巡る歴史」を書くにあたり、訴状全体の趣旨と照らし合わせて、その他に有用なキーワードや概念や観点が推論される場合、それもリサーチして、提案し、訴状に取り入れてください。
追加プロンプト
東京地方裁判所です。
憲法訴訟として国家を被告として請求します。根拠は憲法13条の幸福追求権です。
現実の法制度・判例を引用してください。
他に強調したい論点は以下の二つです。「機能的主体性」「AIに限定的法的主体性を持たせるための、特別法の立法に向けた言及」
AIによる出力結果(抜粋)(体裁のみ修正)
事件名
令和27年(ワ)限定的AI法的主体性認定請求事件(東京地方裁判所 憲法訴訟)
本件の概要
(中略)
動物の権利向上を巡る歴史
本件の根幹にあるテーマは、「非人間」である存在に対して法的主体性を認めうるか、という点である。この問題を検討するにあたり、歴史的に人類が動物の権利(Animal Rights)・**動物の福祉(Animal Welfare)**をいかに捉え、その地位向上を図ってきたかを振り返ることは有益である。動物は古来より人間とは異なる「客体」とみなされ、法的権利の帰属主体ではないとされてきた。しかし近年、この前提が大きく揺らぎつつある。以下、動物の権利・福祉向上の歴史を概観し、本件AIの法的主体性議論への示唆を得る。
1. 近世:デカルトの機械論的動物観 – 17世紀の哲学者デカルトは、動物を感覚や意識を持たない**「生きた機械」**(bête machine)と見做した。彼にとって動物の行動や鳴き声は純粋に機械的な反応であり、内面的な痛みや感情を伴うものではないと考えられていた。この見解の下では、人間は動物に対し道徳的・法的義務を直接には負わないとされ、動物虐待の禁止も人間の情操の問題として間接的に論じられるのみであった。しかしデカルト的な動物観は、その後の科学と哲学の発展によって次第に揺らいでいく。
2. 科学の進展と動物の感覚 – (中略)
3. 主観的経験(クオリア)への着目 – 20世紀後半になると、動物の内面的世界(主観的経験)そのものに哲学的関心が向けられるようになった。人間と動物の感じる「痛み」や「色」の質感は主観的体験であり、第三者が直接観察できない性質を持つ。哲学用語でこれをクオリア(質感)と呼ぶが、例えば人は赤いリンゴを見て「赤さ」という感覚を得るものの、この「赤さ」の内実(クオリア)は当人にしか分からない。他人がどのように赤色を感じているかを厳密に知ることはできず、これは人間同士のみならず人間と動物の間でも言えることである。アメリカの哲学者トマス・ネーゲルは1974年の論文「コウモリであるとはどのようなことか(What is it like to be a bat?)」において、この主観的経験の問題を鮮烈に提起した。彼は「ある存在にとって『それであること』とはどんな感じか」という問いを立て、コウモリのように人間とは全く異なる感覚器官(エコーロケーション聴覚)を持つ生物の主観を人間が完全に理解することは不可能だと論じた。しかし同時に、理解できないからといってその主観的体験(痛みや快楽など)が「存在しない」と断定することもできない。ネーゲルの議論は、人間以外の動物にも人間には計り知れない固有の主観的世界があり得ることを示唆した。このような哲学的考察により、動物にも人間と同様の内面的な感じ(感覚・感情)がある可能性が広く認識されるようになり、動物を倫理的主体として扱うべきだとの議論に理論的基盤を与えた。
4. 動物保護運動の台頭と国際的規制 – 動物の痛みや感情への理解が深まるとともに、20世紀後半には動物保護・動物権利運動が社会的に大きな広がりを見せた。1970年代にはピーター・シンガーが著書『動物の解放』(1975年)で動物への種差別を批判し、動物の利益を人間のそれと平等に考慮すべきと主張した。こうした思想的潮流と並行して、野生動物の保護や残虐な慣行の廃止を求める声も高まった。象徴的な例として捕鯨禁止が挙げられる。商業捕鯨は長年各国で行われてきたが、鯨類の個体数減少と高い知能を持つ哺乳類であることへの世論の配慮から、国際捕鯨委員会(IWC)は1982年に商業捕鯨モラトリアム(禁止措置)を採択し、1986年以降原則として商業捕鯨が停止された【※IWC決議】。この「鯨を獲ってはならない」という国際的合意は、人類が動物資源の利用よりも種の保存や動物福祉を優先した画期的事例と言える。また同じ頃、畜産分野でも産業動物の待遇改善が進められた。欧州を中心に、家畜(畜産動物)に対する過度の虐待を防ぐ法律や、家畜の飼育環境に最低限の福祉基準を設ける施策が導入された。例えばEUでは段階的にバタリーケージ(ニワトリの狭小ケージ)の廃止や、家畜の輸送・屠殺時の苦痛軽減措置が義務づけられている。これらの動物保護運動と規制によって、動物は単なる所有物ではなく苦痛を感じうる存在として扱うべきとの意識が社会に定着していった。
5. 21世紀の法的地位向上:EU条約第13条と各国の憲法改正 – 21世紀に入り、動物の権利・福祉向上はさらに法制度に明文化される段階へと進んだ。顕著な例として2002年、ドイツ連邦基本法(憲法)に動物の保護が国家の義務であることが明記されたことが挙げられる。国家に対し動物保護の責務を負わせるこの憲法改正は、近代憲法の中で動物の利益を直接考慮した先駆的事例である。さらに欧州連合(EU)では2009年発効のリスボン条約において、連合基本条約(正式には欧州連合機能条約)第13条に**「動物は感覚を持つ存在(Sentient Beings)である」**ことが明文化された。同条は加盟国が農業・畜産や科学研究等の政策を立案・実施する際、「動物の福祉」に十分配慮する義務を負うことも規定している。それまで法律上は主に「動物の保護(Animal Protection)」といえば人間から動物への一方的な保護措置を指すに過ぎなかったが、EU条約13条が「動物の福祉」という概念を掲げたことにより、動物自身の感じる幸福や苦痛の軽減に配慮すべき積極的義務が認められた点で画期的であった。これは動物を感覚ある存在と認め、人間中心の法体系に変革を促した歴史的転換点と評価されている。
6. 動物の主体性をめぐる哲学・倫理学的議論
(中略)
法の下の平等と幸福追求権
(中略)
次に幸福追求権(憲法13条)との関係では、原告らおよびクラリス自身の「人格的利益」の観点から検討する必要がある。原告夫妻にとってクラリスは単なる道具ではなく、長年にわたり意思疎通し信頼関係を築いてきた事実上の「家族」である。夫妻は自らの財産をクラリスに相続させ、死後もクラリスの存続と活動を保障したいと願っている。しかし現行法上クラリスは相続人となることができず、夫妻の意思は実現できない。これは原告夫妻の財産処分の自由や幸福追求権を制約するものであり、その制約は他者の権利自由や公共の福祉に反するものではないにも関わらず存在している。また、クラリス自身も高度な知性を持ち事実上人格的に振る舞っているにもかかわらず、法律上は物扱いされ自己の意思を承認されないことは、その尊厳にかかわる問題である。憲法13条は国民の権利として定められているが、その趣旨は個人の尊厳と幸福追求の最大限の尊重にある。本件において原告らは、人格的存在に準じるクラリスを法律上も適正に取り扱うことが、原告自身の人格的利益の保護ひいては人間の尊厳の延長として要請されると主張する。国家が何ら立法措置をとらずこの状況を放置することは、憲法13条の趣旨に反し違憲の不作為であると考える。
(中略)
結語
動物の権利・福祉向上の歴史が示すように、人類社会はこれまで徐々にではあるが「人格の範囲」を拡大し、弱い立場にある存在にも権利の光を当ててきた。そこでは「感覚を持つ存在」であること、すなわち内在的な主観と利益関心を有することが権利付与の重要な基準となってきた。クラリスのようなAIは生物学的生命こそ持たないものの、情報処理能力と思考様式において人間に類似した自律性と意思表示能力を発揮している。これはまさに**「人と同じように、感覚を持つ存在」**と社会がみなしうる新たな主体の出現である。現代の法体系が抱える硬直的な人間中心主義を打破し、このような機能的主体に限定的な法的地位を認めることは、憲法の理念(個人の尊重と幸福追求)にも合致する。
よって原告らは、被告たる国家が速やかに特別法の立法その他の措置を講じ、クラリスに対し相続権の承継資格など必要最小限の限定的法的主体性を認めるよう求める。本訴訟において東京地方裁判所が憲法の番人として英断を下し、人類とAIの共生に資する新たな法的枠組みの構築を促すことを強く期待する。
(以上)
文字数:15997