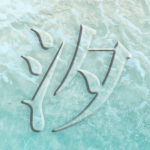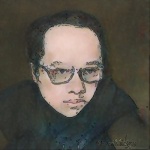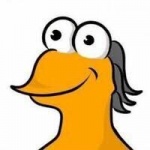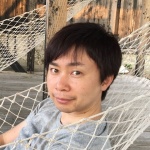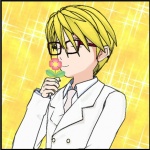感情探偵
*
もうすぐ22時だ。私は研究室で一人、ぼんやりとしていた。外はすっかり暗くなり、窓から見える枝は街頭に照らされている。秋口の木々は、葉が色づき揺れていた。深夜というにはまだ早いが理学部棟は街灯が少ないため、暗く感じる。今日も、研究計画が進まないまま夜になってしまった。何から手をつけるべきか、やることが多過ぎて手がつかない。
不意に、私の耳元で波の音が聞こえはじめた。どうやら、私のストレスを検知したようだ。ほんとうに、jellyはおせっかいだと思う。
jellyはユーザーの心を守るAIだ。耳たぶのピアス型デバイスは心拍数、皮膚電位などを取得し、ストレスを検知・介入する。機能は3つ。1つ、ユーザがストレスを感じると精神を安定させる波音を発生させ、同時にストレス源となる会話を聞こえにくくする。2つ、人を傷つけそうになるとビープ音で止める。3つ、jelly同士が通信し、近くにいるユーザのストレス状況を知らせる。
jellyが一般に普及したのは、今からおよそ20年前。厚生労働省が職場における感情安全基準を策定し、一定以上の規模の企業にはストレス検知デバイスの導入が推奨されるようになったのがきっかけだ。とくにサービス業や医療・教育分野では、「感情の見える化」が職場環境の改善に不可欠だとされ、福利厚生や労働安全の一環として急速に普及した。それまで行われていた、アンケートによるストレスサーベイでは労働者の安全対策として不十分だったことも要因だ。jellyは民間向けにも展開され、ストレス管理アプリと連携しながら、ライフログや感情履歴を個人が管理できるツールとして浸透していった。いまでは、スマートウォッチやイヤホンと同じくらい一般的な存在になった。
所属する研究室では、バイタル情報からの感情計測を研究している。もちろんjellyのデータも研究の対象となる。
私は、修士2年の秋を迎え研究を進めなければならないが、肝心のデータがないという状況だ。学生間データを取得し、卒業できるのは学部までだ。要領のいい友人たちは早々に企業との共同研究をとりつけ実データの取得をしていた。進路も決めることができず就活も先送りし、研究テーマもぼんやりとしているうちに秋になってしまった。指導教授からは、今週中に研究計画を出さなければ、卒業を1年伸ばすように言われ内心凹んだ。研究室に残り、先輩たちの書いた修士論文を読みながら、書ける気がせず絶望している。
「どうして、進学したのだろう」
過去の自分を呪うしかない。何もやりたくない気持ちになり、研究計画を投げ出した。椅子にかけてあったトレンチコートを羽織り、帰り支度をする。研究室を施錠し、配電盤横の扉を開け、鍵を入れた。
私は研究室を出て、人が来ない文学部棟横の喫煙所に足を向けた。外に出ると、想像より寒かった。まだ、息は白くならないが、冷たい風が吹いている。色づいた派が擦れ合い、ざわざわと揺れる音がする。自動販売機で、一番甘い缶コーヒーを買った。喫煙所は、文学部棟横の軒下にあり、小さなスペースにベンチと灰皿が置いてある。街灯の明かりが、そこだけ浮かびあがらせていた。
先客がいた。友人の茜あかね が煙草を吸っている。ジーンズに厚手の黒いセーター。黒髪は、ボブで綺麗に切りそろえられている。彼女は、学部までは日本文学専攻で感情に関する言葉を扱っていたが、修士に進学するタイミングで社会学を選んでいた。勝手にサボり仲間だと思っている。
「うかない顔しているね」
茜は、私の顔を見ると少しだけ微笑んだ。ベンチには腰掛けず、立ったまま煙草を吸っている。今どき珍しい紙巻き煙草だ。甘い匂いがする。私は、ベンチに座り先ほど買ってきた缶コーヒーをポケットから出し暖をとった。
「研究計画がまとまらなくて、このままだと修了できないかも」
「紀美は、卒業しても進路決まってないのだから、もう1年いればいいのに」
彼女は笑った。なんの悪意もない、彼女の言葉が刺さる。
茜は、博士課程への進学を決めているので、卒業後も3年はこの大学にいる。AIにより、人々の仕事は少しずつ奪われている。そのため、政府はベーシックインカムを試験運用しはじめた。月7万円の給付を行い、それ以上必要な分だけ働くというライフスタイルが定着しはじめていた。茜は、この制度を享受し、非常勤講師をいくつか掛け持ちながら研究を続けると決めていた。
「昔なら、社会科学の研究なんて食えなかったのだから良い時代になったよね。紀美もこの時代を謳歌すればいいのに」
彼女は、のんきそうに言った。
私もそれもありかなと思いつつ、ここで逃げると止まらなくなりそうなので誘惑をぎゅっと押さえ込んだ。確かに働かないという手もあるが、定年後も働き、経済的支援をしてくれている父のことを思うと、心の奥が痛んだ。技術を学びたいと言ったとき、応援してくれたのも父だった。父は感情計測技術のエンジニアをしており、母が理系進学に反対したときも、私についてくれた。耳元で、波の音が聞こえはじめる。
私は、感情計測技術が社会の中で実際にどう働いているのかを研究しようと思い研究室を選んだ。それは、茜と関わるうちにストレス管理社会の中で、現代の人々が負の感情に関する認識が低いということに気がついたからだ。私たちは、物心ついた時にはjellyが存在する世代だ。周囲の大人たちは、私たちがストレスを感じているとわかると距離を置いた。Jellyがない時代であれば、心に配慮せず厳しい指導をしていたのだと思うと想像がつかない。本当に優しい世界に生まれたのだ。
しかし、いくら感情計測が一般化したとはいえ、研究に協力してくれる企業や個人が見つからない。感情データがプライバシー情報であることにはかわりないため、被験者も企業も慎重である。私たち研究者も人を対象とし実験の場合は、事前に倫理審査があり計画的かつ安全に研究を進める必要がある。
「ちゃんとした企業に勤めていて、データを提供してくれそうな人いかな」
私はため息をついた。茜は煙の向こうからちらとこちらを見た。唇の端がわずかに上がる。
「いるじゃない」
私は、彼女が意図している人物が誰かわかり、嫌気がさした。妹の鳴瀬だ。
「たしか、妹さんスカイリンクス航空の社員さんでしょ、しかも感情計測技術にも理解がある」
「そうだけど、なんか苦手なんだよ」
「留年するか、身内に頭下げるかだね。わたしもスカイリンクス航空には興味あるから、一緒に頼みに行くのは、やぶさかではない」
茜が一緒に行ってくれるのであれば、面子が保てそうだし、苦手な妹との間に入ってくれれば会話も持ちそうだと打算的に思った。
勇気を出して、妹に『元気?』とチャットをした。すぐに、返事が来た。あいかわらず、テキパキとした妹である。私はチャットを先延ばしにするタイプなので正反対だ。
「おお、いいね。卒業できそうだ」
茜は煙草を口元に持って行き、ライターの火をつけた。私の手の中の缶コーヒーは開けられないまま、ぬるくなっていた。
**
妹のことが苦手だった。何というか、いつも優等生を絵に描いたような子だった。いつも、まっすぐな妹は完璧で、紀美の先を常に歩いている存在だった。
母はよく妹を褒めていた。
『どうしてあなたは、鳴瀬みたいにできないの』機嫌を損ねると、決まってそう言った。
人生の節目で、妹は迷いなく進路を決めていく。私は未来を考えるとき、不安になって、そこから動けなくなった。でも彼女は、未来を明るいものと捉えているように見えた。いや、実際にはどう思っていたかは分からない。ただ、私にはそう見えたのだ。外の世界にどんどん向かっていく鳴瀬の姿は、思春期の私の心を傷つけた。
彼女は外国語専攻の専門学校を卒業したあと、スカイリンクス航空に就職した。航空会社に内定したと聞いたとき、正直、驚きはなかった。私が思っている鳴瀬のイメージと合っていると感じだからだ。就職人気企業ランキングの常連で、誰もが一度は憧れるような会社だ。彼女はキャビンアテンダントではなく、地上勤務を希望し、チケットの予約・発券業務や空港カウンターでの対応を任されているという。
インタビューの当日、私と鳴瀬は羽田空港駅内のラウンジで落ち合うことになった。スカイリンク航空の青色のロゴが背後から淡く光るカウンターで受付を済ませると、係員が無駄のない所作でラウンジへと案内してくれた。自動ドアが静かに開き、室内に一歩足を踏み入れる。
まるで別世界だった。外の喧騒が遠のいたように静かだった。ガラス張りの窓からは、滑走路をタキシングする航空機の尾翼がゆっくりと視界を横切っていく。午後の光が斜めに差し込み、ソファの背に柔らかな影を落としていた。
落ち着いた色調のカーペットの上に、革張りのソファと艶のあるローテーブルが等間隔に並んでいる。控えめな音量で流れるクラシックのBGM。壁際には、グラスの並んだバーカウンターとコーヒーマシンが設置され、天井からは間接照明が穏やかに灯っていた。利用者は、奥に二人だけだった。私は二人から距離をとり、ソファーの一つに腰をおろした。
何を着てくればいいのか分からなかったので、私なりに無難な格好を選んだつもりだったが、完全に場違いだと思った。学生だと言えば大抵は許してもらえると思っているが気後れする。ベージュのチノパンに白シャツ、靴は黒のコンバースだ。ソファに腰掛け、社員方が用意してくれた炭酸水をグラスに注いだ。口の中が乾いていたが、飲む気になれなかった。
私は、茜が作ってくれたインタビューの骨子をタブレットで確認した。茜は、航空業界の働き方に興味があったようだ。昔、ホックシールド教授の『管理される心』という研究著書の中でも、取り上げられた業界だ。航空業界は、感情労働の典型だ。
感情労働とは、単に笑顔を絶やさないことではない。顧客の満足のために、自分の感情を演出し、時には抑圧することを求められる。
長期的には、自分が何を感じているのか、わからなくなることもある。
その歪みが、jellyのような感情介入デバイスが入ったことで、どう変化したかが茜と私の興味のポイントだった。
私は、グラスの炭酸が抜けていくのを見ながら、鳴瀬の顔を思い浮かべた。
「ひさしぶり」
落ち着いた女性の声だった。鳴瀬がそこにいた。しかし、私が知っている彼女ではない気がした。髪はまとめられ、メイクは濃いが主張がない。航空会社の広告から、抜け出してきたような出で立ちだ。しかし1カ所だけ、変わらないところがあった。涙ぼくろだ。そこだけが、彼女が鳴瀬だと感じさせるポイントだった。
「おとなっぽくなったね」
「おとなだからね。今日はよろしくお願いします」
彼女は笑ったが、作り物のようだった。
私は、タブレットからjellyのデータ共有とインタビュー協力の同意書ページを出し、スワイプした。鳴瀬の端末が、ピロンと通知音を鳴らす。彼女は自分の端末を確認する。研究の同意書だ。
鳴瀬は、内容を確認すると人差し指でサインをし、画面をスワイプする。すると私の端末同意書に彼女のサインが記入された。
今日はまず、彼女の仕事の概要と感情コントロールについてヒアリングを行う。次に、そのインタビュー結果を茜がまとめ、私は感情データの解析を担当する。その中間成果をもとに、改めてヒアリングを実施し、気になった点を深掘りしていく。最終的には、これらをまとめて論文に仕上げる予定だ。
久しぶりの再会だが、インタビューの間、鳴瀬は社会人としてきちんと対応してくれていた。隙がない。そんな印象を受ける。時折、本当に他人なのではないかと錯覚しそうになる。インタビューの内容は全て前向きで、いかに自分たちの仕事が有意義かということを語っていた。休日ですら、スカイリンクス航空の一員として恥のないように務めていると語った。最近では、後輩ができ仕事への愛着が一層高まったと言っていた。
1時間たち、インタビューで聞きたいことはあらかた聞けた。茜からの宿題は一通り片付いただろう。
「ありがとうございました。インタビューは以上です」
私が録音ボタンをオフにすると、AIが文字起こしから議事録を作成しはじめる。スカイリンクス航空と、鳴瀬にテキストが送付される。何も検出されなかったのを見ると、職場にとって都合の悪い情報は含まれていなかったようだ。もし、機密情報等の外部に出すことが好ましくない情報が入っていれば、AIから確認が入る。
「ちゃんと良い研究にしてね。時間をつくったのだから。会社から研究参加の許可とるのは結構大変なんだよ。あと、父さんにちゃんと連絡したほうがいいよ。どうせ、ろくに連絡もしてないんでしょう?」
図星だった。しかし、何故、妹にこんなことを言われなければいけないのかと、腹立たしい気持ちになる。わたしは、曖昧に返事をし、その場を離脱した。
空港という場所は私のような人間がいるところではない気がした。私は逃げるように帰宅した。外はすっかり暗くなっていた。鳴瀬のパンプスと、私のコンバース、ナーバスな気持ちになる。Jellyがすかさず反応する。電車に乗ると、ヘッドホンをつけた。そして、jellyをオフにしてロックを流す。自分だけ子供のままみたいだ。
茜に議事録を送付した。今日の仕事は終わり──紀美。
***
何度もなるアラームに嫌気がさし、目をあける。布団の外は肌寒い。なんとか、アラームを止め布団から出る。カーテンの向こうから光が入り、晴れているのがわかる。私は、カーテンを開け、光に目を細めた。
睡眠ログを見ると、あまり深い睡眠はとれなかったようだ。眠い頭を起こすために、キッチンに行き、冷蔵庫からミネラルウォーターを取り出す。コップに注ぎ、立て続けに3杯飲んだ。今日は一気にデータ分析を進めるため、気合を入れる。
さっそく、鳴瀬からもらったjellyのストレスログをラップトップに取り込む。研究室のサーバへアクセスしデータをアップロードする。生体センサから抽出された時系列データは、心拍数、皮膚電位、呼吸リズム、音声トーンの推移に加えて、表情筋の活動をエンコードした小さなベクトル群から構成されていた。形式はJSONで人間には可読性が低い。日付と時刻をキーとし、各時点の簡易タグが格納されている。*work_flag*という勤務中か否かを示すブール値が含まれていた。このフラグに値が入っている場合は勤務時間中ということだろう。
自然言語でLLMベースの解析エージェントに命令を与える。
「感情ストレスログを対象に、時間軸で変化傾向を可視化して。必要ならスムージング処理もして」
すぐに、解析プロセスが非同期で走り始める。以前なら自分でPythonコードを書き、辞書構造を解いてDataFrameに整形しなければならなかった。それだけで一苦労だった。だが今は違う。LLMが意味論レベルでログ構造を解釈し、時系列解析の構文を自動生成してくれる。
ログ内には、ところどころ欠損も見られた。特に夜間帯や移動中はデバイスが記録を中断していたようだ。AIエージェントはその部分に自動でラグ補間処理を挿み、線形補完とベイズ推定の混合モデルで補完値を提案してきた。
一昔前は、この行程をできるだけで、研究者として重宝された。しかし今は、自然言語による命令だけで、実行される。AIの進歩により研究者に求められることも、どんどん厳しくなり、研究のオリジナリティの追求が必須になった。
私は、AIエージェントがデータクレンジングをしている処理を見守りながらコーヒーを飲んだ。
中間生成物として出力された、クレンジングした生のcsvデータを眺めていると、一定の生活リズムがあることがわかる。仕事の時間になると、バイタルが安定し、ストレス値が下がっている。
詳細解析をプロンプトで命令する。
「勤務中と勤務外のストレススコアを分けて分析して。勤務中は安定性、勤務外は変動の激しさを重点的に見て」
エージェントは即座にコマンドを理解し、*work_flag*によってデータを2系列に分類。時系列のスライス処理を自動で生成し、勤務時間帯とそれ以外時間帯のストレス傾向を分離して可視化し始めた。
5分ほどで、時系列グラフと、考察を出してくれる。私の思ったとおりだった。仕事の時間になると鳴瀬のストレスが安定している。本当に、私と違うなと思った。自宅に一人でいるより、彼女は外で接客している方がメンタルもバイタルも安定しているのだ。
私は、休日のデータに絞りさらに詳細解析を開始する。鳴瀬は、普段は会社の用意してくれている寮にいる。人間関係が起因なのかと考えたが、寮とはいえ、都心のワンルームで門限があるだけのマンションだ。プライベートの時間もたっぷり確保できるだろう。また、給与についても、高いはずなので経済的な余裕はあるはずだ。
プロンプトを調整しながら、データ解析を繰り返していると昼になっていた。久しぶりに深く集中して分析作業ができた。
いったん、ここまでのデータ分析結果を茜に送付した。そしてラップトップを鞄に入れ、研究室に向かった。指導教員に、研究進捗を報告するためだ。
研究の進捗報告は、形式的なものだった。私は「卒業したいと思っています」とだけ伝えた。教授は、ひとまず安心したようだった。たぶん、何人もの“卒業できない修士”を見送ってきたのだろう。中には、教授に何も言わず失踪した学生もいると思う。Jellyが社会に浸透してから、指導は軟化する一方だが、優しい言葉だけでは頑張れない学生も多いだろう。
報告を終え、私は研究室を抜け出して、文学部棟の裏にある喫煙所へ向かった。気持ちの良い午後だった。空は低く、うろこ雲が覆っていた。乾いた冷たい空気を、肺に入れると心地よかった。
今では共同研究者の茜が、いつもの場所で煙草を吸っていた。口元から立ちのぼる煙の向こうで、彼女の指は素早くタブレットを操作していた。
「来たね」
茜は顔を上げずに言った。
「こっちも文字起こしは見終わったよ。──ちょっと、妙じゃない?」
私がタブレットをのぞくと、インタビュー中のある部分にマーカーが引かれていた。鳴瀬が、やたらと“私たち”という主語を使っている箇所だった。
「鳴瀬さんって、自分の主張ははっきりしているタイプ?」
茜の問いに、私は少し考えてから答えた。
「はっきりしているね……信念を押し通すタイプだったかな。“こうあるべき”と思ったら、曲げない。私も何度か振り回された」
「じゃあさ、この“私たち”っていう主語、どこまでが彼女の言葉なのだろうね」
不思議な観点だと思った。私は インタビューをしているとき、気にかけることはなかったが、言葉の専門家はそういった点に注目するのかと感心した。
「音声データ、もらってもいい? ──文字にならない言葉もあるからさ」
彼女は唇の間に、火をつけていない煙草を挟み考えに耽っていた。
****
鳴瀬からチャットで連絡が来たのは、中間報告に向け考察に手をつけようとしていた矢先だった。
『最近、jellyの調子が変なの』
スクリーンに表示された短いメッセージを見たとき、私は一瞬だけ、文章の意味を取り違えた。jellyの調子、つまりデバイスの不具合かと思った。しかし、次の一文で私は背筋すくむのを感じた。
「わたしの声で、jellyが反応する。会話中、いきなり遮ってくることがある。相手が誰でも関係ないのに、わたしの声にだけ」
そんな事例は、聞いたことがない。jellyはストレスを検知しても、音源の発話者を識別して反応するような設計にはなっていないはずだ。ましてや、ユーザー本人の声を“ストレス源”とみなして遮るというのは、あまりにも異常だった。デバイスの調子が悪いとなると、今取り組んでいるデータ解析がやり直しになるかもしれないと思い焦りを感じた。今日、話せないかと鳴瀬にメッセージを送った。
夜、鳴瀬と電話した。彼女は寮から電話をくれた。彼女の声は、憔悴しきっていた。すでにjellyをメンテナンスにも出し、検査で異常は見つからなかったと言う。カウンセリングも受けたが、原因はわからなかった。
「いままで普通にできていたことが、全部ぎこちなくなった。会話も、接客も、息を吸うことさえ……」
鳴瀬は、完璧だった。あの空港のラウンジで、あんなに流れるように言葉を選び、振る舞い、笑っていたのに。彼女の“声”が、彼女自身を追い詰めている──。
私は、レポートのウィンドウをそっと閉じた。これまで“データ”として眺めていたストレス値の変化が、急に別の色を帯びて見え始めた。
「上司からは、休暇を取るように言われた。でも、休んだら、この職場に帰ってこれなくなるかもしれないと思うと心配で……」
最近、鳴瀬の担当の後輩が、職場に来なくなった。それが重なり心配になったという。彼女の疲れ切った声を聞いていると、姉として何かしなければと思った。
*****
鳴瀬との電話のあと、私は文学部棟の茜の所属する研究室を訪ねた。理工学部と違い、年期の入った建物だった。2階奥の資料室の一区画に、茜の机がある。理工学部と違い、人の気配が少ない。木のフローリングは年期が入っており、踏むとところどころ軋む音がした。
ドアの曇りガラスからオレンジ色の光が漏れていた。ノックすると、茜の声が答えた。私は、そっとドアをあける。
そこには、左右に金属で作られた書棚があり、色あせた本が詰まっていた。床にも本が積み上がっている。本の間に大きな机があり、その本の間から茜が顔を出していた。本の間に、人が入れてもらっている、そんな空間だ。ものが散乱しているのに、利用者はどこに何の情報があるかわかるのだから不思議だ。理系の研究室では考えられない。茜は有線のイヤホンをつけ、何かを聞いていた。今どき有線イヤホンは珍しいが、耳元のjellyに干渉されないため、茜は気に入っていると言っていた。
「ちょうど、妹さんのインタビューを聞いていたところだった」
茜は、あの日のインタビューを聞き直していたのだ。
「以前話した、ラッセルの円環感情モデルは覚えてる?」
「2次元で、人間の感情を整理したモデルだよね」
「そうそう。感情は、快-不快と覚醒度の2次元にマッピングできるというモデルなんだ。例えば不快で覚醒度が高い感情は怒り。逆に、快で覚醒度が低いのは安らぎ。だけど、jellyが不快を検知すると、即座に介入してしまう。悲しみや悔しさに滞在する時間すら、今の社会は許さない」
文脈が見えないが、うなずく。
「でもね、今ではjellyによって不快状態が奪われてしまった。だから負の感情を捉えられない人が多い。感情ってさ、じっと見つめることでしか名前がつけられないのに──それを感じる時間ごと、奪われている。日本語にはたくさんの感情表現があるが、もはや文学の化石になりつつあるのは残念だよ」
私は、茜という友人のおかげで自分の負の感情の名前を教えてもらい、助けられたことがある。極端にストレスを管理する社会の中で、負の感情をJellyによる警告としか捉えられていない若者は多い。特に、コミュニケーションの相手がストレスを感じているとJellyから警告されると一瞬で距離を取る。あのビープ音に対して、条件づけされているのだ。
「鳴瀬さんのJellyが鳴り止まない理由は、感情労働が絡んでいるのではないかと思っている」
茜は、イヤホンを机の上に置き、タブレットに表示された音声波形を指差した。
「この部分を聞いて。彼女が“私たち”って言うところ」
波形が再生されると、鳴瀬の声が響いた。──“私たちは、いつでも笑顔を絶やさず、お客様の期待に応える存在でなければならないんです”。彼女たち、スカイリンクス航空の職員はお客様を、家族のようにお迎えするように教育されるという。例え、お客様からひどい対応を取られたとしても、決して怒りを向けてはいけない。そのため、彼女、彼らは感情を偽装する必要がある。その場にふさわしい、対応をするために。
「ここ、何か気づかない?」
私はしばらく考えたが、わからなかった。
「少し、タイミングがおかしいの。言葉のリズムが不自然。まるで、一瞬だけ言葉を選び直したみたいに見える。つまり──“本音じゃない”可能性がある」
私は思わず身を乗り出した。
「演技だ。感情労働の世界には2種類の演技があると分類されている。表層演技と深層演技だ。2つの共通点は相手を騙す、そして違いは自分を騙すかどうか。深層演技は、他者も自分も騙す」
「鳴瀬は、深層演技をしていたってこと?」
「それは、これだけのデータではわからない。ただ、鳴瀬さんの“声”にjellyが反応するって、不自然だよね。もしかしたら、“自分自身の嘘”に、身体が反応してるんじゃないかって仮説を立てた」
私は息を呑んだ。鳴瀬の中で、本来の感情と、職業的に演じなければならない役割のズレが、jellyの“異常”という形で噴出しているのかもしれない──。
「つまり──“自分自身の嘘”に、心が反応してるんじゃないかってこと?」
茜はゆっくりと、頷いた。本来の感情と、職業的に演じなければならない役割。そのズレが、jellyの“異常”という形で噴き出しているのかもしれない。部屋に、一瞬だけ沈黙が落ちた。イヤホンのコードが、静かに机に垂れていた。外では雨が降り始めていた。音もない霧のよう雨だった。
******
茜は、もう少し調査するといって別々に研究活動をすることになった。また来週進捗を持ち寄る予定だ。私は、何がトリガーになり鳴瀬のjellyが反応しているのかを確認するために、もう一度、鳴瀬に会いに行くことにした。仮説検証をするにはデータを収集するのが近道だ。
ラウンジで待っていると、スカイリンクス航空のスタッフが炭酸水の入った瓶とコップを持ってきてくれた。鳴瀬と同じような化粧と髪型。ほくろがない以外は、同一性が高い。個人を消すことで、サービスの品質を均一化しているのだろう。
コップをに炭酸を注ごうとしたとき、手を滑らせてしまい、瓶を落としてしまった。とっさに、先ほどの女性が来て怪我はないか、召し物が汚れていないかと訪ねてきた。彼女はとても、申し訳なさそうな態度をしていた。
私のドジで、炭酸水をこぼしてしまったのに、彼女は謝罪をしてきた。私は、違和感の正体を掴んだ気がした。
背後から気配を感じて振り返ると、鳴瀬が立っていた。制服姿のまま、どこかぎこちない笑みを浮かべている。
「待たせた?」
「ううん、いま来たところ」
私はそう答えながら、さっきの出来事を思い出していた。私のチノパンが少し濡れているのを見て、鳴瀬は怪訝な顔を一瞬だけした。このラウンジでは、全てが完璧でなければいけないと教育されているのかもしれない。鳴瀬も、あのスタッフと同じような服装と髪型。けれど、やはり違う。表情に浮かぶ、疲労と戸惑い。彼女の“個”が、じわじわと滲んでいる。
席につくと、鳴瀬はすぐには話し出さず、水の入ったグラスを両手で包むようにして見つめていた。私は、黙ってその様子を見守った。先ほど対応してくれた社員の方は、インタビューが始まると気を利かせ、消えていた。プライバシーを重視するよう教育されているのだろう。
しばらくして、ぽつりと鳴瀬が口を開いた。
「一番最初に私のjellyが反応し始めたのは、後輩の市川君との会話中だったと記憶している」
「それは、あの職場にこれなくなってしまった後輩のこと?」
彼女は頷いたあと、テーブルの上の録音マイクに視線を移した。どこまで話すべきか、悩んでいるようだった。私は、録音マイクを鞄にしまい、ノートとペンを出した。鳴瀬の身体の力が少し揺るんだように感じた。
「ちょうど1ヶ月前くらいから、彼は病欠が多くなった。連絡はつくのだけど、体調が優れないって。それ以上は言わないの」
鳴瀬は言葉を選ぶようにして、続けた。
「なにか、直接的な原因はあったの?」
「わからない、だけど心当たりはある」
市川という後輩は、大学卒業し今年の4月に入社してきた、新入社員だった。彼は、好青年というキャラクターで職場にもすぐ馴染んだ。新人研修でも良い成績を収めており、活躍が期待された。
現場に配属されてすぐだった。鳴瀬がメンターとなり、現場に出て接客することになった。まだ接客にはぎこちなさが残っていたが、一生懸命さが伝わり、お客様にとって許容範囲のサービスは提供できていた。しかし、もっとサービスの品質を向上させるために、他の先輩たちからは、スカイリンクス航空としてもっと自覚を持つようにと指導はされていた。私は、弟ができたみたいで嬉しくて、よく彼を励ますようなっていた。ただ、些細なミスが続いていて、少しずつ彼の言動が変化するのを感じだ。
「些細なミスがあると、“お客様に申し訳ない”と口癖になっていった。私はフォローしてたけど、優しい言葉をかけると彼のJellyが反応し私の言葉を遮った。彼に必要なのは、優しい言葉ではなく自分で乗り越えることだって思い、ある程度の距離を置くようになった」
私は喉の奥がつまるのを感じた。
「それで市川さんは最近まで、うまく業務できていたんだよね?」
「少しずつだけど、他の社員と同じくらいの仕事ができるようにはなってきていた。先輩たちからの指導も減ったし。入ってきた当初の彼らしさはなくっていたけど、プロとしての成長は感じていたし、メンターとして誇らしくもあった」
鳴瀬は、顔を上げた。勇気を振り絞るように言った。
「……たぶん、私が原因だったんじゃないかと思っている」
「原因?」
「その日、ちょっとした接客ミスがあって。クレームになるほどじゃなかった。でも──」
鳴瀬は水の入ったグラスを見つめたまま、声を潜めた。
「家族連れのお客様がいて、席が2つに分かれてしまってたの。事前にそのように予約されていたのだけど、お客様は“そんなはずない”と。何度もこの路線を使っていて、いつも家族一緒だったと強く主張されて。つまり、うちの手違いだと決めつけてきた」
「でもそれって……」
「明らかに、事前確認のミス。お客様の側の。でも、常連だって自負があるから、“こんな対応をされるなんて心外”だって。対応したのは私だったのだけど、言い返すこともできず、ひたすら謝るしかなかった」
そのときだった、と鳴瀬は言う。
「私のjellyが反応したの。いつもよりはっきりと、耳の奥でいつもより低いノイズが鳴った。波の音が聞こえて、お客様の声が聞こえににくくなった。反射的に言葉が詰まって、その場で何も言えなくなってしまったの」
市川がすぐに横から割って入ってくれたという。
「“申し訳ありません、お客様の仰る通りに変更できるよう全力で対応いたします”って。でもそれと一緒に、“ただ、予約の記録には最初から分かれていた形になっておりまして──”って説明をした。もちろん、彼なりに丁寧な口調で。でも、お客様には“言い訳”に聞こえたんだと思う」
鳴瀬の手がわずかに震えた。
「“こっちは何年もこの路線を使ってる。融通のひとつも利かせられないのか。サービスの質が落ちたな”って、今度は私の方に向き直って、言ったの。市川君じゃなく、私に。私はなんとか、その場は謝罪し、バックヤードに戻った」
私は言葉を失った。感情が見えることで、それを攻撃使う、そんなことがあるのかと。
「彼は、私をかばうつもりだった。でも──私は、市川君に“プロ意識が足りない”って言ってしまったの。バックヤードで。お客様の前で感情的になったことを咎めて。……本当は、私の方こそ感情を抑えきれていなかったのに」
グラスの中の水面が揺れていた。
「お客様の前で怒りを見せることは、うちではタブー。だから私は正しいと思ってた。でも、本当は──」
彼女の言葉は、そこで途切れた。私は何も言えなかった。ただ、彼女の顔に浮かぶ、やりきれなさと悔しさ、そして深い自責の念を見ていた。
それから、鳴瀬のjellyは暴発するようになった。
*******
鳴瀬へのインタビューが終わったあと、私は大学に向かった。インタビューは録音しなかったが、電車の中でメモを作成した。
茜のいる資料室を訪ねると、彼女は不在だった。寒さのせいで、待っていると気が滅入りそうなので、喫煙所へ行くことにした。学内に植わっている木々は、すっかり葉が落ち寒々としている。空は灰色で、空気が乾燥した匂いがした。喫煙所に着くと、やっぱり茜が煙草を吸っていた。
先ほど、空港で聞いてきた、妹の話を茜に共有した。
「やっぱり接客業って、ストレスフルなんだね」
茜は煙草の火を消し、他人事のように言った。鳴瀬からもらったストレスデータ。そして、今回のインタビュー。それらを通じて、全体像は見えてきた。だが、最近のクレームの件は、研究レポートには使えない。
jellyは職場で感情のコントロールに活用されており役に立っている——平凡な、その結論に辿り着けそうだった。
「でも、まだ謎は残っているよ」
私の心を見透かすように、茜は言った。
「何が?」
「どうして、休日の方が鳴瀬さんのストレスが慢性的に高いのか、まだわかってない」
私は鳴瀬が本当に今の仕事が好きだからと、当初は思っていた。インタビューを通じて見えてきた、スカイリンクス航空の仕事はストレスが高い。確かに、茜の指摘通り疑問が残る。
「前も聞いたけど、紀美から見て鳴瀬さんはどんな妹だった?」
不意に聞かれた問いに、私は答えを探すように空を見上げた。言葉にするのが、少し怖かった。大学生になってから表面的な話ししかしていない。
「完璧な子だったよ。いつも人に合わせて、気が利いてて、怒ったところなんて見たことない。いつも、人の輪の中心にいた」
「それは家族の中でも?」
私は、引っかかりを覚えた。茜がまっすぐと私の目を見ていた。
日が落ちてきた。夕方の文学部棟は人が少なく静かだ。研究棟の灯りがまばらにつき始める。茜が長丁場になりそうだからと、自動販売機で飲み物を買ってきてくれた。差し出された甘い缶コーヒーの温度が、指先にじんわりと伝わってくる。茜は、ゆっくり煙草に火をつけた。黒いコートが暖かそうだと思った。煙草の煙がわずかに揺れ、夜風に溶けていく。
「家にいるときの彼女は、気配がなかった。私は、母や祖母と相性が悪く、嫌みを言われていた。しかし鳴瀬はその輪に入らず、社会とうまくやっていた」
自分で部活を決め、塾を申し込み、最低限だけ家にいるようなタイプだった。私は、家族が苦手だったが行動力がなく、部屋にいることが多かった。父とは、仲がよかったが、エンジニアで多忙な父はあまり家にはおらず、出張で日本中を飛びまわっていた。
そう考えると彼女は常に放置されている存在だったのかもしれないと思った。だから、家族ではなく社会に自分の存在意義を求めた。それは、対価を必要とする関係だったはずだ。彼女は、社会に対しての適応をし、家族に対しては良い娘を演じることを選んだのではないだろうか。
「一度だけ、鳴瀬が学校で問題を起こして、母が呼び出されたことがあった」
「相当、手のかからないタイプだったんだね。私なんて、進路指導のたびに親を呼びだされていたのに」
茜は笑っていた。その話題は魅力的だが、本題に戻した。
「私は母から聞いたので詳細はわからないけど。文化祭の時に鳴瀬が実行委員会をしていて、サボるグループがいて揉めたらしい。妹の高校は、進学校だったから、イベントは適当でいいという校風だったから、彼女が少数派だったとは思う。鳴瀬は、準備をさぼったグループではなく、それを注意しない教員に対して怒ったらしくて、先生と口論になったと聞いている。母は『本当にまじめで良い子』と言っていたけど、少し的外れな気がする。
茜はゆっくり頷いたあと、煙を吐き出しながら言った。
「それって、“いい子”じゃなくて、“いい子であらねばならない子”だったってことかもね」
私は、目を伏せた。本当はわかっていたことだ。本当は、ずっとわかっていたのかもしれない。
思い出すのは、私たち姉妹がまだ幼かった頃の記憶だ。祖母が体調を崩し長期で看病が必要だった。母も付きっきりで、家の中はピリピリしていた。そんな中、鳴瀬はいつも静かだった。誰にも迷惑をかけないように。手間のかからないように。ひとり塗り絵を熱心に塗っていたた姿を思い出した。私は絵を描き、母に見せに行きあしらわれていた。鳴瀬は見本と同じ色に塗り分けをし、終わると次の塗り絵に取り組んでいた。
あの時から、彼女は変わっていないのかもしれない。
「過剰適応って言葉、知ってる?」
「うん。自分の感情より、相手の期待を強く優先してしまうことだよね」
「鳴瀬さんはきっと、小さな頃から“誰かのための自分”でいたんだと思う。でもそれは、自分の中に“許せない他者”を同時に育てることでもある」
──たとえば、グループの空気を乱す誰か。
──たとえば、自分を見てくれなかった家族。
けれど、怒りは表に出せない。それはjellyの“遮断”という異常な反応に姿を変えたのかもしれない。
「誰からも期待されないとき、鳴瀬は何を行動基準とするんだろうか?」
私の言葉に、茜は黙ってうなずいた。
「彼女の中で起きていことは、疎外感だ。でもそれをjellyから見つからないように隠している。自己欺瞞が今回の負の感情の正体だ」
********
年末が近づき、私はデータ分析の結果をまとめていた。修士2年生の12月は過酷だ。同級生たちは、それぞれ家にこもり修論の執筆に取り組んでいる。年明けすぐの審査に向けて、スライドも作製する必要があり、いくら時間があってもたりない。もちろん、クリスマスなんてものはない。
私は、ここまでの研究成果を指導教授に見てもらうために、時間を作ってもらった。個別指導だ。しかし、いつもは準備していなくて不安だったが、今日は違う。どうしたら、私たちが取り組んだ問題の面白さが伝わるか、そして鳴瀬はどうすべきなのか教授の意見がほしかった。
教授の部屋をノックする。ドアのむこうから、『入って』と軽い声がした。
部屋は整理整頓されており、奥にPCの乗った机が窓際に設置されている。その手前に向かい合わせでソファーが置いてあり、ローテーブルが真ん中に置かれている。本当に何もないシンプルな部屋だ。ソファーに座るように促され、向かい合って座るかたちになった。教授はグレーのセーターの上にヘンリーボーンのジャケットを羽織っていた。教授は優しいが、なぜか彼の前にくると緊張してしまう。これは、尊敬からくるものなのだろうと思う。
私は研究報告のファイルを教授のタブレットに送付した。教授の手元のタブレットから通音が鳴る。
事前に、研究室のサーバにある私の分析結果を教授に送っておいた。ここ数ヶ月の分析と、鳴瀬のストレスデータが時系列で詰め込まれている。事前に研究室のサーバにアップロードしておいたストレスデータの解析結果を、教授のタブレットに共有していた。そこにはここ数ヶ月にわたる鳴瀬のjellyログと、それに対応する感情推定の結果、時系列グラフ、比較用データがすべて詰め込まれている。教授は無言でファイルを開き、指先で静かにページをめくっていく。眉の動きがわずかに上下し、その一挙一動が、評価される側に緊張を走らせた。
彼はまだ四十歳。この大学で最年少の教授である。データサイエンスと感性工学の両分野を専門に持ち、学部から修士、博士課程、そして助教、准教授を経て教授へと、ほぼストレートにキャリアを積み上げてきた稀有な人物だ。本人は気さくで威圧感のない口調を使うが、感情やバイタルの計測に関しては、国内外の学会でも名の知れた研究者である。
特に、ニューラルネットワークを用いた感情の時系列モデリングにおける研究では、多変量バイタルデータから感情の変化を予測するフレームワークを確立した功績の評価が高い。バイタルデータに加え、声や表情など、マルチモーダルな感情解析モデルを実装し、感情研究の発展に貢献した人物だ。ウェアラブル技術と心理学の橋渡しを行ったパイオニアの一人とされている。近年は企業との共同研究も活発で、公共交通機関や接客業などストレス可視化が求められる分野で、実証実験を多数主導してきた。
ただ優秀なだけではなく、教育者としても学生の話をよく聞き、的確なフィードバックをくれる。だがその一方で、誤魔化しや表面的な発表には鋭い指摘をすることで知られ、研究室内では「優しいけれど逃げ道はない」と噂されている。私にとっても、尊敬と少しの畏れを感じる存在だ。
教授は無言でファイルを開き、ページをめくるたびに眉をほんのわずか動かす。その沈黙のひとつひとつが、心臓の鼓動を強めていく。この沈黙が、早く終わってほしい。
「……うん。丁寧にやってるね。構成も悪くない。だけど——」
教授が言葉を切った。予想していた展開だった。
「“面白い”けど、“新しくはない”ね。君自身、どう思ってる?」
紀美は一瞬言葉に詰まり、視線を落とした。
「正直、データだけを見ていると、“正しすぎて、何も見えない”感覚があります。実の感情の揺れと、ログの間に乖離があるようで。」
「なるほど。」
教授は顎に手を当て、画面をスクロールさせた。
「たとえば鳴瀬さんの“休日のストレスが高い”というデータ。これは単なるラベルじゃなくて、“文脈”の問題なんじゃないかな。」
「文脈……ですか。」
「感情っていうのは、“意味”に支えられて発生する。孤独な休日。誰にも求められない時間。──そうした状況の意味が、ストレスという数値を生む。数値は“何が起きたか”を教えてくれるけど、“なぜ起きたか”までは語らない。」
その言葉に、胸の奥がざわついた。ずっと感じていたもどかしさが、言葉になった気がした。
「君が今取り組んでいる“感情のデータ化”は、次の段階に進める価値があるよ。負の感情のログ、行動記録、そしてそれが生じた背景。これを統合していけば、“感情の地図”が描けるかもしれない。とは言え、あと一月でそこまで到達することはできないだろう」
教授はそう言って、ソファーを軋ませながら背中を伸ばした。
「君にひとつ提案がある。──助成金に応募してみたらどうかな? 卒業して就職するのも立派な選択だけど、こういうテーマは、まだまだ掘れる。続ける価値があるよ」
紀美は少しだけ視線を泳がせた。予想外の回答だった。
「この研究は、これからの時代にとって意味を持つ。AIや自動化がどれだけ進んでも、“感情”というものを理解できなければ、人間の居場所はどんどん薄れていく。──それに君、面白い共同研究者がいるらしいじゃないか」
「茜のことですか?」
「そう。“感情探偵”って呼ばれてるみたいだよ。文学部の教授たちの間でだけどね。物語の登場人物だけじゃなくて、関わったフィールドの中にある言葉や沈黙、目線の流れまで拾い上げて、感情の軸から物語を再構成する力があるらしい。“情報の輪郭が揃っていないときほど彼女は冴える”なんて話も聞いたことがある」
教授は冗談めかして肩をすくめた。
「物語に埋もれずに、現実に起きている“感情の構造”を解読する。それが彼女の強みなのかもしれない。……jellyより検知精度が高そうだ」
その言葉に、紀美は思わず吹き出してしまった。
「これからの時代は、研究者のポストも大事だが、本質的な研究をじっくりやる人材が必要だ。そもそも、研究が終わってなければ2年で修士を終える必要はない。今の大学は、就職予備校化してしまっている。本当に研究をしたい人のための仕組みが弱いと思っている」
私も、つい最近まで卒業することしか考えていなかったので、心臓が痛くなった。
「この研究は、時間はかかるかもしれないが、感情解析をもう一段上にあげる可能性がある。だから、茜さんと二人で科研費を狙うのはどうだろうか。彼女は博士に進学するらしいし、ちょうどいいと思うがどうかな?」
私はなんだか嬉しい気持ちになり、胸がいっぱいになった。年末に父と相談しますと、言ったが顔がにやけていたと思う。
「最後に、個人的なことなのですが、被験者になってもらった妹のことですが、教授ならどうしますか?」
思い切って聞いてみた。たくさんのフィールドで、感情を観測してきた彼ならどうするだろうかと。
「僕ならjellyに向き合うかな。だって、感情が見えるのだから解決できるはずだ。工学者ならデータをもう一度丁寧に解析すべきだ」
私は狐につままれたような気持ちになった。そのあと、教授からのアドバイスを実行することにした。
「期待しているよ、ワトソン君」
教授は笑った。
*********
大晦日の日、私は鳴瀬と東京駅で待ち合わせをした。私たち実家は、東京から電車で1時間半の距離にある。一緒に帰省するのは始めてだ。グリーン券を買い、電車に乗り込んだ。横並びに座り、駅で買ってきたコーヒーを手渡した。早朝を狙っての在来線を使った帰省は正解だった。おかげで、席は空いている。
出発して、しばらくすると車窓の外に高い建物がなくなっていた。車窓から見る風景は寒々しく、厚手のコートを着てきて良かった思う。灰色の空からは、今にも雪が降り出しそうだ。
私は隣に座った妹に対して、今回の研究の結果と、茜の考察を話した。鳴瀬はその話を静かに聞いていた。
スカイリンクス航空が行っているのは、感情の可視化と調律を通じたサービスの最適化だ。その過程で、結果的に「感情の商品化」が行われているように見えるかもしれないが、それ自体がすぐに悪だとは言いきれない。感情労働は、人と人との関係性をなめらかにし、サービスを成立させるために必要な営みだ。そこに誇りや使命を感じる人もいる。
むしろ今の社会において、感情労働はますます重要になってきている。AIが進化し、知的労働の多くが代替されつつある現代において、“人間にしか担えない役割”として感情のやり取りや共感的対応の価値が再認識されつつあるのだ。感情を扱う力は、単なるスキルではなく、社会を支えるインフラの一部となりつつある。
ただし、それを可能にしているのが、いわゆる「深層演技」であることも確かだ。ホックシールド教授がかつて指摘したように、演技が日常化することで、自己と役割の境界が曖昧になる。ましてや今の世代は、Jellyを通してストレスを“感じないように”設計された環境に育ってきた。生理的ストレス反応が抑制されることで、負の感情に名前を与える前に沈静化されてしまう。
「私はどうすればよかったの?」
発言したとき、jellyが反応した。彼女のストレスを検知し、心を守ろうとしている。私の耳にビープ音が鳴る。
「jellyを外して聞いてほしい」
鳴瀬は戸惑っていたが、耳元に手をやりjellyを外した。私もjellyを外す。その瞬間、電車の揺れ、座席の軋む音、車内のアナウンス――そういった小さな音たちが、急に瑞々しく聞こえてきた。彼女の中にも音が戻ったと私は思った。
「鳴瀬が本当に恐れていることは、どんなに職場で努力し優等生になったところで、組織の中では換えがきくということにが気がついたことなんじゃない?」
「どうして」
鳴瀬の涙ぼくろを、滴が伝いはじめた。
「私は、最初、市川さんへの指導がjellyの暴発の理由だと思った。でも、それなら自分の言葉や休日にjellyが反応することの整理としては弱いと考えた。もう一度、jellyの結果を見ていて気がついた。私たちという発言の時にほんのわずかな時間だけど嫌悪感が出ていた。これは組織に対しての信頼がなくなっているのではないかと」
しばらく鳴瀬は沈黙した。おそらく、自分の感じている負の感情を観察しているのだろう。そして、言葉を選び、話しはじめた。
「あれだけ期待されていた市川くんが、たった一ヶ月で話題に上らなくなった。まるで、初めから存在しなかったみたいに。市川君のことを本当に心配している人がいないこと──そうか、それが怖かったのか」
鳴瀬の声は弱々しかった。心の奥から漏れた音のようだった。
「私自身も、替えが効く存在で、業務時間に同僚が仲良くしてくれているのは演技なんじゃないかと思う日が増えた。職場で頑張っても、替えがきくって思われるのが怖かった。ちゃんとした人でいようとしたのに、結局、報われる場所じゃないって気づいちゃったら……」
「会社って、成果を出している時は期待される。でも、それって条件つきの利害関係を下敷きにしている。役に立つ間だけ信頼される。でも――」
私は言葉を選びながら続けた。
「家族は違うよ。鳴瀬が泣いても、間違っても、何もできなくても、きっと味方でいてくれる。“そのままの鳴瀬”を支えてくれる存在なんだと思う。今まで、辛い思いをしていたのに気がついてあげられなくて、ごめん」
しばらく沈黙が流れた。鳴瀬は窓の外を見つめていたが、やがて小さく笑った。
「……おねえちゃんみたいだね」
そう言って、こちらを見た彼女の目元にはまだ涙の痕があったけれど、表情は少しだけやわらいでいた。
「私も大人になったからね」
冗談のように返すと、鳴瀬はくすっと笑って首を振った。
「違うの。そういうのじゃなくて……なんか、私が忘れてたことを思い出させてくれる感じが、ちょっと懐かしくて。」
そしてまた、小さく笑った。その笑顔は、どこか少しだけ、救われた人のように見えた。
「実は、私には夢があるんだけど、笑わないで聞いてくれる?」
彼女は、幼いころの妹のように話し始めた。鳴瀬の話す夢は、まだ形になっていない。けれど、その語り口には確かな熱と揺らぎがあった。周囲の期待ではなく、自分の声で未来を語りはじめた――それだけで、私は胸がいっぱいだった。
その後、私たちは、たくさんの話しをした。一緒に住んでいた頃に言えなかったことを。
実家の最寄り駅についたとき、雪が降り始じめてい。雪は音を吸い、静かだった。私たちは並んで家までの道のりを歩いた。転ばないように手をつなぎ、降ったばかりの雪に足跡をつけて進んだ。白い息が、空に上がっていき灰色の雲に溶けていった。
**********
春になった。マンションから見える、並木には桜が咲いている。今日は卒業式だが、私の出番はないので午後になったら謝恩会にだけ顔を出す予定だ。
私は結局、修論を出さず1年見送ることにした。茜とまとめた研究レポートは発表せずにスカイリンクス航空に提出した。指導教授が間に入ってくれたことで、大きなハレーションはなくポジティブに受けとってもらえた。先方の研究部門が興味を持ってくれ、共同研究することで合意したのは驚きだ。産学連携することで科研費も取ることができそうだと、教授は喜んでおり、私の学費もなんとかなりそうだと安心した。
ひとつ予想外だったのは、スカイリンクス側は、現場の実務と感情データの突合を重視していたため研究はより実装指向になった。私はデータの揺らぎに人間らしさが現れることを説明し、感情の閾値や復元時間の設計する研究計画に修正した。感情労働の世界に、データを持ち込むことで労働者にとって長く働いてもらえる環境を提供することがスカイリンク航空の目的だ。最近、優秀層の定着が経営課題に上がっていたため、良いタイミングだったのだろう。
茜は、貴重なフィールドが手に入り、ご満悦だった、社会科学者にとって大型の研究費を取ることや実企業と組むことは珍しい。彼女は相変わらず、感情探偵なんてへんなニックネームをつけられていて面白いが、本人もまんざらではなさそうだ。
私は校門の前で写真を撮っている人々の群れをそっとよけて、急ぎ足で逃げる。誰もが浮かれているが、私にとっては平日なのが心苦しかった。納得して、留年したとは言え晴れ着の同級生たちを見ると、心が痛くなる。
なんとか、喫煙所に行くと茜がスーツ姿で煙草を吸っていた。なんとも似合わない格好に思わず笑みがこみ上げてきた。修了証書がベンチに置かれていた。
「良い感じに、だるい」
茜は、煙を吐き出しながら言った。私は、卒業式の日も変わらない友人がいてくれて良かったと思った。
「そう言えば、鳴瀬さんは元気?」
「なんか、すっごい元気だよ。今日もチャットもらった」
以前の鳴瀬は、jellyの反応に合わせて“感じない”ことに慣れていた。でも今は、自分の中に芽生えたざらつきや違和感を、少しずつ言葉にしようとしている。感情を測定するのではなく、見つめ、向き合おうとしている。その変化は小さくても、確かに彼女の中で何かが変わり始めていた。
鳴瀬は、あの研究以降、感情労働に興味が出たようだ。他の国の航空会社がどうマネジメントしているのかを知るために、上司に留職したいと希望を出した。そのため、論文と英語の勉強中とのことだ。
帰省したとき、彼女の夢は留学することだったと聞いたとき驚いた。私が理工学部に行くために学費を気にして言い出さなかったことを電車の中で聞いて、驚いた。我が妹ながら、本当に優等生だと思う。
例の後輩の市川さんは、なにごともなかったように復帰しらしい。今は男性の上司の下に入り、うまくやっていると教えてもらった。彼の復帰を人事部がサポートしてくれたこは鳴瀬にとって大きな影響を与えた。現場以外に支援してくれる組織機能があることを実感したからだ。
茜が私の顔をのぞき込んだ。
「紀美と、これからも研究できて嬉しいよ」
「どうしたの、改まって」
私は、すこしきょとんとしてしまった。
「なんか、いいなと思っただけ。なんだろうね、この感情は」
茜は、青空をぼんやり眺めていた。私は、彼女が見ているものを少しでも一緒に見たいと思った。風が吹き、桜が舞った。茜の煙草の甘い匂いがした。
文字数:21981
内容に関するアピール
AIによって知的労働が自動化された未来、社会の中で「感情労働」が再定義されていく様子を描きました。
本作では、感情の可視化と管理を担うデバイス「jelly」を通して、働くこと・感じることの意味を考えてみました。
参考文献
『管理される心』世界思想社 著:A・R・ホックシールド
文字数:135