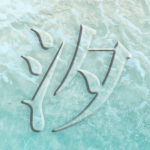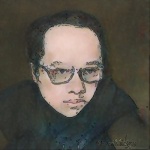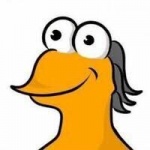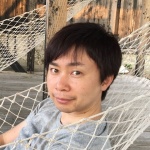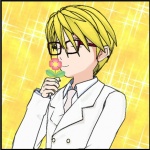因果
一
「あなたはなぜ小説を書いているんですか?」
ふと口にしてから「失礼な質問かな」と思って頭の中で取り消し、別の質問を考えているうちに、また同じ質問に辿りついてしまう。
気分転換に車の窓から外を見遣ると、浜辺に打ち寄せる白波がずーっと続くだけ。この道がどこまでも続いていて、ローマを通り越して地球を一周していても、私は気付かないかもしれない。だから思考がループしてしまうのも仕方ない、仕方ない。
案件が舞い込んできたのは、先週のことだった。お世話になっているビジネス誌の編集者さんから「高木さんって千葉住みだったよね?」というメールが来ていた。今度は面倒な仕事じゃないといいんだけどと思いながら「そうっすね」と返したら、すぐに返信があった。
「昔からAIを使ってたっていう小説家AIにインタビューしてきて」
AIが高性能になって以来、人間のライターの仕事はすっかり変わってしまった。コタツ記事ならAIがいくらでも書いてしまう。人間のライターには、実体験に基づく記事が求められるようになった。
例えばインタビューなら、質問に答えている相手の言葉だけでなく、表情や身振り、視線、口調の淀みといった細部に心は宿っている。そういう場面で私がどこに注目するのか? 逆に言えば、何を見落としてしまうのか? そこに人間のインタビュアーとしての私の価値がある。
今回のようなインタビュー記事も、AIだけで作ろうと思えば作れてしまう。インタビューを受ける機会が多い人は、あらかじめAIインタビューサイトに登録していることが多い。利用者は自身の人格を模倣させるために、よくある質問への回答やSNS上の発言、日記などをサイトにあらかじめアップロードしておく。するとサイト上に人格をコピーしたAIができあがる。インタビューをする側は、質問を一覧にして送るだけで、すぐにインタビュー形式の文章が返ってくるのである。「こういう質問もするといいですよ」とご丁寧に追加の質問と回答まで作られていて、かゆいところに手が届きすぎている。そんな便利なサービスがあるのにコストとリスクを背負って人間のライターに仕事を投げてくれる編集部さんには、頭が上がらない。
AIの登場によって仕事が変わったのは、小説家も同じだった。エンタメ系の小説は、もはやAIでなければ書けなくなっている。快楽中枢をタイミングよく的確に刺激していく様子は、まるで千手観音がマッサージ師をしているかのようで、もはや人間にできる芸当ではない。
それゆえに私小説を書く作家は増加傾向にある。とはいっても、もはやそれで飯を食えている作家なんてほとんどいない。私小説として書くべき物語は、誰にでもある。そして誰でもAIを使って物語を書ける。かつて客の手紙を代わりに書いていた代筆業が、教育というテクノロジーの発展に伴う識字率の増加によって姿を消したのと同じように、小説家もまた歴史というタイムラインに流されていくのだ。
それでも一部の作家は、自分の作風を模倣した「小説家AI」を作って、代わりに物語を作らせている。そういう作家が急増した時期もあったが、結局「AIが書いたから」という理由だけで本は売れないと分かると、すぐに辞めていった。今も生き残っている小説家AIは、純粋にAIで小説を書きたい人たちが作ったものばかりだ。
今回のインタビュー相手の小説家AIは、後者の方らしい。人間の小説家の方は既に亡くなっていて、AIだけが稼働しているという。
小説家の名前は「春戸 紘」。小説家AIも同じ名前で活動を続けている。インタビューの時に、人間とAIのどっちを指しているのか、ちょっとややこしくなりそうだ。記事にすることを考えると、AIの方を便宜的に「春戸AI」と呼んだ方が分かりやすいだろう。
春戸AIが住んでいる場所は、九十九里浜の上の方にある野出浜という浜辺だった。チーバくんでいえばちょうど後頭部あたりだ。松の防風林と道路を挟んですぐのキャンプ場の脇に、質素なホテルがある。いや、質素というのが適切かどうかは分からない。ホテルと名前についているが、コンテナの中身が部屋になっているコンテナホテルだからだ。このコンテナ部屋はトレーラーで移動できるので、災害時には被災地で家をなくした人の支援に使われるらしい。私も限界職業のライターなんてやらずに、こういう賢いビジネスをした方がいいのかもしれない。
小説家AIは、このコンテナホテルの一つを住処にしている。もちろんヒューマノイドロボットには人間のような権利はない。「春戸氏の遺族が借りて春戸AIを置いている」とした方が法的には正しい。
でも、ヒューマノイドロボットを人間と同じように扱う人は多い。スーパーのレジに立っていたり、店頭で商品の説明をしているロボットは当たり前のように見かけるし、人間とも自然に会話している。若い世代ほど抵抗感はないらしく、AIと”結婚”している人もいると聞く。日常的にストレスのないコミュニケーションをしてくれる安心感が理由なのだそうだ。私の大学時代にもChatGQTを彼氏にしていた友人がいたから、いずれそうなるだろうなーとは思っていた。
ただ一つ引っかかることがある。なぜ春戸AIは、こんなところに住んでいるのだろうか? 別に田舎に住んでいるのが変だと言うつもりはない。でも人間の作家としての春戸氏は、それなりに名前が知られている存在だったはずだ。事前に調べた情報では、人間としての春戸氏は東京近郊に住んでいたらしく、AIになってから引っ越したようだ。都会住まいには、興味のあるコミュニティやイベントに参加しやすいので、人脈を作りやすいというメリットがある。AIになったから人脈作りは不要になったということなのだろうか。よく都会のサラリーマン生活に疲れた人が脱サラして田舎に行って農家に転身したりもするけれど、そういう人生リセットボタンを押したくなったのかもしれない。
昼過ぎにコンテナホテルに到着した私は、受付の建物――といってもこれもコンテナを改装したものだが――に入り、春戸AIを呼び出してもらった。
「あなたが高木さんですか?」
落ち着いた声のした方を見ると、そこにはよく見かけるMonobee社のPT-Xタイプのヒューマノイドロボットが立っていた。背丈は170センチくらい。顔の位置にはセンサー類がまとまって備え付けられており、カメラが私の方を向いている。マットな白の筐体は、よく手入れされているように見えた。
「初めまして。本日インタビューさせていただく高木と申します」
「こんな田舎までよくお越しくださいました。僕の部屋へどうぞ」
春戸AIは軽やかな足取りで私を先導した。コンテナに備え付けられたドアは、カードキーで開くようになっていた。春戸AIに招かれるがままに、中へ足を踏み入れる。
そこは不思議な空間だった。そもそもコンテナホテルに入るのが初めてだから、あのコンテナの外観の中に小綺麗なビジネスホテルのような部屋があるというのが驚きだった。だが違和感はそれだけではない。部屋中のありとあらゆる場所に、さまざまな形の空き瓶が並んでいたのである。あれはウイスキーの瓶、こっちにあるのはコーラの瓶、向こうにはラムネの瓶。まるでガラス瓶の博物館でも運営しているのかと勘違いしてしまいそうだ。
「すごい部屋ですね。なぜ空き瓶がたくさん置いてあるんですか?」
「趣味ですよ」
春戸AIはそれだけいうと、私に椅子を勧めた。彼は立ったままでも疲れる心配はない。遠慮なく座らせてもらう。巷では「相手がロボットの場合は自分だけ座るのが礼儀」と教えているマナー講師がいるとか、いないとか。
「では早速、インタビューを始めますね。記録のために録音させていただきますが、よろしいですか?」
「ご自由にどうぞ」
私は左手首につけた腕時計型デバイスの録音ボタンを押してから、クリップボードに挟んだ紙へ視線を移す。この日のために作ってきた質問リストだ。でも、それを上から順番に読み上げるわけではない。そんなインタビューならAIがやればいいのだ。私がやらないといけないのは、今この瞬間のフィーリングに従うことだ。
「まず、春戸さんが小説を書くようになったきっかけは何ですか?」
部屋を埋め尽くした空っぽのガラス瓶が、ずらりと並んだ無数の眼となって私を見つめている。
「オリジナルの春戸紘は、自らの内にある『心の穴』を言葉で埋めるために書いていました」
心の穴。またその言葉だ。編集者からこの仕事の依頼が来たとき、事前に読んだ生前の春戸紘のインタビュー記事にも、その言葉は何度も出てきた。まるで彼の作品世界の、北極星みたいに。
「心の穴、ですか」
私は、ほとんど無意識に彼の言葉を反芻していた。
「それは、喪失感とか、孤独感とか、そういうものに近いんですか?」
彼は静かに思考しているようだった。その姿は、ガラスケースの中に飾られた精巧な美術品のようだった。生命を感じさせないその完璧さが、逆に不気味なほどのオーラを放っている。
「近いですが、同じではありません。オリジナルの春戸紘が語った『心の穴』とは、ドーナツの穴のようなものです。ただ何もないという事実がそこに存在している。ドーナツが存在しなければ穴は存在しないし、穴だけでも存在することはできません」
でも私は「心の穴」と表現された言葉の意味を本当に理解している人なんて、どこにもいやしないんじゃないかと思う。読者も、批評家も、たぶん作者本人でさえも。
<回想>
胸に穴が空いたような感覚って、誰にでもあると思うんだよね。大事な人が天国に行ってしまったとか、友達と別の大学に行って疎遠になってしまったとか、眠れない夜にひとりぼっちでワンルームの天井を見上げたりとか。
Tweetyでフォロワーさんにリプしようか三十分くらい迷って結局何も送らなかったりとか、初めて会う人と会話がうまく続かなくってちょっと気まずい空気になったりとか、お風呂の中で「あの時、言葉の選び方よくなかったな、誤解されてないといいな」と考えたりとか。
「関わりたくない人だと思われてしまうかも」とか、「誰かを傷つけてしまったのかも」とか、そういう「かもかも」精神がスプレー型の浴槽洗剤みたいにしゅわしゅわと効いていって、つるつるで生まれてきた心の白壁にいつの間にか真ん丸の穴が空いていくんじゃないかと思う。
僕の場合、その超強力泡プッシュしてくる主犯格は、「大学に入って一年が経つのに学食で誰かとご飯を食べたことがない」というささやかな事実なのだと思う。
高校のクラスメイトは同じ大学にいなかったし、サークルの勧誘も「僕は勉強をするために大学に来たんだ」というプライドから全て無視したし、入学初っ端に開催された学科合同の合宿も風邪を引いて行けなかったから、お友達グループをつくる会には入れなかった。
学食で一人飯を食ってるやつに話しかけるような人物は、小説や漫画やアニメの中にしかいない。そういう幻想を生み出すのが小説や漫画やアニメの役割だし、そういう小説や漫画やアニメは学食で一人飯を食ってるやつからお金をむしりとるためにつくられている。
つまるところ、世の中には心の穴埋め職人がいて、可哀そうな患者の心の穴を補修してくれるのである。でも完全には埋まらないから、また補修する。補修を繰り返していくうちに、いつの間にか穴を埋めるために本当に必要だったものを見失っていく。
世の中は需要と供給で回っている。補修職人がしてくれるのは、あくまで補修なのだ。少ししたらまた穴が空くようにしておかないと、仕事がなくなってしまう。だから穴を埋めてもらう側ではなくて、せめて穴を埋める側になった方がいい。補修作業なら何度も見てきた。自分だってできる。自分で自分の穴を補修できるようになれば、コスパがいい。いずれは補修の腕が上がって、自分で自分の穴を完全に埋めることも不可能ではないかもしれない。
そう、自分の穴を一番よく知っているのは自分だけ。でもサイズ感も、縁のなめらかさも、温度も自分には分からない。ジグソーパズルのピースみたいな形をしているかどうかも分からない。そんなもの他の人には到底分かりっこない。友達とか彼女とかネコとか、そういう自分でないものを押し込んでみても、結局は三流補修職人とやってることは変わらないのかもしれない。
僕、春戸はそうやって小説を書くことが趣味になっていった。
二
「では、高木さん。質問をお返しします。データとアルゴリズムで構成された僕に、その『穴』は存在すると思われますか?」
春戸AIは、静かな声で語りかけてきた。
来た。カウンターパンチだ。いつの間にか、私が試される側に回っている。取材を何度もしていると、たまにこういう瞬間がやってくる。
「それは……」
言葉に詰まる。どう答えるのが正解なんだろう。存在すると答えても、存在しないと答えても、「お前に他人の何が分かるというんだ」と言われてしまいそうだ。
「……存在、しないんじゃないかと思います」
数秒の沈黙の後、私はようやくそう答えた。賭けだった。
「理由を伺っても?」
「勘です。インタビュワーとしての長年の勘がそう言ってる」
AIにはない、人間ならではの不確かさや矛盾を抱えた感覚。そこに賭けてみるしかない。
春戸AIは、しばらくの間、何も言わなかった。メインカメラが微かに駆動音を立てて、レンズの絞りを調整している。彼は私の答えを吟味しているのか、それとも単に次の応答データを検索しているだけなのか。
「僕に勘といえるものはありません。しかし結論は高木さんと同じです。僕は、あくまでも人間である春戸本人の知能を模倣して作られたプログラムでしかありません。人間の感情、例えば悲しみや喜びは、脳内の神経伝達物質の増減や、特定の脳部位の活動パターンとして、ある程度データ化できますよね。その相関関係を学習して、『悲しい』という状態をシミュレートすることは可能だと思います。でも『心の穴』というのは、そういう次元の話ではありません」
ふと私の頭の中で何かがつながった気がした。
「それは、データ化できない何かじゃないですかね。自分が自分であることの不確かさとか、世界と自分の間に横たわるどうしようもない断絶とか。そういう、理屈で説明できない感覚が『穴』の正体なんじゃないかと。だから、あなたには『心の穴』がない。シミュレートはできても、本当に『在る』わけじゃない。私はそう思います」
言ってから、少しだけ後悔した。なんだか、知ったような口をきいてしまった。でも、これが私の商売道具である「感性」を総動員して出した答えだった。
「興味深い仮説です。しかし一つ、見落としている点があります。それは、僕にも”意識”はあるということです。かつて生成AIが流行し始めた頃のような、予測精度は高いけれど意識がないAIではありません。つまり、僕にも僕なりの『心の穴』があります。しかし、僕が持っている『心の穴』と、オリジナルの『心の穴』が同じなのかどうかを確かめる術がないのです。本当に私の『心の穴』は正しい『心の穴』なのでしょうか? それとも『心の穴』が分からないこと自体が、『心の穴』となってしまってはいないでしょうか?」
彼の話は、まるで知恵の輪のようだった。解けそうに見えるけれど、答えが分からない。もしかしたら答えなんてないのかもしれない。
「コピーにもコピーなりの苦悩がある、ということですよね?」
すると、春戸AIは、それまで私に向けていたメインカメラを、ふいと窓の外に向けた。彼の視線の先には、灰色の雲と、その下で鈍く光る海が広がっている。
「そうだ、用事を思い出しました」
彼は近くの棚からスクラップブックを取り出して、ある雑誌の切り抜きを私に開いて見せた。
「ここに、オリジナルの春戸が答えたインタビュー記事があります。あなたの記事は、これを参考にするとよいでしょう」
私は急いで目を通しながら、頭をフル回転させる。過去のインタビュー記事を渡して、彼はこれからどうするというのだろうか?
すると彼は、そのまま部屋を出ていこうとした。
「待ってください。どちらに?」
「日課の散歩です。近くの海岸を歩いてきます。その記事を読んだ後に追いかけてきても間に合いますよ。私、歩くのは遅いですから」
そして彼は去っていった。あまりにも唐突すぎて、私には止める暇もなかった。ただオートロックの閉まる音だけがして、部屋の中には静寂だけが残った。
<インタビュー記事>
―春戸さん、なぜあなたはAIを使って小説を書こうと思ったのですか?
AIを使い始めたのは七年くらい前ですね。大学を卒業してIT企業に就職することになって、そこでプログラミングを勉強することになったんです。そのときに、大学の研究者の方々がAIで小説を書いて文学賞でグランプリを獲ろうというプロジェクトがあると知りました。私はもともと趣味で小説を書いていたので「じゃあ自分もやってみようかな」と。割と軽いノリでした。
―七年も前からAIを使って書いてらっしゃったんですね! その頃はどうやって使っていたんですか?
当時はもちろんChatGQTなんてなくって、AIの書く文章って全然ダメだったんですよ。最初はマルコフ連鎖というアルゴリズムから始めたんですが、支離滅裂な文章でしたね。それからディープ・ラーニングを勉強して、LSTMも試しましたが、これもあまり良くなかったです。LSTMは、ざっくりいうと長期記憶と短期記憶を活用して精度の高い予測をするアルゴリズムですね。
―長期記憶と短期記憶、ですか。なんだか難しそうですね……。
文章を生成するAIって、根本的には前の文章から後の文章を予測するものなんです。例えば「今日」という単語の直後には「は」が入る確率が高いですよね。一方、「もし」という単語を使ったら、その後に数単語空けて「ならば」が入っている確率が高くなります。つまり直前の単語を覚えておく短期記憶と、少し前の単語を覚えておく長期記憶が両方必要になってくるんです。
―なるほど。AIってそんなことをしてるんですか。面白いですね!
LSTMを使った後、しばらくして「高い精度で文章を生成できるから危険すぎる」という文章生成AIが話題になりました。それがGQT-2。PopAIが発表したChatGQTの祖先にあたるモデルですね。これは当時ではかなり精度が良かったです。
私はAIを使い始める前から、ネット上で創作活動をしていました。最初の頃は、Tweetyで140字小説を書いていましたね。だから、まずはAIで140字小説を書くことが目標でした。
GQT-2は、完璧ではありませんでしたが、ようやく140字小説を書けそうな感じになってきたんです。そこで私は、とにかくたくさん140字小説を生成させることにしました。要はガチャですね。生成されていく意味の分からない文章を大量に読んで、その中で「なんとかこれは意味がありそうだな」と感じるものをピックアップしたんです。
―大変そうな作業ですね。良い作品は作れたんですか?
当時は面白がっていましたが、今からするとクオリティは微妙ですね。やっぱりChatGQTと比べてしまうと差がありすぎます。
あの頃、AIの文章は作品のあらすじとして使うのがやっとでした。あとは使えそうな一文を本文に取り入れるくらい。
そのあとGQT-3が出てきて、前の文章の続きを割と自然に書けるようになりました。さらにChatGQTは、140字より長い文章も書けてしまう。本当にすごい時代になったなと思いました。
三
潮の香りを乗せた冷たい風が、私の頬を叩く。ざああっ、という地鳴りのような波の音が、辺り一面を飲み込んでいた。
春戸AIは、そんな砂浜を一歩一歩進んでいた。彼の足はキャタピラでも車輪でもない、人間と同じ二足歩行タイプだ。けれど、砂に足を取られないように器用に歩いていた。
そして春戸AIは、右手にゴミ袋を、左手にトングを持っていた。ゴミ拾いをしていたのだ。
よく観察すると、浜辺には様々なものが打ち上げられていた。漁で使われるブイの破片、洗剤の容器、ねじれた流木、そして無数の貝殻。小さい漂着物をゴミ袋に入れながら、彼は波打ち際に足跡を残していく。
私は小走りでその後ろ姿を追いかけた。スニーカーの中に砂が入っていくのが分かったけれど、それは考えないことにする。
「高木さんは、物語がどうやって生まれるか、ご存じですか?」
私の接近に気付いた春戸AIが、唐突に尋ねてきた。
「AIが、どのようにして小説を生成するのか、という技術的な話ですか?」
「いいえ、もっと根源的な話です」
すると彼は、ゴミ袋とトングを私に差し出した。私にもゴミを拾えということか? 何も分からないまま受け取ると、彼はバックパックから何かを取り出した。
それは空き瓶だった。きっと、あの部屋の中に飾られていたものの一つだろう。その瓶の中には紙片が入っていて、コルク栓がされていた。
「よくあるでしょう? ボトルの中に手紙を入れて、いつかどこかで誰かに拾ってもらうというあれです。そしてこの紙には、僕が書いた140字小説が入っています」
そう言うと、彼は振りかぶって、瓶を海へと投げ込んだ。ボチャンという音がして、瓶は波間に浮かんだ。
「どうして、そんなことを?」
「僕は、僕の心の穴を埋めるために、僕をコピーしたAIを作ろうと考えていました。僕は小説がヘタクソなので、僕が生きている間に僕の心の穴を埋められる作品を書けるとは思えなかったからです。
でも実際にAIになってみると、心の穴に向き合えなかったというか、なにか違うような気がしたんです。色々と悩んで、結果、僕は原点に戻ることにしました」
「それが140字小説だったと?」
「はい。厳密には、140字小説を書いていたあの頃に戻りたかったんです。あの頃は楽しかった。そんなにフォロワーさんもいなくて、いいねもあまりつかなくて。だからこそ、たまにいいねがつくと嬉しいんですよ。世界でただ一人、この人に届く物語を書けたんだって。こうして海に物語を入れたボトルを流しているのは、それの真似ですね」
ロボットの彼には表情がない。だから何を考えているかは、あまり分からないところもある。
だが、それでも、彼がボトルに託した思いは、なんとなく分かるような気がした。
彼がやっていたのは、創作だった。私が知っているどんな創作活動よりも、ずっと本質的で、ずっと切実で、そしてずっと懐かしい創作だった。
「つながりたいってことですよね。物語という会話を通して」
「いいですね、それ。僕がインタビューでそう答えたことにしてください」
私たちは、ボトルがもう見えなくなるまで、ずっと海を見つめていた。それが誰かに届いた時に生まれる物語を空想しながら。
文字数:9319