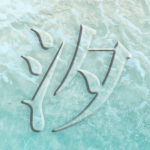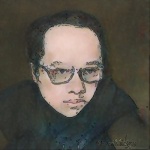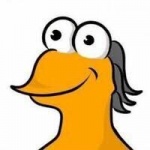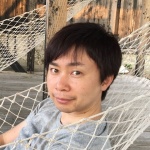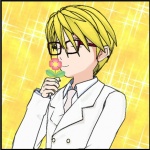沈黙以前
1
静けさには、段階がある。たとえば──葉身が揺れて触れ合うとき。舗道に落ちた木の実が、ひそかに砕けるとき。不意に誰かが金属片を擦るとき。その音は、複雑な過程を通じてただの気配へと変わる。
そうして生まれた沈黙こそが、この都市の本質だと、イオリ・カミザトは思っていた。
早朝は、都市の音響制御が最も精密に機能する時間帯だ。
イオリは誰もいないオフィスから小型のツールケースを携えて社用車に乗り込む。今日の最初の業務は、横浜の臨海居住区画の集合住宅で発生した音環境の不具合調査。音響保全局から発注された、やや急ぎの案件だ。
調査票によると住居空間の音響にごく軽度の雑音が干渉しているという。居住区画は、異常が生じたときの優先度が高く、即時の対応が必要になる。すでに別件の予定が組まれていたイオリにとって、久しぶりの早朝出勤だった。
車両を起動すると、こめかみの奥にかすかな衝撃が走る。〈オルト〉が作動した合図だ。すぐに『感情環境音楽シリーズ 午後のサバンナ』が車内に広がる。乾いた草を渡る風の音や、肉食獣の唸り声が響く。こうしたサバンナのざわめきが、早出のおかげで眠気の底にいる自分を表層へ引き上げていく。この音楽は人の集中と覚醒を促す情動振幅が組み込まれていた。その他の音は意識しないうちにどこかへ消えていった。
走り出してしばらくするとラジオが流れ始める。最初は限りなく控えめな音量。だが徐々にボリュームが上がってくる。
「おはようございます。時刻は八時になりました──」
パーソナリティが朝らしく、爽やかなトーンで問いかける。いつもならこの挨拶を耳にするタイミングは家の中だ。
「まあ、もう少し寝ていたいんだけどなぁ」
イオリはひとりごちた。しんとした静寂を破るように、猛禽類のいかめしい鳴き声がだしぬけに車内へ差し込まれる。
車は湾岸道路を南へ下る。川崎臨海部の物流エリアを抜けると、工場群の合間にちらちらと東京湾が顔をのぞかせた。やがて道路は京浜運河に沿って緩やかに湾曲し、横浜市内へと移る。冷えた朝の光が高架の支柱に斜めの影を落とし、埠頭のクレーンが静かに佇んでいるの横目にしていると、やがて景色は徐々に海沿いの住宅区へと移り変わっていった。
一時間ていどの走行で、現場に到着した。イオリは近くの停留区画を選び、指定の駐車位置に車を滑り込ませる。車体はまもなく静止し、イオリは助手席からケースをとりだすと、そのまま足を進める。
住宅棟に足を踏み入れた瞬間、空気がわずかに変化する。温度や匂いではない。音の密度が別の規則で整えられている、。靴音が吸い込まれて、足裏の感覚は感覚が宙に浮かぶようだった。
人通りの乏しい通路は、イオリの影と、等間隔で植栽された樹影が並んで伸びている。人の痕跡はどれ一つとしてない。この空間はために設計された環境で、常に快適さという静的な均衡に保たれていた。音もまた、重要な要素のひとつである。
中庭へと向かうアーチの前で足を止め、事前に渡された平面図と照らし合わせる。調査箇所の位置を確認し、イオリは小さく一息ついえからケースを下ろした。中には測定キット一式と記録端末、それから補正用の音源パッチなど、業務に使える最低限の機材が収められている。
次に、図面をもとに異常箇所のあたりをつけ、その周りをだいたい五メートル四方になるように、ビーコンを設置する。すると取り囲んだ内側は淡く緑色に光る線の網となって浮かび上がり、音響の分布が視覚化される。ざっとみたあたりでは整って見える。だが、一箇所だけ、波形のごくわずかな歪みをイオリは発見する。
そこは旧型の吸音材が埋められた一帯だった。乱れの特徴から、住人の生活音が完全に抑えられていないことが分かる。|情動振幅を分析すると、『不快』成分がごくわずかに検出された。
HAP 1.2% Loudness 0.01db。
数値を見つめながらイオリは思索する。微妙だな、と。不快音相関(HAP )は音波が『騒音』として認識される主観的な割合を示す指標だ。つまり、この音を不快と感じるのは人口全体の一パーセントにあたる。煩さも微細で、〈オルト〉の補正をすり抜けて耳に届く人数もごくわずかだろう。しかし、響きが乱れることは、生活の乱れに直結する。寝返りの衣擦れや、音楽の残響──それらが空間に滞留するだけで、誰かにの不快は蓄積される。どれほど僅少であっても、それをあると認識されたら、不快は除去の対象となる。
それこそが、二一〇〇年代の価値観だ。
なんにせよ応急処置は必要だ。
波形のサンプリングを一通り終えると、ケースから逆位相ゲルを取り出して吸音材に貼り付けた。透明なゲルは外気に反応して細胞のように膨張し、やがて吸音材の表面全体をおおいかくす。光の網の波紋の乱れはたちまち収束していく。ホログラムに表示された音場はまるで型に嵌めたように均一になった。
音は、そこにあった。だがいまは、磨かれた床のようになめらかさで、まるで最初から存在しなかったかのように。
イオリが戻ってきても、事務所には朝の静けさが少しだけ残っていた。都市の無音とは違い、ここには鋼鉄製の命綱を張りつめたような静寂がある。広いオフィスには数人が散らばって各自の作業に没頭している。デスクに着くとキーボードを叩く音すら空気のなかに沈んでいた。イオリの〈オルト〉が打鍵音を吸収しているせいだ。彼はこの音を不快音として個別補正の対象に設定していた。
無言のまま端末を取り出して、測定データをアップロードする。見慣れた書式に波形の特徴と所感などを打ち込んだ。この報告書は保全局の確認を経て、都市音響台帳の照会を通した後に具体的な対策が出される。それが『音響都市開発制度』における調査業務の一連の流れだ。
送信ボタンに指を伸ばしかけたとき、不意に〈オルト〉を通じて声が届く。
「お疲れさん。朝イチから現場だったってね」
同僚のカドワキだった。イオリも軽く挨拶を返す。声の調子は軽いが、目線はイオリのディスプレイに向けられている。
「HAPが1.2%? へぇ、案外ギリギリだったんだな」
「数値上はね。まあ大きな問題ではなかったよ。逆位相ゲルを貼り付けたらほとんど消えたから。まあ、部材の取り替えで業者は入ることになるとは思うけど」
「そりゃ、よかった」カドワキはデスク脇に立ったままコーヒーの紙カップを傾けた。「そしたら、報告書はそのままモリオカさんに渡せそうだな」
カドワキの言葉に、イオリはわずかに顔を上げる。
「モリオカさんが? わざわざここまで?」
「そう、わざわざ。たしか十時過ぎだったかなあ。課長が言ってたよ。ほら、今どきの官の人って現場もちゃんと見たいって人が多いからさ。調査の前に合流して軽く打ち合わせしたいんだって」
まいったな。イオリは画面の隅にある時刻を確認する。九時四十五分。その次の打ち合わせの対応は、どう考えても自分がすることになる。
午後にあるという現地調査は、音響保全局・神奈川支局から発注された業務だった。今朝とは別件で、むしろこちらの方が重要だ。その担当者がシエナ・モリオカ──資料で名前をみたときイオリは特段の印象は湧かなかったが、以前にやりとりをした同僚から評判を聞いたことがある。曰く、智力胆力兼備。眼光紙背を徹すといった実直な人柄らしい。聞く限りではカドワキがいう『今どきの官人』の最たる例だろう。つまり下手な対応はできない。
「流石にチェックなしで報告書を渡すわけにはいかないしなぁ」とイオリはため息をつく。
「だろ? データ、俺が引き継いどくよ」
カドワキが言い、カップの底を軽く振った。
イオリは軽く頭を下げた。「悪い。助かる」
報告書のデータをカドワキの端末に送信し終えると、イオリはケースを閉じ、記録装置を回収した。こうして空間には、何も起きなかったような均衡だけが残る。制度がこの都市にもたらしたものは、こうした何も起きないことの確実性だった。
「イオリ・カミザトさんですね。よろしくお願いします」
応接室のテーブルを挟んで、対面する女性は言う。両手に名刺を持ち、目線を落として読み上げるように確認しながらの挨拶だった。言葉にも所作にも、無駄や過不足はない。
「はい。こちらこそよろしくお願いします。モリオカさん」
イオリは椅子から立ち上がり、軽く頭を下げる。彼の隣には課長が同席している。最初にこの案件を取ってきた営業部のメンバーは軽い概要説明を進めた後、忙しいので、と言ってさっさと退席した。案件を数字に変換できたら終わり、といった態度。彼らの首尾一貫した考えを、イオリは理解できても共感はまったくできなかった。
残されたミーティングスペースには、外光が差し込み、わずかな緊張感が漂っていた。
シエナ・モリオカ。音響保全局所属の主任技術官。年齢は三十代半ばと見える。身につけているのは局の標準作業着──濃藍のフィールドジャケットに同系色のパンツ、胸元にはIDカードがぶら下がっている。現場主義を絵に描いたような服装だが、清潔感を両立させているあたりは官公庁の職員らしい。
場を取り持つのはイオリだった。促されたわけではなく自然とそうなった。打ち合わせは、事前に共有された調査計画に沿って進む。
「では、午後の現地確認について、ざっとポイントだけ確認させていただければと思います」
「はい。では、必要事項に絞ってお話しします」
モリオカは手元の端末をタップしながら、テーブル上に簡易モニターを立ち上げた。三次元地図には川崎市で計画されている都市再生事業の区画割りが示され、その最北のエリアを拡大していく。
「対象は新百合ヶ丘の都市型施設で、昨年末に開業。供用が開始されました──というのは皆さんもご存知だと思いますが」
「はい。かなり大々的に広告が打たれてましたね」課長は答える。
「自分は着工前に音環境調査に出向いたことがあります。ここまで立派なものになるとは思いませんでした」
そう言いながらイオリを当時のことを思い出す。広大な更地を測定器を抱えて駆けずり回った日々。あの時、主任だった上司は厳しいながら面倒見は良かった。叩き込まれた調査技術は今も通用しており、イオリは感謝している。
「──問題は、施設内部で想定外のサウンドスケープが多数発生しているということです。事例は様々ですが、主な報告は以下のようです」
ホログラムがフロア構造の断面図に代わり、波形データが追加された。全エリアの膨大なデータ群が一挙に表示されていて、乱雑な点描のようになっていた。モリオカは端末を操作しながら数箇所を抜き出した。
「これは、報告のあったエリアの波形データです」
「ふむ」と課長は顎に手をやる「特に目立った異常はなさそうですが」
「はい、私もそう思います。見かけとしては。もしかして残響抑圧が発生しているかもしれません」
モリオカの説明に、イオリは短く息をついた。
「なるほど、施設の環境設計と実情に知覚差があるということですか」
「そのとおりです」
「確かにこの検討は机上では難しい。実際に現場の音をサンプリングしながら原因究明を進めるしかありませんね」と課長
「助かります。ありがとうございます」とモリオカは朗らかに言った後、視線をイオリの方へ向けた。「あ、そうだ。カミザトさん」
イオリは、なんだろうと、内心で首をかしげる。個別に要件はあるとは思えた。
「今朝の音響補正については、すでにカドワキさんという方から第一報を受け取っています。報告書の正式版は後ほどで構いませんので、現場での感触があれば今のうちに伺いたいのですか」
思わず背筋が氷柱と化したかのようにこわばった。あいつ、ノーチェックで回しやがったな。モリオカの穏やかな調子は〈オルト〉の調整が働いたかもしれない。
「はい。臨海区画の件ですね。音響補正は済ませています──」
イオリは自身の端末を操作しながら、処置内容を簡単に説明した。その間、モリオカはメモを取るでもなく、うなずきながらただ静かに聞いていた。ときおり、「そのとき、近接の吸音材は?」や「外部からの透過音は無視できる程度?」などと、ごく要点を突く短い問いを挟んだが、全体として報告は手際よく進んだ。
最後は移動の段取りを確認するだけとなり、それも長引くことなく終わった。
ふと、課長が冗談めかして言った。
「いやあ、朝イチの現場帰りで、そのあとまた現地調査。カミザトもなかなか働かされてるなっ」
「まあ、慣れていますので」とイオリが返すと、モリオカは少しだけ表情を緩めた。
「ありがたいです。こちらとしても、現場を任せられる人が一人いるだけで、ずいぶん違いますから」
それは、事実以上の何かを含んだ言い方だった。責任か、信頼か、それとも──。イオリの中で〈オルト〉の音響位相がわずかに揺れた。言葉の内容ではなく、声の含みに反応していた。
新百合ヶ丘駅の北側に、まるで街全体が建物に吸い込まれたような巨大施設が聳えている。六層構造の地上階と、三層にわたる地下空間。吹き抜けからの自然光が構内を照らし、その奥行きは一目では全容を把握しきれないほどだ。この都市型施設は、震災復興事業の一環として構想され、川崎市の都市再生特区における北側の中核拠点として整備された。行政・民間の複合機能を抱え、再開発計画の象徴とされている。館内はショッピングフロアのみではない。行政窓口や、温浴施設、ゲームセンター、教育塾のサテライト教室などのありとあらゆるサービスを提供する店舗も収容されている。時刻に応じて照明の色温度が変化し、空調は人工気候に連動する。設計の意図は明らかだった──快適さの最大公約数を極限まで突き詰めること。
イオリとモリオカが現地入りしたのは十三時過ぎのこと。館内は平日にも関わらず大勢の来館者がいた。それに反して静謐な雰囲気がある。足音は吸い込まれるように消え、放送は必要な情報だけを耳をすり抜けていく。その代わり、人々のざわめきや鳥の声などが加工されたムード・アンビエントが空間を満たす。
「不自然ですね」とモリオカがぽつりと呟いた。「一見して問題がないんです。見かけのうえでは計測値は正常なんです。環境測定も竣工時とほぼ一致している。生態学的妥当性や心理学的快適性も問題はとくにない筈」
モリオカはわずかに眉をひそめた。
「でも、現場で感じる音の肌触りは、まるで違うんです」
イオリは同意する。ゴーグル型のインターフェースを装着して周囲の音場を視覚化した。波形に乱れはない。ノイズもなく、むしろ過剰なほど滑らかに均されている。まるで感覚の摩擦が全て削り取られたかのような、透明な異物感──それは音響的な空虚に近い。
整いすぎている。それは〈オルト〉の個別補正が必要がないくらいだ。その整然とした具合はイオリには引っかかった。ここには聞こえないはずの命令が隠れている──沈黙のかたちをした、秩序への強制。音がただ上書きされているのではなく、こうあれと指示されている。
目立った異常は何もない。イオリはゴーグルを外した。どうでした、とモリオカは問いかけるが、イオリは首を振った。
そのとき、回廊のガラス越しに外から白い影のようなものが見えた。渡り鳥の一団だ。だが、その群れは施設の屋上付近に差し掛かった瞬間、羽ばたきの軌道は乱れ、まるで見えない壁にぶつかったような挙動をみせた。そして何かを避けるように、群れは唐突に高度を変え、散り散りに飛び去っていった。
モリオカは目を細めて鳥の群れの軌道を追った。「あれ、上層で何かにぶつかったみたいに見えましたよね」
「僕もそう見えました」
「やはり、忌避現象が顕れている?」
イオリは頷いて即座に端末を操作し、該当区画の構造図を呼び出した。屋上には、『作用波形拡散プレート』が敷設されていた。これは高周波音を空間に拡散し、野鳥が建物に接近しすぎるのを防ぐ装置だ。人間には感知できない帯域で作動するが、環境設定が過剰になれば、飛行ルートそのものを阻害することになる。
「設計は問題ないとしても、調整が強すぎる可能性はありそうです」とモリオカ。
イオリはもう一度頷き、画面を切り替えた。詳細図面をいじりながら考える。たしかにコンコース側には異常はない。だが、音場全体にはどこか歪みが滲んでいる。均されすぎた空間のどこかに、抑圧された響きが沈殿している──それがいずれ、別の形で噴き出すかもしれない。
「屋内のバックヤードを確認しましょうモリオカさん。問題があるのは、むしろそちらかもしれません」
施設の案内スタッフに声をかけ、モリオカとイオリは搬送エリアのバックヤードへと案内された。配送業者やメンテナンススタッフの導線であり、施設の来館者がくることはない。
『関係者以外立ち入り禁止』と掲げられた自動ドアが閉まると同時に、環境音が急激に失われた。
空気が変わった、とイオリは思った。わずかに機械油の匂いが鼻をかすめる。けれどその匂いを連れてくるはずの機械の駆動音が聞こえない。足音や、持参した道具のがさがさとした音、いずれも消え入りそうに小さい。まるでこの空間だけ、音がひとつの粘膜の内側に閉じ込められているようだった。
「ここが例の通路です」スタッフが前方を指しながら言う。「たしかに反響が妙だという声はありましたが、いまのところ業務には支障がないとの判断でして」
「問題は、支障がないこと自体が異常な場合もある、という点です」とモリオカが言いながら視線をイオリへ向ける。
イオリはうなずき、ゴーグル型の測定器を起動した。空間の音響波形が端末上に可視化される。そこには──なだらかすぎる曲線が浮かび上がっていた。波形の揺らぎはごくわずかで、通常の環境なら必ず含まれるランダムな高低の変動が、まるで人工的に均されたように消えている。
「『沈黙のポケット』、ですね」とイオリが呟いた。「応答波形に欠損はない。むしろ、削られすぎている。最適化が暴走した例です」
「どんな原因が考えられますか」とモリオカ。
「いくつかあります。よくあるのは、音響調整機材が雑音を検知したとき、アルゴリズムが連動して、本来調整の必要がないエリアにも調整が働いてしまうケースです」
スタッフがきょとんとしていたため、イオリは補足した。
「たとえば小売店を考えてみてください。A店が商品を値下げすると、同じ地域にあるB店やC店は競合するようにして、値段に値引きしようとするでしょう。それに気づいたA店はさらに値下げを敢行します──このように局所的な調整が全体に影響を及ぼしてしまうんです」
「その結果、過剰な数値が表にでてしまう──」モリオカも端末をのぞきこみながら小さく息を吐いた。「たしかに、許容値は満たしているんです。だから、問題はないということになってる。よくある話です。こういうの、設計者も気づかないんですよ。設計上は想定内なんですから」
「とはいえ僕が言ったのは極端な例です。普通なら調整機構が働くはずなんですが」イオリは唸るように呟く。
そのときだった。奥から小さく物音がした。モリオカが目を向け、イオリが反射的に反応する。
警備員のひとりが壁にもたれかかるように立っていた。顔色が優れない。イオリが駆け寄って声をかけると、男は「耳が……詰まるような感覚があって、少しめまいが……」と、要領を得ない返事を返した。
「早く〈オルト〉を外してください。このままだと人体に影響がでます」
すぐに近くのソファに座らせ、モリオカがスタッフに応急処置を指示する。イオリは測定器のログを巻き戻し、先ほどの数秒間の波形を解析する。すると──一瞬だけ、異常な振幅パターンを検知する。逆位相のに振り切った振幅、もしくは極端な抑制フィードバック。音としては知覚されないが、人体への影響はあり得る。
「この空間、完全に過補正されていますね」とイオリが言った。
「これは静けさというよりも、制御された沈黙です。はぁ、なんて瑕疵を……」
モリオカはぼやく。
警備員の安全を確認した直後、計測端末に二つ目の警告が表示された。バックヤード西側の空調ユニット近辺で異常があるらしい。これは〈沈黙のポケット〉が、偏在的に発生していることを意味している。
「ここ、もう少し踏み込んで調査したほうがいいですね」モリオカが言い、制御パネルの前に移動した。イオリも該当区画の音場マップを呼び出す。視覚化されたデータ上では異常は最小限に見える。が、その最小限こそが問題だった。
次の瞬間、施設の照明が一瞬だけ瞬いた。わずか一秒足らずのことだった。
「停電か?」と職員が言う。
「いや、違う」イオリは周囲を確認しながら言う。「これも音波の過補正の影響です。空気の屈折率が乱れれば、照明の波長が歪んでしまうこともある。波が波を呼べば、視界すら揺らぐ。
モリオカが頷いた。警備員たちの表情は不安をいっそう募らせる。
「これは思った以上に、深刻です」とイオリ。
そのとき、通路奥で音がした。人影がよろめく。搬送スタッフのひとりが壁に手をつき、うずくまるようにしてしゃがみこんでいた。
「このままじゃ──封鎖の申請を」とモリオカが判断を下す。「局に連絡します。第三種干渉と判定して、音環境の一時制御権を要請しましょう」
イオリは頷き、外部連携モジュールを展開する。端末上で瞬時に通信ログが走り、保全局の中枢ノードと自動接続された。音響インフラ制御権限を一時的に拡張する要求だ。
保全局からの認証が下りると同時に、イオリの端末に制御権限が付与された。外部連携モジュールが展開され、接続ログが滑らかに走る。音響インフラの局所制御が、いまこの空間に限って彼の手に委ねられている。
イオリは手際よく操作を開始した。まずはバックヤード一帯の波形分布をマッピングし、最適化アルゴリズムのリセットを試みる。空間内に配置された音響中継装置が順次応答し、音場の再構成が始まる。
だが、たマップの端に、違和感のある軌跡が浮かび上がった。
波形ではない。むしろ、ノイズの堆積が柱状に立ち上がっている。通常の環境下で生じる反響定位のどれにも該当しない、縫い込まれたような構造。しかも干渉記録には、何も残されていない。
おかしい。イオリは声を出す前に身を引いた。直後、構造物のような波形が自分の立ち位置に向かって重なってくるのを、確かに視た。
測られている──。
その瞬間、空間の主客が反転したような錯覚に襲われた。波形が彼に応答するのではない。空間そのものが、彼を計測している。いや、解析している。
そして、身体に異常が起きた。
最初は立っていられないほどの平衡感覚の麻痺。足元が傾く。だが視界は水平だ。三半規管だけが、重力軸の異常を察知している。方向感覚が剥がれ落ちていく。
手の中の端末が変質する。接触面の硬さ、温度、触感──すべてが脱落する。指先が、何にも触れていないかのようだ。
逃げなければ。どこでもいい。とにかくこの場から離れなければ。だが足がついてこない。身体が自分のものではなくなっている。
崩れるように片膝をついた。頭の中で、可聴域外の波が反響する。耳に届かないのに、頭蓋に染み込むような圧迫感。音ではない、情報の圧力。
〈オルト〉が警告色を点滅させる、しかしその前に視界、青に染まる。演色プロファイルの異常変調。群青よりも青。夜よりも、深海よりも深い、のっぺりとした青が明滅する。
イオリはさらに崩れ落ち、両手を地面についた。そこに確かに床があるのに、手は地面をつかんでいるという実感を得られなかった。
「カミザトさん!」
モリオカの声が届く。だが、その声は、空気に削られながら届いてくる。存在の縁でちぎれ、音として完成する前に消えていく。
イオリはなんとかして自らの意識をつなぎとめようとした。しかし既に身体は彼に反応してくれない。座標がずれている。皮膚の内側に別の空間が入り込んできたような、居場所の錯誤。
セーフモード。
〈オルト〉が緊急処理を発動し、すべてのフィードバックが遮断され、視覚化データはグレースケールでフリーズする。
気がつくと、深閑とした闇に閉ざされた。
病室の窓際に置かれた観葉植物が揺れている。ちょうど空調の風の下にあるのだろう。音はないようでいて確かに存在していた。ただ、その輪郭は歪んでいる。
イオリはベッドの縁に腰をかけ、ぼんやりと外の景色に目を向けていた。装着を外した〈オルト〉は、消毒ずみのケースに収められてサイドテーブルに置かれている。
これが裸耳の感覚。音は生のまま、耳に届いている。換気扇が回っている。ナースステーションの方向からベルがかすかに鳴る。「あなたは知らないでしょうけど、子供の頃の夜はもっとうるさくて眠れなかったのよ」という老婦人のしつこい話。これらは構造で打ち消さない範囲の音だ。
それでも、透明な膜を通したように、響かない。音が、音であるだけになっている。ただの振動としてそこにある。けれども、それがなぜか感情は象に変換されてこない。
「平衡感覚には一時的な乱れがありましたが、可聴域は安定していますし、聴能への影響は限定的です」診療にきた主治医はそう告げた。データを読み上げるような簡潔な口調で。「なにかご質問ありますか?」
イオリはしばらく考えてから、
「音の聞こえ方が変わった気がするんですが、これはどうしてでしょうか」
「おそらく一時的な神経系の異常でしょう。音響事故に遭われた方はよくあります。主観的な要素なので、あとは気の持ちようです」
「そう、ですか」
「他にはありますか?」
イオリは曖昧に首をふる。
デバイスの再装着許可が下りたのは、その翌日だった。〈オルト〉は医療用のリミットモードが施されていてしばらくはこの状態だ。感覚刺激の閾値が抑えられ、処理速度も制限されている。イオリは耳の後ろに手を伸ばし、〈オルト〉を装着した。薄いフレーム状で耳を塞ぐことはなく、わずかに皮膚に触れる程度の細さ。装置の端から伸びる透明な導波体が、微細な神経刺激をこめかみに伝えている。この感覚には慣れているが、それでも今日はどこか不自然に感じる。
イオリは目を閉じて、何度か深呼吸した。
身体は正常だ。波形は乱れていない。補正アルゴリズムも破綻していない。なにも異常はない。だけど、やはり音に、響きがない。
そのとき、端末が振動した。ベッドサイドの画面に通知が浮かぶ。課長からだった。
表示されたメッセージは簡潔だった。
『カミザト主任
お疲れ様です。状況は確認しました。現場処理は無事に完了したので安心してください。次回報告まで療養を優先のこと』
硬質な定型文。必要最低限の内容だ。文面は、AIによって生成されたものだとすぐにわかる。添付ファイルは事故と復旧、休暇の承認、復職後の予定が整列している。まるで彼自身が、職務工程のひとつに変換されたような──そんな感覚が背筋に降りた。
それから数ヶ月してイオリは職場に復帰した。当面の業務は川崎市内の事務所からほど近い川崎市内の都市音響の業務を任された。復帰者にうってつけな低負荷の仕事。
今朝からどういうわけか雨音だけを残してみたくなった。
街中に流れるムード・アンビエントを受け入れたくなかった。歩行者の接触を防止する目的で設計された、心理的距離を保つための『断続的な空気の振動音』。
車輪の音は強調され、話し声も抑えられる。他人の幼児の泣き声なんてもってのほか。整備された音環境。イメージ通りの綺麗な音。もちろん、どこにもスピーカーはない。路面のマイクロセンサーが人流データをリアルタイムで分析し、音響バランスを即座に演算する。その補正結果が、〈オルト〉と連携して聴覚信号に投影されている。
以前からあった仕組みだ。人々に感情の平穏をもたらすしくみ。
情動振幅が発見され、都市計画に取り入れられたのは半世紀前。感情を音でコントロールするのは理想論と看做された社会は大きく変容した。感情の乱高下を防ぐことで都市の暴力や衝突は確かに減っている。二十二世紀に入ったばかりの現在、傷害事件や交通事故はほとんどゼロになった。誰かが安心して眠り、目を覚まし、予定通りの一日を送れるように。情動を波形で管理するこの制度において、出来事は抑制すべき変動であり、静寂は最適化された日常の保証だった。
だが今は、その潔癖さに、イオリは息苦しさすら感じる。
音が消されたのではない。余計な情報を消去している感覚。
イオリは広場の中央で立ち止まり、〈オルト〉を外して、耳を澄ませた。
ありとあらゆる音響は、すべてが都市の呼吸の一部として流れていく。だが、そのどれもが──借りものの音のように思えた。本物と見分けがつかないのに、決定的に何かが欠けている。この街の音のすべてが、皮膚の外を撫でていく。耳の奥に触れないまま、空気の膜のように通り過ぎていく。
──自分は、戻ってきたのかだろうか、本当に、この街に。
2
都市の静けさは、数値によってかたちづくられている。どこまでが気持ちの良い物音で、どこからが不快の兆しか──それを定めるのは、耳ではなく、統計だった。
詳しくは『都市音響設計・計画令』に基づく。それによれば、『環境音』は発生源・波形特性・情動影響度の三項目によって分類されている。どこから発せられ、どんな波形をともなって、どのような情動の揺らぎを引き起こすか。〈オルト〉は都市音響台帳に登録された膨大な音響データを参照し、音の聞こえ方をその都度、微細に調整している。加工の目的はただ一つ、あらゆる人にとって、不快ではない音だけを残すことだ。逸脱した波形は補正され、必要とされない音は、数秒のうちに世界からそっと剥がされる。そうしてできた『環境音』は、都市という巨大な生物の呼吸を担っていた。
だが、事務所で作業をしているときに確認した通知の内容は、そういった前提に微かなひびを走らせるようなものだった。
団体コード:21 国立音響保全局 神奈川センター
担当者:シエナ・モリオカ。
業務委託コード:EAL-17-断層調律。
依頼内容:対象区画における非準拠波形の確認と補正。
イオリはディスプレイ越しに、その名をしばらく見つめている。
担当者の名前だけで、指先がわずかに反応する。モールで起きた聴覚事故の後、イオリは業務を外れ、互いの関係は希薄なものになったはずだ。だが、その表面をなぞるような接点には、処理できていない、ひっかかりが残っていた。
補足欄に書いてある依頼文は簡潔だった。『音響緩衝地域にて、非準拠波形が確認されたため調査を依頼する』。添付された音源ファイルには注意書きがあり──『この音源は台帳に未登録です。分類タグの割り当ては不可能です』。
つまりその音は、この都市において、制度上は存在しないことになっていた。しかし、実際には存在している。いつものように〈オルト〉が自動補正してさえすれば、誰もその存在に気づかないはずだった。だがこの音は、それすら受け入れず、制度に名を持たないまま、確かにここに在る。その確かさ自体が、不穏だった。
通知を受け取ってから、連絡を返すと、すぐに返信がきた。業務が繁忙期に入ったらしく、しばらくまとまった時間がとれないので、できたら今日のうちに話がしたいらしい。その忙しさだと直接会って話をするのも無理筋なこと。遠隔でのミーティングを打診すると向こうも好意的に解釈してもらえた。時間のすり合わせの結果、夕方に指定されたので、いったん退社して自宅で行うことに決めた。
部屋の照明は点けず、間接照明だけにする。端末を開いた。時間ちょうどに接続アイコンが点滅し、ワンクッションのあと、画面にシエナの顔が現れた。
「こんばんは。お忙しいところ、すみません」
少しだけ髪を切ったようだった。印象は変わらないが、彼女らしい、きっちりとした印象だった。表情はおだやかで、どこか事務的。だがその輪郭には、事故後の時間を計っているような慎重さがにじんでいた。
「いえ、こちらこそ、お時間をいただき、ありがとうございます」とイオリは応じる。「お忙しそうようですが、食事は摂れていますか?」
「はい、なんとか。ご心配おかけしてすみません」
「そうですか。なら、よかったです」
その言葉のあとにぎこちない間が生まれた。音声の背後には無音のリズムが漂い、それが会話のなかにわずかな緊張をもたらす。
「今回、依頼したい区域はこちらです」
端末の共有画面が切り替わる。山間部の簡素な地図が表示された。マーカーが打たれているのは横浜よりも川崎よりも外縁──丹沢山麓の一面だった。
「過去にも小規模な異常はあった場所ですが、今回は性質が異なります」
「異なる、というのは?」
モリオカは別ウィンドウにファイルを開いた。そこには波形グラフとその分析結果が添えられている。
「情動振幅のスケーリングが効かないんです。台帳に収録されていないのでしょうが、HAPの計測も断続的で、再現性がありません」モリオカは口調を崩さずに説明を続けたが、その背後には微妙に苛立ちが込められていた。「そのため、保全局では、非準拠波形と仮ラベリングされました」
音源の再生指示はなかった。イオリも開かなかった。再生するまでもなく、その音の異様さは直感される。
「対象波形は環境音としての統合がなされておらず、既存の調律では補正が不能と判断されました。ですので──」
「現地で拾って、補正可能性を確認する、と」
「はい。ですが」モリオカの声が少しだけ柔らかくなる。「ご体調は、大丈夫ですか……」
「問題ありません。復帰後の調整を済んでますので。」
「そうですか──でも、この仕事、感覚を使いますから。もし、まだ不安が残るようなら、無理しないでください」
イオリは、首を振った。
「大丈夫です。むしろ、こういう依頼は久しぶりで、リハビリとしても助かります」
イオリ発した言葉に、迷いはなかった。けれど、その声色のなかに、ほんのわずかな湿度のようなものが残っていた。自分でも気づかない程度の、それでも確かにどこか濁った感情だった。
シエナは一度頷き、必要事項をまとめたファイルを送信した。
「緩衝域で何か捉えたら報告してください。念のため、測定結果や〈オルト〉の反応だけではなく、主観的な記述も添えていただけると」
「了解しました」
「よろしくお願いします。では、ご安全に」
回線が切れたあと、部屋の空気は元の静けさに戻っていた。
イオリは台所にいき、ポットから直接、インスタントコーヒーを淹れた。湯気がたちのぼる。その静寂は多少、厚みを持って感じられた。
市街地を出ると、空が広くなった。
ビルの並びが低くなり、建物と建物のあいだに、地表の傾きがそのまま姿を現す。アスファルトの反射は鈍くなり、車窓に映る風景も、都市とは異なる構造を帯びていく。
イオリはハンドルに手を添えたまま、深く息を吐いた。
現場までは、およそ一時間。進行方向には、丹沢の前衛をなす稜線がうっすらと浮かんでいた。しかし、それもまだ背景にすぎない。都市の終わりは、目に見える前に、まず音から変わっていく。
音響緩衝地域。都市の外縁に位置する地域は、『都市区域における情動振幅及び騒音レベルを制御する目的で、自然地形及び生態系を活用して音環境を保全する区域のことをいう』と定義されている。つまり都市部の過剰な共鳴や残響を吸収する、いわば耳当てのような役割を果たす地帯だ。
とはいえ、その役割を理解する都市住民は少ない。
この場所に日常的に訪れるのは、保全局の職員か、音響設計に関わる業務者、旧来の地理学や植生音響学の研究者くらいだろう。都市の多数派にとって、このあたりは地図の余白にあり、関心の対象には含まれない。
山麓へと続く細い道に入ると、車載ナビの地図は空白のまま、的外れな案内音声だけが虚しく聞こえていた。震災後の復興事業で道路網が大きく変わり、更新が追いついていないのだろう。山間部にいけばいくほどこうなるものだ。
ゆるやかな傾斜を登っていくたび、開けっぱなしの窓から入る空気の温度がわずかに変わり、肌触りもどこか粒立つように感じられた。やがて、簡易舗装が終わり、管理車両用の小さな駐車区画にたどり着く。標識はなく、案内もない。ただ、かろうじて平坦に均された砂利のスペースが、都市の境界の最後の痕跡のようにぽつんと残されていた。
車を停め、ドアを開けた瞬間、イオリの耳に、都市では決して出会わない静けさが訪れた。
とはいえ、それは都市特有の統御された沈黙ではない。沢のせせらぎ、枝葉が擦れる音、虫の羽音。いずれも〈都市音響設計・計画令〉で定義される『環境音』とは異なる、人の意思を経由しない自然発音だった。まるで世界の底から鳴っている音。
木製の階段を上がると、高台のうえに開けた場所を見つけた。雑木の間にぽっかりと空いたその一画は、かつて整備された展望地のようにも見える。錆びてぼろぼろになったフェンスが頼りない柱のように残っており、その背景には藤沢や横浜、川崎の遠景がぼやけるように見える。
だが、視線を横に向けたとき、不意に異質な存在感を放つ建物が目に入った。古いコンクリート打ちっぱなしの低層構造で、左右対称のファサード、傾斜をもたせた屋根。その佇まいには装飾性はなかったが、不思議と周囲の木々と調和していた。
イオリは一歩踏み出し、建物の前に立つ。雑草に覆われた石畳の先、木製のベンチが置かれていた。そこに誰かが腰掛けている。人影は白い布を膝に広げ、何かをしている。顔は光の反射で見えなかったが、動作は静かで、一定のリズムを保っていた。
一瞬、声をかけるのをためらう。異質な光景だったからだ。だが、ここに住んでいる人物であれば、先に挨拶するのが礼儀だ──そう思った矢先、向こうが先に口を開いた。
「どなた?」
イオリは名乗り、自分の身分を開示したうえで、音響保全局からの調査で立ち寄ったことを説明する。突然の訪問で驚かせたことを詫び、必要以上の立ち入りはしないと約束した。
「そうなのね。なるほど。たしかにあなたの音──青褪めていて、ちょっと擦れてる感じね」
「青褪めた、音?」
「視えるの。それでだいたいわかるのよ」
ゆっくりと女性が振り向く。
端正な顔立ちだった。目元に歳を感じさせる皺があるが、どこか若々しくもある。不思議なバランスの表情だ。
なにより目を引いたのは、耳の周囲からかけられて渡る透明なフレームだった。耳掛けのデバイスではある。だが、〈オルト〉とは構造が大きく異なっている。イオリはふと、かつて講義で目にした『聴覚補助インターフェース』の記述を思い出した。実物を見たのは初めてだった。
「ここにお住まいなんですか?」
イオリは問いかける。少し間があく。
「ええ、そんなところ。あたしくらいになると、こういう場所のほうが合うの。それに都会はうるさいでしょ」
思わずイオリは頷いていた。たしかに、ここは静かだった──だがすぐに違和感が浮かぶ。都市は今や、過剰な静けさこそが当たり前のはずだ。それでも、彼女がいう「都会はうるさい」という言葉には、なぜか妙な説得力があった。
女性は、空をなぞるように指先を動かす。その仕草は、幽霊と会話しているようにも見えた。
「このあたりは、ずいぶん音が溜まってるのよ。誰も聞こうとしないからね。かつてここにあった声、踏みしめる音、名前のない残響──そういうのが、まだ少しだけ、残ってる」
イオリは足元の地面を見た。この空間には、都市のどこにもない濃度があった。〈オルト〉を通して聴いてきた音とは、根本から質が異なる。
「聞こえないって、つまり……」
「聞こえないのではなくて、ただ語らないだけ。音たちは──街に馴染まなかったのよ」
女性は柔らかく微笑んだ。その声は明瞭で、きっぱりしていた。だが、どこか他人行儀でもある。長くひとりでここにいた人の、孤独と親しみの中間にあるような響きだった
「あなたは音を扱う人なんでしょう? なら教えて頂戴。聴くって、どういうこと?」
イオリは返答に窮した。あまりに根本的な問いだったからだ。
マルタ・クワハラと名乗った女性は、イオリを建物の中へと招いた。
玄関からすぐにひらけた一室は、照明が一切ついていないのにも関わらず明るかった。窓の外から入る光が、床材に斜めの線を落としている。 家具は意外なほど多かった。ソファ、ダイニングチェア、スツール、ひじ掛け椅子。どれも形も高さもまちまちで、ある種の博物館のようでもある。十人は軽く座れるほどの数だ。
その中央には、旧式の記録端末、波形可視化装置、調律メーター、そして数冊の古い技術書。都市ではすでに廃れた機器や形式が、ここでは今も使われているらしい。
「もともとはビジターセンターだったの。県が森林教育のために建てたらしいわ。登山客が立ち寄ることもあったけど、閉鎖されてからは放置されていたのを、ちょっと手を入れて──自宅にしてるの」
そう言って、マルタは冷蔵庫からペットボトルの緑茶を取り出し、無造作に差し出した。好きなところに座って、くつろぐようにと促したが、イオリは戸惑った。家具の多さに反してくつろいで良い場所の選択肢が明確でなかった。
「その非準拠波形だっけ? あたしにも聞かせておくれよ。何か協力できることがあると思うわ」
イオリは口を閉じたまま頷き、部屋の片隅にある椅子に腰を下ろした。バッグから端末を取り出し、〈オルト〉の記録データを呼び出す。無言のうちに一連の操作を済ませ、準備が整ったことを目線で伝えると、マルタはうなずいて言った。
「流してみて」
耳に届いたのは、風のざわめきに似たノイズから始まり、次第に低音が奥へうねるように侵入してくる感覚。次いで、細い金属をこすり合わせたような高音が断続的に挿入される。全体の位相は合わず、重心の所在が定まらない。〈オルト〉の補正アルゴリズムは反応を示している。だが、どのタグも割り振れず、分類不能の状態のまま再生が続いていた。
マルタは目を閉じ、少しの間黙っていた。やがて、独り言のように言った。
「これ、たぶん──分類される前の音だね」
「分類される前?」
「現代の都市音響は、ほとんどが最初から意味づけられるようになってるでしょ? 発せられる前から、誰に対してどういうふうに届くか決められてる。聞こえるべき音。快適な波形。整った余韻。でもこれは──そういうフィルターにかけられる前に、どこかしかに引っかかってたものなの」
イオリは端末を操作し、音を切った。
〈オルト〉越しにも違和感は確かにあった。耳には届いているのに、身体のどこにも触れてこない。音がどこにあるのか、自分の内部感覚が判別を拒んでいるような印象。
「いまの音、都市では聞こえません」
「当たり前でしょ。都市のシステムがそう設計されてるもの。聞こえないものは、聞こえないように調律されてる。でも、残された音がちゃんと響くとは限らない」
「響く?」
イオリは、思わず言葉を返していた。
「身体が音に共鳴して、それに応答すること。反射とかじゃなくて、もっと、深い感触だね。響きっていうのは、単なる情報のやりとりじゃない。情動振幅でも、捉えきれない。もっと根源的な感覚」
彼女は言いながら、自分の胸に手を当てる。
「そういうのって、制度では扱いづらいから、だいたい切り捨てられる。でも、あたしにはそれしかないから」
イオリはしばらく黙っていた。彼女の境遇はなんとなく察していたが、それを言明するのは憚られた。
「あなたもわかっていると思うけど、あたしは耳が聞こえない。生まれつきよ。」マルタは、薄く笑って言った。「でも、音が嫌いだったことは一度もない。いまでも大切にしてるわ。こうして見ることによってね」
目元の補助インターフェースが微かに反射する。端末の音声出力と連動して、空間に線のような残光が浮かぶのが見えた。音の発生源、方向、波形のゆらぎ──それらが色の軌跡として視覚化されている。イオリは息をのんだ。それは機能を補うものというよりも、世界を別の知覚方法で再構成する装置のようにも思えた。
「あなた、音響関係の方ですか?」
マルタは短く笑った。
「それに似たような仕事よ。でも、もう辞めたわ。歳なのよ」
イオリは彼女の言葉を反芻した。似たような仕事──おそらく、彼女も一度は、制度の内部にいたのだ。
「自分の体が、音を押し返してる感覚があるんです。最近は特にひどくなりました」
その言葉は、半ば無意識にこぼれていた。数ヶ月前の事故いらい、音というものに身体的な戸惑いを覚えていた。
「それはお気の毒に──」とマルタ。「お仕事先の肩身も狭いでしょう。労災なんて起こされてしまったら」
「まぁ、そうですね。職場の空気は、確かに変わりました。でもそれ以上に、なんというか、自分の感覚が、どこにも接地しないっていうか」
「都市の耳は『沈黙』を正義にするから。誰かの快適は、誰かの沈黙で支える。それが都市の枠組みというものよ」
言葉に鋭さはなかった。だが、静かに突き刺すような響きだった。
「それでも、拾える音はある。音は波形のまま消えるわけじゃないのよ。残光みたいに、空間を漂うの。あたしはそれを、拾って読み上げていただけ」
マルタは窓の外を見た。
イオリも、ふと視線を追う。窓枠の向こうで、どこか遠くの枝が揺れていた。どんな音がしているのか、〈オルト〉は何も知らせてこない。
端末に目を落とす。データ記録されている。しかし、自分の身体が感じた音には乖離があるように思えた。
3
報告書への応答はいつも通りに事務的だった。提出から程なくして返信が届いた。記録された波形に異常なし。
異常なし──その記載にイオリは息を呑んだ。つまり局がサンプリングした音が、すでに都市音響台帳へ収集されていたということでもある。都市に散在する無数の〈オルト〉が、日常的に音響波形を収集し、中央で最適化される。
確かに音は記録されている。だが〈オルト〉は一切処理を返してこない。分類も補正も、何一つ。まるで、聞く必要がまったくないとでも言いたげに。
マルタの言っていることに従うと、制度の中での沈黙とは、規格内で管理され尽くした状態を指している。しかし、あの森の静寂は、何かが封じられたような、不自然な空白だった。
「カシマさん。ちょっと、よろしいですか」
イオリは執務室に隣接する個室を訪ねた。局内の誰もが顔を知っている設計部の古株──ジュン・カシマに話を聞くためだ。
「ん。イオリくんか、珍しいね。どうした?」彼は老眼鏡を額にあげ、にこりと優しい笑みを浮かべる。イオリに柔和な顧問役、という印象だ。
「この音、聴いてもらえませんか?」イオリは端末を差し出し、音響ログを再生する。
「不思議な音だね。倍音に色々な成分が混ざってる」カシマは〈オルト〉を外しながら呟いた。カシマはほとんど現場を回ってた。
「これ、〈オルト〉が反応しないんです。処理ログも残っていないんです」
「へぇ──」
「何か、知ってませんか?」
カシマは老眼鏡を掛け直し、滔々と語り出す。
「昔、似たのを見たことあるな。まだ制度がまとまる前の話だけどね。音響設計や都市計画では音の分類は大きな課題だったんだ。S/N、情動振幅、HAPとか色々な評価軸が複雑に絡み合っているわけだから。ただね、分類不能と称される音響はそもそも扱う前提に置かれていないんだ。ああいう音は、制度の中ではなかったことにされる。誰も分類できなかったからね。でもね、聞こえないからといって、意味がないとは限らない」
「まあ、そうでしょうね……」
「音ってのはね、空間のかすかな共鳴条件で、ふっと出たり、するりと引っ込んだりするんだ。感覚がそれを『音』として意味づける、ほんの手前の状態──たしか、誰かがそれを『ゆらぎの構造』って呼んでたよ」彼はふと思い出したように、目線を棚の奥へと向けた。「そのへん詳しかった建築家がいたんだよ──確か、クワハラという人だ。音のバリアフリーで有名な人でね」
クワハラ。
イオリの脳裏に、あの深いまなざしと、空間の沈黙がよみがえる。時間の糸が、再び手繰り寄せられるような感覚があった。
「その人、今も活動しているんですか?」
「さあね。僕と同年代だからもう引退してると思うよ。でも、ああいう人は、どこかで何かをやっているよ。それくらい精力的な人だったから」
カシマは懐かしそうに笑った。 イオリは小さく礼を言って、顧問室をあとにした。『再計測』の名目で、緩衝域への再訪申請を出すのは時間の問題だった。
申請はあっけないほどに通った。
請けた業務名と『緩衝域・再補正計測』の名目で提出された出張申請に、上層からの返答は「承認」とだけ記された定型の返信だった。そこに異議や関心の痕跡はなく、イオリはどこか拍子抜けしたような気持ちで、翌朝の荷物をまとめた。
再び丹沢へ向かう車内。見慣れたはずの景色が、今回は奇妙にくっきりと立ち上がってくる。記憶のなかで曖昧だった輪郭が、まるで誰かに呼ばれていたかのように、強く、光を返す。舗装の継ぎ目、路肩の湿った苔、風に吹かれた枝が音もなく動く様子──些細な変化のひとつひとつが、何かを語ろうとしているようだった。
携帯端末は、管理道に入ってしばらくしてから自動的に『現地集音モード』へと切り替わった。これはネットワーク非連携下での簡易測定プロトコルで、一定時間ごとに周辺音を圧縮して記録し、復帰後に逐次送信する形式をとっている。
しかし、そのログには、奇妙な一文が付加され続けていた。
> 音響信号:分類不能 波形規格外 解析保留
耳に届くのは、風が落ち葉を舐めるような音。遠くで鳥がひとつ鳴き、それが尾を引いて空間に溶けていく。だが〈オルト〉は、何も応答しなかった──まるで、存在そのものを否定するかのよう。
イオリは車を停め、端末を確認した。記録は継続中だが、解析欄には空白が続いていた。
何も反応しないというのは、何かがあるということではないか──そんな思考が、理屈の前に浮かんだ。
〈オルト〉を外す。 空間が深まったような気がした。
意識の外でも音はある。抑揚も、均質性も、意図もない。すべてが都市で聞き慣れた調律された環境音とは違っている。ただ存在するだけの音。だからこそ、制度はそれを意味なきものとして排除した。
だが、無意味だからといって、価値はないのだろうか?
ふとイオリの指先が震えた。身体のどこかで、かすかな反応が起きている。反射ではなく、もっと原始的な、気づきに近い反応。
〈オルト〉を通じた制御のなかでは、感じることのできなかった何かが、皮膚を通じて入り込んでくるような。
気づけば、足はあの建物へ向かう小径を進んでいた。意識では踏み出すつもりなどなかったのに、足が地面をとらえていた。音の輪郭が、身体の奥でひそかに共鳴していた。
前回の訪問から数日しか経っていないのに、その時の記憶よりも苔の色が濃く、階段の軋みが増している気がする。風が樹間を通るたび、空間全体が微かに震える。
建物の前に立つと、扉はすでに開かれていた。誰かを待ち構えているように、そんな静けさが漂っている。
そして、その静けさを切り裂くように、前回と同じ眼差しが扉の奥から現れた。
「また来ると思ってた。この前みたく、サンプリングじゃなさそうだね」
「制度について、お話を伺いたくきました。」
きっぱりとイオリは言う。
「そう。老人の話でよければ、聞かせてあげると」
マルタ・クワハラは扉の奥を指さした。イオリは黙ってうなずき、足を踏み入れる。
午後の日差しが、相変わらず斜めに室内を横切っていた。
マルタは棚から一枚の古い資料を引き抜き、イオリの前に置いた。ひどく劣化した透明フィルムに、びっしりと音波形と空間構成が描かれている。
「これ『ゼロ響』の協議資料。当時あたしが担当してた案件のひとつ。調査屋さんなら、『ゼロ響』って言葉くらいなら知ってるでしょ」
イオリは頷く。正式には『騒音・雑音ゼロにむけた都市音響設計ガイドライン』。現在につながる都市音響設計の黎明ともいえる、思想を記したガイドラインだ。〈都市音響設計・計画令〉が制定された今は廃止されている。
「でもね、中身はもっと徹底していたわ。感情を動かすような音をすべて排除する──つまり、情動振幅を必要としない都市をつくろうとしていたの」
彼女の声は穏やかだったが、その奥に何かを閉じ込めたような硬さがある。
「当時は、静けさが絶対の正義だった。幸福度は騒音ゼロに比例すると本気で信じられてたの。だから雑音も、生活音も、子どもの泣き声も──再現できない音はすべて異常。記録できないものは、最初からなかったことにされたの」
イオリはフィルムの端に走る手書きの注釈を追いながら、胸の奥に小さな引っかかりを覚えていた。
「あたしもその考えに同調していた。だって、音なんて、人にとってはあってもなくてもいいものだから」
「どういう意味ですか……」
イオリは訊ねた。マルタはふふんと、鼻を鳴らしたような音をだす。
「たとえば、あなたにはざわめきって音に聞こえるものでしょう。でもあたしには、それが光の粒になって、空間を漂って見えるのよ。粒の震えが速いほど、音がきつい。けれど、それは響きとは違う。インターフェースを通せば、音は視えるし、発声補助があれば言葉も伝わる。でも、それはあたしにとっての本当の聞こえ方じゃないし、話し方でもない」マルタはひとつ呼吸をおいた。「だから気づいたのよ。都市の配慮って、人の声を殺すのよ」
マルタは机の引き出しを開け、古びた端末を取り出した。角がすり減った四角い筐体。画面のセンサーも反応が鈍い。
「制度が成熟するほど、余白は許されなくなっていった。たとえば、サウンド・スロット。音の死骸を逃がすための建築的な余白。響きが消える寸前のゆらぎを留めておく、そんな構造だった。壁の裏に小さな空洞を仕込んだり、床面に響きを散らす格子を敷いたりね。音がすこし揺らぐことで、空間に生きた気配を残すための工夫だった」
端末の画面に、かつての建築構造図が浮かび上がる。共鳴孔の仕込まれた壁、反響板の並ぶ天井、そして吸音格子が敷かれた床。今では失われた機能の痕跡だ。
「あたしたちは、聞こえない音を、聞かなくていい音に分類した。でも、そうやって棄てていったものの中に、誰かにとって大事な響きがあったかもしれない」
「響かないまま、終わった音たち……」
イオリは、〈オルト〉が無反応を返した記録音のことを思い出す。音はあったのに、反応しない。それは、制度にとって無価値とされた証だった。
「ついてきて」
マルタはそう言うと、奥の部屋へとイオリを導いた。重い扉を押し開けると、そこはかつての実験室だった。
壁一面に広がる振動レリーフ。点字のような微細な突起が、触れるとかすかに音を伝えてくる。中央には台座のような装置が置かれ、かつて〈オルト〉の先行機として試作された補助デバイスが並んでいる。
「再生空間ってあたしは呼んでる」とマルタは言った。「ここには、制度に拾われなかった音の断片が保存されてる。音の死骸って、あたしは呼んでるけど。建築空間の奥に、制度が扱えなかった音が封じ込められてるの。反射しきれなかった残響や、誰にも分類されなかった音波の名残──本来なら、都市の中で静かに消えていくはずだった響きたち」
イオリは台座に近づき、ひとつの装置に手を伸ばした。ふれると、わずかに空気が震え、何かが耳ではない感覚として伝わってくる。鼓膜ではなく、皮膚や骨で受け止めるような微細な響き。耳の奥ではなく、背筋の中心をなぞるようにして伝わってきた。冷然と、そこに何かがいたということだけが残されるようだった。
マルタは続ける。
「そういえば、前に訊いた問い、まだ答えを聞いてなかった。聴くって、あなたにとっては何?」
イオリは、言葉を見つけられなかった。ただ、手のひらに触れてくるかすかな震えを、皮膚の奥で感じていた。それは旋律でも言語でもない。しかし確かに、何かがここにいると伝えていた。
その夜。イオリは自宅の簡易モニターに端末を接続し、昼間の記録音を再生していた。断層域で収集された、いわゆる〈非準拠波形〉の一群だ。
波形は視覚化され、ディスプレイ上に不規則な軌跡を描く。音量も周波数も分類不能。だがそこには、確かに、音があった。どこかで発せられ、何かに触れ、失われた痕跡。
しかし〈オルト〉は反応しなかった。解析も補正も進まず、『判定不能』とだけ返される。意味は与えられず、音は存在しているにもかかわらず、無視された。
イオリは胸に手を当てる。そこにあったのは微かな不安。そして、それを上回る──制度に分類されない何かへの親和感だった。
音は、聞こえることだけが存在の証ではない。何も返されない音の中に、自分は何を感じていたのか。あるいは──感じたと、錯覚していたのか。
マルタは言っていた。
「音を視ることで残されたものを拾っている。でも、拾ったからって、それでいいとは思っていない」
その言葉の意味が、今になってゆっくりと沈んでくる。
どれだけ精密に設計された都市であっても、規格に収まらない音はある。断層域の記録音は、その存在を証明していた。そしてそれは、〈オルト〉にも制度にも語りかけていない。ただ、そこに在るだけだった。
イオリは一度、再生を止めた。そして改めて、最初のファイルを呼び出す。今度は〈オルト〉を通さず、スピーカーで直接流す。
部屋に、形を持たない音が満ちていく。感情にも触れず、意味も与えない。ただの気配。痕跡。響かないのではない。響かせる器が、最初から存在しなかったのだ。
──それは、制度下の調律とは異なる、まったく別の設計の始まりだった。
イオリはふと、ひとつの言葉を思い浮かべる。
再生空間。
制度に棄てられた音たちを、もう一度響かせるための場所。
それはまだ構想にすらなっていない、ただの予感だった。けれど確かに、イオリの中には芽吹きつつあった。 川崎市の南部。東京都との県境にかかる丸子橋の下で、今朝、異常な波形が記録された。
4
報告を受けてカドワキが現地調査に向かうことになり、たまたま空いていたイオリも同行を求められた。
でこぼこの河川敷には、朝方の冷え込みがまだ残っている。鉄骨のアーチは、上を通る車の音を吸い込みながら、橋脚のあいだから静かに響きを返していた。都市の中心部では聞こえないはずのノイズ──鉄の軋み、水の流れ、遠くの犬の声。都市の音響制御から零れ落ちた音が、ここにはあった。
やがて橋脚の陰から、二人の若者が現れる。
年の頃は二十歳前後。どちらも長いフード付きの上着に、ゆるいワイドパンツ。首元には、無造作に外された〈オルト〉がぶら下がっていた。都市のルールから、あえてはみ出すような格好。音のある場所で生きていることを、まるで主張しているようだった。
「お兄さんたち、何してんの?」
片方がそう訊いてくる。怯えた様子はまるでない。挑発とも違う、ただ当然のような口調。
「調査です」とイオリが静かに応じる。
「ふーん。じゃあ音響屋さんなんだ」と、もう一人が薄くせせら笑う。
カドワキの表情が強張る。
「だからどうした」
「じゃあ、聴いてみてよ。俺の音。今日は、出来がいいんだ」
そう言って青年は、腰に付けたウェアラブル・スピーカーの音量を上げた。
轟音。金属が引き裂かれ、歪んだ電子音が空間を満たす。ビートなのか、断続的な衝撃なのか。秩序も主張もない。だが、音がいる。それだけが確かだった。
イオリとカドワキは咄嗟に、〈オルト〉でその波形を不快音に登録した。音は、まるで吸い込まれるようにその場から消える。
「迷惑行為で通報されなかっただけ、ありがたいと思えよ」
カドワキが怒気を含んだ声で言う。
「つまんねーの。せっかくイケてる音がサンプリングできたってのに」
「どうせわかんねぇよ、大人には──なあ。『再生空間』って知ってる?」
その言葉に、イオリは息を呑んだ。再生空間という言葉が、まさか彼らの口から出るとは。
「その言葉、どこで聞いた?」とイオリが訊ねると、青年たちは肩をすくめた。
「誰かがネットで流したんだよ。今の街じゃ聞けないような音があってさ。意味とか関係なくて、でもカッコいいと思えた。だから真似してみたの」
一人が端末を取り出して動画を見せる。画面には、夜の高架下で何かを再生している人物の姿。マルタではない。だが、スピーカーから流れたその音は、あのとき確かに耳にしたものだった。
制度には分類できない、けれど生きた響き。
──それが、かたちを変えて、拡散されていた。
動画の中の人物は言葉も残していない。ただ短いサンプルを流し、画面の揺れと共に消えていく。それを誰かが録音し、また誰かが再構成し、そして、今目の前の彼らが「真似した」音を響かせている。
音が音を呼び、制度の縁に沿って育っていく。
「で、これをやって、何を得るつもりなんだ」
カドワキが一歩前に出る。
「再生して、響かせる。それだけだよ」
青年は答えた。
「なんでそんなことする?」
カドワキの問う声は鋭く、半ば怒気を含んでいた。
青年は、少しだけ口元を歪めた。照れたようにも、挑むようにも見える。
「だってさ。静かすぎて、つまんねえだろ。この街」
その一言に、カドワキの語気がさらに強まる。
「それで事故が起きたらどうする? 誰かがめまいを起こして転倒したら、お前らに責任が取れるのか。この社会は静かであることを前提に動いてるんだ」
「俺らは怪我させたいわけじゃない」
「ならやめろよ。その音が誰かの行動を狂わせるんだよ!」
「おい、カドワキ!」
イオリが抑えようと声をかけるが、それより先に、もう一人の青年が低く呟いた。
「──でもさ、黙ってるだけで異常者扱いされんの、こっちなんだよ」
その声は怒鳴りでもなく、弁明でもなかった。ただ、吐き捨てるように、日常の一部のように続いた。
「静かにしろって言われて、我慢して──でも生きてるだけで、異常だって言われる。だったら、叫んだほうがマシだろ」
イオリは、口をつぐんだ。制度が描いた「静けさ」の中で、ただ生きていることが過剰とされる。その矛盾に、言葉は出てこなかった。〈オルト〉に、今の音が記録されるのがわかる。分類コードと波形が即座に送信され、不快音として処理されていく。それは、制度の当然の働きだ。けれど──その「当然」が、彼らの存在ごと排除するのだ。
カドワキが舌打ちをする。
「……とにかく、これは都市機能への干渉だ。見逃すわけにはいかない。カミザト、通報するぞ」
イオリは、一瞬だけ迷い、短く頷いた。すでに〈オルト〉は音源の記録を完了していた。通知ひとつで、制度の観測が公式化される。イオリは端末を操作しながら、どこか遠くに自分が置き去りにされている感覚を覚えていた。
彼らは都市の音から落ちこぼれたわけじゃない。ただ、そこにいようとしただけなのだ。
吹き抜ける風の中で、最後まで青年たちは何も言わなかった。垂れ流された音の残響だけが、彼らがここにいたことを告げていた。
音響保全局・本庁舎、地下フロアにあるモニタリング室は、昼間でも薄暗い。壁一面のサウンドマップと、中央に設けられた会議卓には、複数の波形が立体的に投影されていた。
シエナ・モリオカが前列に立ち、胸元に資料端末を抱えながら淡々と報告を始める。
「過去一ヶ月で、都市域内における聴覚系事故は、平時の約三倍に増加しています。一過性の眩暈、吐き気、感覚過敏系の症状が主な症状で、すでに数十件が医療機関に報告されています」
スクリーンには、居住区と商業区をまたぐような範囲に、赤い波形が映し出されていた。そのいくつかは、周囲と色調と微妙に異なり、グラデーションになっている。制度に属する波形が青白く整っているのに対し、それはまるで傷口のように滲み、地図の上に染みを広げていた。まるで抽象画に見えた。イオリはそう思ったが、口には出さなかった。
「特筆すべきは、原因波形が、既存の登録波形と一致しない点です。制度上、許可された振幅域に該当しない。すなわち、非準拠波形です」
室内がわずかにざわつく。
「断層域で拾われた記録と近い構造の波形が、市内の各所で散見されています。ただし再生者──つまり都市内部でこれを流した人物の特定には至っていません」
その言葉に、向かいの席の課長が眉間を寄せ、低く吐き捨てる。
「つまり誰かが、勝手に異音をばら撒いていると」
「そのように解釈できます。通報されたケースもありますが、多くは目撃情報が断片的で、再生装置の所在も特定できていません。波形自体も一様ではなく、複数の発信源が存在していると見られます」
カドワキが身を乗り出し、中央に表示された波形を指差す。
「注目すべきはここです。いくつかの波形には、明確に情動振幅が含まれている。たまたまではありません。どの発信源のものも、感情に作用する設計が意図されている」
「感情に作用? ただのノイズじゃないのか?」
課長が小さく眉を吊り上げた。
「むしろ逆です。ランダムに見せかけながら、特定のパターンが繰り返し出現している。つまり、これは誰かが何らかの目的をもって設計した音です」
カドワキが推察すると、室内には一拍の静寂が落ちた。波形の光だけがかすかに明滅し、空気が冷たく収縮していくようだった。
イオリは、目の前の波形が再生された記録であることを知っていた。あの音を、どこかで聴いた。あるいは似たものを、知っている。けれど、会議の場で口にするにはその行為があまりにもただの騒音として扱われすぎていた。
口を開きかけたイオリに、モリオカが先んじて問いかけた。
「カミザト技師。あなたは非準拠波形を調査していますね。緩衝帯で回収された音源と、市内で観測された波形特性の共通点はありますか?」
一瞬、間があいた。イオリは姿勢を正し、波形と地図の投影を見比べながら答える。
「構造は一部近似しています。ただ、完全一致は確認できていません。けれど……おそらく、あえて似せて再構成されたものです。つまり、模倣だと考えられます」
「模倣犯、ということでしょうか?」
モリオカが重ねて尋ねる。
イオリは小さく頷いた。
「はい。ただし、いたずらや暴発的な行動というより──意志的です。少なくとも、誰かに届けるつもりで流されている」
課長が、机の上のペンを指で弾くようにして呟いた。
「誰が? 何のために、そんなことを?」
すぐには答えなかったイオリが、少し目を伏せ、呼吸を整えてから口を開く。
「仮説ですが──目的は感情を揺さぶることです。制度の外から、誰かに届くことを期待して。意味として分類されない響きとして。あるいは誰かの記憶かもしれない」
制度に認識されるよりも前に、聴かれ、残る何か。考えれば考えるほどあの音たちは、ただの騒音ではない。
会議室に、再び奇妙な静けさが満ちる。誰も言葉を続けようとしなかった。そのなかで、モリオカだけが資料端末に視線を落としたまま、ぽつりと呟いた。
「制度は、音を記録する。でも……意味を与えるのは、常に後手になる」
イオリは、その言葉を受け止めていた。
マルタが残した響きが、制度を通り抜けて、今、誰かの手に届いている。その現実が、初めて立体的な影をもって、目の前に姿を現していた。
会議が終わり、空調の止まった会議室には奇妙な落ち着きが満ちていた。課長が誰にも目を合わせずに資料をまとめ、カドワキはタブレットに結果を転送して退出のタイミングを見計らっている。イオリも同じように資料をまとめ帰り支度をしていた。
「カミザトさん。あなた、緩衝域で誰かに会ってましたね」
モリオカは、イオリの元に寄り静かにそう言った。
「──なぜ、そう思うんですか」
「さっきの話し方。いつものあなたなら、もっとドライに話してたはず。響きとか、記憶とか、あんなに曖昧な表現はしなかった」
イオリは視線を落とす。曖昧な表現──異音の出どころをはぐらかしたこと、とモリオカは指しているのだろう。報告として成立させた筈だ。が、恣意的に余白を持たせたのも自覚的だ。
「変わったのね。少しだけ」
モリオカはそれ以上、詮索しなかった。
「私は制度の外で生きる人を否定はしない。でもね、制度の内にいる人間が何を背負っているのか、わかっていますね」
それは怒りでも諫めでもなく、ただ静かな忠告だった。彼女が扉へと向かって歩き出す。その背中に、イオリは何も言えなかった。
イオリはホログラムのデータログを閉じ、自室の椅子の背に身を預けた。
都市音響台帳が〈芸術的ノイズ〉と分類した波形は、活用されることも、排除することもないまま、ただ一つのログとして架蔵されていた。『創造的試行』という分類タグが新設され、その波形は静寂の裏側へ、まるで展示物のように吊り下げられていた。制度にとって、それはもはや異常ではなかった。
記録はされる。しかしそれは、誰にも聴かれず、誰の感情にも触れない、響きのない記録にすぎない。
「……これが、聴かれない音か」
モニターに映し出された波形は、美しかった。
最初の事件から半年が経っていた。騒動が顕在化してからしばらく、市内の音響調査会社は、痕跡に含まれる情動振幅を解析することに業務を集中させた。そこに浮かび上がったのは、かつての都市生活に根ざした古い音響文化の断片だった。それが過去の文化的反映と見なされるやいなや、事態は制度のもとで整理され、自然と沈静化していった。若者たちによる芸術的テロは、社会に大きな混乱をもたらすこともなく、制度の側に新しい試みとして取り込まれていた。彼らの行為の痕跡も、制度の記録装置に回収されていった。反体制運動としてではなく、創作の一形態として。
それ以降、台帳は、『非準拠』とは判断することはなかった。むしろ過去の文化的反映として捉えて、記録の一部に組み込んだ。
つまり、すべては制度の内側に完結された。丸めこまれたと言ってもいい。
イオリは深く考えていた。この処理は、一体なんだったのか。受容か、それとも封殺か。
実際、その答えはなかった。ただ記録だけが残され、意味は誰の手にも届かなかった。この処理に判定の基準があって、それを作ったものがいるとしたら、この道具の使い手たる存在だろう。つまり僕たち。
再生行為の目的が制度への異議申し立てだとしたら、その手段は制度の枠組みに取りこまれない構造を持たねばならない。
だが、観測されたあらゆる逸脱がアートとして処理されるこの都市では、何を響かせることができるだろうか。
再生空間もメディアを通じて一般的な用語と化した。意味を剥がされない音を作る場所、誰かに届く可能性を失わない場所──という意味で。それは、都市の沈黙に抗するというより、制度が拾い上げなかった意味をもう一度問うための発想だった。
イオリはふと思い立ち、丸子橋へ足を運んだ。理由らしい理由はなく。ほぼきまぐれのようなものだった。
橋の下には、見覚えのある若者たちがいた。黒いスピーカー、古びた再生機器、MDプレイヤーや旧式のノートパソコン──彼らはそうした装置を並べて、何十年も前の都市の音を再生していた。
「何、流してんの?」
イオリの問いに、人懐っこそうな最年少の青年が答える。
「一九八〇年代にあった地下鉄の環境音っす。それとこれは、トタンだっけ? その屋根に雨粒が落ちる音。今じゃこういうのも聞くことができないんすよ。建材の素材が変わってるから」
「どうして、そんな昔の音を?」
彼らは、かつて響いていた音を掘り起こし、もう一度その場に流すことで、そこにあったはずの気配や記憶を呼び戻そうとしていた。その行為は違法ではない。ただ、今のところは制度の監視下にある。それがすべてだった。
「どうしてでしょうね。気持ちいいから? まぁ別に理解してほしいとか、そういうのじゃないんす。でも、なんだか懐かしいんですよ。自分が生まれるずっと前のくせに」
そう言って、青年は少し照れたように笑った。
青年の答えにイオリは素直に驚き、あることに気が付く。制度はなぜ再生したかを問う。要は理由を求められる。だが彼らの行為には、問いの枠組みそのものが存在しない。ただ鳴らしたい音があり、響かせたい空間がある。
その衝動は制度のどこにも分類されない。記録できないまま、誰かの中にだけ残る。
響きを残すことは、記録ではない。
誰かに聴かれること、継がれることを信じる行為だ。
制度が記録しながらも意味を奪うのだとすれば、響きとはむしろ、意味の芽生えにほかならない。
音が響き、響きが記憶を生み、記憶が継承を促す。
それは、誰かの記憶に、空気のふるえとしてだけ残るものだ。
制度のなかに残されるものとは別に、本当に残るものがあるとすれば、それは──。
5
マルタの住居を訪れるのはこれで三度目になる。けれど、その扉を開くたび、イオリは自分の感覚がどこか遠くへ引き伸ばされていくのを如実に感じとっていた。遮音素材に囲まれた都市の空間では決して届かなかった生活音のざわつき。設計には想定されることのない空気のゆらぎ。それらが微細な震えの束となって彼の皮膚をなでる。
彼女は作業台の前に座っていた。手の中で、細い配線を束ねたようなものをいじっている。それは古い補助機器か、それとも音を視るためのインターフェースか。あるいは形状からして〈蓄音機〉と呼ばれていた原始的な音声再生装置かもしれない。イオリが声をかけると、彼女は顔をあげ、少し意外そうに、それでも柔らかく笑った。
「久しぶり。また、来たのね」
「夜遅くにすみません。今度は、ちゃんと話をしに来ました」
マルタは作業を止めることなく、軽く頷いた。
「なにかあった?」
イオリは部屋の中央にある椅子へと歩き、静かに腰を下ろした。少し間をおいてから、言葉を選びながら口を開く。
「川崎と横浜で、若者たちによる騒音撒布事件が多発しました。この数ヶ月はどちらかというと警察に転職したような気分です」
「ふぅん。そんな騒動が──」
「でも、もう落ち着きました。なし崩し的に。台帳が、あれを文化的試行として受け入れたんです」
「大事にならないんだったらよかったじゃない」
「本題はここからです」イオリははっきり言う。「音を作る彼らは、これを〈再生空間〉と呼んでいました。マルタさん、あなたが仕組んだことなんですか」
「知らないわ」マルタは、小さく息をついてから続けた。「けど、きっと響いたんでしょうね、どこかで」
イオリは少しだけ眉を顰めた。これ以上しつこく追及したところで、同じ調子ではぐらかされるだけだ。そう思いつつも彼の声には切実さが滲む。
「あの行為はそれは到底、許されることではありません。制度に従って僕らは静けさを維持している。相応の恩恵も享受しています。サウンドスケープの秩序を打ち壊す挑戦ともいえるでしょう」
「それでも──あなたは戸惑った。そうでしょう?」
マルタの断言に、イオリは言い返す代わりに問いかける。とぼけるような調子で、
「どうしてそう思うんですか」
「だって、あなたの声、濃い緑色をしてるから」
しばしの沈黙ののち、イオリは天井を仰ぐ。
「そうですね──たしかに釈然としない気持ちはありました。彼らに理不尽を押し付けたようで。ただ、響かせたいだけなのに。音が届くということを信じただけのことなのに」
マルタは目を伏せたまま、黙って耳をかたむけている。イオリは言葉を続けた。
「ゼロ響以降、音響制度は、音そのものを制御しようとしてきた。でも、思うんです。制度は、音が意味を持たないように設計されていたのではないかと」
マルタの手がふと止まった。彼女の視線は窓の外へと向けられている。揺れる木々のざわめきが、うっすらと室内に入り込んでいた。
「ええ」マルタは、ため息のように呟いた。「記録はする。でも意味には触れない。そう設計されたの。意味の暴走を、社会が怖れていたから」
「意味の、暴走」
マルタは頷き、一拍の沈黙を置いて言う。
「誰かの言葉が強すぎると、それが正義になってしまうでしょう。社会はそれを怖れたのよ。だから、すべてを記録し、意味づけは保留する。判断は未来に委ねるって、そういう都市の在り方を選んだの。安心の名のもとに」
「それを、あなたも受け入れた?」
「もちろん。あたしも『作る側』にいたから。でもね、分類しようとする人は、どこにでも、いつの時代にもいる。静けさだけが正しさになっていったのは、そういう人たちのせいよ」
マルタの声には、罪の意識ではなく、過去を見つめる者だけが持つ確かな距離感があった。
「マルタさん。すべての音を、管理できますか?」
「まさか、できるわけないじゃない」彼女は首を振り、目元に笑みを浮かべる。「それでも、できると信じたがる人は、今でも多い。あなたも──きっとその一人だったのよ」
イオリ床に置かれた一枚の薄い振動パネルを見つめた。そこには、ごく小さな波形で誰かの声が封じられている。届かなかった音、意味を与えられなかった記憶。
「教えてください。あなたが作る〈再生空間〉はなんのためにあるんですか? 音そのものを遺すことですか」
「ええ。でも、もっと大事なのは思い出させること」迷いなくマルタは言った。「かつて響いたことがある、確かに生きていた音があったってことを。それを身体に通したいの。そ供養に、近いのかもしれないわね」
イオリはそっと頷いた。その頷きは、同意というよりも、自身の迷いをそっと形にするような動作だった。
すると、唐突にマルタは立ち上がった。
「ここまでは車で来てるんでしょ。イオリさん」
「えぇ、まあ」不意をつかれたイオリは、やや面食らう。こればかりは彼女の意図は読めない。
「出してくれるかしら。行きたいところがあるの」
目的地までは一時間ほど。川崎駅まで下るらしい。エンジンをかけたあと、走り出す前に、マルタがぽつりとつぶやいた。
「悪いけど、この音を流してくれるかい?」
そう言って差し出したのは一枚の古びた記録メディアだった。
イオリはうなずき、操作パネルを開いて指定されたデータファイルを選ぶ。車はイオリが所有している型落ちのバン──内装は簡素で、スピーカーも〈オルト〉準拠の標準型。個人最適化まではされていないぶん、こうした汎用音源を流すにはちょうどよかった。
音が流れ出す。旋律もリズムもない。ただ一つの音が、時間のなかで少しずつかたちを変えるドローンになって車内に満ちていった。それは微細なさざなみに似ていた。そして、どこかで触れたことのある、高音域のひっかかりが、まるで誰かの小さな喃語のようにも感じられた。
「これは、情動振幅ですか?」
助手席のマルタに問いかけると、彼女は静かにうなずいた。
「そう。専門的に言えば親和帯域だ。あたしには十分だけど、あなたからすれば、音楽とは言えないだろう?」
確かにそうだ。どこまでも単純で、どこまでも情緒的だった。意味のない情報の連なりに過ぎないのに、妙に身体に染み込んでくる。耳で聞くというより、皮膚で触れるような音だった。
「親和というのは、マルタさんにとっての、ですか?」
それから無音の時間ができたのをイオリは反省した。悪気はなかったが深入りしすぎたかもしれない。
マルタがふと口をひらく。
「昔ね、娘が小さかった頃、仕事に行くあたしよりも先に起きてきて──朝ごはんを食べながら、よく話しかけてきたんだ。意味なんかない、ただのことば。でも、それが一日でいちばんの幸せだったよ」
イオリは静かに視線を落としながら、問いを挟む。
「では、この音、娘さんの声を?」
「そう。わたしの〈オルト〉が拾った波形から抽出してもらったんだ。建築事務所で働いていた頃でね。朝、娘と過ごせるのはほんの数分しかなかったから、その声を、会社に向かう車の中で流すようにしたのさ。いつの間にかそれが習慣になってた」
山から降りた最初の信号が青に変わり、イオリはアクセルを踏み出す。車は静かに再加速した。道路は滑らかに制御され、夜にもかかわらず都市の眠りが音もなく深まっていく。
「娘さんは、今は?」
「独立して、地方の設計事務所に勤めてるらしいよ。連絡はあまり取ってないけどね。夫が亡くなって、秦野の家を手放したときも、特に引き留めることはなかった」 イオリは黙って頷いた。やがて、ゆっくりと口を開く。
「マルタさんには、その音、聞こえてるんですか?」
マルタはほんの少しだけ口角を上げた。
「まさか。完全には、聞こえてないよ。補助インターフェースを通して、輪郭だけを感じてる。それでも、十分なんだ。聴くって行為には、必ずしも聴こえることが要るわけじゃないからね」
しばらくの沈黙ののち、イオリは尋ねた。
「では、その音はどんな色をしてますか?」
その問いに、マルタは小さく笑って、助手席の窓の外を見た。まだ陽は高くない。雲の切れ間から朝の光がわずかに射している。
「ふふ、なんだか恥ずかしいねぇ」
「無理して言わなくてもいいんですよ」
「いや、いいんだ──とにかく言葉にしきれないくらいに美しいんだ。何かに例えるしかできないけど、そうだね、朝焼けの暖色。夏の終わりの、ちょっと冷たい空気を照らす、あの光に似てる気がする」
イオリは、その言葉の意味を咀嚼するように頷いた。
音が自然にフェードアウトする頃、車は駅前のロータリーに差しかかっていた。高層複合施設のガラス面が夜の街灯を受けて、ゆるやかに光っている。
「あそこさ」とマルタは指をさす。「あたしがこの街にあげた唯一の作品さ」
ホールのエントランスに立ったとき、イオリは足元に微かな響きを感じた。
それは聴覚に触れるものではなかった。床材のわずかな弾力、空気の粒の揺れ、肩先に寄せてくる湿度。都市の多くの建築が響きを消すように設計されているのに対し、ここにはまだ響きの痕跡が残っていた。
まっすぐ伸びる通路を進みながら、イオリは壁面に手を添えた。表面はなめらかで均質だが、内側には吸音ではなく、あえて『反響』を抱き込むための空隙が組み込まれていることを彼は知っていた。
通路の先、ゆるやかに開かれた扉を抜けると、客席と舞台を内包したホール空間が広がっている。音を吸い取らず、過不足なく留めるために調整された天井の高さ。装飾のない壁面の角度。むきだしの梁が生む微かな振動。すべてが『響きを消さない』ために設計されている。
マルタ・クワハラが設計した建物は、川崎市内にたった一つだけ存在する。駅のターミナルと直結した再開発区域の複合ホール。駅から直通の連絡通路を抜けると、吹き抜けのアトリウムに導かれ、ガラス越しに舞台袖の天井が垣間見える。
公共性と快適性を求められた建築計画のなかで、マルタがただ一つ貫いた設計理念──音が逃げず、誰かの身体に留まる構造──それがこのホールには宿っていた。
開館から十年。今では多目的ホールとして演説や式典に使われることも増え、当初の用途は次第に薄れている。それでも、イオリは知っていた。ここにだけは、都市の沈黙が完全に入り込んではいない。
「あなたにとって小旅行って感じですか。ここまでの道のりは」
イオリは客席から舞台上にいるマルタに問いかける。
「どうでしょう。むしろ過酷な道のりだったかしら」とマルタは自身の首や肩を揉むような動作を見せる。「身体のあちこちが痛い。この歳になると、どこもかしこもおかしくなるものだから」
「あはは、気持ちはわかります」とイオリは返す。「僕が言っては烏滸がましいですが。人の身体の複雑さって、どこかがおかしくになってから初めて気が付くものなんですね」
〈オルト〉を外してみせる。その瞬間、さまざまな音が鼓膜へ流入し、思わず身体が強張った。彼の聴覚過敏は悪化していた。今となっては一年前の事故から兆候が出ていたかもしれないし、常日頃の音響調査のせいかもしれない。
「やっぱり、すこしキツイ……」
イオリが苦笑すると、マルタは小さく頷いた。
「無理しなくていいのよ。でもね──これまでのあなただったら、外そうとなんて思わなかったでしょう」
その言葉には、責めるような響きはなかった。ただ静かに、過去を手渡すことを促すような口調だった。
「ええ。でも、あのときの僕は確かめたかっただけなんです。いまは──」イオリは小さく息を吐いた。「違う気がするんです」
ホールの奥へと歩みを進め、舞台の縁に立つ。客席には誰もいない。ただ、天井からわずかに降りる照明が、緩やかに彼の影をつくっていた。
「ここ、残ってますね。響きが。波形は録れないと思いますが、確かに……いる感じがする」
「それも、時間が経てば消えるわ」マルタは、ゆっくりと返す。「人がいなくなれば、音はただの空気のゆらぎになる。忘れられれば意味を失うのよ」
イオリは静かに頷いた。
「だから、記録したいと思ったんです。でも、音響制度にある記録とは違うやり方で」
「ふうん」とマルタ。「どういうやり方?」
「地図を作ろうと思っています。音の地図を」
イオリの声は小さかったが、その響きにははっきりとした輪郭があった。
「制度は、音を分類します。タグをつけて、価値を与えて、保存して、管理する。でも、僕が拾いたいのは、もっと──逸れてしまったもので。たとえば、若い人たちが再生した無許可の音や、誰かの囁き、風に消えた歌──そんなものの記録です」
「不思議な言葉つかいね。地図って、場所を示すものでしょうに」
「ええ。音が響いた場所を、響きのままに残したいんです。録音じゃなくて、記憶の地図として」
少しのあいだ、マルタは何も言わなかった。が、やがてふっと笑い、小さく首を振った。
「それこそ、芸術って呼ばれるものじゃない」
「僕は、それを供養と呼びたいです」イオリは視線を落とした。「制度の静けさのなかで消えたものが多すぎる。響かない都市で、それでも誰かが音を出そうとしていた。──その痕跡だけでも、残せるなら」
マルタは立ち上がり、舞台の袖へと向かって歩き出す。その背中に、イオリが声をかける。
「マルタさん」
「なに?」
「僕の聴能、ずれてますか?」
マルタは立ち止まり、こちらを振り返らずに言った。
「ええ。狂ってきたわ。でも、それでいいのかもしれない」
その言葉は、まるで祝福のようにも聞こえた。
ホールは残響がごくわずかに漂っている。言葉にはならない低い周波が、床を這い、壁を反射しながら、イオリの胸の奥まで触れていた。〈オルト〉では捉えきれない微細な震えだった。
6
その朝、風は柔らかく、丹沢の山肌には淡く霧が掛かっていた。
小屋の周囲には、道具を整えているイオリの他には誰一人いないが、遠くから控えめな気配が近づいてくるのがわかった。音よりも先に届く気配──それは静かな山で暮らすうちに自然と身についた知覚だった。
現れたのは、若い訪問者だった。防音パーカーのフードを背に落とし、耳元にはヘッドホン型の〈オルト〉がやたら目立つ。
少し迷ったように立ち止まってから、彼は礼儀正しく頭を下げた。
「こんにちは、突然すみません。こちらって、〈音の地図〉を作っているカミザトさんのところで合ってますか?」
イオリは道具を置いて立ち上がり、ゆっくりと若者を見た。十代後半か、せいぜい二十代前半だろう。警戒心はなく、ただ自分の足でここまで来たという確かな自負が感じられた。
「ようこそ。ええ、僕がカミザトです。地図ならここで細々と描いていますよ。下界から来たのかな?」
「はい。自分、大学で音響生態学を専攻しています。教授からカミザトさんのことを聞いて、ネットでも調べて。それで、どうしても来たくて──」
「焦らなくていい。山の空気は慌てて喋ると咳き込んでしまう」
イオリは微笑んで、彼に小屋の扉を開けて靴を脱ぐよう促した。
小屋の中はひっそりと静かだった。風の入り口を絞った設計で、外の音が柔らかく滲み込んでくる。壁には紙とホログラム、古びた建築図面が重なり合うように貼られ、奇妙な地図群を成していた。
若者はそれらを目にし、思わず小さく息を呑んだ。
「これ、全部〈音の地図〉ですか?」
「もちろん。全部、制度が拾えなかった、音があったかもしれない場所をまとめた記録です」
「でも、再現じゃだめなんですか? 都市音響台帳のログを追うとかで」
イオリは棚から一枚の古びた紙図面を取り出した。表紙には『川崎港湾地域 音響記録図』とあり、タイトルの下には赤字で『未収録波形あり』と記されていた。
「都市は確かに音を保存する。でも、記憶はしない──波形や位置、発話主は残せても、その場にあった意味までは拾えない。〈オルト〉は完璧だからこそ、意味にならないものを全部切り捨ててしまうんです」
若者は、しばし沈黙してから、ゆっくりと頷いた。
「ひとつ聞いてもいいですか。カミザトさんは、どうしてこんな場所に住んでいるんですか?」
「こんな辺鄙なところに、って?」
学生は慌てて否定したがイオリは冗談だよ、と軽く笑って目を伏せた。懐かしさと、少しの寂しさを孕んだ響きだった。
「譲ってもらったんだ。マルタ・クワハラという方から。知ってるかな?」
若者は首を横に振って、申し訳なさそうに頭を下げた。
「すみません、不勉強で」
「そうか。君たちの世代では、君たちの世代には、もう名前だけの存在かもな──彼女はすごい人でした。頑固で、繊細で、ときどき不器用で──でも、誰よりも『響き』を信じていた人です」
イオリはふと、窓の外に目をやった。
「彼女は再生空間という概念を提唱しました。失われた音を選び、解放する空間。制度が排除した意味のある響きを、もう一度外に出すための場所です」
「それ、知ってます。都市の一部で広がってる、あの音響アートのムーブメントですよね」
「今は、そう解釈するんだ──ええ、その再生空間の基礎を作ったのが彼女です」
若者は真剣な眼差しで頷いた。
「その音の地図、もう少し見ていてもいいですか?」
「もちろん。ただ、見るだけじゃわからないことも多いですよ。ちょうどこれから、サンプリングへ行く予定があります。一緒に来てみませんか。ほんの少しですが、耳を澄ます練習になります」
「行きたいです」
イオリは穏やかな笑みを浮かべて立ち上がった。
「じゃあ、準備しましょう。都市の静けさって、見かけよりずっと複雑だから。少しだけ、それを見に行こうか」
地図を一巻き、バッグに入れた。録音機材は昔ながらの小型リニアPCMレコーダーを持参している。音を拾うつもりはない。ただ、鳴ろうとしていた兆しだけを、観測するため。
昼過ぎ、イオリと学生は港湾地帯に降り立った。ここは音響制御の精度がもっとも高いとされる区画で、工場と交通帯が密接しているにもかかわらず、不快音相関は常に最小値を保っている。
「なんというか……耳の奥が閉じてる感じがします」と学生が言った。
イオリはうなずいた。「音が届かないんじゃない。届く前に削られているんだ」
街路樹の葉が風で翻っているのに、ざわめきが伴わない。歩道を人が行き交うのに、靴音が地面に落ちない。視覚と聴覚が分離されているような強烈な違和感。しかし、それに気づく人は少ない。
イオリは一本の橋の下を指さした。スピーカーの痕跡が残る古い構造物。今では制御網に組み込まれ、個別の音声出力は廃されている。
「昔はね、ここで天気予報が流れてた。毎朝、決まった時間に同じ声で」
「では、今は?」
「何も流れないことが、理想になったんです」
二人は公園の縁へと歩いた。遊具はすべて静止していて、砂場に足を踏み入れても、細かな粒がこすれる音はまるで泡のように消えていく。だがイオリは、ベンチの背もたれに手を置き、しばらく目を閉じた。
──誰かが、ここに座っていた気がする。誰かが、ここで、何かを話そうとしていた。
けれどその声は発されず、ただ空気だけが、わずかにゆらいで終わった。
夕方、地下道の一角で、若者たちが小型スピーカーを使って音を再生していた。接続されたデバイスは不明だが、足元に向けられた音波は床材に反射し、わずかに共振を起こしていた。かつてマルタが再生空間で試みた、感情の残響を探る方法──その模倣に近い。
「まだ、残ってたんだな」
「あれもクワハラさんが開発なさった技術なんですか」
「理論的には彼女の延長線上にある。僕のやっている音の地図だって、もとはといえば彼女の試みに触発されたものだよ」
学生はしばらく見つめていたが、やがて小声で尋ねた。
「クワハラさんって、今も都市音響に関わっているんですか?」
「さあ──もう隠居なさったんじゃないかな? 丹沢の家を僕に譲ってからは三年くらい音信不通でね。確か四国に行くって言ってたような」
「なんだか、もったいないなあ。あれだけのことをやって……」
イオリは笑った。「本人は『失敗だった』とだけ言ってたけどね。成果も、継承も、望んでなかった。でも、だからこそ、あの人の音は、今でも誰かの中に響いているのかもしれない」
日が落ちて、都市の音はさらに整えられていた。
歩道を渡る足音は即座に吸収され、交差点の自動音声案内は周囲の環境音に応じて出力を調整している。高架下の車両も、きっちりと周波数帯域が圧縮されていた。今や〈オルト〉による制御すら必要とされていない。都市の空間そのものが、最初から何も鳴らないよう設計されているから。〈オルト〉に残された役割は、静寂のなかに代わりの情動を届けること。まっさらなサウンドスケープの代替として、人に響きを与える。
イオリと学生は、沈黙がより濃くなるような路地の奥に立っていた。吹き抜けの建物と建物の狭間にある空間。都市設計上の盲点で、補正スピーカーの照射がかろうじて届かない盲点だった。
イオリは古い録音機を取り出し、地下道の壁に向けて一つ、印をつけた。学生が不思議そうに覗きこむ。
「今度は何を記録してるんですか? ここ、何も聞こえませんけど」
「完全な無音なんて、どこにも存在しない。ごく稀に──消される直前の影のようなものに出会えることがあるんだ」
学生はしばらく考え込み、ようやくひとこと呟いた。
「なんだか、怖いような、美しいような気がします。何かが、そこにあったのに、もう誰も知らない名残っていうか──」
イオリは小さく頷いた。
「それは、ちゃんと聴こうとしたってことだよ。沈黙以前の音を──静けさには段階があるんだ。その狭間に染みこんだ響きを、僕は記したい」
学生はやや考えてから、
「やっぱり記録、正解だったと思います」
と、目線を地図の上に落としたまま、ぽつりと言った。
「ぼく、もともと〈オルト〉のエンジニアを目指してたんです。でも、途中で、あの静けさがどうしても変に思えて──」
イオリは、学生の横顔に目をやり次の言葉を待った。
「静けさの中に、どこか作られた感じというか、嘘みたいなものがある気がするんです」
彼の声は静かだったが、その奥にある確かさは、確かにイオリに届いていた。
「だから、君は僕の元に訪れたんだね」
イオリの問いかけに、学生は、照れたように笑った。
「はい。まだ、ちゃんとは分かってないんですけど。でも、見てみたかったんです。静けさの外側にあるものを」
文字数:39228
内容に関するアピール
音響SFに挑戦してみました。世界観は固まっていたものの、梗概講評・ゴゴゴ会を経て対立関係が不明確だと感じました。
今回は3つの軸を意識して書きました。すなわち「個人内対立(主人公の仕事と生き方)」、「社会構造対立(制度=秩序対ゆらぎ)」、そして「他者との対立」。これがうまいこと物語に迫力が出てくれることを祈るばかりです。
「音」に関係するSFは個人的体験による作品が多いなか、都市ものに関してはあまりないかと思います。新しい価値を見出すことができたらこれ以上嬉しいことはないです。
何卒、よろしくお願いします。
主な参考文献
「音のデザイン 感情に訴える音をつくる」 岩宮眞一郎 著 九州大学出版会
文字数:299