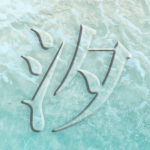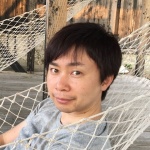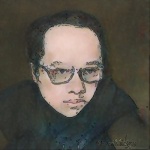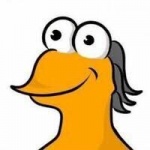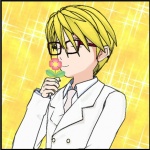梗 概
therapy
外野ゆき子は子供の頃から世界の役に立ちたいと思っていた。
大人になったゆき子は、世界を変えるバーチャル体験という謳い文句に誘われ、VR制作会社に入るが、任されるのは研修用の名刺交換VRなどつまらないものばかり。
せめてもう少しやりがいのある仕事をと思っていた矢先、上司である神谷が辞表を出したことを知る。
新卒時、ゆき子のメンターだった神谷は、彼女が理想とする世界の役に立つクリエイターだった。神谷はこれまでプロスポーツの訓練VRや多言語学習メタバースなど新たな価値を創出する仕事をしていた。
辞める直前、神谷が担当していたのは貧しい国で戦争被害にあったPTSD患者を治療するカウンセリングVRというもの。ゆき子はチャンスだと思い、神谷の後任となる形で治療VR開発を引き受ける。
暴露療法を目的としたVRの没入感は凄まじく、モザイク処理のないプロト版を体験したゆき子は再現された戦場を見て吐いてしまう。それでも映像チェックのために何度も見ているとその暴力性にも慣れていく。
しかし今度は別の症状が現れる。日常生活において自分がナイフや鉈を持っているような幻覚を見るように。あまつさえそれで人を殺す瞬間を幻視するようになる。
異常を感じたゆき子はVRを調査し、そこに奇妙な映像が仕込まれていること発見する。それは男がひたすら犬を殺し続けるカットを何百個も繋いだもの。それがサブリミナルで挿入されていた。映像には神谷の姿も映っており、ゆき子は神谷がアフリカ某国のキャンプにいることを知る。
ゆき子は某国へ飛ぶ。途中VRで見たような戦争の風景が広がっている。しかし神谷のいるキャンプは平和に見えた。皆が平然とした顔で銃や鉈で武装していること以外は。
神谷は村を案内し戦争被害にあった子供達がHMDを被って治療されている姿を見せる。子供達が見ているのは例の犬殺しVRだった。
神谷は説明する。元来ここに住むワトゥ族は周辺を敵対部族に囲まれており、そのような環境ゆえ、ワトゥ族には、いつでも敵と戦えるよう、そして敵である隣国を威嚇するよう、敵に見立てた犬を殺す犬殺しの儀式が存在していた。
しかし近代化に伴い儀式は廃止され、ワトゥ族は大国がバックに付いた隣国に侵略されるように。神谷はそんなワトゥ族を救うため再現された戦場の映像と犬殺しVRを使って野蛮さを再啓蒙していた。それはある意味では治療だった。
暴力が物事の解決手段になることに納得しないゆき子。しかし当の神谷自身が何食わぬ手つきで犬を殺す光景を見て諦める。神谷は現地の女性と結婚しており、彼の守る対象は政治的正しさではなく、いつ侵略されるかわからない家族達だった。
帰国後まもなく、ゆき子はキャンプが隣国ではなく西欧諸国の空爆によって破壊されたことを知る。
ゆき子は元の研修用VRを作る日々へ。そこでVRの中にサブリミナルで犬殺しVRを混ぜる。研修用VRが全国に納入された頃、ゆき子はふと休憩に入った喫茶店で客に理不尽に怒鳴られたウェイトレスがそっと手にナイフを忍ばせるのを目にし、小さく微笑む。
文字数:1264
内容に関するアピール
今回「自分とまったくちがう思想を持つ人」として、異なる地域と習俗のもと、戦争や紛争といった非常事態の中で生きている人間を設定しました。
現実では闇バイトが横行し、戦争も終わらず、世界がどんどんプリミティブで原始回帰的な流れを見せているので、呪術や因習、暴力性といったものが、かなりアクチュアルなものになっているとも感じています。
またVRは航空シミュレーターやスポーツシミュレーターのような没入感が学習の効率に直結する分野では有意性があることが科学的に実証されているので、舞台装置としての〈機械仕掛けの神〉的な役割でオチに使ってみました。
文字数:267
therapy
1.ガラスとスクリーン
こんなことを言うのもなんだけど、私って、それなりに本物の世界を知っている気がする。
深夜一時、いまどき、こんな緩いコンプラがまかり通るのかってくらい、セキュリティの杜撰なオフィスには、ときおり上階のBARの客が間違えて入ってくることがある。
そういうとき、私はエントランスとオフィスを区切る透明なガラス越しに、その他人と目が合ったりする。「降りる場所、間違えていますよ」そんな、ほんのりとしたアイコンタクトで、私たちはいともたやすくお互いが起こすべきアクションについて合意する。
そんな一瞬、人間もまだ捨てたもんじゃないなって、なぜだか上から目線で思ってしまう。なんとなく、世界が透明なガラスで隔てられた――ちょうどいま私がいるオフィスのような場所ではないと確信が持てる。
けれども実際にはその逆かもしれない。ガラスはただのスクリーンで、私はそこに映っている本物のような、でもって本物よりも本物らしい偽物に満足しているだけかもしれない。
それでもこの暗いオフィスだけが、いまのところの真実だ。そして真実が告げる。時刻は朝の四時。今日締め切りだったはずの資料はたったの三行しか進んでいない。自分の手には余る業務を押しつけられたという気がして、どうにも進められない。ここが潮時だろうか。でも明日になれば、上司がこれを引き取ってくれる。そんな気がしていた。
私の勤めている株式会社『リズメディカ』は、社員数七十名のネットメディア会社だ。業界的な立ち位置で言えば、それはちょうど中堅といったところで、上には大手の名の知れた出版社があり、下はほぼ個人経営みたいなところまで。ラインナップとしてはピンからキリまである業界のなかで、比較的、古株の会社だった。
でも実際のところ、業務の実態は他社から依頼されたWEB開発を委託業務として受注製作する、いわゆるWEBデザイン系の会社である。それを最近になって自社開発したサイトでネット記事を載せるようになり、そちらが思いの外、アクセスが伸びたため、会社名も刷新、いまふうな『ネットメディア』会社として、事業を始めたのが弊社リズメディカだった。
けれども、昨今、デジタル化やDX化の波が訪れたことにより、WEB開発事業にまたとない特需が起こっていた。そのため優柔不断もとい、顧客ファーストが社の理念であるリズメディカは現在、WEB開発事業をメインに、サブとして流行りのYourTubeやtoktikをまとめただけの、志の低いネットメディアとして、なんとも中途半端な二足の草鞋でやっているのが現状だった。気持ちは理解できなくもない。選んだ道がいつだって正しいとは限らないのだ。
結局、その日は会社に泊まり込んで朝の始業を迎えた。八時ちょうど。早速、始業してきた同期の宮川さんが私のデスクの前に現れた。
「昨日、リリースされたサイトについてだけど……」
朝一番にいきなりそんなことを言われた私は眠い目をこすりながら「はあ」とか何とか返事をしたかと思う。
「サイトがどうしたんですか」
私はほぼおうむ返しに言うと、彼女が無言で差し出したA4のプリントアウトを受け取った。「何でも」宮川さんは腕を組んで言った「凄いバグがあるって」
「そうなんですか」
私はそこでプリントアウトから目を離し、彼女の姿を見た。
今ふうのグレーなパンツとジャケットのモダンスタイル。でもジャケットの下に着ているブラウスは透っけ透けの実戦仕様で、思わずあなたまだ水曜日ですよとツッコミを入れてしまった。もちろん、脳内での話のことだ。
「あの、ちゃんと聞いてます?」
宮川さんが大きな声で言った。彼女、思ってたより機嫌が悪そうだ。というか半泣きだった。
「ええと、はい」
私は急いでプリントアウトに目を走らせる。宮川さんが朝から情緒不安定な理由が少しだけ理解できた。
そこにはこう書いてあった。
まず初めにお前の書いたコードは産業廃棄物なみのゴミである。そして次にそのことに対して、客先がもの凄い勢いで怒っている。最後に、お前はなぜこんなものを作ったのかという疑問提起。
一般的なレポート・論文の形式では、疑問提起が先にあり、結果や回答がその後に続く。けれど今回に関してはやや特殊な、フリースタイルの構成をしていて、それはこのレポートが問題に適切に対処するためではなく、読んだ者の情緒をズタズタに引き裂くことが目的だからだ。
ここで一つ重要なことを述べておく。とりわけ労働ということに関して重要な格言を述べておく。
仕事における責任の所在とは、最後に手を付けた人、確認欄に押印を押した人、台帳に名前を書いた人のもとへ飛んでいく。マリオカートでは、青甲羅は一位のレーサーに淀みなく飛んでいくが、労働の場合は違う。仕事は一位でも二位の人でも、最下位の人でもなく。手を引くところを見誤った人間のもとへと飛んでいく。確かにこのコードのダブルチェックを任され、最後に確認印を押したのは私だった。
「要求仕様が全然盛り込まれてないんですよ」
もはや半泣きで彼女はそう言うと、最後に「じゃ、私、引き継ぎましたから」と踵を返した。付けている香水だろうか、ちょっぴりスパイシーな香りを残して、宮川さんは去っていった。
おそらく、そのコードを書いたのは私ではないと突っぱねることは簡単だった。それは簡単なだけでなく事実でもある。でも事実と物事の正しい成り行きというのを、私たちは区別しなければならない
だから私は黙っていた。
この仕事を押しつけたことで、今夜、彼女は晴れやかな気持ちで合コンなりクラブなりにハメを外しにいけるだろう。人生の自由で、恵まれた時間。それらはまだ充分にあり余っている。深夜残業申請もなしに会社に泊まり込むような女に厄介ごとを押しつけることで、それを達成することができるなら、どんどん押しつけていくのが賢い生き方だ。それはあなたの若さが擦り切れるまでは常勝無敗の戦術となる。
結局、夕方になるまで、私はその資料に手を付けることができなかった
そのせいで、仕事上あまり関わってこなかった別部署の課長がご立腹であると、なぜか関係ない人事部の人からチャットが送られてきた。内容的にどうやら私は直接出向いて、課長に弁解をしたほうがいいらしい。
私はおっかなびっくり、向かいのビルにある第二オフィスへ向かう。リズメディカは事務所を二つ持っている。一つは私のいる雑居ビルもかくやの角部屋に事務所を構える旧オフィスと、そこから通りを一つ挟んで建てられたガラス張り二十階建てのビルのテナントに居を構える新オフィス。
新オフィスは基本的に来客対応用となっており、あとは専務や部長など偉い人のデスクがある。もちろん私のような下っ端はかび臭い旧オフィスにしか居場所がないわけだが、それでも入社面接の際、この白い綺麗なオフィスに通され、期待に胸が高鳴ったのを憶えている。そしてそんな期待は早々に裏切られることになった。
あのときと変わらず、どこもかしこも真っ白いエントランスに入ると、私はエレベータに乗って十三階を目指す。ID証をかざして、従業員用出入口から入ると、リズメディカ、デジタルクロスメディア部門ユニバーサルメディア第一制作室と書かれた部屋の前で足を止めた。
私はそこで自分のID証を指先でつまんで、そのやけに長い部署名の隣に並べてみる。
編集企画部制作二課 水原ゆき子。
デジタルとか、クロスとか、ユニバーサルとか、そんなものとは全く無縁の平々凡々なとこが、いかにも私らしい。そんな平々凡々な私は、平々凡々な故に、とにかく他人から怒られたり、失望されたりすることに、とてつもない恐怖を憶える人間だ。でも人間ってのは不思議なもんで、そう思えば思うほど、私の人生は人から怒られたり、敬遠されたりするようなものへと姿形を変えていた。むしろ、あえてそういう方向へみずから舵を切っているんじゃないのかって思うくらい。私の人生は、いまやコントロールの効かないものになっていた。
「失礼します、水原です」
早速、私は三回ノックするのを忘れて、第一制作室の扉を開けていた。やば、また怒られる。そんな不安もよそに、オフィスはしんと静まり返っていた。おそるおそる、扉から頭を覗かせた私は、奥の机に座っている社員の一人と目が合った。デスクには平林課長と書かれていた。
「ああ、あなたが水原さん」
平林課長はそう言うと、すっと立ちあがった。動作に継ぎ目がなく60FPSで作られた動画のようだった。
「あの、すみません、昨日リリースしたサイトのことで……」
「リリースしたサイト? 何の話?」
「ええっと、その……。T〇のサイトです。今朝、納品したのにバグが多いって」
T〇とはもちろん仮社名のことだ。客先の名前はコンプラ的に極力隠す方針ゆえに、そういう秘密暗号めいた呼称になる。
「ああ、T〇の。いいよ別に。稼働は来期からだから。定例でレビュー入れとくよ」
え、と私が驚いている間に、平林部長は例の動きで私で近づいてくる。
「それよりさ、水原さん。神谷くんって知ってる?」
「カミタニ……ですか?」
「うん、たぶん君が新卒の頃のメンターだったと思うけど、面識ない?」
数秒の後、私は思いだす。
神谷恭弥。当時、私のメンターをやってくれた先輩社員だった。
企画部のエース社員の一人で、元は外資系でバリバリ活躍していたのを、何を思ったのか(社長に説得されたとの噂もあった)こんな会社にきて、ネットメディア事業部の立ち上げに関わった人だった。
「ああ、神谷さんなら知っています」
「よかった。それが彼、急に飛んじゃってさ」
「とんだ?」
思わず私はタメ語調で訊き返す。とぶとは、あの飛ぶだろうか。ツバメかカラスのような。でも、おそらく比喩であろうことはさすがにわかるけれど。
「先週の金曜にね。辞表だけ出して辞めちゃったの。だからいま彼の引き継ぎ先を探しているんだよ」
そう言って、平林部長は言いにくそうに口をもごもごと動かした。「ようするにさ」平林部長は窓の外を見ながら言った「水原さんにそれを引き継いでほしいわけだよ」
「えっ、あ、はい」
人生とはかくもコントロールが効かないものであると思っていたがまさかここまで効かないものだとは思ってもみなかった。
「じゃあ明日からデスクこっち異動しといてね」
窓の外で音もなくカラスが羽ばたいていった。
2.世界の秩序と自由について
金曜日、私は自分のデスクを引き払い、神谷さんの仕事を引き継いだ。といってもサーバから何個か案件のデータをダウンロードして、それをプリントアウトしただけだ。私はそれを少しも躊躇うことなく、鞄に入れてオフィスを出た。顧客情報を勝手に持ち出してはいけないという世界観は最近になって私の中から消えた。小さなころは誰もが守る意味を感じていないルールを自分の中に適用させるのが好きだったが、ある日ふと空しくなってやめてしまった。その代わり、時と場合による、という言葉が私の頭のなかに強く残った。それでも深夜の赤信号は青になるまで待ってしまう。
私は自宅近くの公園まで来ると、ベンチに座って資料を読み込んだ。まともな家具がマットレスしかない家にいるより、ここで夜風に当たりながらの方が幾らか集中力が出る。
神谷さんが取り組んでいた仕事は、意外なことに弊社のネットメディア事業部とは関係の無い仕事だった。
まだyourtubeやtoktikをまとめただけの語るに落ちる記事を掲載する以前、リズメディカの主力記事のほとんどは彼が書いていた。最新のIT技術情報やガジェット紹介、いまでいうテック系ブログの先駆けと言えば、わかりやすいかもしれないが、そういうエンジニアもしくはクリエイター文化圏みたいなものをメディアで造ろうと考えている人が神谷さんだった。
しかし当時から後のWiresやジズモードなどの競合他社がひしめくネットメディア事業ではパイの奪い合いが激しく事業の採算性はあまり芳しくなかった。社内でも神谷さんの話を聞くことは徐々になくなっていった。
その後、何の仕事をやっているかは私は把握していなかったが、ときおり海外出張に行っていたりしていたので、ネットメディア関係の仕事を続けているのだと思っていた。が、そうではなかったようだ。
神谷さんが取り組んでいた仕事はどうやらVRに関することのようだった。
VR――Virtual Reality。
曰く仮想現実という代物だが、ようはディスプレイやゴーグルに投影された3DCG空間を、現実のように疑似体験することのできるゲームやツールのことだ。
まあ厳密に言えば、VRもメディアではある。けどそれはネットブログのようなマスコミュニケーションとしてのメディアではなく、情報媒体そのもののこと、そういう原義的な意味でのメディアだった。
資料には、VRを利用して様々なサービスを行うプラットフォームを開発するという旨の企画書が入っていた。ペラペラとプリントアウトを捲ってみて、私は自分がどこか異世界に来たような気分になっていた。
サービスにプラットフォーム、それはどこか遠い国の言葉のようだ。いくつか乗っている写真には、顎の割れた外国人が巨大なゴーグルのような機器〈HMD〉を付けて、安楽椅子に深く沈み込んでいる姿が載っていた。
私はさらに資料を何枚か捲る。だんだんとその内容が支離滅裂にオカルト的な色合いを帯びてくる。どこかの避難所のような場所で、一列に並んだ子供たちが、HMDを付けて、危ない薬でもやっているみたいな、ふわふわとした笑顔を浮かべている。
私はひとりごちる。
「私たち、なんでこんなことになってしまったんだろうね」
メンターをやっていたときの神谷さんはトップ社員として、バリバリの現役だった。半年毎の決算報告会では、いつもマイクをとって、ネットメディア事業部の展望について熱く語っていた。
私も私で、メンターだった神谷さんに自分の夢をたくさん話したものだ。世界は多種多様で、そこにはいつだって驚くべき発見がある。本物と呼ぶべき経験、世界がある。
そこで私はたくさんの価値観に触れて試される。そこでは私自身も世界を試しているのだ。そんな感覚があった。あったはずだった。
私は立ち上がると自販機でホットの缶コーヒーを買った。ちびちびと熱い液体を喉奥に流し込むうちに、胃の中に蝋燭の火がぽっと点いたような感覚がした。
その頃には、強い意志が私の中に芽生えていた。神谷さんの仕事が、まだどんなものか判然としていなかったけれど、この仕事を絶対に成功させたい、そんな強固な意志が私の中に生まれていた。
ここで一つ説明しなければならないのは、私がなぜこのリズメディカという会社に入ったのか、だろう。
それは、高校生の頃、仲の良かった友達が、私に黙ってしれっと彼氏を作って、しれっと三年交際記念日にディズニーにお泊まりに行って、そして、しれっと別れて、なにか酸いも甘いも知ったふうな顔で私に愚痴ってきたとき、私は宇宙に放り出されたライカ犬みたいな気持ちで乙女ゲーのキャラのアイコンをタップすることしかできなかったからかもしれない。
あるいは、就活中、駅の階段から落っこちた人の頭から、水たまりができるくらい、たくさんの血を流れているのを見たとき、そしてその血の海を、朝一発目から客先と会議があるんだよって感じの余裕なさそうなスーツ姿の男性が迷惑そうに跨ぎ超えるとこを見て、たまらず駅のトイレで吐いてしまったこと。それが無性に悔しくて、負けたと思ったからかもしれない。
もちろん採用面接の時に、こんなことを話すわけはない。けれど、私のその異様な意気込みはその後、同期となる他の社員たちには伝わっていたらしい。だから私が旧オフィスのデスクを引き払っていたとき、宮川さんを初めとした大半の同期は私が辞めるのだと思っていたらしい。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
すみません、今回、書き上げられませんでした。ここまで読んでくださった方、ありがとうございます。
文字数:6546