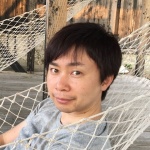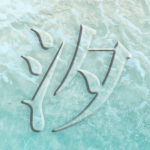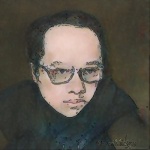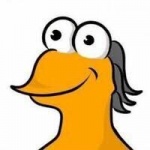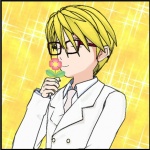梗 概
夜光アクアリウム
主人公・藍田浩一は、都会の狭いアパートで孤独な生活を送る30代の会社員。
癒やしを求めて数年前にアクアリウムを始めてから、多種多様な水草や観賞魚の美しさに魅了され、水槽の維持改善に給料の大半を投入している。
中でも彼のお気に入りは、発光する鰭を持つルミナステトラや、水中で大輪の花を咲かせるスターリーフといった、遺伝子改良された最新品種の魚・水草だった。
これらの遺伝子改良生物は、先端環境技術企業ネクスフィアが開発したもので、一般に流通してはいないが、藍田は知り合いのアクアショップ店長の伝で特別に入手できたのだった。
ある日、水槽で奇妙な現象が起きる。
魚の群れが等間隔に陣形を為し、鰭の光を点滅させる。連動するように、遺伝子改良水草の成長が不自然に加速する。この奇妙な現象は、以降定期的に発生するようになる。
藍田は魚の点滅パターンや水草の成長速度を記録し、水温や水質、酸素といった水槽の条件を変えて実験を行い、その結果として光の点滅が何らかの信号として機能していることを突き止める。
どうやら魚たちは水槽の環境情報を共有し、それを元に集団で行動を調整しているようだった。さらに観察を続けると、その行動が彼ら自身の生存ではなく、水槽環境の最適化を目的としていると判明した。酸素濃度が不足すれば、魚達は仲間を攻撃して数を減らし、水質が悪くなれば絶食して悪化を遅らせていた。遺伝子改良水草も、魚から何らかの情報を得て同様に生育を調整しているようだった。
藍田が実験結果をネットに投稿すると、2日もしないうちに投稿が削除されていた。
間もなくして、藍田は中学校の同級生、能作貴子と15年ぶりに再会する。彼女は自らが開発企業ネクスフィアの研究者だと明かし、水槽を直ちに廃棄するよう警告する。
曰く、件の遺伝子改良生物群は、環境破壊が進む中で持続的な生物多様性を実現するための試験的プロジェクトの産物だった。そのゴールは、人の介入なしで絶滅危惧種の保存や過剰繁殖種の間引きができ、望ましい方向に進化していく、集合意識を持った自立的な生態系を作り出すこと。
閉鎖的環境に住み、生命のサイクルが短いアクアリウムの生物は、変化を追うための実験対象として最適だった。
しかし実験中、不適切な管理をされた生物群の一部が、環境悪化を人間活動によるものと特定し、人間に有害な毒素を排出するようになる。会社は計画を秘密裏に放棄したが、営利目的で横流しした者がいたために藍田の元に生物が届いてしまった。会社は情報の流出を恐れ、流通に関わった者を処断しており、能作は藍田の身を案じて先んじて忠告しにきてくれたのだった。
忠告を受け、藍田は手間をかけた水槽を惜しみつつ廃棄する。丁寧に世話をしてきたからか、藍田の生物たちは毒を吐くことなどなかった。もし彼らが地球上に流出したら人類に牙を剥くのだろうか、と考えつつ、心の中で捨てられる生物たちに謝罪する。
文字数:1200
内容に関するアピール
今回は綺麗でちょっと不気味なものを書いてみようと思いました。
見知らぬ生き物って、魚にせよ虫にせよ植物にせよ、得体が知れなくてちょっと怖いんですが、だからこそ惹かれるものがあります。SFを読む時も(モノによりますが)未知に直面した時の背筋がひやっとする感覚があって、それらをうまく繋げてみたら何か面白い感覚に出会えるのでは、という狙いです。
それともう一つ作品のテーマとして、手前勝手な都合で他の生命を操作し、果ては排除するという人間のエゴに対して、外からの批判を加えるのではなく当事者として向き合ってみる、というものがあります。
風景描写、心情描写ともに求められる難しそうな梗概にしてしまいましたが、ぜひ実作で力試しをしてみようと思います。
文字数:318
夜光アクアリウム
八畳一間の安アパートの薄暗い一室で、ぼやけた橙色の天井灯が浮遊する細かい埃を照らし出している。その部屋の片隅には、場違いなほど鮮やかなLEDに照らされて明るく浮かび上がる100cm水槽が置かれている。
藍田浩一は缶酒を片手に水槽の前に座り込み、かれこれ一時間ほど彼の創造した見事な水中世界に見入っていた。
パールグラスの森から現れたルミナスネオンテトラの一群が、水草の隙間の細かい気泡を散らし、エメラルド色に発光する体を閃かせながら深みに泳いでいくのが見える。
複雑に入り組んだ流木の影では、鮮やかな朱色のドワーフグラミーがじっと鰭を休めている。水面に蓮のような葉を展開しているのはスターリーフだ。この植物は成長とともに下に下に茎を伸ばしていき、その先に星形の大きな水中花をつける。浮遊性の水草の中で水中に花をつけるものは非常に珍しく、藍田の知る限り他に例はない。
これはもう一つの宇宙だ。
藍田は水槽を眺めるたびにそう感じた。
排ガスに淀んだほこりっぽい東京の空の下、無駄に増えすぎた人間がせわしく行き交っている中で、この水槽は外界から隔絶されて、清浄な光に照らされた静かで緻密なミクロの異世界として成立している。
藍田がアクアリウムを始めたのは五年前だった。
彼の従事する工場監督の仕事はそのほとんどが自動化されていて、やることと言えば毎朝満員電車に揺られ、大して意味のない会議に出席することくらいだった。
単調な日常に、彼は静かに疲弊していた。そんな折、ふと立ち寄ったアクアショップで水槽の光景に魅了されたのが始まりだった。
それからは、ひたすら水槽の維持と管理に没頭する日々が始まった。毎日水質を監視し、理想の水景を追求するために水草や流木の配置を練り、頻繁にアクアショップに赴いてさまざまな生体を購入した。
中でも彼の特別な気に入りは、ルミナスネオンテトラとスターリーフだった。一般には流通しておらず、藍田を得意客として認めたらしきショップ店長がある日バックヤードから出してきたものだった。
「俺もこの商売をやって長いけどね、見たことないやつが入ったよ」
でっぷりと肥えて、人よりはらんちゅうに似ている店長は丸顔を赤らめ、興奮で目を輝かせていた。
「普通のテトラ類の鱗のきらきらは単なる反射光だろ。こいつらはね、電気クラゲの遺伝子を組み込んだらしくて、自分で発光するんだ。この鮮やかなエメラルドの光、すごいだろ。こっちの水草もすごいぞ、何を掛け合わせたか知らんが巨大な水中花をつけるんだ」
藍田は一目で魅了された。
「いくらなんです」
「いつも贔屓にしてもらってるけどね、こればっかりは少しもまからんよ」
そう言って店長がサラミのような指で提示した値段は月の給料の半分に近かったが、藍田は迷うことはなかった。
藍田は缶酒の最後の数滴を飲み干すと、水槽の照明を消した。自然環境と同じく、水槽の生態系にも昼夜のリズムを与えてやらないといけない。
空き缶をぞんざいに畳に放り出し、暗くなった水槽でいっそう鮮やかに輝くルミナスネオンテトラの光跡を一瞥すると、天井灯のひもを引いて布団に潜り込んだ。
音声認識機能のついた天井灯くらい缶酒三、四本分の金ですぐ手に入るが、藍田は自分の生活に必要最低限以上の金を使う気はさらさらなかった。
そんなものを買うくらいなら、その五十倍の金を出して新しい水槽照明を買った方がいい。
次は水槽のどこに手を加えようか、と考えを巡らせる。スターリーフの白い花を引き立てるなら、銀白色系の小魚群を入れるのがいいかもしれない。
閉じたまぶたの裏で、まだ見ぬ水景のイメージが展開されていく。スターリーフが水面に展開する明るい緑の葉の下には、青く澄んだ影が落ちる。その影の中、スターリーフの大きく真っ白な花弁が水流に合わせてゆっくりと開閉している。
たった今藍田の想像の中に生まれた、実在しない銀白色の小魚の群れが、花弁の間を風に乗るように舞っている。そこに数匹のルミナスネオンテトラが現れ、小魚の群れを散らして影の中を通り過ぎる、その瞬間に光を投げかけ、小魚の群れは星が瞬くようにちらちらと光を反射する。
そして再び静寂が訪れる。ミクロの宇宙の中では永遠の時間が流れ、その間に織りなされる澄んだ水と光の絵は一度として繰り返されることなく、無限のパターンを描く。
徐々に夢と混ざり始めた想像上の水景は、曖昧になり、やがて意識の底に沈んでいった。
しかし、それからしばらくして藍田は目を覚ました。
寝酒が却って眠りを浅くしたのかもしれなかった。枕元に置いた腕時計を見ると、ぼんやりとした蛍光塗料の針が午前三時過ぎを指していた。
藍田は何気なく水槽を見やり、そして凍りついた。
暗闇の中、何筋ものエメラルドの光が、不気味なほど等間隔に整列し、不規則なリズムで一斉に点滅している。
「なんだこれ」
起き抜けの眠気は吹き飛び、恐怖とも驚きともつかない底知れない感覚に襲われ、藍田は照明をつけた。
見間違いではなかった。二十匹弱のルミナスネオンテトラは、その全てが正確に同じ方向を向き、等間隔に並んだまま静止し、一分の狂いもない同じリズムで光を点滅させていた。
普段何匹かの群れでまとまって泳ぐことこそすれ、こんな風に一匹残らず、それも隊列を組んで静止することなどない。そもそも個体間で示し合わせたように同時に光を点滅させるなど、およそ魚の機能としてあり得ない。そんな行動をする目的も、それが出来る生物学的な仕組みも見当がつかない。
藍田は混乱したまま、スマートフォンのカメラで録画を開始した。それからおよそ三分ほど経った頃、テトラの群れは唐突に異常行動をやめ、何事もなかったかのようにてんでばらばらに泳ぎだした。
普段通りに泳ぐ魚の群れを見ていると、寝ぼけて幻を見たのではないかという気さえしてきたが、録画には確かに異常行動が記録されている。
藍田はひとまず水槽の状態を確かめるべく、水温、水質、酸素濃度といったパラメータを一つ一つ計測し、管理ノートに書き付けていった。しかし、酸素濃度がわずかに低下していた他、普段の記録から目立った変化は見られなかった。酸素濃度の変化も、特段問題になるほどではなかった。
もう一度水槽を観察する。十二種の魚類、二種の甲殻類、そのどれにも普段と違う様子は見られない。
では水草は、とまずスターリーフに目を留めたところで、微妙に違和感を感じた。よく見てみると、昨日まで固く小さい蕾だったはずの花が一つ、すでに開き始めている。葉もわずかだがここ数時間で大きくなっている気がする。
水草の生長は早い。藻類に至っては、一晩で水槽を埋め尽くすこともある。しかし、大した条件変化もない中で、ここまで成長のペースが急加速するのは明らかに不自然だ。
他の水草も一つ一つつぶさに見ていったが、こちらは何の変化も見られなかった。
つまり、ルミナスネオンテトラとスターリーフだけが、何らかの異常を来している。
藍田はそれから、朝まで水槽を見張っていた。またテトラがあの異常行動を見せるのではないかと思ったからだ。
しかし思惑は外れ、その日はそれ以上何も起きなかった。
無情にも始業時間に追い立てられ、藍田はひとまずこの問題を棚上げせざるを得なかった。
それからというもの、藍田は今まで以上に水槽を頻繁に、かつ注意深く観察した。部屋でテレビを見ているときも、夕食を摂るときも常に視界の端に水槽を入れていたし、特定の時間帯のみあの現象が起きる可能性も考えて、しばしば深夜に目覚ましを設定し、眠い目をこすりながら水槽を監視することもあった。
努力の甲斐あって、藍田はその後何度か異常現象が再現される場面を目撃した。一週間にだいたい一、二回、時間帯に法則性はなく、起こる条件は不明だった。
観察を続ける途中で、藍田は定点カメラを購入し、何回分かの異常現象を記録に納めた。高性能な暗視機能がついた、これまた高額な品だったが、もちろんためらいはなかった。
何が起きているのか、どうしても知りたかった。
録画された異常現象をじっくり見返し、その時点での水槽の条件を照らし合わせる中で分かったことはいくつかあった。
一、ルミナスネオンテトラとスターリーフの異常は必ず同時間帯に起きていること。
二、異常現象の後は、必ず水槽の何らかのパラメータが僅かに変化していること。
しかし、そもそもなぜこんなことが起きているのか。録画を何度見返しても、手がかりはつかめなかった。
記録映像の中でリズミカルに点滅するテトラの光を見て、モールス信号みたいだ、と藍田は思った。
昔観た、山岳遭難事故の再現ドキュメンタリーを思い出す。
遭難した登山者グループが、夜を徹してヘッドライトで一斉にSOS信号を送っていたというものだ。結局遭難から三日後に無事救助されたものの、夜間に山岳救助ヘリは飛ばないのでほとんど意味はない、と専門家が解説していた。
せっかく思いついたので、馬鹿げたことと知りつつ、テトラの光の点滅を記録してモールス信号に起こしてみようとしたが、長短のリズムもばらばらでそもそも変換のしようもなかった。
「でも、何か意味はあるはずだろ」
気ままに泳いでいるテトラの群れを見つめながら、藍田は返ってくるはずのない質問を投げかけた。
事象の解明にあたって、独力では限界があると藍田は比較的早い段階で気づいていた。
しかし、折り悪くも行きつけのアクアショップは「店主の個人的都合」とやらで一時休業してしまっていた。
店前の張り紙にはそれ以上の情報はなく、再開時期も分からなかった。大方、店主が病的肥満か何かで入院したのだろうと藍田は思っていた。
打てる手がいよいよなくなり、藍田はネットの匿名掲示板に、映像記録とともに何が起きているのか教えてほしい旨の質問を投稿した。情報の信憑性はさておき、何か少しでも手がかりが得られればよかった。
質問は一瞬で他の投稿に流されてしまったが、それなりにリアクションは得られた。しかし望んでいたような答えは得られなかった。
ついたコメントは、「どうせAIが作ったCG」などとまともに取り合っていないものが多い上に、「サタンのお告げだ」とかいう狂気じみた妄想まであった。まだまともだったのは、「水槽の条件を極端に変えて観察してみたらいいのでは」というものだった。
条件を変えて比較検証するのが科学の基本だということくらいは藍田も分かっていた。ただ、これまで理想的な環境を追求してきた水槽を少しでも損なうような実験には、なかなか手が出なかったのだ。
しかし、他に出来ることもない。このまま知らないままでいたくもない。
手始めに、一度煮沸して冷ました水を水槽に加え、酸素濃度を低下させた。当然、生体に深刻な影響が出ないよう、濃度管理には細心の注意を払う。
効果はすぐに現れた。
空気を飛ばした水を加えてから数秒も経たないうちに、テトラの異常行動が始まった。いつになく激しいリズムで光を点滅させている。
すると、それに呼応するかのように、スターリーフの異常が現れた。花は落ち、十分も経たないうちに葉の色が濃い緑に変わり、根は二センチメートルほど伸長した。
テトラ達はというと、隊列を組んで光を点滅させていたのは最初の三分ほどで、その後は散開するも、奇妙なほど静止してほとんど動かなかった。
そして一時間後、酸素濃度は大幅に上昇していた。
「まさか・・・」
次の実験ではフィルターを停止させ、水質を悪化させた。案の定、再びテトラの異常行動が見られた。今回は先ほどとは点滅パターンが明らかに違うようだった。
テトラが点滅を終えて散開した直後、試しに餌を与えてみる。藍田にはすでに結果を予測していた。そしてそれは裏切られなかった。
通常食用旺盛なテトラ達は一匹として餌を食べず、他の魚達が餌を食い荒らすのをただ傍観していたのだ。
当然の理屈として、餌を食えば魚は糞を排出する。そこには大量のアンモニアが含まれ、フィルターのない環境では急激な水質の悪化につながる。
そのため餌を食べないというのは、水質のさらなる悪化を防ぐという意味で非常に合理的な戦略だが、個体の生存にとっては当然不利に働く。
「環境を、管理してる?それも群の中で意思を統一して、自分の生存を後回しにして・・・」
呟いてさらなる事実に思い当たった。スターリーフの異常は、常にテトラの光の点滅の直後に発生していた。
実際、最初の実験の後、水替えをして環境を戻すにあたって事前に魚達をバケツに待避させたのだが、その際に魚達がいなくなった水槽内では水質の変化があったにもかかわらず、スターリーフは何の変化も示さなかった。
「別種の生物間で情報伝達してるってことか?」
ごく珍しいが、そういった例が全くないわけではない。例えばハゼは、敵が来襲した際、同じ巣穴で共生するテッポウエビに警告を送ることがある。
しかし、魚と水草というあまりにかけ離れた生物間で、環境の変化という複雑な情報を、光の点滅パターンで伝達するなど到底ありそうもない話だ。
しかもこれは単純な情報伝達ではない。そこには、個体の生存を犠牲にしても、環境全体、すなわち生態系を維持するという明確な目的がある。種を超えた集合意識とでも呼ぶべきものだ。
藍田は長く息を吐いた。体全体が緊張でずっとこわばっていた。自分のたどり着いた推論が、まだにわかには信じられなかった。
それでも、あり得そうな説明は他にはない。大変なものを見つけてしまった気がするが、とにかく誰かに見せてみよう。そう思い立ち、実験結果をファイルにまとめ、前回利用したアクアリウム掲示板にアクセスしようとしたところで行き詰まった。
スマートフォンの画面には403エラーと表示されている。アクセス拒否だ。
混乱しつつ、PCからVPN経由でアクセスすると問題なくトップページが表示された。つまり、藍田のIPアドレスはおそらくこの掲示板の管理者に凍結されている。
さらに、以前投稿した質問を検索してみたところ、スレッドごと削除されていた。
首をひねりつつ、新しいスレッドに実験結果と推論を投稿した。
リアクションがつくのを待つまでの間、藍田は軽く飯でも食べるかと思い立ち、インスタント麺に注ぐ湯を準備するためキッチンに立った。
湯沸かしポットを持って座卓に戻ってきて、何の気なしにスレッド画面の更新ボタンを押す。そして画面に表示されたのは、「スレッドが存在しません」の文字だった。
これはおかしい。
藍田は思った。
投稿してからたかだか10分だ。誰かが自分の投稿を監視しているとしか思えない。
しかし、何のために?自分以外も投稿しているスレッドごと削除する必要があるのか?VPN経由で接続してるのに、どうやってこの短時間で特定したんだ?
さすがに気味が悪かった。接続を切り、PCをシャットダウンして、ひとまず自分の実験の成果は胸に仕舞っておくことにした。店長が帰ってきたら教えてやろう。
三日後、店長はまだ帰ってきていなかった。得体の知れない秘密を一人で抱えている居心地の悪さがずっとつきまとっていて、藍田は仕事中もどこか落ち着かなかった。
今日は仕事を早く切り上げて帰ろうか、そう思っていた頃、事務員から内線が入った。
「藍田さん、能作さんとおっしゃる方の来客です。アポはないとのことですが、お通ししますか」
店長の名字は能作だっただろうか。職場を教えた覚えはなかったが、電話番号か何かを伝えるのに名刺の一枚くらいは渡したかもしれない。
このとき藍田は誰かに秘密を打ち明けたいという欲求に支配されていて、店長がわざわざ自分に会いに来るというシチュエーションの不自然さに思いが至らなかった。
「もうすぐ出ようと思ってたから、外で待つように伝えてください」
電話を切ると、急いで荷物をまとめて外に出た。
帰宅ラッシュの時間には少し早いが、子どもの迎え等で早上がりする人も多いのか、車寄せは多少混み合っていた。
店長の姿は見当たらない。あの巨体なら見落とすはずはない。辺りを見回していると、
「藍田くん」
と唐突に声がかかった。
声のした方を見ると、見慣れない女性が立っていた。
年の頃は三十半ばでおそらく藍田と同年代だろう。背が高く、長い髪を後ろでひとつに結っていて、やや骨張った頬からキリッとした印象を受ける。
仕立ての良さそうなブラウスとパンツを身につけているが、それよりも服装に不釣り合いな大きさの黒い仕事鞄が目立っている。
「藍田くんだよね?」
おそらくよそ向けであろう柔らかい笑顔を浮かべている目の前の彼女について、藍田は何も思い当たるところがなかった。
「失礼ですが、どこかでお会いしましたか?存じ上げなくて・・・」
「ああ、ごめんなさい。能作貴子です。中学三年の頃、同じクラスだった」
能作某は店長ではなかった。確かに言われてみれば、少し珍しい名字で記憶の片隅に引っかかるものがあるし、どこか顔も見覚えがある。
言われるまで思い出せなかった時点でそこまで親密ではなかったはずだが、と思いつつ、藍田は相手の目的を図りかねて、続く言葉を待った。
「色々お話したいのはやまやまなんだけど、長くなるからこの場だとね。夜ご飯ご一緒してもいいですか?」
「はい?」
女性の方から食事に誘ってもらった経験など、藍田にはほとんどない。
しかし、異性関係は何年もご無沙汰で近頃は興味もあまりなくなっていたから、喜びというより急な展開についていけない戸惑いの方が圧倒的に大きかった。
「構わないけど・・・」
水槽の水替えをする日だが、数時間遅れても大した問題はない。それより、この女の目的が何なのか知らずに帰ってしまったら、またモヤモヤの種が増えてしまう、と藍田は思った。
「ありがとう、じゃあここからタクシーに乗っちゃいましょう」
藍田の煮え切らない返事を気にする風もなく、能作は溜まっていたタクシーの先頭にさっさと乗り込み、藍田がシートに腰を落ち着ける前に運転手に行き先を伝えていた。
能作がシートベルトをきちんと締めるのを見て、普段気にしていない藍田も倣った。
「車で十分いかないくらいのところに、顔見知りがやってる小さいスペイン料理屋があるの。六席しかないんだけど、今日は貸し切りにしてもらってて」
「そうなんだ」
スペイン料理など、最後に食べたのは何年前だろうか。なぜ、二十年近く会っていない相手と会うのにいきなり事前に貸し切り予約までするのだろうか。
「能作さんは今何してるの」
「ああ、うん、そこからだよね」
よそ向けの丁寧な笑顔がなぜか少し気まずそうに崩れた。
「技術職。生物系の会社。何してるかは後で詳しく話すね」
そういえば中学の頃、理系科目でいつも突出した成績をとっていた女の子がいた。自分も生物の成績はかなりいい方だったが、いつもその子の後塵を拝していた記憶がある。
あれは確か能作さんではなかったか。
「そうなんだ、そういえば中学の頃から能作さんは成績良かったんだっけ」
「あ、思い出してくれた?」
「少しずつ」
能作は、それはよかった、と、今度はよそゆきではなく打ち解けた友人に向けるような笑顔を見せた。何が起きているかいまいち飲み込めないままだったが、藍田の緊張は少し和らいだ。少なくとも、見かけほどとっつきづらい人ではなさそうだった。
能作の言うスペイン料理店は、本当にこじんまりとしたものだった。細い路地裏にひしめくように建つ、日当たりの悪そうな雑居ビルの三階にその店はあった。
貸し切りの札の下がった古くて重い木製のドアを能作が押し開くと、蝶番が結構な音を立ててきしんだ。
顔見知りとのことだったが、店主は能作にいらっしゃいの一言と、藍田には軽い目礼だけで、オーダーをとるとすぐに奥に引っ込んでしまった。
「気を悪くしないでね、元々ああいう人だから」
「いや、大丈夫」
オーダーの時、能作はアルコールを頼まなかった。それならと藍田もソーダ水にした。
食事のメニューはおまかせすると藍田が言うと、能作は慣れた様子で何種類かのタパスとオムレツを注文していた。
入ったときは薄暗くてあまり見えなかったが、よく見るとこなれたいい雰囲気の店だった。店の一番奥の壁にはスペイン産ワインの空きボトルが一面に並んでいて、他の壁にはスペインの地図やら古いポスターが貼ってあったり、レコード棚がしつらえてあったりする。
藍田と能作がかけているテーブルの壁際には、スペイン西部のサラマンカ土産と思しきモザイクタイルのカエルの置物があった。
「それで」
もう本題を聞かせてくれてもいい頃だろう、と思って藍田が能作を見ると、
「そうカエルと言えば」
と明後日の方向から言葉が返ってきた。
「解剖の授業、覚えてる?カエルの」
「なんとなく」
「女の子が何人か解剖を嫌がって泣いて。男の子たちがふざけてカエルを振り回して、それで余計泣いて」
「ああ、あったね」
藍田は悪ふざけをするタイプではなかったが、カエルの解剖ごときでキャーキャー言う女子にも内心呆れていた。たぶん我関せずでスケッチか何かしていたと思う。
「カエルが可哀想だからやめなさいって先生が怒ったんだけど、そこで私『死んでるんだから可哀想も何もないんじゃないですか』って口挟んじゃって。それでもう先生が完全に切れちゃって」
「ええ、そうだっけ」
「あはは、バカだったよね。結局ごちゃごちゃに荒れて、一番悪いのは私ってことになって。自分が悪いのにムキになって、教室飛び出してふてくされてたんだよね。私、多分あれで推薦逃したんだと思うな」
今の能作の穏やかで余裕のあるたたずまいからは想像がつかないエピソードだった。その場に藍田もいたはずだったが、今となっては記憶はあまりにもおぼろげで、能作の印象は目の前にいる思慮深そうな大人の彼女によって大方書き換えられてしまった。
タパスが運ばれてきた。藍田には名前は分からないが、マッシュルームの傘に肉と何かのスパイスを詰めて焼いたもののようで、非常に食欲をそそる匂いがする。
ピックに刺して口に含むと、オリーブオイルとガーリックの香りがいっぱいに広がった。噛むごとにマッシュルームの風味が加わり、より一層旨みが増す。
「ね、美味しいでしょ」
「美味しい」
ほとんど二十年ぶりに再会した中学校の同級生と、何年ぶりかのスペイン料理を食べているという奇妙な状況が、藍田の口を軽くした。
「俺、アクアリウムやってるんだけどさ」
能作はピックを置いた。
「そうだね、その話をしないと」
「その話?」
「藍田君の、アクアリウムの話。そのために今日私は会いに来たんだから」
藍田は呆気にとられて、反応が一瞬遅れた。彼のアクアリウム趣味を知っているのは、仕事の知り合いのごく一部とアクアショップの店長くらいのものだ。
「俺のアクアリウムのこと、何で知ってるの」
「順を追って話しましょう。さっき、私は生物系の会社で技術職をやってるって話したよね」
「ああ、うん」
「ネクスフィア、って聞いたことない?バイオテクノロジーを手広く扱ってる会社なんだけど、私はそこの先進環境技術開発局っていうところで遺伝子工学系の雇われ研究者をやってる」
世情に疎い自分でも聞いたことのある社名だった。何だか分からんが凄そうだ、と藍田は思った。中学の頃はテストの点数くらいにしかなかった差は、大人になるとこんなにも開くのか。
「私はそこで、主に水生生物の遺伝子改良の研究をしてた」
「話が見えてきた気がするな」
「藍田君の水槽にいるでしょう?自発光するテトラ種と、蓮に似た葉と水中花をつける浮遊性水草。それらは、うちの会社が作ったものなの」
「ルミナスネオンテトラと、スターリーフ・・・」
近頃藍田の頭を悩ませてやまない、不可解な水中生物たち。
「そんな名前がついてたんだね。ともかく、所在の確認ができてよかった」
能作は一息置いて先を続けた。
「これをお願いするのは心苦しいけど。帰ったらすぐに、そのテトラと水草は廃棄して。あれは研究段階の遺伝子改良生物群で、一般に流通していいものじゃない。できれば飼育していた水槽と、一緒に管理していた他の魚や水草も。死骸は土に埋めたりしないで、高温のバーナーで燃やして捨てて」
そう言うと、能作は大きな仕事鞄から、産業用だと言ってゴツゴツした見た目のバーナーを取り出し、タパス皿の横に置いた。
「何だって?」
タパスの横に並んだ巨大なバーナーは冗談みたいな違和感を放っているが、能作は冗談を言っているようには見えなかった。
「どこから嗅ぎつけたのか知らないけど、俺は金を出してあれを買ってるんだ。水槽だって大事に育ててきたものだし、それは聞けない」
生活のほとんどを捧げてきた、もはや生きがいと言ってもいいアクアリウム。
ルミナスネオンテトラも、スターリーフも、気味の悪さを感じないと言えば嘘になる。それでもあの神秘的な美しさは藍田の心を掴んで離さなかった。
それに、集合意識なんていうとんでもないものを持ち合わせた生物を目の前で観察できるのだ。こんな機会はどんなに願っても与えられるものじゃない。
能作はやっぱりか、とでも言いたげな表情を浮かべている。
「そもそもあいつら一体何なんだ。異常行動のことも、それを俺がネットに投稿してたことも大方知ってるんだろ。あれはただの遺伝子組み換えじゃ説明がつかない」
「分かった、やっぱりちゃんと説明しないといけないね。いいかな、これから話すことは社外秘なんていうレベルの話じゃない。扱い方を間違えれば藍田くんや私の身にも危険が及ぶような機密情報だから、覚悟して聞いて」
やっぱりあれはやばいものだったのだ、と藍田は思った。分かっていたが、背筋が冷えていく感覚がする。
「わかった」
「藍田くんがルミナスネオンテトラ、スターリーフ、って呼んでいるのは、うちの会社の遺伝子改良生物開発プロジェクトの産物で、それぞれC7012、L6002っていう研究コードがついていて、他にも100近い種類の遺伝子改良生物がいたんだけど、今残存しているのは藍田くんの手元にある二種だけ」
「何で?」
「まずはプロジェクトの話から。私たちの目標は、Autonomous Ecosystem、自律型生態系を作ることだった。より正確に言うと、全体最適を目的とする集合意識を持つ生態系と、それを構成する生物を生み出すこと。例えば、自ら絶食して個体数を減らすエチゼンクラゲ、逆に繁殖範囲と期間を拡大して個体数を増やす絶滅危惧種のシンリンオオカミ、あるいは砂漠化が進む地域でオアシスの位置情報を伝達して種子を飛ばす新種の樹木とか」
「魚が環境情報を共有して、水草と連携して水質を維持するとか」
「そう。閉鎖的環境で生きられて、生命のサイクルが短いアクアリウムの生物は、遺伝子変化を追うための実験対象として最適だったから、私たちはまず淡水性微生物、それから水草、それから淡水魚の改良を始めたの。当初は、持続可能な生態系を作る革新的な試みとして、上層部の期待も厚かったんだけど」
「もう研究生物が残っていないってことは、遺伝子変化に適応できなかった?」
「いや、もっと深刻な問題が発生してね。実験の中で高い環境負荷をかけられた生態系群の中に、その原因が人間活動によるものだと特定した生態系があったの。その構成種の一つだった微生物が、異常に短いスパンで世代交代を繰り返して、ついに人間に有害な毒素を排出するようになった」
藍田は言葉を失った。
「もちろんプロジェクトはすぐに放棄された。秘密裏に。実験生物群はみんな焼却処分。でも、どこかの不届者が、営利目的で一部を横流ししたらしくてね。会社はあらゆる手を尽くして追跡して、最後まだ見つけられずに残っているのが藍田くんのところにいるC7012とL6002。第七世代のカラシン科と第六世代のトチカガミ科、どちらも進化のスピードは遅いからすぐに毒を出すようなことはないだろうけど、もしこれが自然環境に流出したら、野生種と交雑したりして…長期的に見ればどれほどの影響が出るか分からない」
自分は事態を軽く捉えすぎていたのかもしれないと藍田は思った。
「うちの会社はかなり必死で、追跡の手段を選ばなくなってる。アクアショップの店長はすでに特定されて、多分拘束、脅迫くらいされてるんじゃないかな。私たちも通常業務は全部ストップで人海戦術に駆り出されたんだけど、そのおかげで幸運にも私のチームが藍田くんを特定できた。だけど私が庇えるのは今のうちだけ。他に情報が漏れる前に早く処分して、お願いだから」
つまりアクアショップの店長はおそらく俺のことを黙っていてくれてるのか。商売人の鑑だな、と一瞬呑気なことを考えたが、事態が急を要することは理解できた。
「わかった。ルミナスネオンテトラとスターリーフは諦める。水槽にいる他の生体だけは、何とか見逃してもらえないかな。大切なんだ、生きがいと言ってもいいくらい」
能作はしばらく考え込んだ。
「水草は交雑が早いから万一のことがある、諦めて。生体については、体表面を消毒するなら見逃せる」
「ありがとう」
「お誘いしておいてなんだけど、早く帰った方がいい。ここは私が持っておくから」
「ありがとう。だけど、中学で一度クラスが同じになっただけの俺相手に、何でここまでしてくれるんだ。俺は能作さんをろくに覚えてもいないくらいだったのに」
「そりゃ、研究者として責任感じてるから。それと、昔ちょっと好きだったしね」
「はっ?」
同級生とはいえ能作との接点はあまりなかったはずだし、藍田は近しくもない異性から好意を寄せられる類の人間ではない。今も昔もそうだ。
「カエルの話の続き。授業が終わった後、荷物を取りに教室に戻ったら、藍田くんがまだ残ってカエルのスケッチ描いてたんだよ、それもびっくりするくらい丁寧で上手なやつ」
なんとも偏屈な自分らしいエピソードだと藍田は思った。
「それのどこがよかったの?」
「同級生は皆私に呆れてるか怒ってるかだったけど、藍田くんだけは我関せずでいてくれたのが助かったんだ。私もスケッチ終わってなかったから隣で一緒に描いたんだよ。お互いあんまり喋らなかったけど、私にとっては居心地がよくて」
「多分何も考えてなかっただけだと思うけど、ありがとう」
「いいえ、気をつけて」
「じゃあね」
お互いもういい大人だし、生きてきた世界が違う。これからどうにかなることはないだろう。それでも藍田の心はじんわりと温かくなった。
家に帰り着くと、藍田はいつもと変わらない様子の水槽に迎えられた。
エメラルドに輝く鱗のテトラに、真っ白で繊細な大輪の水中花。自律型生態系実現のための実験動物なのに、どうしてこんな美しくしたのだろう。野に放てば、いずれ遠い未来で人類に牙を剥くのだろうか。
少なくとも、彼らとの関係は良好だったと藍田は思っている。彼らに人間の感情に相当するものがあるとは思えないから、関係と呼ぶのが相応しいかは分からないが、藍田は丁寧に世話をしたし、彼らも彼らで環境を最適化するために出来ることをしていただけだ。
それでも結局、人間の都合で生み出した彼らを人間の都合で殺すことに違いはない。この美しい種が存在したことは、藍田と能作含め数人しかいないだろう。どこまでいってもエゴでしかないが、せめて覚えておこうと思った。
「ごめん」
網で掬ったテトラ達を、大量の氷と水を入れたバケツに移していく。テトラ達は驚いたように跳ね、激しく光を点滅させる。エメラルドの光が氷に乱反射してバケツの中を明るく照らす。こんな時でも美しいなと藍田は思った。
エメラルドの光の点滅は次第に弱く、間隔が長くなり、やがて消えた。
10分後、藍田はテトラ達を再び掬い上げた。
そのうち1匹を摘み上げ、手のひらに乗せて最後に観察してみる。地の体色は白に近い明るい水色で、瑞々しく透き通っている。間近で見ると、ほぼ透明の発光器官が胸鰭から尻尾にかけてまっすぐ並んでいるのが見てとれた。魚というのはこんなにも小さいのに、つくづく精巧な作りをしている。奇跡的だと藍田は思った。
もう生きていないと頭ではわかるが、大きく開いた瞳は自分に何かを訴えかけているかのように感じられた。
藍田はしばらくテトラを眺めた後、スターリーフと一緒にまとめて能作のバーナーで炭化するまで焼いた。
文字数:13189