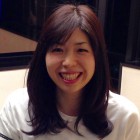キャピタル・オブ・ザ・デッド 資本主義と伝染病
まず資本主義という概念に関する諸処の性質から扱いたい。capitalism(資本主義)はその語幹にcaput(頭)を持つ。capitalism(資本主義)は先端(caput)でありcape(岬)でありcapital(首都)、cattle(家畜)などを含む。これらの語源から愉しい想像をふくらませることはできる。岬、確かに資本主義の拠点の多くは先端である沿岸に位置しているし、水源が近く通商が行われやすかった場所で成立するのは道理だろう。世界四大文明は言うまでもなく、資本主義の多くの首都は今でも執拗に沿岸である(ニューヨーク・ロンドン・東京・上海・シンガポール,etc)。また、家畜を私有財産制の象徴として扱うのも適切だ。
しかし並べても幹部となる意味はやはりcaput「先端」というラテン語の語幹である。先端は確かに資本主義の意気軒昂な様を理解するのに容易いだろう。しかし、守護天使を掲げながら海を切り進み前進する船首のその鋭利な先端や、風を切り裂いて進む飛行機の鋭い両翼をこそ資本主義と呼ぶならば、それに対して膨大な量をたたえつつ、その進行によって大きな波を産む海や空のほうは何と呼ばれるべきだろうか。実際には資本主義は先端のほうだとこの語義こそは示している一方、我々はしばしば資本主義が世界に与えた影響のほうこそを資本主義と呼んでいるのではないか。この矛盾の解説は「資本主義」という語の意味がどのように充填されるのかが鍵である。
この世界を循環させている「先端」としての資本主義は決定的には概念ではなく、進行中の出来事であるが、定義とはそのような運動性を包括した関して完全に無力である。というのも、「資本主義」という名前に充溢した「私有財産制」やら「牧畜性」などの意味や定義は、まるで「ミネルヴァの梟」の例えのように、しばしば資本主義が「及ぼしてきたもの」が残した轍から逆算してようやく輪郭が立ち現れてきたものであり、そのときに、各々にとって資本主義という意味を全うするような概念と表象がそこにあてがわれ、形式だけだった資本主義という言葉の意味が満たされていく。そのとき始めて、資本主義が理解できるような形を取るのであるが、しかしこれは話が逆であって「理解できないものを理解できるかたちに」落とし込んだ不出来なカリカチュアでしかない。定義では「先端」というナイフが今、この世界というパイにいかなる断面つけていくのかを問題にすることはできない(つまり資本主義の切っ先とは原ー暴力である。)、ゆえに「資本主義」という言葉には聖典がない。100年前や50年前の文献を対象としてなら可能でも我々の現代に対して「資本主義」が何を及ぼすかを思考することは不可能だと考える所以だ。
では定義によっては巧妙に削ぎ落とされる資本主義の性質を含有したまま表すことをどのように考えればよいのか。資本主義の性質を運動を蓄えたまま表現するためには、成功しているかどうかは別としてもある種のアレゴリーを通してしか機能しないと考えるべきだろう。例えば飛んでいる鳥を描写しようというなら、その運動性自体を絵の中にある種の抽象性として保存しなければならないが、それは運動的な対象の運動全体を抽象した一瞬を切りとるギリシャの彫刻のごとき手法である。これとは別に運動全体をある種の換喩の中で含有するしか無い。だからこそ小説や画家たちが「運動性」をアレゴリーとして用意する試みが生起してくるのだ。ゴッホの「ひまわり」は蓄えられた熱エネルギーの放出、太陽と地面の熱エネルギーの循環などを表現するためにあのような「みたまま」の姿からは脱輪していく。というわけで今から試みるのは冗談めかした寓話の試みである。 資本主義とは伝染病である。資本主義の甚だしく、その一息の出現と伝播を説明するためには、むしろ、元始から人間の生態ともっとも緊密な関係にあった存在の関与を疑ってみよう。
伊藤計劃と円城塔は「屍者の帝国」の中で意識についてのとある寓話を用意した。彼ら二人は、人間が世界を受容する媒介であり、世界と自己の袂を分かつ意識は、とある菌株であると考えたのだった。「屍者の帝国」の世界では、人間の意識は言葉は生成されたとあるパンチカードを挿入することで簡単に「屍者」として操作できるが、それは言葉を理解する意識そのものである菌株に働きかけているのであって人間にではない。「意識は伝染病だ。」それはベルクソンが意識と自然の境界をイマージュという概念で説明した更に先を行く、機械論的唯物論(mechanical materialism)である。魂はやはり21グラムを持つのか、それでは意識は何ミリグラムなのか、「私が私を持つ」というとき、前者の私は後者の私に対してどのような比率で存在しているのか。このような思考の試みは非常に興味深い。しかし同じ仮説を我々の中で最も強力で広大な謎に対しても適用することが出来るだろう。要するに私はこう言いたい。資本主義自体の探求と、資本主義が人間に及ぼす奇妙な習性を同時に考えるためには、社会学よりはむしろーー疫学の適用のほうが有効なのではないかということだ。
ロイコクロリディウムという寄生虫の生態を知っているだろうか。鳥の糞の中に胎児として潜伏した彼らはカタツムリがそれを食らうまで注意深く待つ。カタツムリの腸中に侵入した後、その栄養を恣にして急速にその半透明な身体の中にカラフルな緑色の存在感を増し、やがてカタツムリの生態に逆らう昼日中に面に出るように誘導された後、触覚に移動しその神経を刺激し、違和感から緑色の触覚を蠕動させることで、まるで芋虫のように見えるよう誘導する。これに空中の鳥が騙されこれを捕食する。これによって再び鳥の糞として地中にひり落とされることで寄生のサイクルが成立するのだ。
これはカタツムリを「ゾンビ」化することで自己を最適な環境の中で存続する寄生虫だが、資本主義がこの生物と同じような動きをすることを指摘することをどうしてためらうだろうか。資本主義というこの小さな菌株は産湯と洗礼の前に我々の精霊に寄生し、我々のあらゆる呼吸のたびごとに小さく蠕動し、小さな電気信号を持って我々の思考にインセンティブを与え操作することで依代を最適化し、身体と霊魂の前に死の床からするりと離れ、また大きなサイクルへの回帰を待つ。一方で資本主義という寄生虫に侵された検体である私は、自らをエコノミック・アニマルであると自称し、自らが自主的に資本主義下に参入する若人であると考えるが、実は彼は被支配を受けたゾンビなのであり、特定の動機を常に菌株から与えられることで、菌を存続させる手助けをしているとすれば、どうだろうか。
資本主義の円環(そしてその終焉)を語るのであれば、この2つの点から考えてみよう。マス・エフェクト=マクロコスモスとしての「疫病」=「現象」としての大きな資本主義、そしてミクロコスモスとしての「寄生」=「操作」として、個人の行動や思考を操作して自らを存続させる小さな資本主義、前者において強調されるのは、大きな資本主義には常に総体として進行しているよう見え、その結果として空虚な中心を創出すること。そして小さな資本主義はその最も純粋な形態においては、我々のただ一人一人の中を循環する共生関係にある。資本主義はこの2つを渡り、それが空虚な中心を創出しながら、つねに寄生体に信号を送ることでその空虚な中心に向かって個人を牽引し引きずり込もうとする。その奇妙な緊張関係は、現代において非常に有名な映画のジャンルによって、つまりーーゾンビ映画によって表象される。
各時代のゾンビ映画に登場する腐乱死体たちは、よく言われることだが、ただのゾンビではない。ゾンビとは常に現代を生きる我々の不安の表象である。例えば古きよきジョージ・A・ロメロの「night of the dead」(1968)の中のゾンビは、空虚な中心から疎外され、しかし中心に向かう前に、誘蛾灯のように個々人の欲望を求め彷徨う悲しき躯であり、彼らの欲望は穴の空いたワイン樽のように哀しいが、それは同時に大きな物語の終演の後の個人の喪失感との戦いでもあった。彼等はメディアを自分の身体に通過させておらず、まだ半分死んでいることへの挟持があり、身体は腐り落ちようとする気概があった。それはまだ走り出すまでの深い煩悶の中を生きている。
だが「28日後…」(2002年)以後、状況が一変する。ゾンビたちは走り出し、モッシュを組み、嘆きの壁(ワールド・ウォー・Z)に押しかけ、ついに突破する。彼らは信号や非常に小さな音に矢のように反応する準備をしながら、そこにもはや何の煩悶もない。資本主義体はようやく極めて洗練された形でロメロの時代の「良識ある空虚」を押しのけ、そこに居座りつつあるのではないか。つまり、個人が複数のイデオロギー的な中心を見極める時代ではなく、常に正確無比な最新が上流からダウンロードされる。彼だけの欲望=ニュ―スフィードによって投影される中心に向かっていつでも駆け込む。ミサイルたちに与えられる命令はもっとも単純な形態だ、「中心に合流せよ」。結果的に、彼らは個人の欲望をドライブさせたように見えて、その欲する所の先で他人と大差ない所に到着してしまう。それは日々の商いにおいてはニッチへの大挙であり、もっと巨大な規模で言えば、これはアイロニーに聴こえるかもしれないが、反資本主義運動としてのストライキを含む。
たとえば2011年に99%を自称する人々がウォール・ストリートに集合したとき、資本家を出せ、自分たちは何をするかわからないぞと言い続け、ひたすら次の司令がダウンロードされるのを待っていた。だが、彼らはアナーキズムまでは行く気がない。彼らは資本が適切に分配されないことに怒っているのだから、適切に資本が再分配され、悩みが解消されればここにはイデオロギー的な対立はなく、革命の予感すら見出すことができない。資本主義体の一般的な生態であり、いかにもゾンビらしい軌道と暴動に始まりながら、最後には更に古典的なブードゥーの死霊魔術としてのゾンビ、つまり使役される存在として資本主義という土に回帰してしまうとき、彼らは不幸にも資本主義というゲームのルールを遵守する健康なプレイヤーである。そして誰もが資本主義という運動する概念のルールを少しだけ押し広げて通過していく。何もかも資本主義というゲームのいきすぎた拡大解釈だ。なぜなら中心と定義がないからこそ、形式は無限に押し広げられる。資本主義をイデオロギーに押し込めるという人類史上最も稀有な社会実験だった社会主義が失脚してしまった。今、どのようにそれが達成されるというのか。
広義の資本主義自体の解体が不可能でも、個人の精神の中における内的な離脱を試みることは可能であるように見える。例えば「断捨離」や「ミニマリスト」たちは我々に一縷の希望を抱かせるだろう。だがこの資本主義の菌株との蜜月を自ら断ち切るというときにすら、資本主義体は狡猾にも、あらゆる逸脱と差異にすら値札を着けなおして商品化し、自らの力に変換する力を持つことを思いださなければならない。それは個人においてはまるで群れからはぐれた子ヤギの帰巣本能のような不思議な発動を見る。アメリカの科学者グレゴリー・ベイトソンはもともと文化人類学が統合失調症の研究のため『ダブルバインド』など有名な概念を創出し人間の無意識と非文明世界を探索していたが、同時にイルカの脳の研究を通して、後期にはサイバネティクスの発展に大きく貢献した。そのサイバネティクスとは人間という存在をグリッドの上に配置するための諸学であり、ようするにいずれは軍事学であり今のNSAの始祖である。資本主義体から逃れるあらゆる孤独な歩みが、逆に資本主義の寄生体に発見され、捉えられてしまったのだ。本当の「断捨離」や「ミニマリスト」とは、「ライ麦畑の捕獲者」の甲斐甲斐しい救いの手(※1)を払い除けて、もっとも遠くまで行かなければ達成されない。
だがそんな生き方は、この資本主義の統治下では死人も同様だ。どうしたことか、我々は今や自主的に完全に自殺するチャンスすら探らなければならないようだ。ゾンビとは要するに、本当の生はおろか、死も得ることもできない傀儡であり、今の状態では我々は資本主義から逃れる手段も、それを自主的に脱出する手段もないのだ。しかし、陰気なビジョンばかり提示してしまったが人類の資本主義的ゾンビ化が加速化するのは悪いことではないかもしれない。資本主義が全ての世界を覆い尽くしてしまいくまなく差異が充填されることになれば、資本主義は疫病としての役割を終え死滅する。要するに、搾取と差異というのがある種のエントロピーで成り立っているのならば、燃え尽きる所を見据えるのも悪くないと提案してみよう。そのとき、資本主義菌は人間の中に完全に死滅するだろう。だがその途方もなく長い時間の間に横断による無数の戦争に人間と地球が耐えられるかについては賭けてみるしかない。
(※1)「とにかくね、僕にはね、広いライ麦の畑やなんかがあってさ、そこで小さな子供たちが、みんなでなんかのゲームをしているとこが目に見えるんだよ。何千っていう子供たちがいるんだ。そしてあたりには誰もいない――誰もって大人はだよ――僕のほかにはね。で、僕はあぶない崖のふちに立ってるんだ。僕のやる仕事はね、誰でも崖から転がり落ちそうになったら、その子をつかまえることなんだ――つまり、子供たちは走ってるときにどこを通ってるかなんて見やしないだろう。そんなときに僕は、どっかから、さっととび出して行って、その子をつかまえてやらなきゃならないんだ。一日じゅう、それだけをやればいいんだな。ライ麦畑のつかまえ役、そういったものに僕はなりたいんだよ。馬鹿げてることは知ってるよ。でも、ほんとになりたいものといったら、それしかないね。馬鹿げてることは知ってるけどさ」
ところで、本作「ライ麦畑で捕まえて」の主人公ホールデン・コールフィールドはどこにも寄り付きたくないという考えの元あちこちを放浪しながらも、自分を貫く決定的な事件を探すという矛盾した行動を続け、結果、最後には精神病院に入ってしまう。この発言も一見支配者・調停者への合一の欲望に見えるが、同時に彼が持っている決定的な逸脱傾向に対する資本主義体の「帰巣本能」の発動であると捉えることができる。
文字数:5912