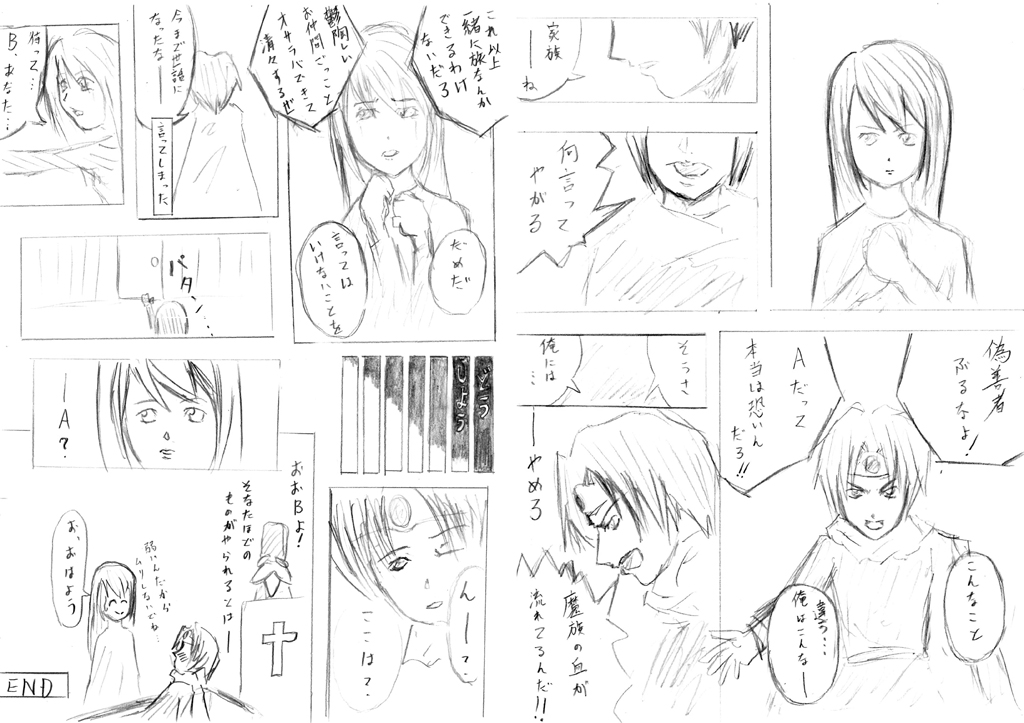感情×ロールプレイ、あるいは弱さの発露
【課題1】
【課題2】
『コロリころげた木の根っこ』の初出は「ビッグコミック」1974年4月10日号である。
まずはこの作品が同時代の東京辺り(日本)を舞台に描かれているということを確認してみよう。
主人公である西村の職業は書籍の編集者であるらしい。彼の勤めている文芸公論社の社屋を描いたコマを確認してみると、少し離れたところに藤子スタジオがあるらしいことがわかる。有限会社藤子スタジオは1960年代に西新宿に設立されており、文芸公論社の場所も西新宿近辺であると推測できる。
作品は西村が結婚一年目の妻・優子と公衆電話を通して会話を交わしている場面から始まっており、西村は編集長の突然の指示により作家(であると考えられる)の大和のもとに原稿を取りに向かう途中であることが明かされる。
作中のやり取りから時間経過を考えると、朝、西村は優子と暮らしている家を出て、西新宿のオフィスへ出社したのち、編集長の指示を受けて大和の家へと向かい、昼食前には到着している。その後、原稿を受け取って、遅くともその日のうちに帰宅するつもりであったことから、大和の家は都内、あるいは東京近郊であると考えられる。
時期については、作中で交わされる会話の一つで話題となる新聞の占い記事から季節が4月であるということが明確となっている。さらに作中には「水銀汚染魚安全献立表」なるものが登場するが、東京都が「魚介類等の水銀汚染調査」を開始したのが昭和48(1973)年の4月以降ということから、その調査結果が雑誌や新聞の記事として掲載されるのは、早くともそれ以降の時期になると考えられる。1974年4月の平均気温が14.8度という点を考えると作中に登場するルミの服装がやや軽装すぎるという点が気になるが、作中の年代を1974年4月と考えても大きなズレはないように思われる。
ひとまず作品の舞台が1974年の東京(日本)であるという前提を置いたうえで、作中の大和夫妻の「愛情」について考えてみたいと思う。
大和夫妻は結婚して既に20年の歳月を共に過ごしている。つまり二人が結婚したのは1954年頃ということになる。国立社会保障・人口研究所の出生動向基本調査によると1950~1954年当時の結婚の内訳は「見合い結婚」が53.9%、「恋愛結婚」が33.1%であり、割合だけをみれば二人が見合い結婚であった可能性のほうがやや高いと考えられるだろう。大和が妻との関係を語る際に、結婚第一夜をことさら強調し、そこを「最初」と位置付けていることからも、二人が見合い結婚である可能性が高いように思われる。
ちょうど作中のもう一つの夫婦である西村夫妻の結婚した70~74年の結婚内訳が「見合い」33.1%、「恋愛」61.5%と逆転しており(その前のタームの65~69年は「見合い」44.9%、「恋愛」48.7%とほぼ半々)、西村と優子がお互いに対等な関係性のなかで電話越しに喧嘩をしている様子と、家父長的な大和家の様子は時代の変化をうまく対比させて描かれている。
大和夫妻が見合い結婚であると仮定すると、その出会いは愛情を介さずに親族や知人の縁によって引き合わされたものだったのだろうか。あるいはそうなのかもしれない。ちなみに1954年前後の平均初婚年齢は男性26.6歳、女性23.8歳(統計局e-Statより)とのことで、26歳前後の大和が果たしてすでに作家だったのかは残念ながら作品から読み取ることはできないが、1974年現在の大和が作家としてある程度大成しているのは、大和に家庭のことをすべて任されている妻の内助の功が多少なりとも影響しているのではないだろうか。作中の描写からも大和家はかなりすっきりと片付いている印象があり(妻の意図からトイレが汚れている描写はあるが)、大和が酒好きで乱暴なだけの人物ではなく、むしろ家庭内が片付いて安定していることを是とするような神経の持ち主であることもうかがえる。
また、仮にも大成している(と思われる)作家である大和が、単なる粗暴な人物であるはずもなく、彼の書いている作品のジャンルは不明であるが、読者を獲得し、出版社からもそれなりに評価を得ていることを考えれば、人並み以上の観察眼と、それを文字に置き換える描写力や感受性は持ち合わせていると考えられるだろう。
以上のような大和の性質を鑑みるに、妻がわざとウィスキーの空きボトルを廊下に放置したり、トイレの清掃を怠ったり、あれほどわかりやすく切り抜かれた新聞記事や、無造作に放置された怪しげな記事を貼り付けたスクラップブックの存在に気がついていないとは考え難い。つまり、大和は妻の自分に対する殺意に気がついていながら、あえて放置している可能性が高いのではないだろうか。妻の方としても、殺意を悟られてしまうことに怯えるような素振りを見せつつも、初めて大和家を訪れて数時間滞在しただけの西村に「秘密の」スクラップブックを発見されたり、それほど付き合いの深いとは思えないルミに殺意を見抜かれてしまっていたりすることなどから、本心では殺意を隠すつもりがないのではないかとも感じさせる。
殺意を隠そうとしながらそれを示唆し続ける者と、殺意に気がつきながらも気がつかないふりをして振る舞う者、この二人の歪な緊張関係が大和家には満ちている。
作品を執筆するための刺激について大和は西村に以下のように語って聞かせる。
「ぼくはね、ひとりになるといつまでたってもエンジンがかからんのだよ。やっぱりね、きみなんかがついてて……こわーい顔でつっついてくれないとさ。」
今でこそ、西村のような担当編集がつきっきりで原稿を待つ大作家となっている大和だが、駆け出しの頃は一体どうだったのだろうか。彼が小説を書くために、傍についてつっついていたのは、誰だったのだろうか。彼のことを最も近くで、ある時期からはおそらく「怖い顔」で、見守り続けてきたのは、他でもない妻ではないだろうか。
ある種の作家にとって、作品を書くということ、書くためのインスピレーションを得るということは、身を削ることや、追いつめられて絞り出すことに近いと考えられないだろうか。それが大和の場合、自分の生命への危機感や日常に潜む殺意によって研ぎ澄まされた緊張感から生み出されるものであるとしたら、彼にとって妻の存在はかけがえのないもの、作品を生み出すためになくてはならないものだと言える。
作中、妻が大和の作品について言及することはない。だが、大和がライフワークと考えている瀬戸内海を舞台とする作品、かねてからその取材旅行に行きたがっていたことを妻は知っており、自分の存在を差し置いてでも取材旅行に行ってこいと送り出す姿勢を見せている。つまり、ある意味において妻は、大和が作品を完成させるということについては協力的な姿勢を見せているのである。それは日頃からの大和の横暴な態度を耐え忍んでいる様子を、周囲からあの奥さんだからやっていける、と思われていることからも伺える。妻がこれまで大和からの仕打ちに耐えてきたのは、大和の作品が一家の収入源だから、という理由ももちろんあっただろう。だが、家を出ることもせずに20年間連れ添ってきたのには、大和の創作行為への献身のようなものが見えてこないだろうか。
ここでもう一つ、作品に登場するモチーフにカニクイザルのキー公の存在がある。これは妻の殺意を表す小道具として、東南アジア産の猿からの伝染病、を示すために登場しているように見える。一見、この猿の登場は唐突なように見えるが、川西康夫と本庄重男による「わが国におけるサルの輸入状況」(1971年)によれば、1970年当時のサルの輸入頭数は11,075頭(うちマレーシアからのものが1,611頭)で、サルの種類は主としてカニクイザル、アカゲザル、グリーンモンキーであるとされている。そのうち実験用動物として輸入されているのは2,000頭前後であり、それ以外の目的(動物園の新設、ペット・ブームなど)でも多くのサルが輸入されていることが報告されており、大和がアカゲザルを飼っていることには、それほど違和感はないのかもしれない。先に、サルと感染症の関連について述べたが、1974年とサルを結びつけて考えるとすれば、むしろサルから読み取れるのは1974年1月26日に発売され、一大ブームとなった「モンチッチ」人形だろう。モンチッチは子供向けの玩具であるが、それを大の大人の男性である大和が愛でている姿は何となく滑稽だが愛らしくもある。モンチッチのネーミングにはフランス語の「モン」と「プチ」を合わせて「私の可愛いもの」という意味が込められているが、妻が大和にサルを送ったことで彼のなかにある種の幼児性を見出しているようにも見える。
作中からは推測することしかできないが、もしかしたら大和夫妻には子供がいないのではないか、と考えてみると、一つは妻が大和をある種、わがままな幼児(しかし自身の子供のような存在)として甘やかしながらその仕打ちを受けているという構図と、もう一つ、大和の書く作品こそが、二人の愛憎によって生み出された「子供」であるという構図も見えてくる。先にも述べたように、読者には大和の書くものが、どんなジャンルのものなのか、彼がどういった作風なのか、知ることはできない。一見、粗暴で豪放そうに見える大和だが、外面がよく、些細なことに怒り出すなど、神経の細かい面も見て取れる。そんな彼が一体どんな雰囲気の作品を書くのかと思いを馳せながら、作品の最後のページを眺めてみると、不思議とその雰囲気の一端が垣間見られるように思えるのだが、いかがだろうか。
文字数:3959