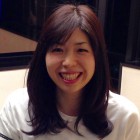藤子F不二雄作品における夫婦関係の形式と欲動
まず、藤子・F・不二雄の『コロリ転げた木の根っこ』(1974年)(以下『コロリ』)を簡単に俯瞰してみよう。小説家である大和は、編集者の若手社員である西村には優しく接するのだが、その前ではドメスティック・ヴァイオレンスを振るう暴君の姿を見せる。妻には家事の一切を任せているが、酒が用意されていないなど、些細なことで暴言を吐き、時には暴力を振るうことを辞さない。また、公然と妻に自分の愛人へと電話をかけさせるなど常軌を逸した振る舞いをする。20年間連れ添ってきた妻の感謝の気持ちもあるのだが、だからと言って手綱を緩めることがない。一方で妻は、夫の常習的な暴力の裏で、様々な復讐を試みている。怪我の誘導(階段の前にボトルを置く)、トイレの引火爆発の誘導(喫煙者の夫に対して、トイレにガスを充満させる)、危険な食物の提供(水銀汚染の可能性のある魚)などを連続的に行う。大和の愛人として現れた女は妻が将来的に夫を殺害することとなると、編集者の若手社員西村に予言をし、西村の目には、そのような事実が浮き彫りになっていくのだ。
次に、同作者による『老雄大いに語る』(1976年)(以下『老雄』)ではどうだろうか。宇宙局長のサミュエル・クリンゲラインが、異例中の異例とも言える宇宙船の搭乗券の指名を自らにし、宇宙旅行へと旅立つことになる。それはしかし、職務上の倫理観によるものではなく、極めて私的なものであった。家庭内では一言以上喋ろうとしても、多弁な妻によって常にすぐに遮られる男が、宇宙旅行に行くことを決断した。それは宇宙船のモニターから、沈黙している妻に対して一言以上しゃべりたいという機会を持ちたいという理由によってのみ実行されたのである。最後に嬉々として、積年妻に遮断されてきた積もった想いを口にしようとするところで幕は閉じる。
まず二つの物語を、ファルスを起点として比較してみよう。
『コロリ』と『老雄』において、夫婦における象徴的ファルスの存在と、それに左右される異常な夫婦の姿が描かれている。端的に、『コロリ』における小説家として働く夫のファルスは、編集者の西村が家に原稿を取りに来る姿や、編集者の社員たちの態度から、ある意味形式化されているとはいえ、未だ健全であるとわかるし、実質的にはそれを支える妻の姿がある。『老雄』には、家庭内では常に妻に支配圏を奪われている宇宙局長が満を持して、宇宙船のモニターから妻に語るのだが、妻に対してより巨大なファルスを希求する夫の姿がある。両者に共通するのは、ファルスを支える、古き一夫一妻制という文脈であった。
しかし、『老雄』において夫の試みは成功するようには思えない。それはなぜか? これは端的に言ってクリンゲライン自身が行く必要の全くない宇宙旅行であった。また、大統領補佐官のカブレ氏の言及するように、社会的、政治的なリスクを背負っている。しかし、クリンゲラインの目的はそうした社会的な業績やリスクを背負っていくという自負はない。妻によって発言権が奪われた夫には、生活におけるすべての決定権は妻に奪われているのだが、一瞬でも夫婦間におけるファルスを取り戻したいという、社会的というよりむしろひたすら私的な理由で妻に自己のファルスを誇示するという意識しかない。つまり、クリンゲラインには、他人にそして社会的に承認されていきたいという大きな物語を背負うことなしに、データベース的な行動の仕方をしているのだ。それは極めて「動物化」的な行為である。
では、そのような状況下で、夫婦の関係性は変化するだろうか?夫は、確かに妻に対して積年言いたかったことを言うことになるだろう。しかし、それが物語中で「地球を象徴している」とさえアナウンスされる妻の笑顔に対して、宇宙からの発言という行為は端的にあまり意味をなさないように思えるし、クリンゲラインの、あくまで妻に向かってのみ、ファルスを求める示威的な行動も、妻によってデータベース的に消費されるのみではないか?そして結局は、日常における夫婦の支配力が変わることはなさそうである。そのとき、私たちは『老雄』における夫婦の情愛を考察すると、それは妻による普段の同一性の希求であり、それはエロス的な感情で充溢されている、ということができよう。
それでは、『コロリ』の場合は、夫婦をめぐる生活の形式はいかなるものであろうか?『コロリ』における小説家の夫は、単純に男性優位的な価値観を常に旧態依然とした形式性にこだわっているように思える。例えば「男子は厨房に口を出さない」、「家のことは全て妻に任せる」といった発言はそのような形式性の重視である。その形式性のおかげで、猿の購入、あるいは料理の決定権など、単なる男性優位的な夫婦には考えられない自由度を妻に与えたのである。それは別の言い方でいうならば、「スノビズム」的な形式性の遂行にあった。その「スノビズム」とは夫婦の共犯関係にあると言えるのだが、それは二人の深い欲動に基づいているといえはしまいか?
フロイトは、大きなものへと不断に同一化しようとする欲動であるエロスと、その同一化を不断に破壊しようとする欲動であるタナトスは、互いに性愛=死の欲動につきものであると明らかにした。そしてこのふたつは完全には分割不可能であるが、その割合は状況に応じて変化していく可能性がある。
これを踏まえもう一度整理してみよう。ファルスの新しい具現化が不可能な『老雄』の場合は、夫婦の形式は「動物的」なものへと移行していく。そしてそこには、妻による支配的なエロスが存在する。他方で、『コロリ』における夫婦は、形式性を重んじる「スノビズム」的な形式によって、二人の共犯性を見ることが可能である。そのとき、妻の小さな復讐の連続は、単なる復讐ではなく、夫に容認した自由のもと、半ば夫が無自覚的に認める復讐であり、そこに一種のエロスを見いだすことができる。物語の最後の場面で、編集者の西村が階段の上に妻が空きビンを置いているのを目撃するのだが、そのとき大和の妻はある種の中毒性を持って行為を行っているように思えるのだ。ただ、これはあくまでも日常的な行為であり、スノビズム的な生活の中で、同一化を求めるエロスの、一種の変性した欲動の形として存在している。しかし、ドメスティック・ヴァイオレンスが一やがてそのエロスはエスカレートしていき、タナトス的な欲動へと移っていくのではないか。大和の愛人が西村に「先生いつかおくさんに殺されるよ。」と言い放ったとき、同じ女性として敏感に、妻の抱える欲動がエロスからタナトスへと移行していくことに気づいたのである。
藤子・F・不二雄は、『コロリ転げた木の根っこ』と『老雄大いに語る』において、一夫一妻制における夫婦の形式性と欲動という、極めてリアルな視点を提供したと言える。
文字数:2800